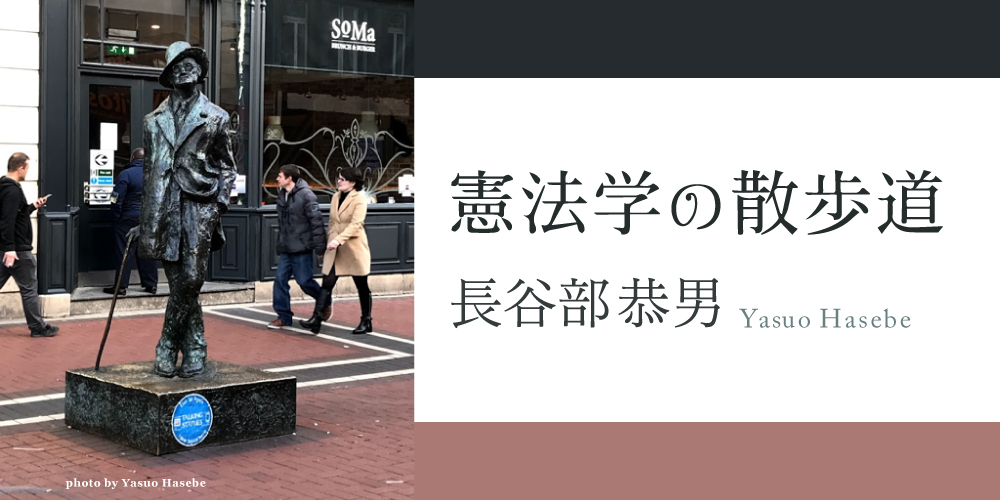「憲法学の散歩道」単行本化第2弾! 書き下ろし2編を加えて『歴史と理性と憲法と――憲法学の散歩道2』、2023年5月1日発売です。みなさま、どうぞお手にとってください。[編集部]
※本書のあとがきはこちらでお読みいただけます。⇒『歴史と理性と憲法と』あとがき
ヘーゲルが1802年から1803年にかけて公表した論稿に、「自然法の学問的取扱い方について Über die wissenschaftliche Behandlungsarten des Naturrechts」*1がある。彼は1801年に、友人のシェリングの助けもあってイェナ大学に教職を得たばかりであった。
ヘーゲルがこの論稿で採り上げた論点の1つは、カントが『実践理性批判』(1788)で提示した定言命法の要請の妥当性である。カントは、冒頭の第1部第1章第7節「純粋実践理性の根本法則」で、次のように定言命法の要請を定式化している*2。
君の意思の格率が、つねに同時に普遍的法則を定立する原理として通用することができるように行為しなさい。
カントはこれに先立つ第4節「定理 3」で、次のように述べる*3。
理性的[存在]者たるものが、自分の格率を実践的な普遍的法則と考えなければならないとすれば、それを、内容に関してではなく、もっぱら形式に関して、意思を決定する根拠を含む原理として以外に考えることはできない。
カントが、定言命法の要請に反する、つまり普遍的法則としては成り立ち得ない格率の例として挙げるのは、「自分の資産をあらゆる確実な手段で増やすこと」である*4。この格率からすると、自分の手許に他人からの寄託物があり、その所有者は死亡していて、しかもその寄託物について何の遺言も残していない場合、それを横領しても構わないことになる。誰も気付く者はいない。
しかし、かりにこうした格率が普遍的法則として妥当しており、誰もがそれを承知しているとすると、誰も寄託をしようとはしなくなり、もはや寄託なるものが存在し得なくなる。つまりこの格率は、自己破壊的であり、普遍的法則としては妥当し得ない。
ヘーゲルは異議を唱える。カントは寄託を含む財産制度が存在すべきことを所与の前提としている。しかし、それは内容を捨象し、もっぱら形式に依拠して普遍的法則を探究するというカント自身の立てた要請に反している。財産制度が存在すべきことが前提であればカントの言う通りであるが、財産制度が存在しない事態も、普遍的法則として妥当し得ないわけではない。
カントが言っているのは、「財産制度があるのであれば、それが存在しなければならない」、「財産制度が存在しないのであれば、それはあるべきではない」というただのトートロジーである*5。
つづきは、単行本『歴史と理性と憲法と』でごらんください。
 憲法学の本道を外れ、気の向くまま杣道へ。山を熟知したきこり同様、憲法学者だからこそ発見できる憲法学の新しい景色へ。
憲法学の本道を外れ、気の向くまま杣道へ。山を熟知したきこり同様、憲法学者だからこそ発見できる憲法学の新しい景色へ。
2023年5月1日発売
長谷部恭男 著 『歴史と理性と憲法と』
四六判上製・232頁 本体価格3000円(税込3300円)
ISBN:978-4-326-45128-9 →[書誌情報]
【内容紹介】 勁草書房編集部webサイトでの好評連載エッセイ「憲法学の散歩道」の書籍化第2弾。書下ろし2篇も収録。強烈な世界像、人間像を喚起するボシュエ、ロック、ヘーゲル、ヒューム、トクヴィル、ニーチェ、ヴェイユ、ネイミアらを取り上げ、その思想の深淵をたどり、射程を測定する。さまざまな論者の思想を入り口に憲法学の奥深さへと誘う特異な書。
【目次】
1 道徳対倫理――カントを読むヘーゲル
2 未来に立ち向かう――フランク・ラムジーの哲学
3 思想の力――ルイス・ネイミア
4 道徳と自己利益の間
5 「見える手」から「見えざる手」へ――フランシス・ベーコンからアダム・スミスまで
6 『アメリカのデモクラシー』――立法者への呼びかけ
7 ボシュエからジャコバン独裁へ――統一への希求
8 法律を廃止する法律の廃止
9 憲法学は科学か
10 科学的合理性のパラドックス
11 高校時代のシモーヌ・ヴェイユ
12 道徳理論の使命――ジョン・ロックの場合
13 理性の役割分担――ヒュームの場合
14 ヘーゲルからニーチェへ――レオ・シュトラウスの講義
あとがき
索引
「憲法学の散歩道」連載第20回までの書籍化第1弾はこちら⇒『神と自然と憲法と』
連載はこちら》》》憲法学の散歩道