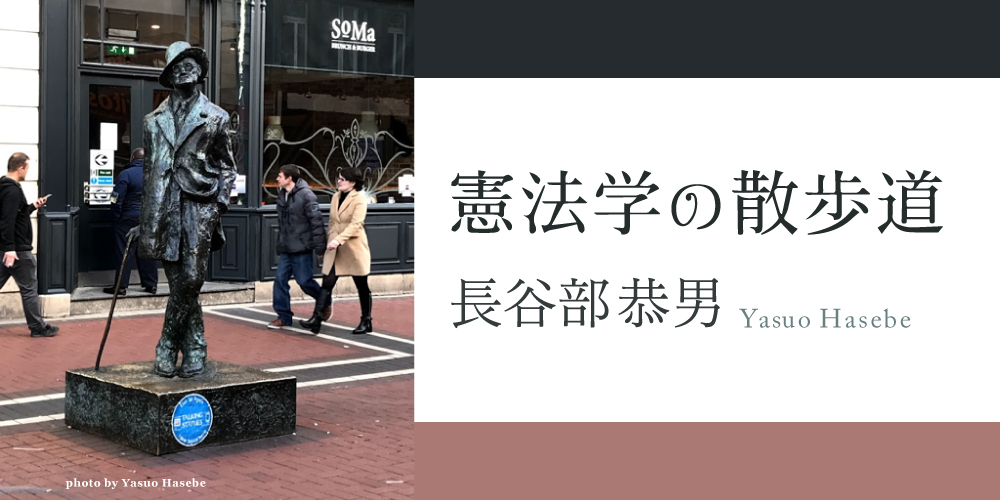「憲法学の散歩道」単行本化第2弾! 書き下ろし2編を加えて『歴史と理性と憲法と――憲法学の散歩道2』、2023年5月1日発売です。みなさま、どうぞお手にとってください。[編集部]
※本書の「あとがき」をこちらでお読みいただけます。⇒『歴史と理性と憲法と』あとがき
『神と自然と憲法と』第18章で紹介したように、ジョン・メイナード・ケインズは、世界を支配するのは思想であるとし、それに比べて既得権益の影響は誇張されているとする*1。これと対蹠的な観点に立つのが、歴史家のルイス・ネイミアである。ネイミアによると、思想や原理と言われるものはすべて、人間の真の動機を覆い隠すためのイデオロギーにすぎない。歴史を動かすものは、別にある。
ネイミアは、イギリス議会史研究のありようを変革したと言われる。時につれて変化する事実を描くのではなく、それぞれの時代の個々の政治エリートを詳細に研究することこそが、歴史家の役割である。テューダー朝史研究で知られるサー・ジョフリー・エルトンは、次のように述べる*2。
[かつては]議会に関する物語は、憲法上の自由に関する物語で、それは時代を経て着実に成長し、闘争は17世紀に決着がついた。庶民院の興隆、特権の確立、財政の統制、不平・不満の救済──それらすべての成果は、代表制の究極の勝利へと至る。議会制定法のうち関心の対象となるのは、こうした憲法政治の歴史に組み込み得るものに限られるし、詳細な検討の対象となる活動は、議員の独立性の強化を示すものだけであった。……1929年、ルイス・ネイミアが、なぜ人は議員になるのかと問いかけ、その問いに対して、少なくとも18世紀中頃の議員の大部分は、所属政党や[王権の抑制という]政策とは無関係の事情で議員になったのだと答えたことで、上述のような政治と政党に関する心地好い物語は、深刻な打撃を受けた。選挙を焦点とする議会史研究の時代、多様な人物史の分析に信を置く時代が、こうして幕を開けた。数を増す研究者たちによって、下院議員たちの個人生活・家族生活の秘密が明らかにされ、議会の役割は社会構造に支えられていると結論付けられた。……議会政治は、立憲主義とも、自由とも、さらには(少なくとも18世紀末までは)政党とも無関係で、すべては個人的な立身出世と栄達のためであったと考えられるようになった。
ネイミアの研究手法は、「ネイミアするNamierise」ということばを生み出した。ある制度の歴史を、関係する人々の集合的伝記(prosopography)を描くことを通じて分析する手法である*3。
イギリスのゴードン・ブラウン元首相は、マーガレット・サッチャー政権下における公共サービスの理念の衰退は、「すべては思想や世論ではなく、エリートたちの策謀の帰結」だとするネイミア一派の有害な影響に起因すると述べている*4。
ネイミアは1888年、分割されたポーランドのロシア領内で、ルドヴィク・ベルンシュタイン(Ludwik Bernstein)として生まれた。父親のジョゼフ・ベルンシュタインはワルシャワ大学で法律を学んだユダヤ人で、ローマン・カトリックと称していた。父方の元々の姓であるニエミロヴスキ(Niemirowski)は、18世紀末のドイツ化の強制でベルンシュタインに変えられていた。父親は妻の実家の営む農園を管理して生計を立てた。
少年期のネイミアは、家庭教師に教育を受けた。レンベルクとローザンヌで法律を学び、その後、「世界でもっとも文明的で人間的」*5だと考えるイギリスに移ってロンドン大学経済学院(LSE)で、そして最終的にはオクスフォードのベルリオール・コレッジで近代史を学んだ。ロンドンとオクスフォードでは、フェビアン協会の活動に参加している*6。オクスフォード在学中に、彼は姓をベルンシュタインからネイミアに変え、1913年に英国臣民となった。
第一級の成績をおさめたにもかかわらず、オール・ソールズ・コレッジのフェロウとなることができなかった彼は*7、アメリカに旅立ち、父の知り合いの事業家の下で働いた。彼の仕事の内容については、情報が錯綜している。アイザィア・バーリンが当の事業家の息子から得た情報では*8、彼は事業家の発行する雑誌の編集と原稿執筆に携わったが、彼のオーストリア批判とアメリカ参戦論が激化したために雇い主と対立し、1914年4月にイギリスに戻った。
ネイミアは、滞米中に知り合ったイェール大学の歴史家たちから、史料にもとづく「客観的」で「科学的」な歴史研究の方法を学び、同大学のチャールズ・アンドリュー教授から、18世紀のアメリカ独立時の歴史について、アメリカでは多くの研究がなされているが、イギリスからの貢献はほとんどないと聞かされて、この時代のイギリス史研究を志したとされる*9。
第一次大戦が勃発するとただちに兵役を志願し歩兵連隊に配属されたが、1915年2月には軍務を解かれ、陸軍省の広報局(the War Propaganda Bureau)で勤務することとなった。中東欧情勢に関する彼の知見は広く知られていた。組織再編で、彼は外務省の政治情報局(the Political Intelligence Department)に所属することになる。
戦後はオクスフォードでチューターをしばらく務め、その後、綿花をチェコに輸出する貿易業に携わった。その間、チェコやオーストリアの情勢を分析する記事をマンチェスター・ガーディアン紙に寄稿している*10。さらに、支援を募ってイギリス議会史に関する研究書を刊行するとともに*11、イスラエルの建国を目指すシオニズム運動にもかかわった。
彼の歴史研究に対する評価は高く、1931年にはマンチェスター大学教授となったが、彼自身が強く望んだにもかかわらず、オクスフォードに教授として迎えられることはなかった。歴史関係の講座が空席になる度に彼は候補とされたが、選任はされなかった*12。オクスフォードの学者たちは、選考委員たちがネイミアを選ばないのは恥だと噂したが、自分たちが選考する立場になると、同じことをした。専門領域が狭すぎるとか、シオニズム擁護が示すように彼の政治に関する考えは不穏当だとか、同僚に対して傲慢だとか、学生に対して厳格にすぎるとか、自分の関心事について一方的に話し続ける恐るべく退屈な人間だとかが、理由として挙げられた。彼の天才を疑う者はいなかったが、それに十分な比重が置かれることはなかった*13。
彼は定年までマンチェスターで講義を続け、第二次大戦後は、議会史基金(the History of Parliament Trust)で、イギリス議会の人物史をまとめるプロジェクトを率いた。1947年、彼はロシアの上流階級出身のジュリア・ドゥ・ボーソーブルと2度目の結婚をしたが、その際、妻の求めに応じてイギリス国教会の信徒となった*14。逝去したのは、1960年である。
アイザィア・バーリンは、ネイミアに関する回想録を残している*15。若きバーリンがオール・ソールズ・コレッジのフェロウであった1937年の夏、すでに著名であったネイミアが彼に会いにきた。なぜ、バーリンがマルクスに関する本を執筆しようとしているのか、それを訊ねるためである*16。
オール・ソールズ・コレッジのフェロウたるもの、本物の研究をするに足る知的能力を備えているはずだとネイミアは言う。それがなぜ、マルクスなのか。マルクスは憎悪で目のくらんだ二流の歴史家であり、経済学者だ。なぜフロイトについて本を書かないのか。マルクスと違って、フロイトの著作は天才の仕事だ。それにフロイトは存命で、インタヴューすることもできる。幸いマルクスは死んでいる。マルクスの信者たち、とりわけ知的に壊滅したロシアの追随者たちは、印刷用インクを必要以上に費やしている。この点では、ドイツの哲学者たちも同じで、同じ程度にバランス感覚も文才も趣味も欠如している。
つづきは、単行本『歴史と理性と憲法と』でごらんください。
 憲法学の本道を外れ、気の向くまま杣道へ。山を熟知したきこり同様、憲法学者だからこそ発見できる憲法学の新しい景色へ。
憲法学の本道を外れ、気の向くまま杣道へ。山を熟知したきこり同様、憲法学者だからこそ発見できる憲法学の新しい景色へ。
2023年5月1日発売
長谷部恭男 著 『歴史と理性と憲法と』
四六判上製・232頁 本体価格3000円(税込3300円)
ISBN:978-4-326-45128-9 →[書誌情報]
【内容紹介】 勁草書房編集部webサイトでの好評連載エッセイ「憲法学の散歩道」の書籍化第2弾。書下ろし2篇も収録。強烈な世界像、人間像を喚起するボシュエ、ロック、ヘーゲル、ヒューム、トクヴィル、ニーチェ、ヴェイユ、ネイミアらを取り上げ、その思想の深淵をたどり、射程を測定する。さまざまな論者の思想を入り口に憲法学の奥深さへと誘う特異な書。
【目次】
1 道徳対倫理――カントを読むヘーゲル
2 未来に立ち向かう――フランク・ラムジーの哲学
3 思想の力――ルイス・ネイミア
4 道徳と自己利益の間
5 「見える手」から「見えざる手」へ――フランシス・ベーコンからアダム・スミスまで
6 『アメリカのデモクラシー』――立法者への呼びかけ
7 ボシュエからジャコバン独裁へ――統一への希求
8 法律を廃止する法律の廃止
9 憲法学は科学か
10 科学的合理性のパラドックス
11 高校時代のシモーヌ・ヴェイユ
12 道徳理論の使命――ジョン・ロックの場合
13 理性の役割分担――ヒュームの場合
14 ヘーゲルからニーチェへ――レオ・シュトラウスの講義
あとがき
索引
「憲法学の散歩道」連載第20回までの書籍化第1弾はこちら⇒『神と自然と憲法と』
連載はこちら》》》憲法学の散歩道