あとがき、はしがき、はじめに、おわりに、解説などのページをご紹介します。気軽にページをめくる感覚で、ぜひ本の雰囲気を感じてください。目次などの概要は「書誌情報」からもご覧いただけます。
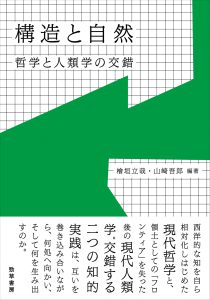 檜垣立哉・山崎吾郎 編著
檜垣立哉・山崎吾郎 編著
『構造と自然 哲学と人類学の交錯』
→〈「はじめに」「あとがき」(pdfファイルへのリンク)〉
→〈目次・書誌情報・オンライン書店へのリンクはこちら〉
*サンプル画像はクリックで拡大します。「はじめに」「あとがき」本文はサンプル画像の下に続いています。
はじめに
哲学はギリシアからはじまったとするのが通説であるが、人類学について同じようにはじまりを考えられるわけではない。たしかに、文化という探究領域を定義したという意味で、エドワード・タイラーはそのもっとも初期の重要人物であろうし、エスノグラフィーという方法については、ブロニスワフ・マリノフスキーの名前をその先駆者として挙げることが定説となってはいる。一九世紀末から二〇世紀初頭にかけて近代的な学問としての人類学が確立したと考えるのは、一つのとらえ方であろう。このとき人類学は、非西洋の他者について考えるための、固有の概念、方法、そして歴史を有した研究分野として理解されていることになる。
しかし、他者についての記述や思索ということであれば、時代はさらにさかのぼることができる。大航海時代の旅行記や宣教師の記録をはじめ、さまざまな文学作品に登場する他者の表象、なかでもミシェル・ド・モンテーニュやジャン= ジャック・ルソーのテクストに、人類学的な思考の萌芽が見いだされてきた。「最初の人類学者」として、ヘロドトスが引き合いに出されることさえある。こうなると、哲学と人類学ははじめから交錯していたということになってしまう。そこまで時代をさかのぼらなかったとしても、人類学がある哲学的関心のなかから、それに抗して、あるいはそこから逸脱することによって生み出されてきたと考えることは、もう一つのとらえ方であるだろう。
本書は、このうち後者の見方、つまり哲学と人類学をそれぞれに異なる「研究分野」と考えるのではなく、むしろ互いに「外」との関わりにおいて自らを問い直し、そのことで変容しつづけてきた思考の実践としてとらえ、その現代的な意義を確認することを主たる関心としている。したがって、その議論の範囲は、人類学という研究分野の成立条件そのものを問い直すことから、構造主義の再評価、実践と創造性をめぐる方法の問題、そして開かれた知の生産といった主題にまで及ぶ。人類の思考とその広がりという意味で「広義の哲学」を考えようとすれば、哲学は、次第にその西洋的な起源から逸脱してそれ自身が変容していくことに無関心ではいられなくなるだろう。西洋的な知やその前提を自ら問い直しはじめた現代哲学と、領土としての「フロンティア」を失った後の現代人類学が、近い関心をもちはじめているのだと言ってもよいかもしれない。非近代的な事象を理解しようとその議論の範囲を拡張し続ける人類学が、自らの拠って立つ近代的な認識論の前提に批判の目を向け始めるとき、哲学と人類学が交錯する特異な場が現れてくることになる。哲学と人類学の現代的な交錯は、それぞれの学問のおかれた歴史的コンテクストを互いに巻き込み合う形で生み出されているのである。
こうした相互の影響関係をテクストのなかに見いだすことは、決して難しくはない。人類学という学問をある意味で決定的に特徴づけてきた「現地人(ネイティブ)の視点」という考え方が、そもそもその成り立ちにおいて解釈学や理解社会学からの強い影響を受けていること、そして、人類学の歴史においてもっとも重要な理論的関心事であったといえる構造主義が、合理性や普遍性をめぐるさまざまな論争を引き起こし、特定の分野を超えて、広範囲に影響を及ぼしてきたことを思い起こしてみればよいだろう。このほか、本書で扱われているテーマに限ってみても、デュルケムの社会学的な構想にみられる人類学と哲学からの色濃い影響、京都学派の哲学において熱心に参照される当時の人類学の文献の数々、女性の身体をめぐるフェミニズムと人類学の関わり、精神分析批判としてのスキゾ分析に持ち込まれる呪術論の解釈、そしてアクターネットワークと呼ばれる新しい概念と構造との関わりなど、その余波は隣接領域にも広がっていることがわかる。
本書は、こうした哲学と人類学の交錯を主題とするにあたって、構造と自然という二つの概念に注目し、その問い直しを試みた論集である。このとき念頭におかれているのは、何よりまず、レヴィ= ストロースを震源として多方面へと展開した構造主義の再評価という問題意識である。しばしば静態的で共時的な分析だとして批判され、過去の理論としてかたづけられることの多い構造主義であるが、本書のとくに第六章から第九章にかけて詳しく論じられるとおり、近年のレヴィ= ストロース研究、なかでも『神話論理』の研究が進むにつれて、こうした理解は刷新されようとしている。本書の第八章で檜垣は、レヴィ= ストロースが『野生の思考』においてすでに、構造に対する出来事性を重要な問題とみなしていたことを指摘している。そしてこの出来事性への関心は、まったく別のコンテクストで、たとえばメラネシアを舞台に展開してきた民族誌的な関心と奇妙な符合をみせることになる。第三章で里見は、ストラザーンの研究にみられる関係主義と予期せぬ出来事性という二つの読み筋に注目することで、構造主義的な関心の別の現れ方を浮き彫りにしている。構造主義をどのように引き継ぐことができるのか、その理論的創造性を考えなおすことが、現代哲学および現代人類学に共通の関心をかたち作っているのである。
「自然」という主題は、まさにこの創造性に関わっている。人類学の近年の研究において、単一の自然を想定することから多自然の様態を理解することへと議論の前提が大きく転回していることについては、すでに各所で精力的に紹介もなされ、批判的な検討が続けられている。本書においても、ティム・インゴルドの生態学的な知覚論、フィリップ・デスコラによる自然の人類学、ブリュノ・ラトゥールにおける非人間的なものへの関心、そしてマリリン・ストラザーンが論じる身体の多産性といった議論に触発されて、「自然」をめぐる新しい人類学が構想されている。他方で、哲学の研究においても、自然はそのローカル性、マイナー性への着目とともに重要な検討主題となっている。第五章で小林は、レヴィ= ストロースの同時代に、おそらくは別の仕方で野生をとらえようとしたメルロ= ポンティの身体論に、「もうひとつの自然」として身体をとりあげようとする近年の人類学の関心との接点を読み取っている。また第四章で山森は、ドゥルーズとガタリの『アンチ・オイディプス』および『千のプラトー』に登場する、しばしば統制を欠いているとも形容できる多様な人類学、および人類学もどきの記述をとりあげ、彼らがそうした記述に現れる呪術の理解をとおして、スキゾ分析という実験的で創造的な思考をはじめようとしていることを論じている。
かくして哲学と人類学は、現代の歴史的コンテクストにおいて多様な交錯の様相をみせ、そして理論的関心を新たに形成し続けているのである。関連するテーマを網羅的に扱うことは到底かなわないとはいえ、本書では、こうした交錯から新しい哲学、そして新しい人類学へと向かうための基本的な問いかけと、そして実験的な試みがなされることになる。
本書は、九章からなり、各章の内容は次の通りである。
第一章で山崎は、「人類学はエスノグラフィーではない」と述べるインゴルドの議論をとりあげ、今日の人類学が、他者についての研究から、自らの哲学者になることへと変容しつつあるのだと論じる。自己から見た他者と、他者から見た自己が同じでないとされるとき、「視点」とはどのようなものとして考えられるのか。日本哲学における人類学の受容という契機にこれと類似した関心が見いだせることに目を向け、三木清がたどり着いた構想力の論理と、今日の人類学にみられる歴史的存在論の関心の異同を議論する。
第二章では、「ネイティブの視点」という考え方が生まれてきた学説史的な背景がとりあげられる。視点は、必ずしもフィールドにおける経験から必然的にもたらされるのではない。磯は、ウェーバーの理解社会学とギアツの解釈人類学の違いを検討するなかで、「ネイティブ」という概念そのものが生み出されていったプロセスこそを問題にすべきだと指摘する。この概念が近代的な二元論の産物であることが理解されると、現代の人類学にとって、調査者自身のネイティブ性や調査者の視点の獲得プロセスの問い直しが、もっとも基本的な議論の出発点となることが明らかになる。
第三章で里見は、メラネシア人類学の革新を主導してきたマリリン・ストラザーンの仕事を取り上げ、メラネシア研究が、なぜどのようにして人類学の理論的な震源地となりえたのかを検討する。メラネシア研究では、しばしば関係論的な人格がとりあげられ、西洋的な個人や社会の考え方を組み替える大きなインパクトが引き起こされてきた。しかしながら、ストラザーンの議論では、メラネシアにおける関係論的な人格論に加えてもう一つの関心として、身体から未知の力能を引き出そうとする社会実践の問題、つまり行為論が重要な意味をもっている。この身体-行為論は、身体を普遍的な対象とみなしてきた一九七〇年代のフェミニズムに対して、メラネシア社会のエスノグラフィーを通じて多自然的な身体を提示するものであり、そのことでストラザーンは、ポスト構造主義的な論客として知られるようになったのだと里見は論じる。第一章、第二章で議論されたネイティブ性のとらえ直しは、ここでネイティブ性の変容という主題として引き継がれている。
第四章では、哲学の観点から、人類学と人類学もどきの活用が議論される。ドゥルーズとガタリは『アンチ・オイディプス』において多くの人類学的研究を参照し独自の概念創造を行っているが、その関心は、本章で主に検討される『千のプラトー』にもみられる。山森は、ドゥルーズとガタリが提唱するスキゾ分析が、いまだ謎めいた実践であるとしたうえで、その解釈に際して、呪術論が重要な役割を果たすことを指摘する。ただし、ここで呪術論として参照されているのは、当時から創作や捏造の疑いが指摘されていたカルロス・カスタネダの著作であり、また人類学者というよりは詩人であり演劇人であるアントナン・アルトーの著作である。この実験的ともいえる呪術論の活用は、書くことによる生成変化、つまり人類学それ自身の生成変化に関わる主題であることが示される。
第五章では、構造主義を継承する哲学、人類学の行方を描くことで、構造主義そのものの生成という主題が論じられる。小林は、デスコラが「それと知らずに構造主義者になった」と書き記していることに目を向け、このとき構造が、これまで批判されてきたような普遍主義的な発想としてではなく、ローカルな経験を理解するための母型として理解されていることを明らかにする。デスコラの試みは、民族誌的な経験をわたしたちの身体において聴き取ろうとする営みにほかならない。そしてそれは、メルロ= ポンティが論じた連合的な身体との関わりにおいて構造主義を再開するということでもある。構造主義と実存主義という、しばしば対立的にとらえられてきた思考の交錯を検討し、またその継承と変容のなかで「野生」を捉え直すこと、それが構造主義の生成を論じるということなのである。
第六章では、構造の概念とアクターネットワークの比較を通じて、両者の相補的な論点、および相容れない点を炙り出す作業がなされる。それぞれの概念には、いずれも関係論的な記号観をもち、自然と文化の関係を従来と異なる仕方で捉えているという点で、共通性が認められる。しかし、構造は人々が世界を認識し思考する過程に力点を置くのに対して、アクターネットワークでは対象が人間以外に拡張されていることに大きな違いがある。この違いを久保は、自然から人間への移行を論じる非対称的な論理としての構造主義と、そこに対称的なアプローチを持ち込むアクターネットワークという対比によって整理する。そのうえで、いずれも近代と非近代を把握しようとする思考である以上、それぞれが互いに補完的であるためには、認識の多様性と存在の多様性を両方面に展開していくことが必要になるとして、人類学の今後の課題を提示する。
第七章では、近年のレヴィ= ストロース研究の動向を踏まえた上で、構造主義が、自らを変化へと導く思考の実践となっていることに焦点があてられる。そこで注目されるのは、レヴィ= ストロースが初期から晩年にかけて繰り返しとり上げた「絶えざる不均衡」という表現の、一貫した意味というよりは、その多義的な使用である。近藤は、「絶えざる不均衡」の意味内容が、時間をかけて次第に否定的なものから肯定的なものへと移り変わり、またその対象が社会の領域から思考の領域へと推移していることを、テクストに即して示していく。そして、それが他者の思考を自らの思考において引き受けること、つまり自らを脱植民地化する思考の契機となっていることを論じる。
第八章では、レヴィ= ストロースの思考を、哲学の文脈に位置付けることによって議論が展開する。レヴィ= ストロースの思考と哲学との関わりを、檜垣は三つの場面でとりあげている。すなわち、メルロ= ポンティとサルトルとの関わり、「マルセル・モースの業績への序文」の哲学史における受容、そして今日の構造主義の受容、とりわけヴィヴェイロス・デ・カストロやラトゥールとの関わりである。この三つの関わりから檜垣は、構造の概念が、いずれにおいても出来事性を含んだ通時的な反復として考えられていること、構造とはその根幹から共時性と通時性との交錯であること、そしてそれは弁証法的な理性が求めるのとは異なる、もう一つの実践の契機であることを指摘する。そして、レヴィ= ストロースを未来へ向けて開いていく方向性を、「自然」に向かう思考、自然と文化にまつわる探究として取り出す。
第九章では、哲学が人類学の研究を受容し損ねてきたとの問題意識に基づき、新たな交錯を生み出す準備として、デュルケムの問題意識をたどりなおす作業がなされる。人類学にみられる非人間主義への傾向と、哲学における人間主義との相性の悪さを確認したうえで、近藤は、デュルケムの仕事が、現代哲学と現代人類学の分岐点であると同時に交錯地点となっていると述べる。そこで問題となるのが、集合表象である。社会学の創始者としてのデュルケム像から離れ、未熟な人類学者として彼の集合表象を取り上げ直すとき、そこには個人と集合の渾然一体となった理解、つまり個人と集合の重なりとして人間を見る視座があることがわかる。デュルケムは、この重なりに自然をみいだし、そして社会性の成り立ちをみようとしたのだが、その問題性に気づきながらも、十分に議論を展開することはなかった。こうしてわれわれが受け取る機会を逸した問題意識こそ、非人間主義的な社会論という、近代の前提から見ればパラドクスにしか映らない議論の可能性であることが示される。
*
哲学と人類学、そしてその関連領域には、多彩で豊かな歴史的・概念的な交錯がみられ、かつそれらは、人文学における理論的革新に決定的にかかわってきた。そうした議論の重要性と可能性にひきかえ、哲学と人類学、そしてその関連領域において、相互の議論が参照され詳細に検討される機会は、これまであまりに限られたものだったと言わざるを得ない。これは、本書に関わる研究者たちが抱える、また別の関心事であったといえる。
本書では、哲学と人類学の交錯をめぐる議論の足掛かりがいくつか取り上げられているに過ぎない。その歴史的実態の解明や、実践的な意義を明らかにするには、さらなる研究が必要になるだろう。創造性が、異質なものの出会いや、予期せぬ一致から生み出されるものだとしたら、本書は、まさにそれを引き起こすべく企てられたのである。その試みが、知の閉鎖的状況を乗り越え、そこから逸脱しようとするさらなる思考と実践を生み出していくことを願っている。
編者 山崎吾郎
あとがき
かつて私が若かった頃、つまり一九七〇年代から一九八〇年代にかけて、「文化」人類学と哲学の境界がきわめて近い時期があった(なお、日本では「文化」人類学という呼称と―近年の人類学は明確に文化と自然との境界を狙っているのだが―、柳田國男由来の「民俗学」という呼称が標準的にもちいられてきた)。正当なアカデミズムの評価はおくとしても、山口昌男の『アフリカの神話的世界』(岩波新書、一九七一年)や山口と共同での仕事もある中村雄二郎の『魔女ランダ考』(岩波書店、一九八三年)は、そもそも当時の必読書であった。さらに、こうした流れを継ぐように、浅田彰の『構造と力』(勁草書房、一九八三年)や中沢新一の『チベットのモーツァルト』(せりか書房、一九八三年)を中心とする「ニューアカデミズム」なるものが出現し、「現代思想」を強力に牽引した。かつては人類学と哲学は接近した領域にあったのである。
山口昌男が意図的に自らを「トリックスター」と称したように、彼らによる人類学と哲学の連携は、意図的に「講壇哲学」の解体(ただし、けっしてそれには成功しなかった)を目指していたのだから、彼らの「学会的」な位置づけが「微妙」であったのは戦略的ともいえる。とはいえ、山口昌男も中村雄二郎も明白な「岩波文化人」であり、アカデミズムよりもその影響力ははるかに甚大であった。
だが当時、クロード・レヴィ= ストロースの『野生の思考』(一九六二年)、ジル・ドゥルーズとフェリックス・ガタリの『アンチ・オイディプス』(一九七二年)、ピエール・クラストルの『国家に抗する社会』(一九七四年)、あるいはメアリー・ダグラスの『汚穢と禁忌』(一九六六年)に、人類学者も哲学者も、そして一般読書人も着目しないということはありえなかった。それは、フランス系の人類学関係者が抱えもってきた「構造主義」および「ポスト構造主義」が、ヨーロッパ的理性の「外部」を導入し、哲学の伝統的思考に即しつつそれを変革するように迫ってくる内容をそなえていたからであるだろう。
しかし残念なことに、この動きは継続しなかった。人類学者は胡散臭いポストモダンの「理論」よりもフィールドだ、現場だ、国際協力だ、という方向に散っていった。「実践」と「実証性」がより強く求められる世の中になっていった。またそのなかで、おそらくフランスの国際的な地位低下もあいまって、レヴィ= ストロースをはじめとするフランス語の文献を翻訳しうる人類学者が激減したということがある。他方で哲学の方も、分析哲学を継いだ英米系の思考が主流を占めることになり、思想の本流から人類学との関連は次第に消えていった。フランス哲学の側でも、人類学を射程に収めつつ、英米系的な語用論的展開を企てるダン・スペルベルなどの例外(菅野盾樹による紹介がなされていた)はあるものの、人類学自体が主題から遠のいていったことは確かである。
不幸な数十年であったとおもう。その間にも両者のあいだでの連携は模索されていたにちがいない。もちろん、一九七八年にすでに『オリエンタリズム』を出版していたエドワード・サイードや、「サバルタンは語ることができるか」の論考が一九八八年に出版されたガヤトリ・スピヴァクを軸とした、政治色のより強固な「ポスト・コロニアル思想」が一世を風靡し、「新植民地主義」的状況を重視する方向に関心が移ったということはあるだろう。だがそれでも、時代が「理論」を求めることは少なくなり、また哲学も「人類学的な経験」から離れていくなかで、このすれ違いの年月はやむをえなかったのかもしれない。日本においてもレヴィ= ストロースの『神話論理』は二一世紀になるまで翻訳が刊行されることはなく、マリリン・ストラザーンの名高い『贈与のジェンダー』(一九八八年)は未邦訳である。かつての「翻訳大国」であった日本での、人類学「理論」への関心の薄さが際だつ年月があった。
またこれに、人類学側の事情としても、英米圏と仏語圏との乖離がかさなってくる。英米圏では、クリフォード・ギアツの『ヌガラ』(一九八〇年)や、先述のストラザーンの『贈与のジェンダー』等が刊行され、ポストコロニアルの議論の影響から、ライティング・カルチャーにかんする議論が盛んになされていた。フランスでもレヴィ= ストロースを継いだフィリップ・デスコラやフレデリック・ケックなどの仕事があり、ブリュノ・ラトゥールは科学人類学を広域に拡げアクターネットワークセオリーを形成しはじめていた。だが一時期、英仏思想自身が、かつての帝国主義の時代さながらに、交流することがきわめて少なかったのも確かである。
事態が急変しだしたのは二〇一〇年代前後からであるとおもう。哲学や思想の側としては、レヴィ= ストロースやドゥルーズとガタリがもはや「古典」になるとともに、彼らの理論が別のかたちでもちいられる動きが全世界で生じてきた。ドゥルーズやジャック・デリダ、ミシェル・フーコーといった「フレンチセオリー」は、ジェンダー論やポストコロニアルの議論において(サイード、スピヴァク、それにジュディス・バトラーらの活躍により)、一九九〇年にはすでにほぼ「英米化」されていたが、フランス現代思想がもはや「フランス語圏のもの」ではなくなる動きは今世紀にはいって急である。そのなかで、人類学と哲学をつなぐ動きが、従来とは異なった方向から出現してきたことは、これも必然だろう。
二〇一〇年頃であろうか、ベルクソンにかんする国際会議が福岡で開催されたとき、来日していたケックが、昼食時にたまたまエデュアルド・ヴィヴェイロス・デ・カストロを話題にしていたことを想いだす。レヴィ= ストロースの『神話論理』とドゥルーズ= ガタリの『千のプラトー』を軸に著述を展開し、「観察されるアマゾン」を背景にもったブラジルの側から、フランス思想の展開をたきつけたことへの驚嘆を隠さなかったことを鮮明に覚えている。ヴィヴェイロス・デ・カストロの『食人の形而上学』は、ポルトガル語や英語などが原文の論文からなるが、フランス大学出版のcollection MétaphysiqueS からフランス語版が出版され(二〇〇九年)、本人もこれを「原典」として構わないということで、山崎吾郎とともに私も翻訳に携わらせてもらった。ブラジルはもはや「第三世界」ではなく新興資本主義国家であるが、ずっとヨーロッパにとっては「観察対象」であった。そこからレヴィ= ストロースやドゥルーズとガタリの議論を拡張する「パースペクティヴ主義」が出現することは、もはや人類学が西洋(欧米)対非西洋、英仏といった懸隔を軽々と乗り越えていることを意味する。
またラトゥールの「アクターネットワークセオリー」が、科学人類学という枠組みを超えながら、本人も英語で膨大な著作を出版し、多大な影響を与えたこともおおきい。グローバル世界で、英米人類学とフランス人類学が、もはや英米でもフランスでもない場所でおおきく絡みあう素地はできあがってきた。そのなかで人類学の「存在論的転回」以降、現在きわめて隆盛をほこる「マルチスピーシーズ人類学」(エデュアルド・コーンの『森は考える』(二〇一三年)や、その監訳者でもある奥野克巳による多くの仕事が代表的である)に至るまで、人類学の側が、五〇〜六〇年代の「構造主義」期を彷彿とさせるように「思想」を利用し(そこにはほぼ必ず、レヴィ= ストロースはもとより、フーコー、ドゥルーズ、デリダあるいはガタリのエコゾフィー的思考が顔をのぞかせるだろう)「思想」に刺激を与え返す状況が現出してきた。頃合いをみるかのように、日本でも長らく待ち焦がれていた「人類学理論」の翻訳が、水声社の「叢書 人類学の転回」において続々となされ、この論集に寄稿された方々の活躍もあり、ストラザーンの『部分的つながり』、ヴィヴェイロス・デ・カストロの『インディオの気まぐれな魂』、デスコラの『自然と文化を超えて』、さらにケックやアネマリー・モル、アルフォンソ・リンギス、マイケル・タウシグなど多くの文献が邦訳された。人類学と哲学のあいだに横たわっていた「冷たい」関係は、ここ一〇年ほどのあいだに一新されたといってもよい。
パンデミックで一時期の勢いは消えたとはいえ、学問の世界のグローバル化は凄まじく、今後、日本でこれらの文献を受容するわれわれは、もはやただの思想潮流の「受益者」として振る舞うことはありえない。「ニューアカデミズム」の時代には、言語の問題も、また当時の日本の経済的な優位性(日本語環境以外のことを考える必要がなく、人文学者は仕事ができた)も相まって、われわれが世界発信するということは、一部の例を除いてはあまりなかったといえる。日本のオリジナルな人類学・哲学がヨーロッパやアメリカを動かしたということは、一部の日本学者に向ける場合以外はほぼありえなかった。ただそうした姿勢は、今後は通用しないだろう。フランス語圏と英語圏という分断も、欧米圏とそれ以外という区分ももはやあらゆる領域で溶解し流動化してきている。
ただしこれは「好機」である。そもそも人類学の「存在論的転回」も「アクターネットワークセオリー」も「マルチスピーシーズ」も「パースペクティヴ主義」も、それが思想的にどれほどのものなのか、あるいは今後の哲学思想そのものを変えてしまう起爆性を秘めたものなのか、自由な問いを発せられる素材がそろってきている。二一世紀の思想的世界で哲学の側でも「思弁的実在論」や「オブジェクト指向存在論」が喧伝されるなか、それらとも連動する人類学的思考の位置を、すでに古典思想であるレヴィ= ストロースやドゥルーズとガタリ、あるいはそれ以前の近代思想の流れを背景として再検討することも、そこから新しい思考を「日本」から「世界」へ発信することも、いとも容易になしうるのである。
それは、もう還暦を目の前にした私のなすことというよりも、より若い人が向かう先なのかもしれない。だが、私のようなものでも、基本的な地盤整備はできるはずであるだろう。とりわけこうした人類学者が、「いまだに」レヴィ= ストロースやドゥルーズとガタリの仕事の影響を隠さず、しかもその哲学的文脈を一面では大胆に裏切りながら新しいアイデアを創出していることの意義は、フランス哲学者の立場としても多大な関心をもたざるをえない。
ゆくゆくは「日本」発でありながら、すでに日本であるか、欧米であるか、アジアであるか、そんなことも問題にならないかたちで、人類学と哲学の交錯は描かれつづけるだろう。この書物は、それに向けた研究会の、ほんの端緒をつけるだけの成果報告である。だが私以外の若い寄稿者は、そんな私の思惑をはるかに超えて、世界そのものの土俵で勝負しているのだろう。そうであり、またそのような状況が拡がりつづけることを望むのみである。
本書は、大阪大学の山崎吾郎が研究代表者となる、科学研究費基盤研究(C)「技術・制度・環境の連環からなる世界への人類学的・哲学的アプローチ」(課題番号19K01198)および、同大学の檜垣立哉が研究代表者となる、科学研究費基盤研究(C)「哲学と人類学との新たな交錯」(課題番号19K00004)の共同の成果発表として刊行される。刊行に際しては両科学研究費より出版の補助をいただいた。同じ大学ということもあり、はじめは個別に研究を進めていたが、ここ数年のコロナ状況下でZoom での研究会が中心になり、そのうちに両科研合同での研究会・合評会も数をかさねることにもなった。そうした意味で、共同で成果出版物を刊行するという流れは自然であった。繰り返すがこれはまだ中間報告書にすぎない。各人の仕事もさることながら、国際的な場面を巻き込んでの本格的研究はこれからである。
今回も出版に際して、勁草書房の関戸詳子氏には大変お世話になった。すでに一冊、編著の出版でお世話になり、現在も自分自身の単著の仕事を同時にお願いしているところであるが、いつもながら仔細きわめる指示をだしていただき感謝に堪えません。勁草書房という、哲学分野の人間にとって特別な意味をもつ出版社から、今回も編著を出版できることを、心よりありがたくおもいます。
二〇二二年九月一九日
編者 檜垣立哉
(傍点は割愛しました)










