あとがき、はしがき、はじめに、おわりに、解説などのページをご紹介します。気軽にページをめくる感覚で、ぜひ本の雰囲気を感じてください。目次などの概要は「書誌情報」からもご覧いただけます。
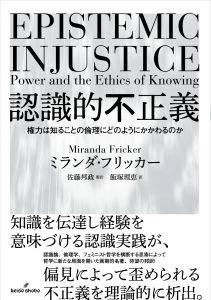 ミランダ・フリッカー 著
ミランダ・フリッカー 著
佐藤邦政 監訳、飯塚理恵 訳
『認識的不正義 権力は知ることの倫理にどのようにかかわるのか』
→〈「序文」「序章」冒頭(pdfファイルへのリンク)〉
→〈目次・書誌情報・オンライン書店へのリンクはこちら〉
*サンプル画像はクリックで拡大します。「序文」「序章」の本文はサンプル画像の下に続いています。
序文
倫理学者たちは、哲学としての倫理学がかつて言語分析という実証主義の潮流にあったという内部崩壊の状態を回顧し、徐々に倫理学の主題が再発見されたことに胸を撫でおろすことがあるだろう。その主題が再発見されたのは大部分、広く倫理的心理学と呼べるもの──すなわち、倫理的価値についての人々のリアルな経験──に対する再注目を通じてであった。つまり、瀕死状態にあった哲学の一領域は、生きられた経験にいっそう注目することで息を吹き返したのだ。私は時々、認識論者もまもなく概念分析の潮流のなかで行われてきた認識論に、同様な懐古的視線を向けるようになるかもしれないという思いを抱く。このような比較には無理もありうるかもしれないが、私には、倫理学がかつてそうだったように、認識論も現実の認識実践といっそう密接な関係を築こうとする様々な努力のおかげで徐々に拡張され、活性化されているように見える。本書は、認識的心理学をよりいっそう真剣に扱うとき──つまり、知識が獲得されたり、あるいは逆に失われたりする人々の実践を認識論の中心的主題に据えようとするとき──、認識論に開かれてくると感じられる可能性に強く動機づけられている点で、そうした努力に貢献するものである。より詳細に述べるなら、私は、社会的に位置づけられた主体が経験せざるをえない認識実践に対して関心を抱いている。この社会的に位置づけられた者として主体を説明するという考え方のおかげで、社会的アイデンティティや権力にかんする問題が〔認識論の〕中心に据えられる。この考え方は、認識的生活における正義と不正義という特定の倫理的次元を明らかにするための前提となるのだ。これが本書で探究される領域である。
本書の探究は正義ではなく、不正義に向けられている。ジュディス・シュクラー(Judith Shklar)が指摘するように、哲学は正義について雄弁に語るが、不正義に対してほとんど何も語らない。シュクラーがアートに対して同様なことを主張するのはたしかに誤っていると思うが、哲学についての彼女の指摘は真であり、非常に重要である。人文学のなかでも哲学にきわめて固有な特徴は、人間とその活動の合理的理想化に中心的関心があることである。哲学者は、正しいことを行うとはいかなることかを熱心に理解しようとする。それはそれでよい。しかし私たちが、そうした合理的理想に継ぎ接ぎだらけの部分的な仕方でしか近づけないような人間の実践についても理解したければ、そこで歩みを止めてはならない。正義に焦点をあてることで、正義が常態であり、不正義は不幸な逸脱であるという印象が生まれる。しかし、これが大きく誤っているのは明白だろう。また、不正義はつねに正義についての先行理解を通してネガティブに理解されるべきものだという印象も生まれる。しかし、先ほどより明白ではないにしても、〔正義と不正義についての〕理解のための道筋は逆のこともあるかもしれないのだ。本書での私の関心は認識活動という領域における不正義にあり、この領域では不正義が常態である場合があることは確かだと私は思っており、認識的正義にかかわるのはどのようなことなのかを明らかにするための(それどころか、認識的正義なるものが存在することを見てとるためにも)唯一の方法は、認識的不正義というネガティブな空間を検討することを通してだと思っている。本書はそうしたネガティブな空間について探究するものである。(以下、本文つづく)
序章
本書は、際立って認識的な種類の不正義が存在するという考えについて探究する。認識的不正義という一般項目に分類される現象はいくつも存在する。哲学において、正義が通常どのように捉えられているのかを考えると、認識的不正義というアイデアは、情報や教育といった認識的財(epistemic good)にかんする分配的不公正(distributive unfairness)についての思考を真っ先に喚起するかもしれない。この場合、次のような社会的行為者、すなわち、認識的財を含む様々な財に利害関心があり、「すべての人が公正な分け前を得ているのだろうか」と疑問をもつ社会的行為者が思い描かれている。認識的不正義がこのような形態をとる場合、その不正義に、まさに認識に固有と言えるようなものは存在しない。というのも、ここで扱われる財が認識的財として特徴づけられうるのは、ほとんど偶然と思われるからである。それに対して、本書のプロジェクトは、認識的不正義のなかでも認識に固有な種類の二つの形態に焦点をあて、それらの不正義の本質が、もっとも根本的には、人々がとりわけ知識の主体としてもつ能力にかんして被る不正にあることを立証するものである。以下では、これらの不正義を証言的不正義(testimonial injustice)と解釈的不正義(hermeneutical injustice)と呼ぼう。証言的不正義が生じるのは、聞き手が、偏見のせいで話し手の言葉に与える信用性(credibility)を過度に低くしてしまうときである。一方、解釈的不正義が生じるのは、それに先行する時点、すなわち、人々が自分たちの社会的経験を意味づける際に、集団的な解釈資源にあるギャップのせいで不公正な仕方で不利な立場に立たされてしまうときである。一つ目の証言的不正義の一例は、警察官が特定の人々を、その人々が黒人であるがゆえに信じない場合だろう。二つ目の解釈的不正義の一例は、たとえば、セクシュアル・ハラスメントという、必要不可欠な概念がまだ存在しない文化において人々がハラスメントに苦しんでいる場合だろう。証言的不正義は信用性の調整における偏見によって引き起こされ、解釈的不正義は集団的な解釈資源の調整における構造的偏見によって引き起こされると言えるかもしれない。
本書全体の目標は、もっとも基本的な日常の認識実践のなかでも、次の二つの実践、すなわち、他者に語ることで知識を伝えること、および、私たち自身の社会的経験を意味づけることについての倫理的側面に光を当てることである。これから議論される倫理的特徴は、認識的な相互交流における社会的な力(social power)の作用から生じるため、その特徴を明らかにすることは、認識実践の政治性(politics)を明るみに出すことでもある。英米の認識論の文脈では、認識的関係について私たちがどのように考えるのかについての政治的意味合いを部分的に含む考え──認識的信頼は社会的な力と否応なく結びついているかもしれないという考えや、社会的不利益は認識上の不正な不利益を生みだしうるという考え──は、まともに取りあげられない傾向にある。ひょっとすると、こういった考えは、ポストモダニズムがその極致であった相対主義的な見方と必然的に結びついていると前提されているために取りあげられにくいのかもしれない。あるいは単純に、伝統的な認識論がその内部で生みだす、個人主義や合理的理想化を不可欠だと見なす理論的枠組みが、このような〔認識実践の権力構造についての〕問いが認識論に固有の問題といかなる関係にあるのかをきわめて見えにくくしているからかもしれない。どのような説明がなされるにせよ、本書の推進力となるのは、伝統的に追究されてきた認識論が、私たちの認識行為にかんする倫理的側面と政治的側面を明らかにするのに有益ないかなる理論的枠組みも欠くことで貧弱化している、ということである。英米の伝統では、フェミニスト認識論だけがこの問題点を果敢に指摘し続けることで唯一と言える声を上げてきたが、私は、徳認識論がこのような諸問題を有意義に論じることのできる一般的な認識論的表現方法を提供することを示したいと思っている。
似たような盲点は倫理学にも見出される。これまでの倫理学が、私たちの認識行為を検討の対象としてこなかったことは、先ほどと同様に残念なことだと思われる。しかし、倫理学の場合、私たちの認識的生活における正・不正に注意を向けてこなかったのは〔認識論の場合よりも〕いっそう偶然的であり、倫理学が歴史的に、もっぱら二階の理論的問題に取り組んできたという一般的な説明以上に特別な診断所見につながるものは何も見当たらないと思われる。いずれにしても、以上の伝統的背景を考えると、本書は倫理学の研究書とも、認識論の研究書とも明快に分類できるものではない。むしろ本書は、倫理学と認識論という、哲学の二つの異なる領域のあいだの広漠たる境目について、あらためて解きほぐすものなのである。
これまでの哲学分野のなかではポストモダニズムこそが、私たちの認識実践についての倫理的側面や政治的側面を探究するための理論的空間を、とりわけ多くのフェミニスト哲学者に約束しているように見えていた。ポストモダンの哲学的思考のもつ非常に大きな魅力は、理性と知識を社会的な力が発揮される文脈にしっかり位置づけた点にあった。理性という権威に対する長きにわたる懸念は、〔その懸念の〕政治性がいっそう色濃く反映されるように表現しうる、新たな、一見すると急進的変化をもたらす理論的文脈を獲得した。しかし、それもおおかた、虚しい望みにすぎないことが判明した。なぜなら、極端なポストモダンの心酔者によるかなりの数の作品があまりにも極端に還元主義に傾いたからであり、また、ポストモダニズム精神の背景にある原動力が、正義と不正義にかんする様々な問いを理性と社会的な力がどのように絡み合っているのかという点と関連づけて論じる前向きな意志として現れるのではなく、理性についての擁護不可能な幻想にほかならないとする主張として現れたからである。理性というカテゴリーそのものへの懐疑、および、理性を権力(power)作用に還元しようとする傾向は、「権力は、合理的主体としての私たちが取る行動にどのように影響を及ぼしているのか」という、私たちがまさに問うべき問題を実際には先回りして封じてしまう。というのも、そのせいで、私たちが理由に基づいて思考することと、単に権力関係が私たちの思考に作用しているにすぎないこととの区別が消え去る、あるいは、少なくともその区別が見えにくくなるからである。正義への問いが、私たちの認識実践との関係においていかなる仕方で立ち現れるのかに関心をもつとき、還元主義の傾向は次の必要不可欠な区別、すなわち、十分な理由があって他者の言葉を拒否することと、単なる偏見に基づいて拒否することの区別を覆い隠す。こうしてポストモダニズムは、認識実践における正義と権力についての様々な問いを考えるための理論的空間を創りだすどころか、逆に、そのような問いを巧妙に封じるのであり、そのため、ポストモダニズムが認識論的な関係性について述べてきたことは最終的に少しも進歩主義的な方向に向かうことなく、何らかの進展があるにしても保守的なほうへ戻ってしまったのである。
しかし、ポストモダニズムがかつてざわめいていたところで、私たちは沈黙ばかりしていてはならない。というのも、私たちはきっと、理性が社会的な力とどのように絡み合っているのかを論じるための別の、より良い方法を見出すことができるだろうからだ。では、そうした議論はどのような形態をとるべきなのだろうか。この問いに対する一つの答えは、そうした議論は、私たちの認識実践を社会的に位置づけられたものとして説明する文脈において、一階の倫理的問題を検討するという形態をとるべきだ、というものである。私たち人間の従事する実践を社会的に位置づけられたものとして説明するということは、〔認識実践への〕参加者を社会的な力関係を捨象して捉えるのではなく(伝統的な認識論は、ほとんどの社会認識論も含めて、参加者をこのような仕方で捉えてきた)、他者との相互の力関係のうちにあり、社会的タイプとして行動する人々として捉える、ということである。社会的に位置づけられた者として主体を説明するこのような考え方のおかげで、私たちが認識実践を説明しようとするとき、権力、および、時に合理的で時に反合理的な権力の律動にかんする様々な問いがおのずと喚起される。哲学的問題の多くは、連綿と受け継がれてきた、最大限に抽象化された人間主体という考え方によってもっとも適切に扱えるかもしれないが、そのような考え方だけに自分自身を狭めると、私たちが導きだせる哲学的問いや洞察の種類を制限することになり、結果的に哲学の扱えるレパートリーが不必要に貧しくなる。対照的に、社会的に位置づけられた者として主体を説明する考え方から出発するならば、権力、理性、認識的権威のあいだの様々な相互依存を突き止めることができ、私たちの認識実践に不可欠な認識実践の倫理的特徴を明らかにすることができる。このような探究を通して、最終的に、私たちの認識行為はどのようにして、いっそう合理的なものとなると同時にいっそう正義にかなうものとなるのかを理解することが重要なのである。(以下、本文つづく。注番号と傍点は割愛しました)









