あとがき、はしがき、はじめに、おわりに、解説などのページをご紹介します。気軽にページをめくる感覚で、ぜひ本の雰囲気を感じてください。目次などの概要は「書誌情報」からもご覧いただけます。
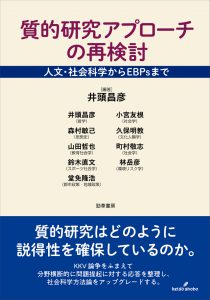 井頭昌彦 編著
井頭昌彦 編著
『質的研究アプローチの再検討 人文・社会科学からEBPsまで』
→〈「序章 なぜ質的研究アプローチを再検討すべきなのか」「編者あとがき」(pdfファイルへのリンク)〉
→〈目次・書誌情報・オンライン書店へのリンクはこちら〉
*サンプル画像はクリックで拡大します。「序章」「編者あとがき」本文はサンプル画像の下に続いています。
序章 なぜ質的研究アプローチを再検討すべきなのか
井頭昌彦
本書は,社会科学方法論の一環として質的研究アプローチを再検討することをテーマとしている.以下では,このテーマの内容と意義について説明することで本書全体の構想を示し,その後で各章の概要を述べていくことにする.
まず,「質的研究アプローチ」という語で何を指しているかについて説明しよう.社会科学においては,研究手法やそこからの知見を区別するラベルとして,「量的quantitative/質的qualitative」という対比がしばしば用いられる.ざっくりとしたイメージとしては,「量的研究」と言えば数量化されたデータを用いて統計分析を行うような研究が想起され,「質的研究」としてはフィールドワークやインタビューの記録あるいは文書などを用いてその解釈を行うような研究が想起されることが多いだろう.ただし,両者を弁別する基準が複数あり,境界が曖昧であることは広く指摘されている.本章では,とりあえずの規定として,以下で触れる「KKV 論争」における区別の仕方を暫定的に採用して話を進めることにしよう.すなわち,質的研究と量的研究の区別を,①用いられる測定尺度(名義尺度or 順序尺度までを質的データとする),②標本の数の多寡(10-20 が境界線となることが多い),③統計的検定を行うか否か,④個々の事例の詳細に立ち入らず広く浅い分析をするか詳細についての濃密な分析をするか,という四つの基準で捉えつつも,明確な境界線は与えられないものとして理解するのである.
次に,質的研究アプローチを「社会科学方法論の一環として」検討するということの趣旨についてだが,これは,他の研究手法との比較を視野に入れた方法論的議論を行う,ということを意味している.まず,前提として,質的研究アプローチに分類される研究手法は無数に存在する.たとえば,サトウタツヤ・春日秀朗・神崎真実『質的研究法マッピング』(2019)は,ライフストーリー法,KJ 法,グラウンデッド・セオリー・アプローチ,エスノメソドロジーなど様々な質的研究法を幅広く紹介しつつそれぞれの特徴をタイプわけして整理した便利な書籍であるが,そこに登場する研究法の総数は26 にも及ぶ.ここで重要なのは,こうした質的研究法に共通した「論理」ないし仕組みというものは基本的には想定できないということである(これは量的研究における様々な推論手法が統計学という中核を共有した形である程度統合的に描かれうることと対照的である).質的研究に関するこうした事情がもたらすのは《分野や手法を跨いだ対話のハードルが高くなる》という事態である.もちろん,それぞれの質的研究アプローチの具体的な進め方や作業段取りについては,方法論的な洗練化が進んでいるし,掘り下げた解説を行う充実した教科書や入門書も多く執筆されている.他方で,様々なアプローチの間に共通した「論理」ないし仕組みが存在しない場合には,そうした洗練化が進むほど,相互の対話は難しくなる.すなわち,どういう問題意識のもとでどういう事象をとりあげるのか,事象のどういう側面に着目するのか,どういう理路に支えられたどういう手法を用いるのか,それによって何をどこまで明らかにするのか,といった基本的枠組みが共有されにくくなることにより,研究の眼目や説得性を互いに理解し合うことが困難になるのである(この問題は,基本枠組みがある程度統合された形で共有・標準化されている量的研究との対話においてより顕著になる.後述するように,本論集の企図の一つはこの点への対処にある).こうした問題に対処する上では,従来の教科書や入門書に見られる《当該手法を用いてこれから研究しようとする初学者を想定し,自分達の研究の進め方に焦点化してそれを詳細に説明する》という対自的なスタンスを少し切りかえ,《別の研究手法とその基本枠組みを体得している人々を想定して,それとは異なる研究手法の理路とその合理性を背後的な問題意識と共に理解してもらう》という対他的なスタンスを組み込むことが有効だろう.質的研究アプローチについて「他の研究手法との比較を視野に入れた方法論的議論を行う」ということで想定しているのは,この後者のスタンスのもとでの議論である.
しかし,なぜ特に質的研究アプローチをとりあげて,他の研究手法との対話を想定した事情説明をする必要があるのか.その背景的理由の一つとして挙げられるのは,近年では質的研究がその信憑性や意義に関して疑問視されることがしばしばある,という事実である.そうした意見は,特に,量的研究を行う学問分野・領域を背景とする形で提示されることが多いが,このような動きには(その正当性はともかくとして)理解できる部分が全くないわけではない.まず,量的研究方法の中核にある統計的手法は様々な学術分野・調査研究領域で大きな成果をあげ続けており,その実績はこの手法に対する信頼を生み出している.また,統計的手法にはそれを専門的に研究する分野として統計学が存在し,そこでの集中的な検討の結果が統計的手法の方法論的洗練化を強力に推し進めてきた,という背景も重要だろう.こうした「確固たる手法」がもっぱら用いられる分野・領域の内部にいる研究者が《統計的手法こそが方法論的スタンダードである》という認識に至るのは,それがどこまで正当かは別にしても,ある意味で自然なことではある.とすれば,そうした人々が,統計的手法の理路を共有しない質的研究に対して違和感を覚えたり,統計的手法の考え方を前提して質的研究を評価することでその信憑性を疑問視したりすることも,理解できないことではない.
こうした流れをある意味で体現するものとして,キングほか『社会科学のリサーチ・デザイン――質的研究における科学的推論』(King et al. 1994=2004/以下,KKV)をあげることができるだろう.国際関係論・政治学の研究者であるキング,コヘイン,ヴァーバの3 名によって執筆された同書は,質的研究に対する助言を目的としたものであり,扱える事例数が少ない場合でもある程度説得的な仕方で主張を展開するための具体的な方法を提案している.しかし,その一方で,質的研究の問題意識や手法の内実に対するKKV の理解が不十分であったこと,量的手法(具体的には回帰分析)の理路を前提とした上で質的研究者への助言を展開してしまったことにより,質的研究者たちから多くの批判的応答を招くことになった(この「KKV 論争」については本書第1 章および第2 章で中心的に検討される).とはいえ,その後もKKV は社会科学方法論における必読文献の一つであり続けており,近年でも,質的研究の意義や信憑性について吟味検討される際には《検討すべき重要な問題提起を行った先行研究》として参照されている.つまり,統計的手法の考え方を前提して質的研究を評価したりその信憑性を疑問視したりするというこのような傾向は,いまなお存在感をもっているのである.こうした状況下では,先述の《別の研究手法とその基本枠組みを体得している人々を想定して,それとは異なる研究手法の理路とその合理性を背後的な問題意識と共にわかってもらう》という対他的スタンスが必要になる場面は多いし,統計的手法の実績と普及度合いに鑑みるならば,その必要性はなおさら高いものとなるだろう.
もう一つの背景的理由として挙げられるのは,証拠に基づいた政策立案(EBPM)をはじめとした「証拠に基づいた実践(Evidence Based Practices: EBPs)」の盛況ぶりである.上述の対他的スタンス,特に量的手法の理路を背景とする人々に対するそれが質的研究サイドに求められることとEBPs がどうつながっているかを理解するためには,右の二つの図表を見てもらうのが早いだろう.これらは,しばしば「エビデンス・ヒエラルキー(ハイアラーキー)」と呼ばれる図表であり,上に行くほど証拠としての質が高いとされるが,この図表では質的研究アプローチから得られる知見は(位置づけるとしたら)よくても下の二つに位置づけられることになってしまう.実際には,EBPs それ自体について議論する専門研究者の間ではこの「エビデンス・ヒエラルキー」は否定的に言及されることが多く,少なくともこれを無批判に当然視するような捉え方は全体としては放棄されつつある.他方で,EBPs に関与する多様な関係者のすべてにそうした専門的理解の共有を期待することは難しいため,これらの図表が一人歩きしてしまう恐れは常に存在する.たとえば,不十分な理解のもとでこの図を安易に受容してしまった人が,質的研究全体を劣位に位置づけた上で批判する,といったことは大いに懸念されるだろう.こうした事情が,上述の対他的スタンスによる方法論的議論が質的研究者たちに要請されるもう一つの背景的理由になる.
上で述べたように,質的手法のそれぞれについてそれを実践するための優れた入門書や教科書はすでに多く書かれている一方で,量的研究手法の理路を内面化した読み手を想定した対他的なスタンスで書かれたものはそれほど多くない.そして,これまで見てきたように質的研究手法に対する(しばしば十分な理解を伴わないままでの)批判的な視線が増えつつある現状を踏まえるなら,特に「量的研究者」から向けられがちな疑問や疑念への応答につながる形で彼我の相違を理解させるような説明のニーズは高まっていると言える.質的研究方法論に関する先行書籍群に加えて本書をさらに公刊することの意義の一つはこの点にある.
こうした状況認識を踏まえ,本書では,第3 章から第9 章にかけて,思想史・教育学・社会学・アクション・リサーチ・政策学・文化人類学の各分野における質的研究のあり方と分野事情の解説が行われる.また,第10 章では統計的因果推論の詳細な整理を通して量的手法がどのように質的知見に依存しているかが確認される.これらが本書のメインコンテンツとなる.もちろん,それぞれの学術分野の内部での質的手法・質的知見の用いられ方にはかなりのバリエーションがあるし,本書で扱われたもの以外にも質的手法・質的知見が用いられる学術分野は多数ある.したがって,本書の各章での議論は質的研究全体の一部を扱ったものでしかないし,各章のそれとは違った応答や事情説明の仕方が無数にありうるはずである.本書の議論は,そうしたさらなる応答・事情説明について考えていく上での手がかりにもなるだろう.
以下,各章の内容を概観していく.なお,それぞれの章はある程度独立して読むことができるように工夫されている.
第1 章「質的研究方法論を再検討する契機としてのKKV」と第2 章「KKV論争の後で質的研究者は何を考えるべきか――論争の整理と総括」では,いまや社会科学方法論の古典となったKKV と,それに端を発する「KKV 論争」が主題的に取り扱われる.著者の井頭昌彦(哲学)は第1 章においてKKV の概要を整理したのち,第2 章においてKKV に対する「質的」陣営からの批判的応答群を論点ごとに整理し,それぞれにコメントを加えることで,これまでの論争の全体像を概観している.このKKV 論争は,質的研究方法論を論ずるうえで参照すべき重要な先行研究であり,本書第3 章以降においてさらなる争点や応答可能性を描き出すための《土台》という位置づけを持つ.なお,第1章と第2 章については,質的研究について具体的なイメージを持っていた方が理解しやすい場合があるので,読者によっては以降のいくつかの章を読んでから戻ってきた方がよいかもしれない.
第3 章以降では,KKV 論争を視野に入れつつ,それぞれの学術分野の事情を踏まえた上での状況説明や応答がなされる.
第3 章「個別事例研究は何を目指すのか――歴史研究における質的アプローチ」において森村敏己(思想史)は,歴史学において質的アプローチがその明確な方法論的自覚とともに重視されるようになった契機を,1960 年代以降に隆盛を誇った数量的歴史学への反動にみてとることから議論をはじめている.そして,質的歴史学の問題意識と有効性について,ミクロストリアを例として挙げつつ,過去に生きた人々の主体性を扱えること,社会構造の変化の契機を説明できること,そして例外的な事象に観察対象を絞ることで社会構造と個人の軋轢,あるいは社会構造の空隙や矛盾を見えやすくすること,という形で説明している.他方で,質的歴史学に指摘されうる課題の一つとして森村が指摘するのは,構造と主体性のバランスである.社会構造の中に埋没しない主体性を重視するために例外的な個別事例をとりあげる場合であっても,社会構造が主体性をある程度限界づけていることは認められねばならない(研究対象の言動のうちに社会構造が一定程度反映されていなければ,個別事例の分析を社会構造の再検討に結びつけることはできない).それゆえ,構造と主体性のバランスをとりながら叙述の説得性を確保する必要があるのだが,その基準を明確にすることは難しく,この点について森村は「研究者の資質,心構え,自覚,経験といったものにその解決が委ねられがちなのではないだろうか」としている.質的歴史学のもう一つの課題としてあげられるのは解釈の妥当性の確保と検証である.この点について森村は,KKV の問題意識を受け止めて政治思想史のテキスト解釈に関するガイドラインを提示したブロー(2019) に言及しつつ,そうしたガイドラインは扱うテーマや事例によって遵守しがたい場合もあること,そしてこの問題は量的アプローチに訴えても解決されないことを指摘して,この章を締めくくっている.森村の論考は,質的な歴史研究について,その成立経緯・問題意識・認識関心を含めた包括的な理解を提供するものであり,量的な研究との差異や関係性について考えるための有益な参照点となる.
第4 章「教育研究における質的研究方法論の位置――教育社会学の視座から」では,山田哲也(教育社会学)が,教育という営みを対象とする様々な学問領域の一つである教育社会学の視点から,質的研究方法論についての現状解説を行っている.そこでは,教育という事象に固有の事情として,入力(教育的関与)がどういう出力(人格形成)につながるかが学習者の自由意志次第で変わりうることが指摘され,これによりKKV が社会科学の中心的な目的に据える一般的主張や因果的主張に困難が生じるとされる.すなわち,個別事象の連鎖からなりたつ教育的コミュニケーションについての知見を一般化することが困難になり,教育的な関与によって意図通りの帰結をもたらそうという厳密な因果制御も期待できなくなるのである(「技術欠如」).教育研究においてこうした難題がどのように対処されているかについて,山田は「因果プラン」や「混合研究法」に言及しつつ解説を行い,個別具体的な場面における教授学習行為については質的なアプローチが選好される一方,制度化の度合いが高い局面になると量的なアプローチが選ばれる傾向がある,と整理する.また,山田は,教育社会学領域における質的研究のレビューや自身の査読経験を踏まえつつ,質的アプローチの信憑性・説得性評価の基準に関する現状を整理している.そこでは,反証可能性の確保や解釈の論理的一貫性といった一般的な基準のほか,教育研究が現場の教育や制度設計といった実践とつながっていることに由来する特有の評価基準の存在についても触れられている.この章の議論は,教育社会学分野において「ゆるやかに共有されている」信憑性・説得性基準を可能な限り明確に示していることに加え,そうした基準が研究対象となる教育行為の理解の仕方および教育学固有の事情とどのように関係しているかについても明らかにしており,包括的な分野理解を提供するものと言える.
第5 章「『量』対『質』をプラグマティックに乗り越える――生成的因果,GTA,移転可能性」では,鈴木直文(スポーツと政策)が,グラウンデッド・セオリー・アプローチ(GTA)に依拠した自身の研究を振り返りながら,KKV に対する批判的検討を行っている.そこで扱われる論点は多岐にわたり,研究の説得性を「データの総量」によって確保しようとする点で量的研究と質的研究が同形であること,生成的因果generative causation という構想に照らすとKKV が想定している因果理解は「狭い」と言えること,プラグマティズムを背景としたGTA の分析の仕方とそこでの検証基準としての「理論的飽和」概念についての説明,社会構造の可変性・流動性を踏まえた場合には「母集団」なるものを想定できない現象が社会には多くみられること,そうした研究対象を扱う際には「サンプルの挙動から母集団の挙動を推定する」という推論形式とは異なる質的手法がより適切なものになること,などが手際よく論じられている.以上を踏まえた上で,鈴木は,統計的な因果的推論が妥当するのは対象となる現象についてその母集団が措定できる場合(すなわち概念の揺らぎの少ない,安定的な社会構造が想定できる場合)だけであり,それは社会の総体からみれば極めて限定的な状況だ,と述べる.鈴木の詳細かつ広範な議論は,《何が適切な研究方法であるかは,研究対象がどのようなものであるか,あるいは研究対象をどのようなものとして想定するかに応じて異なりうる》という,研究方法論を論じる上での基本原則に改めて立ち返ることを我々に要求するものとなっている.
第6 章「なぜ政策学では1 事例のみの研究であっても評価されるのか」で堂免隆浩(都市政策・地域政策)は,「社会問題の解決に関する学」としての政策学において,単一事例研究がどのように扱われているかを論じている.そこでは,日本都市計画学会・日本計画行政学会・社会政策学会による三つの学術誌をとりあげ,論文採否基準と掲載論文における単一事例研究の総数と割合を確認した上で,それぞれの単一事例研究論文がどのような狙いを持ったものであるかを六つのタイプに分類する,という膨大な作業が行われている.その中で堂免が指摘することの一つは,何が政策学に特有の評価基準であるかはある程度識別できる,ということだ(有用性,先駆性,適時性,緊急性,実務を含めた応用可能性,有益性).また,堂免は,学会員における民間企業の実務者や行政担当者の割合が相対的に多い学会では事例研究に対するニーズが大きくなる,という可能性についても指摘している.この点については,直面している社会問題にすばやく対応するために日頃から試行錯誤している実務者にとって,政策課題についての解決方策や目指すべき《望ましい状況》についての検討結果の実例を参照することに大きな意義がありうるから,という仕方で説明されている.こうした諸々を踏まえつつ,堂免は最後に,政策学における事例研究を四つのタイプ(政策史,概念形成と仮説形成,別事例への知見応用を想定した事例分析,基礎資料の共有)に分類した上で,それぞれについて「事例研究を遂行し論文を執筆する上でのガイドライン」を提示している.こうした取り組みは,質的研究においてしばしば暗黙のうちに運用されている質保証基準を可能なかぎり明示化しようとする試みの端緒として評価できる.
第7 章「事例の観察と知見の一般性の関係――会話分析の場合」では,小宮友根(社会学)が,エスノメソドロジー/会話分析(EMCA)の観点から,KKV による提言の不適切さについて論じている.小宮によれば,KKV が「極端な解釈主義」に対して批判的検討を加える際に例示されていたのがまさにエスノメソドロジー研究の考え方である.そこでは研究者側のカテゴリや理論を研究対象に適用するのではなく「行為者自身にとっての意味」を明らかにすることが課題とされるが,この課題がKKV の言う「科学的」推論によって達成されると考える点でKKV は間違っている,と小宮は主張する.この点を説明するために,小宮は,まずKKV にも登場する《ウインクに関するライルとギアツの議論》をとりあげ,そこで行われているのがウインクという概念を構成する規則の同定作業であることを指摘する.そして,その作業は,KKVが想定するような「事例で観察された既知の事実から未知の事実を推論する」という理路ではなく,ウインクについてすでに確保されている概念的把握を元手にしつつ事例を参照することで構成的規則の内実を記述していくという仕方で進められること,それゆえKKV の方法論的提言が当てはまらないことが説明される.同様のことは,より洗練された研究例として挙げられる会話分析についても指摘される.小宮によれば,《質問を受けたら答えを返すべきだ》といった会話を構成する規範ないし規則は,それを理解していないとそもそもある発話を《質問》や《答え》として認識することはできないようなものであり,会話事例のうちにそうした規則を見出し記述する作業は《個別事例の観察から仮説を立ててそれを検証する》という手続きには馴染まない.彼の言葉を借りるなら,「会話分析はそもそも,KKV がいう意味での『科学的推論』をおこなう研究ではない」のだ.もちろん,社会的実践を成り立たせている規範や規則についての研究者の分析が間違ったものになる可能性(不確実性)は当然あるが,それは,事例の収集や比較を通じて(因果推論の精度向上ではなく)規則の記述をより明確なものにするよう努めること,他の研究者が再分析できるようにトランスクリプトを提示しながら知見の報告を行うことなどによって対処されるものであり,KKV が前提するようにバイアスや有効性といった形で評価・対処されるものではない.こうした小宮の議論は,KKV の提言が当てはまらない質的研究の存在を明確に示すものであると共に,質的研究において重要な位置づけを持つにもかかわらずKKV 論争において十分な扱いがなされてこなかったいわゆる「解釈主義」の路線について理解を深めるうえでも大きな意義を有している.
久保明教(文化人類学)は,「質と量はいかに関わりあうか――現代将棋における棋士とソフトの相互作用をめぐって」と題された第8 章の前半において,文化/社会人類学の問題意識がどのような仕方でKKV の問題意識とすれ違っているかについて説明している.久保によれば,文化相対主義やポストモダニズムを背景にする人類学において,学術的主張の有効性は,①「彼らにとっては○○である」は妥当か,②「私たちにとっては××である」は妥当か,③「彼らにとって○○であることを私たちにとっては××であるものとして理解する」ことはいかなる妥当性や効果をもつのか,という相互に絡み合った三重の観点から評価される.そして,KKV の議論は②や③と切り離して考えられた限りでの①についてのみあてはまりうるものであり,それゆえKKV の問題意識は(特に③に見られる「文化の翻訳」を固有の関心事とする)人類学のそれと噛み合わない,とされる.この章の後半部分では,以上のような特徴を持つ文化/社会人類学的な分析の具体例が提示されている.そこでは,将棋ソフトという異他的なものの指し手を(困惑しつつも)自分たちの将棋文化との関係性において捉え直そうとする棋士たちの語りと実践がとりあげられ,対戦時の状況を表現する言葉の意味がズラされつつ状況解釈が与えられていく過程についてヴィヴェイロス・デ・カストロの言う“Controlled Equivocation” を手掛かりにした分析が提示されている.久保の議論は,人文学・社会科学にはKKV論争において設定されている議論構図をはみ出るような問題関心に基づいて展開される研究領域が存在するという事実を明快な形で例示するものであり,またそうした研究に対してKKV のような仕方で不確実性評価を求めることの適切性について再検討を強いるものとなっている.
第9 章「社会学における『素朴な折衷主義』はなぜ(あえて?)『失敗』してきたのか――〈データサイエンス〉状況を追い風としつつ,やり過ごすために」において,町村敬志(社会学)は,日本の社会学における質的研究と量的研究の関係を回顧することから議論を始めている.それによれば,「社会的なもの」の独自のリアリティに迫ることを重視する社会学では,方法に囚われず質的研究と量的研究を併用して研究を進めることが一般的であり(「無節操な,しかし活力ある折衷主義」),2000 年頃の方法論的洗練化に伴う分断が一部にありつつもこの姿勢は基本的に保持され続けてきた,とされる.町村は社会運動論をめぐる自身の研究履歴に照らしてこの点を確認しつつ,質的研究と量的研究を同一の論理のもとで統合しようとするKKV の方向性はそうした社会学の基本姿勢と大きく対立するものではない,と指摘する.むしろ,KKV という著作は多数事例を扱う量的研究のみが「科学的」だと考える研究者に対して少数事例を扱う質的研究の意義を主張するための「技法と心構え」を記したものなのであり,この意味においてKKV の議論は「社会科学系のあり方をより豊かにする契機」として捉えるのが適切だ,というのが町村の見立てである.他方で,町村は,素朴な計量化をもとにEBPM 的アプローチを強引に推し進めるような流れ(素朴な「データサイエンス」状況)に対しては警戒を示す.もちろん,証拠に基づいて政策遂行過程を透明化することは一般的にいって望ましいことである.しかし,町村によれば,政府による「統計改革」の中でEBPM が主役化されていった結果として生じたこの流れには「因果推論テクニック活用の公的制度化」という側面があり,そこには,公的統計の「エビデンス」化の進行によってEBPM にとってのみ都合のよい偏ったデータや利用環境が作り上げられてしまう恐れや,統計やEBPM を扱う人材育成が過度に強調される懸念がある,というのだ.同章の結論部分において町村は,こうした状況に対して人文・社会科学系の研究者がとりうる態度類型をいくつか例示しつつ,論争や対立も含めた多様性こそが人文・社会科学分野の知の基盤にあることを指摘し,立場選択の自由と闊達な意見交換のルートを確保することの重要性を強調する.広範な視野と長大な射程を備えた町村のこの論考は,社会学分野についての掘りさげた理解を与えるに留まらず,我々が現在の学問的・社会的状況における諸課題に取り組む上での一つの羅針盤としても機能しうるだろう.
第10 章「Evidence-Based Practices にとって『良いエビデンス』とは何か――統計的因果推論と質的知見の関係を掘り下げる」では,林岳彦(環境リスク学)が量的研究と質的研究との繋がりについて統計的因果推論の視点から整理を行っている.この章は,社会利用の観点からエビデンスの「良さ」を評価するための五つの「観点軸」について説明するパート(第1 節),統計的因果推論のプロセスを分解した上で各作業段階における質的知見と量的知見の関係性を整理するパート(第2 節),証拠に基づいた実践(EBPs)に内在する「固有性と法則性の往復運動」の側面を論じるパート(第3 節),という三つの議論によって構成されている.この論考は,統計的因果推論およびエビデンス実装において見られる様々な形での《質的知見への依存》のあり方について極めて明快かつ体系的に説明したものであり,EBPs の従事者たちにとっても非常に有益な見取り図を与えるものとなっている.このように同章では,全体として質的知見の重要性を強調する方向性で議論が展開されているのだが,その一方で林は,質的研究者達に課題を突きつけることも忘れていない.というのも,締め括りとなる第4 節で述べられているように,質的知見が重要であるという事実は「現状の質的研究アプローチ自体の妥当性を何ら担保しているわけではない」からである.彼自身の印象的な言葉を引くなら,「学術共同体の中で築かれた内輪の相場観の中で,『なんとなく正当化された気になっている』だけになっている可能性はないだろうか?」という問いかけに応答すること,そしてそのために「学術共同体自らが何らかの質保証のための基準を可能なかぎり明示化」することが質的研究者たちにも求められているのである.
終章となる「『質的』『量的』をめぐる社会科学方法論争の整理――科学哲学の視点から」では,井頭昌彦(哲学)が,パラダイム論の後継理論である「網状モデル」に定位しながら,研究方法論についての様々な見解がどのように整理され,それらの間での合理的な議論がどのようになされうるかを論じている.網状モデルのもとでは,研究方法論についての見解の相違は,研究目的の観点から天下り式に裁定されるものとしてではなく,理論・研究方法・研究目的の間に成立することが期待される斉合性関係に基づいた「相互調整と相互正当化」という形で合理的に調停されうるものと理解される.井頭によれば,この網状モデルとそこで想定される斉合性関係を参照することは,社会科学方法論における論争をより効果的に前進させる上で役に立つ.具体的には,異分野に対して自分たちの研究方法の合理性を説明する際の手がかりとしても,よく知らない分野に対して敬意を払い安直な決めつけをしないための歯止めとしても,ある分野の研究方法を内在的観点から批判しより合理的なものへと改善していく際の参照軸としても,これらの道具立てが有益だというのである.こうした点を踏まえた上で,さらに井頭は,網状モデルに定位することで質的研究方法に対する多様な擁護論を統一的な視座のもとで整理できることを示しつつ,それによって「KKV 的な提言への応対の仕方について十分な検討がまだ行われていない質的な研究伝統」に関してもその方法論的合理性を説明する擁護論の展開をサポートできる,という可能性を示唆することでこの章を締め括っている.
なお,各章の間には,「コラム」という形で,様々な学術領域における研究方法論関連のサーベイを配置している.とりあげられた主題と執筆者は以下のとおりである.
-因果メカニズム(清水雄也,小林佑太)
-ミクロストリア(鈴木良和)
-欧米の教育学研究における質的研究方法論の系譜(栗原和樹)
-社会政策研究における質的アプローチ(山邊聖士)
-政治学方法論(狩谷尚志)
-方法論の定式化に抗する人類学(谷憲一)
-フェミニスト方法論(永山理穂)
これらを参照することで,本書各章の議論をより広範な議論文脈のうちに位置づけて理解することができるようになるはずである.また,各コラムでは研究方法論史における重要文献が多数とりあげられているが,そのうちの一部および関連論文についてのレビューがWeb 上にまとめて公開されている(https://www.soc.hit-u.ac.jp/~methodology/review.html).論文タイトルをクリックすると各論文についての詳細な内容解説レジュメを見ることができるので,興味のある方は是非参照されたい.
*本稿はJSPS 科学研究費補助金(19K00028)及びJSPS 課題設定による先導的人文学・社会科学研究推進事業:領域開拓プログラム「分野間比較を通した質的研究アプローチの再検討」(2020 年度-2022 年度)による研究成果の一部である.
(図表、注、傍点は割愛しました。pdfでご覧ください)
編者あとがき
この「あとがき」では,本書成立の土台となった研究会(先端課題研究19「質的研究アプローチの再検討」(2020-2022)) について触れておきたい.この研究会は,KKV の議論を踏まえた上で質的アプローチを重視する研究者たちに意見を求め,国際関係・政治学分野でなされた論争の範囲を超えるような応答の可能性を検討し,その先に,質的研究と量的研究の関係性についてよりよい理解を得よう,という企図のもとで立ち上げられたものである.
ただ,研究会の準備を進める中で一つ予想外だったのは,KKV について「名前を聞いたことはあるけど読んだことはない」あるいは「名前すら聞いたことがない」という人がメンバーのほとんどを占めていたことだった.そこで,2020 年6 月と7 月に行われたキックオフミーティングは,KKV の内容解説とそれへの批判的応答の整理に充てられることになった(これが本書第1 章と第2章の原型になっている).
もう一つ予想外だったのは――振り返るとこれは筆者の認識の甘さでしかなかったのだが――研究会メンバーからのKKV に対する反発が想像以上にキビしいものだったことである.そうした反発は,KKV に対してだけでなく,KKV への既存の応答群が基本的にKKV の土俵にのった上でなされていることに対してもしばしば向けられた.研究会はディスカッションの時間をかなり長くとって行われたが(一回の報告と討議で5 時間を超えることもあった),そこでは,KKV の主張がいかに的外れなものであるかの指摘から始まり,自分たちの研究関心がKKV 論争の枠組みのうちにいかに位置づけにくいものであるか,KKV の提言がいかに現実離れしたものであり何を根本的に見落としているか,といった論難が続出したのである.
もちろん,研究会の主旨からしても,その先に見据えていた論集の出版に向けた準備としても,KKV 的な見方に対する批判的意見が様々な角度から出されるのは重要なことだったが,他方で,運営サイドとしてはそれなりに神経をすり減らすことになった.というのも,質的研究者がメンバーの大半を占めていること,KKV の内容をある程度把握しているメンバーが筆者以外にあまりいなかったことにより,ディスカッションにおいて筆者がKKV の問題意識を代弁する機会がはからずも増えていったからである(たとえば,強い反発と共に出される様々な意見に対して筆者から「KKV だったら〜と返してくると思うんですけど,それにはどう回答しますか」といったコメントをする機会は非常に多かったと思う).そうしたやりとり自体は非常に有意義かつ建設的なものであり,研究会全体としても多くの学びを得られたが,他方で,質的研究者たちがほとんどを占める研究会においてKKV 側に立って議論に参加する(その結果,代理として集中砲火を浴びる)という厳しい立ち位置を強いられることは,精神的にはなかなか苦しいものであった.それでもなんとか研究会を運営し続けてこられたのは,研究会メンバーのフェアな態度と粘り強い議論姿勢のおかげである.こうした態度や姿勢は,取り扱われている問題の性質を考えれば,普通に期待できるものではない(一般的に言って,自分たちの研究方法について,よく事情を把握せずになされる異分野からの批判的提言ないし「断罪」を聞かされるのは,特にその提言が統計的手法に対する社会的評価の高さといった《圧》を伴った形でなされる場合には,あまり愉快なことではない).研究会メンバーには,それぞれの専門性に対して敬意を表すとともに,その忍耐強さと知的誠実さに対して改めて心からの感謝を申し上げたい.また,各分野の研究方法論関連の文献について詳細かつ膨大なレビューを作成してくださった研究員の山邊聖士,栗原和樹,谷憲一,鈴木良和,清水雄也,小林佑太,永山理穂,狩谷尚志の各氏,正規メンバーではないが頻繁に研究会に参加して貴重な意見を述べてくださった大杉高司(文化人類学),佐藤文香(ジェンダー研究),中澤篤史(スポーツ社会学)およびご著書『姦通裁判』(星海社,2018 年)を題材にKKV 的視点からの批判的検討に付き合ってくださった秋山晋吾(歴史学)の各氏にも,この場を借りて御礼を申し上げたい.ありがとうございました.
勁草書房の山田政弘さんには本論集の成立を傍でずっとサポートしていただいた.研究会を立ち上げた2020 年から出版計画について相談に乗っていただいたこと,原稿を取りまとめるプロセスの中で常に的確な助言をいただいたことについて,感謝申し上げる.
最後にもう一つ個人的な思い出を.本書およびその元となる研究会の立ち上げのきっかけは,筆者が社会学部1 年次必修科目「社会科学概論II」の授業担当を依頼されたことにさかのぼる.当時を振り返ると,この授業担当の引き受けには相当逡巡した覚えがある.というのも筆者は,学部時代は物理学を,大学院以降は哲学を専攻しただけで,社会科学に関する正規トレーニングは一切受けて来なかったからだ.しかし,職業的義務感――筆者の所属は「社会学研究科Graduate School of Social Sciences」である――もあり,また依頼をしてくださった町村敬志研究科長(当時)の「ご自身の考える社会科学概論を」という言葉にも後押しされて,2018 年度から2021 年度まで担当を引き受けることになった.そして,授業準備を進める中で様々な疑問につきあたり,それを同僚や知人にぶつけて教えを乞う,という形で議論を続けるうちに上記研究会を立ち上げることになったのである.その後も様々な人たちからたくさんのことを教えてもらって社会科学方法論という課題の重要性と面白さに気づかされていくうちに,当初は気の進まなかった「社会科学概論II」はいつのまにか自分のお気に入りの講義題目になり,自身の研究テーマの中でも社会科学の哲学の1 領域という形で重要な位置づけを持つに至っている.授業に出席し質問やレポートを通して多くの気づきを与えてくれた受講生の皆さん,そして学術的な視野を広げるよい修練の機会を与えてくださった町村先生に御礼を申し上げたい.
2022 年11 月7 日
井頭昌彦











