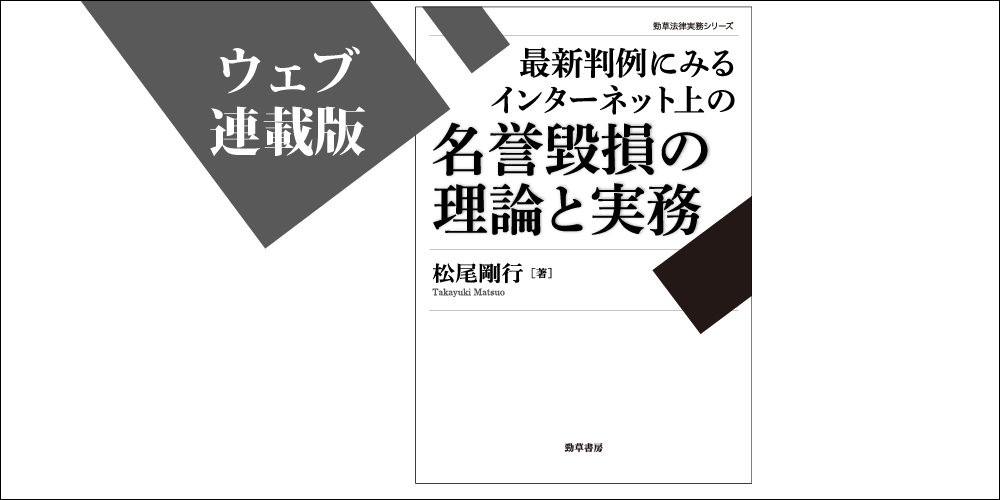最新! 「記者会見による名誉毀損」重要判決を最速で解説します。[編集部]
記者会見による名誉毀損・東京高判令和5年7月13日解説
1 はじめに
東京高判令和5年7月13日(Hプロジェクト名誉毀損事件)は、記者会見における名誉毀損が問題となった重要判決である。すなわち、農業アイドルとしてデビューした未成年者が自殺する事態が生じ、遺族が所属事務所運営企業や社長等に対し、自殺は社長のパワハラのせいだ等と主張して訴訟を提起した。本判決はその際の訴訟提起記者会見における遺族代理人弁護士等(以下「被告」と総称する。)の言動が、事務所運営企業及び社長等(以下「原告」と総称する。)の名誉を毀損するか問題となり、名誉毀損を肯定したものである。本連載第42回においても、記者会見に関する裁判例をまとめたが、以下、本判決を簡単に紹介しよう。
2 記者会見における摘示事項
本判決では、記者会見における摘示事項が問題となった。即ち、被告は、記者会見においては、参加者をメディアの記者に限定し、訴訟を提起したこと及び同訴訟での主張内容を説明したものにすぎないところ、このような記者会見の性質を踏まえた摘示事実の認定をすべきだ、と主張したものである。
この点は、摘示されたものが、もし結果的に「訴訟の一方当事者がそのような主張をしている」というだけであると認定されれば、(一方的な主張を超えて、)それが真実だとして摘示したものではないため、社会的評価低下の認定の部分でも、真実性の認定の部分でもこの点を加味すべきということになり得るだろう(松尾剛行・山田悠一郎著『最新判例にみるインターネット上の名誉毀損の理論と実務 第2版』74頁参照。以下、「本書」という。)。
しかし、以下のとおり裁判所は本件の具体的事実関係に鑑み、摘示されたものは、「訴訟の一方当事者がそのような主張をしている」というものにとどまらないとした。すなわち、本件では、訴状の写しをダウンロードするためのURLを記載した書面が記者会見当日に配布されたのみであり、参加者に対して、訴状等の該当箇所を参照するような具体的指示等はなされず、記者会見全体の発言をみても、訴訟における一方当事者の主張内容を説明しているということを十分に伝えようとしている形跡はなく、かえって、断定的に事実を述べる形式となっていたこと、記者会見に先立って報道関係者に配布された「地方アイドルのハラスメントによる自殺問題について」と題する書面及び記者会見全体の発言内容によれば、原告による度重なる過重労働の強要やパワーハラスメントにより精神的に追い詰められていたところに、貸付けの申出の撤回発言や1億円発言が加わった結果として、当該アイドルが自死に至ったとのストーリーが、一貫して強調されていること等から、提訴前の記者会見であり、参加者が報道機関に限定されていたことを考慮しても、記者会見における摘示事実が、一方当事者の主張にとどまるものとはいえないとした。
このような事実認定を前提に、本判決は、被告の行為が原告に対する名誉毀損であると認めた原判決を是認したものである。
3 対抗言論
本判決では、対抗言論の法理が問題となった。要するに、被告の主張が原告の社会的評価低下を招いたとしても、原告は十分に反論主張をして社会的評価低下を低減させている、というものである。
一般には、対抗言論が可能な状況が存在する場合において、それだけで一律に名誉毀損を否定するといったドラスティックな見解は採用されていない。但し、よりマイルドに、対象者に事後的な対抗言論を通じて名誉回復を行う機会があることを、社会的評価の低下の有無や違法性阻却の可否、損害等で考慮するべきではないかという問題意識自体は存在するところである(本書323頁)。
本判決は、被告の広報活動が反響を呼んだことを1つの契機として、原告が一方的な批判にさらされ、中には卑劣な誹謗中傷や脅迫に及ぶものも多数あったというのであるから、原告らが広報活動により毀損された名誉を対抗言論によって回復することが可能であったなどとは到底認め難いとした。また、原告の被った損害が、原告の行った対抗言論により軽減されたのではないかという点についても、原告の広報活動が、被告の広報活動を大きく上回っていたことを認めるに足りる証拠はないし、これにより原告の損害が十分回復したとも認められないとした。
その結果として、本判決は、本件の具体的状況においては、名誉毀損は否定されないし、損害も低減されないと認定したものである。
4 正当業務行為
加えて、弁護士である被告が、かかる広報活動は、弁護士としての正当業務行為であり、違法性を欠くと主張した。
一般論としては名誉毀損についても、正当業務行為という抗弁自体が成立する余地は否定できない(本書434頁)。
しかし、裁判所は、広報活動が弁護士業務の一環であり、報道機関から遺族を守ることや、芸能活動に従事する未成年者の労働環境という社会問題を提起するという、それ自体は正当な目的を含んでいるとしても、本件における広報活動に至る経緯及びその態様等に照らせば、被告が、十分な裏付調査をすることなく原告らの社会的評価を低下させる発言を断定的に行うなどした点において、相当性を欠くことは明らかであるから、弁護士としての正当業務行為として違法性が阻却されるとは認められないとした。
要するに、目的がいくら正当であっても、正当業務行為という抗弁を主張する上では手段も併せて評価するところ、本件の具体的な認定事実を前提とすると手段が不相当だったと判断されたものである。
5 共同不法行為
問題となった名誉毀損発言を実際に行った登壇者ではなく司会者にとどまった弁護士についても、共同不法行為が成立するかが問題となった。
共同不法行為の点については、具体的事案における主観的客観的関連共同性の認定次第である(本書186頁以下)。
そして、裁判所は、訴訟提起に至るまでの間、グループにおける活動内容や自死に至った経緯等の事実関係の確認等の作業を繰り返し行い、検討を重ねた結果、訴訟を提起するに当たり、記者会見の実施をするという意思決定に至り、また、その内容を掲載し、インターネット上において不特定多数の者によって閲覧可能な状態に置くことを認識していたものであるから司会者にとどまった弁護士についても、共同不法行為責任を負うというべきである等として、その共同不法行為責任を肯定した。
ここで、東京地判平成28年10月25日D1-Law.com判例体系〔28250488〕は、話し手及び聞き手がインターネット番組に出演して対談したところ、聞き手も相槌を打ったり、話し手の発言にそう形で発言し、話し手の発言の否定、訂正にわたる発言がないのみならず、発言の根拠を確認する発言もなく、話し手の発言の摘示する事実を当然の前提として対談を進めているので一連の対談における発言について、共同不法行為が成立するとした(本書187頁)。本件においては、このような議論も適用可能だったかもしれない。
6 昭和38年判決の法理
(記者会見ではなくツイートに関し、)遺族の名誉を毀損する内容の週刊誌の記事に対する正当防衛類似の言論だったという昭和38年判決の法理も抗弁として主張された。
最高裁(最判昭和38年4月16日民集17巻3号476頁。「昭和38年判決」)は、「(民事名誉毀損に関し)自己の正当な利益を擁護するためやむをえず他人の名誉、信用を毀損するがごとき言動をなすも、かかる行為はその他人が行つた言動に対比して、その方法、内容において適当と認められる限度をこえないかぎり違法性を缺く」とした(本書317頁。強調筆者)。
このような昭和38年判決の法理に基づき、被告は、要するに、原告も被告の名誉を毀損する週刊誌記事等に関与しており、ツイートはそれに対する正当防衛類似のものだったと主張した。しかし、本判決は、問題となっている被告の行為が、被告の名誉を毀損する内容の週刊誌の記事に対する正当防衛類似の言論として行われたことや上記記事の情報源が原告であることを認めるに足りる証拠はないとした。また、昭和38年判例は、学界誌が、学者本人の承諾を得ずに不明朗な手段で講演原稿を入手した上、本人から掲載の承諾を得ている他学界誌に先駆けて掲載発表したという事例において、当該学界誌を誹謗する他学界誌の記事につき名誉毀損の成立を否定したものであって、事案を異にし、本件に適切でないとした。
昭和38年判決は直接的には正当防衛そのものではなく、それを拡張する法理であるが、同判決が「その他人が行つた言動」とするように、AがBに対して(Bの正当な利益を侵害する)言動を行う場合に、Bがその正当な利益を擁護するためやむをえずAの名誉毀損をする場合を想定している。
本件では、原告(A)が被告(B)に対して行った被告の正当な利益を侵害する言動が問題となったのではなく、「週刊誌」という第三者(C)の報道が問題となっており、本判決の事実認定、すなわち、原告(A)が当該週刊誌報道に関与していないという認定を前提とすると、そもそも昭和38年判決の法理の適用場面ではないとする本判決の判断は正当である。
7 依頼者と代理人の責任関係
最後に、遺族である特定の被告は、あくまでも依頼者に過ぎず、記者会見に参加していないのだから、責任を負わないのではないかという点も問題となった。
委託者・委任者が受託者・代理人に表現行為を依頼した場合の双方の名誉毀損に関する責任は、その依頼の趣旨によるだろう(本書189頁)。
そして、本判決は、代理人弁護士である被告らと、訴訟提起に至るまでの間、グループにおける活動内容や自死に至った経緯等の事実関係の確認等の作業を繰り返し行い、検討を重ねた結果、同訴訟を提起したものであるところ、その方針として広報活動(多数のメディアによって報道され、広く伝播していくことを企図していたことは明らかである)を行うことを相互に認識の上決定したものであるから、上記方針に従って行われた広報活動による結果について、共同不法行為責任を負うというべきであるとした。その上で、弁護士らが、法律専門家として独自の判断に基づき適切に対応することが要請されているとしても、記者会見の開催は、自死の真相を明らかにしたいとする遺族の要望でもあったところ、そのことをもって、上記の調査確認作業において事実関係を積極的に説明し、広報活動を行う意思決定に参加した(記者会見の開催は、自死の真相を明らかにしたいとする遺族の要望でもあった)遺族が責任を免れるものとはいえないとした。
要するに具体的な依頼の状況や趣旨を踏まえ、遺族としても共同不法行為責任は免れないとしたものである。
8 若干のコメント
本判決は、その事実認定を前提とする限り、従来の裁判例の理屈を当該認定事実に適用したものとして基本的に支持できる(なお、本稿は被告による控訴に関する判断について検討したものであり、原告による控訴に関する判断について検討するものではない)。
重要ではあるが、あまり具体的に判断された先例が多くはなかった多数の論点について、具体的な判断がされており、今後これらの論点が問題となる事案における先例になると思われる。
》》》これまでの連載一覧はこちら《《《
 2019年2月発売!
2019年2月発売!松尾剛行・山田悠一郎著
『最新判例にみるインターネット上の名誉毀損の理論と実務 第2版』
実例をもとにメルクマールを示す、ネット時代の名誉毀損の決定版法律実務書、3年分の最新裁判例を多数加え、圧倒的充実の第2版!
書誌情報 → https://www.keisoshobo.co.jp/book/b432305.html