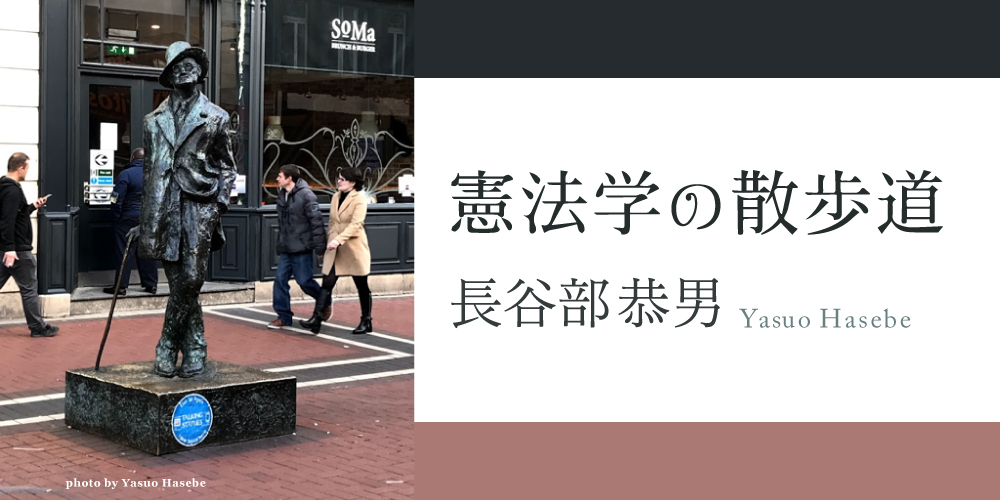「憲法学の散歩道」単行本化第3弾! 書き下ろし1編を加えて『思惟と対話と憲法と――憲法学の散歩道3』、2025年10月15日発売です。みなさま、どうぞお手にとってください。[編集部]
カール・シュミットは『政治神学』の冒頭で、「主権者とは、例外事態(Ausnahmezustand)について決定する者である」と断言する*1。Ausnahmezustandは、非常事態と訳されることもある。
引き続いてシュミットは、主権概念は限界概念(Grenzbegriff)であるとする。限界概念とは、比喩的に言えば、遠近法の消失点である。われわれが暮らす、この世界だけが実在する世界だと思われている日常的な世界と、そんなものが存在するとは思ってもみなかった、尋常ではない外側の世界とを連絡する概念である。
シュミットの言う主権者は、その決断によって全法秩序を停止する。
法秩序は日常的な状態が妥当していることを暗黙の適用条件とする。主権者は、日常的な状態が妥当しているか否かを決定する。妥当していないと判断されれば、法秩序は停止される。
そうした主権者は、ブルジョワ的な法治国思想やリベラルな法の支配の観念からすれば、あり得べからざる存在である。だからこそ、通常の法律学ではこの主権概念は存在しないものとされ、普段は消失している。しかし、法によって主権者の存在を否定することはできない。実定法秩序がたとえシュミット的な主権者を無視し、それに一切触れていないとしても、主権者が事実上、出現する事態を抑え込むことはできない*2。
全法秩序を停止する主権者の権限は、前もって存在する法規範が与えるものではない。主権者が決断を下すべき例外事態にあたるか否かは、主権者自身が決定する。だからこそ彼(彼ら)は、主権者である。
ハンス・ケルゼンの純粋法学とは異なり、シュミットにとっての国家は法秩序そのものではなく、法秩序が停止されても、国家が活動を停止することはない。国家の生存と自己保存のために主権者は活動し続ける。マックス・ウェーバーの指摘とは異なり、主権の本質は強制力の独占ではなく、決断の独占である*3。この特殊な意味における決断の。
『政治神学』の冒頭にあらわれる決断主義的なシュミットの見方からすれば、憲法典に修正を加えて非常時における権限行使に法的制限を加えようとする試みが、幼稚園のおままごとの類にすぎないことがよく分かる。およそ憲法学において、主権という概念を安易に使うべきではない。使うには、よほどの覚悟と慎慮が必要である。
法治国思想に代表される規範主義は、法をすべて規範に、典型的には議会制定法へと還元しようとする。規範主義は、法はすべてその内容ではなく、法のとる形式──憲法か、法律か、判決か──のゆえに妥当すると考える。
つづきは、単行本『思惟と対話と憲法と』でごらんください。
 遠い昔の学説との対話を楽しみつつ、いつしか「自意識」が揺さぶられる世界に迷い込む。憲法学の本道を外れ、気の向くまま杣道へ。
遠い昔の学説との対話を楽しみつつ、いつしか「自意識」が揺さぶられる世界に迷い込む。憲法学の本道を外れ、気の向くまま杣道へ。
2025年10月15日発売
長谷部恭男 著 『思惟と対話と憲法と』
四六判上製・216頁 本体価格3200円(税込3520円)
ISBN:978-4-326-45147-0 →[書誌情報]
【内容紹介】 書き下ろし1篇を加えて、勁草書房編集部webサイトでの好評連載エッセイ「憲法学の散歩道」の書籍化第3弾。心身の健康を保つ散歩同様、憲法学にも散歩がなにより。デカルト、シュミット、グロティウス、フィリッパ・フット、ソクラテス、マッキンタイア、フッサール、ゲルバー、イェリネク等々を対話相手の道連れにそろそろと。
「憲法学の散歩道」連載第20回までの書籍化第1弾はこちら⇒『神と自然と憲法と』
「憲法学の散歩道」連載第32回までの書籍化第2弾はこちら⇒『理性と歴史と憲法と』
連載はこちら》》》憲法学の散歩道