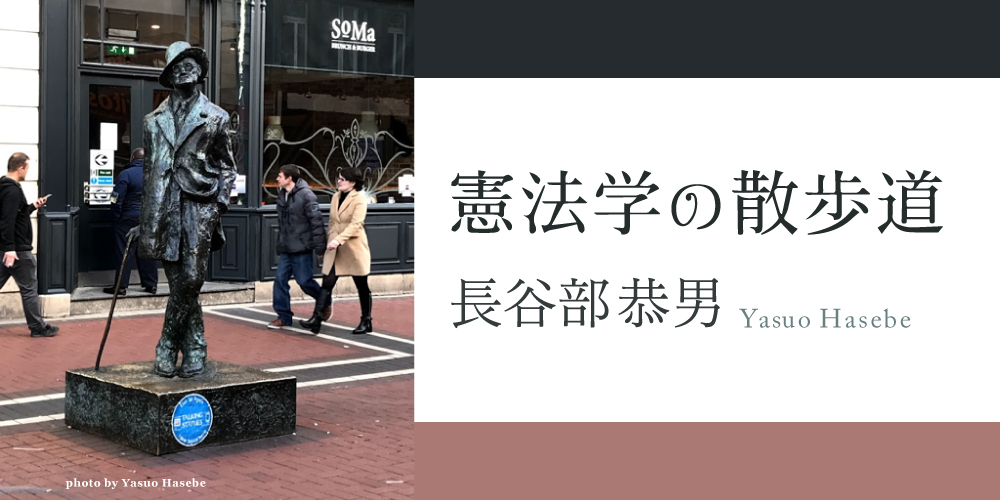「憲法学の散歩道」単行本化第3弾! 書き下ろし1編を加えて『思惟と対話と憲法と――憲法学の散歩道3』、2025年10月15日発売です。みなさま、どうぞお手にとってください。[編集部]
今回はややこしい話なので、短めに済ませることにする。刑法230条には、「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する」とある。表現の自由との関連で、憲法学でもおなじみの条文である。『広辞苑』によると、「摘示」とは、「かいつまんで示すこと」である。隅から隅まで逐一にというわけではなく、要点を示すということであろう。
続く刑法230条の2は、たとえ公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した場合であっても、一定の条件の下では、「事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない」とする。そうしたときは、人の名誉を毀損する表現であったとしても違法ではなく、不法行為責任や刑事責任を問われることはない*1。
ところで、事実が真実であるとか真実ではないとは、何を意味しているのであろうか。事実であるのに真実ではないことがあり得るものだろうか。常識的に考えれば、事実であれば、当然真実であるし、真実でなければ、それは事実ではないはずである。
おそらくこの条文では省略語法が用いられている。事実が真実であるか否かが問題なのではなく、これが事実だとする言明が真実であるか、つまり本当に事実であるかが問われている。真実であったりなかったりするのは、事実ではなく、言明である。
さて、真実であるとは何を意味するのだろうか。直観的に広く受け入れられているのは、対応説という考え方で、言明が事実と対応していれば、その言明が真実だというものである。オクスフォードの日常言語哲学の創始者であるJ. L. オースティンは、プラトンやアリストテレスと同様、対応説の立場を支持した*2。
ところが、同じ日常言語哲学のメンバーであるピーター・ストロウソンは、対応説を批判する。彼によれば、「対応説に必要なのは、その除去(elimination)」である*3。
ストロウソンは次のように、議論を進める。対応説は、事実が言明と対応するか否かを問題にする。そこで言う「事実」とは何であろうか。「クロは犬である(Blacky is a dog)」という言明は、「クロ」が特定の個体を確実に指示し、しかもその個体がたしかに犬であれば、真(true)である。つまり、「クロは犬である」は真である(It is true that Blacky is a dog)。そこに「事実」が入り込む余地はない。「クロが犬であることは真である」と「クロは犬である」とは、同じことを言っている。
つづきは、単行本『思惟と対話と憲法と』でごらんください。
 遠い昔の学説との対話を楽しみつつ、いつしか「自意識」が揺さぶられる世界に迷い込む。憲法学の本道を外れ、気の向くまま杣道へ。
遠い昔の学説との対話を楽しみつつ、いつしか「自意識」が揺さぶられる世界に迷い込む。憲法学の本道を外れ、気の向くまま杣道へ。
2025年10月15日発売
長谷部恭男 著 『思惟と対話と憲法と』
四六判上製・216頁 本体価格3200円(税込3520円)
ISBN:978-4-326-45147-0 →[書誌情報]
【内容紹介】 書き下ろし1篇を加えて、勁草書房編集部webサイトでの好評連載エッセイ「憲法学の散歩道」の書籍化第3弾。心身の健康を保つ散歩同様、憲法学にも散歩がなにより。デカルト、シュミット、グロティウス、フィリッパ・フット、ソクラテス、マッキンタイア、フッサール、ゲルバー、イェリネク等々を対話相手の道連れにそろそろと。
「憲法学の散歩道」連載第20回までの書籍化第1弾はこちら⇒『神と自然と憲法と』
「憲法学の散歩道」連載第32回までの書籍化第2弾はこちら⇒『理性と歴史と憲法と』
連載はこちら》》》憲法学の散歩道