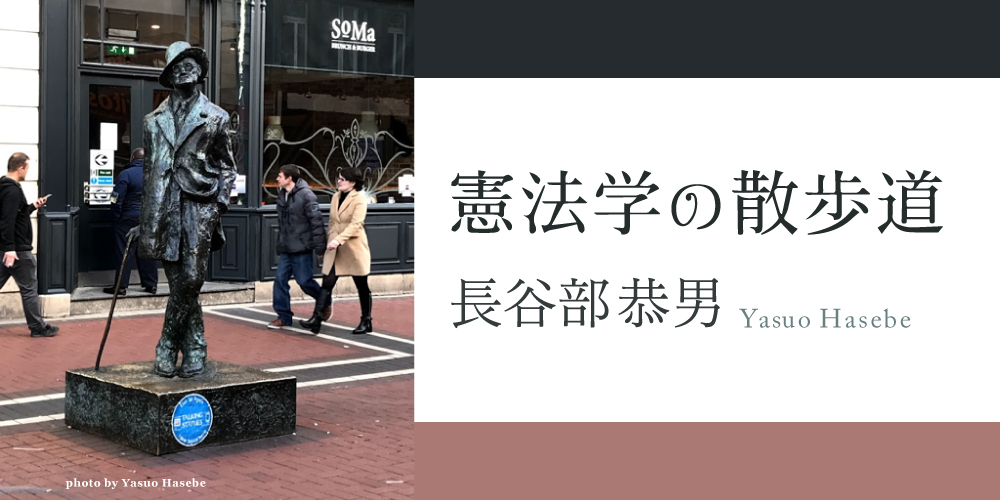「憲法学の散歩道」単行本化第3弾! 書き下ろし1編を加えて『思惟と対話と憲法と――憲法学の散歩道3』、2025年10月15日発売です。みなさま、どうぞお手にとってください。[編集部]
フィリッパ・フットは、アメリカ合衆国のグラヴァー・クリーヴランド大統領の孫にあたる。オクスフォードのサマヴィル・コレッジを卒業した彼女は、同コレッジで長く哲学を教え、カリフォルニア大学をはじめとするアメリカの諸大学でも教鞭をとった。
彼女が1958年に公表した論文に、「道徳的議論」がある*1。論文の冒頭で、彼女はリチャード・ヘアの指令主義(prescriptivism)を取り上げている。
アルフレッド(フレディ)・エアが論理実証主義の強い影響下に1936年刊行した『言語・真理・論理』は、意味のある言明は、数学や論理学などのトートロジーか、または経験に即して実証可能な言明──その典型は自然科学──に限られ、形而上学の命題や道徳的言明には意味がない(nonsense)と主張した*2。善悪や正義・不正義に関する言明は、各人の主観的選好の表明にすぎず、「フレー、フレー」と喝采したり「コンチクショウ」と野次ったりするのと同じで、およそ論理的分析の対象とはなり得ない。形而上学と倫理学の存在意義は否定される。
他方リチャード・ヘアは、道徳的言明が論理的分析の対象となり得ないとは考えない。善悪や正義・不正義に関する道徳的言明は、「そうしろ」とか「そうするな」という指令としての意味を持つ。一連の道徳的言明は、特定の行動を指令しているか禁止しているか、あるいは指令も禁止もしていないかを判別することで、相互に整合しているか否かを判断することができる。
「すぐ出発しろ」と「まだここにいろ」とは衝突する。「オムレツを作れ」は「卵を割れ」を含意する。論理的な矛盾に陥らないためには、言明と同様、指令は一定の論理規則に従う必要がある*3。
個別の状況での特定人に対する指令や禁止の根拠となるのは、普遍的な指令や禁止である*4。ただ、カントの定言命法の要請についてしばしば指摘されるように、普遍的な姿形をしていても相互に衝突する指令(禁止)は無数に考えつくことができる*5。いずれの普遍的指令(禁止)にコミットするかは、本人の決断次第である。二人の個人が究極的な道徳的判断について異なる立場をとるとき、いずれが正しいかを客観的に判定することはできない。共通了解の基盤がそこには欠けている。
ヘアは1937年、オクスフォードのベイリオル・コレッジに入学した。フィリッパがサマヴィル・コレッジに入学する2年前である。1939年に第二次世界大戦が勃発すると、兵役を拒否すべきか否か苦悩した挙げ句、ヘアは砲兵隊に志願し、シンガポールに派遣された。制空権を失った当地のイギリス軍は1942年2月、日本軍に降伏し、ヘアは捕虜となった。
投降前のことだが、イギリス軍は日本兵を2名捕虜とした。シンガポールが陥落すると彼らは直ちに元の部隊に帰還し、指揮官に敬礼したのち、虜囚となった恥を濯ぐため切腹した。文化の多様性(cultural diversity)を目の当たりにしたヘアは、彼がオクスフォードで学んだ直観主義──人は直観を通じて普遍的かつ客観的な道徳原則を把握することができるという立場──を放棄した*6。
つづきは、単行本『思惟と対話と憲法と』でごらんください。
 遠い昔の学説との対話を楽しみつつ、いつしか「自意識」が揺さぶられる世界に迷い込む。憲法学の本道を外れ、気の向くまま杣道へ。
遠い昔の学説との対話を楽しみつつ、いつしか「自意識」が揺さぶられる世界に迷い込む。憲法学の本道を外れ、気の向くまま杣道へ。
2025年10月15日発売
長谷部恭男 著 『思惟と対話と憲法と』
四六判上製・216頁 本体価格3200円(税込3520円)
ISBN:978-4-326-45147-0 →[書誌情報]
【内容紹介】 書き下ろし1篇を加えて、勁草書房編集部webサイトでの好評連載エッセイ「憲法学の散歩道」の書籍化第3弾。心身の健康を保つ散歩同様、憲法学にも散歩がなにより。デカルト、シュミット、グロティウス、フィリッパ・フット、ソクラテス、マッキンタイア、フッサール、ゲルバー、イェリネク等々を対話相手の道連れにそろそろと。
「憲法学の散歩道」連載第20回までの書籍化第1弾はこちら⇒『神と自然と憲法と』
「憲法学の散歩道」連載第32回までの書籍化第2弾はこちら⇒『理性と歴史と憲法と』
連載はこちら》》》憲法学の散歩道