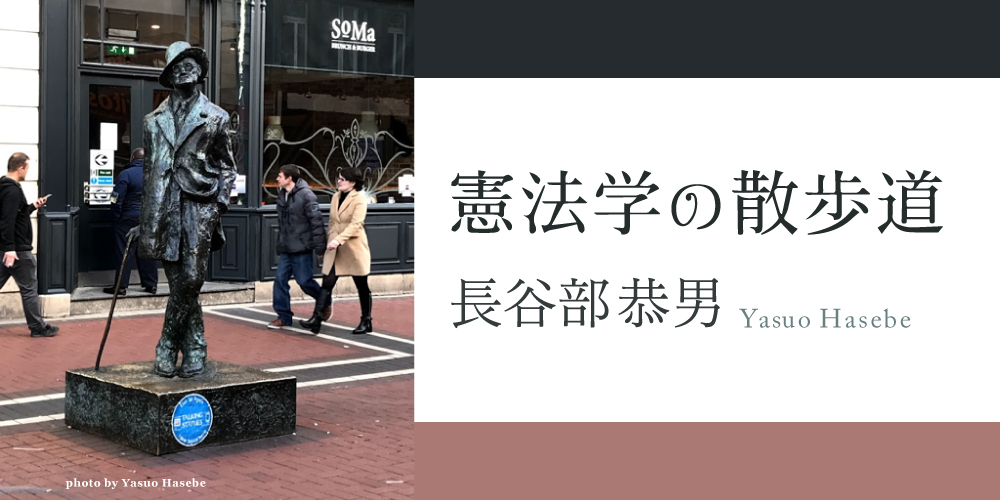「憲法学の散歩道」単行本化第3弾! 書き下ろし1編を加えて『思惟と対話と憲法と――憲法学の散歩道3』、2025年10月15日発売です。みなさま、どうぞお手にとってください。[編集部]
エミール・ペロー=ソウシン(Émile Perreau-Saussine)は、パリ社会科学高等研究院で博士号を取得した後、ケンブリッジ大学で政治思想史を講じた。彼の著書に『アラステア・マッキンタイア──知的伝記』*1がある。彼はさらにマッキンタイアをテーマとする雑誌の特集を企画したが*2、特集が刊行される前の2010年、37歳で逝去した。
マッキンタイアと言えば共同体主義者であり、リベラリズムを批判する保守主義者であり、その知的源泉は、かつてはマルクス主義であったが、その後、カソリシズムとアリストテレス主義へと転向したというのが一般的なイメージであろう。もっとも、彼がはたして真正の共同体主義者と言えるかは問題である。少なくとも現代国家に関する限り、社会全体で共有される善の観念など存在しないとマッキンタイアは考える*3。
古代ギリシャのポリスと違って、ニーチェ後の価値観がどうしようもなく多元化した現代の国家は、すべての市民が共通する善の観念について協働しつつ論議を重ね、その形成に参与する共同体としてはあまりにも規模が大きすぎる。そうした社会で共通する善の観念を目指して政治を遂行しようとすれば、結局のところ少数のエリートによる善の観念の押しつけがもたらされるだけである。
リベラルは国民国家の政府は対立する善の観念について中立的であるべきだとするが、現代の共同体主義者は、政府は特定の共有された善の構想、共同体の特性となる構想を表明すべきだと主張する。リベラルは共有された善の構想を具体化するのは、宗教団体のような結社であるべきだとするが、共同体主義者は、国民自身が国家の諸制度を通じて共同体を構成すべきだと主張する。……私の見るところ、共同体主義者は、リベラルな論者の方が一貫して正しい、まさにその点でリベラリズムを攻撃している*4。
社会内部の多様な実践固有の内在的善に耳を傾け、固有の生の形式を尊重することは、国民を単位とする大規模な国家の政治にとっては不可能である*5。家族単位の農業という生活様式はすでに失われ、関税障壁のないグローバルな市場を相手に多国籍企業が莫大な資本を投下し、優遇税制を各国政府に要求し、利潤が生まれなければ素早く退出する世界のみが、そこでは可能である*6。
つづきは、単行本『思惟と対話と憲法と』でごらんください。
 遠い昔の学説との対話を楽しみつつ、いつしか「自意識」が揺さぶられる世界に迷い込む。憲法学の本道を外れ、気の向くまま杣道へ。
遠い昔の学説との対話を楽しみつつ、いつしか「自意識」が揺さぶられる世界に迷い込む。憲法学の本道を外れ、気の向くまま杣道へ。
2025年10月15日発売
長谷部恭男 著 『思惟と対話と憲法と』
四六判上製・216頁 本体価格3200円(税込3520円)
ISBN:978-4-326-45147-0 →[書誌情報]
【内容紹介】 書き下ろし1篇を加えて、勁草書房編集部webサイトでの好評連載エッセイ「憲法学の散歩道」の書籍化第3弾。心身の健康を保つ散歩同様、憲法学にも散歩がなにより。デカルト、シュミット、グロティウス、フィリッパ・フット、ソクラテス、マッキンタイア、フッサール、ゲルバー、イェリネク等々を対話相手の道連れにそろそろと。
「憲法学の散歩道」連載第20回までの書籍化第1弾はこちら⇒『神と自然と憲法と』
「憲法学の散歩道」連載第32回までの書籍化第2弾はこちら⇒『理性と歴史と憲法と』
連載はこちら》》》憲法学の散歩道