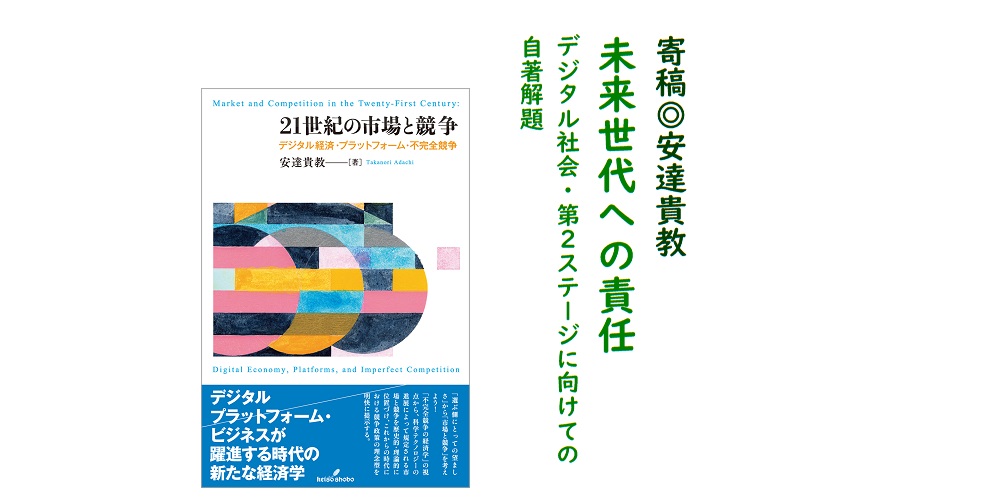
1. 誤っていたハイエクの競争観
経済学者のフリードリヒ・ハイエク(1899-1992)は、1948年の論文「競争の意味」*1において、時間の流れを考えない静態的な枠組みによっては、経済における「競い合い」が捉えきれないとして、標準的な経済学を批判した。しかし、彼はそのように述べるとき、競争を主として、消費者といった選ぶ側からではなく、選ばれる側からしか見ていない。
そうではなく、選ぶ側からの視点から捉え、競争を「選ぶ側が何かを選ぶと、それ以外の何かは選ばれなくなるということから、選ばれる側に競合が生じるという状況」と定義すれば、時間的な流れを特段に強調する必要はない。
もちろん、時間的に生じる「競い合い」を細かく見ようとすること自体は興味深い試みではあるが、そうしないからといって、競争の意味が捉えられないと考えるのは甚だしく筋違いというべきである。
ハイエクは、また、同論文において、このような動的な「競い合い」とは本質的に知識の獲得過程であるとも主張した。しかし、これも付随的な論点でしかない。競争の本質は、上の定義に尽きているのだ。
競争をこのように定義することの適切さについては、経済学を学んだことがある人であれば、大方、同意するものだろう。しかし、大部分の経済学の教科書では、選ぶ側の視点が、ここでのように明示的にはされず、言わば暗黙的に埋め込まれた前提となっている。選ばれる側が置かれている状況だけに焦点が当てられているのが現状だ。
これでは、経済学学習の初期段階から競争の本質的な意義、すなわち、選ぶ側にとっての選択肢を保障するものであるという点を理解できない。経済学の研究者でなければ、「競争はしんどい」という嘆息、あるいはその裏返しとして、「競争はしんどいからこそ意義深い」という処世訓が生まれてきても無理なかろう。今年6月に上梓した『21世紀の市場と競争』において、筆者は、この双方を「通俗的な競争観」と呼んでいる(p.298)。
2. マークアップの視点から理解する「競争の不完全性」
こういった選択肢間の競合関係を前提とした上で、筆者が重きを置く「不完全競争の経済学」においては、商品・サービスの価格とは、新たな一単位の生産に必要な費用(限界費用)にマークアップが上乗せされて決まっているものという理解を提示する。
対して、標準的なミクロ経済学で重点的に扱われている「完全競争理論」では、価格は限界費用と一致するという帰結が導かれ、必然的に、価格と限界費用の「差異」である価格・費用マージン(以下、マークアップと呼ぶ)はゼロということになる*2。
しかし「不完全競争の経済学」では、マークアップがゼロになるような完全競争とは、マークアップが正であることを許容する不完全競争の一特殊ケースとして、経済の現実を包括的に扱うことが可能だ。
しかも、筆者の提唱する「不完全競争の経済学」は、「不均衡」ならぬ標準的な「均衡」論の体系を組み替えて活用するものであり、その意味では、突飛なものではない。またハイエクが指摘するような時間的要素を考えようとする「動学」ではなく、あくまで「静学」であるので、理解が徒に複雑にはならない。
筆者が、大学の教養課程はもちろん、公共や政治経済といった高校の公民科目であっても、このような「不完全競争の経済学」の普及を願うゆえんである。拙著『21世紀の市場と競争』の前半部(第3・4章)で、高校の教科書での記述を重点的に取り扱っているのは、そのような意味合いも込めたものだ。
しかし、ここで説明したマークアップとは、いわば、「純粋なマークアップ」というべきものであり、現実の経済の理解のためには、次の二つも合わせて理解しなくてはならない。
一つは、21世紀のデジタル経済を主導するプラットフォームで生じる「マークダウン」、そして、競争阻害作為によって企業側が獲得する「不当なマークアップ」だ。
(1)プラットフォームが消費者から得るマークアップ
=(対消費者市場だけを考慮した)純粋なマークアップ-(出店者市場も考慮された)マークダウン
(2)競争妨害的な行為から生じるマークアップ
=純粋なマークアップ+不当なマークアップ
3. 現代の問題を考えるために
まず一つ目から見ていこう(1)。デジタル・プラットフォームはしばしば利用者に対して「料金無料」を提示する。これはなぜか。
前節では、料金は、限界費用にマークアップが上乗せされていると考えられていた。しかし、デジタル・プラットフォームは、一般消費者に対してだけでなく、出品者とも取引をしている。出品者を引き込むには、多くの消費者が自分のプラットフォームを利用していなければならない。
消費者にとっても、多くの出品者を抱えているプラットフォームでなければ魅力的には映らない。こうして、プラットフォームは、一般消費者に対しての価格と、出品者に対しての手数料の両者をバランスさせる必要がある。
もし、多くの消費者を引き込むことが必要であるならば、限界費用にマークアップを足すだけでは不十分で、マークダウン(負のマークアップ)を働かせることで価格(利用料)をむしろ引き下げることが必要となる。このことによって、より多くの消費者を獲得することができ、それが、より多くの出品者を呼び込むことになるのだ。
その極端な結果が「料金無料」である。そういったバランスが勘案される結果として、消費者にとっての利用料と、出品者にとっての手数料は、前者はゼロになるようなアンバランスになることが多い。その分、後者から利益を得ることになる。これは、デジタル・プラットフォームが関わるような両面市場の大きな特徴だ。
もう一つは、「不当なマークアップ」である(2)。今までは、企業やプラットフォームは、他のライバルの存在を前提としつつ、自身の商品やサービスの内容を加味しながら、独立に行動していることが前提であった。
しかし時に寡占的な企業やデジタル・プラットフォームは、潜在的参入者を妨害したり、あるいは、ライバルとも関係をもつ取引相手を排除したりする。また、わが国では「優越的地位の濫用」として知られるような搾取行為を行う場合もある。さらには、ライバルと結託するようなことも生じうる(カルテル)。
これらは総じて、純粋なマークアップに追加される「不当なマークアップ」の形成・維持・強化につながるものだ(詳しくは『21世紀の市場と競争』最終第9章を参照)。
なお、ここで説明してきた「不完全競争の経済学」は、商品やサービスの市場に限らず、金融・資本市場や、労働市場を対象とする場合にも、有益な視点を提供する。例えば、金融・資本市場における貸出金利は、資金調達コストにマークアップ(利鞘)を足したものと考えれば、上の議論を適用できるし、労働市場を対象とする場合は、労働者側の賃金は、企業側によるマークダウンによって切り下げられて決まっていることが常態であるという認識から出発できる。
もちろん、実際問題として、どこまでが純粋なマークアップで、どこからが不当なマークアップなのかを区分することは、それほど自明ではない。実証の観点から、具体的な数字を伴った議論をするためには、詳細なデータ分析が必須だ。この方向でのさらなる進展が求められるのは言うまでもない。
しかし、ここで提示した理念型に基づく経済の見方は、市場と競争が関わる経済問題、すなわち、経済問題の全てを考えるための基礎中の基礎となる。
4. 21世紀のエコノミック・リテラシーとは:競争の不完全性を市民層の常識に
「消費者重視の経済学」を標榜していたはずの完全競争理論が、容易に企業礼賛イデオロギーに転化してしまうという「逆説」が生じるのはなぜか。それは、企業の利潤最大化行動がパレート効率性(経済活動に関わる主体全員の満足度が最大限に達成されている状態)達成の一環として許容され、是認されているからにほかならない。賃金を始めとする価格は市場における「見えざる手」が決定する。このような「おとぎ話」によって、現実世界の企業に対しては、自社の利潤を高めるようとする行為全般が肯定されがちになるのだ。
これに対して経済学の側から自己反省的に講ずべき対策としては、完全競争をベンチマークとした上で市場の「失敗」としての不完全競争を導入する、のではなく、不完全競争を市場の「常態」としてベンチマークと考えるよう、経済学の体系を組み替えていくほかはない。拙著『21世紀の市場と競争』は、筆者が「プラットフォームの経済学」第2世代として行ってきた研究の紹介に留まらず、そのような持論を背後に、経済学に必ずしも馴染みのない一般読者層を念頭に置きながら、「市場と競争」を適切に把握するための統一的視点を打ち出してみたものだ。
その際、やや図式的ではあるが、「20世紀の経済=供給側の『規模の経済性』が重要となる重工業化」、「21世紀の経済=需要側の『ネットワーク効果』が重要となるデジタル化」、といった対比を強調するようにしてみた。このような「時間の流れ」への意識は、筆者が幼い頃に憧れ、また、最近、再び深い関心を持つようになってきている歴史研究への憧憬が反映された結果なのかもしれない。出版後数か月が経った回顧的視点からは、図らずも、我流の「唯物史観」を提示する格好になったものとも言える。「21世紀の唯物史観」と言ってしまえば、自画自賛が過ぎるということになろうが(笑)。
今後は、ここで提案したような「不完全競争の経済学」が、上で述べたような競争妨害的な行為の規制を目的とする競争政策の理念的な基礎づけを提供しながらも、ゆくゆくは、21世紀のデジタル経済の特徴であるプラットフォーム型ビジネス、そして、AI(人工知能)が今後の経済社会に与える影響を理解するための基礎的フレームワークとして、一般市民層が持つべき「エコノミック・リテラシー」(経済を見通す素養)に位置づけられなければならない。
21世紀も早いもので、その四半世紀の最終年が目前に迫っている。デジタル社会の「第2ステージ」は希望と不安とが交錯しているが、私たち人類の未来世代を保護主義・排外主義・権威主義そして拡張主義から守り抜く。平等・平和そして成長を確かなものとするために、立憲主義に基づきながら自由主義と民主主義を保障する。2025年を迎えるにあたり、私たち一人ひとりが未来世代に対して負う責務を考える上で、拙著『21世紀の市場と競争』がその一助となれば幸いである。
追記
本稿脱稿と前後して、国際政治学者・猪口孝先生の訃報に接しました(2024年12月1日)。筆者は、東京大学在学1年目の秋、猪口先生とは立食でお話しをさせていただいたことがあります。東京大学の学生は、2年次において、3年次からの専門学部を選択しなければなりませんが、筆者は、引き続き、1・2年生が通う駒場キャンパスに属する教養学部の一専攻である国際関係論専攻に進学を希望していました。そのような折、国際政治関係の学会運営のための学生バイトの募集を見つけ、学会の様子を覗いてみようと思い切って応募してみたのです。学会終了後、駒場キャンパスの生協食堂で行われた懇親会で猪口先生を見かけ、思い切って挨拶をさせていただきました。
短い時間にどのようなことをお話ししたのか、残念ながら、記憶には残っておりません。しかし、「先生は新潟県ご出身かと思いますが、僕もそうです」とお伝えして、談笑したことは覚えています。ご著書の『社会科学入門 知的武装のすすめ』(1985年、中公新書)は、大学入学直後に購入し、また、『国家と社会』(1988年、東京大学出版会)にも手を伸ばしていた頃です。著者略歴での情報から、同郷の研究者として仰いでおりましたが、実際にお話しをしてみると、笑顔の絶えない気さくな方という印象を持ちました。猪口先生とお会いしたのは、それが最初で最後です。
『社会科学入門』は、社会科学とは何かを多岐に亘って説く入門書です。大学では、特定の分野に特化することなく、政治学、経済学、国際関係論などを幅広く勉強しようと考えていた筆者にとっては良き導きの書となりました。ただ、苦手意識があった経済学を重点的に勉強するようになるに連れ、段々と「はまる」ようになり、皮肉にも、3年次から経済学部に進学することになったのです。歳を重ねるにつれ、もし、そのまま初志貫徹をしていれば、どのような人生になっていただろうかという反実仮想が頭をよぎることもしばしばです。
同書の第11章「情報処理のシステムを作る」は、社会科学のための情報の入手・利用について述べる一章です。筆者は、20世紀末からのインターネットの普及によって、1985年当時の記述は古びたものになってしまったと、この20年間ほど思い込んでいました。しかし、この度、確認をしてみると、幾つかの情報ソースに関する記述については、そこにデジタル技術の普及を前提に読み込んであげれば、説かれている方法論は全く古びていないことに驚かされたのです。自身の不明を恥じるほかはありません。実のところ、引越しを経て、学生時代の一冊は散逸してしまっており、国立国会図書館のデジタル・コレクションによって、そのことを確認できたのです。まさに、手段は変われども、そのスタンスは不変であることを実感する結果となりました。
先生は、「狭いところから広い場所へ出て行き、外界から刺激を受ける」、そのようなご自身をタンポポに喩えて、半生を振り返っておられます(日本経済新聞夕刊2014年3月10日)。その綿毛は、国境を越え、世界中で確実に種子を行き渡らせました。それは筆者のような者にまで及んでいます。猪口孝先生は、社会科学徒としての筆者の人生を形づくっていただいたお方です。先生の足跡が筆者に影響を与えなかった反実仮想を想像することは決してできません。ここに、ご遺族やご親族・ご友人の方々の悲しみを思い、『国家と社会』の「むすび」からの引用を添え、この小文を、先生、そして共に亡くなられたご令嬢の霊前に捧げます。猪口先生が1988年当時に指摘した21世紀に向けての課題は、21世紀の四半世紀が過ぎようとする現在にあっても、私たち一人ひとりの課題であり続けています。
高度産業社会に適合する高度民主主義の確立は日本のみの課題ではなく、先進国共通の未来の挑戦であり、どの国家も社会もそれぞれに苦悩している。はたしてこの時代を統治する国家とこの時代を生きる人々が、近代国家誕生以来の民主主義の発展史に新たな貢献を加えて二十一世紀に「成熟した、力強い民主主義」という名の贈り物を確実に届けることができるかどうかは、私たちすべての市民と市民社会に立脚する国家の課題である。(p.167)
注
*1 新版ハイエク全集第I期第3巻『個人主義と経済秩序』(2008年、春秋社)、92-147頁。
*2 なお、「マークアップ」という用語が使われる場合は、価格を限界費用で除した「比率」を考えることが多いので、ここでの定義との違いに注意されたい。
安達貴教(あだち・たかのり)
京都大学経営管理大学院・大学院経済学研究科教授。Ph.D.(経済学)。「不完全競争の経済学」の視点から、産業組織、競争政策、公共政策などに関する問題を対象としたデータ分析や経済モデル分析を行なうことに主要な研究関心がある。過去の研究成果の一端は、著書『データとモデルの実践ミクロ経済学 ジェンダー・プラットフォーム・自民党』(2022年、慶應義塾大学出版会)にまとめられて刊行された。また、「不完全競争の経済学」の歴史に対する関心の一環として、『ジョーン・ロビンソンとケインズ 最強の女性経済学者はいかにして生まれたか』(ナヒド・アスランベイグイ、ガイ・オークス著、2022年、慶應義塾大学出版会)を訳出している。
 2024年6月発売
2024年6月発売
安達貴教 著
『21世紀の市場と競争 デジタル経済・プラットフォーム・不完全競争』
3,520円(税込) 四六判 336ページ
ISBN 978-4-326-55093-7
【内容紹介】デジタルプラットフォーム・ビジネスが躍進する時代の新たな経済学。
「選ぶ側にとっての望ましさ」から「市場と競争」を考えよう!「不完全競争の経済学」の視点から、科学テクノロジーの進展によって規定される市場と競争のあり方を歴史的・理論的に位置づける。デジタル時代における競争政策の理念型を明快に提示する意欲作。
本書の第1章抜粋とあとがきはこちらからお読みいただけます。→《「第1章 市場とは何か、競争とは何か」抜粋、「あとがき」》
