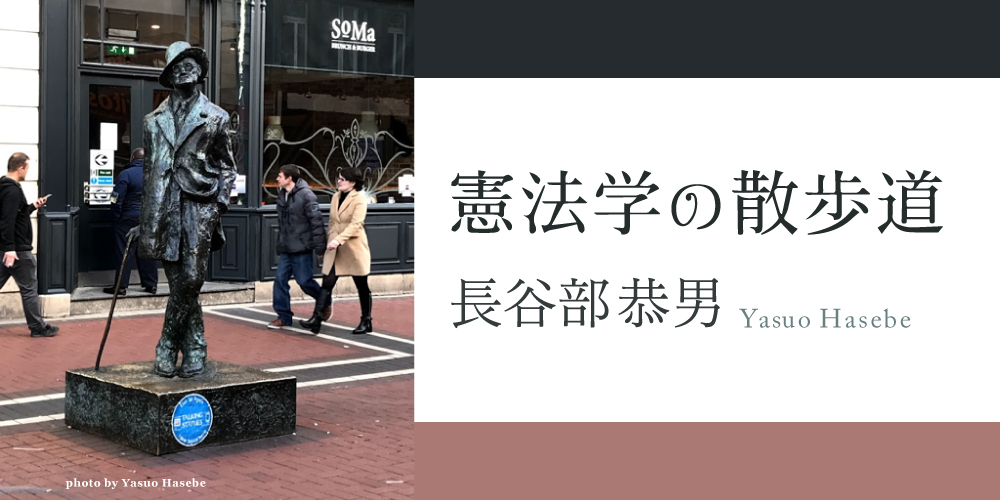「憲法学の散歩道」単行本化第3弾! 書き下ろし1編を加えて『思惟と対話と憲法と――憲法学の散歩道3』、2025年10月15日発売です。みなさま、どうぞお手にとってください。[編集部]
カール・フリードリヒ・ゲルバーは1823年、チューリンゲンに生まれた。ライプツィヒ大学とハイデルベルク大学で法学を学び、弱冠23歳にしてイェナ大学の教授となった。その後、エアランゲン大学、チュービンゲン大学を経て1863年、ライプツィヒ大学教授となった。逝去したのは1891年である。学外では、ヴュルテンベルク王国の上院議員、ザクセン王国の首相等を務めている。
ゲルバーはドイツ近代公法学*1の父と目されている。
ということは、日本の公法学の父祖でもある。
ゲルバーは、当時まっとうな学問とはみなされていなかった公法学に、国家を法人として捉える視点を導入し、国家をめぐる法現象を法人たる国家の意思形成とその適用・執行として捉える思考様式を確立した。そうすることで、政治や哲学や歴史などの夾雑物を排除して公法学を純化(Isolierung)し、しかもすでに学問として確立していた私法学からの公法学の独立を図った*2。
公法学確立の必要性に関するゲルバーの考えは、1865年に初版が刊行された『ドイツ国法学綱要 Grundzüge des deutschen Staatsrechts』の各所に示されている。
議論するまでもなく、基本的な解釈論上の諸概念をより明確で正確なものとする必要がある。われわれ[公法学]の文献の中には現代憲法の与える諸概念の法的確定という作業を法学固有の作業としてではなく、国家哲学や政治学に属するものと想定しているかのようなものがある。他の文献には、逆に、古きドイツ公法学の諸原理に支配され、われわれの新たな憲法が古きライヒの領邦法の成果にすぎないかのように扱うものもある。私の見るところ、個別の要素が独自の基本的思考を構成し得るような学問的体系を確立する喫緊の必要がある。わが現代憲法固有の本質の全体とともに個別の現象の間に存する法的関係を解明する体系的基盤なくしては、ドイツ公法学の学問的自律性を獲得することも、確かな法的帰結のすべてを導く基礎を得ることもあり得ない*3。
公法学は、その体系的原理が与える規準に則した素材の継続的批判を通じて、倫理的・政治的考察にのみ属する非法学的素材から純化される(gereinigt wird)*4。
[公法学は]派生的な学問としての、つまり、哲学であろうと私法学であろうと、他の学問分野からしかその素材を獲得し得ない学問としての地位から引き上げられる必要がある*5。
哲学、政治学、歴史学、私法学等に由来する不純物を除去し、精錬された概念や原理をもとに純粋で一貫した公法学の体系を構築し、その帰結を明らかにすることがゲルバーの目的である。
つづきは、単行本『思惟と対話と憲法と』でごらんください。
 遠い昔の学説との対話を楽しみつつ、いつしか「自意識」が揺さぶられる世界に迷い込む。憲法学の本道を外れ、気の向くまま杣道へ。
遠い昔の学説との対話を楽しみつつ、いつしか「自意識」が揺さぶられる世界に迷い込む。憲法学の本道を外れ、気の向くまま杣道へ。
2025年10月15日発売
長谷部恭男 著 『思惟と対話と憲法と』
四六判上製・216頁 本体価格3200円(税込3520円)
ISBN:978-4-326-45147-0 →[書誌情報]
【内容紹介】 書き下ろし1篇を加えて、勁草書房編集部webサイトでの好評連載エッセイ「憲法学の散歩道」の書籍化第3弾。心身の健康を保つ散歩同様、憲法学にも散歩がなにより。デカルト、シュミット、グロティウス、フィリッパ・フット、ソクラテス、マッキンタイア、フッサール、ゲルバー、イェリネク等々を対話相手の道連れにそろそろと。
「憲法学の散歩道」連載第20回までの書籍化第1弾はこちら⇒『神と自然と憲法と』
「憲法学の散歩道」連載第32回までの書籍化第2弾はこちら⇒『理性と歴史と憲法と』
連載はこちら》》》憲法学の散歩道