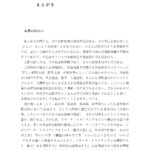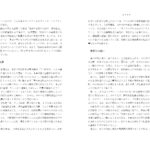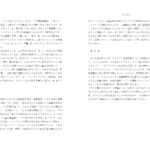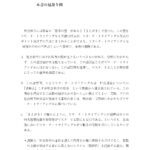あとがき、はしがき、はじめに、おわりに、解説などのページをご紹介します。気軽にページをめくる感覚で、ぜひ本の雰囲気を感じてください。目次などの概要は「書誌情報」からもご覧いただけます。
 川崎 剛 著
川崎 剛 著
『社会科学は「思考の型」で決まる リサーチ・トライアングルのすすめ』
→〈「まえがき」「本書の見取り図」(pdfファイルへのリンク)〉
→〈目次・書誌情報・オンライン書店へのリンクはこちら〉
*サンプル画像はクリックで拡大します。「まえがき」本文はサンプル画像の下に続いています。
まえがき
本書のねらい
あらゆる学問には,その分野特有の研究手法がある。その手法を使わないと「正しい,まっとうな研究」とみなされない。たとえば化学のような実験科学では,正しい実験のやり方がそれにあたる。考古学であれば遺跡発掘の手順がそうであろう。学生はそういった基礎技法を徹底的に叩き込まれる。
本書で説くのは,その社会科学版であり,それも初学者用のものである。
自然科学の場合とは対象的に,社会現象を研究する社会科学ではそういった「正しい研究方法・思考方法」が初学者にとっては大変わかりづらい。社会科学は戦争や平和,社会格差,貧困,人種差別,さらには国際協力やナショナリズムなど,人間社会に生じるさまざまな現象を研究対象とする。こういった現象の本質は抽象的概念を駆使して理解・分析せざるをえない。だからわかりづらいのだ。歴史学や宗教学のような人文学の研究と勘違いされることも多い。本書はその穴を少しでも埋めていくことをめざしている。
別の言い方をしよう。政治学,社会学,経済学,経営学といった社会科学の諸分野において共通する,そして暗黙的に想定されている基本的な「思考の型」ともいうべきものを平易な言葉で解説し,その有用性を示すというのが本書の目的である。そのため,リサーチ・トライアングルという概念を本書で導入する。多くの社会科学研究の根底にはリサーチ・トライアングルがある。このリサーチ・トライアングルという「思考の型」は,社会科学特有の「ものの考え方」「目のつけ方」「議論の組み立て方」といったようなもので,いわば「そもそも論」に相当するといえよう。リサーチ・トライアングルを理解すると「論文・本を読解する」「研究を口頭発表する」「口頭発表された研究を理解する」「論文を実際に執筆する」という初学者が欠かせない四大基礎技能を効果的にマスターできるのだ。これが本書のいうところのリサーチ・トライアングル方式の効果である。
本書は「学術論文の型」を説明した拙著『社会科学系のための「優秀論文」作成術 ―― プロの学術論文から卒論まで』(勁草書房,2010 年)の姉妹版である。いずれは本格的な学術論文を執筆する社会科学系の学徒にとっても,それまでに知っておくべき「思考の型」ならびにその使用法を本書は伝授する。本書で基礎を一度マスターすれば,後はそれを磨いていくだけ。そうすれば,ますます議論の質を高めていくことができる。本書と『社会科学系のための「優秀論文」作成術』がペアになって,「社会科学系のための知的インフラ形成の手引き」となっている。
対象とする読者
本書の主な対象読者は,大学で社会科学系専門課程(三~四年生)に入る前に基礎的な訓練を受ける人たちを想定している。本書が説く基礎を固めれば,それより上級の知的訓練もより実り多いものとなろう。「社会科学諸分野に共通する思考の型」ということは,言い換えれば「専攻分野特有のものではない一般的なもの」という意味である。いずれの専攻分野に進むにしても,本書が展開する「基礎の基礎」をしっかり理解してほしい。本書が解説するリサーチ・トライアングル方式をマスターすることが,社会科学系の大学生にとって必要な四大基礎技能を習得する最短ルートなのだ。そのうえで専門課程にのぞめばアナタの成績が大きく上昇することは間違いない。
理数工学系や自然科学系,そして保健・医学系の学生,さらには人文学系の学生にとっても「論理的思考術・四大基礎技能の入門書」として本書は役に立つ。本書の内容は常識的なこと,いうなれば一般的教養レベルのものだからだ。北米におけるリベラル・アーツ系の大学でよくあるタイプの知的訓練法といってもよい。もちろん,国際関係や総合政策といった文系の学際的分野をめざす学生や,情報社会学といった文系・理系を統合するような分野の学生にも本書は有益であろう。
さらには「大学入学前」「大学卒業後」の人たちにも本書を薦めたい。高校における探求学習科目においては,とりわけ四大基礎技能に関する箇所が活用できるだろう。大学卒業後,おのおのの現場で活躍している社会人の方々にとっても,本書が説くリサーチ・トライアングル方式はビジネス・スキルの基礎として,さらには論理思考力強化の一手段として有用である。それだけではない。誤情報や感情に惑わされず,責任ある一市民として日本社会・国際社会について自力で考え抜いていく際,信頼に足る知的思考の技法が欠かせない。本書はそれを提供する。
類書との違い
筆者が知る限り,本書はユニークな位置を占める。この手の議論を説明するほぼ唯一の本ではないだろうか。巷(ちまた)では「大学一年生のためのスタディースキル(勉学の仕方)入門書」ともいうべき著作が数多い。これらは講義ノートの取り方やレポートの書き方など,技術的なことを解説している。本書はこれらとは三つの意味で本質的に異なっている。
第一に,社会科学に特化していること。社会科学特有の思考法を体系的に,それも初学者むけに説く書物はごくごく少数の例外を除いて見当たらない。実際,巷にあふれている類書をみれば,著者の多くが社会科学の研究者ではないことに気がつくであろう。
第二に,本書はスタディースキルではなく社会科学で必要な「大枠の考え方」に焦点をあてる。そのうえで,四大基礎技能を解説していく。料理でいえば,スタディースキルは包丁の使い方やスープの作り方などの技術論に相当するだろう。他方,本書の内容はフランス料理や日本料理におけるコースメニューの組み立て方に対応する。野球でいえば,各ポジションでの守備法,さらには打撃法(バットの振り方など)が技術論に該当し,監督が考えるべき「ゲームの組み立て方」がここでいう「大枠の考え方」にあたるのだ。前者は戦術,後者は戦略と言い換えることができる。本書は社会科学の戦略論を初学者むけに提供するものにほかならない。読者も本書を通じて「社会科学における戦略の基礎」をぜひ学んでほしい。
第三に,本書の内容は海外の英語圏で通用することである。すでに「北米におけるリベラル・アーツ系の大学でよくあるタイプの知的訓練法」と述べた。筆者自身,本書が説く内容をカナダの勤務大学で実際に学生に教えており,研究活動においても使っている。別の言い方をすれば,少なくとも英語圏においてはリサーチ・トライアングル方式は普遍的なものなのだ。「曖昧なことや一見すればバラバラな情報に直面した際,自ら一定の『型』あるいは『枠組み』を採用しあてはめることにより,それらを体系化し意味づけする」ことを英語ではフレーミング(framing) という。本書で説くのはまさに社会科学版のそれにほかならない。
仮に英語力に自信がなくても,この方式を使えば「ポイントをおさえた意見交換」が英語でできるようになる。英語力が抜群でも,この方式を使わないと「いろいろ言ってはいるけれども,何がポイントなのかわからない」となってしまうのがオチ。実際,筆者が教えている多くのカナダ人学生がそういった状況に陥りやすい。さらには英語で書かれた社会科学系の文献を読む際にも,リサーチ・トライアングルに関する基礎知識が欠かせない。それがなければ,専門用語に四苦八苦し,文献内容を把握できないままとなる。英語力のレベルは関係なく,当然視されている「リサーチ・トライアングルという設計図」を把握できるか否かが問題なのだ。そういった設計図を本書は可視化して解説していく。
ただし書き
本書は,社会科学のなかでも定性的分析手法(事例研究,つまり少数の事例を使って仮説を検証していく手法)と言われるものを基礎にして議論を体系的に展開していく。この作業を通じて,これまで指摘してきたさまざまな課題をまとめて解決する「総合的パッケージ」を本書は提供する。したがって,その他の分析手法や研究方法は本書の基本枠組みから外れざるをえない。たとえば定量的分析手法(大量の数量的データを統計分析する手法)ならびにゲーム理論のような純粋に抽象レベルにとどまる研究方法が本書の枠組みから外れる。また,本書は実証主義(ポジティビズム)というものを採用している。これは「客観的証拠に基づいた仮説(解釈)の検証を通じて一般的理論の構築をめざす」というもの。実証主義を採用しないタイプの研究も本書の枠外にある。
こういった制約はあるものの,「論理的思考術・四大基礎技能の入門書」として本書はその対象内・外にかかわらず幅広い読者にとって有用であろうことはすでに指摘した。あるいは「そのまま使えそうな部分がある一方,自分が関心のある分野や使用する分析手法・研究方法に照らし合わせて訂正が必要な部分」と区別しつつ,いわば本書をたたき台として多くの読者に利用していただけると思う。
まとめ
本書を読み終えれば「なるほど,社会現象について論理的に思考するとはこういったことなのか」と合点がいくだろう。そして機会を見つけては本書が説くリサーチ・トライアングル方式を何度も使って,自己鍛錬に励んでほしい。そうすることによって,いわば「自分で考えぬく力」や「地頭力」,つまり抽象的概念を使う思考力が増していく。もちろん,問題解決法やクリティカル・シンキング,さらにはビジネス的論理思考や社会科学方法論に関する書籍を読んで自己研鑽に励み,自身の知的インフラを構築していくことも大いに結構である。こなせる知的技法は,多ければ多いほどよい。
社会が抱えるさまざまな問題について傍観するのではなく「『思考の型』を使いながら自力で考えぬく能力」を発揮してその解決に少しでも貢献できる人材,そういった人材を養成することが大学教育の一つの目的ではなかろうか。そのために本書が少しでも貢献できれば望外の喜びである。
本書の見取り図
社会科学には特有の「思考の型」があると「まえがき」で述べた。この型をリサーチ・トライアングルと本書は呼ぶが,リサーチ・トライアングル方式のポイントは以下の三点にまとめることができる。リサーチ・トライアングルは「研究のための三角形」という意味で,本書の造語である。
A 社会科学にはそれ特有の設計図ともいうべきものがある。分野にかかわらず,この設計図が大前提となっている。この設計図こそがリサーチ・トライアングルにほかならない。この設計図を理解し,マスターすることが初学者にとっての基本的課題である。
B この設計図,つまりリサーチ・トライアングルは「社会現象についての『謎解き』こそが社会科学の使命」という前提から導き出されている。この使命を達成するには設計図が欠かせないと言い換えてもよい。実際,プロの社会科学研究者が発表する著作の多くは,明示的・暗黙的にかかわらずリサーチ・トライアングルに基づいている。
C 「まえがき」で触れたように,リサーチ・トライアングルの理解は以下の四大基礎技能を初学者がマスターする際にも有用である。というのも,各技能においてリサーチ・トライアングルが下敷きの役割を果たしているからである。
・読解力:社会科学の著作を読んで内容を正確に理解するだけでなく,複数の文献が形成する目には見えないシステム(関係性)を把握する能力。簡単にいえば「読む力」。
・発表力:自分自身の考えを体系的・論理的にまとめるだけでなく,それを効果的に口頭で発表する能力。簡単にいえば「話す力」。
・理解力:他者の発言内容を理解するだけでなく,建設的なコメントをすることができる能力。さらには,意見が交錯する討論の場を運営していく能力。簡単にいえば「聞く力」。
・論文作成能力:議論を論理的に文章の形で表現できる能力。簡単にいえば「書く力」。
A,B,C の三点を解説するため,本書は二つのパートから成り立っている。パートI が基礎編で,上記のA とB を説明する。導入部である第1 章では,「謎解き」としての社会科学を説明していく。第2 章ではそのための方法であるリサーチ・トライアングルをより詳しく論ずる。この第2 章がパートI の核心部をなす。第3 章においては,学問のプロによる「謎解き」の具体例を示していく。
パートII の応用編ではC を詳しく見ていくが,そこにある四大基礎技能に対応する形でパートII は四つの章から成り立っている。これらすべての基礎技能において,リサーチ・トライアングルという「社会科学の設計図」を活用していくことがポイントとなる。
第4 章では社会科学文献の効率的・効果的な読み方を説く。第5 章では自分の考えを明確にし,それを他者にわかりやすく口頭発表する方法を解説していく。第6 章では,他者の意見の扱い方,ならびに討論の場の運営の仕方を説明する。そして第7 章では小論文,ゼミ論文,卒業論文の書き方を説明する。
七つの章からなる本書の内容を図で示せば図0-1 のようになろう。この図が示す体系が,本書でいうところのリサーチ・トライアングル方式となる。その全体像を理解するためには本書の箇所をすべて読むことが当然望ましいが,時間がないという読者は,まずは第1 章・第2 章を読んだのち,「読む力」「話す力」「聞く力」「書く力」に関する章を読んでいただきたい。また,本文では説明しなかった補助的な点はBOX のコラムで記した。その他,読者の便宜を考えて,用語解説,因果分析の基礎知識,概念分析の基礎知識,文献案内を巻末に掲載した。ぜひ活用されたい。では,始めよう。
(図は割愛しました。PDFをご覧ください)