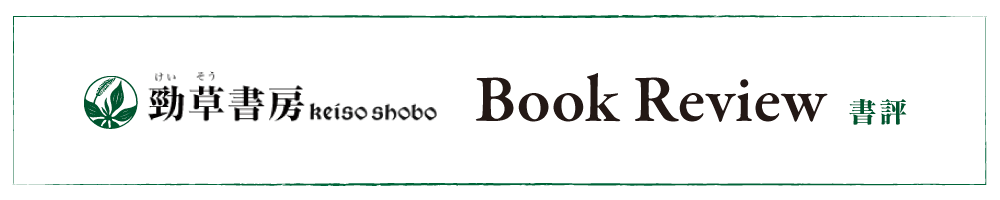書評 ケアすることと「家族」であること
評者 土屋 葉

ケアの場面で「やっぱりお母さんが一番だよね」という言葉が発せられることがある。この言葉自体はすぐにジェンダー化されたケア責任を意味するわけではないが、「ケアされる人が何を必要としているか」を探るのは女性たち(母親/娘/妻)であり、それを一番理解しているのもやはり女性たちである、ということが含意される表現として捉えられるだろう。こうしたSA(sentient activity)すなわち、「相手を注視し、何を必要としているか、何をしてあげたらよいかを考えること」を女性たちが担うことが前提とされると、ケア責任が女性に集中するだけでなく、女性たち自身が、ケアを担うことが不可避であるように感じたりすることがある。本書はこうした「ケアのしんどさ」を読み解くことにより、「ケア責任の重さ、時にケアラーが感じる罪悪感の原因を明らかにする」ねらいがある。
本書の特徴の一つは、ここからさらに「ケア責任を分け持つこと」の議論に踏み込んでいる点にある。具体的には、女性に偏っているケア責任を、男性や専門職とも分有・協働することについて目を向けている。高齢者や障害児者へのケアを、施設や自宅において専門家と協働して行う場面は、いまやあたりまえのものとなりつつある。この意味で本書の議論は、とりわけ仕事としてケアに携わる専門職が、実際のケアのみならずケアにかかわる「責任」を、だれとどのように分かち合うのかという問いに直面する際に、大いに示唆を与えるだろう。
例として、家族と専門職のSAの協働について論じた第Ⅱ部において、障害のある子どもを育てる母親たちの経験に言及している藤原里佐の論考に注目したい(ちなみに、高齢者については井口高志と斎藤曉子が論じている。たとえば斎藤は在宅ケアの場面で、ケアワーカーが家族介護者のSAを含めたケアの負担の理解が、家族介護者の負担感を軽減させる可能性について述べており、興味深い)。
藤原は、母親たちは専門家からの手ほどきや指示により、領域横断的にまた総合的に子どもをサポートするという高い専門性を有する「子どもの専門家」とみなされてきたと指摘する。彼女たちは、子どもの幼少期から成人期にいたるまで、日常動作、服薬の効果、訓練の状態等々を、領域を超えて観察し、子どもからのサインを受け止めるという〈感知・思案〉する活動(SA)を担いつつ、それらをトータルに判断しケアを担っている。
母親(女性)が子どもについて「察し、気を回し、手を回すことに長けている」ことが所与の前提とされてきた点については、本書では明確に批判されているが、藤原も、母親たち自身も自分のケアを「唯一無二」のものとしてみなしたり、「母親だから」できると捉えたりしているわけではないと述べている。さらに母親たちは、自分を含めた家族のみが適切にケア出来るということではないことを、重々承知しているという。たとえば児玉真美は母親の立場から、施設で暮らす子どもが、理学療法士の対応により明らかに身体状態を改善させ、生活の質を向上させた例について言及している(児玉 2019:268)。
しかし同時に児玉により、SAの共有やケアの協働が困難であった経験も語られている。たとえば子どもに耳の褥瘡が出来たとき、自宅では車いすに座っている時のポジショニングに気を配るなど、「生活の中」の親の「知恵」で対応した。しかし施設にこれを求めたところ「拒絶」されたという(児玉2012: 102-6)。こうした例は、ケアの「周辺」で行われる親の微細な気遣いは、集団生活のなかで蔑ろにされ、かつ「サービス」の提供という枠組みからは排除されがちであることを示すとともに、社会資源や福祉サービスの不足が、親のケア役割の継続につながることを示唆している。
こうしたことをふまえ、本書では、〈感知・思案〉する活動を脱ジェンダー(母親)化するためには、親密な他者がいるいないにかかわらず、専門職によって、まずはニーズが尊重されること、そしてサービスが調整され、問題状況が解決されるような支援の仕組みが必要不可欠であると指摘される。
ところで、高齢となった母親はケアを「できない」認定され、ケアを他者へ移行するように求められる。しかし先に述べた視点からすれば、ケア「できない」家族であっても、専門職のSAを含むサービス提供により「家族」を実践するという議論へと拡張できる。高齢となり自身もケアを必要とする母親は、障害があり母親となった女性の姿と重ねて捉えることができる。この点は筆者にとっても新たな発見であった。専門職や政策立案者は、ケア「できない」状況にありながらも「家族」でありたいと願う人びとのニーズに、どのように答えることができるのだろうか。本書は、こうした問いに対して明確な解答を提示するものではないものの、今後のケアのあり方を構想するための重要な理論的手がかりを提供している。
■文献
児玉真美,2012,『新版 海のいる風景:重症心身障害のある子どもの親であるということ』生活書院.
児玉真美,2019,『殺す親 殺させられる親:重い障害のある人の親の立場で考える尊厳死・意思決定・地域以降』生活書院:268
愛知大学文学部教員。専門は家族社会学、障害学。編著書に『障害があり女性であること――生活史からみる生きづらさ』(2023年、現代書館)、論文に「強制不妊手術はどのように「問題」化されたのか――「声にならぬ声」をめぐって」『福祉社会学研究』(2025年、22,29-47)ほか。
『ケアする私の「しんどい」は、どこからくるのか――見えないケア責任を語る言葉を紡ぐために』
- 著者
- 山根純佳・平山 亮 著
- ジャンル
- 社会・女性
- 出版年月
- 2025年6月
- ISBN
- 978-4-326-65448-2
- 判型・頁数
- 四六・288ページ
- 定価
- 2530円(税込)
なぜ、こんなにも息苦しいのか──ケアをめぐる「常識」が作り出す困難と、日常生活に織り込まれた見えないジェンダー不均衡に迫る。
勁草書房ウェブサイトへ https://www.keisoshobo.co.jp/book/b10136268.html