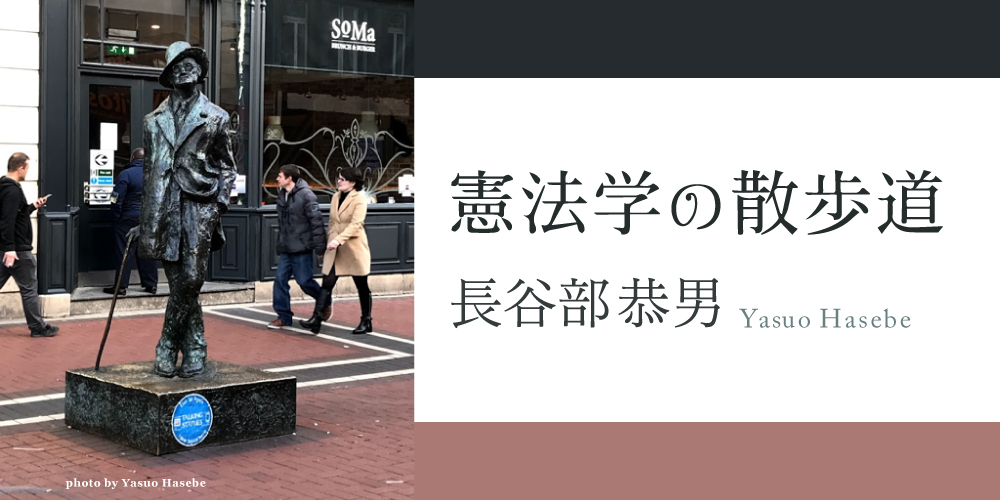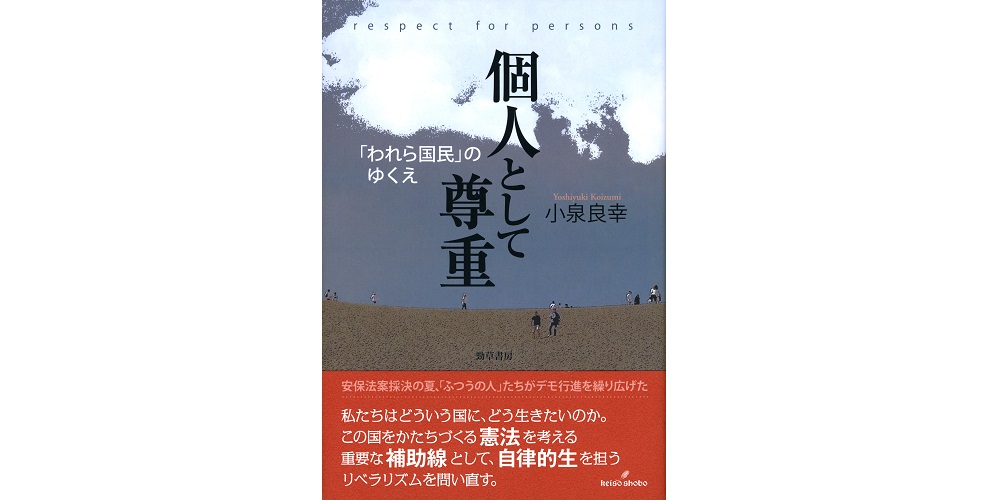憲法学の散歩道
第42回 二つの根本規範──ケルゼンとフッサール
エトムント・フッサールは現象学の祖である。彼は判断停止(epoché)による現象学的還元という手段を用いて意識の構造を分析した。 人の意識には志向性(Intentionalität)がある。庭の梅の木を見る、ショスタコヴィチの交響曲第5番を聴く、軽やかなピノ・ノワールを味わう、フッサールはフライブルク大学の教授だったと考える。対象を見たり、感じたり、考えたりする。そのとき人は意識している。 意識の内容は「梅の木」、「第5番」、「ピノ・ノワール」「フッサール」であり、そうした意味(Sinn)を持つ。人は意味を通じて対象を意識する。フッサールは、意識の内容をノエマ(noema)と呼んだ(複数形はnoemata)。人はノエマを通じて対象を意識する。……