暦のうえではすでに夏をすぎていたのに暑い日がいつまでもいつまでもつづいていたから、もう涼しくなることなどないのではないかとおもいかけたりもした、そんな朝、目覚めたときの空気がぐっと冷たくなっていた。
道にでるとそこいらにあるものをとりあえず重ね着したといった格好の人がちらほら。秋を忘れたまま、夏は冬へとうつろったかのようだった。
植木屋さんが終わったから、と母から聞いて、サイェをつれて実家に行ったのは、そんな日からそろそろ一月半ほどして、だったか。
庭の片隅には落葉がポリ袋にいくつもいっぱいになって、粗大ごみにだされるのを待っていた。
常緑樹のあいだ、銀杏の木、柿の木はほとんどの葉をおとし、幹と枝だけの姿となっている。高いところに柿の実がいくつか。
――あれは……
サイェはどことなくぼんやりと実に目をむける。
あれは、母が、サイェの祖母、おばあちゃんがひきとる。
あれはね、鳥たちに、と植木屋さんがのこしておくの。あとのはみんなとってしまって。たくさん、とってあるから、紗枝に、おかあさんに、持って帰って。
柿は甘かったり渋かったり、豊作だったり不作だったりを年ごとに不定期に気まぐれに実をつけた。そして植木屋さんが庭木を手入れしてくれると、もう、とおくないうちに年があらたまるというのが庭にでると感じられるようになる。
午後も三時をまわるとわずかに陽がかげってくるような気になり、四時をすこしすぎると新聞がみえにくくなる。
母はそんなとき、きたばかりの夕刊に目をとおしながら、切ってある柿をひとつ口にする。夕飯のしたくをするのに、甘みがからだにいるから、と。そしてわたしにすすめる。わたしはくびをふる。いつでもおなじしぐさだ。母は、でも、何年も何十年も、もちろんいまでも、おなじようにすすめ、そのあとに、おいしいのに、と洩らす。妹の紗枝は黙ってお相伴したものだったが。
サイェは柿を一口かじって、半分以上のこっている一切れをそっとガラス皿のうえにおいて、すこしよこになっていい?と誰にともなく言う。
目は柿にむいている。
こころなしか、頬は上気しているかにみえる。
駅で待ちあわせたときには特に変った様子もなかった。ふだん自分からあまり口をひらかないから、気づかなかったけれど、すこし熱があるのかもしれない。
押し入れから布団をだして、奥の間に敷く。
来客用と呼んではいるが、ぼんやりおぼえているかいないか、わたしが小さかったときをさいごに、ほんとうの意味でのお客さんにつかわれたことはない。年に一二度は虫干しされているからけっして不潔ではないのだが、鼻をよせるとどことなく古びたにおいがしみついている。
サイェを寝かせ、紗枝には一晩あずかると連絡をいれる。わたしも親がわりと泊っていくことにする。
と、暑さで疲れたからだがゆっくり回復してゆく余裕がないままになってしまう。
疲れののこったまま、こんどは寒さをこらえなくてはならないから、からだに無理がくるのだろう。
サイェ、そんな風邪をひいたんだよ。
母、がいう。しろうとのみたてだけれど。
サイェが休んでいる八畳間は、まだ部屋が持てない小さなころ、わたしも熱のでたとき、床を敷いていた。ふだんはふすまに隔てられた六畳間に父と母とならんで布団を敷いた。親たちは八畳間でテレヴィをみている。子どもたちは寝る時間になるとテレヴィの音をふすま越しにききながら、番組を想像しているうちに眠りにおちてゆく。紗枝かわたしかどちらかひとりに熱がでると、朝、寝たままの子どもをそのままに、布団をずるずると引っ張って、八畳間に移された。
天井はとても高い。梁にしきられてさまざまな木目がはしっている。どれかひとつ、ならんで曲線を描く一点に目をあわせ、それがどこまでいくのかを、いけるのかを、たどってゆく。途中で途切れたり、ほかの曲線とまじったり、ぐるっとまわって、節で終点になったり。細い線がいくつも集まっていて、どれがどれだか区別ができなくなってしまったり。
やわらかい布団から手をだして、畳にふれてみる。
指先でさっとこすり、絃をはじくように、じゃらんとはずみをつける。爪でもひっかいてみる。織られている藺草一本一本をたしかめ、たたみべりのざらざらした模様を何度も何度もなでる。
縁側でやわらかい日差しをあびながら、冬至を過ぎると、日がすこしずつすこしずつのびていくんだよ、一日に畳の一目ずつ、ってね、ともう四半世紀も前にいなくなってしまった祖母が教えてくれたこともあった。
八畳間にはステレオがあって、小さいときには意識してつけることがなかったけれど、ふせっているときだけは、微熱のなか、音楽を聴いた。
いつも《未完成》をかけた。
なぜだったのかわからないけれど、ふつうのレコードより小さい、20センチくらいの盤を。
だから、大人になってからも、《未完成》がなっていると、あの八畳間を、ほてったからだを、糊のきいてかたくなったシーツをおもいだす。
一晩泊って、翌日の夕方、紗枝がくるまでやってきた。
熱のある顔ではなかったけれど、サイェの動作はゆっくりで、機嫌がいいようにはみえなかった。
紙袋につめられた柿は、例年よりずっと多かったようだ。
両親がはたらいているサイェは、学校を終えるとわたしのところに寄ってしばらく過ごしてから自分のところに帰るという習慣だったが、かるいかぜがぬけるまではということで、下校時間をみはからって、わたしがむこうのうちに寄ることにした。ひとのうちではあったけれど、わたしはソファで本を読んだり考えごとをしたりし、サイェはそばで、わたしのところでしているように、宿題をしたり、本を読んだり、ぼんやりしたりし、あいまあいまに、ちょっとおしゃべりをする。
おばあちゃんちで、あんなふうに寝たのはじめてだった。
ふしぎ、だった。
サイェがすこし前のことを言っている。
――ふつうにではいりしているのと、布団にはいって横になっているのと、部屋のかんじが、まるっきりちがってる。
なにも、ない、ところが、とってもたくさんあって、空気がいっぱい、というか、体積? 容積? がある、って。
――古い家だからね。天井、高いし。
――つりさがっているまるい蛍光灯に照らされて、天井の木目がゆらゆらうごく。得体のしれない生きものみたいに。
おばあちゃんやおじさんがむこうで部屋をではいりすると、部屋がふわっと一瞬ふくらんで、すっ、とぬける。
――片方は大きなアルミサッシになってるけど、板ガラスがのこってる。曇りガラスになってて。
――なんかね、ガラスとささえがちょっとずれて、振動があると、かたかたする。雪見障子、っていうの? あれもかたかたしてたよね。
――そうだね、あの部屋、けっこう音がするかもしれない。
夏だと、レースのカーテンが風にあおられて、ふわっと持ちあがってさ、二重三重に模様がかさなって、いくつもべつの模様がみえてくる。
――畳に布団を敷いて寝ていると、むこうのほうの音が伝わってきて。耳が床にちかい、から? ちかくにおじさんがくると畳がむっと沈むのがわかったりもする。おばあちゃんだと、す、す、っとすれる音。
サイェは目で、いまいる自分のうちのなかを、さっと見回してみる。
そうして、すこし黙ってから、手元に冷えたお茶を一口飲む。
――うちのベッドとちがってる。
マンションだと、よその音が伝わってくる。ならびの、べつのうちのなかで何かがあっても、ときどき、わかる。むかいのうちの鍵があいたな、とか、となりのうちで何かがぶつかったり、上の階で誰かが歩いていたりものを落としたりひきずったり。
うちのなかの扉がぜんぶあいてると、廊下をとおして、よそんちの赤ちゃんの泣き声もしてくるし。
――そっか……あまり気にしていなかったけど、そうだね、たしかに、聞こえるね。大抵はそのときだけはわかっても、すぐ忘れてしまう……
――うちのなかはね、引き戸を開け閉めしたり、すぐわかる。冷蔵庫がうなって、なぜか、安心することもあったり。
かあさんがね、クローゼットをあけて何かしまったりだしたりするでしょ。そのとき、すぐわきのわたしのベッドにぶつかったりする。そうすると、ごん、と鈍い音がするけど、それだけじゃなくて、そのあとがおもしろいの。マットレスのばね、なのかな、びいん、とか、びょーん、とか、振動して、揺れて、それがしばらくつづく。けっこうつづくんだ。いつまでだろ、って感じてる。
サイェの、というか、紗枝の、といったらいいのか、このうちはマンションだから、一戸建ちとはだいぶひびきが違うのだろう。でも、サイェは、まわりでひびいている電子的な音より、偶然の物音のほうが気になるみたいだ。
――腋の下に体温計をいれると、しばらくして、ぴ、ぴ、ぴ、となるじゃない。そんなのはどうということもない。でも、昼も寝ていたから、夜、みんなが寝たあと、ちょっと目が覚めたりしてしまうの。
タイマーがセットしてある加湿器が、急に、切れたりする。そうすると、あ、夜、静かだな、静かのかんじ、がわかる。わかるような気がする。夜だな、まわりはみんな寝ているんだ、って気づく。
窓の外でくるまがゆっくり通りすぎてゆく。
むこうからこっちへ、ふわあっと紡錘のようなかたちに音がとおりすぎてゆく。
犬が一回だけ、吠えたり。足早な靴音がしたり。
この、歩いてる人、まわりの静けさ、感じてるかな、ってもおもったり。
でね、あかりをつけずに台所に行って、水を一杯飲む。よく知っているはずの部屋が、大きくなったみたい。でも、カーテンがあって、窓があって、そのむこうからほんのりと外のあかりがはいってくるから、家具たちの輪郭がわかる。
サイェ、おばあちゃんのところ、と、このうち、とどっちがいい?
サイェはしばらく黙っている。そして、どうして選ばなくちゃいけないのかな、とぽつりと言ってから、加える――わたし、選べないな。
――寝てるでしょ、ほんとには眠っていなくて、ぼんやりはしてるけど、なんとなくわかってる。
暗いなか、誰かが、寝床にやってきて、てのひら、が、額にふれる、の。
つめたかったり、あたたかかったり。
それから、布団をね、ぽん、と一回、やわらかく、たたく。
そして、むこうに。
よくわかってないんだけど、いっちゃうときに、ひろがってるかんじがする。
何なんだろ、何か、が。
あ、やだ、というのと、うん、でもいいんだ、っていうのと、そんなかんじのなかで、またとろとろしてしまう。
――ね、なんで、おばあちゃんも、かあさんも、おじさんだって、ぽん、とたたくんだろ。
わたしも、いつか、いつから、か、たたくこと、あるのかな。
[編集部より]
東日本大震災をきっかけに編まれた詩と短編のアンソロジー『ろうそくの炎がささやく言葉』。言葉はそれ自体としては無力ですが、慰めにも、勇気の根源にもなります。物語と詩は、その意味で人間が生きることにとって、もっとも実用的なものだと思います。不安な夜に小さな炎をかこみ、互いに身を寄せあって声低く語られる物語に心をゆだねるとき、やがて必ずやってくるはずの朝への新たな頼と希望もすでに始まっているはず、こうした想いに共感した作家、詩人、翻訳者の方々が短編を寄せてくださいました。その一人である小沼純一さんが書いてくださったのが、「めいのレッスン」です。サイェちゃんの豊かな音の世界を感じられる小さなお話、本の刊行を記念した朗読会に小沼さんが参加されるたびに続編が生まれていきました。ここではその続編にくわえ、書き下ろしもご紹介していきます。
【バックナンバー】
〉めいのレッスン ~クローゼットの隅から
〉めいのレッスン ~ゆきかきに
これまでの連載一覧はこちら 》》》
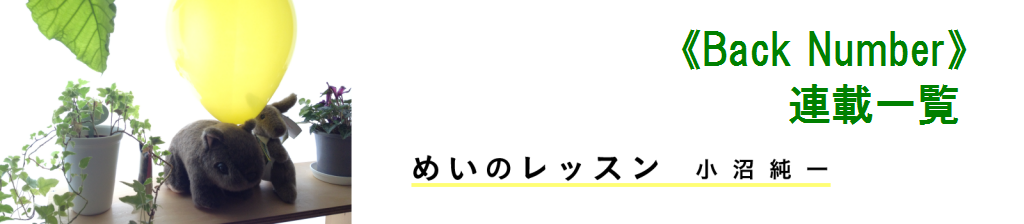
 管啓次郎、野崎歓編『ろうそくの炎がささやく言葉』
管啓次郎、野崎歓編『ろうそくの炎がささやく言葉』「東日本大震災」復興支援チャリティ書籍。ろうそくの炎で朗読して楽しめる詩と短編のアンソロジー。東北にささげる言葉の花束。
[執筆者]谷川俊太郎、堀江敏幸、古川日出男、明川哲也、柴田元幸、山崎佳代子、林巧、文月悠光、関口涼子、旦敬介、エイミー・ベンダー、J-P.トゥーサンほか全31名
書誌情報 → http://www.keisoshobo.co.jp/book/b92615.html


