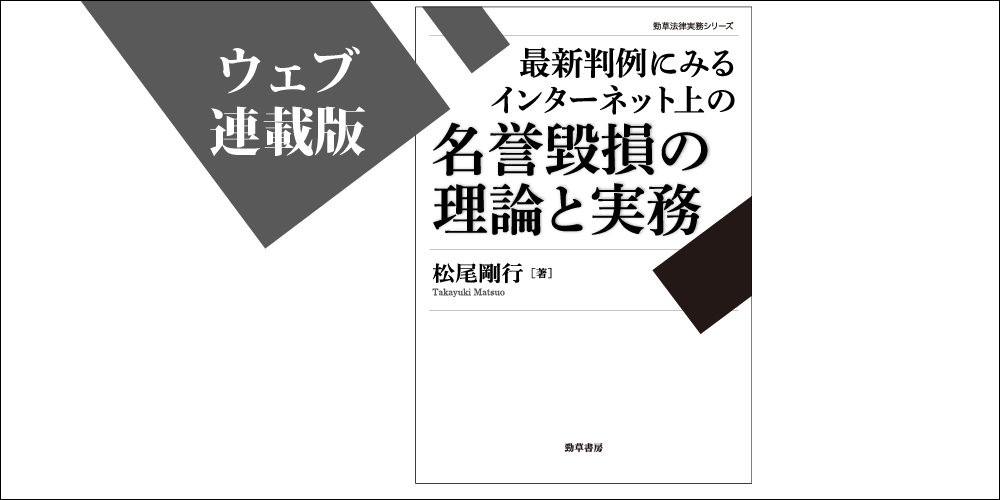虚偽の事実で名誉を毀損しても、免責されることがある? なかなか容易ではないようですが。[編集部]
最高裁判所の決定から、インターネット上の名誉毀損に関する相当性について探る
連載第8回、第9回、第12回では真実性の法理を主として検討してきました。たとえある表現が他人の社会的評価を低下させる場合であっても、①「公共の利害に関する事実」に関するもので(公共性)、かつ、②専ら「公益を図る目的」に出ているのであれば(公益性)、③摘示された事実が真実である場合(真実性)には免責されるというものです。
では、公共性も公益性もある事実を公表したものの、結果的にそれが真実ではない場合はどう考えるべきでしょうか。虚偽の事実を公表した以上は、免責を認めるべきではない。これは1つの考え方としてありえます。しかし、この考え方を貫いてしまえば、慎重に取材等を行ったものの、結果として真実とは立証できなかったときに免責が認められず、名誉毀損の不法行為ないしは名誉毀損罪が成立してしまいます。
ここで留意すべきは、この真実性は、表現者(たとえばマスメディアやインターネット上に書き込んだユーザー)が立証しなければならないということです。そして、民事訴訟でも刑事訴訟でも、日本の裁判ではある事実が立証されるには相当高いハードルがあります(注1)。
真実性がなければ絶対に免責を受けられないとすると、社会的に重要な事柄(「公共性」のある事項)について慎重な調査・取材の上で公表しても、事後的に裁判所によって真実性立証のハードルを超えていないと判断されれば、重い責任を負うわけです。それでは、名誉毀損リスクを懸念して表現・発言が萎縮してしまいかねません。
十分な取材や調査もせずに安易に他人の名誉を毀損するような情報を公開することは許されません。しかし、相当程度慎重に取材、調査をしていれば、結果的に真実性を証明するに至らなくとも、そのような行為について名誉毀損の民事・刑事責任を負わせるべきではない、これが裁判所の基本的な方向性です。
そこで、相当性の法理といわれる考え方が認められています(注2)。
この考え方によれば、たとえある表現が他人の社会的評価を低下させる場合であっても、①「公共の利害に関する事実」に関するもので(公共性)、かつ、②専ら「公益を図る目的」に出ているのであれば(公益性)、③摘示された事実が真実であると信じたことに相当の理由がある場合(相当性)には免責されます。
真実性の法理と比較すれば、①公共性と②公益性は共通しており、違いは③相当性だけです。
では、どのような場合に、相当性があるといえるのでしょうか。最高裁判所がインターネット上の名誉毀損について、相当性の有無を判断した事件をもとに、検討してみましょう(注3)。
*以下の「相談事例」は、最高裁決定の内容をわかりやすく説明するために、最高裁決定を参考に筆者が創作したものであり、省略等、実際の事案とは異なる部分があります。最高裁決定の事案の詳細は、判決文をご参照ください(注4)。
相談事例:カルト集団とラーメンチェーン店が一体だとする書き込み
Bはラーメンチェーン店を経営する会社である。これに対し、インターネットユーザーで甲というカルト集団を批判するウェブサイトを運営しているAは、Bが甲と一体性があり、Bのチェーン店でラーメンを食べると資金が甲に提供される等との投稿をした。
Bは、Aの行為がBの名誉を毀損するものであるとして、法的措置を講じたいとしている。
M弁護士はBに対しどのように助言すべきか。
1.法律上の問題点
カルト集団というのは、一般には強いマイナスの意味をもつ言葉です。
そして、客商売をしているBにとっては、そのようなカルト集団と自社が関連づけられることによる評判の悪化は到底看過できないでしょう。
そして、本件では、第2審である東京高等裁判所までの段階で真実性について主張・立証および判断が行われ、この判断を最高裁も前提としています。そして、東京高等裁判所は、Aが出したすべての証拠を検討したものの、裁判所は甲とBの間に、Aの主張するような一体性ないしは資金提供関係があるとは認められないとしたのです(注5)。
つまり、真実性が否定されてしまったのであって、Aはもはや真実性の法理に基づく免責を受けることはできません。
問題は、このような事実について、Aの主観としては虚偽を主張するつもりはなく、本当にそのような事実があったと信じていたことです。そこで、相当性の法理によって免責されないかが問題となりました。
→【次ページ】相当性の法理による免責