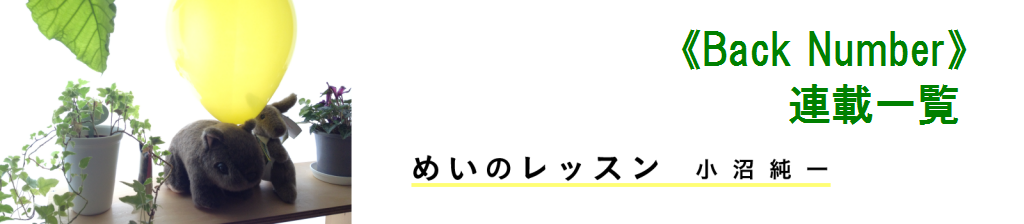サイェ、これ、なんだかわかる?
かつては勝手口と呼んでいた裏口の土間に、いくつかダンボールが積み重なっている。なかには買いおきの果物や野菜が、さもなければちょっとおいただけのあとでべつのところに片づけようとしながらついついそのままになっているものたちが、はいっている。
サイェとわたし、母は三人でお茶を飲んでいた。それがふと、そうだ、と母は席を立って裏にまわりごそごそと箱を漁る、と、てのひらにおさまるほどのものを持ってきたのである。
ごつごつしている。白い。わたしはすぐにわかる。ユリ根だ。でも、すこし、変化している。サイェは、しばらくじっと見つめ、考えていたけれど、結局、くびをふる。ううん。わからない。口にはださなかったけれど。
お正月、おせちにはいってたのよ。厚い花びらみたいになってたの、おぼえてない? ほんのり甘くて、ほくっとおいもみたいな。
あ。
サイェはくちをあける。小さく声がでる。でもそこでとまる。
ゆ・り・ね。
母がゆっくり発音する。
もう3月も終わりじゃない。年末に買っておいたの、使い忘れちゃったのが、でてきたの。食べるにはもう芽がでちゃったから、ちょっと、でしょう? 捨てちゃうにしても、まずはサイェにみせてから、って。
とはいえ、母はすでにどうするか決めていた。決めていたはずだった。大抵はそうだ。相談するときには決まっている。決めたことを伝える。ところが今回は言おうとしない。こっちの意見を聞こうともしない。しばらくサイェにいじらせたあと、またユリ根をダンボールにしまいに行ってしまった。
どうするの? 尋ねてみても生返事。まあ、内緒でやりたいことがあるんだろう。そんなふうにおもっていた。おばあちゃん、どうするのかな。サイェの表情が問いかけてくるが、わたしは口をちょっととがらせるだけで、わからない、を伝える。
サイェは母・紗枝にゆりねのこと、話しもしなかった。祖母の気まぐれをいちいち伝える必要もないとおもったにちがいない。わたしはといえば、なにか、特別な調理法でもどこかで耳にしたのではとはじめは考えていた。でも、そんなことさえすぐ忘れてしまった。
2カ月くらいしただろうか、母が電話で言うのである。あした、サイェと来る予定だったでしょ、と。
いつもはこちらから、一緒に行くから、と告げる。そう、とあっさり返されるものの、母は孫が来るのを楽しみにしている。それでいて自分から先に確認をすることなどあまりない。いや、あるのだが、そういうときはかならず「何か」あるときだ。そう決まっている。
最寄りの駅から歩いて、戸を開ける。一二歩はいって短い勾配を上がると、右に玄関、左にガラスばりの小さな温室。勾配のわきに植えられている小さな庭木には、春、花が咲く。つつじやぼけだ。でもそんな季節はすぎて、とおもっていたら、眼のはしに見慣れない鮮やかな色が。

そうおもって、視線を、眼の焦点をあわせようとしたときには、すでにサイェがそっちにむかっていて、呼ぶのだ。
――大きな花、いくつも!
そうだ、温室のわき、下のほうには福寿草が冬に、上のほうはついこのまえまで梅の花が咲いていた、そのあいだあたりに、ひょろりと高い茎が、わたしより高いところに、濃いオレンジに黒いまだらのある花が、オニユリの花が、まだこれからもとふくらんだつぼみとともに、咲いている。
大きな花で、こっちを見下ろすように。わざと花の様子をからだ全体で真似してみるが、めいはわたしのそんなおふざけにふっと口のはしを動かしただけで、また花をじっとみつめている。まんなかには長いめしべ、まわりには花弁よりもっと濃い色をした花粉のついたおしべがたっぷりと。大きなまだらがほくろのようにある花弁は、大きく曲線を描き、おしべとめしべがとびだしている。
花糸ははえている奥のところからだんだんとほそくなり、花粉をいっぱいにつけたやくを支える。やくは重たいのだろう、ふらふらしている。まんなかにあるめしべはもっと長く、独特なかたちをした白い柱頭は、ぬれて光っている。
 きっと待ちかまえていたのだろう、花に熱心になっているあいだに、母がやってきていた。ほら、少し前のユリ根。せっかく芽をだしてるのに捨てるのはもったいないから、植えてみたの。そうしたらあっという間に大きくなって、花まで咲いて。
きっと待ちかまえていたのだろう、花に熱心になっているあいだに、母がやってきていた。ほら、少し前のユリ根。せっかく芽をだしてるのに捨てるのはもったいないから、植えてみたの。そうしたらあっという間に大きくなって、花まで咲いて。
このユリ、かつて庭に咲いていたことがある。まだわたしが子どもの頃で、こんなに背が高くなることはなかった。いまある温室をまだ祖父がつくっていなくて、すこしはなれた柿の木の下にある小さな花壇に、年に1本か2本、ひょろりとたった茎と大きな花、そしてむかごが記憶にある。あのゆりはどこからきたのだったろう。そんなことは考えもしなかった。いやそれだけじゃない。多くのことは気になどしないまま、いつのまにかそこにあることがほとんどだった。何かがそこにあるのは、いつか、どうにかして、のはずなのに。
食べそびれてしまったけど、かえってこんなに楽しませてもらっちゃって。そうだね。おもいがけない贈りもの、かな。
――帰ったら、おかあさんに。
大丈夫、まだこんなにつぼみがついてるし、今度は紗枝といらっしゃい。しばらくは咲きつづけるから。
サイェは、大きく、うなずく。そして、おそるおそる手をだし、人差し指でめしべの柱頭にちょっとさわる。指先のねばねばを人差し指と親指で確かめてから、こっちをむいて、小さく微笑む。

》》バックナンバー《《
〉めいのレッスン ~冷蔵庫のなかで(2)
〉めいのレッスン ~冷蔵庫のなかで(1)
〉めいのレッスン ~なくなった駅、焼野原のご飯
〉めいのレッスン ~知らないところ
〉めいのレッスン ~ふいてつぶして(2)
 管啓次郎、野崎歓編『ろうそくの炎がささやく言葉』
管啓次郎、野崎歓編『ろうそくの炎がささやく言葉』「東日本大震災」復興支援チャリティ書籍。ろうそくの炎で朗読して楽しめる詩と短編のアンソロジー。東北にささげる言葉の花束。
[執筆者]小沼純一、谷川俊太郎、堀江敏幸、古川日出男、明川哲也、柴田元幸、山崎佳代子、林巧、文月悠光、関口涼子、旦敬介、エイミー・ベンダー、J-P.トゥーサンほか全31名
書誌情報 → http://www.keisoshobo.co.jp/book/b92615.html