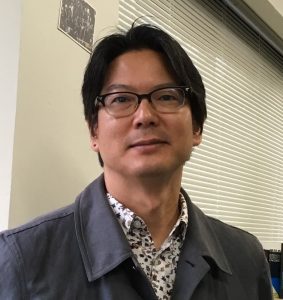[政治的に愛を語ることの難しさ]
森川 たとえばハンナ・アーレントという政治思想家がいます。私の研究対象でして、自由主義系列の思想家ではないのですが、アーレントもやはり、愛の非政治的、あるいは反政治的性質を強調しています。二者間の性愛(エロス)も、キリスト教的な愛(アガペー)も、多種多様な人間どうしを隙間なくくっつけてしまうはたらきであり、公共空間に持ち込むと市民の自由を破壊してしまう。キリスト教の隣人愛というのは、私たち各々の身体(コルプス)は、キリストの身体としての信仰共同体(コルプス)の一部なのだから、実は一体のものなんだ、という論理だが、信仰共同体を世俗国家に変えれば、自分は国家や民族の一部だ、という近代ナショナリズムの論理になる、というような批判をするわけです。愛は私的なものであり、公的政治的な領域に持ち込んではだめだ、ということを繰り返しアーレントは主張する。アイヒマン論争で批判にさらされたときも、私はユダヤ人だけどユダヤ民族愛なんか知らん、と言い放って、火に油を注ぐようなことをしている。
では、愛というものを政治の領域から追い出せばいいのか、というと、そういう話では済まないところがあります。ここからがむしろ本番なのですが、実は、愛なしでは、政治も成り立たないのではないか。アーレントは、性愛とか隣人愛なんて非政治的だと主張しておきながら、自由な政治を実現するには「世界への愛」が欠かせない、と言うのです。世界への愛とは、一体何か。本人もあまりきちんと論じてくれていないのですが、自由な共和政体をつくり、支え、将来世代に引き継ぐには、自分自身の安心立命を超えて公共的に活動する態度や覚悟のようなものが必要で、それは「世界への愛」としか呼びようがない、というような話です。もう1つ例を挙げると、ジョン・ロールズの『正義論』という、現代リベラリズムの聖典みたいな本があります。自由な政治社会の基本となる正義原理を理路整然と導きだし、正当化する、という理論書で、当然ながら愛の話なんか出てきません。ところが、邦訳で800頁くらいある『正義論』のラストに近いところで、「正義の原理に馬鹿正直に従って生きたら不幸になるかもしれないじゃないか」という疑問にどう答えるか、というくだりで、「愛の冒険」のたとえが出てきます。愛し合う2人は、たとえその結果不幸な結末を迎えたとしても、自分たちの愛を後悔したりしないだろう、それと同じように、まっとうな人間なら結果を顧みず正義原理に従って生きるものなのだ、とロールズ先生は言うんですね。なんか無茶苦茶な理屈のようにも思えるのですが、ともかく、ロールズにしろ、先のアーレントにしろ、本当に正しい政治とか社会とか、あるいは人間の生き方といったものを追求してゆくと、自分の生命とか生活とかを顧みずに他なるものへ飛び込むことをよしとするような、「愛」としか呼びようのない何かについて触れざるをえない、ということです。しかし、そうした「愛」について語ることは本当に難しくて、安易に口にするとイデオロギーと化してしまい、「愛」本来の尊さが失われてしまう。だから2人とも滅多に口にしない、ということだと思うんですね。
以上の話は、もっとわかりやすく考えることができます。たとえば、社会福祉制度が成り立つには、自分の納める保険料なり税金なりが、どこかの見知らぬ人の健康や生活を支えるために使われてもいいです、ぜひ使ってください、というような感情の共有が必要です。それを「愛」と呼ぶかどうかは別にして、「なんで俺の稼いだ金を、どっかの貧乏人が使うんだ、ぜんぶ自己責任だろ!」とかいう気分が広まったら、福祉なんて成り立ちません。実際には、世界でも日本でも、世の中はそっちの方向にむかっているわけですが。
[お金では実現できないかのように見える愛を求めてお金を稼ぐ私たち?]
森川 では、グローバルな新自由主義化のなかで、愛はもはや語られることもなくなるのか、というと、そうではない。実はますます人々は愛について語るようになり、純愛イデオロギーは強化されるんじゃないかな、という話をしてみたいと思います。さきほどから出ているように、性や家族については自己決定や自由選択の余地がどんどん増えているわけですが、われわれが生きているのは資本主義社会ですから、要するに、金さえあれば自分の欲求を実現できる、という話になります。不妊に悩む夫婦が、途上国へ行って代理母を雇って子どもをもうける、というように。普通のいわゆる恋愛結婚にしたって、「婚活市場」という言葉が示すように、そこに参入して勝ち抜いていくには、収入とか職業などの自分のスペックを高める必要があり、そのためにさまざまな自己投資をしなければならない。言ってしまえば、ぜんぶ金次第ということになる。しかし、世の中何でも金次第ということに、大抵の人は耐えられない。まあ、私もそうですが。金はあくまで手段であって、本当に欲しいものは別にあるんだ、と言いたくなる。で、それは何ですか、というと、「愛です」ってことになっちゃうんじゃないかな、という気がするんですよね。
恋愛で本当の自分を見つける、という近代日本の「恋愛」は、富国強兵の愛国イデオロギーと表裏の関係、みたいなことをさきほど言いましたが、また「立身出世」という競争社会化・資本主義化とも表裏であったわけで、それは現代でも基本的に変わっていないように思います。で、世の中ぜんぶ金次第、すべて自己責任と自由競争、ということになると、ますます純愛願望が強まり、恋愛結婚イデオロギーは脱構築どころか、強化されていくんじゃないか。家族についても同じで、多様な生殖テクノロジーが発展して、お金があればいろんな方法で子どもがもてるようになる、たとえばですけれど、私がシングルファーザーになりたいなと思って、代理母を雇う契約を結んだんだけれども、実は精子に元気がないことがわかり、精子もどなたかからお借りすることにして、子どもをもうけた、とします。ちょっと現実味のない想定ですけれども、ともかくその子が育ったときに、「自分とあんたの関係って、何で繋がっているわけ?」と訊かれたら、「愛だよ」って言うしかないんじゃないかなって。つまり、さっき王寺さんが性の自己決定についておっしゃっていた、何でも主体が自由に選んで決める、という話にしていいのか、という点にもかかわるかもしれませんが、「俺が子ども欲しかったからそうしたんだ、欲望を金の力で実現したんだ」とは言わないだろう、と。「愛だよ」と言いたくなるだろう、というのは、愛こそは自分の自由にはならないもの、やむにやまれぬもの、ゆえに尊いもの、だから。ますます選択肢が増えて、すべて市場で金次第、ということになってくると、愛がますます必要になってくる。金か愛か、ではなくて、実は金がないと愛が得られないというかたちですから、よけいに愛への渇望というかドライブが強くなっていくんじゃないかな、という気がするのです。
[愛というマジックワードの前で]
森川 で、そのとき、愛というマジックワードが政治的に利用され、動員されるのではないか、と。いわゆるネオリベ的、新自由主義的な経済政策を進めたい人たちというのは、一方で、愛国心とか伝統的家族とかが大好きだったりする。みんな政府に頼らず、強い個人になって市場を勝ち抜け、世の中は金次第なんだ、しかし同時に、みな家族を大事にしろ、国を愛せ、家族とネーションは、金には替えられない尊いものなんだ、というわけです。カジノを解禁したい人たちは、伝統的家族――というのは実際には「近代家族」なわけですが――を復活させたい人たちでもある。そういう傾向にどうやって抵抗するか、どうやったらずらしていけるか、と考えてみて、さきほどの家族の話では、家族を居場所や空間として論じてみたわけです。人が特定の他者と集い、住まう親密な場所や空間というのは、金銭には置き換えられないものではないか、ということですが、もう1つは、身体なのかもしれません。さっきの王寺さんの言い方をお借りすると、何か性別をも超越したかのような超越論的な自己がいて、そういう自己が身体を客体として自由にいじっていい、ぜんぶ決めていくというのではない、やはり身体というのは私たちの自由にならないものであり、むしろ自己とか自我のほうが、身体に属している。ちょうど、家族が自分の自由意志の産物ではなく、むしろ自由にならないものとして、そこに自分が属しているように。そこでモヤモヤしながら、生きているし、生きていくしかないのではないか、と思うんですね。
[割り切らないでモヤモヤ考えていこうよ]
森川 その関連で、さっき王寺さんのお話にでた、ピルについての相澤さんの論文は、私も興味深く拝読しました。ざっくりといえば、日本の女性解放運動では、ピルに対して非常にネガティブな評価があった。つまり、女がピルを飲めば避妊の問題は解決ということになったら、男のほうはますます何も考えなくなるだろう、そうではなくて、男に対して、「あんたコンドームつけなさいよ」ってちゃんと女の側が主張できること、そういう対等な関係をめざすことが大切だろう、という問いかけがあった。で、相澤さんはそうした問題提起に理解を示しつつ、結論としては、ピルは女性の自己選択を増やすからよい、という。論理的には、相澤さんの議論のとおりだと思うんですね。そのとおりだとは思うんですけど、それだと、女性が薬局へ行ってピルを買ったら問題は解決するよねっていう話になってしまうのではと、なんていうか、モヤモヤするわけです。フェミニストの人たちが、ピルも悪くないけどちょっとまってよ、って思ったときのモヤモヤ感を、残しておきたい、という気がするのですね。ベストな結論なんか出ないけど、男と女でやり合いながら、どうしたもんか、とモヤモヤ考えていくことって大事なんじゃないか。自己決定の自由が広がればよい、またその自己決定というのが、お金を出して薬なり技術なりを利用するというかたちをとる、ということに対するモヤモヤ感。それは、すべてが市場に放り込まれて、金があれば自己決定できるよ、愛を得るためにも金を稼がないと、という世界のなかで、いやいや愛ってそういうもんじゃないでしょう、なんかこう、もっとどうにもならなくて、だからこそ大切なものでしょう、明快に語れないものでしょう……というモヤモヤ感と通じているような気がするのです。なんか全然明快な議論にならなくて申し訳ないですが、最初に申し上げたように、愛について語るのは難しいのです! みなさんも、藤田さんと宮野さんが編まれた本を読んで、モヤモヤしてください。金で愛は買えませんが、本は買えますから、金出してください。と、最後は宣伝で終わりまーす。ありがとうございました。
宮野 結局、金かっていう話になっちゃった(笑)。では、次は王寺さんからのお話です。
[愛の擁護をします]
王寺賢太 さきほど宮野さんから、愛はイデオロギーだといってなんとなく済んでるけど、それでいいのかっていう話がありましたが、実は、僕は今日は断固、愛の擁護をするぞ、と決意を固めてやって来たんですね(笑)。森川先生がおっしゃるように、現在、すべてが交換可能になってゆく世界のなかで、実はいたるところで、あらゆる人が愛に飢えているのかもしれない。そこで愛と言われるものには、もちろん、祖国愛も、同胞愛も、ある種の友愛も考えられるし、それぞれがイデオロギー的に妙な方向に行ってしまうリスクも抱えているわけですが、ここではとくに性とのかかわりで愛について考えてみたい。その際に、これまで宮野さんが批判的に語ってこられたような恋愛結婚の「恋愛」とはまたちょっと違うレベルで、愛について考えてみる必要があるだろうと思います。
[家族制度をなりたたせる愛のイデオロギー]
王寺 おそらく恋愛結婚の最大の哲学書はヘーゲルの『法哲学』なんじゃないかと思います。そこでは、婚姻論のなかで「愛」が二度にわたって出てくるんですね。
最初は結婚に行く前です。情熱的な恋愛から結婚に進む者がいる。まさに恋愛結婚ですね。もっとも、ヘーゲルは世間的常識の王様のような人ですから、「見合い」というオプションにもちゃんと場を確保しています。家族同士がアレンジした結婚です。恋愛結婚か、見合い結婚か。ただし、いずれにせよ、情熱だけでは結婚にはならないんだよ、ということをヘーゲルは強調します。そこで出てくるのが契約です。藤田さんも論文のなかでヘーゲルにおける契約についての議論には触れているんですが、僕にとっておもしろかったのは、その契約のあとにもう一度、ヘーゲルが愛について言及していることです。婚姻は契約だけでは、個々人の意思による合意にもとづくという話にしかならない。でも、婚姻、夫婦、家族は1つじゃなきゃいけないんだ、というわけです。1つであるためには、やっぱり愛がなくちゃね、というかたちで、ふたたび愛が持ち出されるんですね。いわば婚姻は2人の契約であるのに、これを無理矢理1つであると言いくるめなければいけないときに愛が持ち出される。この「愛」は典型的にイデオロギー的なものでしょう。イデオロギーなしで制度など保たれないのだとすれば、これこそが結婚なり家族なりという制度とセットになった規範的な考え方だったのだと言っていいと思います。この愛のイデオロギーで何が成立するかと言えば、1つの単位としての家族が成立する。家父長が財産を所有し、家族の成員がその財産を共同使用する、経済的単位としての家族です。「愛」は夫婦を性的に結びつけることで、生殖や養育の問題、世代の再生産の問題にも結びつきますから、「家族」はそうして生まれた成員のあいだでの相続の秩序を定めることにもなる。
次ページ:どうしても上手くいかないものを繋ぎとめてくれるものとしての愛