
『情報法のリーガル・マインド』著者の林紘一郎さんが長く続けられた教育現場を卒業されるにあたり、4月20日に「情報を生業にして56年」と題した最終講義が開かれました。その講義準備で生まれた原稿を寄稿いただきました。56年の集大成ともいえる、“最後の単著”の『情報法のリーガル・マインド』要約版「情報法」、どうぞお楽しみください。[編集部]
ストーリー・テラーとしての自己研鑽
“もしも情報学事典の執筆依頼を受けたら”
林 紘一郎
これまで多くの著作物を生み出してきた(単著7冊、共著44冊)し、多くの査読や論文指導を引き受けてきたにもかかわらず、文筆家を断念した経験がトラウマになったのか、「私にはストーリー・テラーとしての資質が欠けている」という劣等感から、抜け出すことができないでいました。
退職を直前に控えた、おそらく最後の論文指導をしている過程で、以下の書物に出会いました。著者は「自然科学者は、自分が知っていることを細大漏らさず論文に書く時間を削って、ストーリーを作るべきだ」と言い、論文をABTで構成することを勧めています。
AAA:And ばかりが並んだストーリー性が欠けた形式。
DHY:Despite、However、Yet が多用された一貫性にかけ、否定的な形式。
――『なぜ科学はストーリーを必要としているのか』ランディ・オルソン著、坪子理美訳、慶應義塾大学出版会、2018年(Olson, Randy [2015] “Houston, We have a Narrative”, University of Chicago Press)
これは社会科学にも当てはまると考えたので、「80近い手習い」を敢行(?)し、「林流情報法」を4,000字以内で説明し、かつ著者が言うABTテンプレートに合わせる試みをしてみました。ご笑覧ください。
以下は、空想書房という志のある出版社が現れて『新情報学事典』編纂の企画を立て、「情報法」の項目を執筆するよう依頼されたら―――、という前提で、拙著『情報法のリーガル・マインド』(勁草書房、2017年)の要点をまとめ直したものです。同時に、『社会学理論応用事典』(日本社会学会理論応用事典刊行委員会編、丸善、2017年)において著者が執筆した「情報の所有と専有」の項の内容(約3,000字)を改定し、拡張したものでもあります。
《情報法》
情報法という法概念と、その総論が必要とされる理由: 1970年代以降、物質やエネルギー以上に情報の価値が高まる「情報社会」の到来が予言され、2010年代にはサイバー事象が現実社会と相互作用する「サイバー・フィジカル融合社会としての情報社会」が、より身近になった。しかし、新しい社会を律する法制度の基本は、依然として有体物に対する「所有権」に代表される「排他的支配権」である。
財産的価値のある「情報」(無体財)に、最初に権利を付与したのは1899年の旧著作権法であるが、有体物への固定を前提にした所有権アナロジーを軸にしていた。また近時刑事法分野から発展した「電磁的記録」の概念も、有体物への固定を要件にし、流通過程にある情報には適用できない。極言すれば、「無体である情報そのもの」を適切に捉えた法律は存在しない(例えば、刑法において「情報窃盗」を法定することは難しい)。
こうした「情報の捉えにくさ」を反映して、「情報法」研究は言論の自由・個人情報保護・サイバー犯罪など個別具体的な法領域の考察に追われ、「権利」や「責任」のあり方を含めた「情報法総論」は不在に近い。「所有」概念では、有体物に対しても有効に機能しない例が現れているが、無体財である情報に対してはまったく別のアプローチが必要と思われる。
所有(とその基礎にある占有)概念の適用限界: 「物を所有する」(さらには、その前段の「物を占有する」)ことを法的にどう位置づけるかは、人間社会の秩序を形成する基本的な枠組みで、生産手段や市場機能の発展と密接な関係にある。近代においては国民一人ひとりが所有権を持つことが当然とされるが、そこに至る変化は国や風土により、文化や生産方式によって多様である(加藤[2001])。
20世紀には、一時所有権を国家に統合する動き(社会主義または共産主義)があったが、「私的所有と市場」を前提にした分散的意思決定が優れていることが明らかになった。現代の民主主義社会では、所有権と自立・自律、所有権と自己決定などが同義語のように理解され、「所有」をめぐる言説は経済学や法学にとどまらず、人文・社会科学全般に広く行き渡っている(アタリ[1994]、大庭・鷲田[2000])。
しかし「所有」概念にも、有体物・無体財への適用の両面で、以下のような限界が見えつつある(大庭・鷲田[2000]、日本法社会学会[2014])。① 排他性が絶対視されると公益が阻害される(市街地の景観維持や、地震で機能不全になったマンションの建て替え、空き地・空き家問題)、② 個を尊ぶことが行きすぎると他人への配慮を欠いた無縁社会につながる(共助の難しさ、老人の孤独死)、③ 生命情報の扱いをめぐって自己決定をどこまで認めるべきかの規範が定まっていない(臓器移植、遺伝子操作)、④「会社は株主のもの」という論理を徹底しすぎると利潤が自己目的化する(リーマン・ショックの原因となった強欲資本主義)、⑤ 知的財産も「所有できる」こととし他人の利用を排除すると全体最適にならない(フェア・ユースなどの弾力的利運用が困難になる)。
情報は所有(占有)できるか: 情報などの無体財に対して所有権と同じような権利を設定できるか、設定することが機能的に優れているかは、いまだ十分検証されていない(Branscomb[1995])。わが国の民法は、「この法律において『物』とは、有体物をいう。」(85条)とし、知的財産等の情報財の取扱を特別法に委ねているが、「所有権信奉」の雰囲気の中では、アナロジーとしての所有権が生き続けている(知的所有権という表現が代表例)。
しかし情報財は、① 排他性(他人の利用を排除することができる)も、② 競合性(私が使っていれば他の人は使えない)も欠いており、むしろ「公共財」に近い面があり、「排他性」を中心にした権利設定では対応できない。加えて、③ より根源的な「占有」(一人占め)状態も不確かで、その移転(内容が受け手に移転され、渡し手には残らない)も起きず、④ デジタル化された情報は複製により拡散するが、複製は簡単で費用はゼロに近く、また品質も劣化せず、⑤ いったん(意に反して)流出したら、これを取り戻すことはできない(取引の不可逆性)し、⑥ どこに複製物があるかもわからないので削除も効果が薄い。また取引対象の財貨に限っても、⑦(財としての)価値が不確定である、といった特質を持っている。これに所有権アナロジーで対処するのは無理である(林[2017])。
知的財産権と専有: 現行の著作権制度は、上記のような難題を避けるためか、「占有」ではなく「権利の専有」という概念を用いている(著作権法21条「著作者は、その著作物を複製する権利を専有する」など)。この用語は、1887年の出版条例にさかのぼる歴史を持ち(野一色[2002])、他の知的財産制度と共有される(特許法63条など)が、学界では「排他的支配権」を示す以上に特別な意味があるとは解していない(三省堂『知的財産権辞典』にも、標準的教科書の索引にも収録されていない)。おそらく「占有論」に古くから付きまとっていた「権利は占有の対象か」という議論を避けたいためと思われる。
いずれにせよ、知的財産制度が所有権(物権の代表)アナロジーに拠っていることは否定ないが、物権と債権を峻別するわが国(あるいは大陸法系)の法制にあっては、物権には対世的(世間一般に対する)排他性があり、それが制限されるのは例外だという大原則を貫かざるをえない。したがってわが国の著作権法は、英米法的なフェア・ユースの規定を持たず、「著作権の制限」(同法2章3節5款)という素人にはわかりにくい表現をしている。その実態は、公共財的性格を有する情報財に排他権を設定する以上、権利者と利用者との間の利益のバランスを取ろうとする点にあると思われる。
現状の不便さは、all right reserved という権利貫徹(コピー・ライトの主張)と、public domain という権利不存在(コピー・レフト)の二者択一で、その中間形態(some rights reserved)がないことである。そこで、レッシグが主導したクリエイティブ・コモンズ運動では、attributionと、non-commercial、no derivatives、share-alike の3つの権利表明の組み合わせにより、6種類の中間形態を可能にしている(レッシグ他[2005])。
これは、創作者にインセンティブを与えて知的創作物の過少生産を回避しつつ、創作された著作物はなるべく利用しやすくする両睨みの作戦であり(レッシグ他[2005]、林[2004])、その限りで上述の情報財の特質を踏まえた、実効性のあるモデルと言える。
情報法総論の方向性: しかし選択肢は、あくまでも基本的な権利設定の補助手段にすぎず、現代において必要なのは、「情報財にどのような法的位置づけを与えるか」「人は情報を正しく評価できるのか」といった基本問題である。そのための試論も見られる(青弓社[2004])し、20世紀中庸の「所有権論争」(川島[1949])を乗り越える議論が起きたのも注目される(日本法社会学会[2014])が、そこでも個人データ・個人情報とプライバシーが混同されたままである。
このように批判はできるが、現時点で今後の具体案を提示することはできないので、検討すべき方向性だけを仮説的に提起すれば、以下のようになろう。
① 情報の特性を踏まえた権利設定:「排他性」より「関係性」を重視し、著作権と個人データ保護に共通の概念であるattribution(帰属)を中心に据える(主体と客体が逆転して「個人が著作物や個人データに帰属することで同定される」という発想が必要)。
② 3種の規律の組み合わせ:伝統的な権利付与法制(英米法的にはproperty rule)と同時に、不法行為法制(liability rule)や特定行為規制(categorical behavior regulation)を併せて検討する。
③ 「限定合理性」と「不確実性」:「人は合理的な判断ができる」という法原則は、両要素を取り入れて修正し、意思表示(特に「同意」の法的効果)や責任論を再構築する。
④ 「契約自由の原則」を補う「信任の法理」:前項と連動して、英米法的な「信任」の法理を活用する。
⑤ 存在証明としてのIDや証跡が前提:デジタル時代には認証が不可欠であり、実体法と手続法を一体として検討する(例、ウィルス作成罪を実体法で定めても、立証プロセスを併せて定めなければ実効性がない)。
⑥ 実体規定よりも救済手段に重点が移動:前述のとおり一旦流出した情報は取り戻せないし、デジタル社会では迅速(agile)が決め手になるので、仮処分と本案処理を統合し、短期・長期一体化したinjunctionを中心にした救済を考える。
引用文献
アタリ、ジャック・山内 昶(訳)[1994]『所有の歴史』法政大学出版会
大庭健・鷲田清一(編)[2000]『所有のエチカ』ナカニシヤ出版
加藤雅信[2001]『「所有権」の誕生』三省堂
川島武宣[1949]『所有権法の理論』岩波書店
青弓社編集部(編)[2004]『情報は誰のものか?』青弓社
日本法社会学会[2014]『新しい所有権法の理論(法社会学80号)』有斐閣
野一色勲[2002]「特許権の本質と『専有』の用語の歴史」『知的財産法の系譜』青林書院
林紘一郎[2004]『著作権の法と経済学』勁草書房
林紘一郎[2017]『情報法のリーガル・マインド』勁草書房
レッシグ、ローレンス他[2005]『クリエイティブ・コモンズ』NTT出版
Branscomb, Ann Wells [1995] “Who owns Information”, Basic Books
 著者:林紘一郎(はやし・こういちろう)
著者:林紘一郎(はやし・こういちろう)
1963年東京大学法学部卒。日本電信電話公社入社。NTT民営化後、常務理事NTTアメリカ社長などを経て、97 年慶應義塾大学教授、2004年以降情報セキュリティ大学院大学教授(この間2009年~2012年同学長)。1991年経済学博士(京都大学)取得、2004年法学博士(慶應義塾大学)取得。
主著に『ネットワーキングの経済学』(NTT出版、1989年。第6回テレコム社会科学賞。湯川抗・田川義博氏と共著で第3版(2006年))、『情報メディア法』(東大出版会、2005年。電気通信普及財団特別賞)、『引用する極意 引用される極意』(名和小太郎氏と共著、勁草書房、2009年)、『セキュリティ経営』(田川義博・淺井達雄両氏と共著、勁草書房、2011年)。2017年2月、『情報法のリーガル・マインド』を刊行。
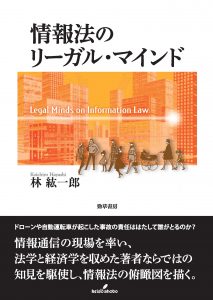
第26回大川出版賞受賞!
林 紘一郎 著
『情報法のリーガル・マインド』
ドローンや自動運転車の事故責任は誰に? 情報通信の現場を率い法学と経済学を修めた著者ならではの知見を駆使した情報法の俯瞰図。[2017年2月刊行]
「営業秘密は知的財産としてではなく、秘密として管理すべき」「ヒトがデータを所有するのではなく、データがヒトと帰属関係を持つに過ぎない。あくまでもデータが主体」「情報流通の不可逆性を前提にすれば、差止と削除命令など手続的な正義実現の重要性が増す」など、情報法に特有の法的現象を摘出したリーガル・マインドを提示する。
