あとがき、はしがき、はじめに、おわりに、解説などのページをご紹介します。気軽にページをめくる感覚で、ぜひ本の雰囲気を感じてください。目次などの概要は「書誌情報」からもご覧いただけます。
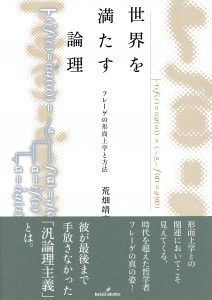 荒畑靖宏 著
荒畑靖宏 著
『世界を満たす論理 フレーゲの形而上学と方法』
→〈「はじめに」「あとがき」(pdfファイルへのリンク)〉
→〈目次・書誌情報はこちら〉
はじめに
21 世紀も最初の5 分の1 が過ぎようとしている昨今、通常われわれが「論理学」と聞いて想像する研究領域からやや外れたところで、「形而上学的論理学」、あるいは「哲学的論理学」と呼ばれる研究が静かな盛り上がりを見せている。この動向を代表するのがS・レードル(Rödl 2005)とI・キムヒ(Kimhi2018)であるが、彼らが推進する形而上学的論理学のプログラムは、ある意味で、20 世紀の論理学研究と「分析哲学」と呼ばれる(英語圏では「哲学」と同義の)伝統を、つまり論理学と哲学における前世紀の100 年間をほぼまるごと否定しようとする過激な企てであると言えるかもしれない。というのも、形而上学的論理学は、論理学と形而上学(存在論)を完全に同一視し、論理の形式とは存在の形式にほからないと主張するからである。そのかぎりで、この形而上学的論理学は、一般に「論理学の哲学」と呼ばれているものとも、また現代の分析哲学の一分野としてのいわゆる「分析形而上学」とも異なる―それどころか、それらと対立さえすると言える。論理学の哲学が、さまざまな形式論理体系や論理学的研究プログラムのもつ哲学的含意の研究であるとするなら、形而上学的論理学は、論理学と存在論の同一性を説くがゆえに、論理的諸概念の形式的研究としての―いわばフィールドの―論理学研究とそれを対象とする哲学的研究の区別を認めない。また、分析形而上学が、論理学者の開発したツールを使った言語の論理分析から形而上学的帰結を引き出す研究であるとするなら、形而上学的論理学は、論理的なものの形式と存在の形式の同一性を説くがゆえに、分析の道具としての(用途によって使い分けられる)論理学という考えを認めないのである。
ところで、このような現代の形而上学的論理学の企ては、フレーゲ以前 の論理学の伝統への―カントやフッサールの超越論的論理学や、はてはアリストテレスの形而上学的論理学への―回帰を謳うものであると思われるかもしれない。ある意味ではそのとおりである。しかしながら不思議なことに、レードルもキムヒも、現代の形式論理学の第一の始祖であるはずのフレーゲを、いわば最後の形而上学的論理学者【傍点】として扱い、フレーゲから出発し、フレーゲの考えを批判的に継承することによって、彼らなりの形而上学的論理学を展開しているのである。その意味で彼らにとっては、フレーゲの中にこそ、古典的な形而上学的論理学と現代的な形式論理学との必然的な決裂点が見られるのであり、したがって、フレーゲの読み直しこそが、前世紀の論理学と哲学の決算報告にとって不可欠な作業なのである。
こうした形而上学的論理学からのアプローチとは手法をまったく異にするものの、本書の狙いもやはり、フレーゲの思想を古い意味での―つまり、現代の分析形而上学以前の意味での、したがって分析哲学の黎明期に決定的な影響力をふるった論理実証主義者たちが必死に排斥しようとした意味での―形而上学との関連において見ることにあり、そのかぎりで形而上学的論理学のプログラムと同じく「反時代的」であると言えよう。また本書の信じるところでは、そうすることによってしか、数理論理学の創始者、アリストテレス以来の論理学の改革者、命題論理の完成者、形式言語の意味論の創始者、分析哲学の祖……といった歴史的レッテルを貼られて博物館に陳列されている単なる過去の知的偉人ではなく、時代を超えた真の哲学者としてのフレーゲの姿は見えてこない。なぜなら、前世紀のフレーゲ受容は、まるで彼を―互いに必然的な繫がりをもたない論理思想や「言語哲学」などに―知的に分裂した人格であるかのように扱ってきたが、統一的な哲学的人格としてのフレーゲは、彼の思想全般の母胎となっている形而上学からしか見えてこないと本書は考えるからである。これを以下で―導入部としての分をわきまえた範囲内で―簡単に説明しておこう。
ドイツの数学者にして論理学者であったゴットロープ・フレーゲ(Gottlob Frege : 1848︲1925)がその学問的生涯のほとんどすべてを捧げたのは、数学は論理学の一部門であり、数学の基本原理は論理学の基礎概念や基本法則を用いて基礎づけることができるとする「論理主義(logicism)」のプログラムであった。フレーゲをいわゆる分析哲学の始祖のひとりに数える者ですら、論理学と言語哲学に革命をもたらした彼の論理的言語(概念記法Begriffsschrift)が、当初は論理主義のプログラムに仕えるものとして開発されたという経緯を否定はしないであろう。そしてこの論理主義は、数学の―たしかに基幹部分であるとはいえ―一部門である算術と解析学の身分と本性についての―他に心理学主義や形式主義をライバルにもつ―ある特定の考え方であり、その意味では、数学基礎論という一分野の中でのひとつの立場にすぎない。そしてこの脈絡の中でフレーゲがわれわれに見せる顔は、主として数学者や論理学者の顔であって、哲学者の顔ではないように思われる。なぜなら、その脈絡で彼のもっとも身近にいるのは、G・ブールやG・ペアノやE・シュレーダーやD・ヒルベルト、あるいは『プリンキピア・マテマティカ』の著者のひとりであるかぎりでのB・ラッセルといった者たちであって、彼らを哲学者と呼ぶことに躊躇を覚える者は―わたしも含めて―多いだろうからである。そして、この文脈で話題にされるフレーゲの思想には、どうしても挫折の影がつきまとう。言うまでもなくそれは、『算術の基本法則』(第Ⅰ巻1893 年、第Ⅱ巻1903 年)の論理主義が素朴集合論のパラドクスに躓いて挫折したという歴史的事実のためである。
これに対して、フレーゲの哲学(彼の認識論や存在論)が、しかも単なる歴史的回顧においてではなく、現在進行形の議論の中で積極的に(肯定的にという意味ではない)論じられるとき、それは分析哲学や言語哲学の文脈においてであるのがほとんどだと思われる。ここでのフレーゲは、ラッセルやウィトゲンシュタインと並ぶ分析哲学の創始者のひとりとして、人工的な形式言語を駆使した言語の論理分析が哲学的問題への取り組みにとってどれほど実り多いものであるかを最初に身をもって示した人物として現れてくる。そして、ここで問題とされるフレーゲ哲学は、彼が実際に目指した算術の論理主義的基礎づけのプログラムと、すくなくとも必然的な結びつきはもたないものとみなされている。こうして、現代のフレーゲ研究においては、数学者-論理学者としてのフレーゲと、哲学者としてのフレーゲは、まるで別人格として扱われているように見えるのである。
本書は、この分裂した人格を完全に統合できるという大それた考えを抱いているわけではない。ただ本書は、論理主義の脈絡においてこそ見えてくるフレーゲの哲学者の顔、というものを描き出すことによって、せめてこの2 つの人格を二重写しに見ることができることを示したいと考えている。もうすこし具体的に言うなら、本書が明らかにしたいのは、数学の哲学における彼の論理主義は、また別の意味で論理主義と呼んでもよい、もっと包括的なある形而上学的理念に支えられている―正確には、その帰結である―と考えられるということである。それをフレーゲの「汎論理主義(Panlogismus)」と呼ぼうと思う。これは、フレーゲ研究者たちが彼の「普遍主義(universalism)」[*1] と呼び慣わしてきたものと同じではない。本書が汎論理主義ということで考えているのは、フレーゲの思考の奥深くに根ざす形而上学的信念のようなもののことであるが、フレーゲのいわゆる普遍主義は、さしあたりは量化についてのある特定の考え方、あるいはせいぜい、その量化理論が体現しているある特定の論理観にすぎないからである。解釈者たちの一部は、彼の普遍主義がある形而上学的帰結をもつと考えている。一例として、「概念は明確に境界づけられていなければならない」(GGA︲II : 69)というフレーゲの有名な原理を挙げよう。彼によれば、これは排中律(P∨~P)という論理法則の別名ですらある。この原理は、後期のウィトゲンシュタインが『哲学探究』で形而上学的な先入見として攻撃したことで有名だが(cf. Wittgenstein 1953 : §71)、T・リケッツとW・ゴールドファーブによればそれは、1 階の変項は対象に関して無制限であるとするフレーゲの普遍主義の直接的な帰結である(cf. Heijenoort 1967 : 325f.; Ricketts 1985 : 6 ; Goldfarb 2001 : 30)。しかし本書は、フレーゲの論理観と形而上学の関係性については、反対の見方をとる。つまり本書は、フレーゲの形而上学的な汎論理主義が必然的に、数学の哲学における論理主義に加えて、論理学におけるいわゆる普遍主義を彼にとらせたのだと考えるのである。
本書がフレーゲの「汎論理主義」と呼ぶものがいかなるものであるのかを、ここで簡単に2 つの観点から示唆しておこう。
第1 にそれは、概念は「性質(Eigenschaft)」をもつという考えに示されている。フレーゲは概念の「性質」を、その概念に包摂される―彼の言い方ではその概念の「下に属する(fallen unter)」―諸対象がもつ「徴表(Merkmal)」から区別する(cf. GLA : 64 ; GGA︲I : XIV)。たとえば、「4 頭の純血種の馬」という表現においては、「4 頭の」という表現は明らかに「純血種の」という表現とは異なる論理的役割を果たしている。というのも、純血種の馬であるような4 頭のそれぞれについて、それは純血種であると言うことはできるが、それは4 頭であると言うことはできないからである。つまり、「純血種の」が「馬」をより詳しく規定しているようには、「4 頭の」が「純血種の馬」をより詳しく規定しているわけではないということだ。むしろ、「純血種の」という表現は、〈純血種の馬〉[*2]という概念の下に属する諸対象がもつ「徴表」を指しているのに対して、「4 頭の」という表現は、〈純血種の馬〉という概念そのものについてなにかを述べている、つまりその概念にある「性質」を帰属させているのである。同様に、「直角をもつ、直線で囲まれた、等辺な三角形は存在しない」という文においては、「直角をもつ」、「直線で囲まれた」、「等辺な」といった表現は、〈直角をもつ、直線で囲まれた、等辺な三角形〉という概念の下に属する対象の徴表を指しているのに対して、「は存在しない」は、そうした対象についてなにかを述べているのではなく―存在しない対象についてそれは不可能である―当の概念の性質に言及しているのである。フレーゲによれば、この文は当の概念に数ゼロを帰属させているのである。これが、フレーゲ論理主義の根幹をなす「個数言明(Zahlangabe)は概念についての言明を含む」というテーゼ[*3] の根拠である。ところでフレーゲにとって、概念は主観的な表象とは違って客観的である。したがって、ある概念にある数を帰属させる個数言明は、なんらかの客観的な事実を記述していることになる(cf.GLA : 60)。もちろんその「事実」は、ある対象がある属性をもつという客観的事実と、類比的ではあっても同一ではない。つまり、〈直角をもつ、直線で囲まれた、等辺な三角形〉という概念には数ゼロが帰属するということは、それを把握する主体の心的作用とは独立に成り立っているという意味では、雪は白いという事実と同じ意味で客観的な[*4] 事実ではあるが、しかし雪の白さのように物理的な事実ではなく、論理的な事実なのである。
フレーゲの「汎論理主義」を特徴づけるもうひとつの方法は、それはM・ダメットが次の発言によって批判している考えそのものであると言うことである。「実在が論理法則に従うと言うことはできない。そうした法則に従ったり反したりするのは、実在についてのわれわれの思考である」(Dummett 1991b :2)。ほとんどの論理学者にとってと同様、フレーゲにとっても、論理法則はもっとも普遍的な法則である。だがそれはフレーゲにとって―そして現代の多くの論理学者や哲学者にとってとは違い―論理法則は記述的ではなく思考の規範であるということを意味するのではない。その意味でなら、幾何学の法則であれ、生物学の法則であれ、物理学の法則であれ、およそ法則と名のつくものはすべて、思考のための規範でありうる(cf. GGA︲I : XV)。ある実在領域を支配する法則は、われわれがその実在領域について真であることを考えようとするなら、その法則に従って思考すべしという指令的な力をもちうるからだ。するとフレーゲに言わせるなら、いまのダメットの言葉は、ある危険性を孕むような仕方で不明確である。第1 に、もしその言葉が、論理法則は「思考法則」にほかならないということを含意しているなら、論理法則は自然法則が自然界の出来事を支配するのと同じ仕方で思考を支配するという考えへと導く。だがそのとき、論理法則は心理学的法則であることになる。いわば、論理法則は外なる自然と対立する内なる自然の法則であることになってしまう―そしてもちろんダメットはこれを否認するだろう。第2 に、ダメットの言葉が、論理の法則はわれわれの思考にとっての規範であるということを意味するのなら、その規範的な指令の力がどこに由来するのかを説明しなければならない―そしてもちろんこれはダメットの哲学的目標となろう。この点ではたしかにフレーゲのほうが素朴で楽観的であると言えるかもしれない。たったいま述べたように、実在(のある領域)を支配する法則であれば、どんなものでも思考のための規範的法則になりうる。したがって、フレーゲにとって論理法則は、第一義的には思考のための規範的法則(規則)ではない[*5]。「論理法則のほうがより正当に「思考法則」という名に値するというのは、それでもって言わんとしているのが、論理法則とは、およそ思考がなされるところではどこであれ、どう思考すべきかを指令するもっとも普遍的な法則だということである場合だけである」(GGA︲I : XV)。論理法則だけが思考の法則であるわけではないけれども、いかなる対象についてであれ、いかなる話題についてであれ、思考一般にとっての規範でありうるという意味では、論理法則は卓越した意味での思考法則である。だがそれは、論理法則が思考一般を支配するからではなく、およそ思考の対象でありうるすべてのもの【傍点】を支配するのが論理法則だからである。「われわれの思考や真とみなすこと〔Fürwahrhalten〕のための規則は、真であること〔Wahrsein〕の法則を通じて決定されると考えなければならない。後者とともに前者が与えられるのである」(L︲II : 139)。本書は、フレーゲのこの「形而上学」こそが彼のいわゆる普遍主義や論理主義の母胎であって、その逆ではない、という立場をとる[*6]。
ところで、ヴァン・ハイエノールトが現代論理学の歴史を回顧しつつ指摘して(Heijenoort 1967)以来、フレーゲのいわゆる普遍主義は、フレーゲとラッセル[*7] に共通の立場だとされてきた。その意味でこの立場は、レーヴェンハイム︲ タルスキ以前の「古い」論理学者に特有の立場だと評されもする[*8]。現代的な観点から見ればそのとおりであろう。けれども、普遍主義者としての両者のあいだには、決定的な違いがある。それは、この普遍主義によって(フレーゲの場合は、その根底にある汎論理主義によって、と言うべきだが)科学としての論理学の「方法」にどのような制約が課せられるかということについてはっきりした自覚をもっていたのはフレーゲだけだ、という点にある。たしかに、彼らの普遍主義は、彼らをいわゆる「形而上学的内部主義(metaphysical internalism)」(Sullivan 2005 : 85)に加担させ、最終的には、シェファーが「論理中心的窮境(the logocentric predicament)」[*9] と呼んだものへと追い込むように思われる。これは、ただひとつの普遍的論理はいかなる説明も正当化も不可能である、なぜならそのためには当のその論理を使用するという循環を犯さざるをえないからだ、というものである。本書の見るところでは、フレーゲはそれを窮境だとは見なしていなかったが、それによって自身の論理学が、そのもっとも根幹の部分で、現代論理学から見るときわめて特異な方法―すくなくとも、論理学や算術の形式的体系の内部で許されるやり方とはまったく異なる方法―に訴えざるをえなくなるということは自覚していた。この方法をフレーゲは「解明(Erläuterung)」と呼んだのである。おそらくはギーチが最初に指摘したように[*10]、フレーゲの普遍主義と、それによって要求される解明という方法は、『論理哲学論考』のウィトゲンシュタインに受け継がれていると考えられる。語りうるすべてのものに浸透し、つまりは「世界を満たし」(Wittgenstein1922 : 5. 61)、またそれゆえに「自分で自分の面倒を見る」のでなければならない論理(cf. Wittgenstein 1979 : 2)は、フレーゲにとってと同様ウィトゲンシュタインにとっても、語る主題にはなりえないものであったと考えることができる。
本書が最終的に明らかにしたいことは、大きく分けて次の2 つである。第1は、数学の哲学におけるフレーゲの論理主義は、彼の汎論理主義によって動機づけられておりながらも、皮肉なことにその挫折[*11] も、ほかならぬ彼の汎論理主義によって必然的にもたらされたものだということである。第2 は、いまなおその解釈をめぐって論争が続行中である「フレーゲの不思議なところ」のいくつかは、彼が解明という方法を用いて汎論理主義を貫徹しようとしたことの結果として理解することができるということである。
以下、まず第1 章では、数学の哲学におけるフレーゲの論理主義が、彼の「汎論理主義」とも呼ぶべき形而上学的な根本理念を母胎とし、そこから生い育ってきたものでありながら、最終的にはその同じ形而上学によって完遂を妨げられたということが論じられる。第2 章は、彼の汎論理主義が、彼を普遍主義者たらしめ、それによって同時に彼を「内部主義者」(あるいはパトナムの言い方では「内部実在論者」)たらしめ、その帰結として彼が「論理中心的窮境」と呼ばれるものに追い込まれてゆく(ように見える)経緯を追う。それを受けて第3 章は、それが実はフレーゲにとって窮境ではなかったことが理解されないのは、自身の汎論理主義が自身の方法にいかなる制約を課すことになるかを(ラッセルとは逆に)彼が完全に認識していたことが真剣に受け取られていないためであると論じたい。彼がそれを自覚していたことの証左が、彼の特異な「解明」という方法なのである。
ところで、ヴァン・ハイエノールトに始まり、リケッツやダメットにまでいたる、フレーゲを内部主義者として読もうとする解釈伝統は、近年、フレーゲが実際に書いていることを素直に読むかぎり、彼にメタ的視点が―したがってメタ理論や意味論が―不可能であったとは到底信じられないと主張する解釈陣営からの猛攻撃に晒されている。フレーゲが論理中心的「窮境」にはまったことは否定するものの、彼の普遍主義はいわゆる「内部主義」と深く関係すると考える本書は、当然ながら、この反論にも対処せざるをえない。それが第4 章の主題となる。
いま述べたとおり、このように議論を進めていく中で、本書が期待していること―したがって本書が配慮せねばならないこと―がある。それは、現代のわれわれの目から見ると明らかに誤っていると、あるいは控え目に言ってもきわめて奇妙だと思われるフレーゲの数々の主張や議論のいくつかが、彼の形而上学と方法―「汎論理主義」と「解明」―の観点から見ればその奇妙さを失うということが、読者にとって明らかになることである。
(傍点省略、脚注は末尾にまとめて掲載)
あとがき
本書のタイトルは、本書の主人公であるゴットロープ・フレーゲ自身の言葉ではなく、L・ウィトゲンシュタインのよく知られた言葉―「論理は世界を満たす。世界の限界は論理の限界でもある」(『論理哲学論考』5.61)―からとられたものである。このねじれは、本書の誕生の経緯に由来する。おそらく5年前くらいまでは、それまでの研究の集大成として、L・ウィトゲンシュタインとM・ハイデガーという、20 世紀を代表する2 人の哲学者を、彼らの哲学的方法という観点から比較検討した一書をまとめようと考えていた。彼らを一緒に扱った研究書や研究論文は、それほど多くないとはいえ、あるにはある。しかし、論じられている内容や論述のスタイルの点では似ても似つかない『論理哲学論考』と『存在と時間』を、方法の共有という点から読み解こうとした研究は世界的に見ても類例がないと思われたのである。それをわたしはそれぞれ、ウィトゲンシュタインの「示し(Zeigen)」の方法とハイデガーの「形式的告示(formale Anzeige)」の方法として取り出そうとしていた。ところが、この研究構想を具体的に肉づけしようとしてあれこれ読んだり書いたりしているうちに、彼らの方法の独自性と、なによりもその眼目を明らかにするためには、どうしても他の哲学者の、しかも彼らが哲学的方法の点でそれぞれ決定的な影響を受けながらも、それを乗り越えることで独自の方法を彫琢していった、そんな当て馬を物語に登場させることが必要だと思われたのである。「当て馬」というと聞こえは悪いが、いわば彼らの大恩ある師匠筋に当たる哲学者たちである。ハイデガーの場合それは現象学の創始者であるE・フッサールであり、ウィトゲンシュタインの場合は―本書を読んで頂いた方ならすでにお分かりだと思うが―B・ラッセルではなく、フレーゲだったのである。
しかし、わたしはここでも自分の見込みの甘さを思い知らされることになった。フレーゲの書いたものを読み進めるほどに、彼が、わたしの本の序論部分で当て馬として扱えるようなスケールの哲学者ではないことが否応なく明らかになっていったのである。とりあえずそれまでの研究成果を試行的にまとめておこうと―そしてできればこれを序論にしてしまえと目論んで―書いた論文がある。それが5 年前に書いた「フレーゲの「形而上学」と「方法」―汎論理主義と解明」(『ヨーロッパ文化研究』成城大学大学院文学研究科紀要第33 集、2014 年、pp. 29-120)である。この論文は結果として本書の第1 章の前半(1. 1~1. 3. 1)、第2 章、そして第3 章の一部(3. 1~3. 3)の元となったものだが、ウィトゲンシュタインの当て馬としてのフレーゲの姿を描ききろうとしただけでこの分量(約65,000 字)になってしまった時点で、わたしはすでにフレーゲに夢中になっていたのだと思う。本文でも何度も強調したように、フレーゲは言語哲学や論理学の歴史博物館に入れてしまうにはあまりにももったいない存在である。本書がそのことを読者にすこしでも印象づけることができたなら、筆者としては望外の喜びである。
本編ができあがっていないし、できあがる予定もいまのところないので、こういうのはスピンオフとは言わないのだろうが、5 年前のわたしにはとても想像できなかった本がそれこそ瓢簞から駒のように出版されることになったことに、わたし自身がいちばん驚いている。しかしもちろん、本書がこのように刊行にまでたどり着けたのは、多くの方々から教示・支援・?咤激励をいただいたおかげである。そうした方々に、この場を借りてお礼を述べさせていただきたい。
まず第一にお礼を申し上げたいのは、首都大学東京(悦ばしいことにもうすぐ伝統ある「東京都立大学」に戻る)の岡本賢吾教授である。岡本先生は、小さな研究会で本書の原稿の一部を発表する機会に何度もお越しくださり、そのたびに多くのご批判と有益なご教示を賜った。けっして大げさではなく(また冗談でもなく)、本書の最終稿の一行一行は岡本先生を想定上の読者として仕上げられたと言える。それはたぶん、本書をいちばん最初にいちばん真剣に読んで、いちばん真面目に(たぶんメタクソに)批判してくれそうなのが、岡本先生だからなのである。この場を借りて衷心よりお礼を述べさせていただきます。
また、昨年度わたしが慶應義塾大学文学部で開講した「哲学倫理学特殊ⅠB・ⅡB」に出席して毎回熱心にリアクションペーパーを書いてくれた学生諸君にも感謝いたします。できあがった原稿をコピーして学生に配布し、指名して段落ごとに読み上げさせ、口頭でまとめさせる、というムチャな授業によくついてきてくれたと思うが、わたしの文章に対する彼らの誤解、彼らの素朴な疑問、そしてもっともな批判のおかげで、わたしの独善的な文章はかなりましになった、と思いたい。本当なら覚えているかぎりの学生の名を挙げておきたいところだが、万が一漏れがあった場合不公平になるので、やめておきます。ともあれ、皆さん、どうもありがとうございました。
また、本当に藪から棒に持ち込んだこんな売れそうもない原稿の刊行を、たいした注文もつけずにご快諾くださり、あまつさえメールで「失礼な言い方になってしまいますが、相当に専門的な研究書であるにもかかわらず、意外に売れるのではないかなと思っています」というありがたいお言葉を頂いた、勁草書房編集部の渡邊光さんに感謝申し上げます。渡邊さんの予言が当たりますように!
最後に、わたしの愚かなミスと面倒な注文でさんざんご迷惑をおかけしたにもかかわらず、このようなものすごく素敵なカバーをデザインして頂いた寺山祐策さんに、心より感謝いたします。
私事になるが、本書の原稿を書いているあいだに、私の人生には大きな変化がいくつかあった。そのうちのひとつが、父親の死去である。たぶん何歳で死なれてもそう思うのだろうが、比較的若い父親だったために、逝くのがあまりにも早すぎる気がした。死なれるまでありがたみが分からないとは、なんとも親不孝な息子だが(いや、それこそ息子らしいのかもしれないが)、最近とみに父親に似てきたと言われても、以前ほど嫌ではなくなってきている。たぶん書いてあることは一行も理解してもらえなかったと思うが、本書の刊行をこの世でいちばん喜んでくれた人だったのではないかとも思うのである。
本書を亡父・憲一に捧げる。
2019 年(令和元年)7 月24 日
神奈川県川崎市にて 荒畑靖宏
「はじめに」脚注(傍点省略)
*1 フレーゲにこの立場を帰属させ、この立場こそが彼にメタ理論的発想を不可能にしたとする解釈としては、Heijenoort 1967 ; Goldfarb 1979, 2001 ; Dreben & Heijenoort 1986 ; Ricketts 1985, 1986 ;Dummett 1991a ; Hintikka & Sandu 1992 などがある。この解釈については本書第4 章で扱う。
*2 以下では、集合やクラス、概念の外延、述語表現などと概念そのものを区別することが必要になるため、当の概念それ自体を指すための苦肉の策として、原文で通常の引用符(“horse” や„Pferd“や»Pferd« など)が付されている箇所を翻訳して引用する場合は除いて、このように山括弧を用いることにする。
*3 Cf. GLA : 59︲60 ; GGA︲I : 3 ; RH : 328 ; LM : 269 ; AD : 277 ; ZA : 295.
*4 フレーゲの客観性概念については、『算術の基礎』(GLA)の第26 節がもっとも明快な説明を与えている。それによれば、「わたしは客観的なものを、手で摑めるもの、空間的なもの、現実的なもの〔das Handgreifliche, Räumliche, Wirkliche〕から区別する」(GLA : 35)。「現実的なもの」が客観的なものから区別されるのは、前者が、主体に因果的に働きかけて(wirken)主体の内部に主観的な感覚や表象を「引き起こす(bewirken)」ものであるかぎりにおいてである。したがってたとえば、「白い」という色彩語は、それがわたしがたとえばいまここで―対象からの働きかけ(Wirken)をつうじて―感じているものを指すかぎりでは、主観的かつ現実的ななにかを指しているが、わたしが概念を用いて考えているものを指すかぎりでは、客観的かつ非現実的ななにかを指している。「雪を白いと呼ぶとき、ひとは、通常の日光の下で一定の感覚に基づいて認識される客観的性質〔objektive Beschaffenheit〕を表現しようとしているのである。雪に色つきの照明が当てられている場合には、ひとは判断に際してその点を考慮に入れる。場合によってはこう言うだろう。雪はいま赤く見えるが、しかし実際には白いのだと。[…]このように色彩語がわれわれの主観的感覚を指していないことはしばしばある[…]むしろ客観的性質を指すことはよくある。以上のように、わたしが客観性ということで理解するのは、感覚する、直観する、表象する、かつての感覚の記憶から内的像を描く、というわれわれの働きからの独立性であるが、しかし理性からの独立性ではない」(ibid.: 36)。よって、「客観的であるのは、法則的なもの、概念的なもの、判断可能なものであって、これは言葉で表現されうる」(ibid.: 3)。
*5 このことは、算術は第一義的に規則に従った記号操作ゲームであるとする形式主義に対する批判という文脈での、フレーゲの次の発言からも窺える。「行動の指針としては、形式的算術の規則は、内容的算術の法則よりも道徳法則のほうに親近性がある。内容的算術の法則は、たしかに誤認されることはあっても、違反されることはありえないからだ」(GGA︲II : 117)。わたしがある道徳法則に違反していながら、それでもある行為をおこなっていることは可能である(それどころか、もしそれが行為でないなら、わたしに関して道徳法則の順守や違反が問題となるはずもない)。これに対して、フレーゲの考える内容的算術―意味(Bedeutung)の領域に根拠をもつ算術―の法則に違反しながら、それでもわたしが算術をしていると言うことはできない。したがってわたしは、算術をしたままで算術法則に違反することはできないのである。これはそのまま論理にも当てはまる。よって、道徳法則を典型的な規範的法則とするなら、その意味では算術法則と論理法則は規範的法則ではない。
*6 もちろん、以上の2 つの主張を含む立場の名称としては、本書の提案する「汎論理主義」よりも、もっと流布している「論理的実在論」などのほうがふさわしいのではないかという異論もあろう。しかし、以下で明らかになるように、本書がフレーゲのうちに見ている形而上学は、ただ単に、論理的対象や論理的事実が存在するとか、論理法則は実在的法則であるという立場には留まらない。詳細は以下の1. 2 ならびに1. 3 を参照せよ。
*7 正確には「初期ラッセル」と言うべきかもしれない。というのも、ラッセルは1914 年の『外界の知識』(Russell 1914)で「論理形式」という概念を導入したが、この観念や、それと似た「形式的論理特性(formal logical property)」といった観念によって、しかじかの形式をもつ命題はすべて真であるという内容のメタ命題を与えることが可能となるからである。Russell 1919 のChap.XIV, XV を、とりわけp. 158 を参照せよ。この解釈についてはCartwright 1982 を参照せよ。
*8 たとえばゴールドファーブは、フレーゲがすでに現代の量化理論の中心的観念を―したがって形式化された体系の完全性と健全性の観念も―手にしていたも同然であるという解釈に反対し、1920 年代の論理学の展開がどれほど辛苦に満ちたものであったか、量化と形式的体系についての現代のわれわれの見方とはどれほど異質な動機づけと観点をもっていたかを、フレーゲ、ラッセル、ホワイトヘッド、パース、ブール、シュレーダー、レーヴェンハイム、スコーレム、ヒルベルト、エルブランを通覧し、説得力ある歴史物語を展開している。このときゴールドファーブは、フレーゲをどちらかというと時代遅れの論理学者として描いているように見える。Cf. Goldfarb 1979.
*9 「「自我中心的」窮境のせいで、形而上学において一定の理論を証明することが、絶望的ではないにしても、困難になるのとちょうど同じように、同様の「論理中心的」窮境によって、論理の基礎を定式化しようという試みは、非常に厳しいものとなる。論理を説明するためには、論理を前提としかつ使用しなければならないのである」(Sheffer 1926 : 227︲8)。アナロジーの元ネタである「自我中心的窮境」というのは、デカルト以来われわれが置かれていると自明視されている状況を指すものとしてR・B・ペリーの命名によるものであり(cf. Perry 1910)、この状況が、彼が「存在論的観念論」と呼ぶ立場(バークリーやショーペンハウアー、または英国のへーゲリアンとして有名なブラドリーなどがその例として挙げられている)を支持するとされる。この論文でのペリーの意図は、かりにわれわれが本当にこの状況に置かれているとしても、そのことは観念論者の考えるような形而上学的な帰結をもたない、と論証することにある。
*10 Geach 1976 : 55︲56:「(1)フレーゲはすでに次のような論理的カテゴリーの区別が存在すると考えていたし、また彼の論理学の哲学のせいでどうしてもそう考えざるをえなかった。すなわち、うまく構成された形式言語の中にはっきりと示されているが、言語で適切に主張することのできないようなカテゴリーの区別である。そうした区別を自国語で伝達しようとしてわれわれが用いる文は、論理的に不適切であり、記号論理の適格な式への翻訳を許さない。[…](2)問題のカテゴリーの区別は、言語表現の特徴であると同時に、われわれの言語が記述している実在の特徴でもある。その結果として、「意味論的上昇〔semantic ascent〕」という操作―世界の中の物事についての言説を言語の中の表現についての言説に変形すること―は原理的には、問題を解決するための企てとしては、あるいはとくに、(1)の下でもちあがる、語りえないものにまつわる諸々の困難を取り除くための企てとしては、完全に無駄であることになる。(3)ウィトゲンシュタインの『論考』はテーゼ(1)をフレーゲから受け継いでおり、変更点はといえば、フレーゲが認めていなかった他のカテゴリーの区別が認められているということくらいである。テーゼ(2)はそのまま引き継がれ、より声を大にして述べられている」。また、Geach 2010 : 13︲14, 16 をも参照せよ。
*11 近年では、フレーゲの挫折の元凶を除去したうえで彼の論理主義のプログラムを継承しようとする、いわゆる「ネオ・フレーゲアン」たちの研究が注目を浴びている。この新しい論理主義の試みについての概説と評価については、野本2012 の第IV 部ならびに田畑2002 の第9 章、ならびに以下の1. 4 を参照せよ。

