あとがき、はしがき、はじめに、おわりに、解説などのページをご紹介します。気軽にページをめくる感覚で、ぜひ本の雰囲気を感じてください。目次などの概要は「書誌情報」からもご覧いただけます。
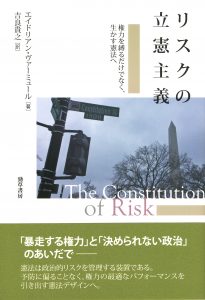 エイドリアン・ヴァーミュール 著
エイドリアン・ヴァーミュール 著
吉良貴之 訳
『リスクの立憲主義 権力を縛るだけでなく、生かす憲法へ』
→〈「訳者あとがき エイドリアン・ヴァーミュール:制度的キャパシティへの全体論的視点 」(pdfファイルへのリンク)〉
→〈目次・書誌情報はこちら〉
訳者あとがき
エイドリアン・ヴァーミュール:制度的キャパシティへの全体論的視点
吉良貴之
本書はAdrian Vermeule, The Constitution of Risk, Cambridge University Press, 2013 の全訳である。原題を直訳すれば『リスクの憲法』であるが、既に同様のタイトルの書があることから『リスクの立憲主義』とした。副題の「権力を縛るだけでなく、生かす憲法へ」は原題にはないが、本書の内容を踏まえ、訳者の側で付記したものである。帯の文章もすべて訳者による。
英語のconstitution には「憲法」の他に「構成」という意味もあり、政治的リスクを最適に配分=構成するものとしての憲法という意味合いも当然に込められている。また、本書に直接登場することはないが、経済学者のフリードリヒ・ハイエクにはThe Constitution of Liberty, University of Chicago Press, 1960(気賀健三・古賀勝次郎訳『自由の条件(ハイエク全集Ⅰ‐六、七、八)』春秋社、二〇〇七年)という著作があり、その反設計主義的な思想も念頭に置かれていることだろう。
著者のエイドリアン・ヴァーミュールは一九六八年生まれの気鋭のアメリカ公法学者である。母のエミリー・ヴァーミュールはギリシャ古典の研究者であり、ハーバード大学教授を長く務めた。父のコーネリアス・クラークソン・ヴァーミュール三世は古代芸術の研究者であり、ボストン美術館の学芸員を長く務めた。特に世界の貨幣の研究で知られ、日本貨幣史についての研究書もある(Japanese Coinage, Numismatic Review, 1953)。妹のブレイクリー・ヴァーミュールは英文学者であり、現在、スタンフォード大学の教授を務めている。エイドリアン・ヴァーミュールの著作は狭義の公法学にとどまらず、社会科学全般、人文諸学、および自然科学にまたがる分野横断的な問題関心と道具立てが特徴的であるが、そうした関心の広さにはこの学者一家における生育環境が強く影響していることだろう。
ヴァーミュールは一九九〇年にハーバード・カレッジを卒業し(AB)、一九九三年にハーバード大学ロースクールを修了している(JD)。その後、連邦最高裁判事アントニン・スカリアのロークラークなどを務めた。スカリア判事は現代アメリカの憲法理論において、憲法制定者の当時の意思を憲法解釈の基準とする原意主義(originalism)の代表的論客である。ヴァーミュールの憲法解釈理論、とりわけ司法におけるそれはテクスト主義(textualism)であり、憲法テクストから自然に読むことのできる範囲に解釈の幅を限定する。両者は同じものではないが、司法による解釈を通じた憲法作成に一定の歯止めをかけようとする点が共通しており、ヴァーミュールの議論にはスカリアの影響も当然にある。もっとも、ヴァーミュールのテクスト主義はあくまで暫定的に採用される戦略であり、その理論的根拠は(後にまた触れるが)司法のキャパシティ不足によっている。制度状況によってはまた別の解釈戦略が推奨される場合がありうることは確認しておく必要がある。
ヴァーミュールの学者としてのキャリアは、一九九八年のシカゴ大学ロースクールへの着任から始まっている。その後、二〇〇六年にハーバード大学ロースクール教授(公法学担当)に就任した。二〇一二年には四三歳の若さでアメリカ芸術科学アカデミー会員に選出されるなど、早くから目覚ましい活躍をしている。
日本語でアメリカ憲法学の議論状況を概観できる有益な書として駒村圭吾・山本龍彦・大林啓吾編『アメリカ憲法学の群像――理論家編』(尚学社、二〇一〇年)があり、そこではフレデリック・シャウアー、ブルース・アッカマン、キャス・サンスティン、マーク・タシュネットといった、本書でも検討の対象とされている学者たちが取り上げられている。本書『リスクの立憲主義』原著が出版されたときにはサンスティンやタシュネットがコメンテイターを務めるパネル・ディスカッションが開催されており、YouTube でその様子を見ることができる(https://www.youtube.com/watch?v=VDTUlWFw30c)。ヴァーミュールはそうした世代に続く、現在最も主導的な公法学者の一人である。
ヴァーミュールのこれまでの単独の著書には以下のものがある。
Judging under Uncertainty, Harvard University Press, 2006
Mechanisms of Democracy, Oxford University Press, 2007
Law and the Limits of Reason, Oxford University Press, 2009
The System of the Constitution, Oxford University Press, 2011
The Constitution of Risk, Cambridge University Press, 2014(本書)
Law’ s Abnegation, Harvard University Press, 2016
このほか、エリック・ポズナー、キャス・サンスティンといった著名な学者との共著や、多数の学術論文がある。二〇一五年にはオンライン書評サイトThe New Rambler をエリック・ポズナーらと共同で設立するなど、幅広い場で活躍中である。
本書『リスクの立憲主義』は彼の著作の初の日本語訳である。日本語でのヴァーミュールの議論の紹介・検討はまだそれほど多くないが、代表的なものとして、松尾陽「法解釈方法論における制度論的展開(一)(二完)」(『民商法雑誌』一四〇巻一号、二号、二〇〇九年)、大林啓吾『憲法とリスク:行政国家における憲法秩序』(弘文堂、二〇一五年)などがある。本書の翻訳および本解説の執筆にあたってもおおいに参考にさせていただいた。
ここでは以下、本書の内容について若干の解説と検討を行う。
一、憲法は政治的リスクを管理する
まず本書の中心的主張を簡単にまとめると、〈特定のリスクのみに焦点を当てた予防策は往々にして逆効果をもたらしかねず、リスク規制は関連するすべてのリスクを考慮に入れて最適化されなければならない〉というものである。本書は二部構成をとっており、第一部は主に理論的な水準での議論が展開される。ヴァーミュールの論述は明快だが、アメリカ憲法学の最近の議論に慣れていなければ取っつきにくいところもあるかもしれない。そう感じた読者は、第二部の応用編から読み始めるのもよいと思われる。たとえば第四章の自己裁定禁止原則「何人も自身の事件の裁定者たることはできない」とか、第五章で扱われるセカンド・オピニオンの仕組みなどは、それをできる限り厳密に守ったほうが、公職者による利己的な行動や、熟慮に欠けた判断を防ぐためによい、というのはほとんど常識だろう。しかし、そうした予防策そのものがまったくの逆効果をもたらす例が多く示されていく論述は非常識きわまりなく、特に予備知識を前提とせずに面白く読むことができる。その後で第一部の理論的記述に戻ると、各種の憲法上の議論でどのような場合を想定すればよいのかがイメージしやすくなるかもしれない。
さて、本書の内容に入る。本書はリスクの憲法的規律を主題とするが、通常のリスク論で取り上げられる具体的なリスク、たとえば公衆衛生や環境、セキュリティや金融といったことについて直接論じる箇所は残念ながら(?)ほとんどない。ヴァーミュールによればそうした具体的なリスクは「一階のリスク(first-order risk)」に分類される。一階の諸リスクは現代の行政国家化の進展によってますます複雑に、そして多種多様になっている。その規制(regulation)や管理(management)が法にとって大きな課題であることは言うまでもないが、本書が焦点を当てるのはその具体的なあり方ではなく、そうした一階のリスクに法が適切に取り組むための制度設計である。ひとまず憲法システムに限ってみても、各種の一階のリスクに取り組む部門(branch)には大きく分けて司法府、行政府(執行府)、立法府の三つがある――むろん、その中でもいくらでも細かく分けることができる。さて、多種多様な一階のリスクに対応するのに最も適した部門はどこだろうか。
従来の憲法理論であれば、人権保障の最後の砦として司法府に多大な期待がかけられていた。それに対し、現代においては行政府や立法府の専門的な能力こそ重要になっていると主張する論者も多いことだろう。しかし本書のヴァーミュールの最も重要な主張の一つは、一階のリスクを管理する部門をあらかじめ決定することはできないということだ。それは具体的な問題ごとに文脈依存的に見ていかなければならない。たとえば裁判所はある一階のリスクを最もよく管理するかもしれないが、情報収集能力が貧弱であるといった事情によって、他の一階のリスクにはうまく対応できないかもしれない。制度によって構成される各部門はそれぞれに異なったキャパシティを有しており、それにそぐわないリスクを担当したところでうまくいくわけもない。ヴァーミュールは、その名声を一気に高めた最初の著作『不確実性下の判断(Judging under Uncertainty)』以来、意思決定理論をはじめとした領域横断的な視点でもって各制度のキャパシティに着目する議論を展開している。そして本書では、リスクとキャパシティの制度的組み合わせに失敗するリスクのことを一階のリスクと区別して「二階のリスク(second-order risk)」または「政治的リスク」と呼ぶ。憲法がなすべき仕事は、各制度部門のキャパシティに応じた権限配分によって、そうした二階のリスクが実現する可能性を減らすことなのである。
本書の議論は一見したところ、執行権・行政権への予防的制約を取り払うことに重点が置かれすぎているようにも見えるかもしれない。それには従来の司法中心主義的な法理論から脱却し、また立法府の民主的正統性を強調する近時の議論からも距離を取り、執行権・行政権のパフォーマンスにとっての制度に関心をシフトさせているという理論的背景がある。もっとも、少なくとも本書でのヴァーミュールの関心はあくまで制度設計における権限配分の最適化であり、それは取り組むべきリスクの種類に応じて微調整されるべきものである。結論での印象的な表現に見られるように、本書の議論は権限配分にあたって一定の「スタイル」を持つことを戒めているのであり、執行権・行政権への権限集中を原理的に主張するものでないことには注意が必要である。
二、予防的立憲主義から最適化立憲主義へ
とはいっても、何を指針としてそうした権限配分を行えばよいのだろうか。その点についての本書でのヴァーミュールの議論は、もっぱら消極的である。
一階のリスクの実現を防ぐために何重もの予防策を憲法ルールによって構築しようとする種類のアプローチを彼は「予防的立憲主義(precautionary constitutionalism)」と呼ぶ。不確実なリスクに対処するために系統的な「安全寄り」の措置を取るように要求するのが予防原則(precautionary principle)であり、たとえばフランス環境憲章を典型として現代の各国の憲法にはそれを明記するものもいくつかある。むろん、それは現代に限ったことではなく、本書での憲法史的記述が印象的に示しているように、そうした予防的アプローチはアメリカ合衆国憲法制定時からずっと有力なものであり続けた。そして、本書でのヴァーミュールの議論は一貫して、そうした憲法上の予防策がいかにして失敗してきたかを描き出している。予防すべきものとして特定された対象リスク(target risk)の実現を避けるために設定された憲法上の予防策が過剰になるとき、それ自体がまた別の競合リスク(countervailing risk)を生み出しかねない。
リスクの予防策そのものがまた別のリスクを高めてしまう。ヴァーミュールはこうした事態を、アルバート・ハーシュマン『反動のレトリック』での三分類を用いて分析している。それは「無益(futility)」「危険性(jeopardy)」「逆転(perverse)」の各論法である。「無益」はある予防策がその目的に失敗する場合であり、「危険性」は対象リスクとはまた別の競合リスクを高めてしまう場合である。そして「逆転」は、ある予防策が予防しようとしたリスクそのものを逆に悪化させる場合である(本書七二頁)。
そうした失敗がなぜ起こるかについて、ヴァーミュールは各部門や各機関に特有の制度的キャパシティだけでなく、実際にそこで働く個々のアクターのインセンティヴ構造にも着目している。現実の個々人は自己利益の最大化といったことともに、あるいはそれ以上に、リスク回避的なインセンティヴを持っている。予期される予防策が厳重であればあるほど、現時点でリスクのある判断を行うインセンティヴは減ってしまいかねない。言い換えれば、予防策は先延ばしへのインセンティヴを生じさせることもある。このように、各機関や各アクターのリスク対応を一定の時間的幅でもって眺めてみるとき、過度の予防策は現在のインセンティヴと整合的でない場合がありうる。
こうした分析はハーバート・サイモン以降の意思決定理論や組織管理論を踏まえたものであり、ヴァーミュールの議論の分野横断的な特徴があるといえる。とはいっても議論自体はさほど複雑なものではないのだが、本書にはそれぞれの興味深い具体例がアメリカ憲法史に即して、抽象的なものから具体的なものまで大量に示されている――分野横断的性格とともに、こうした歴史的関心が強いのも近時のアメリカ憲法学に特徴的なことといえそうである。もっとも、そのあてはめの中には正直なところやや強引ではないかと思えるものもあるのだが、そこでのヴァーミュールのリスク計算が果たして妥当なものであるかどうか、また別の関連リスクが見過ごされてはいないか、といった批判的な検討に開かれた議論になっている。
ヴァーミュールの積極的な立場は、彼が「最適化立憲主義(optimizing constitutionalism)」と呼ぶものである。それによれば、ある一階のリスクに対処するための制度枠組みは、その対象リスクの予防のみに焦点を合わせるのではなく、関連するすべてのリスクを考慮に入れて計算し、その最適な実現水準を目指すようにデザインされなければならない。このように関連するすべてのリスクを「最適化」しようとするアプローチを、ヴァーミュールはふたたびハーシュマンにならって「成熟した立場」と呼ぶ。ヴァーミュールの議論の特徴として制度的キャパシティへの着目があることは既に述べたが、ここで第二の特徴として、そうしたキャパシティ(およびインセンティヴ)を、つねに法システム全体との関係で相互作用的に捉えようとしていることがあげられる。そこで予防的アプローチは単に退けられるのではなく、最適化の結果として採用されることは十分にありうる。
むろん、こうした最適化立憲主義が具体的にどのような制度デザインを支持するのかは明らかでない。むしろ、事前にそれを原則的に述べることはできない、ということが要点といえるだろう。こうした見方は、ヴァーミュールも自覚している通り、予防的アプローチと比べて積極的な魅力に乏しいことは否めない。しかしヴァーミュールの述べるところ、最適化アプローチは消極的なチェック方針としての意義が十分にあるという。あるリスクを予防する枠組みを作るにあたって、見過ごされている別のリスクはないか。各アクターのインセンティヴ適合性は十分なものか。そうした視点から、現状の制度配置と権限配分をつねに問い直していく漸進的な姿勢が示されている。我々はまったく新しい憲法ルールをゼロから作り上げる必要はない。アメリカ合衆国憲法は(そしてもちろん日本国憲法も)既に十分に長い期間、それなりにうまく機能してきた。憲法ルールの作成者にとって必要なのは、ともすれば別のリスクを生じさせかねない大きなヴィジョンではなく、憲法システムの全体を見渡しながら微調整していく「成熟した立場」である、というヴァーミュールの保守主義的な姿勢が本書にはよく現れているといえるだろう。
三、正当性と正統性
もっとも、こうしたヴァーミュールの「成熟した」見方は、特定の立憲民主主義体制において共有されている価値観の範囲内の狭いものであるという批判は可能かもしれない。特に本書の第四章~第六章の議論に顕著だが、自己裁定禁止、セカンド・オピニオン、専門家委員会といった各種の主題において、到達されるべき「正解」の存在が当然に想定されているかのような論の運びである。こうした見方は憲法上の諸制度を「正解」到達のための手段として理解することにつながる――それは近時、政治哲学者のロバート・グッディン(Robert Goodin)やデイヴィッド・エストランド(David Estlund)らを中心に精力的に展開されている「認知的デモクラシー(epistemic democracy)」論とも親和的な議論であるが、これには現代世界における根源的な価値対立を十分に扱えないのではないかという批判がありうる。法哲学者のジェレミー・ウォルドロンが言うところの「政治の状況(circumstances of politics)」では、人々は根源的な価値対立に引き裂かれながらも何らかの集合的決定を行わなければならない(Jeremy Waldron, Law and Disagreement, Clarendon Press, 1999)。そこで当該決定の正当性(justness)だけでなく、納得しない人々がなお当該決定を尊重する理由としての正統性(legitimacy)の探求が別に求められるという議論がなされる(参照、井上達夫『立憲主義という企て』東京大学出版、二〇一九年、第一章など)。
こうした見方に対し、ヴァーミュールの議論はずいぶんとあっさりしている。本書で用いられる「正統性(legitimacy)」は、「認知的な用語によって、政府の決定が正しいという公衆の確信や信頼として理解することができる」(二〇五頁)。ここで正統性は正当性と区別される独立の価値ではなく、当該決定の正当性に対する人々の確信の度合いとして捉えられている。権力の暴走に対する予防策が過度に入念になされるときには一貫した決定が難しくなり、認知的な意味での正統性は損なわれてしまう。それがあまりにも低くなるとき、人々が制度的障害を一掃するような強い権力の登場を求めるという逆転の結果が生じかねない(八六頁以下)。そうした政治的リスク(二階のリスク)を防ぐための成熟した制度設計において、正統性はリスク計算において算入されるべき諸要素の一つとして捉えられることになる。ここで正統性はよりよい政治的決定を実現する制度設計のための計算要素として認知的・手段的に理解されるが、「よりよい政治的決定」がいかなるものであるかについての根源的な不一致(disagreement)を強調する論者からすれば、ヴァーミュールのそうした理解はとても「成熟した」ものには見えないだろう。政治的決定に対する不一致が立憲民主主義体制にとって計算可能なリスクの一つにすぎないのか、それとも体制そのものを脅かす別種のリスクとして対応しなければならないのか、という理解の相違が生じることになる。いずれの立場が適切かについての私の判断は留保するが、仮に後者の立場をとったとしてもヴァーミュールの認知的・手段的な立憲主義構想が無効になるわけではまったくなく、少なくともそれが成立する範囲においては十分に強力なものであるだろう。
* * *
本書の翻訳は、吉良が単独で行った。私自身は法哲学の専攻であるが、本書はできるだけアメリカ憲法学の標準的な用語に合わせるように留意した。結果として法哲学やその他の分野の用語法とズレが生じている箇所が多少あるが(たとえばprinciple は法哲学では「原理」と訳すことが多いが、本書では「原則」にしている)、分野横断的な議論が多くなされている本書の性格に鑑み、ご理解をいただきたい。
なお、多少個人的な事情も関わってくるのだが、私が以前に翻訳を手掛けた科学技術社会論の古典、シーラ・ジャサノフ(渡辺千原・吉良貴之監訳)『法廷に立つ科学:「法と科学」入門』勁草書房、二〇一五年)と、本書は多くの点で共通している。ジャサノフ著は現代科学技術問題についてアメリカ司法がどのように関わってきたかを法社会学的な視点で考察するが、本書のヴァーミュールはそれを憲法基礎理論的・憲法思想史的な問題関心から捉え直すものといえるかもしれない。つまり、それぞれの制度機関のキャパシティを踏まえたうえで、想定されるリスクに応じた権限配分の最適化を検討しているということだ。簡単にいえば、司法にできること・できないことを問題の性質に応じて考察していこうとする――そして現代科学技術の規制は残念ながら、司法には多くを期待できない場合が多い。これはジャサノフとヴァーミュールの他の著作も合わせて読めばより鮮明になる。私としては本書の翻訳を開始した当初は両者のつながりをそれほど意識していなかったのだが、同じ人が取り組むものは自然と同じような主題に関わってくるものだと現在では感慨深く思っている。むろん、これはまったく個人的なことに過ぎない。
著者のヴァーミュール氏には、本書冒頭に訳出した「日本の読者へ」の執筆をお願いした。また翻訳にあたって、本書の中のいくつかの不明な箇所についてもお尋ねした。いずれも快くご対応くださったヴァーミュール氏に深く感謝する。氏が希望されている通り、本書の翻訳が日米両国の研究者の意見交換をさらに活発にするきっかけになることを、私も心より願っている。
訳文の最終的なチェックにあたっては、誤りを予防するため、特にアメリカ憲法学・憲法思想史に関わる箇所について清水潤氏(白鴎大学・憲法学)、川鍋健氏(一橋大学・憲法学)、経済学に関わる箇所について今喜史氏(宇都宮共和大学・経済学)、自然科学に関わる箇所について戸田聡一郎氏(東京大学・脳神経科学)のご協力を得た。また、訳文全体について服部久美恵氏(早稲田大学大学院・法哲学)、中机進也氏(会社員)から有益なコメントをいただいた。本書の訳文がより正確に、読みやすくなっているとすれば各氏のおかげである。しかし不確実性下の私の判断で各氏のコメントを反映していない点もあり、それによって無益、危険性、逆転といったリスクが実現した部分もあるかもしれない。そうした最適化の失敗はすべて私の責任である。
本書の装丁は、デザイナーの吉田憲二氏にお願いした。カバーに使われている写真は私がアメリカ・ワシントンDCに行ったときに撮ったものである。きれいに仕上げてくださった吉田氏に感謝している。なお、この写真について若干の説明をすると、場所はワシントンDC中心部の「憲法通り(Constitution Avenue)」である。この通り沿い、およびその近辺には連邦最高裁判所、連邦議会、そしてホワイトハウスなど、合衆国憲法上の重要施設が集中している。ワシントン記念塔の方角を向いている信号機は裏向きになっているが、さて、それは赤と青のどちらを示しているだろうか。それは無条件には決まらない、という本書の主張をこの写真は表している、というのもできすぎのように思えるのでこのあたりにとどめておく。
本書の企画、編集にあたっては、勁草書房編集部の山田政弘さんにお世話になった。山田さんは先端的な法政策分野から、本書のような法学・政治学の基礎理論、そして哲学・倫理学に至るまで幅広い書を手掛けていらっしゃるが、今後広がっていくべき分野を「耕す」という強い意識をお持ちである。専門的な議論に閉じこもっているだけではその分野は先細りになりかねない。特に、私が専攻する法哲学は、多様な分野に出張っていって面白い議論や人々をつなげていくフットワークの軽さこそ最大の持ち味だと思っている。だが、軽いだけであってもならない。そうした越境の基礎となるのが基本的文献の共有であり、翻訳はそこで大きな力を果たすはずだ。もっとも、私の能力的限界ゆえにご期待に沿えないことも多く申し訳なく思っているが、今後も、面白い分野をつなげ、切り開き、より多くの方々に読んでいただける仕事をご一緒できることを心より願っている。

