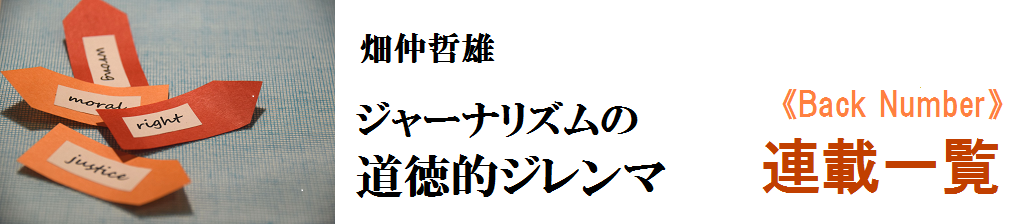3:: 実際の事例と解説
『週刊文春』2020年5月28日号のスクープは、政界だけでなく、メディア業界を大きく揺るがした。文春によれば、法務省の大臣官房長や事務次官を務めたこともある東京高検検事長の黒川弘務が、新聞記者たちと賭けマージャンをしていたというのだ。黒川は事実を認め、検事長を辞任した。
黒川は、当時のニュース番組で取りあげられない日がないというくらい注目を集めていた人物だった。なぜなら安倍内閣が2020年1月末の閣議で、2月に定年を迎える黒川の検事長としての勤務を半年間延長するという異例の決定をしたためだ。
社会を動かした文春砲とネット世論
もともと検察官の定年は検察庁法で63歳と決められていたが、安倍内閣は黒川が定年を迎える段になって不自然な閣議決定をして、国家公務員法改正案に束ねるかたちで検察庁法改正案を委員会審議にかけた。
野党は「政権べったりの黒川氏を次の検事総長にすえて、自身の疑惑追及を防ごうとしている」と安倍政権を猛烈に追及。ツイッターでは「#検察庁法改正案に抗議します」という投稿に、それまで政治的な発言をしたことがなかったタレントや芸能人も名前を連ね、「ネット世論」が高まっていた。
渦中の人物である黒川が記者たちと密室で賭けマージャンに興じていたのは、新型コロナウイルス感染拡大防止のため全国民が自粛を強いられているまっただなかだった。絶妙のタイミングで放たれた「文春砲」は、政府・与党だけでなく産経・朝日両新聞社をも撃ち抜いた。
情報源の明記は原則
黒川と一緒に「3密」状態で博打をしていたと報じられた社員がいる産経新聞社と朝日新聞社の対応は、新聞ジャーナリズムの信頼を著しく毀損した。[異論対論]で取りあげたジレンマを具体的に考える前に、この点を指摘しておこう。
産経は、井口文彦・東京本社編集局長の見解として、次のコメントを公開した[1]。
産経新聞は、報道に必要な情報を入手するにあたって、個別の記者の取材源や取材経緯などについて、記事化された内容以外のものは取材源秘匿の原則にもとづき、一切公表しておりません。
取材源の秘匿は報道機関にとって重い責務だと考えており、文春側に「取材に関することにはお答えしておりません」と回答しました。
ただし、本紙は、その取材過程で不適切な行為が伴うことは許されないと考えています。そうした行為があった場合には、取材源秘匿の原則を守りつつ、これまでも社内規定にのっとって適切に対処しており、今後もこの方針を徹底してまいります。
この短い文章で井口が3回使った「取材源の秘匿」は明らかな誤用である。なぜなら、事実報道において、取材源/情報源を秘匿しないことが大原則だからだ。事件や事故を伝えるニュースは「○○氏が語ったところによると」「○○警察の調べでは」と情報源が明記される。それはなにも報道分野に限ったルールではない。学術論文でもソースの表示は検証可能性を示すための鉄則である。
「取材源の秘匿」の法理
取材源の秘匿の論理を持ちだせるのは、そのニュースが何に/誰に基づいて書かれたのかを明らかにできない特殊な事情がある場合、限定的に主張しうるものである。典型例は、情報源が内部告発者の場合がそうだ(書籍版『ジャーナリズムの道徳的ジレンマ』196~198頁参照)。
これが日本で広く知られるようになったのは、ワシントン・ポスト紙による一連のウォーターゲート報道が大きいのではないか。記者ボブ・ウッドワードは自分の情報源を「ディープスロート」とはぐらかし、社内でも名前を明かさなかったとされる。もし情報源を秘匿しなければ、その人物に危険が及ぶことが明らかだったからだ。

“Playing mahjong” by yui-flickruser:21903607@N04 is licensed under CC BY 2.0
記者と社員の区別はどこに
もう一方の朝日は岡本順・執行役員広報担当のコメントを公表した[2]。
社員が社内でのヒアリングに対し、検事長とのマージャンで現金を賭けていたことを認めました。新型コロナ感染防止の緊急事態宣言中だったこととあわせて社員の行動として極めて不適切であり、皆さまに不快な思いをさせ、ご迷惑をおかけしたことを重ねておわびします。取材活動ではない、個人的な行動ではありますが、さらに調査を尽くし、社内規定に照らして適切に対応します。また、その結果を今後の社員教育に生かしてまいります。
ここで注目されるのは「取材活動ではない、個人的な行動」という表現だ。謝罪している点は、産経の姿勢と対照的だ。しかし、記者による取材活動ではないという説明に、問題を矮小化しようとする意図が見え隠れする。つまり、記者にはジャーナリズム上の倫理を求められるが、一般社員の不祥事は別枠で処理したいというふうに読める。
ここで、朝日が2006年1月から実施した「ジャーナリスト宣言」と題するキャンペーンを振り返っておきたい。当時の新聞社としてはかなり大規模なキャンペーンであり、連日テレビやラジオのスポットCMが流れ、津々浦々の朝日新聞販売店に「ジャーナリスト宣言」の幟が翻った。朝日新聞社は宣言を「新聞人としての決意表明」であると謳った[3]。
「新聞人」の精神はどこへ
十数年前のキャンペーンではあるが、朝日は、前線の取材記者だけでなく、ネット部門や総務、経理、営業のスタッフ、さらには新聞を配達している人たちも含めて、みなが「ジャーナリスト宣言」を体現すべき「新聞人」であると表明したといってよい。
当時、東京本社で編集局長(ゼネラルエディター)を務めていた外岡秀俊は2006年4月2日の1面の署名記事でこう書いた。
「宣言」には、自らへの戒めと読者への誓約の二面がある。私たちは、ただ読者の信頼にのみ支えられ、権力を監視し、現場で自らを鍛え直すことを確認したい。読者の皆様には、気骨ある紙面、血の通った紙面づくりをお約束したいと思う。
朝日は、当時の志をどこかに忘れてしまったのだろうか。
文春報道によれば、朝日が「社員」と呼ぶ人物は、2017年まで検察を担当する記者で、賭けマージャン当時は経営企画室で管理職をしていた。ふつうに考えれば、その人物は有能な記者として評価され経営部門に出世したエリートである。記者ではなく社員という方便は、法政大学の上西充子教授による流行語「ご飯論法」と言われるだろう。
事実報道に意見を追記
問題の矮小化は、記事のなかにもみられた。朝日は2020年5月23日朝刊社会面で、賭けマージャン事件をめぐる法務省の調査結果を詳しく報じた。その事実報道の末尾に奇妙なパラグラフが追記されていた。
◇
法務省の調査結果は賭けマージャンを行っていた朝日新聞の社員を「記者C」としていますが、この社員は、2017年に編集部門を離れており、以降は記者ではありません。この点について朝日新聞社広報部から法務省に伝えました。
事実の報道の末尾に、自社の見解を加えることは、新聞ジャーナリズムが掲げてきた「事実と意見」の区別を破ることになりかねない。もし法務省の見解に異議があり、自社の考えを示したいのならば、別の記事で独立した見出しを立て、それが朝日の意見であることを読者に伝えるのが誠実な対応であったはずだ。
多様な権力監視の方法
事件から一歩離れて、一般論として、記者は公権力を持つ取材対象とどのように向き合えばよいのかという問題を考えてみたい。今回は[思考実験]で県警本部の捜査二課長をモデルにしたストーリーを示し、その後[異論対論]で論点を検討した。
記者たちが監視の対象としている権力の側にはさまざまな情報がある。とりわけ公務員の場合は不用意に情報を漏洩させると罪に問われることもある。うまく情報を引き出してニュースとして報道できるかどうか。そこが記者たちの腕の見せどころとなる。
権力監視がジャーナリズムに期待される任務だということは、多くの記者に共有されている。しかし「監視」とは何なのだろう。以下、3種類の監視手法を検討してみよう。
《現場に行く》
わかりやすい監視は、記者自身が現場を訪れて権力被害などの目撃者になることだ。直接目撃できなくても、権力が悪用されて傷つけられた当事者の証言を集めたり、証拠資料を収集したりする。公権力が正しく使われず被害が広がっている現場や、放置され見捨てられた現場についても同様である。
戦場にジャーナリストがいるだけで、虐殺や非道な暴力を抑制すると言われる。すくなくとも記録に残し伝える行為は、反戦平和や非暴力の思想に寄与するだろう。ただし、取材者自身が落命することもある。殉職した日本のジャーナリストとしては、沢田教一、一ノ瀬泰造、橋田信介、長井健司、山本美香、後藤健二らの名前が挙げられる(書籍版『ジャーナリズムの道徳的ジレンマ』34~44頁参照)。
軍事基地や原発などに由来する被害を現地から発信し続けることも権力監視となる。沖縄から本土に向けた情報発信といえば、森口豁による映像作品や著作が挙げられる。近年は三上智恵、阿部岳、大矢英代たちの作品が目立つ。
原発事故では、報道各社は現場から記者を退避させた(書籍版『ジャーナリズムの道徳的ジレンマ』22~33頁)。その反省から、多くの社は事故に由来する問題を継続して取材するようになっているようだ。
ちょっと変化球かも知れないが、内閣総理大臣を1日中追いかけ、その行動を詳細に記録する「総理番」「首相番」の記者たちの存在も、権力監視に貢献している。彼ら彼女らが書くのはデータだけの記事だ。何時何分に、どこで誰と会った。昼食は誰と何を食べた。休日は朝からゴルフ場でゲームした。夜はどこで誰とお酒を飲んだ……。
政官界の関係者を除けば、熱心に目を通す人がそれほどいない記録だが、ある時期からソーシャルメディアで注目を集め始めた。大手メディアの経営者や編集幹部が首相と会食していることが記されていたからだ。ネットでは、マスメディアが権力に取り込まれたり、癒着したりすることを危惧する声が圧倒的だったことは言うまでもない。
《文献を調べる》
情報公開制度などを用いて調査をするのも有力な手法だ。公開請求した情報が届くまでには時間がかかるし、黒塗りされることもある。意図的に公文書として保存されないものもある。さまざまな文献を総動員して分析するには、技術と知識が必要となる。それでも、官僚制の特徴の一つは文書主義なので、文献調査は説得力のある監視となる。「森友・加計学園」や「桜を見る会」の問題をめぐる、毎日新聞の大場弘行記者らのキャンペーン「公文書クライシス」はその好例といえる。
上記二つの手法は、大学の研究者や社会活動家、NGO/NPOとの協働が可能である。むしろ、市民社会からの協力を得ることで精度の高い仕事ができることもある。
続いては、組織内部の人から直接情報を得る手法を考察しよう。組織内部の人から直接的に話を聞くのはいろいろなケースが考えられるが、ここでは典型的な二つを考えてみる。
当事者から直接聞く
《中の人から聞く――内部告発者を探す》
政府機関や捜査機関のような組織はリアルタイムで公表できない情報を扱うことも多く、完全ガラス張りにはできない。このため、内部で何がおこなわれているのか、外から見えづらい。密室性の高いところで権力が行使されるため、かのジョン・アクトンが残した至言「権力は腐敗する」という事態を招く危険性が常にある。
どのような組織にも腐敗や不祥事を見過ごせない倫理的な人がいて、情報提供者になるケースがある。義憤に駆られてマスメディアに駆け込む人もいるし、罪悪感にさいなまれて苦しむ人もいる。
元CIA職員エドワード・スノーデンは義憤に駆られたケースだ。彼は香港のホテルで英ガーディアン紙などの記者に情報提供し、取材源である自分の名前を出すことを認めた。その結果、スノーデンは指名手配され故郷に戻ることができなくなった。
罪悪感にさいなまれたケースとしては、森友問題で文書改竄に関わり命を絶った財務省近畿財務局職員の存在は無視できない。命を絶つまえにジャーナリストがアクセスできていなっかたことが悔やまれる。
内部の情報を外に持ち出すことは恐ろしく危険なことなので、取材者はいやが上にも慎重を期して接触しなければならない。
むろん、もたらされる情報が錯誤や虚偽、あるいは私怨や個人攻撃を企図したものであれば報道に値しない。だが、納税者や有権者の信頼を裏切る権力の不正や欺瞞を証明するものであれば、民主主義の促進や社会正義の実現のため取材源を例外的に秘匿して報道しなければならない。
《中の人から聞く――取材先に食い込む》
公権力をもつ組織の幹部たちは、記者から注目されさまざまなアプローチを受ける。彼ら彼女らがたくさんの情報を握っているからだ。記者の側は情報を聞き出すため、あの手この手で接触をはかる。両者の間に駆け引きが生じる。
記者の側は単独で接触したい。できればオフィシャルではない場で、可能ならライバル会社のいないところで会いたい。会って話を聞きたい。でも、たんに「教えてほしい」だけでは話が通らない。まずは人間関係を作る必要がある。礼儀正しい態度、相手の立場への気遣い、問題意識や正義感の共有、腹を割った本音の語らい……。
互酬的な関係ができたとしても情報を得られるとは限らない。なぜなら、記者のほしい情報は取材先にとって守秘義務となっていることが多い。それでも人間的に親しくなれば「書いてもらっては困るが」という条件で教えてもらえることもある。ただし、せっかく重要な情報が得られたとしても、書けなければ意味がなくなる。そこに取材者のジレンマが生まれる。
取材者と被取材者という関係を超えて強固な信頼で結ばれることもありうる。ふるさとが同じだとか、同じ高校や大学の出身であるとか、共通の友達がいるとか、配偶者どうしにつながりがあるとか。記者が取材先の相手を尊敬しているケースも考えられるだろう。
社会学者のニクラス・ルーマンは信頼を「リスクを賭した前払い」と論じている[4]。仮に、取材先が記者を信頼し、危険を承知で情報提供してくれたとしよう。そのとき記者は、相手にリスクを負わせて自分だけ手柄を立てようとするだろうか。そこにもジレンマが生じる。
清濁併せ呑む付き合い
上記4種類の権力監視のうち、《現場に行く》《文献を調べる》《内部告発者を探す》は動かぬ証拠を提示できるため、とても強力な手法といえる。それに比べれば、《取材先に食い込む》は、上述したようなジレンマと直面しやすい。もっといえば、公的な場での取材ではないので、検証可能性に乏しいという弱さもある。
しかし日本の報道関係者は《取材先に食い込む》ことができる記者を、あきらかに高く評価する傾向が強い。たとえば元NHK記者の池上彰は、朝日新聞に連載しているコラムで同社の元記者の能力を絶賛した。
黒川検事長という時の人に、ここまで食い込んでいる記者がいることには感服してしまう。自分が現役の記者時代、とてもこんな取材はできなかったなあ。/朝日の社員は、検察庁の担当を外れても、当時の取材相手と友人関係を保てているということだろう。記者はこうありたいものだ。(/は改行)[5]
池上も、賭けマージャンをしたことを厳しく批判しているが、黒川と賭けマージャンできるくらい「食い込んでいる記者」に対する評価は極めて高い。
元読売新聞記者の大谷昭宏も結論としては、賭けマージャンに加わったことを厳しく批判しているものの、こうも述べている。
記者は取材相手に食い込むために、お酒を飲んだり、マージャンやゴルフをしたりすることもある。まして黒川氏は検察でいえばナンバー2だ。同業者としては複雑な思いもあり、建前で語りたくはない。[6]
長らく事件記者をしていた大谷の口調からは、記者の仕事は、素人がいうような「きれいごと」で達成できないこともあるというニュアンスがにじみ出る。そうした大谷の取材観は、新聞労連が2020年5月26日に発表した声明の一節で書かれた内容と符合する。声明の第3段落に以下の記述がある。
公権力の取材においては、圧倒的な情報量を持つ取材先から情報を引き出すために、新聞記者は清濁合わせ呑む取材を重ねてきました。特に、捜査当局を担当する記者は、ごく少数の関係者が握る情報を引き出すために、「取材先に食い込む」努力を続けています。公式な説明責任に消極的な日本の公権力の動きを探り、当局が把握している事実を社会に明らかにしていく上で有用とされ、そうしたことをできる記者が報道機関内で評価されてきました。[7]
新聞労連の結論としては「食い込む」タイプの取材手法が時代にそぐわなくなっていると断じ、、経営幹部に体質転換を迫っている。だが、「取材先に食い込む」ことが記者の力量を測る重要な指標であったことを、業界内側からあきらかにした点に注意したい。
エスタブリッシュメント化
取材先に「食い込む」記者が、かくも高く評価されるのはなぜか。それは「食い込む」ことが難易度の高い仕事だからだろうか。高度なスキルが求められるのは、他の取材方法も同じはずだ。この謎を解く鍵の一つに、記者クラブ制度を前提とした取材体制という主要メディアの構造的な問題がある。賭けマージャン問題に関してライバル新聞社は朝日と産経の問題を厳しく非難する記事を載せていないのは、パンドラの箱を開けることになりかねないからだろうか。
記者クラブ制度は、組織の閉鎖性や報道内容の画一性をもたらすとして批判されてきた。だが、報道各社にとって、記者会見に参加し、発表資料を受けとれる利点がある。そうしたルーティンの取材を効率化できるのは記者クラブのおかげである。
加えて、記者クラブは記者の力量を測る場としても機能している。取材先に食い込んでいる記者は、権力と「太いパイプ」をもつがゆえに、権力が何を考え何しようとしているのかが見通せる。そんな記者を何人も抱えていることが報道機関としての強みとなることは間違いない。
「ブンヤ」と蔑まれていた新聞記者という職業は、かならずしも品行方正とはいえない若者にも門戸を開いていたことはよく知られている。学生運動に入れ込みすぎて一般企業に就職できなかった学生たちに、報道各社は比較的寛容であった。
とはいえ、大手新聞社や巨大放送局の採用試験の倍率は極めて高く、実態としては受験戦争を勝ち抜いた高学歴エリートたちが採用される傾向が強く、記者たちは何十年も前からエスタブリッシュメント化していた。先述の池上も大谷も、日本を代表する有名大学の出身者である。
市民社会との再接続
格差が拡がり女性や子供の貧困が深刻化するなか、ソーシャルメディアでは大手メディアの記者たちが、既得権益に守られた特権階級であるかのように批判されることは珍しくない。総理大臣と会食するメディア幹部も、検察幹部と賭けマージャンをする記者も、一部のネット民に言わせれば十把一絡げに「癒着するマスゴミ」である。
「権力監視」を掲げる大手報道機関自身が社会の分断を促し、自身が市民社会から「監視」される対象とみなされないようにするためには、《現場に行く》《文献を調べる》《内部告発者を探す》に力を入れ、市民社会との信頼関係を回復させることだろう。
少なくとも、文春砲に代表される週刊誌のスクープは、記者クラブ制度とも「食い込む」取材とも異なる手法で権力監視を実現している。
公権力の《取材先に食い込む》ことが全面的に悪いというわけではない。ギブ・アンド・テイクの深みに陥って権力に取り込まれたり、市民社会から攻撃の対象となったり、危険がつきまとう仕事である。どこまでなら許され、どこからが許されないのか。社会の倫理観は時代に応じて変化するため、単純な線引きは不可能だ。安易なガイドラインを作ることで、思考停止が始まりかねない。倫理問題は繰り返し問い続け考え続けることに意味がある。
[注]
[1]産経ニュース「黒川検事⻑ 「賭けマージャン」文春報道」2020.5.20 21:46
[2]朝日新聞デジタル「朝日新聞社員、賭けマージャン認める」2020年5月22日 5時00分
[3]「ジャーナリスト宣言。」の広告キャンペーンは、朝日新聞記者が読売新聞の記事を盗用していたことが発覚したため2007年2月に打ち切られた(読売新聞2007年2月9日)。
[4]ニクラス・ルーマン『信頼:社会的な複雑性の縮減メカニズム』(大庭健・正村俊之訳, 勁草書房, 1990)39頁に「信頼の問題をいっそう明確に規定して、リスクを賭した前払いの問題として捉えることができる」とある。
[5]池上彰「黒川氏との賭けマージャン 密着と癒着の線引きは(池上彰の新聞ななめ読み)」朝日新聞デジタル2020年5月29日
[6]竹内麻子「律しながら取材を 大谷昭宏氏」毎日新聞デジタル2020年5月22日
[7]新聞労連「『賭け麻雀』を繰り返さないために」(2020年6月5日取得、http://shimbunroren.or.jp/200526statement/)
[担当者の線引き] 引けない線を、毎回毎回、引きつづける、引き直しつづける。そうしなければ自分たちの仕事に正統性をもたせられないしんどさを引き受けるしかない……。
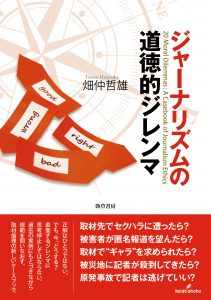 取材先でセクハラに遭ったら?
取材先でセクハラに遭ったら?
被害者が匿名報道を望んだら?
取材で“ギャラ”を求められたら?
被災地に記者が殺到してきたら?
原発事故で記者は逃げていい? etc.
現場経験も豊富な著者が20のケースを取り上げ、報道倫理を実例にもとづいて具体的に考える、新しいケースブック! 避難訓練していなければ緊急時に避難できない。思考訓練していなければ、一瞬の判断を求められる取材現場で向きあうジレンマで思考停止してしまう。連載未収録のケースも追加し、2018年8月末刊行。
〈たちよみ〉はこちらから→〈「ねらいと使い方」「目次」「CASE:001」「あとがき」(pdfファイルへのリンク)〉
【ネット書店で見る】
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
畑仲哲雄 著 『ジャーナリズムの道徳的ジレンマ』
A5判並製・256頁 本体価格2300円(税込2484円)
ISBN:978-4-326-60307-7 →[書誌情報]
【内容紹介】 ニュース報道やメディアに対する批判や不満は高まる一方。だが、議論の交通整理は十分ではない。「同僚が取材先でセクハラ被害に遭ったら」「被災地に殺到する取材陣を追い返すべきか」「被害者が匿名報道を望むとき」「取材謝礼を要求されたら」など、現実の取材現場で関係者を悩ませた難問を具体的なケースに沿って丁寧に検討する。
これまでの連載一覧》》》