あとがき、はしがき、はじめに、おわりに、解説などのページをご紹介します。気軽にページをめくる感覚で、ぜひ本の雰囲気を感じてください。目次などの概要は「書誌情報」からもご覧いただけます。
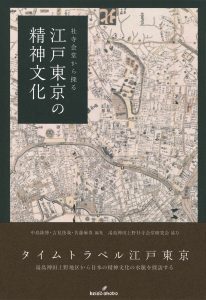 中島隆博・吉見俊哉・佐藤麻貴 編
中島隆博・吉見俊哉・佐藤麻貴 編
湯島神田上野社寺会堂研究会 協力
『社寺会堂から探る 江戸東京の精神文化』
→〈「はしがき」「序論 精神文化の水脈」「Ⅲ 鼎談 新しい精神文化を求めて(抜粋)」(pdfファイルへのリンク)〉
→〈目次・書誌情報・オンライン書店へのリンクはこちら〉
はしがき
吉見俊哉
本書の成り立ちをご理解いただくには、まず東京文化資源会議がどんな団体なのか、簡単に説明しておかなければなりません。この会議は、都心北部の大学、研究機関、文化・宗教施設、企業、NPO、国の省庁などの有志からアーティストや地域活動家までが半脱藩志士的に集まって、二〇一四年に結成されました。「半脱藩志士的」と形容したのは、それぞれのメンバーが、自分の組織に所属し続けながら、日本型のタテ割り組織とは異なる横断性に社会を変える契機を見出しているからです。出身も立場も考え方も様々ですが、唯一、東京文化資源区を実現していこうとする意志において一致しています。
それでは、その東京文化資源区とは何でしょうか。地域的には、この文化地区は、秋葉原、神保町、湯島、本郷、上野、谷中、根津、千駄木、根岸など、東京都心北部の旧神田区、旧下谷区、旧本郷区にまたがる一帯です。この一帯は、まさしく江戸・東京の宗教や知、広義の精神文化の中心でした。明治になると、ここには多数の大学や専門学校が林立し、日本最大の学生街の様相を呈します。また上野は、寛永寺の壮麗な仏教伽藍から博覧会や博物館、動物園が並ぶミュージアムシティに転換しました。
この地域の文化は、もともと一方では湯島聖堂、神田明神、湯島天神、寛永寺などが連なる本郷台地や上野台地の東端の社寺によって、他方では台地東端の崖下に広がる下谷や不忍池、湯島などの茶店や職人町によって担われていました。これが明治以降、近代国家の学芸や観覧の文化に取って代わられ、やがては書店からラジオ、アニメやゲームなどのメディア文化とも結びついていきます。近世・近代を通じ、これほど多様な文化的凝集性を蓄積してきた地域は、世界の大都市を見渡してもありません。
東京文化資源会議では、これまでこの地区の文化的一体性を再生するために、浅草から上野、御徒町、秋葉原、神保町、水道橋というように地域を貫いてスローモビリティの路面電車を復活させていくトーキョー・トラムタウン構想や、上野公園の夜をアーティストや文化活動、露店に開放し、良質の夜の賑わいを公園に創出する上野ナイトパーク構想、上野不忍池畔から湯島・御徒町にかけての一帯の街づくりを進める上野スクエア構想、ラジオの街から始まった秋葉原一帯の街づくりを地域の人々と考える広域秋葉原作戦会議などの草の根的な街づくり、文化運動を同時多発的に展開させてきました。
そうしたなかで、この地域の文化・宗教施設を横断的につないでいこうという湯島神田上野社寺会堂研究会は主要な、そしてとても挑戦的な試みです。というのも、この文化資源区の多様なものの結びつきを象徴するのが、この地域に集中する異なる社寺会堂群なのです。この地域には、神道、仏教、儒教、カトリック、正教会、プロテスタント、イスラームなど、実に多くの文化・宗教施設が集中しています。わずか半径二キロほどの広がりのなかに、これほど多様な歴史ある施設が集中している地域は、他の世界の都市にはありません。エルサレムには、ユダヤ教とキリスト教とイスラームの施設がありますが、おそらく仏教や儒教、神道、正教会のものはなく、しかも三つの一神教は厳しく対立しています。そのような対立は、東京都心北部に集中する文化・宗教施設にはありません。
私たち東京文化資源会議では、この地域の異なる精神文化を横断的に結ぶために、過去約五年にわたって六つの文化・宗教施設、すなわち神田神社(神田明神)、湯島聖堂、東京復活大聖堂教会(ニコライ堂)、湯島天満宮(湯島天神)、アッサラーム・ファンデーション、寛永寺を運営する方々に数カ月ごとに集まっていただき、地域の未来をデザインするコンソーシアム的会議を運営してきました。この会議のなかで主に精神文化、思想面について議論する場として展開されてきたのが、中島隆博先生を塾長とする社寺会堂塾です。「塾」という命名が卓抜で、冒頭にも触れた幕末の草莽の脱藩志士たちが、藩などのタテ割り組織の壁を越えて横断的に交流していた時代を想起させます。本書はこの「塾」活動の主要な成果です。
東京は世界都市ですが、ニューヨークやロンドン、シンガポールのような都市とは異なります。そのネガティブな面は、文化的、民族的多様性に劣り、これらの都市ほどにはグローバルにオープンでない点ですが、ポジティブな面は、丘や谷や坂、川などの微地形に富み、時代を超えて比較的小規模な施設が多様に息づいている点です。東京にニューヨークのメトロポリタン美術館やロンドンの大英博物館はありませんが、細かく魅力的な施設をつないでいくと、人類の文化的営みの多様さ、豊饒さを集約するような都市風景が浮かび上がってきます。本書のタイトルにある「社寺会堂」は、その典型です。
序論 精神文化の水脈
中島隆博
東京の中心部は水に恵まれている。三四郎池や不忍池さらには江戸時代から続く大名庭園にこしらえられた池などを見ると、豊かな水脈がその地下を走っていることがわかる。それは、関東ローム層が削られてできた台地を廻るような水脈である。それらと重なるように、数多くの宗教施設や精神文化施設が存在している。それらもまた、俯瞰的に見れば、江戸東京の精神文化の豊かな水脈を形成しているのである。
そうした施設を繋ぐことで、江戸から東京にかけての精神文化の水脈を明らかにすることができないものか。こうした問いを抱えて、東京文化資源会議のなかに、湯島神田上野社寺会堂研究会が発足した。
吉見俊哉先生(東京大学)、宇野求先生(東京理科大学)、柳与志夫先生(東京大学)の見事なイニシアティブのもと、議論を深めていったのである。その後、精神文化に特化した議論を行うために、中島を塾長とする社寺会堂塾というプロジェクトを立ちあげた。そして、湯島、神田から上野へと、徐々にその範囲を拡大しながら、六つの施設にご協力をいただいたのである。すなわち、神田明神(神田神社)、湯島聖堂、東京復活大聖堂教会(ニコライ堂)、湯島天満宮(湯島天神)、アッサラーム・ファンデーション、寛永寺である。それぞれ由来や来歴が異なる多様な施設であるが、いずれも東京の中心部で、生き生きと活動している。それらを繋ぐことで、この地域での精神文化の未来を展望しようというのである。
本書の第Ⅰ部では、これら六つの社寺会堂の来歴と現在そして未来を、インタビューを通じて明らかにしていった。吉見俊哉先生と中島がそれぞれインタビューアーを務めて、各施設の精神文化の形を対話から探ってみたのである。公式の案内文からだけでは見えてこない歴史の襞や思いに触れていただければ幸いである。浮かび上がってきた興味深いポイントを少し紹介しておこう。
江戸の都市計画では、江戸城を中心として、北東の鬼門の方向に神田明神と寛永寺を配し、南西の裏鬼門の方向に日枝神社と増上寺を配していた。ところが、明治になると、江戸を精神的に支えていたこの配置が崩れ、神田明神は平将門を祭神から外され、社格を下げられる一方、寛永寺は上野戦争で焼かれるだけでなく、明治政府に寺領の相当部分を没収された。その暗い時代を支えたのが、神田明神の場合は庶民であり、寛永寺は渋沢家と大倉家そして檀家であった。こうした記憶を辿り直すことによって、サブカルチャーに積極的に関与している現在の神田明神の背後にある歴史に触れることができるし、かつての寺領であった上野公園とそこにある博物館などの近代的な諸施設と寛永寺の複雑な関係に思いを馳せることもできる。
神田明神のすぐ南には湯島聖堂があり、そこから聖橋を渡ったさらに南に東京復活大聖堂教会(ニコライ堂)がある。「聖橋」とは、二つの聖堂を結ぶという意味である。湯島聖堂は江戸から東京にかけて、一貫して儒教の中心であった。毎年四月の第四日曜日に孔子祭を行っていて、神田明神の方々が儀礼を担当されている。かつては湯島聖堂と神田明神は繋がっていて、今のように道路で寸断されてはいなかった。この湯島聖堂にも、昌平坂学問所という江戸の記憶とともに近代の記憶が刻まれている。つまり、その敷地には、近代的な大学である東京師範学校(現在の筑波大学)や東京女子師範学校(現在のお茶の水女子大学)そして博物館(現在の東京国立博物館)がまず置かれたのである。
東京復活大聖堂教会は、一九世紀末に建てられた時は、東京のあちこちから見える壮麗な建物で、多くの絵画に描かれている。しかし、この壮麗な建物も、その後は歴史と政治に翻弄されていく。二〇世紀の前半は日露戦争やロシア革命を経て、ロシアとの関係が細くなったし、後半はアメリカの政策でロシアから主教を迎えることが禁じられるまでになった。それでも、ソ連崩壊の後は、ロシア正教会との関係が再び深まりつつある。そのような中で、外交官としてリトアニアでユダヤ系を含む難民にビザを発行した杉原千畝のような信徒がいたことは特筆されることだ。
神田明神から北に進むと、湯島天満宮がある。こちらは歴史の古い神社で、ある時期から菅原道真を祀っている。江戸時代には寛永寺の別当が入っていたようだが、両者の関係を示す資料がないために、実際のところはわからない。興味深いのは、日光東照宮の本殿の造りが京都の北野天満宮の権現造をモデルにしているということだ。徳川家光が、庶民に親しまれた菅原道真を家康に重ね合わせたのではないかと推測されている。
アッサラーム・ファンデーションが位置するのは上野の南、御徒町である。宝石商を中心としたビジネス・コミュニティーが支えていて、グローバル化した東京のひとつの突端である。クルアーンを読むことは、それ自体が信仰の実践であり、そのためには英語への翻訳だけでなく、ローカルな言語への翻訳、とりわけ東京では日本語への翻訳が重要になってくる。その翻訳を通じて、あらためて日本文化もまた問い直されているのである。
第Ⅱ部では、精神文化の専門家に寄稿いただいた四本の原稿と、それをもとに行った座談会の記録を掲載している。現在の学問の到達地点から、仏教、神道、キリスト教、イスラーム、儒教をどう考えることができるのか、またこれらの多様な精神文化を重ね合わせて論じることで、普遍的なものに向かっていかなる寄与ができるのかを示したものである。
学問的な関心から見れば、近年注目されているのは、「脱世俗化」や「宗教復興」と呼ばれる世界的なうねりである。近代において、キリスト教とりわけプロテスタンティズムをモデルにした宗教概念が世界を覆った。それと同時に、そうした宗教を個人の内面的な信仰に位置づけて、公共空間から宗教を押しやり、公共空間を世俗的なものにすることが推進された。ところが、二〇世紀の終わり頃から、世界的な規模で「脱世俗化」や「宗教復興」が生じ、近代的な宗教と世俗という枠組みが大きく問い直されるようになったのである。
これはひとつのチャンスでもある。というのも、近代的な宗教概念にわたしたちはずいぶんと翻弄されてきたからである。たとえば「儒教は宗教なのか」という問いがしばしば問われてきた。しかし、それは宗教の定義によって異なる答えが出てくるものであり、近代的な宗教概念(聖職者集団、教会のような制度、聖典、内面的な信仰等にもとづく)を範例にすれば、「儒教は宗教ではない」ということになる。また、神道であっても、戦前であれば「神道は宗教ではない」という公式見解が出されていたのである。仏教を考えてみても、近代の仏教がキリスト教的な意味で宗教化していったこともあったが、すべてが宗教化に還元できるものではなく、その世俗との繋がりは決して無視できない。さらに、一神教という概念でキリスト教と同じように括られるイスラームにしても、キリスト教との違いは無視できないものがある。何よりも、「一神教」という概念それ自体は決して古いものではなく、一七世紀のイギリスのプラトン主義という特殊な背景で成立したものであることを考えると、必ずしも適切なものではない。
そうであれば、狭い意味での宗教概念から解き放たれて、東京の中心で水脈を形成している精神文化を読み直すチャンスが到来していると考えることができるだろう。それは、日本にあった、これまた近代的な「世俗」とは異なる世俗の意義をも見直すことにも繋がっていく。
ただし、注意しなければならないのは、このことが近代的な「宗教」や「世俗」概念の果たした意義をすべて否定しようというわけではないということだ。それらが因習化された従来の精神文化に風穴を開けて、自由に物事を考えることを可能にしたことには、重要な意義があったからである。そうではなく、結果としてある桎梏となってしまった近代的な諸概念を再考することで、そのあらたな可能性をもう一度見出そうというのである。
その際に、近代の荒波に揉まれ、多くの変容を遂げながらも、今に至るまで生き生きと活動し続けてきた諸々の精神文化のあり方は、大いに示唆的である。そこにある多様性と複雑性を損なうことなく、お互いがその変容してきたプロセスを確認することで、あらたな対話が可能になる。そして、そうした対話から、この困難な時代において、わたしたちが単に「生きる」のではなく「よく生きる」ためのヒントが浮かび上がってくるのだ。
第Ⅲ部は、湯島天満宮の押見権宮司と吉見先生そして中島による鼎談で、現場における実践と学問が連携することによって、いかなる新しい精神文化が開かれうるかを考えたものである。
その未来のとなるのは「寛容」ではないだろうか。異なる宗教や精神文化が、東京の中心において、平和的に共存していることは、それ自体が実に貴重なことである。かつてイスラエルを巡った際に、「空気までもが緊張している」と感じざるをえなかったのだが、東京の中心で感じる空気感はそれとはまったく異なっている。「よく生きる」ために、「寛容」が二一世紀の宗教や精神文化の概念のひとつになるとすれば、その具体的な姿を、わたしたちは東京の中心において感じることができる。
もはや近代的な諸概念がそのまま普遍的であるわけではない。しかし、普遍的であろうとすることを諦めて、特殊なものに閉じこもるばかりでは、分断や孤立は深まるばかりである。根底的な多様性や複雑性を尊重することが、同時に、それを貫いて、普遍的なものに関与するような道をどう見つけることに繋がるのか。「寛容」はそのひとつの答えではあるだろう。
この本を通じて、こうした精神文化の未来について読者の皆さんと一緒に考えてみたい。
なお、この本には、六施設を一望できる地図を入れている。これは真鍋陸太郎先生のプロジェクトである「地図ファブ」と連携したもので、「地図ファブ」が作成したオンライン上の「精神文化ぶらり」というサイトでは本書の記述の一部が地図上の該当箇所で読めるようになっている。是非、この地図とともに、この地域を歩いていただいて、一種の「巡礼」のように、多様な精神文化を繋ぐ旅をしていただければと思う。それが二一世紀的な新しい精神文化を開く、具体的な一歩になるはずである。
Ⅲ 鼎談 新しい精神文化を求めて
中島隆博×押見匡純×吉見俊哉
中島隆博 この鼎談では、二一世紀にお いて新しい精神文化をどう考えればよいのかを主題にしていきたいと思います。その時に、東京という地域性の問題をどのように評価するのか、また、世界的な文脈で宗教や宗教性が問い直されているなかで、新しい精神文化とりわけ宗教文化をどのようにして位置づけたらよいか、この二つを柱にして、未来を展望していきたいと思います。
宗教と近代│世俗化と宗教復興
中島 まず、わたしから最初に少しお話をさせていただいて、その後お二人にうかがっていければと思います。
二一世紀における精神文化や宗教文化の使命について考える際に、近代のなかでの宗教の意味や位置づけが、現在大きく変わってきていることを確認することが重要だと思います。近代において中心になっていたのは、世俗主義です。そこでは宗教を個人のプライベートな問題であると捉え、公共的な空間から切り離しました。公共的な空間は世俗的であるべきだ。これが近代の大原則です。
ところが、二〇世紀の末あたりから、そうした近代的な分割に収まらないような動きが出てきます。それが、世界各地に見られる様々な宗教復興という現象です。極端な場合には、原理主義の運動になってはいきますが、近代の大原則である世俗主義だけではうまく生きていけないのではないかという、人々の不安を汲み取った面もあったかと思います。
これをユルゲン・ハーバーマスは「ポスト世俗化社会」と呼びました。とはいえ、それは世俗主義を見直すだけではありません。宗教自体がもう一度問い直されようとしています。プロテスタンティズムをモデルにした近代的な宗教だけが唯一のモデルではないのではないか。宗教ならぬ宗教性あるいは精神性に注目しなければならないのではないか。それによってはじめて、ある宗教を信仰している人と世俗的な人の間の対話や翻訳ができるのではないのか。このような見直しが出されているのです。
断ち切り、再び繋ぐという宗教の役割
中島 宗教と訳されている言葉の元になっているレリジョン(religion)という言葉の起源は、諸説ありますが、ラテン語のレリギオ(religio)、つまり人々を再び繋げていくという意味があると言われています。従来の繋がりを断ち切った上で、再び繋ぐということですね。しかし、そもそも人と人とが繋がるということはどういうことなのでしょうか。近代の宗教と世俗の枠組みでは、内面の問題は個々人に任せておけばよいことになりますから、人と人が繋がって宗教的なコミュニティを作る意義は薄れます。キリスト教においては、聖書を通じて個人が直接神に向かえばよいということになり、教会のような中間的な組織は存在理由を失っていきかねません。しかも、二一世紀になりますと、人々の孤立感や分断化はますます深刻になってきました。近代自体が個人の内面を重視する以上、それは孤独や孤立を生みやすいシステムだったわけですが、二一世紀はそれを加速していきました。「居場所がない」とか「自分のアイデンティティが揺らいだ」というケースに対して、いったいどう応ずればよいのでしょうか。
簡単に考えてしまえば、何か安心できるコミュニティがあって、そこで人と繋がればよいとなります。しかし、今はそう簡単なことではありません。「絆」という言い方がもたらした問題がどれだけ深刻であったかを思い出せばよいかと思います。人と人が繋がることの意味をきちんと考えていかないと、非常に安易なイデオロギーに回収されてしまい、かえって戸惑ってしまうのです。精神文化や宗教文化の意味や役割を考えるのは、まさにこうした人と人との繋がり方に関わっているのです。
そこで、お二人には、今日における精神文化や宗教文化の役割や意味をどのようにお考えになっているのかをうかがいたいと思います。その際、二つのことに注意を払いたいと思います。ひとつが、世界的な文脈において理解すべき、ポスト世俗化の問題や宗教復興といった現象です。もうひとつが、人と人とのあらたな繋がり方です。あらたに繋がり直すためには、今までの繋がりを断ち切る力がどうしても必要です。こうしたことを、東京の中心地で展開している様々な精神文化や宗教文化の活動から考えてみたいのです。
世俗化におけるプロテスタンティズムとナショナリズムの影響
吉見俊哉 中島先生から、「近代」と「宗教」という大変大きな課題が提示されましたね。近代の世俗化に関しては、学問的文脈で言うと、少なくとも二つのことが 長く議論されてきました。
ひとつはプロテスタンティズムで、もうひとつはナショナリズムです。まず、通説的には、近代には二段階あるとされます。一六世紀に始まる近代と、一八世紀末に始まる近代です。一六世紀に始まる近代は、大航海時代や宗教改革、ルネッサンス、印刷革命などの時代でした。日本は安土桃山時代です。「近世」ないしは「初期近代」とも言われます。これに対して、一八世紀末からの近代は、フランス革命や産業革命、英仏の帝国主義と日本の幕末維新、つまり狭義の近代です。世俗化が支配的な流れになるのは、一八世紀末以降の近代です。
それ以前、一六世紀から世界に広がった初期近代は、世俗的な時代ではありませんでした。そもそも宗教戦争をしているわけです。この時代、プロテスタントとカトリックは極端に原理主義的になっていました。キリスト教とイスラームの抗争も世界で起きていました。それが反転して、一八世紀末以降、世俗化が急速に起こっていくのです。この世俗化という問題は、人々が宗教に関心を持たなくなったというよりも、プロテスタンティズムが内面化して資本主義の精神となり、社会がどんどん個人化していった変化と繋がっています。
ところが、同じ一八世紀末からもうひとつの変化が生じます。それがナショナリズムです。ナショナリズムが勃興し、それに人々が強力に統治されていくなかで、世俗化が起こっていったという面もあります。つまり、一方の市民化と他方の国民化、これは同じコインの表裏ですね。
そうすると、世俗化の限界とともに個人の限界とナショナリズムの限界が見えてきます。一方で、個人が独立した存在で、内面の問題として宗教が語られるという前提が崩れていくのと同時に、他方で、ナショナリズムも限界に達して、国民国家というフレームが壊れていく。この両方が同時に起こってきたのが現在です。言うまでもなく、この背後にあるのは資本主義の高度化です。
神道の特徴、特殊性
吉見 こうした前提を置いた上で、日本の神道を考えますと、いろいろと面白いことがあります。神社の参詣は、個人の内面的な意志として参詣している人もいるかもしれませんが、多くの場合、社会的慣習の一部をなす行為で、プロテスタント的な個人化をしてはいないように見えます。神道は、個人よりも家族やコミュニティの結びつきの結節点にあることが重要ですので、プロテスタンティズムとは真逆と言えます。神道的な信仰のあり方は、内面よりも外面というか、共同体においてどう振る舞うかということが大切ですね。信仰が、個人を世間から離脱させる契機にはあまりなっていない。
神道の基盤は、村や町内会といった地域コミュニティの繋がりですね。神道にとって一番大切なものは、祭りです。それに対して、プロテスタントにとって一番大切なものは聖書であり、カトリックにとって一番大切なものは教会です。もちろん神社の社殿も大切だとは思いますが、祭りが最重要であるような信仰のあり方は、キリスト教的な信仰とは非常に違う気がします。そこに日本の神社の可能性もあるでしょうし、キリスト教やイスラームを中心に世界で起きてきたこととは、宗教性のフェーズがかなり違う面があると思います。
押見匡純 戦後の急激な都市化に伴い、郊外の里山が宅地へと変わり、そこに新しい人が移り住むようになりました。そこで、昔からの住民と新しく移り住んでこられた方々との交流の場となっているのが、鎮守の神さまのお祭りであるといえます。お神み輿こしやお旅たび所しょの準備、運営で氏子をはじめ新旧住民同士が強く結ばれます。すると、人生の苦しい時、悲しい時、お祭り仲間は互いに支え合い、助け合うことができるようになるのです。
お祭りのもつ不思議な力は、目には見えませんが、老若男女がお祭りに参加し、お互い強い絆きずなで結ばれ、地域社会がひとつにまとまり発展していくことができるものと考えます。
言うまでも無く、お神み輿こしの巡じゅん行こうも氏神様と氏子また住民同士の絆を結束する役割をはたしているのです。
近年、災害がとても多く生じています。あちこちに復興支援活動に行かせていただいたのですが、社殿が損壊している姿を見て、地域の人がとてもがっかりしているのを感じました。地域の中心であり、心の支えでもある神社を早く復興しないといけないと思いました。今度はコロナ禍で、お祭りがなかなかできない状況にあります。それは、東日本大震災やほかの災害のときも同じでしたが、祭りがないことは多くの日本人にとって、日常ではなくなることだと思います。祭りの際に地域の人たちが集まって、今年のお祭りはどうしようかと話し合いをするなかでコミュニティが形成され、こうした有事のときに地域の和が生きてくるわけです。
神社は宗教かどうかというと、宗教学者の中でも意見が分かれています。宗教的な要素はもちろんありますが、日本人の生活習慣そのもので、神道は習俗だと言う方もいらっしゃいます。
神道と疫病の古い関係
吉見 新型コロナ感染症のパンデミックは、神道とも関わりが深い。今起こっていることは、全世界的な疫病です。疫病の流行を、日本は昔から経験してきています。古来、神道において地震や水害などの災害以上に頻繁に鎮めなければならなかったのは、疫病だったと思うのです。菅原道真公にしても、平将門公にしても、怨霊は災いをもたらす神となり、その荒ぶる神を鎮めることが神社にとって非常に重要な機能でした。疫病は、人々に最も身近な災いで、近代に至るまで、いや近代に至っても絶えなかった。
そして疫病は、イメージとして「怨霊」の形をとりますね。神田明神であれば平将門公、湯島天満宮であれば菅原道真公は、死後、怨霊となり、そして神社に祀られます。考えるべきは、誰が、道真公や将門公を怨霊や神にしていったのかということです。もちろん、歴史上の人物としての菅原道真は調べればわかります。そうではなくて、彼を怨霊にした力は何であったのか、そして怨霊化した道真公を鎮めるために神社がなぜ全国に生まれていったのかを考えたいのです。彼を怨霊化していった力と、それを鎮める神社の力の関係は、グローバルな構図としても、パンデミックになっていく疫病とそれを鎮める宗教的な力という関係に対応していると思います。
したがって、現在のようなパンデミック的な状況に、神社は昔から比較的慣れているはずです。共同体的な空間を何か恐ろしい疫病が外から襲って、その安定が大混乱に陥ったとき、祭りによってそれを鎮めるという機能です。現在のコロナパンデミックを、怨霊の視点から考えると、神社の役割が、多くの人が抱える疫病への不安やそこからの救済にそもそもあったことに気づきます。
押見 天神信仰の形態のひとつに、「綱つな敷しき天神」があります。綱の上に坐して忿ふん怒ぬ 相そうのすさまじいものです。大宰府左遷の折、菅原道真公が海岸に上陸すると漁師が船の艫とも綱づなを巻いて円座とし、休息を願ったという伝承があります。目は半眼で憤り、荒ぶる神の代表として畏怖されました。しかし、このような荒ぶる神としての信仰はほんの一部です。むしろ慈悲深く、冤罪になげく弱者の味方のやさしい神でした。
留意すべきは、古代より地方では、天神の社やしろは村の外れや町の入口に鎮座されていたということです。荒ぶる力の強い神、怨霊といわれた天神を祀ることで、疫病をもたす疫やく病びょう神から村や町を守っていただけると考えていたのです。荒ぶる神によって荒ぶる神から守っていただく、これも日本人の信仰のひとつなのです。
宗教のアナログ性――「触れる」という力
押見 ところが今やネット社会となりました。しかしながら人間がデジタルになってしまうわけではありません。心はずっと一定しているわけではなく、紆余曲折して変化していきます。心が揺れたり不安になったりしたとき、神社としては、お参りに来ていただいて、清々しい気持ちになっていただく。それが神社に求められる第一のものだと思います。
今、御朱印が人気ですが、御朱印は帳面に手書きする、実にアナログなものです。ネット上で御朱印は手に入りません。御朱印を受けることには、行く道中や、行ったときの空気感、お参りしたときのその気持ちが全部入っています。ネットでは絶対に感じることができません。人間のアナログ的な感覚を満たすものが神社にはあって、人々はそれを求めに行っているのだと思います。
吉見 押見さんが御朱印の話をされましたが、江戸時代であれば、伊勢参りをして伊勢神宮のお札をもらうことが大切でした。お札に触れ、持つことによって力をもらうわけですね。神社の信仰では、何かに触れたい、何かものを持ちたいという触覚的な部分がとても大きいと思うのです。触れたときに与えられる力が重要なのですね。
ところで、全国に天神様はいくつくらいあるのでしょうか。
押見 約一万二〇〇〇社です。
吉見 約一万二〇〇〇もの天神があるということは、道真公はとてつもないスーパーパワーの持ち主ですね。しかし、彼に力を持たせたのは、彼自身ではありません。人々が彼を神様に祀り上げていったのです。そしてその祀り上げられた天神様から、人々は力をもらう。道真公や将門公の力は、人々の恐れや不安、疫病など、社会にとって破壊的でネガティブな力が反転したものでしょう。祀り上げることによる反転で、マイナスの力がプラスの力になる。そして反転した力を、神的なものに触り、また同時に触ってもらうことによってもらうわけです。見るだけ、話を聞くだけでは力はもらえません。
この触ることの宗教化は、日本人の清潔感とも関係があるのではないかという気がします。実際、日本政府が政策的に大したことをしているわけではないのに、日本で新型コロナウィルスの感染者が、今のところ抑えられているのは不思議ですが、その理由のひとつに、マスクや手洗いなど、清潔好きな日本人の生活習慣が作用していそうです。接触に対する感度・感性は、日本の神社信仰の中で長く制度化されてきた面があると思うのです。
ですから、やはりコロナも怨霊なのです。現代の将門公、道真公です。この新型コロナウィルスという怨霊を鎮めるスーパーグローバルな神社ができるかもしれません。その神社は、コロナ怨霊を祀り上げてプラスの力に変えられるかもしれません(笑)。道真公や将門公に表象される力があり、それに触るということを宗教化する伝統が日本の神社にはあります。そして、それが日本人の習慣に深く根づいていることが面白い点です。
触れることへの畏れ、敬意と距離
押見 触れることに関して考えてみると、日本では挨拶の際に基本的には握手ではなくおじぎをします。欧米など海外だと握手はもちろんのこと、抱擁もします。そういう文化圏では、身体接触が親密であればあるほどよいとされているかもしれませんが、日本では逆に触れるということに対しては畏れがあるのです。
古来日本では、基本的には、直に対象に触れることは不敬にあたると考えられています。神社に参拝する際には手水がありますが、それはまずは自分の中で心を祓い清めるためです。祭典の前にもお清めをします。触れる前にまずを清めます。清めをひとつの区切りとして世俗と神聖な場所や物を分けているのです。
その上で触れるということは、そこに繋がるという大きな意味が生じ、それは、その方(神や人)の力をいただくことになるのです。神道では、触れることは、とても高い段階にあると思います。
それは畏れという言葉でも説明できると思います。神様にも、尊い方にも畏れを感じます。尊い方であればあるほど日本人は畏れを感じ、その最も尊い存在が神様で、触れるどころか目を合わせることも憚られるのです。つまり、日本人は、畏れや敬意をその距離で測るのです。本当に親しければ、握手をしても肩を組んでも構わないのですが、目上の方であれば、握手を最初から求めるのは不作法になるというわけです。
吉見 坂部恵先生が昔、「触れる」ことの西洋と日本の違いについて、非常に鮮やかに書いていらっしゃったような気がします(『「ふれる」ことの哲学│人称的世界とその根底』、岩波書店、一九八三年)。たとえば「気がふれる」とか、「魂たま振ふ り」だとかにも現れています。それらは触覚的に触れることと意味論的には繋がりがありますが、日本の語彙体験の中で「触れる」という語の展開形はとてもたくさんあるわけです。それが、日本人にとって触れることの意味合いの深さである。こうしたことを坂部さんは非常に上手に書いていました。
(以下、本文つづく)

