あとがき、はしがき、はじめに、おわりに、解説などのページをご紹介します。気軽にページをめくる感覚で、ぜひ本の雰囲気を感じてください。目次などの概要は「書誌情報」からもご覧いただけます。
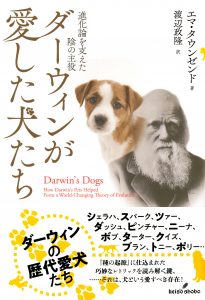 エマ・タウンゼンド著
エマ・タウンゼンド著
渡辺政隆 訳
『ダーウィンが愛した犬たち 進化論を支えた陰の主役』
→〈「はじめに」「訳者あとがき─犬たらしの天才ダーウィン」(pdfファイルへのリンク)〉
→〈目次・書誌情報・オンライン書店へのリンクはこちら〉
はじめに
一八六〇年代初頭の夏のひととき。ダーウィン家の人々が愛犬とともに写真に納まっている。写真は、ケント州ダウン村にあったダウンハウスの庭に面した窓辺で撮られたものだ。窓枠に腰かけているのは、成長した子供たちの母であるエマ・ダーウィン。ボンネットをかぶり、本を読んでいる。いちばん左の帽子をかぶっている背の高い少年は、一三歳のレナード。その右隣で日傘をさしているのは、父親の仕事を手伝っていた一九歳のヘンリエッタ。母親といっしょに窓枠に腰かけているのはホレス。このときはまだ一二歳だが、後に有名な科学機器メーカーを創設することになる。スカートを広げて腰かけているのは、一六歳のエリザベス。愛称はベッシーで、素っ頓狂な帽子をかぶっていることからも、性格に問題がありそうなことがうかがわれる。窓の右に立っているのはフランシス。ベッシーの一歳年下で、やがて父親の研究助手を務めることになる。一家の犬好きをもっとも受け継いだ息子だった。
写真にはもう一人写っているが、末席に甘んじているこの少年が誰かはわかっていない。一八六三年頃の夏の日にダウンハウスを訪れていたこの少年の名前はこの先もわかりそうにないが、犬の名前はボブにまちがいないと思われる。黒と白の大きなレトリーバーで、『人間と動物の感情表現』(一八七二)の中で、著者で飼い主であるダーウィンに、その「温室顔」を紹介されたことで名を残している。
犬の飼い主なら、誰もが「温室顔」には心当たりがあるはずだ。いかにもがっかりした様子で、耳を前に向け、最後の希望を託してお願いと訴えかけるような表情である。ボブの場合は、散歩が中断されることの失望感の表われだった。ボブにとって、庭に面したドアを開けてダーウィンが芝生に出てくるのは、いっしょに庭を横切って大好きな朝の散歩に出かけるサインだった。しかし、ダーウィンが部屋を出た目的が散歩ではなく、実験観察用の植物を育てている小さな温室を訪れることだった場合、温室への曲がり角で、ボブは「がっかりした態度」を示すことが多かった。
ボブの温室顔を見たダーウィンは、そのまま見捨てるわけにもいかず、散歩に切り替えるほかなかった。それでもダーウィンは、何かを目論んでいるボブを責めることはなかった。「私には自分の感情を理解するはずだと彼がわかっているとは思えない。まして、そうすることで私を懐柔して温室仕事を断念させることになるとは思ってもいないだろう」(『人間と動物の感情表現』より)。ダーウィンにしてみれば、ボブは単に、飼い主の行動を変え、仕事はあきらめて大好きな散歩に変更させたくて、本能に従っているだけなのだ。ダーウィンは、飼い主と犬とのちょっとした交流においてさえ、目の前の犬のしぐさに魅了され、その行動を分析し書き留めていた。
ダーウィンは著書や書簡で愛犬に言及しているが、なかでもボブへの言及は頭抜けて多い。ダーウィンの愛犬の写真はごくわずかしか残されていない。ダーウィンが生きた時代は、写真が一般的になるギリギリの時期だったからだ。ダーウィンのせめてもの慰めは、最愛の娘アニーが一八五一年に亡くなる二年前にわざわざロンドンに出かけ、銀板写真にその姿を残せたことだった。その十年後には、それなりの機材をそろえた写真家が自宅を訪れ、ボブと家族を撮影できる時代になっていた。
ヴィクトリア時代のプロの写真家たちは、撮影技術を猛スピードで向上させていた。それでも標準的な白黒写真の撮影では、明るい夏の日差しの屋外でも、露光時間が何秒もかかっていた。家族の足元で臥せって写っているボブは、地面に結び付けられているかのように頭を下げている。おそらく縛られていたのだろう。写真家が露光させているあいだ、紐をはずそうと首を振ったような痕跡はない。完全にじっと臥せっていたのだろう。しかし写真撮影にあたっては、少なくともちょっとした問題くらいはあったにちがいない。エマとエリザベスが顔に微笑みを浮かべている理由が、その理由かもしれない。
この写真撮影は、人と動物のあいだに横たわる大きな溝を完璧に要約している。犬は家族の一員として家庭内で暮らしている。しかし、どんなに幼い子供でも、短い時間でもじっと座らせておくには説明が必要である。それに対して犬は、待てと命令しなければならない。なだめすかしや論理的な理由で犬を説得することはできない。犬をじっとさせておくには、直に命令するしかない。会話や説得は効きめがない。人間の世界と動物の世界とのあいだには大きな隔たりがあるのだ。
単に写真を撮るだけのことでもそのようなコミュニケーションギャップの影響を受けるとしたら、人と犬が毎日いっしょに暮らすというのは、ややこしくて危なっかしい話で、予測できないことだらけだろうと思えるはずだ。結局のところ、犬は生きるために狩りをしていた動物の子孫ではないか。ヒトが動物といっしょに暮らすとはどういうことなのか。分析的で知的な猿が、予測のつかない不可解な心を持った犬といっしょに暮らすとは。言葉によるコミュニケーションが成立しない上に、両者の心は多くの点で大きくかけ離れているという事実を前にするなら、両者の関係は、どう見ても微妙なものとならざるをえないだろう。
動物界に関するチャールズ・ダーウィンの業績を思うとき、すぐに思い浮かぶのは、ガラパゴス諸島の小さなフィンチ類のくちばしやガラパゴスゾウガメの大きな甲羅を調べる姿だろう。あるいは、イギリスから遠く離れたアフリカなどの森にすむゴリラやサルといった珍しい動物だろうか。しかし、ダーウィンがもっとも深く長く接した動物は、自宅でいっしょに暮らす動物たちだった。子供時代も、ダウンで家庭を構えてからも、ダーウィンが飼っていたのは犬だった。
彼の愛犬生活は、十代のときにとても可愛がっていたシェラハ、スパーク、ツァーで始まった。ケンブリッジ大学では従兄のウィリアム・D・フォックスといっしょに、二人の犬サッフォー、ファン、ダッシュを伴って狩りをした。その後のハンティングドッグのピンチャーと小型犬のニーナの二匹は、ダーウィンがビーグル号の航海に出ていた五年のあいだ、実家で留守番をしていた。
子供を授かったダーウィンは、犬も飼った。写真のボブは白と黒のぶちのお行儀のよい大型犬で、家族みんなに愛された。ディアハウンド犬の子犬ブランは、一八七〇年にやって来た。一家は犬を途中から引き受けるのが得意で、クイズ、ターター、ペパー、バタートンはそうやって家族になった。トニーは、もともとはダーウィンの義妹であるサラ・ウェッジウッドの飼い犬だった。サラが一八八〇年に亡くなったため、ダーウィンが引き取った。最後の犬ポリーは、最初は娘のヘンリエッタの犬だったのだが、ヘンリエッタが結婚してダウンを離れた後も、ダーウィンはポリーを手放さなかった。息子のフランシスによれば、ダーウィンはポリーをいちばん可愛がっていたという。
ダーウィンがもっとも親密にいちばん長く観察した動物が犬だった。生涯を通して、ビーグル号の航海時を除いてほぼ毎日、犬といっしょだった。ダーウィンが育ったのは、農地に囲まれた商業都市シュルーズベリだった。そこでは家畜市場や農産物品評会が定期的に開かれていた。ダーウィン少年はペットの犬を連れ歩き、犬が獲物を追う姿を眺め、犬といっしょに野山を駆け巡った。
しかし、シェラハ、スパーク、ツァー、ダッシュ、ピンチャー、ニーナ、ボブ、ターター、クイズ、ブラン、トニー、ポリーは、ダーウィンの研究においてきわめて重要な面々でもあった。この犬たちは何を考えているのだろうかと思案し、その行動を説明しようとした。そしてそうした問題について、ブリーダーや愛犬家と手紙を交換した。それは決して意味のないことではなかった。ダーウィンの研究は、いろいろな面で犬に刺激を受けていたのだ。その証拠に、進化の理論に真剣に取り組むにあたっては、フィンチやゾウガメではなく、鳩、牛、豚、犬といった飼育動物の話から始めているのではないか。
そして、世間を騒がすことになる『種の起源』をついに世に送り出すにあたっては、第1章をイギリスの田園地帯で見られる動植物の話から説き起こすことで、波風を抑えることにした。よちよちと歩くアヒル、ミルクを絞られる牛、穂を実らせる小麦など、農家の見慣れた光景を第1章に盛り込んだのだ。ダーウィンは、育種家や品種改良家の例を出し、自然淘汰説のはたらきも、選り好みの激しい犬のブリーダーが好みの形質を選び、好ましくない形質は除去するのと同じだという喩えを用いた。目新しい自然淘汰説を親しみやすいものにするために、おなじみの例を出し、苦い薬をオブラートにくるみ、ヴィクトリア時代の一般読者にとってとっつきやすいものにしたのだ。ダーウィンは愛犬を介して、ヴィクトリア時代の家庭の居間に進化理論を持ち込んだのである。
進化理論はたしかに苦い薬だった。ボブが写っている写真が撮られた当時、ダーウィンの進化理論をめぐる論争は最高潮に達していた。学術論争が罵倒に堕すると、批評が誹謗中傷に代わった。最大の罵倒は、自然界における人間の地位をめぐる問題に向けられた。ダーウィンが言うような進化が起こってきたとしたら、それには人間も含まれるはずではないか。だとすれば、人間はただの動物にすぎないことになる。それ以上でもそれ以下でもない。この考えに、多くの人がおののいた。敬虔なキリスト教徒にとって、人間は特別な資質を備えたおかげで畜生の上に立てたという説明は信じがたいことだった。協力、利他行動、宗教心はみな、人間は特別な存在だという証拠のはずだった。そうした独自の資質は、進化したのではなく、神によって付与された特別な資質であるはずなのだ。ダーウィンの言う生存闘争のどこに、利他的なやさしさが入る余地があるのかと、批判者は問うた。
それでもダーウィン理論の支持者たちは激しい論陣を張った。ときには顕微鏡のスライドグラスをめぐる論戦まであった。ダーウィンの「ブルドッグ(番犬)」とも呼ばれたトマス・ハクスリーが、解剖学の権威リチャード・オーエンを相手に、ゴリラの脳の切片に関する解釈が間違っていると非難したのだ。激高したオーエンはハクスリーの罠に落ちた。人間の脳は特別であることを証明しようとして類人猿の脳の構造を誤って解釈していたことで、オーエンの名声は永遠に損なわれた。
しかしダーウィン自身は、そうした論争からは距離をとっていた。ダーウィンは、『種の起源』出版後十年をかけて、この問題についての答を練り上げた。ダーウィンにとって、人間が進化したことは自明だった。しかしだからといって、卑下することはない。人間の祖先が動物であることを受け入れたからといって、下等な動物に降格されたことにはならないと考えていたからだ。その考えのすべてに、愛犬が貢献していた。人間と動物とのあいだに存在するとされる深い溝は、思うほどには深くないというダーウィンの主張を支えていたのが、愛犬たちだったのだ。人間が怒る表情と、犬が怒る表情には共通点が見つかる。人間は夢を見るが、犬も寝ているときに脚をぴくつかせたり唸ったりする。それは、犬も夢を見ているからだ。
ダーウィンは『人間と動物の感情表現』の中で、最後に飼った愛犬のホワイトテリア、ポリーの話を書いている。ポリーは、書斎で仕事をするダーウィンに一日中つきそっていた。「父はポリーにいつもニコニコと優しかった」と、フランシスは父親の思い出を語っている。「部屋に入れてほしいとか、ベランダの窓から外に出たいとか、『いたずらっ子』に吠えたりとか、夢中になっている動作など、ポニーが気を引こうとする行動に短気を起こすことは決してなかった」という。ダーウィンが老いると、ポリーが入る籠は書斎の暖炉のそばに据え付けられた。そのバスケットは、家族が写した書斎の写真で見ることができる。ダーウィンが亡くなった翌日、ポリーは主人の後を追うように旅立った。その遺体は、フランシスによってダウンハウスの庭に埋められた。ダーウィンの一生は、犬大好き人生だった。そこで私は、ダーウィンの生涯を別の角度から紹介することにしたい。すなわち、犬の視点から語ろうというのだ。フィンチやゾウガメの物語はすでに語られている。どうか、ボブとポリーが語る物語に耳を傾けていただきたい。
(写真は省略しました。pdfでご覧ください)
訳者あとがき――犬たらしの天才ダーウィン
進化理論の祖チャールズ・ロバート・ダーウィンは、大の犬好きだった。ビーグル号の航海に出ていた五年間と帰国後のわずかな年数を除いて、ダーウィンは常に犬を友としていた。本書『ダーウィンが愛した犬たち─進化論を支えた陰の主役』が生まれた所以である。
本書の原題はきわめて直截なDarwin’s Dogs(ダーウィンの愛犬)で、サブタイトルはHow Darwin’s pets helped form a world-changing theory of evolution(ダーウィンのペットは世界を変えた進化理論の形成をどのように助けたか)。
著者のエマ・タウンゼンドは一九六九年イギリス生まれのサイエンスライターである。ケンブリッジ大学キングスカレッジで歴史学を学び、インペリアルカレッジ(ロンドン)の修士課程で科学史を専攻し、ケンブリッジ大学の博士課程に進んだが、音楽活動にシフトするため中退した。
エマの父親は、伝説的なロックバンド「ザ・フー」のメンバー、ピート・タウンゼンド(タウンゼントの表記もある)であり、十代の頃から父親のアルバムのバックコーラスなども務めていた。一九九八年には自身のアルバムWinterland をリリースしている。九九年には、テレビ映画The Magical Legend of the Leprechauns の主題歌We Can Fly Away を歌って注目を浴びた。
大学院中退後は社会人講座などの講師を務める傍ら、新聞や雑誌に記事を書くようになった。現在、音楽活動はしておらず、ガーデニングなどに関する記事を新聞などに寄稿している(そのため、ご本人はガーデニングライターを名乗ってもいる)。
本書を書くことになったきっかけは、「謝辞」にもあるように、サマースクールでのダーウィン講座で、「ダーウィンの愛犬の視点でダーウィンの話が書けたらおもしろいだろうね」というジョークだったようである。嘘から出たまことというべきか、自身の妊娠も重なって難渋した末、ダーウィン生誕二〇〇年、『種の起源』出版一五〇年にあたる二〇〇九年に、本書は日の目を見た。
ダーウィンが進化理論に思い至ったのは、ガラパゴス諸島のフィンチ類やゾウガメに出合ったのが大きかったとよく言われる。しかし、それらの生きものは、自然淘汰説の援護射撃では重要な役割を演じたが、真の主役は、ダーウィンがいちばん長く付き合った犬たちだった。それが、著者の発想の源だった。
本書でも紹介されているように、ダーウィンは、友人や家族の犬の愛情を横取りする名人でもあった。豊臣秀吉や坂本龍馬を「人たらしの天才」と呼んだ司馬遼太郎に倣うなら、ダーウィンは「犬たらしの天才」だったと言えるだろう。
ダーウィンが一八五九年一一月二四日に出版した『種の起源』は、一晩で世界を変えてしまった。キリスト教を基盤とした西欧社会の価値観を一変させることになったからだ。
しかし、そうした予備知識をもって『種の起源』をひもとくと、「えっ」と驚くかもしれない。
なぜなら、冒頭から「種とは何か」と論じているのかと思いきや、第1章のタイトルは「飼育栽培下における変異」であり、「長年にわたって飼育栽培されてきた植物や動物において、同じ種類の変種や亜変種に属する個体を見比べてみよう。そのときにまず気付く点は、野生状態にある同一種や同一変種の個体間に見られる変異よりも、飼育栽培されている変種や亜変種の個体どうしのほうが一般に変異がはるかに大きいということだろう」と説き起こしているからである。
これではまるで育種学の本ではないか。「種の進化」の話ではなかったのか。
著者タウンゼンドに言わせると、これはダーウィンの周到な策略だという。天地創造説をひっくり返す革命的な書を野に放つにあたり、ビクトリア時代の人々にとって身近な存在である、家畜や家禽、野菜や作物の話から入ることで、警戒心を解こうとしたというのである。そういうわけで、『種の起源』第1章の主役は飼い鳩である。日本では伝書鳩とドバトのイメージしかないが、当時のイギリスでは観賞用鳩の品種改良が盛んで、ダーウィン自身も自ら鳩を飼い、紳士階級と労働者階級の愛鳩クラブ二つに入会して情報交換をしていた。
観賞用鳩のさまざまな品種が、野生種であるカワラバト一種から驚くほど短時間で作出されたという事実をもってして、選抜育種の威力のほどを示そうというのだ。人間が短時間でできることなら、時間はたっぷりある自然淘汰の潜在力や推して知るべしというのだ。
テントに鼻を入れさせてやったラクダにテントを乗っ取られる故事よろしく、読者の懐にするりと入りこんで少しずつ意識革命を達成する作戦というわけである。
ダーウィンは、鳩以外にもさまざまな飼育動物の品種改良に関する情報収集に怠りなかった。そのなかで特に精力的に集めていたのが、犬種の維持改良に関する情報だった。
ダーウィン少年が博物学に目覚めたのは愛犬のおかげだった。彼は犬との交流を通じて自然に目覚め、観察の大切さを学んだのだ。一時は、父親から、「犬と猟ばかりに夢中になって」とあきれられるほどのめり込んだ。
自然淘汰説を思いつくにあたっても、犬のブリーダーたちから情報を集め、人間による品種改良と自然による淘汰を関連付けたのだ。
『種の起源』に人類進化の話は登場しない。言及はただ一カ所のみである。
遠い将来を見通すと、さらにはるかに重要な研究分野が開けているのが見える。心理学は新たな基盤の上に築かれることになるだろう。それは、個々の心理的能力や可能性は少しずつ必然的に獲得されたとされる基盤である。やがて人間の起源とその歴史についても光が当てられることだろう。(『種の起源』第14章より)
しかしダーウィンは、人類進化に関する証拠も着実に収集していた。そこで満を持して一八七一年に出版したのが『人間の由来』と、七二年の『人間と動物の感情表現』だった。
『人間の由来』にも、人間のルーツも他の動物と同じであることを論じるために、動物それも特に犬の例が頻出している。『人間の由来』は、当初二巻として出版されたが、一八七四年には大幅に改編されて一巻本として出版された。本書でも同書からの引用が多数なされているが、第二版を典拠にしている。そこで訳書では、初版にはなく第二版のみにある文章については、出典を第二版と明記した。
『人間と動物の感情表現』は、人間と動物の表情やしぐさの共通性を扱っており、心理学と動物行動学の原典とも言われている。このテーマに関するダーウィンの関心は、第一子ウィリアムの赤ん坊時代の観察に始まっている。
折しもその二年前から、ロンドン動物学会の動物園にオランウータンの子供ジェニーが展示されて人気を博していた。ダーウィンは動物園に足しげく通い、ジェニーとウィリアムが見せるしぐさの共通点を探ったのだ。
『人間と動物の感情表現』の陰の主役は、ダーウィンが最後に飼っていたテリア犬ポリーである。最初は娘ヘンリエッタの犬だったのだが、一八七一年に結婚して家を出たのを機に、ダーウィンと相思相愛の仲になった。
ポリーは、ダーウィンが仕事中は書斎の暖炉前に置かれたバスケットの中にうずくまり、日課の散歩のときは楽しげに付き従った。一八八二年四月一九日、ダーウィンがダウンの自宅で息をひきとると、ポリーは見るからに落胆し、その翌日、主人の後を追ったという。
ポリーが死んだのはダーウィンの死の数日後という説もあるが、妻エマの日記には、四月二〇日の欄に、「ポリーが死んだ」とある。
ここに掲げた図は、ダーウィンが亡くなって間もなく撮られた写真をもとに作成された、主亡き後の書斎の様子である。暖炉の前に置かれたバスケットも、その主を失って寂しげである。
ダーウィンは、一日に何度も散歩に耽った。家の庭から温室の横を通り、隣地の牧草地との境界に沿って続く小石混じりの小道を「サンドウォーク」と名付け、そこを何周もしていた。温室では、ランやつる植物、食虫植物など、実験観察用の植物が栽培されていた。
本書でも言及されている、『人間と動物の感情表現』で有名になったレトリーバー、ボブの「温室顔」のエピソードは、その散歩コースが、温室の横を通っていることで生まれた逸話である。
書斎を出た時点では、主人が向かう先がサンドウォークなのか温室なのかはわからない。温室の横をそのまま通過すれば大好きな散歩だが、温室の方向に折れれば、散歩はお預け。ボブは落胆した「温室顔」になるというわけだ。
本書で紹介されている、五年間の不在を経ても主人との習慣を覚えていた犬のエピソードも印象深い。
ケンブリッジ大学を卒業したダーウィンは、南アメリカ沿岸の測量のために出港する軍艦ビーグル号に、艦長の客分として乗船した。館長とディナーをともにする以外は、ナチュラリストとして好きなことをしていいという願ってもない条件だった。
五年に及んだ航海を終えたダーウィンは、実家で待つ父と姉妹たちとの劇的な再会を画策した。イギリス南西端の港ファルマスからイングランド西部のシュルーズベリまではおよそ三百マイル。馬車を乗り継ぎ、自宅に到着したのは二日後の夜中だった。その日は誰にも会わず自室で休み、翌朝、朝食の場に予告なしの登場を果たしたのだ。
家族との再会を喜んだ後、最初にしたのは姉と手紙で示し合わせていた実験だった。実家には、ダーウィンにしかなついていなかった犬がいた。不愛想ではあるが、いつもいっしょに散歩していた犬だ。はたしてその犬は、主人との再会にどのような反応を示すのか。
朝食を終えたダーウィンは、その犬がいる厩舎へと向かった。以前のように犬に呼び掛けると、昔と変わらぬ様子で外に出てきて、あたりまえのように主人の散歩に寄り添ったという。その犬は、再会を喜んだふうには見えなかったが、五年前の習慣を昨日のことのように覚えていたのだ。
この経験からダーウィンは、犬にも意識や思考力、長期記憶があるという信念をもつに至ったのだろう。
もしかしたらこの実験は、ギリシャの古典にヒントを得ていたのかもしれない。同じような逸話が、古代ギリシャの詩人ホメロスの『オデュッセイア』に登場するのだ。
十年に及んだトロイア戦争を木馬の知略で勝利したオデュッセウスは、凱旋の途上で遭難し、さらに十年の放浪を経て、国を離れてから都合二十年ぶりに帰宅する。オデュッセウスは、貞淑な妻ペネロペイアに言い寄る男たちを倒すために老人の身にやつして屋敷に戻るのだが、唯一、その正体に気付いたものがいた。それは、子犬のときに主人と別れ、すばらしい猟犬に育ったものの、今は老いさらばえ、世話もされず糞尿にまみれて横たわっていた愛犬アルゴスだった。
この時その場に横になっていた犬が、頭と耳をもたげた。(中略)犬のアルゴスは、犬だに、に塗(まみ)れて臥(ね)ていたが、この時近くに立つオデュッセウスの姿に気づくと、尾を振り両耳を垂れたものの、もはや主人に近づいてゆく力はなかった。(中略)犬のアルゴスは、二十年ぶりにオデュッセウスに再会すると直ぐに、黒き死の運命の手に捕らえられてしまった。『オデュッセイア』松平千秋訳(岩波文庫)より
オデュッセウスは、敵に正体を知られまいと、顔を背けて涙をぬぐい、愛犬の横を通り過ぎるしかなかった。耳を倒して尻尾を振るポーズは、親愛の情を示す表現である。立ち上がる体力も気力もなかったアルゴスにとって、それが、二十年前、子犬のときに別れた主人への精一杯の挨拶だったのだ。
『種の起源』出版百五十年にあたる二〇〇九年、ぼくも光文社古典新訳文庫から『種の起源』の新訳を出版した。同じダーウィン年に本国イギリスで本書が出版されていたことは、寡聞にして知らなかった。
本書を知ったきっかけは、時間に余裕が出たことから、ダーウィンと愛犬との交流を調べようと思い立ち、文献漁りをしていた中でのことだった。
かれこれ四半世紀前、ダーウィンの長大な伝記『ダーウィン─世界を変えたナチュラリストの生涯』(工作舎、一九九九)を翻訳していたときのこと。一日十時間近くも机に向かっていたせいでひどい腰痛に襲われ、運動不足を自覚したことから、散歩の友として犬を飼おうと思い立ち、奈良県桜井保健所の保護犬紹介で雑種の子犬の里親となった。付けた名前が、ダーウィンが学生時代に飼っていた犬の名前サッフォーだった。
そんな謂れを知った勁草書房の鈴木クニエさんと当時の同僚の方から、歴史上の科学者の愛犬列伝を書きませんかという提案をいただいたのは、十年も前のことだったと思う。その間にわが愛犬は二代目となり、今はやんちゃなゴールデンレトリーバーと同居している。
そのことがずっと頭に引っかかっていたことから、列伝の実現は差し当たって難しいものの、翻訳ならばということで提案したのが本書である。
幸い、翻訳権が開いていたことから話が進み、上梓する運びとなったしだいである。鈴木クニエさんとは、同じ愛犬家という縁もある。
進化学、科学史に興味ある読者のみならず、愛犬家の方々にも楽しんでいただけたら幸いである。
二〇二〇年八月二八日 戌刻黄昏時
渡辺政隆
(図版は省略しました。pdfでご覧ください)

