あとがき、はしがき、はじめに、おわりに、解説などのページをご紹介します。気軽にページをめくる感覚で、ぜひ本の雰囲気を感じてください。目次などの概要は「書誌情報」からもご覧いただけます。
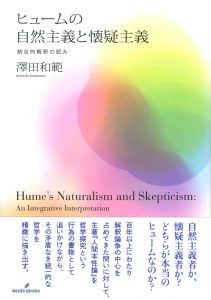 澤田和範 著
澤田和範 著
『ヒュームの自然主義と懐疑主義 統合的解釈の試み』
→〈「序」(pdfファイルへのリンク)〉
→〈目次・書誌情報・オンライン書店へのリンクはこちら〉
序
一八九三年、『人間知性研究』と『道徳原理研究』を収めた(かつての)標準的なテキストを編集したセルビー・ビッグは、それに「編者による序論」を付し、その冒頭で次のように述べた。
ヒュームの哲学的著作は多大な警戒心を持ちながら読まれなければならない。彼の書物の頁、とりわけ『人間本性論』の頁には、あまりにたくさんの内容が詰まっており、彼はあまりに多くの異なった事柄をあまりに多くの異なった仕方と異なった文脈で言っており、しかも彼は以前に言ったことにはあまりに無関心であるために、あれこれ特定の教説を彼が教えたとか教えなかったとか確信して言うことはきわめて難しいのである。[……]このために、ヒュームにはどんな哲学でも見つけ出すことが簡単にできるし、ある言明を別の言明にぶつけることによって、まったく何も見つけ出さないということも簡単にできるのである。(Selby-Bigge 1975, p. vii)
たしかに、ヒュームの著作に真剣に取り組んだことのある人なら、これと似たような感慨を少なくとも一度は抱いた経験を持つのではないだろうか。ヒュームという哲学者は、その正体を捕まえたと思ったら、次の瞬間にはまったく異なった姿で現れるように見える。ヒューム哲学と呼べるものなんて実際にあるのだろうか、と。
本書は、デイヴィッド・ヒュームが主著『人間本性論』(第一巻・第二巻は一七三九年、第三巻は一七四〇年に匿名出版)で展開した哲学を、全体として整合的な仕方で理解できるような解釈を提案することを目的とする。本書の解釈を提示する際とくに念頭にあるのは、ここ一世紀以上に渡ってヒューム哲学の解釈論争の中心であり続けてきた問題である。すなわち、ヒュームは、結局のところ、懐疑主義者だったのか自然主義者だったのか――。
研究者の間ではもはや周知のことだと思われるが、この論争の来歴を簡単に振り返っておこう。ヒュームの哲学は、基本的にはロックが『人間知性論』において創始した経験主義の理論枠組みに基づいている。ロック自身の観念説(theory of ideas)は、ボイルやニュートンの世界観を受け継いで微小粒子の離散集合からなる物質世界を想定したうえで、我々がその物質世界を我々の精神における観念を通じていかに認識できるのかという問題を解明しようとしたものである。しかし、ロックの観念説に懐疑主義へ通じる道を見て取った僧正のバークリは、神の存在を証明すると同時に、常識的な知識を確保するという神学的なモティベーションのもと、『人知原理論』を著す。そこでは、ロックが設けた「一次性質」と「二次性質」の区別は抽象観念を正しく理解すれば不可解なものとなるという議論によって、外界の物体の存在を否定する大胆な「物質否定論(immaterialism)」が展開された。こうして、いよいよヒュームが登場する準備が整ったのである。二十過ぎという若さで『人間本性論』を著したヒュームは、ロックの観念説に対するバークリの批判の多くを踏襲したが、同時にバークリの体系に理論的な不徹底を見る。バークリは、一方では彼がロックの物質から取り去った因果的力能を、他方では人間精神や神へと帰すことによって存続させてしまっているのである。しかし、因果性というものを正しく考察してみれば、物体に因果的力能を発見できないのと同様に、大小の精神にも因果的力能を見出すことはできない。それゆえ、ヒュームの体系においては、物体が消滅したのと同じように精神も消失し、後にはただ「知覚の集まり」だけが残される。
いま記述したような理解は、ヒューム哲学のある側面を切り取ったものとしては優れた解釈だと私には思われる。そして、これこそがヒュームの生前にスコットランド常識学派のトマス・リードが激しく糾弾した「懐疑主義者」ヒュームの姿である(Reid 2000[originally published 1764 ])。このような「懐疑主義」解釈は、二十世紀までほぼそのまま存続する。カントやヘーゲルの「ドイツ観念論」を学び、いわゆる「イギリス理想主義(British Idealism)」を最盛期に導いた哲学者T・H・グリーンは、一八八二年にヒュームの著作集を編纂した際に長い「序論」を著してヒューム哲学を攻撃したが、エアーが言うには、その内容は「トマス・リードのそれとほとんど変わるところがない」(Ayer 1970, p. 25)。ラッセルの『西洋哲学史』においても、経験論哲学はヒュームの懐疑論によって「袋小路(dead end)」へと至ったということになっている。「彼はロックとバークリの経験哲学をその論理的結論まで発展させ、それを自己矛盾しないものにすることによって、信じがたいものにした」(Russell 2004[originally published1946], p. 600)。このように長い間、ヒュームは非常に破壊的な哲学者だと見なされてきた。
しかし、ラッセルのこの言葉が出るより以前、すでにケンプ・スミスが、まず一九〇五年の「ヒュームの自然主義」という記念碑的論文(Smith 1905)で、そして、一九四一年の『デイヴィッド・ヒュームの哲学』(Smith 2005)という大著によって、たんに破壊的ではない独自の積極的な見解を持った哲学者として、まったく新しい魅力的なヒューム像を提示していた。ケンプ・スミスによれば、ハチスンらいわゆる道徳感情学派の教説を理論哲学の領域にまで敷衍し、「人間本性に関する純粋に自然主義的な理解を、理性の感情と本能への完全な従属によって打ち立てることが、ヒュームの哲学の決定的な要素である」(Smith 1905, p. 150)。人間の理性は情念と本能へ完全に従属するものであるという、この教説の真実性を鮮やかに提示するために、ヒュームは懐疑主義を活用したというのである。よく知られているように、ヒュームは「理性とは情念の奴隷であり、そうでなければならず、情念に奉仕し従うほかには何の役割を主張することもけっしてできない」(T 2.3.3.4)と主張している。ケンプ・スミスによれば、それまでの通念に反して、このフレーズは我々の価値判断だけに関するものではない。実際には、事実判断においても感情と本能とが理論理性に優越するのである。ヒュームが懐疑論を提示する意図は、むしろ、理性的懐疑によっては破壊されない「自然的信念(natural belief)」の存在を明らかにすることによって、理論理性に対する我々の実践の優位性を証明することにある。「自然的信念」とは、我々が自らの実践において前提とせざるを得ないような諸信念である。要するに、ケンプ・スミスによれば、ヒュームとは人間本性の事実を明らかにしようとした「自然主義者」にほかならない。
どちらが本当のヒュームなのか。「懐疑主義」解釈の擁護者たちは、「自然主義」解釈の説明はヒュームの懐疑論を無害なものとするには不十分だと反論してきた。それに対して、「自然主義」解釈の擁護者たちは、なぜヒュームが提示する懐疑論は本当の懐疑論ではないのか、あるいは、どのようにそれらの懐疑論がヒューム自身によって解消されるのかを説明しようとしてきた。ケンプ・スミスが二十世紀の初頭にその引き金を引いて勃発した論争は、それ以来一世紀以上に渡って、ヒューム解釈においては避けて通れない難題となったのである。
さて、この論争を考えるにあたって、我々は最初に引用したセルビー・ビッグの言葉が真実の一端を突いていることに注意しなければならない。実際、この論争がいつまでも絶え間なく継続してきた理由は、おもにヒュームの論述の独特の複雑さにあると思われる。セルビー・ビッグに倣って思い切って言ってしまえば、「自然主義」解釈も「懐疑主義」解釈も(あるいは他のさまざまな解釈も)、ヒュームの論述からそれぞれの解釈に有利な見かけ上の「証拠」をいくらでも取り出してくることができるのである。ただし、私ははっきりと言っておきたいのだが、それはヒュームの哲学が哲学探究という行為として叙述されていることを失念して、個々の議論の文脈を十分に踏まえることなく解釈できると思ってしまう場合に限られる。ヒューム自身は、「以前に言ったことにはあまりに無関心」で、あからさまに矛盾していることに平気だったわけではけっしてない。そう見えるとすれば、ヒュームの探究が次の段階に達していることを読者が見落としているのである。要するに、この論争は、ヒュームの議論の文脈を丁寧に解きほぐしていけば、決着をつけることが十分に可能である。
本書で提示される解答ははっきりしている。まず第一に、私はヒュームが自然主義者ではなかったと主張するつもりはまったくない。たしかに、ヒュームは「懐疑主義(scepticism)」という言葉は用いたが、「自然主義(naturalism)」という言葉は自らは用いなかった。しかし、ヒュームを自然主義者と呼び得る十分な理由は存在する。ただし、ヒュームの自然主義は、私が「人間本性主義」と「方法論的自然主義」と呼ぶものに区別して理解されたほうがよい。とりあえず簡単に説明すると、「人間本性主義」とは、そのように探究される対象は何よりもまず人間本性であるという主張である。もう一方の「方法論的自然主義」とは、『人間本性論』に「実験的推理法を精神の諸問題に導入する試み」という副題が付けられていることによって示唆されている考えのことであり、人間精神の働きを因果関係によって把握できる限りにおいて十全に解明しようという方法論のことである。
まず前者の「人間本性主義」についてもう少し言えば、よく知られているように、ヒュームは人間本性を探究する「人間の学(science of man)」を企てることによって、「論理学」、「道徳学」、「文芸批評」、および「政治学」は言うまでもなく、そうした人間についての学知を基礎として「数学」、「自然学」、果ては「自然宗教」にまで貢献できると宣言している(T intro. 4-5)。
それゆえ、ここに哲学探究において成功が期待できる唯一の方策があることになる。すなわち、これまで従ってきた退屈で捗らない方法を捨て、辺境の城塞や村落を一つ一つ占領する代わりに、諸学の首都であり中心である人間の自然本性そのものにまっすぐ進撃することである。人間本性をひとたび征服すれば、他のすべての土地で楽に勝利することが期待できる。[……]したがって、我々は人間本性の諸原理の解明を企てることで、じつはほとんどまったく新しい基礎のうえに、しかも諸学を安全に支え得る唯一の基礎のうえに、諸学の完全な体系を建てることを目論んでいるのである。(T intro. 6)
このように、デカルトが哲学の基礎を形而上学に置いたのとは異なり、ヒュームはそれを人間本性の学に置いている(Passmore 2013, p. 12)。ただし、ヒュームの自然主義を懐疑論との関係のみで捉えて、ヒュームは人間本性が懐疑論を論駁ないし解消するための基礎になると考えたのだ、と言って満足してしまってはならない。それは完全に間違いではないにしても、ヒュームの自然主義を矮小化してしまうことになる。(このように、ヒュームの自然主義の中心的意義が懐疑論の超克にあると捉える解釈は、本書を通して鉤括弧つきの「自然主義」解釈と表記しよう。反対に、ヒュームの懐疑論は「自然主義」によっては防ぐことができないと主張する解釈のことを、「懐疑主義」解釈と呼ぶことにしよう。)それに対して、人間本性主義という呼び名を与えて私が強調したいのは、どのような学問分野であっても人間本性についての経験的事実と矛盾した教説を立ててはならない、というヒュームの主張である。ヒュームの自然主義とは、何よりもまず、諸学の基礎を人間本性の解明を通して明らかにしようとする哲学の構想と見なされるべきなのである。
本書の主題である『人間本性論』という書物は、まず第一巻に人間の推論能力と諸観念の本性を明らかにする「論理学」が置かれ、やはり論理学の一部をなすとともに道徳感情説の基礎ともなる第二巻の情念論を挟んで、法学上の問題も含んだ広い意味での人間倫理を扱う「道徳学」が最後の第三巻に置かれている。しかし、すでに明らかなように、「人間の学」自体はそれよりもはるかに大規模な学問的構想である。ヒュームの「人間の学」とは、いわゆる哲学・倫理学に限定されるものではなく、後年の『道徳・政治・文学論集』や『イングランド史』などを含んだ、いわば人文社会総合学の構想であったと言うべきである。本書は『人間本性論』を集中的に分析するという方法を採用しており、その議論のほとんどは第一巻の内容が中心になるとはいえ、我々はこのことによく注意を払っておくべきであろう。
さて、以上がヒュームの人間本性主義についての最低限の説明であるが、他方で、すでに述べたように、本書ではヒュームの自然主義について「方法論的自然主義」という別の特徴づけも与える。よく知られているように、ヒュームの『人間本性論』の基本方針は、人間精神の働きをその原因と結果を特定することによって解明しようというものである。しかし、それだけではない。ヒュームは我々の因果推論の持つ規範性をその自然的起源から解き明かそうとする優れた洞察を示している。さらに、ヒュームは因果推論の基礎となる人間本性の諸原理を因果的に解明することによって、因果推論を基礎とする彼自身の自然主義的な探究の擁護を行っている。じつは因果推論による探究の基礎づけをその因果推論自体によって行うというこの循環にこそ、ヒュームの自然主義の核心があると言うべきであろう。このように、何よりも人間本性の探究の方法論に関して、ヒュームは近世の傑出した自然主義者なのである。本書の第Ⅰ部では、この方法論的自然主義に重点を置いて、ヒュームの自然主義の内実を具体的に描き出すことを目指す。
しかしながら、ヒュームが自然主義者であることは、彼が懐疑主義者でないことを含意するわけではない。近年の主流派である「自然主義」解釈は、ヒュームは懐疑主義者ではないと主張するにあたって、ヒュームの懐疑主義の源泉をその根底から誤解しているのである。この誤解が一世紀以上に渡って存続してきた最大の理由は、「自然主義」解釈がヒュームのさまざまな懐疑論を個別に検討することはあっても、その全体像を統一的に理解する視点を欠いていたことによると考えられる。そして、そのことによって、ヒュームの懐疑論のピュロン主義的性格を正しく理解することが妨げられてきたのであろう。(同時に、「懐疑主義」解釈の擁護者たちもこの点を十分に解明していないからこそ、これほどまでに「自然主義」解釈に対して優位を与えることになってしまっているのだと思われる。)したがって、ヒュームがどのような懐疑主義を展開しているのかを解明し、ヒュームをピュロン主義者として見定めることが、本書第Ⅱ部の主題となる。
要するに、ヒュームは懐疑主義者か自然主義者かという二者択一を迫るような主流のアプローチは、その論争の舞台設定そのものが究極的には間違っている。言い換えると、「自然主義」派にしても「懐疑主義」派にしても、ほとんどの解釈者たちが明示的ないし暗黙的に支持している想定が、すなわち、最終的には自然主義と懐疑主義の一方が他方に優越するはずだという想定が、そもそも誤りなのである。とはいえ、私がこれまでに蓄積されてきた研究から学んだことは数え切れない。いやむしろ、ヒューム研究の蓄積はあまりに莫大であるため、残念ながらそのすべてに通暁することは到底できない。何かしらの論点で参照すべきだった先達が私の目を逃れていることもきっとあるだろう。そのことは承知のうえで、しかし、いま私が自分のオリジナルだと信じる主張や議論は、思い切ってそのように提示することを断っておこう。ヒュームがそう教えるように、具体的な根拠のない疑いのために、あえて自ら卑屈になるべきではないだろうから。
いずれにしても、本書の最終的な結論をあらかじめ述べるならば、ヒューム哲学は、従来の解釈者たちが考えているよりも、より優れて自然主義的であり、しかも、徹底して懐疑主義的であるということになるであろう。これはたしかに逆説的な主張である。とりわけ次のようなことが問題となるはずである。すなわち、ヒュームは本当に、このような意味で懐疑主義者であったり、自然主義者であったりするものなのか。そして、もしそうだとしても、自然主義者としてのヒュームと、それに相容れないように見える懐疑主義者としてのヒュームは、いったいどのようにして両立的な関係を実現しているのか――。
本書の各章はこうした疑問に正面から答えようとしたものである。すでに述べたように、本書は第Ⅰ部「自然主義」と第Ⅱ部「懐疑主義」とに大きく分かれる。第一章から第三章までの第Ⅰ部では、ヒューム哲学における自然主義を、これまで比較的論じられてこなかった方法論に注目して描き出すことが目指される。それに対して、第四章と第五章からなる第Ⅱ部では、ヒューム哲学の懐疑主義的展開に焦点を合わせて、第Ⅰ部で確認された自然主義的方法論との分かち難い関係を見定めることが目指される。各章の概要は以下のとおりである。
第一章 「必然的結合」と因果推論
本章では、ヒュームの哲学探究の前提となる理論的枠組みを説明すると同時に、彼の探究の基礎となる因果論の内容を明らかにすることを目的とする。とくに問題となるのは因果推論の基礎と言われる「必然的結合」についての議論の解釈であるが、私は「必然的結合」の観念は、逆説的にも、原因と結果のあいだの必然的結合についての内容を含まないという「非表象説」解釈を擁護する。また、ヒュームの有名な「原因の二つの定義」を二つの推論方法を記述していると解釈し、以降の議論のために反省的な因果推論の重要性に注目する。
第二章 「一般規則」の発生論的解釈
本章では、ヒュームの因果推論の規則として注目を集める「一般規則」について、発生論という観点から、まったく新しい独自の解釈を与える。一般規則についてヒュームが考えていたのは、じつは従来の諸解釈が提案してきたような認識的正当化の問題ではなく、その規範性の起源と発生に関する自然主義的な説明である。ヒュームが一般規則を正当化する超越的な基準の存在を否定し、きわめて現代的と言い得る自然主義的な発想を展開していることを明らかにする。
第三章 情念論における「実験的推理法」
ヒュームの掲げる「実験的推理法」は実際にはまったく実質がないとしばしば批判されてきた。本章では、ヒュームが実際に行っている「実験」のパラダイム・ケースとして、第二巻の一節を取り上げ、その当時影響力を持ったニュートンの『光学』における「分析と総合の方法」と比較することを通じて、こうした批判を再批判する。私はヒュームの方法を仮説演繹法の一種と特徴づけることになるが、その眼目は実験的推理法における仮説と反証の地位を適切に理解することにある。
第四章 懐疑と自然
本章では、ヒュームの提出したいくつかの懐疑論から、よく知られた「理性に関する懐疑論」と「感覚能力に関する懐疑論」という重要な二つの議論を検討する。この二つはかなり異なった議論に見えるが、「方法論的自然主義」と「人間本性主義」という二つの観点から分析してみれば、かなりパラレルな議論の構造を持っていることが判明する。こうした分析によって、ヒュームの懐疑論においても自然主義が通底していることを論じる。
第五章 ピュロン主義的メタ哲学
ヒュームは、第一巻の「結論」において、これまでの探究を振り返って、哲学探究それ自体への懐疑と、それにもかかわらず哲学探究を再開しようという心情を語る。本章の目標は、これにたんに文献学的ではない理論的な解釈を与えることである。「自然主義」解釈の擁護者たちは、この「哲学探究に関する懐疑論」が、いわばヒュームの「懐疑的」諸議論を総合した「統一的懐疑論」であるということを見逃してきた。一方で、「懐疑主義」解釈の側も、ヒュームの「哲学探究に関する懐疑論」のピュロン主義的性格を誤解し、しばしばヒュームを悲観主義者にしてしまう。こうした誤解を解くことによって、ヒュームの自然主義的哲学とピュロン主義的懐疑主義との関係を一貫したものとして捉え直すことを目指す。
まとめると、第Ⅰ部は、ヒュームの方法論的自然主義について、いわばその基礎(第一章)、展開(第二章)、応用(第三章)を論じるものである。第Ⅱ部は、ヒュームの懐疑主義を第Ⅰ部で描かれた方法論的自然主義と連続的なものと捉えたうえで(第四章)、それらがヒュームの最終的な立場としてどのように矛盾なく統合されるのかという問題に答える(第五章)という筋書きとなる。これが本書の全体像である。
さて、最後に本書を読む際の注意を一つだけ述べておきたい。私は現時点で自分が理解したと信じるヒュームの哲学の展開を、できるだけ分かりやすく物語ることを最優先した。そのため、先行研究との比較検討や関連する論点の説明など専門的には重要であっても、本題の筋を追うのに必ずしも必要ではない議論の多くを、本書では註釈にまわすことにした。そうした詳細を吟味しようという読者には、少し煩雑で申し訳ないが、関連する註釈まで覗いていただくようにお願いする次第である。
(傍点と注は割愛しました)

