あとがき、はしがき、はじめに、おわりに、解説などのページをご紹介します。気軽にページをめくる感覚で、ぜひ本の雰囲気を感じてください。目次などの概要は「書誌情報」からもご覧いただけます。
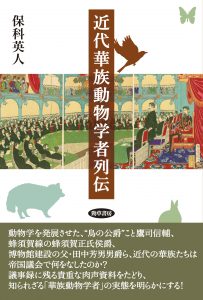 保科英人 著
保科英人 著
『近代華族動物学者列伝』
→〈「目次」「序章 華族と華族動物学者たち」(pdfファイルへのリンク)〉
→〈目次・書誌情報・オンライン書店へのリンクはこちら〉
*サンプル画像はクリックで拡大します。序章の本文はサンプル画像の下に続いています。
本書『近代華族動物学者列伝』で描くのは、華族と呼ばれる特権的な家々に生まれた動物学者たちの生き様である。そして、本書を列伝形式にしたのには意味がある。筆者は史伝作家の海音寺潮五郎のファンで、なかでも愛読したのが『武将列伝』『悪人列伝』である。また、新保良明『ローマ帝国愚帝列伝』も著者の筆致が軽快であるうえに、またローマ帝国には愚帝の登場が相次ぐ素因がもともとあったことが、わかりやすく解説されている。一冊の本全体で、単独の人物を描き切る専門書は、概して敷居が高い。そこで筆者は、華族動物学者たちの生涯は、章ごとに主役が入れ替わる列伝形式で描く方がなじみやすいと考えた。第一章以降、この列伝形式で華族動物学者たちを取り上げていく。その前に、序章ではそもそも華族とは何か、また華族動物学者はなぜ帝国議会にも籍を置いていたかなどを解説しよう。
●1――華族制度と華族学者たち
榎本武揚率いる旧幕府軍が函館で降伏した翌月の明治二(一八六九)年六月、「公卿諸侯之称廃せられ、改て華族と称すべし」との行政官達第五四三号で、公家と諸侯(藩主)をあわせた華族という貴族集団が設定された。明治二年の時点では、公家や諸侯は「華族」との一括りでしかなかった。その後、政府内の種々の議論を経て明治一七(一八八四)年七月に制定されたのが華族令である。この華族令によって、公、侯、伯、子、男爵の五種の爵位およびその序列、華族の特権や義務が規定され、近代華族制度が整った。そして、華族たちは祖国が大東亜戦争に敗れた後、日本国憲法が施行された昭和二二(一九四七)年五月三日のその日まで、その地位と特権を保持し続けた。
明治維新後、旧公家や大名、そして維新の勲功によって爵位を得た華族の子息たちは、公務(陸海軍人や官吏)、銀行業、交通業などさまざまな分野の職種に就いたが、そのうちの一つの分野が博物学である。研究に没頭できる時間と経済力を持ち、また専門書に触れる機会に恵まれた華族が、いわば趣味的な学問の博物学の世界に雄飛したのはある意味当然だ(注①)。山階鳥類研究所を設立した山階芳麿侯爵(一九〇〇―一九八九)や、〝鳥の公爵〟と称された鷹司信輔公爵(一八八九―一九五九)、黒田長禮侯爵(一八八九―一九七八)、生物地理学の蜂須賀線に名を残す蜂須賀正氏侯爵(一九〇三―一九五三)などの鳥類学者たちがその代表といえる。一方で、これら錚々たる鳥類学者たちから知名度は大きく落ちるが、昆虫学者(博物学者)の高千穂宣麿男爵(一八六四―一九五〇)や応用昆虫学者の中川久知(一八五九―一九二一)、蝶類学者の仁禮景雄(一八八四―一九二六)なども華族動物学者である。
ここで小田部雄次『華族』を参考にして、華族制度について簡単に紹介しておこう。爵位所持者と華族はイコールではない。爵位はその家の戸主だけが持つ。一方、華族とは爵位を持つ戸主と、その同一戸籍の家族全体を指す。ようするに、爵位を持つ家の当主に加え、配偶者や子女全員が華族だが、戸主の次男や三男が分家したり、娘が平民の家に嫁に行ったりすると、その時点で華族ではなくなる。前述の中川久知や仁禮景雄は華族動物学者の一例として挙げているが、二人はそれぞれ次男坊と四男坊なので、中川伯爵家と仁禮子爵家を継ぐことはなく、終生爵位を持つことはなかった。また、両名は若くして実家から分家したので、平民として生涯を終えている(注②)。
●2――爵位と経済力
明治一七(一八八四)年、旧公卿や諸侯への爵位は明治以前の家格や石高などを基準にした叙爵内規に従って、各家に授けられた。爵位決定はこの叙爵内規が厳格に適用された。よって、戊辰戦争で賊軍となった藩主は低い爵位しか与えられなかったというのは俗説にすぎない。叙爵内規の詳細については、浅見雅男『華族誕生』をご参照いただきたい。この内規に従った結果、旧公卿の場合、五摂家は公爵、太政大臣になれる家格の清華家は侯爵、内大臣や大納言を極官とする大臣家等は伯爵となった。一方、旧大名の場合は、徳川宗家と、維新に絶大な功があった島津・毛利両家が公爵、徳川御三家や現米一五万石以上の大藩が侯爵、旧御三卿や現米一五万石未満の中藩が伯爵、現米五万石未満の小藩が子爵に振り分けられた。極端に単純にいうと、江戸期の藩の石高で旧藩主のおおよその爵位が決まった。無論、旧領の大きさだけで単純に爵位が決められたのではない。たとえば、仙台伊達家と越前松平家は、江戸期はそれぞれ六二万石と三二万石の国持大名であったにもかかわらず、授けられた爵位はともに伯爵である(越前松平家は維新の功によって、のちに侯爵に陞爵した)(注③)。それはさておき、本書で取り上げる鷹司信輔は旧五摂家出身なので公爵、黒田長禮と蜂須賀正氏は、それぞれ五〇万石および二五万石の旧大名家なので侯爵というわけである。
旧公家・大名以外では、維新で活躍した旧藩士の志士たちも授爵した。また、全国の大神社の中から神職一四家が男爵の爵位を授けられた。第六章の博物学者高千穂宣麿は、この神職華族の一員である。さらに、明治以降、西南戦争、日清・日露両戦役で軍功を立てた軍人や、外交や内政で顕著な功績をあげたものも順次、華族に列せられていった。仁禮景雄の父・景範は西南戦争等の功績によって子爵となった海軍軍人である。また、本書第七章の田中芳男は、長年の官僚および貴族院議員としての業績によって、死去半年前に男爵となった。いわば本人の実力で爵位を勝ち取った点で、家柄だけで華族となっていた黒田や高千穂らとは事情がまったく異なる。
細かい爵位の話はさておき、華族の経済力についても見てみよう。近代日本の華族はおおよそ欧州の貴族に該当するが、華族の皆が皆金持ちではない。たとえば、奈良興福寺の僧職で、明治以降還俗して華族に列せられた二六家を奈良華族と呼ぶが、経済的に苦しかったいくつかの家は後に爵位を返上してしまった。華族としての体面を保つ資産がない、というのが理由である。
明治以降、華族たちは起業や投資によって資産形成に励んだ。もちろん、蓄財がうまくいくかどうかは運と力量次第である。蜂須賀侯爵家のように北海道に日本有数の大農場を経営できたところもあるが、仁禮子爵家は農場および塩田経営に失敗してしまった(第八章)。
旧諸侯の武家華族は概して経済的に恵まれていた。旧石高が五万石以上の武家華族は、第十五国立銀行に預金した禄券額の利子だけで生活できたので、無職の者も少なくなかった(刑部『三条実美』)。そして、明治以前の石高の大きさが維新以後の彼らの経済力を測る目安となる。さらに、江戸期の石高と爵位はほぼ直結しているのだから、ざっくばらんに言うと爵位の差は経済力の差でもある。鳥類学者で黒田長禮と蜂須賀正氏の両侯爵が世界のあちこちを回り、鳥類の剥製標本をかき集められたのは、一にも二にも彼らが旧大大名の侯爵で、自在に使えるカネを潤沢に持っていたからである。一方、同じ華族動物学者であるにもかかわらず、高千穂宣麿の採集旅行の行き先がせいぜい琉球に留まったのは、彼が神職の男爵であり、常にカネに困っていたからである。また、蝶類学者の仁禮景雄は南米と欧州を巡る機会があったが、仁禮は雑誌記者としての仕事で海外渡航したにすぎない。実家の仁禮子爵家の資産に頼った渡欧ではない。実際、彼の南米と欧州滞在が、後の研究成果に生かされることはなかった。雑誌記者として渡欧している以上、仁禮は現地で虫捕り網をふるってばかりはいられなかったのである。海外で自由気ままに鳥を追えた黒田や蜂須賀とは事情が大きく異なる。
爵位の違いが生み出す経済力の著しい格差。このカネの有無が、華族動物学者の研究対象の選択に大きく影響した、というのが筆者の仮説であり、本書の大きなテーマの一つでもある。これについては、本書末の終章で総括することにしよう。
●3――帝国議会議員の華族動物学者たち
ここで本書にて取り上げる華族動物学者たちを専門分野とともに爵位順に列記してみよう。
(1)鷹司信輔公爵、鳥類学。
(2)黒田長禮侯爵、鳥類学。
(3)蜂須賀正氏侯爵、鳥類学。
(4)三島弥太郎子爵、昆虫学。
(5)高千穂宣麿男爵、博物学(昆虫学)。
(6)田中芳男男爵、博物学。
(7)中川久知、応用昆虫学。
(8)仁禮景雄、昆虫学(蝶類学)。
(9)名和靖(平民)、昆虫学。
本章1節で述べたように、中川と仁禮は華族家の生まれではあるが、爵位はない。また、(9)の名和靖は平民なので、本来なら『近代華族動物学者列伝』に掲載される資格のない、いわば番外者である。しかし、彼が設立した私立の昆虫研究所が、華族動物学者たちの強力な支援を受けていたことが明らかになっている。華族学者がどのような形で名和を援助していたかを明らかにするうえで、あえて名和を本書で取り上げた次第である。
これら九名の学者のうち、有爵位者の上位六名はいずれも貴族院議員である。また、七番目の中川久知は衆議院議員を一期務めた。つまり、全九名のうち七名は、今風にいうと国会議員経験者である。
現在の国会議員は、議員になりたい人が必死に選挙活動をした後になれる職業だ。衆議院の選挙制度については、戦前の帝国議会と戦後の国会で似通る部分は多い。中川久知は現在の与野党代議士のごとく、涙ぐましい選挙活動によって、ようやくその地位を得た(第四章)。一方で、帝国議会の貴族院は、議員の選出方法が戦後の衆議院と参議院とはまったく違う。そして、その独特な選出方法は、鷹司や蜂須賀、黒田などの議員活動に大きく影響を与えているので紹介しておく。明治二二(一八八九)年二月公布の貴族院令によれば、以下の議員でもって貴族院を構成すると定められた。
(1)皇族(ただし成年男子のみ)
(2)満二五歳以上の公爵と侯爵
(3)満二五歳以上の伯爵・子爵・男爵から互選で選ばれたもの。任期七年
(4)満三〇歳以上男子で、国家に勲労がある、または学識があるものから勅任されたもの
(5)各府県で満三〇歳以上の男子の多額納税者から互選で選ばれたもの。任期七年
爵位は男性しか持てないので、必然的に(1)から(5)まですべてが男性となる。衆議院も含め戦前日本には女性国会議員がいなかったのは周知のとおりだ。本書で扱う鷹司、黒田、蜂須賀、三島、高千穂、田中の六人の貴族院議員のうち、鷹司、黒田、蜂須賀は公侯爵家の生まれだから、二五歳以上になり、かつ親から爵位を受け継いだ時点で、自動的に世襲の貴族院議員になった。本書では取り上げなかった鳥類学者の山階芳麿の爵位は侯爵なので、彼もまた貴族院議員である。もっとも、公侯爵議員は議員歳費をもらえなかったので(内藤『貴族院』)、彼らは議員になれるというよりは、義務として議員をさせられると表現した方が正しい。この三人の議員活動が概して低調だったのも推して知るべしである。
次に三島子爵と高千穂男爵は、選挙で勝たなければ議員になれない。貴族院に解散はないので選挙は七年ごとに行われるのが原則である。ただし、議員の死去等で欠員が生じると任期途中でも補欠選挙が実施されることもあった。なお、伯子男爵の議員選挙は同爵位者のなかでの互選なので、爵位が異なる三島と高千穂が票を争うとの事態が生じる余地はない。伯子男爵議員選挙はあくまで互選が建前なので、立候補した人間が昇りを立てて自分の名前を街頭で連呼する方式ではない。形式としては小中学校のクラス委員長の選出のようなイメージである。ただ、しょせんそこは政治の世界。選挙が近づくと、議員ポストをめぐって、虚々実々の駆け引きがあった。伯子男爵議員は高い給料がもらえるからである。そこで、議員になりたい華族は同じ爵位を持つ有力者宅を訪ね、「次の選挙では、なにとぞ拙者をよろしく」と頼み込んだ(注④)。財政基盤が弱く、議員歳費が喉から手が出るほど欲しい子男爵華族は、死に物狂いで運動したはずである。三島弥太郎は子爵の実力者だったから、選挙のたびに気を揉む必要はなかっただろうが、政界の有力者ではなかった高千穂は違う。この人は議員になりたくてなりたくて、必死に運動し、ようやく議員ポストをつかんだ。そのあたりの経緯については、第六章で述べることとしよう。
一方、田中芳男(第七章)は高千穂と同じ男爵であるが、男爵華族のなかから選ばれた議員ではなく、(4)の終身の勅選議員に該当する。よって、田中は七年ごとの選挙に杞憂することなく、議員活動に打ち込むことができた。
●4――華族履歴と参議院所蔵の議員履歴書
華族たちの生涯を知る一つの重要資料が『華族履歴』である。『華族履歴』とは、宮内庁書陵部が所蔵する資料の一群で、文字どおり華族個人の履歴書が収録された文書である。その記載項目は既刊の『昭和新修華族家系大成』『平成新修旧華族家系大成』の旧華族名簿資料にも利用されているが、履歴書の原文自体は未刊行のままだ。各華族の履歴書の中身は、書式がまったく統一されていない。たとえば、福井藩士の堤正誼男爵(維新後は宮内官僚)の履歴書には幕末の元治元(一八六四)年禁門の変で敵を一人討ち取った、との個人的武者働きにまで言及されている一方で、同じく福井藩出身の医師の岩佐純男爵の履歴には生年以外の明治維新前の項目が一切ないのである(拙文「福井藩医師岩佐純及び橋本綱常履歴書」)。また、鷹司信輔の履歴書は華族制度が消滅した昭和二二(一九四七)年で途切れているのに対して、高千穂宣麿は昭和二五(一九五〇)年に死去したことがちゃんと記されている。なぜ高千穂については、華族制度がなくなって以降も、『華族履歴』に死去の項目が書き加えられたのか、その点は不明だ。何はともあれ、華族学者たちの生涯を知るうえで、彼らの履歴書は重要資料である。また、『華族履歴』は彼らの職歴だけでなく、「年俸〇円」など、彼らがもらったカネの動きが一部読み取れる点も大変ありがたい。
貴族院に籍を置いた華族学者の別の履歴書として、現在の参議院が所蔵している『貴族院議員履歴書』がある。現物を見せてもらうことはできないので、参議院事務局に「誰それの履歴書を見たい」と申し込む。すると、後日事務局で翻刻されたものが送付されてくるとの手順を踏む。『貴族院議員履歴書』は、記載項目が貴族院議員になっている時期に限定されていることが多く、内容そのものは『華族履歴』と比べると少ない。しかし、『華族履歴』未記載の項目も若干見受けられるので、調べるにこしたことはない。なお、筆者の問い合わせに対し、現在の衆議院事務局からは「衆議院は戦前の衆議院議員の履歴書を保管せず」との回答があったことを付け加えておく。
●5――帝国議会議事録から読み取れるもの:憲政史上初の乱闘議会を例にして
本書は、九人の動物学者を取り上げるが、科学史視点で彼らの研究業績の再評価を試みるのは主な目的ではない。前述のように九人の学者のうち、七人は帝国議会議員である。そこで、議会議事録から帝国議会の本議会や委員会の場で彼らが何を語ったのかを明らかにしようというのが一番大きな狙いだ。では、なぜ筆者は議会議事録にこだわるのか? それは、議事録が彼らの貴重な肉声資料だからである。
議会議事録が当時の議員たちの発言、そして下らないヤジまでもいかに正確に記録しているか。ここで、明治三八(一九〇五)年一二月開会の第二二回帝国議会を例にとってみよう。この議会で可決された法案の一つが鉄道国有化法案であるが、進歩党を中心として反対意見が根強く、議場は大混乱に陥った。翌明治三九年三月一六日、国有化法案は衆議院で可決されたのち、審議は貴族院に移った。そこで、大幅な修正が行われた後、修正案が同月二七日に可決された。同日は議会最終日だったので、ただちに貴族院の修正案が衆議院に回付され、再審議となったが、ここでも反対の怒号が乱れ飛んだ。ここで同法案の特別委員会委員長で、与党・立憲政友会の長谷場純孝が「もはや議論はすでに尽きている。よって、討論を省略し、直ちに採決すべし」との緊急動議を提出すると、反対派の怒りは最高潮に達した。ここに、日本憲政史上初の乱闘が勃発することとなる(老川『日本鉄道史』)。長谷場が動議を提出した直後からの様子を、議事録から再現してみよう。
与野党の間で長谷場の緊急動議に対して「賛成賛成!」「そんな不当なことはない!」との怒号の応酬となった。議事録はその様子を「議論喧囂ヲ極ム」と形容する。衆議院議長で立憲政友会の杉田定一が「静かに願います」と何度もたしなめるも、議場はまったく鎮まる気配がない。まずは長谷場提出の緊急動議の採決となり、賛成起立者多数で可決となったが、反対派は「異議あり異議あり!」と叫び続ける。対して長谷場は「議長の命に従わぬものは退場を命ぜられたい」と反対派の野党側を挑発する。この騒然としたなか、森本駿議員が「議場において腕力を用いることは許されない! 議長の命に従わない奴は誰だ!」とヤジを飛ばした。議事録の森本の発言から、この時点で議場がすでに暴力沙汰になっていることが読み取れる。反対派の福井三郎議員は「今の採決は不当だ!」と大声をあげるが、与党側も「議長の命令に従え!」とやり返す。この後も議事録には「議場騒然」との単語が何度も綴られている。結局、鉄道国有化法案の修正案は、この日の衆議院で賛成多数で可決された。
なお、同月二八日付東京朝日新聞、東京二六新聞、都新聞、萬朝報などの諸新聞の記事から補足すると、長谷場提出の緊急動議の採決直後に法案反対派の複数の議員が怒って杉田議長を取り囲んだ。当然、与党側の議員は自派の議長を守るために駆けつけたので、議長前席の演壇で与野党議員間の大格闘が始まってしまったのである。この事態に多数の守衛が出動して、この騒動を取り鎮め、杉田議長は何とか緊急動議の可決を宣言することができた。
これが日本憲政史上初の乱闘議会の顛末である。もはやコントの域に達しているといえよう。議場がここまで大混乱に陥った理由は、もちろん鉄道国有化法案は賛否が激しくぶつかる案件だったからだが、もう一つは杉田定一議長の議会運営の手腕が稚拙だったからである。杉田は福井市の豪農出身で自由民権運動たたき上げの政治家だ。彼は地元では今や大変な英雄となっているが、その業績に対して過大評価があることは否めない。杉田は議長として失敗したこと一度ならず、加えて声が小さいとの致命的弱点を持っていた(拙文「新聞報道から見た政党政治家杉田定一」)。彼は平時ならばいざ知らず、乱闘国会を鎮めるには、あまりにも不向きな議長だったのである。
何はともあれ、帝国議会議事録が当時の議員たちの肉声や振る舞いをいかに詳細に記録しているかがお判りいただけたかと思う。
●6――華族動物学者議員は帝国議会で何を語ったのか?
このように、議会議事録は議場における真剣な討論だけでなく、どうしようもないヤジの類まで漏らさず記録している。つまり、登壇した帝国議会議員が、個々の法案にいかなる見解を述べたか、後世の我々にすべて筒抜けだ。議員の個人史に重きをおく著作を書きたいなら、議会議事録は彼らの肉声を録音した、まさに宝の山である。
にもかかわらず、華族動物学者議員たちの帝国議会における言動に対して、これまで焦点がまったく当てられなかったのは不可解というほかない。たとえば、村上紀史郎氏の蜂須賀正氏の伝記『絶滅鳥ドードーを追い求めた男』がある。蜂須賀の伝記としては最も詳細な力作であるが、蜂須賀が貴族院議員になったとの事実は記すものの、彼の議員活動に関する著述はほぼゼロである。また、「博物館建設の父」として知られる田中芳男も、膨大な関連研究論文がある。にもかかわらず、田中がいかなる議員活動をしていたか、となると明治二三(一八九〇)年の博物館設立の建議案の発議者になったこと以外、誰も文章にしてこなかった。筆者は「せっかく議会の議事録が残っているのに、これでは宝の持ち腐れではないか」と痛感し、五年ほど前から華族動物学者の議会における発言を拾ってきた。高千穂宣麿、中川久知、鷹司信輔、田中芳男の四名については、すでにその成果を発表済みである。そして、本書では新たに蜂須賀正氏、黒田長禮、三島弥太郎の三名についても、議会における発言の発掘を試みる。
結論から言えば、華族動物学者の多くは、帝国議会の本議会の場では概して口が重かった。彼らはシャイだからなのか奥ゆかしいからのか、何百人もの同僚の前で堂々と演説するのは不得手だったようだ。高千穂宣麿、中川久知、蜂須賀正氏にいたっては、本議会における発言はゼロである。しかし、より少人数の委員会になると話は別だ。本議会では口をへの字に結んでいた高千穂であったが、委員会の場では卓見をしばしば披露している。帝国議会の各委員会についても議事録はおおよそ残されているので、それらもまた彼らの肉声資料である。
とくに筆者が着目したのは請願委員会の議事録である。ここで請願委員会とは何かを簡単に解説しておこう。請願は大日本帝国憲法で保障された権利である。請願書は紹介議員を通じて提出され、請願委員長が規定に合するかどうかを確認した後、議長名で受理する。受理された請願は、委員長名で請願文書表を作成し、議長から全議員に配布される。そして、請願委員会で審査された後、採択すべきか否かを議決する。採択されれば本会議で特別報告がなされ、ここでも採択が議決されれば、意見書を付けて政府に送付される、との手続きを踏んだ(小林『明治立憲政治と貴族院』)。もっとも請願が可決されたとしても、その実行を政府に強制できはしないが、帝国議会に議席を持たない一般国民でも実行できる議会への直訴制度として機能したのである。
では、当時の帝国臣民はいかなる陳情を請願委員会に持ち込んだのか。具体的には、自分たちの村に郵便局や神社を作れとか、故郷の山々を国立公園に編入してほしいとか、国立研究機関の地方支部の建設を求める、といった内容のものである。請願の内容はきわめて雑多だ。それゆえに、請願委員会における各委員の発言から、国の研究体制や国立公園の在り方などなど、さまざまな課題について彼らがどう考えていたかを読み取れるのである。
個別の法案を審議する特別委員会では、中身の本質的な議論に加え、どうしても法案の文言の修正といった地味な審議が繰り返される。無論、法治国家として適切な文言の選択は大事なことなのであるが、審議過程を追跡しても面白くも何ともないことが多い。一方、請願委員会では、臣民の陳情の採否を審議するので、この時点では細かい文言修正は行われない。委員会ではその陳情の採択が適切か否か、時として委員同士の意見のぶつかり合いの場となる。しかも、委員会では同日に多数の案件が扱われるので、「はい、次はこれ」「はい、終わりました。では、次に行きましょう」といった感じで、スピーディーに審議が進む。個々の請願案件に対する議員の発言から、彼らの発想が読み取れて、非常に面白いのである。
筆者にとって、華族動物学者の議員活動が現実の法案や議会政治に与えた影響は、はっきりいってどうでもよい。彼らが成立に邁進した法案が最終的に可決されたかどうかも重要ではない。そもそも、三島弥太郎を除くと、華族動物学者たちの乏しい政治力では、政局に寄与することは土台無理な話であった。本書では、華族動物学者議員の議会での発言、とくに生き物や研究施設が絡む法案や請願への彼らの発言から、彼らの動物学への理念や問題認識を明らかにしたい。取り上げるのは、彼らの頭のなかの思考そのものである。では、次章より彼らの議員活動を中心とした生涯を振り返ってみることにしよう。






