あとがき、はしがき、はじめに、おわりに、解説などのページをご紹介します。気軽にページをめくる感覚で、ぜひ本の雰囲気を感じてください。目次などの概要は「書誌情報」からもご覧いただけます。
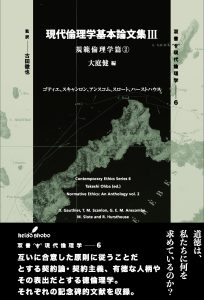 大庭健 編
大庭健 編
古田徹也 監訳
『現代倫理学基本論文集Ⅲ 規範倫理学篇②』
→〈「監訳者まえがき」「監訳者解説(抜粋)」(pdfファイルへのリンク)〉
→〈目次・書誌情報・オンライン書店へのリンクはこちら〉
*大庭健編、古田徹也監訳『現代倫理学基本論文集Ⅱ 規範倫理学篇①』のたちよみはこちら→〈「監訳者解説(冒頭)」〉
*サンプル画像はクリックで拡大します。「監訳者まえがき」「監訳者解説(抜粋)」はサンプル画像の下に続いています。
監訳者まえがき
〈双書現代倫理学〉シリーズの一環として編まれたこの『現代倫理学基本論文集』全三巻は、二〇世紀半ば以降の英米圏における倫理学の展開を追う上で、まずおさえておくべき重要文献を集成したアンソロジーである。
第Ⅰ巻はメタ倫理学、第Ⅱ巻および第Ⅲ巻は規範倫理学の分野において、それぞれ画期的な主題や問い
を提示した記念碑的文献を採録している。(そのため、論文集と銘打ってはいるが、文献の重要度などに鑑み、制度化された狭義の論文だけではなく、著書からの抜粋を採録している場合もある。また、現代倫理学に巨大な足跡を残しているデイヴィッド・ウィギンズ、ジョン・マクダウェル、サイモン・ブラックバーン、バーナード・ウィリアムズの著作に関しては、〈双書現代倫理学〉シリーズ内において個々に単独の巻を刊行しているため、今回の『現代倫理学基本論文集』には採録していない。)
そのうち、ここに他巻に先駆けて上梓する第Ⅲ巻は、契約論および契約主義、そして徳倫理学に関する主要な文献を収めている。
本巻に入っている各文献の概要や位置づけなどに関しては、監訳者解説をお読みいただきたい。ここでは、この三巻本が成立した経緯を簡単に説明する。
勁草書房編集部が大庭健さん――生前の御本人の意向を尊重し、敢えて「先生」とは呼ばない――に論文集の編纂を打診したのは、十年以上前の二〇一〇年に遡る。メタ倫理学と規範倫理学の分野でそれぞれ一巻ずつ刊行する企画が立てられ、二〇一二年初頭には収録文献が確定し、訳者の選定も大庭さんの構想に沿って進められた。
しかしそれ以降、大庭さんは体調を崩され、監訳の作業を開始することができず、企画は事実上中断することとなった。病状が悪化するなか、大庭さんは監訳の作業を奥田と古田に託した後、惜しくも二〇一八年一〇月に逝去された。
その後、奥田と古田の両名ならびに勁草書房編集部の土井美智子氏が三人で協議を重ねながら、企画の再起動と再検討を行った。特に、規範倫理学の文献に関しては訳稿の分量が嵩んだため、当初の予定を変更して二分冊で刊行する判断を下した。その結果、〈第Ⅰ巻 メタ倫理学篇〉、〈第Ⅱ巻 規範倫理学篇①〉、〈第Ⅲ巻 規範倫理学篇②〉という三巻本のかたちに最終的に落ち着いた。
また、企画の立ち上げからすでに相当の時間が経過していることを考慮し、刊行までのスピードアップを図るために、第Ⅰ巻の監訳作業は奥田が、第Ⅱ巻と第Ⅲ巻の監訳作業は古田が、それぞれ単独で行う体制に変更した。(とはいえ、企画全体の進行は、奥田・古田・土井のチームで終始協力して担ってきたことは、ここに記録しておきたい。)
二〇二〇年にはすべての巻の訳稿が揃い、それと前後して、訳者同士での相互チェックや、専門家による外部チェック、監訳者によるチェックなどを繰り返し、訳稿をブラッシュアップしてきた。思いもかけずかなり長い道のりとなったが、いまようやく、第Ⅲ巻の刊行に漕ぎ着けることができた。今後も随時、第Ⅱ巻、第Ⅰ巻の順に刊行が続く予定である。
この『現代倫理学基本論文集』全三巻に収録されているのはどれも、大庭健という、九〇年代以降日本の倫理学界を牽引してきた碩学が厳選した必読の文献であり、その選定自体に、彼が捉えてきた倫理学の風景が映し出されている。
大庭さんは常に、次の世代によって本格的な哲学的倫理学の議論が新たに展開されることを願ってきた。今回の訳業がそのひとつの礎を与えうるのだとすれば、監訳者としてこれ以上の喜びはない。
奥田太郎
古田徹也
監訳者解説(古田徹也)
(前略)
第II部 徳倫理学、またはその先駆
《3》第三章 G・E・M・アンスコム「現代道徳哲学」(一九五八年)
現代倫理学を代表する論攷のひとつ
G・E・M・アンスコムは、ウィトゲンシュタインの高弟であり、彼の遺稿の管理人および英訳者としても知られているが、いまやそれ以上に、現代の英語圏を代表する哲学者のひとりという評価が確立している。なかでも、本書で取り上げるアンスコムの論文「現代道徳哲学」は、倫理学の分野における彼女の仕事のなかで最も著名なものだと言えるだろう。実際、本論文は、現代において徳倫理学の復興を準備したとも言われる画期的な仕事である。(なお、現代の徳倫理学の特徴については、後のマイケル・スロート「行為者基底的な徳倫理学」の解説において触れる。)
本論文の主張は、次の三つに大別される。
- 現時点ではわれわれはまだ、意図や動機、あるいは性格といった、心理にまつわる適切な哲学を手にしていない。それを手にするまでは、道徳哲学を研究することは有益ではない。
- 道徳的な意味での「義務」や「正しさ」、「べき」といった概念は、倫理を神の法という観点から理解する昔の(ユダヤ教やキリスト教などの)捉え方を前提にするものであり、この種の捉え方なしでは上記の諸概念は意味を成さない。それゆえ、もはやこの種の捉え方を共有していない現代のわれわれは、上記の諸概念を放棄するべきである。
- シジウィック以降、今日に至るまでのイギリスの諸々の道徳哲学の間に見られる違いに重要なところはない。言い換えれば、それらは皆、帰結主義であるという点で共通しており、共通の根本的な問題を抱えている。
アンスコムはこれら三つの過激なテーゼを、行きつ戻りつ、かなり錯綜した仕方で示している。それが、この論文に「難解」という悪名がついてまわるゆえんでもある。一読しただけではほとんどの人がその内容を消化できないだろう。それゆえ以下では、論文の構成を適宜組み替えたり例を改変したりしつつ、他の論攷の解説よりも幾分丁寧に、その議論の内実を整理していくことにしよう。
テーゼ①をめぐって
まずアンスコムが強調するのは、アリストテレスの倫理学と現代の道徳哲学の噛み合わなさだ。『ニコマコス倫理学』等においてアリストテレスは、道徳的な非難や義務や善といった概念に議論の中心を置いて個別に論じる、ということをしていない――われわれがそう感じ、それがなぜかと疑問を覚えるとしたら、道徳にまつわる諸概念に対するわれわれの捉え方が現代に特有のものであるからだ。しかも、そうした現代風の捉え方には重大な問題があるというのがアンスコムの基本的な立場だが、その点は後で語られる。さしあたり論文の冒頭部では、現代の道徳哲学の方向性に直接資するような知見をアリストテレスの倫理学から得ることはできない、という点が確認される。
さらにアンスコムによれば、ジョゼフ・バトラー(一六九二~一七五二)やデイヴィッド・ヒューム(一七一一~七六)、イマヌエル・カント(一七二四~一八〇四)、そしてジェレミー・ベンサム(一七四八~一八三二)およびJ・S・ミル(一八〇六~七三)という、しばしば現代の道徳哲学の源流に位置づけられる論者たちも、実は、道徳的な非難や義務や善に関して直接的な見識を与えてはくれない。ただしその理由は、アリストテレスのように探究の方向性や諸概念の捉え方自体が現代の道徳哲学と異なるから、というよりも、彼らの理論自体に明確な欠点があるからだという。以下、アンスコムの指摘を列挙しよう。
まず、バトラーは、欲求や自己愛などに対する良心による監督を称揚するけれども、人間はときに良心に導かれて下劣な行為をなしうるという、当たり前の事実に考えが及んでいない。
また、ヒュームは、「……である」という真理ないし事実から、「……べき」という道徳的判断は導けないと論じた。いわゆる「ヒュームのギロチン」である。しかしこれは、道徳的判断が排除されるようなかたちで真理(事実)を定義した上で、真理から道徳的判断は排除されるという、まさしく論点先取を犯している。また、彼の議論に従うならば、「である」からは「べき(ought)」と同様に、「負っている(owe)」や「必要がある(need)」も導出されないことになるだろうが、これも受け入れられない結論である。(なぜ受け入れないかについては後で議論される。また、こうしたヒュームの主張には、歴史的状況を鑑みれば一理あるとも言えるが、この点についても後述される。)
さらに、カントは、自身の道徳哲学の基本的な原理として「自己立法(自己が自己に対して法を立てる)」というアイディアを導入したが、このアイディアは明らかに馬鹿げている。なぜなら、立法という概念はそもそも、立法者が他者――立てられた法に従うべき者、たとえば個々人――に優る権力を有することを要求するからだ。(それゆえ、立法者は神や王、議会といったものである必要がある。)また、なすべき行為の規準ないし規則をカントは定式化しようとしたが、そこには、何がその行為の有意味な記述とされるのかに関する規定が抜けている。たとえば、殺人鬼に追われている友人Aを家に匿っているとしよう。このとき、家に押し入ってきた殺人鬼に対して、「Aはこの家にはいない」と言うことは、一方では「嘘をつく」という行為として記述されうるが、他方では、「殺人鬼から友人を助ける」という行為としても記述されうる。カントはこうした点を適切に考慮できていないのだ。
ベンサムとミルの問題は、そもそも「快」という概念の不可解さ、捉えがたさというものに気づいていない点にある。たとえば、一九五四年に刊行された『ジレンマ』(篠澤和久訳、勁草書房、一九九七年)第四章においてギルバート・ライルが指摘するように、「快」とは身体的な苦痛と対比されるべき感覚的体験である、という近代以降の通念は様々な点で問題がある。少なくとも、そうした内的印象としての「快」によって人間の行為の動機等を説明することはできない。
さらにまた、ミルの理論にはカントと同様の問題もある。ミルは、行為が多様な仕方で記述されうるということに十分に考えが及んでいない。ある行為が功利に基づく何らかの原理の下に包摂されるとしても、その行為は別の多様な原理の下に包摂されるようにも再記述できるのである。
アンスコムは以上のように、行為を導く動機や規則、道徳的判断などの原理、あるいは行為そのものについて、近代の道徳哲学者たちの理論が抱える欠陥を列挙し、その延長線上で次のように結論づけている。心理にまつわる諸概念の分析を適切に遂行する哲学をわれわれはまだ手にしていない。何が行為の有意味な記述とされるのか。また、意図や動機、判断、性格などによって行為の記述がどのように影響されるのか。また、そもそも、意図や動機とはいかなる概念なのか。さらにまた、行為へと例化される「徳」とはどのような種類の性格なのか。――これらの問いに応えるべき哲学が、目下のところ欠けているのだ。
アンスコムによれば、心理にまつわるそうした適切な哲学を構築するまでは、「不正な行為」とか「正義」という徳といったものをめぐる研究――つまり、道徳哲学ないし倫理学の研究――を行っても益はない。(そして、この論文の前年の一九五七年に彼女が上梓した『インテンション』(菅豊彦訳、産業図書、一九八四年)は、こうした意味での心理にまつわる哲学を彼女自身で開拓しようと試みたものとして捉えうるだろう。)
ヒュームのギロチンが明るみに出す、近代以降の道徳概念の歪み
このようしてアンスコムは前掲のテーゼ①を示すわけだが、それと平行して、論文全体にかかわる重要な論点も提示している。それは事実の相対的な厳然性(bruteness:生(なま)さ)と彼女が呼ぶものである。たとえば、以下の三つの文を見てみよう。
(A)私が店にジャガイモ百個を注文し、店がそれを供給し、私に請求書が送られたのが現状である。
(B)私は店にジャガイモ百個の代金分の債務を負っている(owe)。
(C)私は店にジャガイモ百個の代金を支払うべきである(ought)。
ここでアンスコムは、(A)が表している事実は、(B)が表している事実に対して相対的に厳然たる事実である―― 生(なま)の事実、剝き出しの事実である――という表現の仕方をする。そしてここで重要なのは、(A)から(B)へは、論理的な導出の関係にあるわけではないものの、全く無理のない自然な移行に思われるということである。つまり、少なくとも上記の例の場合、「である」から「負っている」の移行は不可能とするのは馬鹿げているということだ。
では、(B)から(C)の移行はどうだろうか。この移行も無理がないように思われる。「ought(べき)」が「owe(負っている)」に由来する言葉であることを踏まえるなら尚更だ。言い換えれば、(B)と(C)の違いもまた、事実の厳然さの程度差に過ぎないように思える。しかし、ヒュームに従うなら「である」から「べき」への移行は不可能だったはずだ。では、ヒュームのギロチンは、(B)と(C)の間に落とされるべきなのだろうか。それとも、本当は(A)と(B)の間にすでに落としておくべきものだったのだろうか。
アンスコムの考えでは、(A)と(B)と(C)の違いは、事実の厳然さの相対的な違いとして捉えることができる。その場合には――すなわち、「負っている」や「べき」をある種の事実を示す表現として捉えた場合には――、(A)から(C)に至るまでの移行、すなわち、「である」から「べき」への移行は自然に可能である。(同様に彼女は、「である」から「必要である(need)」への移行にも不自然なところはないと指摘する。なお、そのように論じることによってアンスコムは、「負っている」、「べき」、「必要」といった概念が、価値ではなく事実の範疇である、と主張しているわけではない。むしろ、ヒュームのギロチンが示唆するような事実と価値の二分法自体に疑義を示し、後にバーナード・ウィリアムズが言うところの「厚い概念(あるいは、濃い概念)」へと倫理学的探究の矛先を向けるよう促していると考えられる。)
ただし、彼女によれば、「べき」を特に近代以降の特異な道徳概念として捉えるならば、「である」から「べき」への移行はヒュームの言う通り不可能だという。この点で彼女はヒュームを皮肉交じりに賞賛している。すなわち、彼女によればヒュームは、「である」と「べき」の間にギロチンを落とすことによって、近代以降の道徳にまつわる諸概念が何か特異なものであること――もっと言えば、歪んだものであり、打ち棄てるべきものであること――を、それと知らずに明るみに出している、というのである。
(以下、本文つづく。傍点は割愛しました)







