あとがき、はしがき、はじめに、おわりに、解説などのページをご紹介します。気軽にページをめくる感覚で、ぜひ本の雰囲気を感じてください。目次などの概要は「書誌情報」からもご覧いただけます。
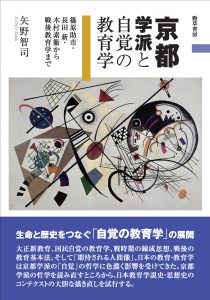 矢野智司 著
矢野智司 著
『京都学派と自覚の教育学 篠原助市・長田新・木村素衞から戦後教育学まで』
→〈「序章 京都学派の哲学を中心に日本教育学を描きだす試み」(冒頭)(pdfファイルへのリンク)〉
→〈目次・書誌情報・オンライン書店へのリンクはこちら〉
*サンプル画像はクリックで拡大します。「序章 京都学派の哲学を中心に日本教育学を描きだす試み」冒頭はサンプル画像の下に続いています。
序章 京都学派の哲学を中心に日本教育学を描きだす試み
1 近代日本教育学説史・思想史の再検討
研究が専門化して、主題や対象領域が限定され細分化し精密化していくことは、なにも自然科学にかぎられたことではない。教育学説史・思想史研究のような領域でも、学術誌に掲載されるような専門的な研究論文を書こうとするなら、主題や対象領域を狭く限定する必要がある。
しかし、教育思想は社会情勢や内外の政治情勢はもとより、同時代の哲学・思想の動向や他の教育思想の潮流から孤立して単独に生まれ発展するわけではない。個々の教育思想は、同時代の主導的な哲学・思想の運動態によって生みだされる新鮮な哲学的造語=思考アイディアの息吹を強く受けながら、他の教育思想との対話や論争、連帯や競合、ときには抗争や闘争に曝され鍛えられて展開する。そのように思想間にさまざまな形の交通が生じるためには、哲学・思想が互いに連携し競合することが可能となる理論的地平が生成しなければならない。
ところが、この哲学・思想の理論的地平は、個々の教育思想の独自性に焦点化して単独で捉えていたのでは決して見いだすことはできない。テクスト間を横断し結び合わせる無数のラインを読み解き、それらのラインを明示化して結び合わせて、思想全体の相関的動態図(コンテクスト)を浮かびあがらせるようにデザインする構成力が必要となる。その意味でいえば、教育学説史・思想史の生成する地平の研究は、字数が厳しく制限されている学術誌のような場では議論されにくいテーマといえる。しかし、連携しあるいは競合する複数の思想群が動的に織りなすコンテクストの理解なしには、個々の思想のテクストの読解は、不完全なものにしかならない。
論者が支持し立脚している政治的立場から、思想のテクストのイデオロギー的機能的側面のみを単一的一面的に抽出して選り分け、それぞれに政治的立場のレッテルを貼り付け、それをもとに裁断するのであれば、このような生成する理論的地平の研究という作業を飛び越してもできようが、そのような奥行きを欠いた思想研究は既存の価値観に基づいてテクストの字面をただなぞって解釈しているにすぎない。まして抵抗と屈服とが紙一重の関係にあったといわれる戦時期・占領期の厳しい言論統制下で出版されたテクストを、コンテクストを十分に顧慮することなく、字義どおりにそうした立場から読んでしまうと、近代日本の学説史・思想史研究は底の浅いものとなるだろう。しかし、従来の日本教育学説史・思想史研究の多くは、このような作業に終始していたように思える。
いま当たり前のように、「日本教育学説史・思想史」という書きだしで出発してしまったが、「日本教育学説史・思想史」という設定の仕方自体が問題である。「学問の政治学」からみたとき、多様で重層的なものを単一単層の固有な特性として画定できる「日本文化」や「日本史」として「日本」なるものを実体化し前提としてしまうことになり、民族や国家の歴史という枠組みに回収されてしまう危険性がある。戦前において「帝国」として海外に植民地をもち多民族・多言語国家であった時期も本書では考察の範囲に入るため、「日本」なるものの画定をめぐる議論自体が問いとなること、また同様に、トランスナショナル・ヒストリーが求められている時代に、一国思想史に立って「日本教育思想史」なるものは成立しえないということに[桂島 2013]、注意を払いつつ論を進めよう。
従来の日本の教育学説史・思想史研究の評価によれば、日本の教育学研究は海外とりわけ欧米からの教育学・教育思想の輸入と受容そしてその解釈に終始し、さまざまな思想潮流の錯綜にほかならず、「日本の教育学」と呼びうるような独自の教育思想の展開はなかったといわれている。しかし本当にそうだろうか。現在の学問研究の内容と形式とが近代社会・国民国家の成立した欧米で誕生したこと、そして学問研究が人と情報の交通のなかで発展することを考えれば、近代国家の建設とともに欧米からこうした学問が輸入され紹介され翻訳されたことも、またたえず欧米の最新の学問動向に注意を払うことも、当然のことといってよい。このことは別に教育学研究にかぎられたことではない。このことをもって日本の教育学研究を欧米の教育学の「送迎・展示」(森昭の言葉)といった一語で解してしまうと、先入観にしたがった誤謬というべきであろう。日本の近代的な学問知の成立ということでは、一九三〇年代に政治学・民族学・社会学や倫理学・宗教学が自前の近代学術の成立を果たしたといわれているが、日本の教育学もまた同時期に成立したと考えられるのである。
教育学もまた、学問知の一つとして、経済学や政治学・法学、哲学や社会学・心理学といった隣接領域の学問動向と連動しつつ、近代社会において共通して問われるべき思想的課題の設定と、その課題の解明そして克服の方向を明らかにすべく展開されるとともに、それぞれの国内事情に特有の教育課題と結びついて展開してきた。ドイツ・フランス・イギリスそしてアメリカ・ロシア(旧ソビエト)の教育学を、それぞれ比較検討してみれば明らかであるように、欧米においても、それぞれの国家に特有の歴史・社会・文化・経済・政治体制に制約されつつ、学校制度・教員養成制度や教育学の他の学問との学問上の位置関係や、教育思想家・実践家がおかれている状況によって、教育学はさまざまに異なった形を取って独自に発展してきた。同様に、日本の教育学が海外の教育学説の輸入と受容に終始することなどそもそもできないことである。日本の教育学が向かいあう現実の教育課題は欧米のそれと同じではない。
また、外国文献の翻訳という作業を取りあげてみればわかるように、ギリシア語からラテン語へ、ラテン語から個々の民族語への西欧における宗教・哲学用語の翻訳経験がそうであったように、古代中国において多数の仏典が組織的に漢訳されたときの翻訳経験がそうであったように、あるいはまたイスラム文化史の初期にギリシア哲学の基本的典籍が組織的にアラビア語に翻訳されたときがそうであったように、一つの概念の適切な訳語の選定をめぐって、伝統的な思考法との思想的葛藤や思想的融合、「誤読」による「意味の歪曲」や「ズレ」、あるいは「解釈」による「新たな意味の創造」や「意味の再発見・拡張」が起こるのである。つまり異なる思想の受容とは、それまでの世界の区切り方が根底的に組み変わることだから、すべてにおいて主体的で思想的な創造的抗争を孕んでいるのである。ちなみに「自覚」「主体」「形成」「実存」は、すべて京都学派の哲学者たちが関わった哲学的思考の中核に関わる訳語だが、日本語における意味論的変容をもたらしただけでなく、西欧での哲学用語としての使用法との間に差異を生みだしてもいる。教育学もこのようなコンテクストにおいて、欧米の教育学・教育思想を受け身的に受容するだけでなく、課題としての教育状況と向かいあうことで、主体的にカスタマイズしてもいた。
このように教育学の性格を捉えるとき、日本の教育学の展開が、状況への哲学的思想的応答のなかで最も影響力のあった同時代の哲学の動態と無関係であったとは、到底考えられないことである。日本の哲学において、西田幾多郎と田邊元という二人の卓越した哲学者を中心とする京都学派の哲学、またその哲学の特殊形態である人間学は、同時代の先端的課題とつながり展開されていたハイデガーの存在論とマルクス主義とを批判的に参照し受容しつつ、状況(戦時期では「時局」と呼ぶ方が正確か)の切迫した課題(「時務」と呼ぶ方が正確か)と切り結びながら展開してきたことが知られている。一九一〇年代後半から六〇年代において、他の人文社会諸科学と同様に、日本の教育学(あらためて限定的にいえば本書では教育哲学・教育思想)もまた受容するにせよ批判するにせよ、西田─田邊哲学をはじめとする京都学派の哲学に大きな思想的影響を受けていたのである。しかし、「戦後教育学」は教育学説史を「講壇教育学」から「教育科学」への発展というシンプルで単線的な進歩の物語にすることで、京都学派の哲学と日本の教育学との思想的つながりを意識的無意識的に抑圧し忘却してしまった。そのことによって、京都学派の哲学という知的ネットワークの運動態とつながることで独自に培われ展開されてきた「日本の教育学」の主題と論理の系譜的理解ができなくなっただけではなく、同時に西田─田邊哲学を淵源とする生動的─歴史的な「自覚の教育学」の新たな展開の可能性も閉ざされてしまったのである。
2 教育学における京都学派の哲学の忘却
京都学派の哲学との関係が見失われた理由
一九四五年八月の敗戦後の「新生」日本の出発点において、戦前・戦時期の記憶は、国家への忠誠心から積極的に戦争に協力した者は当然のことながら、迎合し便乗し追従した者も、半ば強制されて面従腹背を余儀なくされた者も、あるいはまた表面では協力するふりをしつつ戦争の意味自体を別のものに転換しようと「戦時変革」を企て挫折した者も、できれば忘却し、それが知識人であれば戦時期の著作や発言や講演記録を抹消したいと考えたことだろう。多くの知識人たちが戦時期に戦争への抗議の声を上げる勇気を欠いていたことへの自責と悔恨を共有していた。丸山眞男はこうした敗戦後の知識人たちの連帯と責任の感情の拡がりをさして「悔恨共同体」と呼んでいる[丸山 1977: 256]。特に教育学は、学校教育とのつながりを考えればわかるように、政治学とならんで国民の統制を担い、戦争遂行において直接的な実行力をもつ制度と連関した学問領域であったため、超国家主義・軍国主義のイデオロギーと緊密に結びついていた。思想戦の重要な担い手であった教育学者たちの多くに、戦時期の言動への責任追及を逃れるために、できうるかぎり早く「過去の過ち」を清算し、あるいは弁明し、「正しい立場」に立ちたいという欲望が働いたことはまちがいない。何はともあれ、戦前・戦時期の教育思想をまずは否定し告発し批判することによって、新生への道の第一歩を踏みださなければならなかったが、死者たちへの贖罪の意識は内攻し屈折し、悔恨・屈辱は憎悪となって反転して、痛みを伴う自身の反省を欠いたまま、戦争責任の所在を外部に求めていった。
京都学派の哲学は、一九四二年の文芸誌『文学界』での有名な座談会「近代の超克」での西谷啓治らの発言や、あるいは『中央公論』での高坂正顕・高山岩男・西谷啓治・鈴木成高による座談会「世界史的立場と日本」「東亜共栄圏の倫理性と歴史性」、同じく翌年に発表された同様の座談会「総力戦の哲学」等での発言、あるいは皇室を基軸にして「日本の使命」を論じた西田幾多郎の『日本文化の問題』(一九四〇年)や軍部に屈したと喧伝された「世界新秩序の原理」(一九四三年)、さらには戦場で死ぬことの意味を学生に説いた田邊元の京都帝国大学での講演(一九三九年)とその講演記録「歴史的現実」(一九四〇年)や、講演「死生」(一九四三年)ならびに京都帝国大学新聞に寄稿した「征く学生におくる贐はなむけの言葉」(一九四三年)などが、戦争協力として非難され批判された。高坂正顕と高山岩男は「大日本言論報国会」の理事をしていたという理由によって公職から追放され[花澤 2008: 19]、西谷啓治と鈴木成高は「著作の超国家主義的ないし軍国主義的傾向によって」教職から追放された[京都大学 1998: 465]。
しかし、「戦後教育学」が京都学派の哲学に否定的批判的であったのは、戦時期における京都学派の哲学者たちの「戦争協力」という理由だけでなく、戦後の政治的立場において戦後教育学が立脚していた立場と京都学派の主要な哲学者たちの立場とが対抗関係にあったことが大きな理由であったろう。「戦後啓蒙と思想運動」を推進してきた丸山眞男や大塚久雄にとって、「近代」は日本が実現すべき理念であり[中野 2001]、その「近代の超克」(近代批判)を課題としていた京都学派の哲学に、戦時期にそれぞれがどれほど深く思想的影響を受けていたとしても(中野敏男は戦前から戦後を経て継続することになる丸山への田邊・務台・三木の思想的影響を、そして大塚への三木の影響を指摘している[中野 2001: 41-42, 127-134])、「近代の超克」こそが「戦争とファシズムのイデオロギイ」を代表するものとして否定し批判すべきものと見なされた[竹内 1959: 287]。京都学派の哲学者たち──といってもそのなかでの思想的立場の差異の幅は大きくて、正確には個別に精査すべきことではあるのだが──は、戦時期においては、超国家主義・自民族中心主義の立場に立つ者から、普遍主義的立場を擁護し軍部や国家と対立する者として指弾・恫喝され、戦後においては、戦後啓蒙を推進する立場の者から、天皇制と日本文化の伝統を守護し国家の立場に立った国民道徳・保守的道徳教育の擁護者・戦前の体制への回帰を目論む「反動」として批判された。
西田の門下生の天野貞祐が第三次吉田内閣の文相のとき、「教育勅語」に代わる新たな国民道徳の基本を「国民実践要領」として制定しようとしたが、この「国民実践要領」は天野が高坂正顕と西谷啓治と鈴木成高とに執筆を依頼したものだった。また高坂は、「期待される人間像」の立案においても、指導的立場に立ってこの政治的教育的プロジェクトを推進した。さらにまた家永教科書裁判では、文部省教科用図書検定審議会委員の経験をもつ高山岩男が、被告国側の証人として証言し、原告家永三郎からの批判に対して検定制度を弁護している。また天野貞祐(文相 一九五〇年五月から五二年八月まで)・高坂正顕・下村寅太郎をはじめとする京都学派の哲学者たちは、安倍能成(文相 一九四六年一月から同年五月まで)・和辻哲郎・谷川徹三・志賀直哉・武者小路実篤・山本有三・田中耕太郎(文相 一九四六年五月から四七年一月まで)といった教養主義者が中心に結成した「同心会」とともに、生成会誌『心』(一九四八年─一九八一年)などを表現媒体にして、天皇制の擁護と反マルクス主義に立つ「保守」的な国民道徳論・国民教育論・道徳教育論の思想的代弁者として活躍した。彼らは後に「オールド・リベラリスト」と呼ばれるようになる[小熊 2002: 196-199]。
もちろんそのときの国民道徳論・道徳教育論は戦前の吉田熊次らが推進した皇国民の育成をめざした「教育勅語」に基づくものとは異なり、人類主義の普遍主義的立場と個人の自由とを組み入れたものであって、戦前の「国民道徳論」「修身科」との連続性のみに注目することは、戦後の京都学派の哲学・思想を捉え損ねるものであるし、むしろこの連続性に焦点をあてることで京都学派の社会的政治的影響力を削ごうとした戦後啓蒙を中心とする論壇の政治性を見逃すことにもなるだろう。国民道徳・道徳教育に関わる領域において、京都学派の哲学者たちが、「保守」の論客として論壇に再登場したことに対して、対抗関係にある戦後啓蒙の革新派知識人たちそして彼らと同盟関係にあった戦後教育学の先導者たちは、否定的批判的にならざるを得なかった。そのこともあって、教育学者たちは京都学派とその周辺の哲学者たちとの戦前における思想的関係も、また戦前から連続している戦後の関係も、意識的あるいは無意識的に表に出すことが困難になったのではないかと推測される。
しかし、京都学派の哲学と教育学との関係が見えなくなった理由はこれだけではない。後でまた具体的に例示することになるが、篠原助市や長田新ら当時の教育学のテクストでは明らかに西田や田邊の思想であるにもかかわらず、そのことを表記せずまた叙述においても引用という形を取らずに直に自分の文章に埋め込んでしまい、さらには参考文献として文献欄に表記してもいない。同時代の読者には、その特有の哲学用語やフレーズから京都学派の哲学としてある程度は理解できたであろうが、ある時期から教育学研究者に西田・田邊をはじめ京都学派の哲学に対する基本的な知識が失われてしまい、その用語やフレーズの出所が理解できなくなった。このようなことが京都学派の哲学と教育学との関係の忘却に拍車をかけることになった。
(以下、本文つづく。注と傍点は割愛しました)






