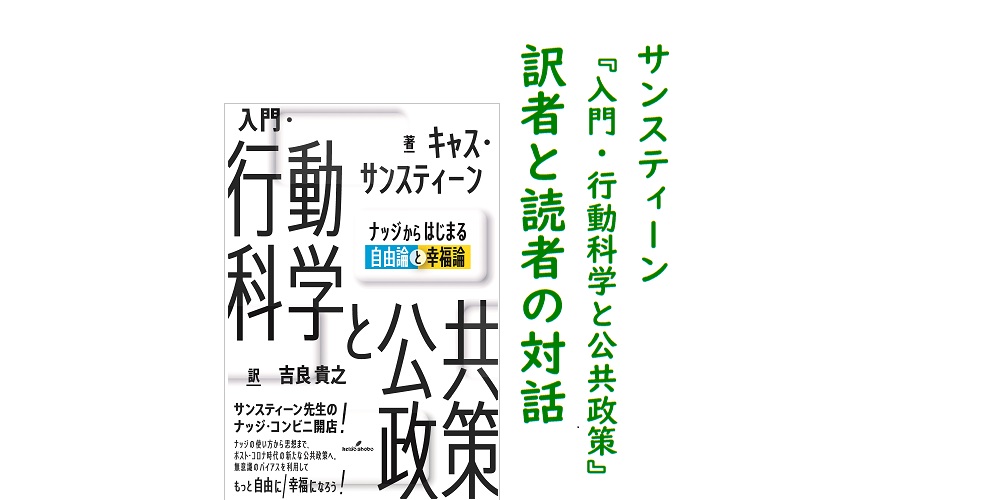
■導入
![]() レガスピ: 本読書会は、学生を中心に私が7月よりインターネット上で主催している「来るべきアナキズムのための読書会(来ア会)」の第二回として企画されたものです。アナキズム=無政府主義と、公共政策の手段であるナッジは一見まったく無縁の概念であるように思われるかもしれません。しかし、ナッジの実践の背景にある主体の自由と権力勾配には、人間の相互行為の別のあり方が示されているように思います。そしてそれは既存の権力構造に挑戦してやまないものなのです。それを手がかりにナッジを考えていけたら、というのが本読書会の趣旨です。
レガスピ: 本読書会は、学生を中心に私が7月よりインターネット上で主催している「来るべきアナキズムのための読書会(来ア会)」の第二回として企画されたものです。アナキズム=無政府主義と、公共政策の手段であるナッジは一見まったく無縁の概念であるように思われるかもしれません。しかし、ナッジの実践の背景にある主体の自由と権力勾配には、人間の相互行為の別のあり方が示されているように思います。そしてそれは既存の権力構造に挑戦してやまないものなのです。それを手がかりにナッジを考えていけたら、というのが本読書会の趣旨です。
……といったことをツイッターに書いていたら訳者の吉良さんに見つかって(笑)、ご参加してくださるということになったので、吉良さんと一緒にいろいろざっくばらんと意見交換できればと思います。では最初に、本書の第一印象みたいなことを一人ずつざっくり話していきましょうか。
■第一印象
![]() レガスピ: ナッジという概念自体は、梶谷懐・高口康太『幸福な監視国家・中国』(NHK出版新書、2019年)で知って、でも詳しくはわかっていなかったんですが、納得半分、もやもやが半分、という感じですね…。僕の個人的な意見としては、ナッジされた主体はいわゆる中動態的にふるまうのかなと思いました。中動態は能動と受動の間の概念なんですが、受動の割合が高い主体的な行動が中動態なんですよね(國分功一郎・熊谷晋一郎『〈責任〉の生成:中動態と当事者研究』新曜社、2020年)。リバタリアン・パターナリズムといわれているものも中動態に即して考えると納得しやすいのかなと思います。
レガスピ: ナッジという概念自体は、梶谷懐・高口康太『幸福な監視国家・中国』(NHK出版新書、2019年)で知って、でも詳しくはわかっていなかったんですが、納得半分、もやもやが半分、という感じですね…。僕の個人的な意見としては、ナッジされた主体はいわゆる中動態的にふるまうのかなと思いました。中動態は能動と受動の間の概念なんですが、受動の割合が高い主体的な行動が中動態なんですよね(國分功一郎・熊谷晋一郎『〈責任〉の生成:中動態と当事者研究』新曜社、2020年)。リバタリアン・パターナリズムといわれているものも中動態に即して考えると納得しやすいのかなと思います。
![]() 環原望: ナッジの一例として、できるだけ健康的な食品が見えやすいように食事のメニューを配置する、というのを聞きかじったことがあるくらいのざっくりした理解だったので、今回読んでナッジがどんなことを指しているのかが明確になったのと、かなり広い射程で使われている言葉なのだなというのが第一印象ですね。僕の中でもしっかりまとまっていないんですが、「強制ではないがそうしたほうがいいと促す」という定義でナッジを捉えるとあまりにも概念の射程が広すぎて、あるアーキテクチャによって人の行動を規定することへの解像度を、「ナッジ」という言葉を使いながら詰めていかないとどうとでも使えてしまうなと思ったので、そのへんを細かく話せたらと思います。
環原望: ナッジの一例として、できるだけ健康的な食品が見えやすいように食事のメニューを配置する、というのを聞きかじったことがあるくらいのざっくりした理解だったので、今回読んでナッジがどんなことを指しているのかが明確になったのと、かなり広い射程で使われている言葉なのだなというのが第一印象ですね。僕の中でもしっかりまとまっていないんですが、「強制ではないがそうしたほうがいいと促す」という定義でナッジを捉えるとあまりにも概念の射程が広すぎて、あるアーキテクチャによって人の行動を規定することへの解像度を、「ナッジ」という言葉を使いながら詰めていかないとどうとでも使えてしまうなと思ったので、そのへんを細かく話せたらと思います。
![]() 幸村燕: 簡単にオプトアウト(選択の取りやめ、脱退)できるという話があったんですが、個人的な経験としてサブスクは一回入っちゃうと全然やめられないんですよね。ナッジされた後に選択できるという考え自体、どこまで妥当性があるのかと思いました。それとどこまでがナッジなのかなと。いわゆる排除アートもナッジであるならば、選択として排除されないことも選べるようにしないといけないはず。でも完全にはナッジと同じじゃないからどうとでも言えるというか。
幸村燕: 簡単にオプトアウト(選択の取りやめ、脱退)できるという話があったんですが、個人的な経験としてサブスクは一回入っちゃうと全然やめられないんですよね。ナッジされた後に選択できるという考え自体、どこまで妥当性があるのかと思いました。それとどこまでがナッジなのかなと。いわゆる排除アートもナッジであるならば、選択として排除されないことも選べるようにしないといけないはず。でも完全にはナッジと同じじゃないからどうとでも言えるというか。
これだけナッジという概念が広くなりすぎると問題があるんじゃないか、たとえば「排除アート」のような、アーキテクチャによる支配と何が違うのか、という指摘もあります。サンスティーン自身、他の本では「天気だってナッジだ」とか書いていて、概念的な混乱に加担しています(?)。幸村さんの例のように、立入禁止したいのか何なのか、意図がよくわからないものもあります。「アーキテクチャのトマソン化」なんて言われることがあるんですが(笑)、ナッジも意図がよくわからなくなったり、元々の意図とは違う効果を持ったり、ということはありますね。
この本のポイントの一つは、ナッジとそれ以外をあまりきっぱり分けるのではなく、ナッジを程度問題として捉えようということかと思います(19-20頁)。ナッジというからには人々の自由を保障するというのもあるし、露骨にお金で釣ったりしないとか、そういったこともあるんですが、たとえば自由保障点がこれぐらい、福利厚生点がこれぐらい、行動促進点がこれぐらい……だとか、そんな感じで細かくナッジを評価していく視点を出したのが一つ大きなところかなと。ナッジは単なるお役所仕事じゃなく、何より楽しくないといけない(52頁)という記述もありますが、そうすると芸術点(?)なんて入れてもいいでしょうね。日本だと、松村真宏『仕掛学:人を動かすアイデアのつくり方』(東洋経済新報社、2016年)のように、人を動かすにはまず楽しさだ、という「仕掛学」の試みがありますが、本家のナッジもそれに合流してきた感じです。
レガスピさんが中動態の話とあわせて考えると面白いんじゃないかということで、たしかにナッジによって誘導された行動って能動的なのか受動的なのかよくわからないところがあるんですよね。それを「中動態」と言っていいのかどうかわかりませんが、そこにナッジの気持ち悪さのポイントが一つあると思うんです。実際には悪い官僚たちに誘導されている、にもかかわらず「自分から自由に選んだんでしょう、自己責任ですよね」と、能動的であるように見せかけられている、そのへんの気持ち悪さがナッジの嫌なところとしていわれるのかなと思います。
■「ナッジ」は「評価」できるのか?
[1]「普及とポップ化」という表現で想定しているのは、たとえば行動療法、ネットワークビジネス、自己啓発と自己啓発セミナー、ナンパ・マニュアルといったもののことですが、私は、「ナッジ」もこの場所に並べてよいものだろうと考えています。[2]酒井泰斗+高 史明「行動科学とその余波:ニクラス・ルーマンの信頼論」(小山虎編『信頼を考える:リヴァイアサンから人工知能まで』 勁草書房、2018年)。論文タイトルの意味は「ニクラス・ルーマンの仕事は行動科学の余波として捉えるべきものだ」です。この論文の注3で、行動科学運動を手短にまとめたので、ここに自家引用しておきます:
[3] Miller, J. G. (1955). Toward a general theory for the behavioral sciences. American Psychologist, 10(9), 513–531. https://doi.org/10.1037/h0045498語「行動科学」は、国立科学財団の創設(1950年)を巡って生じた、心理学・人類学・社会学を中心とする非自然科学系の学界を横断的に連合した政治的圧力活動のために1940年代末に作られたものである。学問的には、それは人間に関する新しい総合科学の理念を掲げた統一科学運動であった。
なお「行動」という語の心理学史上の位置については、カート・ダンジガー『心を名づけること』(河野哲也ほか訳、勁草書房、2005年)第6章「行動と学習」が参考になる。[4]日本語圏への紹介記事として: フランチェスカ・ジーノ(ハーバード・ビジネス・スクール教授)「あなたのちょっとした工夫が、不合理な人たちを合理的に動かす」(ハーバード・ビジネスレビュー、2015.12.16)(記事原文)。この記事にもサンスティーンの名が登場しています。
記事のリード文には「2015年9月15日、オバマ大統領は政府機関に対し「行動科学の知見を活用せよ」と公式に発令した。人間の不合理を認め、個人と組織を正しい方向へと導くために、行動科学に基づく手法の効果がますます明らかになっている」とあります。
一つ目。合衆国の学問は、薄く緩いコンセンサスのもとで、小さく具体的な課題に対して実践的な解決を指向した膨大な試行錯誤が集積される、というかたちを取ることが多く、結果として、「しかじかのムーブメント・流行があるらしいのだが、全貌は誰も知らない」といったことになりがちです。おそらく、公共政策分野におけるナッジに関する知見の集積にもそうしたことが生じていて、本書も、そうした事態を踏まえたうえで、この分野の第一人者によるレビューとして書かれたのだろうと想像しました。内容的には、概説書にふさわしい大まかさで知見を紹介しつつも、比較的丁寧に文献参照が挟まれてもいるので、これから発展的な内容を知りたいひとにとっても「導入の一書」にふさわしいものだと思います。よいものを訳していただいたなと思いました。原著では本文に置かれている文献参照を邦訳版では巻末に移すといった工夫もされていて、読みやすさにさらに貢献しています。
二つ目。読み終わって気になったのは、「日本にこれを輸入した場合に何が起きるだろうか」ということでした。本書でも紹介されているように、「ナッジ」は善きものにも邪悪なもの にもなりうるので(9、129-130頁など)、「いかにして善き意志のもとでナッジするか」という議論をするために、サンスティーンの場合には「ナッジ+リバタリアン・パターナリズム」のセットで話を進めているのだろうと思います(19頁)。これが日本に輸入された場合、「いかにしてナッジの意図と帰結を評価するか」──リバタリアン・パターナリズムもしくはそれに相当・代替するもの──の方はあっさりと落ちて、よくない意味で「技術化」されるだろう、というのは想像に難くありません。「それを落とした場合に残るのは何か」と考えてみたときに「手間がかからず安上がりな行政」という基準(?)以外に何があるのか疑問ですし、評価基準がないところでは実験的施策の意図も帰結も評価が難しくなるだろうとも想像されるところです。以上のことは、「日本に輸入した場合、リバタリアン・パターナリズムを誰が嬉しがるだろうか」という問い方で提示することもできるでしょう。
三つ目。本書でサンスティーンは「行動科学」を「認知心理学、社会心理学、行動経済学という、重なりあう三つの分野を指」すものだと特徴づけています(10頁)。行動科学史に関連して1930〜50年代あたりの文献を読むことが多い私からすると、この特徴づけは非常に興味深いものです。1940年代末にこの言葉が作られたとき、それは、
・〈社会主義〉と間違われやすい〈社会科学〉という言葉を避けるために〈行動〉という語を選び、
・すでに米国において地位を確立していた経済学との緊張関係・対抗関係のもとで、
・〈心理学と人類学という先進的な学問分野が牽引し・後進の社会学がそれについていく〉という諸学科の連携ヴィジョン[5]とセットで、
提起されたものでした[6]。つまり、60年のほどのあいだに、〈心理学+人類学+社会学〉のセットから〈認知心理学+社会心理学+行動経済学〉というセットへの 驚くべき転換が生じているわけです。ここには論じるべきたくさんの科学史的話題があるように思うのですが、この論点が本書の評価にとって重要だとは言えないでしょうから、ここでは以上の指摘にとどめておきます[7]。
[5]1940年代の合衆国では この発想が比較的ひろく共有されており、「人間の科学」など他の幾つかの語も同じ発想のもとで使われていました(このもっとも直接的の背景となったのは、心理学と人類学が相互乗り入れしていた「文化とパーソナリティ」という課題領域です)。たとえばラルフ・リントン編著『世界危機における人間科学』(池島重信ほか訳、実業之日本社、1952年(原著は1945年)))、ジョン・ギリン編著『人間科学の展開:社会学・心理学・人類学の交流による』(十時厳周ほか訳、早稲田大学出版部、1961年(原著は1949年))など。リントンは人類学者、ギリンは社会学者です。
この発想を極めてベタに具現しようと試みた著作としては、たとえばタルコット・パーソンズ『社会体系論』(佐藤勉訳、青木書店、1974年(原著1951年))、パーソンズ&シルス『行為の総合理論をめざして』(永井道雄ほか訳、日本評論新社、1960年(原著1951年))を挙げることができます。当時(1946年)ハーバード大学には、心理学・人類学・社会学を専攻する学生たちが同じカリキュラムで学ぶことを目指した「社会関係学部」が設置され、パーソンズは学部長の地位にありました。[6]ここでいう「経済学」は「自由放任主義的市場主義」くらいのことを意味します。したがって、非常に大雑把な政治的特徴づけをおこなうなら、この構図は、「市場主義と社会主義の双方に抗しつつ、科学にもとづく上からの社会改良をそれらに対置する」というものになっていると言えるでしょう。[7]二点だけ、特に注目すべきことを指摘しておきます。そもそも行動科学を批判して登場した認知科学が、新しい分類に含まれていること(行動科学/認知科学の対立は方法に関するものなので、新しい分類は方法論的なこだわりなくおこなわれていると言えそうです)。そしてまた、やはり新しい分類に含まれている経済学は、そもそも行動科学とは対抗的な位置にあったはずであること(これはおそらく経済学側の変貌を意味するのでしょう)。
ちなみに、新旧の学問セットのどちらにおいても中心にある心理学が 行動科学史においてもまた中心に位置することは動かないのですが、しかし心理学史だけを見ていても学問諸分野の配置の変遷はなかなか見えません。これに対して、行動科学の盛衰にもっとも大きな影響を受けた学問分野の一つは政治学なので、ここに注目すると変遷がやや見えやすくなるのではないか、と私は考えています。これに関わって参考になる古い文献と新しい文献2つを紹介しておきます。山川雄巳『アメリカ政治学研究』(世界思想社、1977年/1982年)。西山真司『信頼の政治理論』(名古屋大学出版会、2019年)。
![]() 吉良貴之: 酒井さんのご指摘その二にあった、これを日本に持ってきたときに誰がどれくらいうれしいのか、という問題はどうでしょうね。まず具体名でいうと、日本でいちばん目立っているのは横浜市で、横浜市行動デザインチーム「YBiT」というのを作って大々的にやってます。それから国レベルでは経済産業省が本腰を入れて取り組んでいます。ではそもそも、行政はナッジを何のために使っているのか。リバタリアン・パターナリズムというからには、パターナリズムということで国民を幸福な方向に導いてやろうと考えているのか。もちろん「国民のためによいことしてる」っていう感覚は現場レベルではあると思うんです。でも、もっと背景的な動機としては、補助金を出したりしてゴリゴリにインセンティブ操作して人々を誘導するのはお金かかっちゃうんで、ナッジみたいな安上がりな手段で税金節約できたらうれしいよねと、そういうネガティブな面も無視できません。
吉良貴之: 酒井さんのご指摘その二にあった、これを日本に持ってきたときに誰がどれくらいうれしいのか、という問題はどうでしょうね。まず具体名でいうと、日本でいちばん目立っているのは横浜市で、横浜市行動デザインチーム「YBiT」というのを作って大々的にやってます。それから国レベルでは経済産業省が本腰を入れて取り組んでいます。ではそもそも、行政はナッジを何のために使っているのか。リバタリアン・パターナリズムというからには、パターナリズムということで国民を幸福な方向に導いてやろうと考えているのか。もちろん「国民のためによいことしてる」っていう感覚は現場レベルではあると思うんです。でも、もっと背景的な動機としては、補助金を出したりしてゴリゴリにインセンティブ操作して人々を誘導するのはお金かかっちゃうんで、ナッジみたいな安上がりな手段で税金節約できたらうれしいよねと、そういうネガティブな面も無視できません。
ナッジの評価の仕方がそんなふうになるのはどんなものかという問題は、元々のアメリカというか、サンスティーン自身の議論の(本書だけではない)大まかさにすでに表れています。リバタリアン・パターナリズムというときに、パターナリズムの目標は何なのか。サンスティーンは「社会厚生(social welfare)」の増大という、功利主義っぽいことを述べてはいますし、本書でも「厚生」ってそもそも何なのかというのがテーマですが、なるほどそうかという明快な話にはなっていないんですよね。これは私が前に訳した、サンスティーンの同僚のヴァーミュールの「最適化立憲主義」構想と似たところがあって[8]、「基準なき最大化」「基準なき最適化」みたいな変な話なんです。でも本人たちは変とは思ってない。ヴァーミュールよりはサンスティーンはもっと積極的で、社会全体でのコスト・ベネフィット計算ができたらいいなっぽいことも言うんですが、まあそれもネガティブな議論というか、計算を妨げる要素を排除するにはどうすればいいか、みたいな話になっていきます。今回のナッジだと、そこの食堂に来る人が野菜を多く食べるようになったとか、労働者がちゃんとした年金プランに加入するようになったとか、ローカルな水準では目標も立てられるし、それに応じた評価もできます。でもそれが社会全体としてどうあるべきかというと、これだけナッジが多様化して、ナッジどうしで打ち消し合ったりもしている以上、全体としての評価を積極的にやるのは無理だと。なので、ナッジがうまく働かない要因である「ノイズ」(ある集団の多様性を損なう系統的バイアス)とか、ナッジが悪い方向に使われる「スラッジ」とか、そういった阻害要因を個別に潰していこう、という話になります。そういう意味での「技術化」はアメリカでもそうだったし、日本に輸入された場合でも、これはもともとそういうものだ、という話になりそうです。本書のサンスティーンの話だと、ナッジは実験的・漸進的なものであって、誰かが上から設計したってうまくいかないよ、むしろ人々の自由をちゃんと保障しておいたほうが、想定外の失敗を通じて何か面白い方向に行くかもしれないよ、ぐらいの楽観的な感じなんですけど、まあ、仮にそうだとして、それがイヤかどうかというところですね。
[8]サンスティーンとヴァーミュールは以前から共著も書いています。最新の『法とリヴァイアサン』(Law and Leviathan, Oxford University Press, 2020)では、現代の肥大化する行政国家においては細かな「ルール」よりも指針としての「原理(principle)」が大きな役割を果たすといいます。そこで持ち出されるのが遡及法や朝令暮改の禁止といった、ロン・フラー(Lon Fuller)の「法の内在道徳」です。それは行政活動においてとりわけ破られやすいものとして位置付けられており、両者の「ネガティヴ・チェックリスト」方式はここでも一貫しているといえます。しかし同書の大部分は司法審査の敬譲(deferance)基準をめぐる煩瑣な議論にあてられており、それ自体、行政をめぐる「原理思考」の困難さを裏書きしているようでもあります。日本語での部分的紹介として、吉良貴之「行政国家と行政立憲主義の法原理」『法の理論 39』(成文堂、2020年)。
三点目、「行動科学」という語の変容ですが、これは私には積極的に話せる材料がないので、注でお話しされていることも含め、めっちゃ面白そうです、という程度の感想になります。
![]() 酒井泰斗: なるほど。「リバタリアン・パターナリズム」という名前がついているから「何かある」ように見えているけれど、その内実は定かではないということですね。そもそも公共政策の評価というのは複雑で難しい仕事なのであって、それを「その背景にある思想」で裏打ちさせようという発想は単純すぎる、ということでもあるのでしょう。それはそれで理解できます。
酒井泰斗: なるほど。「リバタリアン・パターナリズム」という名前がついているから「何かある」ように見えているけれど、その内実は定かではないということですね。そもそも公共政策の評価というのは複雑で難しい仕事なのであって、それを「その背景にある思想」で裏打ちさせようという発想は単純すぎる、ということでもあるのでしょう。それはそれで理解できます。
■排除と自由意志
![]() レガスピ: 最近読んだ西井開『「非モテ」からはじめる男性学』(集英社新書、2021年)に、「緩やかな排除」という概念が出てくるんですよね。それは主に「非モテ」の男性が大学のサークルなんかで受ける排除のことなんですが、サークルの運営に携わる上で中心的になる人たちというのがいて、その運営から「非モテ」の男性は疎外されている。その人が積極的に関わりにいくと、中心的メンバーは困惑を示すんですよね。要は自分たちから排除するんじゃなくて、男性の側に主体的に排除を選ばせようとしている、というのがそこでなされた主張です。男性を中心的メンバーがからかったり、問題を不問にしたりすることで、取るべきでない選択を取らせてしまうというところに、ナッジとは少し違うと思いますが、似た面があるというのが僕の意見です。
レガスピ: 最近読んだ西井開『「非モテ」からはじめる男性学』(集英社新書、2021年)に、「緩やかな排除」という概念が出てくるんですよね。それは主に「非モテ」の男性が大学のサークルなんかで受ける排除のことなんですが、サークルの運営に携わる上で中心的になる人たちというのがいて、その運営から「非モテ」の男性は疎外されている。その人が積極的に関わりにいくと、中心的メンバーは困惑を示すんですよね。要は自分たちから排除するんじゃなくて、男性の側に主体的に排除を選ばせようとしている、というのがそこでなされた主張です。男性を中心的メンバーがからかったり、問題を不問にしたりすることで、取るべきでない選択を取らせてしまうというところに、ナッジとは少し違うと思いますが、似た面があるというのが僕の意見です。
![]() 吉良貴之: 排除の方法にナッジっぽいものがあるかもしれないという話ですね。この本のテーマは公共政策なので国や自治体が前面に出ていますが、中身としては民間のやることも入っています。思いっきり身近な話としては、サークルの中の人間関係みたいなものも考えられます。先ほど日本にナッジが導入されたら誰がうれしいのかということを話しましたが、ナッジは通常、対話をしない一方的なコミュニケーションなので、楽な場合があるわけですね。わざわざ注意していたら反論されるかもしれなくて面倒なので、「非モテお断り」みたいな貼り紙をしてなんとなくいづらくさせていく、そんないやらしいやり方もあるわけです。でもそういうのも「情報提供型ナッジ」ではある。はっきり言わないでちょっとずついびり出すような文化が日本には至るところにあるんだけれども、そこにナッジみたいなよくわからないものがはびこると怖いかもしれない。というか、日本にはもともとナッジみたいなのたくさんあったでしょ、アメリカからやってきたものをありがたがる必要あるの?という反発の原因でもあると思います。まあ、それに対しては、ナッジは実験的・漸進的なやり方で科学的な装いをしていますよ、というのが応答なんですが、身近すぎる例だとちょっとわかりにくいですよね。
吉良貴之: 排除の方法にナッジっぽいものがあるかもしれないという話ですね。この本のテーマは公共政策なので国や自治体が前面に出ていますが、中身としては民間のやることも入っています。思いっきり身近な話としては、サークルの中の人間関係みたいなものも考えられます。先ほど日本にナッジが導入されたら誰がうれしいのかということを話しましたが、ナッジは通常、対話をしない一方的なコミュニケーションなので、楽な場合があるわけですね。わざわざ注意していたら反論されるかもしれなくて面倒なので、「非モテお断り」みたいな貼り紙をしてなんとなくいづらくさせていく、そんないやらしいやり方もあるわけです。でもそういうのも「情報提供型ナッジ」ではある。はっきり言わないでちょっとずついびり出すような文化が日本には至るところにあるんだけれども、そこにナッジみたいなよくわからないものがはびこると怖いかもしれない。というか、日本にはもともとナッジみたいなのたくさんあったでしょ、アメリカからやってきたものをありがたがる必要あるの?という反発の原因でもあると思います。まあ、それに対しては、ナッジは実験的・漸進的なやり方で科学的な装いをしていますよ、というのが応答なんですが、身近すぎる例だとちょっとわかりにくいですよね。
![]() 幸村燕: レガスピさんの話を聞いてて思ったんですが、ネットでも自殺した人の自由意志を尊重する立場の人ってたまにいると思うんですけど、実際の研究では自殺した人ってゆるやかに追い込まれていたパターンが多いわけじゃないですか。誘導はするけど選択の自由は残しておく、というのを、ナッジという概念を媒介しない場合、「自殺という選択の尊重」という純粋な自由主義やリバタリアン的なもの(ホームレスは選択の結果だ、など)みたいなスタンスになりかねないと思って。むしろそこを透明化する意味で肯定的にナッジを挟むというか。
幸村燕: レガスピさんの話を聞いてて思ったんですが、ネットでも自殺した人の自由意志を尊重する立場の人ってたまにいると思うんですけど、実際の研究では自殺した人ってゆるやかに追い込まれていたパターンが多いわけじゃないですか。誘導はするけど選択の自由は残しておく、というのを、ナッジという概念を媒介しない場合、「自殺という選択の尊重」という純粋な自由主義やリバタリアン的なもの(ホームレスは選択の結果だ、など)みたいなスタンスになりかねないと思って。むしろそこを透明化する意味で肯定的にナッジを挟むというか。
![]() 吉良貴之: そのご指摘も面白いですね。ナッジの思想の背景にある「自由」の尊重に気持ち悪いものが入っていないかということです。実際にはゆるやかに追い込んでいる部分があるんだけれども、それを自由な選択だと見せかけてしまう。これはさっきの「中動態」的なものを能動的に見せかけるのとつながっているのかもしれません。コロナ禍の今、自粛という形でいろんな社会的圧力が利用されているわけですけども、現実に起こっているゆるやかな追い込みが見えなくされてしまうのはたしかに問題です。なので、それが見えるようなナッジを挟むべき場合もあるかもしれない。もちろん見えにくいナッジもあるので、もっと見えるもの、たとえばゴリゴリの強制をして、従わないんだったら罰金を課すぞとか、それくらい見えるようにしてくれたほうがいいんじゃないかとか、規制手段をどれぐらい見えるようにするのがよいかという問題もあります。本当は無意識のうちに誘導しちゃうのが効率がいいかもしれませんが、サンスティーンは、いやそれは自由を保障してないからいけませんよ、透明性を確保しないといけませんよ、と言ってますね(124頁)。ナッジはある程度の人々に脱退(オプトアウト)されることで「失敗」する、それで改善されていくという実験的な営みでもあるんで、まったく見えなくしてしまうと有効なデータが取れないという問題もあります。見えすぎても困るし、見えなくても困る。じゃあ、ちょうどいい程度を実験を通じて確かめていこう、というのがナッジの改善の一つといえます。
吉良貴之: そのご指摘も面白いですね。ナッジの思想の背景にある「自由」の尊重に気持ち悪いものが入っていないかということです。実際にはゆるやかに追い込んでいる部分があるんだけれども、それを自由な選択だと見せかけてしまう。これはさっきの「中動態」的なものを能動的に見せかけるのとつながっているのかもしれません。コロナ禍の今、自粛という形でいろんな社会的圧力が利用されているわけですけども、現実に起こっているゆるやかな追い込みが見えなくされてしまうのはたしかに問題です。なので、それが見えるようなナッジを挟むべき場合もあるかもしれない。もちろん見えにくいナッジもあるので、もっと見えるもの、たとえばゴリゴリの強制をして、従わないんだったら罰金を課すぞとか、それくらい見えるようにしてくれたほうがいいんじゃないかとか、規制手段をどれぐらい見えるようにするのがよいかという問題もあります。本当は無意識のうちに誘導しちゃうのが効率がいいかもしれませんが、サンスティーンは、いやそれは自由を保障してないからいけませんよ、透明性を確保しないといけませんよ、と言ってますね(124頁)。ナッジはある程度の人々に脱退(オプトアウト)されることで「失敗」する、それで改善されていくという実験的な営みでもあるんで、まったく見えなくしてしまうと有効なデータが取れないという問題もあります。見えすぎても困るし、見えなくても困る。じゃあ、ちょうどいい程度を実験を通じて確かめていこう、というのがナッジの改善の一つといえます。
![]() 環原望: これまでの話とずれちゃうかもしれないんですけど、副題にも「自由論と幸福論」とあるように、選択したときの幸福というところが論旨として出てきたと思いますが、僕としては、ナッジはあくまで統治の一つの方法であって、そこで幸福論を持ってくるのはわりと建前かな、と思います。たとえば燃費のいい車を買ったほうが将来的に経済的にお得で安上がりなのに、燃費の悪い車を買ってしまうことで幸福ではなくなっているとか、タバコを吸うことによって将来的に不幸になるとか、個人の主体的な選択の結果不幸になるからその選択が正しくない、というのが論として出てくるんですけど、「燃費のいい車を買った自分」と「燃費の悪い車を買った自分」を比較して結果的にいくら損をしたというのを後から考える人ってあまりいないと思いますし、あくまでも統計的にみてこの人が損をしている、というのは、選択した場合・していない場合をサンプルとして比べてわかる場合であって、その人個人の選択というところで比べる例を自分自身で持っていない場合は幸不幸の軸で考えるのって適切なのかと。大きい統治の側面から見て温室効果ガスが増えて気温が上昇したり、タバコで医療費が増えたり、それは損だからということで長い目で見てナッジをやっていくこと自体は、政策の面では有効とは思いますが、そこと個人の主体的な選択と幸福というところで論じるのはもやっとしました。
環原望: これまでの話とずれちゃうかもしれないんですけど、副題にも「自由論と幸福論」とあるように、選択したときの幸福というところが論旨として出てきたと思いますが、僕としては、ナッジはあくまで統治の一つの方法であって、そこで幸福論を持ってくるのはわりと建前かな、と思います。たとえば燃費のいい車を買ったほうが将来的に経済的にお得で安上がりなのに、燃費の悪い車を買ってしまうことで幸福ではなくなっているとか、タバコを吸うことによって将来的に不幸になるとか、個人の主体的な選択の結果不幸になるからその選択が正しくない、というのが論として出てくるんですけど、「燃費のいい車を買った自分」と「燃費の悪い車を買った自分」を比較して結果的にいくら損をしたというのを後から考える人ってあまりいないと思いますし、あくまでも統計的にみてこの人が損をしている、というのは、選択した場合・していない場合をサンプルとして比べてわかる場合であって、その人個人の選択というところで比べる例を自分自身で持っていない場合は幸不幸の軸で考えるのって適切なのかと。大きい統治の側面から見て温室効果ガスが増えて気温が上昇したり、タバコで医療費が増えたり、それは損だからということで長い目で見てナッジをやっていくこと自体は、政策の面では有効とは思いますが、そこと個人の主体的な選択と幸福というところで論じるのはもやっとしました。
![]() 吉良貴之: 環原さんは幸福ということに着目したわけですね。この本のずるがしこいのはとても身近な例を出しているところなんですよ。たとえば映画を観る順番(40頁)とか、お菓子の配り方(43頁)とか、別に失敗してもどうともないような例を出して、「ナッジっていいよね、失敗してもオプトアウトすればいいよね」というのが納得しやすくなっている。でも、ナッジをやりたい人の本当の狙いは、いかにして社会全体の統治を効率化するかです。サンスティーンは、自分は社会厚生主義者であり、社会全体の「厚生(welfare)=幸福」を最大化するためにナッジを使っている、ということをと言っています(8、138頁など)。要するに、個人個人の身近な幸福なんてわりとどっちでもいいんです。にもかかわらず、出す例は身近なもので納得させておいて、もっと重要なところでナッジを大々的に使おうとしている。まあ、「全体」といってどこまで積極的に考えているのか?という問題はすでに述べたとおりなんですが。
吉良貴之: 環原さんは幸福ということに着目したわけですね。この本のずるがしこいのはとても身近な例を出しているところなんですよ。たとえば映画を観る順番(40頁)とか、お菓子の配り方(43頁)とか、別に失敗してもどうともないような例を出して、「ナッジっていいよね、失敗してもオプトアウトすればいいよね」というのが納得しやすくなっている。でも、ナッジをやりたい人の本当の狙いは、いかにして社会全体の統治を効率化するかです。サンスティーンは、自分は社会厚生主義者であり、社会全体の「厚生(welfare)=幸福」を最大化するためにナッジを使っている、ということをと言っています(8、138頁など)。要するに、個人個人の身近な幸福なんてわりとどっちでもいいんです。にもかかわらず、出す例は身近なもので納得させておいて、もっと重要なところでナッジを大々的に使おうとしている。まあ、「全体」といってどこまで積極的に考えているのか?という問題はすでに述べたとおりなんですが。
■ナッジ的人間観と法的主体
![]() 酒井泰斗: 先ほど話題に出た「中動態」については、コメントと質問があります。
酒井泰斗: 先ほど話題に出た「中動態」については、コメントと質問があります。
「我々の社会生活の非常に多くの部分はオートマティックな振る舞いの織り合わせからできていて、それ自体としては「能動態/受動態」という文法的区別には収まらないものである」というヴィジョンは、それこそ行動科学を含む20世紀中葉の諸学問の流行意匠だったといえるかと思います。そしてこのヴィジョンは、一方では「ナッジ」の発想に馴染みやすいものであり、他方では「自由」「責任」「主体性」といった観念と正面からバッティングするものだということもまた言えるでしょう。しかしこの事態を表すのに、別の文法的カテゴリ──たとえば「中動態」──を持ってきて話が進むとは思えません。そうではなく、文法的カテゴリの方が──我々はこれらのカテゴリを、いつどこでどのように使って何をしているのかの方が──説明されるべきでしょう。それだけでなく「能動態/受動態」に「中動態」を対置することは、あたかも「人間の振る舞いのグループには、〈能動態〉と〈受動態〉のほかに、〈中動態〉と名づけることができるもう一つのグループがある」かのように考える方向へと思考を誘ってしまいます。というわけで、これは いろいろな意味で危険な言葉遣いであるように思います。以上がコメントです。
これを踏まえた上で別の問いを立ててみようとすると「能動的な主体というのはいったいどこに存在するのか」という問いを思いつきます。そういうつもりで探してみると明確な「能動的な主体」を見つけるのは意外に難しいのですが、私が見たもののなかで「これはそうなのではないか」と思った一つは「民法」でした。民法の教科書には「自らの意志を持ち、それを的確に言葉にして表明できる人間と、その表明された言葉を的確に判断して受け入れたり拒絶できる別の対等な人間とのあいだの合意として行われる契約」というヴィジョンが出てきます[9]。これは非常に珍しく相当特殊な、いわば素の「主体的な人間」ヴィジョンだといえるのではないか、と思ったのです。そして──上にも述べたように──このヴィジョンはたしかにナッジのような発想とは折り合いが悪そうです。吉良さんがナッジに関心を持たれたのは、こうした、法的人間像との関係もありましたか?
[9]私が読んだのは、道垣内弘人『リーガルベイシス民法入門』(日本経済新聞出版、2014年)です。ただし数ページ進むとすぐに、この建前を実現するのがいかに難しいかという話が始まり、分厚い頁のほとんどがそちらの話題で埋め尽くされていることに気づきます。
![]() 吉良貴之: 私は法哲学をやってるので法的な人間像っていうのもちゃんと答えられないといけないんですけど、まず、「能動的主体」というのは法制度が普及させた人間ヴィジョンだというのはそうなんですが、では、どういう法制度がそれを普及させたのか。というとまず、民法ですね。自由で対等な主体たちが契約して秩序を作り出す、そういった社会のルールを描き出すのが民法です。こういう主体像はもちろん現実にはない便利なフィクションなんですが、それに修正を迫るような法の領域が社会法ということになります。わかりやすいところだと、消費者法や労働法といった領域では、現実の人間たち(この本でいう「ヒューマン」:23頁)はまったく対等でないし、自由な判断なんかできてないでしょと。なので消費者法だったらクーリングオフを認めるとか、労働法だったら個人じゃ無理なので組合を作って団体で戦えるようにするとか、そういった発想になっていくわけですね。それに対し、ナッジはあくまで選択の自由を押し出しているので、民法的=能動的な主体は崩していないんです。ナッジは法と区別されるもので、そこを根本的に崩すような修正まではかけません。便利なフィクションは保持しながら、でも現実にはちゃんと判断してくれないと困ることもある、なのでナッジで「お手伝い」する、それぐらいの感じかなと。
吉良貴之: 私は法哲学をやってるので法的な人間像っていうのもちゃんと答えられないといけないんですけど、まず、「能動的主体」というのは法制度が普及させた人間ヴィジョンだというのはそうなんですが、では、どういう法制度がそれを普及させたのか。というとまず、民法ですね。自由で対等な主体たちが契約して秩序を作り出す、そういった社会のルールを描き出すのが民法です。こういう主体像はもちろん現実にはない便利なフィクションなんですが、それに修正を迫るような法の領域が社会法ということになります。わかりやすいところだと、消費者法や労働法といった領域では、現実の人間たち(この本でいう「ヒューマン」:23頁)はまったく対等でないし、自由な判断なんかできてないでしょと。なので消費者法だったらクーリングオフを認めるとか、労働法だったら個人じゃ無理なので組合を作って団体で戦えるようにするとか、そういった発想になっていくわけですね。それに対し、ナッジはあくまで選択の自由を押し出しているので、民法的=能動的な主体は崩していないんです。ナッジは法と区別されるもので、そこを根本的に崩すような修正まではかけません。便利なフィクションは保持しながら、でも現実にはちゃんと判断してくれないと困ることもある、なのでナッジで「お手伝い」する、それぐらいの感じかなと。
![]() 酒井泰斗: 民法は古く消費者法や労働法は新しいものですが、民法的な強い主体を調整する作業は社会法その他とのあいだですでに行われてきたものであって、「ナッジ」についての議論もその成果の上でおこなわれている、と考えればよいでしょうか。たしかに例えば製造物責任法は「自由で能動的な・責任を引き受ける主体」という人間観とは相当にかけ離れたものに見えますよね。
酒井泰斗: 民法は古く消費者法や労働法は新しいものですが、民法的な強い主体を調整する作業は社会法その他とのあいだですでに行われてきたものであって、「ナッジ」についての議論もその成果の上でおこなわれている、と考えればよいでしょうか。たしかに例えば製造物責任法は「自由で能動的な・責任を引き受ける主体」という人間観とは相当にかけ離れたものに見えますよね。
![]() 吉良貴之: そうですね。民法的な主体像そのままだとうまくいかないので、現代的な社会法だけでなくその他たくさんの法で、というか民法の中でも、昔からいろいろと修正をかけてきた歴史があります。ナッジもその知見を踏まえていますが、法律と違うのは、従わなくていいですよ、と最初から言ってるところですかね。法律はまあ、従わなくていいですよとはいえない。実際には必ずしも従われることを想定しないでとりあえず作った、みたいなメッセージ型の法律もあるので、そういうのはナッジぽいんですが。
吉良貴之: そうですね。民法的な主体像そのままだとうまくいかないので、現代的な社会法だけでなくその他たくさんの法で、というか民法の中でも、昔からいろいろと修正をかけてきた歴史があります。ナッジもその知見を踏まえていますが、法律と違うのは、従わなくていいですよ、と最初から言ってるところですかね。法律はまあ、従わなくていいですよとはいえない。実際には必ずしも従われることを想定しないでとりあえず作った、みたいなメッセージ型の法律もあるので、そういうのはナッジぽいんですが。
あと社会法ということで付け加えると、経済法も重要な領域ですね。自由で対等な主体が取引すれば政府が介入しなくても市場はうまくいく、というのも重要なフィクションですが、そういった市場観にも修正がかけられますし、そういう目的のナッジもあります。
■本書を訳した経緯
![]() 吉良貴之: 次に、私がどんな関心でこの本を訳したのかというと、去年ナッジのイベント(那須耕介・橋本努・吉良貴之・瑞慶山広大『ナッジ!したいですか?されたいですか?:される側の感情、する側の勘定』勁草書房、2020年)に呼ばれた延長というのもあるんですが、研究関心としてもっと内在的な点では、最近、アメリカの公法学の新しい潮流に興味を持っております。この本の前に訳したエイドリアン・ヴァーミュール『リスクの立憲主義』(勁草書房、2019年)もそうなんですが、あまり原理原則で考えない。使えるものはなんでも使おうというプラグマティックな考え方があるんですね。もうちょい学問的にいうと、他の領域の成果をどんどん取り込んで、公法学を総合的な社会科学に組み替えようとしている。でも少なくとも日本ではまだこういう考え方はとっつきにくいところがあって、それをちゃんと理解したいなということでやってみたというのがあります。今回の『入門・行動科学と公共政策』はあくまで入門書なので、研究としての展開は今後にご期待ということで。
吉良貴之: 次に、私がどんな関心でこの本を訳したのかというと、去年ナッジのイベント(那須耕介・橋本努・吉良貴之・瑞慶山広大『ナッジ!したいですか?されたいですか?:される側の感情、する側の勘定』勁草書房、2020年)に呼ばれた延長というのもあるんですが、研究関心としてもっと内在的な点では、最近、アメリカの公法学の新しい潮流に興味を持っております。この本の前に訳したエイドリアン・ヴァーミュール『リスクの立憲主義』(勁草書房、2019年)もそうなんですが、あまり原理原則で考えない。使えるものはなんでも使おうというプラグマティックな考え方があるんですね。もうちょい学問的にいうと、他の領域の成果をどんどん取り込んで、公法学を総合的な社会科学に組み替えようとしている。でも少なくとも日本ではまだこういう考え方はとっつきにくいところがあって、それをちゃんと理解したいなということでやってみたというのがあります。今回の『入門・行動科学と公共政策』はあくまで入門書なので、研究としての展開は今後にご期待ということで。
![]() 酒井泰斗: ドイツ人だと「原理原則にしたがって事例を系統的に整理する」というのをやってくれるんですが、アメリカ人はひたすらケースを積み上げていくので付き合うのがたいへんなんですよね。今日は「公法でもそうだった」と教えていただき、感慨深いです。
酒井泰斗: ドイツ人だと「原理原則にしたがって事例を系統的に整理する」というのをやってくれるんですが、アメリカ人はひたすらケースを積み上げていくので付き合うのがたいへんなんですよね。今日は「公法でもそうだった」と教えていただき、感慨深いです。
後編は次週公開いたします。お楽しみに。[編集部]
■参加者紹介■
★Website: https://jj57010.web.fc2.com
★Website: http://socio-logic.jp
 2021年7月刊行!
2021年7月刊行!キャス・サンスティーン 著/吉良貴之 訳
『入門・行動科学と公共政策 ナッジからはじまる自由論と幸福論』https://www.keisoshobo.co.jp/book/b584353.html
ISBN:978-4-326-55086-9 四六判・192ページ 価格1,980円(税込)
ナッジの使い方から思想まで、本家サンスティーンによるコンビニエンスストア開店! ポスト・コロナ時代の新たな公共政策へ!
※本書の「目次扉(要約)」「第1章 イントロダクション」「訳者あとがき」をたちよみ公開しています。→【こちらでご覧ください】
 2020年12月刊行!
2020年12月刊行!那須耕介・橋本努・吉良貴之・瑞慶山広大 著
『ナッジ! したいですか? されたいですか? される側の感情、する側の勘定』https://www.keisoshobo.co.jp/book/b553349.html
ISBN: 978-4-326-99955-2 電子書籍のみ 価格550円(税込)
2020年8月に開催された『ナッジ!?』刊行記念のオンライン・トークイベントの内容を1冊にまとめました。法哲学と憲法の若手研究者二人が『ナッジ!?』編者二人と討議するとともに、イベント参加者からたくさんもらった質問にていねいに答えたやりとりは、巷間話題にのぼるナッジのさらなる理解に役立つ内容です。

