あとがき、はしがき、はじめに、おわりに、解説などのページをご紹介します。気軽にページをめくる感覚で、ぜひ本の雰囲気を感じてください。目次などの概要は「書誌情報」からもご覧いただけます。
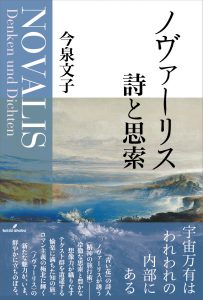 今泉文子 著
今泉文子 著
『ノヴァーリス 詩と思索』
→〈「まえがき」(pdfファイルへのリンク)〉
→〈目次・書誌情報・オンライン書店へのリンクはこちら〉
*サンプル画像はクリックで拡大します。「まえがき」の本文はサンプル画像の下に続いています。
まえがき
おりしも二〇二二年は、ノヴァーリスことフリードリヒ・フォン・ハルデンベルクの生誕二百五十年にあたる。
近代の幕開けから現代へいたるこの二百五十年のあいだに輩出した数多い詩人・作家たちのなかでも、〈ドイツロマン派〉のノヴァーリスほど極端な毀誉褒貶にさらされつつ、しかもなお現代思想のなかで意味深く取り上げられている作家は、他にあまり例を見ない。
夢に見た青い花を求めて旅をゆくという体裁の小説『ハインリヒ・フォン・オフターディンゲン〔青い花〕』や、昼を厭い、夜や死の世界に憧れるという内容の長詩『夜の讃歌』で世に知られることになったノヴァーリスは、「ロマン主義の精華」とも呼ばれ、かれと、そしてロマン主義とは、このような現実離れした夢想的なものとしてまさしく〈ロマンチック〉に受容されていった。
固定化されたイメージから脱却するのは難しい。日本での受容にかぎってみても、その初期には、「月朦朧なる夜の世界にあこがるゝは、ロマンチックの特徴なり」と藤代禎輔(東京帝国大学独文科の最初の日本人講師)がまとめれば、北原白秋は『邪宗門』の一章を「青き花」と題し、「わが羅曼底時代のあえかなる思出のために、この幼き一章を過ぎし日の友にささぐ」と扉書きするなど、まことに〈ロマンチック〉に受け取っている。その一方、ロマン主義は「日本浪漫派」などのナショナルな反動思想に取り込まれたりもして、ノヴァーリスやロマン主義に対しては「現実離れ」、「幼稚」、あるいは「反動」などと烙印を押され、あたかもDNAのように日本人の体内に消しがたくしみ込んでいるようでさえある。
わたしが、美学科でヘーゲルの『美学』の演習を受け、カントの『判断力批判』とドイツ文芸学を特別演習として学んだのち、実際の〈作品〉に向き合うべくドイツ文学専門課程に移ったとき、自分の研究対象をノヴァーリスと決めることにしたのはたまたまのことではなかった。というのも、かねてから〈ドイツ〉に関して問題とすべきはナチズムとロマン主義と思い定めていたからである(前者については、ミュンヘン大学での研究滞在のもとに『ミュンヘン 倒錯の都 ─「芸術の都」からヒトラー都市へ』筑摩書房、一九九二年、として上梓した)。
当時ロマン主義を「〈いま・ここ〉にないものを求めて衝迫する思想」と思っていたわたしの修士論文のタイトルは「浪漫的憧憬とはなにか」というえらく大時代的なものであった。世界の若者が圧制的な権力機構に対して抗議の声をあげ、「〔ノヴァーリスの〕あの青い花は赤いのだ」とパリの学生たちが壁に大書する頃、ノヴァーリスやフリードリヒ・シュレーゲルの大部の批判校訂版が出版されだす。一九七〇年前後のこうした世界の変容と、圧倒的な批判校訂の仕事に支えられ、ロマン主義のいわば革命的な要素と、極めて理知的な哲学的要素とがようやく明らかにされていくようになった。
二百五十年ほど前の一八世紀末、産業革命とフランス革命に象徴されるように、封建制から資本主義へ、身分制社会から市民社会へとドラスティックな変貌を遂げるヨーロッパに、その変化に対峙するようにして思想・芸術の分野に革新をもたらす〈ロマン主義〉という思潮が登場した。以後、ロマン主義は、一九世紀の前半にかけてイギリス、ドイツ、フランスその他の国で、それぞれ独自の様相を示しつつ展開・変貌をとげていった。
このように地域的にも時代的にも広範な広がりをもつロマン主義を概括的に語ることは、教科書的には不可能でないにしても、その粗い網の目からは多くのものがこぼれ落ちてしまうにちがいない。であるとすれば、ひとつに局限してそこから広げていくような手法をとるのがいいだろう。それはひとつの国か、ひとつの詩派か、ひとりの詩人か、ひとつの詩句か。
本書は、「ドイツ初期ロマン派」に数え入れられるノヴァーリスについて、その思索と詩作のありようを探求するものである。
ノヴァーリスが書き遺したものは、未完の小説ふたつ(『ハインリヒ・フォン・オフターディンゲン』と『サイスの弟子たち』)、数多くの詩(長詩『夜の讃歌』、『聖歌』のほか、若書きの詩も多い)、講演風の小論(『キリスト教世界、またはヨーロッパ』)やアフォリズム風の作品(『信仰と愛』)などのほか、夥しい数の断章(最初の断章集は「花粉」と題されて「アテネウム」誌に掲載、またロマン主義的百科全書の試み「一般草稿」のほか、多方面にわたる思索を書きつけた大量の断章がある)や、研究ノート(膨大な「フィヒテ研究ノート」やカント、ヘムステルホイスなどの哲学研究ノート、フライベルク鉱山学校時代の「自然科学研究ノート」など)があり、また、ロマン主義解明にも意味深い多くの書簡や日記がある。
ハルデンベルクは夭折した。しかし、じつに大量の断片から成り立つ「ノヴァーリス」という思索圏は、ひとつひとつの断片がなおも生命を孕んで燃え上がろうとしている。この迷宮じみた思索圏に分け入るためにはアリアドネの糸が必要である。その導きの糸に選んだのが、『オフターディンゲン』に挿入されたメルヒェン、通常「クリングゾールのメルヒェン」と呼ばれるものである。
さらに、かれの思索のありようをより理解するためにいくつかの補助線を引いた――それはわたしの好きな思想家や詩人の文言である。あまりに恣意的だろうか? しかし、「読み手はそもそもひとつの本から自分の欲するものを創りだす」とはノヴァーリスの言葉である。本書は、この言葉に勇気づけられながらのひとつの〈読み〉の旅となった。ともに歩んでいただければ幸いである。
*追補
ドイツ初期ロマン派とは、ロマン主義の誕生を目の当たりにさせてくれるような機関誌「アテネウム」に拠ったか、その周辺にいた面々、すなわち、ノヴァーリスとその盟友F・シュレーゲル、その兄のA・W・シュレーゲル、神学者のシュライアーマッハー、作家のルートヴィヒ・ティークとその親友ヴァッケンローダー、哲学者のシェリングなどである。後期ロマン派とされるのは、機関誌「隠者新聞」に拠ったアヒム・フォン・アルニムやクレーメンス・ブレンターノなどで、初期ロマン派のような哲学性はなく、ドイツの古い民謡を掘り起こすなど(『少年の魔法の角笛』)、復古主義的でナショナルな傾向をもつとされる。また、多才・多作のホフマンや、抒情詩にすぐれたアイヒェンドルフなども後期ロマン派に数え入れられる。






