あとがき、はしがき、はじめに、おわりに、解説などのページをご紹介します。気軽にページをめくる感覚で、ぜひ本の雰囲気を感じてください。目次などの概要は「書誌情報」からもご覧いただけます。
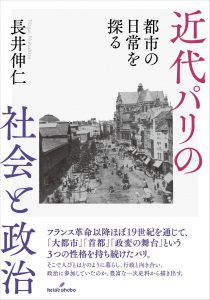 長井伸仁 著
長井伸仁 著
『近代パリの社会と政治 都市の日常を探る』
→〈「序章」(pdfファイルへのリンク)〉
→〈目次・書誌情報・オンライン書店へのリンクはこちら〉
*サンプル画像はクリックで拡大します。「序章」本文はサンプル画像の下に続いています。
序章
本書は、一九世紀のパリがいかなる社会であり、人びとはどのように暮らしていたのか、そこでは行政はいかに機能し、政治はどのように争われていたのかなどについて、いくつかの観点から考察することを試みるものである。
この目標を設定した理由と考察の際の観点を述べるため、まずこの時期のパリの特徴を概括し、ついで先行研究がもたらした成果を確認したい。
一 一九世紀のパリ
パリはフランス革命以降ほぼ一九世紀を通じて、「大都市」「首都」「政変の舞台」という三つの性格を持ちつづけた。いずれもたいへんよく知られた側面ではあるが、順に確認しておきたい。
パリは近世以降、フランス国内はもちろんヨーロッパでも屈指の大都市であった。宗教戦争がはじまる一五六〇年代、フランス王国の人口は約一三六〇万であったが、パリのそれは三〇万に達していたとみられる。パリの人口はその後も増加をつづけ、一七〇〇年時点では五三万、一七八九年の革命勃発時には六〇万前後の住民を擁していた。近世のフランスでパリに次ぐ規模の都市は、一六〇〇年頃であればリヨンで約九万人、一七〇〇年頃はマルセイユで約八万八〇〇〇人、一八〇〇年頃はリヨンとマルセイユがほぼ同水準で約一一万人であった。パリは国内では文字どおり群を抜く存在であった。ヨーロッパ全体をみると、一七〇〇年時点で五〇万人以上の住民がいた都市はロンドン(五五万人)とパリのみであった。
一九世紀に入ると人口増加のペースは上昇する。革命期に六〇万前後であったパリの人口は、一九世紀半ばには一〇〇万を超え、第一次世界大戦前夜には二八八万に達した。この間、いわゆるパリ改造にともない一八六〇年に市域が三四平方キロメートルから七八平方キロメートルへと拡大していたが、それを考慮しても爆発的といって過言ではない増え方であった。
この増加の大部分は人口流入によりもたらされていた。一八二一〜一八九〇年のパリの人口増の内訳は、自然増すなわち出生と死亡の差によるものが一五%、社会増すなわち転入と転出の差によるものが六四%、市域拡大によるものが二一%であった。一九世紀後半のロンドンでは自然増が八四%を占めていたことを考えると、パリへの人口流入がいかに大規模なものであったのかがわかる。このような社会増は、自然増にもまして大きな影響を都市社会に及ぼすと考えられる。都市の物質的基盤が構築の途上にあり、社会保障がいまだ存在せず各種のセーフティーネットも脆弱であった時代に、地域の共同性の枠外から大量の人びとが移入してくることは、貧困、疫病、失業などのリスクを高めることと同義であったといってよい。そしてそれは、政治的な不安定さを高めることでもあったはずである。
パリは、このような大都市であっただけでなく首都でもあった。現在のフランスには日本と同様に首都を規定する法令はなく、歴史上も宮廷が各地を移動していた時期やヴェルサイユに置かれていた時期もあったとはいえ、フランス革命以後は今日に至るまで、戦争中など例外的な時期を除いて、パリは政府、議会、省庁などの所在地でありつづけている。
首都と位置づけられ国家機構の所在地になることが当該都市に際立った重要性を与えることは、英語やフランス語の « capital / capitale » が語源において「頭部」を意味していたことにもうかがえるが、中央集権的な性格が強いとされるフランスにおいてはとりわけ大きな意味を持ったと考えられる。国制のあり方を超歴史的に単純化することは控えねばならないにしても、フランスでは二一世紀の現在でも、国が有する権限を自治体に委譲する「分権化dé centralisation」が進められていること自体、中央集権的な性格が現実のものであることの証左である。そして、国家の中央集権的な性格が「ジャコバン的」との形容で批判されてきたことに明らかなように、フランス革命はこの点で画期をなしている。
そのような国家の首都であることは、右にみた人口上の突出した比重と相まって、パリの政治的な重要性を高めた。この重要性は一九世紀に顕著になる。
革命以後のフランスで頻繁に生じた体制交代は、一八一四年および一八一五年の二度の王政復古を除き、直接にはパリで発生した出来事によってもたらされた。一八三〇年の七月革命と一八四八年の二月革命はいずれもパリで起こり、どちらも三日で体制交代に至った。一八五一年一二月のルイ= ナポレオン・ボナパルトによるクーデタも、これへの反動が全国各地で発生したことは重要であるが、クーデタそのものはパリで遂行され、国会議員が捕縛されるなどして第二共和政は空洞化した。一八七〇年九月の体制交代に際しては、パリよりも早くリヨンやマルセイユで共和政宣言がなされたが、帝政の廃止はパリでの共和政宣言が県行政を通じて各地に伝えられたことで確定した。
以上に確認した一九世紀パリの三つの特徴は、いずれもフランス史の基本的な事柄というべきであり、歴史叙述は枚挙にいとまがない。しかしながら、多様な出自の住民から構成され、突出した人口規模と政治的重要性を持つこの都市の歴史には、解明すべき部分が少なからず残されている。このことを研究動向にもとづきつつ確認したい。
二 研究史から展望する
一九世紀パリにかかわる研究は、大別すれば、(一)政治史や社会史・文化史の観点からなされ、地理的枠組がパリと重なるかパリを含むもの、(二)都市としてのパリに視座を据えつつ一九世紀の一定期間を対象とするもの、の二つがある。
(一)について、先にふれたように革命以降の政変はパリを中心的舞台としたため、近代フランスの政治史研究は、それが国政にかかわる限りパリ史研究の部分をおのずと含むことになる。また、パリでは貴族やブルジョワジーから職人や労働者に至るまで多岐にわたる社会集団が存在しているため、こうした社会集団を取り上げる研究も、パリが事例に含まれることが多い。(二)については、都市基盤や住宅問題を対象とするものが典型的である。もっとも、「オスマンのパリ改造」がそうであるように都市の物質的次元にも国政や市政は深く関連しているのであり、研究は多かれ少なかれ政治史の観点をとることになる。
このように実際には両方の側面を備える研究も少なくないが、それでも、これまで(一)が前面に出る研究が相対的に多かったことは間違いない。革命以後のフランスにおいて政変が頻繁に生じたこと、政変に貴族やブルジョワジーなど社会集団が重要な役割をはたしたと長く考えられてきたこと、あるいはそれら社会集団が文化的にも特徴を備えた存在とみなされたことなどが研究の動因となり、数多の成果を生み出してきた。
それに比べて(二)が少ないのは、相対的な問題であることに加え、この観点からの研究をおこなう動向が強いとはいえなかったことも背景として指摘できる。端的に述べれば、都市史研究の進展がイギリスなどに比べて遅れていたのである。
フランスでは、近代史研究において都市は長く社会学者や建築家の領域とみなされており、多くの歴史研究者が都市に目を向けるようになるのは一九七〇年代であった。加えて、パリの場合は「中央」や「中心」と同義の存在として扱われることが多く、都市としての側面はそうした観点からの叙述の陰に隠れがちであった。
一九世紀のパリを対象とし、その都市としての側面に注目した歴史研究の先駆的なものとしては、一九五〇年代に発表され、パリの人口現象を経済構造や犯罪などの社会現象と関連づけて研究したL・シュヴァリエの一連の著作が挙げられる。また、A・ドマールは、一九六〇年代前後に盛んであった社会構造研究の観点から、立憲王政期(一八一五〜一八四八年)におけるパリのブルジョワジーの資産、経済活動、居住街区などを詳細に分析した。
一九七〇年代には都市史研究も増えはじめるが、この時期の成果を代表するのが、G・ジャックメとJ・ガイヤールの学位論文である。ジャックメは、パリ屈指の労働者地区とみなされていたベルヴィルを主題として、土地と住宅、商工業、人口、社会階層、疫病、社会運動などの観点から一九世紀全体を詳細に考察した。とくに人口については、民事籍簿などを活用して空間的移動や社会的上昇を住民個人のレベルで明らかにしており、一九世紀フランスを対象とする社会史研究がマクロからミクロへと焦点を絞る流れに棹さしていた。ガイヤールは、改造事業の只中にあった第二帝政期のパリについて、事業そのもののほか、人口、学校教育、公的扶助、商工業などについて調査をおこない、工業化が進むなかでも小規模の作業場(アトリエ)や商店が都市社会の骨格をなしつづけたことを明らかにした。
一九八〇年代になると、フランスの都市史研究は精度を高めただけでなく射程においても広がりを見せた。その際の牽引役となったのはパリ郊外についての研究であった。パリの膨張は一九世紀後半に入ると行政上の市域を越えて郊外にも及ぶようになった。そこではパリ市内に比べて基盤整備が遅れていたことに加え、外部からの流入人口の比率が急速に高まったため、地域社会は脆弱さを増した。そうした社会や、そこで展開される政治に注目した個別研究が、一九八〇年代以降、蓄積されるようになったのである。初期の研究を代表するものは、J・P・ブリュネによるサン・ドニ、そしてA・フルコーによるボビニの研究であり、いずれも中心的な対象時期に両大戦間期を含んでいる。両大戦間期のパリ郊外では共産党が強い勢力を形成し、「赤い郊外」の異名が与えられるに至ったが、研究においてはそうした政治勢力の地域的な基盤や、それが構成、運営する市政が主要な分析対象になり、社会経済史と政治史の複雑な連関が析出された。とりわけフルコーの研究は、「赤い郊外」という表象と都市社会の現実との相互作用を、共産党市政の活動や住民の社会的結合などに注目しつつ考察したものであり、総体的な現象としての現代都市を浮かび上がらせたものとして画期的であった。このような、社会経済的な格差と、それを強化する偏向した認識により特徴づけられるパリ郊外は、自治体や街区を単位とした数多くの個別研究を生み出した。そのなかでパリもあらためて対象とされるようになり、郊外も含めた都市圏の枠組みのなかで研究が進められている。
これらパリ郊外を対象とする研究の多くは、この地が都市問題や社会問題が凝集されている地域として注目されるようになった両大戦間期以降に重心をおいている。それに対し、一九世紀についての近年の研究は、当時は拡大がはじまって間もなかった郊外よりも、パリそのものが研究対象になることが多い。ここでそれらを網羅的に紹介することはできないが、重要と思われる動向を述べておきたい。
ひとつには、歴史研究全体の動向を反映するかたちで、文化史の視角が重要な位置を占めていることである。明快な例は、文化を担う集団や制度を取り上げた研究であり、とくにC・シャルルはパリとヨーロッパ主要都市との関係史や比較史を精力的に構築している。
一九世紀フランス史研究ではつねに枢要な位置を占めてきた政治史についても、文化を対象に含めることは不可欠になりつつある。公的空間でおこなわれる顕彰や追悼は、メディアが限られていた一九世紀にあって、政治的意見を表明する場として、あるいはそれへの支持を獲得する場として重要であったことが明らかにされている。七月革命や二月革命は、当初は「勝者」の言説と見解に沿って解釈され、のちには参加者の社会経済的な様態にもとづいて説明されてきたが、現在では、出来事にかかわった人びとの心性や表象という意味での文化を視野に入れて研究することが一般的になっている。L・アンケルは、一八四八年二月から一八五一年一二月までにパリで発生した革命や蜂起に参加した人びとを取り上げ、彼ら彼女らを対象に行政や司法が作成した種々の調書と、そこに添えられた上申書を史料にして、参加者の様態から経験の描写すなわち「語り」までを幅広く分析している。このように文化史の視角を積極的に取り入れることは、一九世紀フランスを政治体制単位で、もしくはそれらの集積として理解するのではなく、より長期的な展望から認識するという動向の帰結であり、またそれを促してもいる。
都市パリの物質的な側面に関しては、急激に進展する都市化を背景に、いわゆる都市改造事業だけでなく、公共交通や環境汚染についての研究が進められている。民衆の日常生活については、文化史の視角を取り入れた研究が積み重ねられているほか、徴兵記録、民事籍簿、選挙人名簿(有権者名簿)などの情報を集積して再構成したJ・C・ファルシとA・フォール、パリ公的扶助局Assistance publique de Paris や治安判事の史料を活用したB・ラトクリフとC・ピエットらによる社会史研究が重要な知見をもたらした。これら研究によって、一九世紀のパリは、かつてシュヴァリエが「危険な階級」を主役に描いたような歴史像とは異なり、移住者を包摂しうる都市、民衆が日々の暮らしを送ることを可能にする都市であったことが示されている。より近年の研究では、M・グリボディが、革命時の国有財産売却を一因とする空間的・社会経済的変容と、その変容のなかで形成された民衆の豊かな社会的結合を明らかにし、そこから一九世紀前半の革命を捉えようと試みている。
かつてジャックメが取り組んだ街区レベルでの詳細なモノグラフとしては、近年、J・L・ロベールが第一四区のプレザンス街区を取り上げ、政治から余暇に至るまでの多様な事象を街区の刊行物など膨大な史料にもとづき描き出している。
本書はこれら先行研究を踏まえ、その成果を活かしながら、一九世紀パリの社会・行政・政治の諸側面を考察するものである。その際、大きく二つの目標を設定したい。ひとつには、人びとの日常生活を紐帯と文化の両面から明らかにすること、もうひとつには、行政や政治を、人びとの日常生活との関連のなかで明らかにすることである。
第一の目標は、端的に民衆の社会史・文化史といってもよい。この領域は二〇世紀中葉から今日に至るまで研究が継続してなされ、先に述べたように新たな史料の開拓も進んでいる。日本でも喜安朗、相良匡俊、木下賢一、福井憲彦、赤司道和、中野隆生らが、文書館史料を積極的に利用しつつ精緻で生彩に富んだ研究を公表し、水準を大きく引き上げた。そのような流れのなか、街区や街路に分け入って住民の日常に迫る研究もいまではめずらしくないが、本書は、できるだけパリ全体を見渡せる位置に立ち、そこから、日常生活における紐帯や、言語や宗教などの文化事象が、パリという都市のなかでどのように存在していたのか、それが都市社会をいかに作り上げていたのかを考察したい。
この課題に取り組むにあたり、労働がきわめて重要な事象であることは言を俟たない。一九世紀のパリでは、大多数の住民は何らかの労働に従事しており、それにより自身の生存をかろうじて確保していた人びとも多かった。また、社会や階層のあり方が現在ほど複雑ではなかった当時、帰属意識や社会観もしばしば労働の場で形成され、それに強く規定されていた。歴史研究においても、労働をめぐっては膨大な数の研究が蓄積されており、右に挙げた日本のフランス史研究もそこに含まれる。本書としては、言語や宗教に注目することにより、従来の研究を補完することを目指したい。
一九世紀のパリは、人口構成をみると、出自や属性の異なる人びとの「るつぼ」といって過言ではなかった。フランス国内の諸地方において出生した後、何らかの理由で上京してパリに居住していた人びとの割合は、一八三三年で四一%、一八九六年には五〇%を超えていた。外国人の割合も多く、一八五一年時点でパリの人口の五%、一八八六年には八%を占めていた。フランスがほぼ一九世紀を通して言語的・文化的に多様な国であった事実を考えると、そうした多様性がパリにどのように反映していたのかを考察することは重要であると考えられる。宗教についても、近世にはじまる非キリスト教化の流れがあったとはいえ、信仰を維持し実践していた人びとが今日よりもはるかに多かった時代に、都市社会における宗教事象のあり方や重みの考察が同じく重要であることは間違いない。
第二の目標については、行政や政治についての歴史研究が、現実における機能や地域社会との関連を対象に含めてなされるのが一般的になっていることを考えれば、当然のものともいえる。ただ、本書が注目して取り上げる政治は、革命や蜂起などの非日常的な政治変動ではなく、選挙という制度化された過程であり、この点でパリを対象とした研究はいまでも多くはない。普通選挙がはじまった一八四八年以降をみると、第三共和政期の下院議員選挙を主題とした社会学者ジアールの学位論文、一九世紀末の社会主義者を対象とした政治学者オフェルレの学位論文があるが、いずれも未刊行である。その後、政治史研究者Y・コンボーが第三共和政期のパリ市議会議員選挙を概観してまとめたものの、パリにおける選挙の重要性を考えると研究は少ないままである。いっぽうで、都市史研究において選挙が取り上げられることも少ない。一九世紀前半を対象にしたシュヴァリエや第二帝政を対象としたガイヤールが選挙の分析をほとんどおこなわなかったのは、この時期の選挙制度の性格を考えれば理解できるものである。この点で、ベルヴィルを取り上げたジャックメやプレザンスについてのロベールの研究は、住民たちが政治にどのようにかかわり、いかなる議員を選出していたのかを分析しており、貴重な成果となっている。本書では、議員を務めた人物を軸にして、政治と社会の両方を視野に収めた研究を試みたい。
行政については、本書は警察組織に注目する。一九世紀のパリで発生した革命や蜂起に対しては軍隊が頻繁に動員されていたが、日常的な秩序の確保も行政や為政者にとって優先度の高い課題であった。当時は軍隊もその役割を担っていたが、専門的な組織としては警察が存在しており、パリでも段階的に拡充された。警察の組織については法制史研究などによりはやくから明らかになっていたが、現実の活動に関する研究がはじまったのは比較的最近である。本書では、近年の研究による成果のほか、警察制度をめぐり市政や国政でおこなわれた議論を読み直すことで、行政が警察を通してどのように住民を掌握しようとしていたのかを考察する。
三 本書の構成
以下に本書の構成を示しておきたい。
第Ⅰ部「社会と文化」では、民衆層を中心とした住民の社会的・文化的な様態を扱う。
第一章では、一九世紀フランス都市において、住民はいかにしてみずからの生存を確保していたのか、生きるためにどのような紐帯を形成していたのか、そして教会や行政はどのような対応や政策を用意していたのかを概観する。また、その作業を通じて研究動向を振り返り、これから取り組まれるべき主題についても考えたい。
第二章では、一九世紀のパリで住民の言語的・文化的特性がどのように表れていたのか、都市社会はそれにどのように規定されていたのかを、カトリック教会の認識と活動を通じて考察する。教会は、革命と共和政が文化的統一を志向していたことへの対抗から、そのような特性を擁護する傾向にあったため、重要な視座を提供しうる。
第三章では、急速に膨張する都市社会を前にしたカトリック教会の対応を取り上げる。一九世紀にパリ市内で実施された教区の再編と、二〇世紀にパリ郊外で進められた聖堂建設を考察し、それを通じて、近代都市における宗教事象の理解につなげたい。
第四章では、一八七二年にはじまるパリ民事籍簿復元事業を取り上げる。コミューンの際の火災によりパリ住民に関する多数の記録が焼失したが、国と市は四半世紀かけて相当量の資料を復元した。その事業を振り返ることで、行政による住民個々人の把握について、行政や住民自身がどのように考えていたのかを考察する。
第Ⅱ部「行政と市政」では、行政や市政のあり方と機能を、住民との関連のなかで研究する。
第五章では、パリにおける警察機構である警視庁を取り上げ、組織の規模や特徴を概観したうえで、活動の実態の一端を明らかにする。とくに、警察制度の拡充を進めた第三共和政が、警察による秩序維持をどう考え、それをどのような目的に用いていたのかを、警視庁をめぐっておこなわれた議論と、外国人の監視の実態を通じて考察する。
第六章では、プロソポグラフィ(集団的人物誌)について、手法としての特徴を確認し、その意義と射程を考える。個々人にかかわる史料群を体系的に分析するこの手法は、自明のものとされがちであった諸集団を研究の俎上に載せたという点で、フランス近現代の歴史像を刷新し、社会史研究の進展に寄与したことを明らかにしたい。
第七章では、前章で述べたプロソポグラフィの手法を用いて、一八七一〜一九一四年のパリ市議会議員を、出自、経歴、資産などと政治潮流とを関連させつつ分析する。第三共和政を樹立した共和派は「新たな社会階層」の到来を謳ったが、それがパリ市議会において実現していたといえるのかどうかを実証的に考察したい。
第八章では、第七章で考察した市議会議員が、どのようにして選挙に出馬するに至り、選挙運動をどのように展開していたのかを、具体的な事例に則して描き出してみたい。その際、一八八〇年代後半にフランスを席巻し、パリの選挙でも多数の支持を得たブーランジスムを事例とする。
第九章では、日本で盛んに刊行されている自治体史が、フランスではどのように編纂されているのか、その背景は何かなどについて、歴史学の研究動向とも関連させつつ考察する。
本書の巻末にはパリの行政区や教区の地図を付している。適宜参照されたい。
(注は割愛しました)







