あとがき、はしがき、はじめに、おわりに、解説などのページをご紹介します。気軽にページをめくる感覚で、ぜひ本の雰囲気を感じてください。目次などの概要は「書誌情報」からもご覧いただけます。
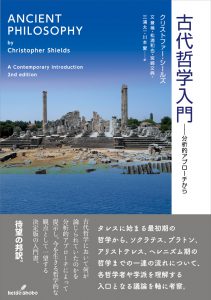 クリストファー・シールズ 著
クリストファー・シールズ 著
文 景楠・松浦和也・宮崎文典・三浦太一・川本 愛 訳
『古代哲学入門 分析的アプローチから』
→〈「序文」「訳者解説」(pdfファイルへのリンク)〉
→〈目次・書誌情報・オンライン書店へのリンクはこちら〉
*サンプル画像はクリックで拡大します。「序文」「訳者解説」本文はサンプル画像の下に続いています。
序文
哲学は、西洋のとある時期のとある場所、つまり前6 世紀後半のギリシア、小アジア沿岸にて誕生した。その最初の歩みはごく小さな一歩を積み重ねることで始まったが、ソクラテス(紀元前469-399 年)の生と死を経て、哲学はある意味では驚くほど急激に花開いた。この1 人の男は、どうやらほぼ独力で次のことを成し遂げたと思われる。すなわち彼は、人間存在の性格と方向性に関する広大でまとまりの薄かった一群の問いを、それ独自の目的と方法を持つ1 つの学問へと昇華させたのである。
もとより、哲学が追い求める問いは、哲学のみが独占するようなものではない。それどころか、哲学者が追い求める主題の多くを、ギリシアの偉大な悲劇作家や叙事詩人たちが検討している場面に出くわすのは、簡単なことである。しかし、次に述べるアプローチをひたむきで断固とした態度で導入したのは、まさにソクラテスだったと思われる。彼は、すべての内省的な人々が関心を持つ問い(人間の幸福の本性、人間が到達しうる最良の生のあり方、徳と自己の利益の関係、そして、人間の生の究極的な価値といったものに関する問い)に対して、哲学固有のアプローチ─分析的アプローチ─を導入したと考えられている。これらの問題に分析的アプローチを導入するさい、ソクラテスは大抵いつも、徳や幸福の本性、自己の利益、人間の善に関する、拍子抜けするほど単純な問いを投げかける。われわれは皆、幸福とは何かを自らが知っていると思っている。それは、結局のところ、われわれ皆が求めているものなのだから。ここでソクラテスのような人は、次のように問う─「幸福とは何か?」。ソクラテスは、安易な応答を許さない。彼が要求してくるのは確固たる答えであり、それは、身を焦がすような自己省察と注意深い批判的洞察力をともに用いることで、やっと産み出されるようなものである。ソクラテスの学生なら誰でもすぐに気づくことだが、こういった問いに対する答えは単純でわかりやすいものであるはずだと考える者は、丁寧に精査されたとたん、自らを弁護するのに困難を覚えるようになる。この点において、人間が獲得しうる最良の生について考察することを望むすべての人が、ソクラテスや彼の門下との出会いから恩恵を受けることになるだろう。
射程と目的
本書は、このような出会いを与えることを目指すものである。ただし本書は、そこで論じられる哲学者の著作を直接読むことの代わりにはならない。当たり前だが、古代の哲学者の書物を読むことの代わりになるものなどありはしない。よって、ここで本書が望んでいるのは、現代の読者のために古代の哲学者の絶えざる貢献の一端を明瞭に示すことで、それらに光を当てる手助けをすることにすぎない。本書は、この時代の思索家による貢献が、その後の歴史におけるこの学問の発展によって時代遅れになったとか、信用に値しないものになったとは決して考えない。また本書は、古代の著者たちの哲学的立場に今風の衣装を着せ直すことで、現代人の好みに合わせようとも思っていない。その代わりに本書が目指すのは、その時代の思索における重要な発展を、共感を伴うが隷属はしない仕方で、正式な哲学の訓練をまったく、あるいはあまり受けていない読者にもわかる言葉で提示することである。また本書は、そこで論じられている哲学者の見解で哲学的に擁護可能なものは、まさにそれ本来の形で述べられ擁護されるべきであるという信念のもとで進められる。同様に本書は、自らが扱う対象に対して、もし彼らが論じる理論に誤りや間違った擁護が見られた場合には、その理論を批判することも行う。端的に言えば、本書の一貫した目的は、彼らの見解を、思想史の博物館の陳列物としてではなく、今を生きる哲学的な観点として理解し、評価することにある。
ソクラテスはたしかにここで述べられる物語の核心となる人物だが、本書が扱うのは彼だけではない。本書は、ソクラテス以前の最初期の哲学者とともに始まる。彼らは自然哲学者であり、学者たちによって「ソクラテス以前〔の哲学者たち〕」と呼ばれている。この呼び方そのものがすでに、古典哲学の発展においてソクラテスが有しているそびえ立つような重要性に関する1 つの判断を反映している。そして本書では、緩いつながりを持つ一群の知識人と教師たち(ソフィスト)による貢献と挑戦も考察する。彼らの見解は、ソクラテスと、特に彼の直接の継承者であるプラトン(紀元前429-347 年)にとって、重要な関心事だった。本書において、プラトンは非常に綿密に論じられる。というのも彼は、西洋において初めて次のことを成し遂げた哲学者だからである。彼は、形而上学や認識論として知られることになった哲学の下位分野において、その中心的トピックのいくつかに関して、積極的なテーゼを体系的に発展させた。彼の学生であり同僚でもあるアリストテレス(紀元前384-322 年)も、同様に詳しく論じられる。プラトンとともに約20 年間学んだ後、アリストテレスは、プラトンと同じく哲学の歴史全体における巨人となった。両者の意見が食い違うときは、それぞれの方向性を表すために彼らの名前が用いられる。そしてそれらの方向性は、今も彼らの名前とともに残されているのである。たとえば、われわれは普遍に関する「事物に先立つ」実在論者(彼らは、心や言語から独立して必然的に存在する抽象的性質があると信じる)を「プラトン主義者」と呼ぶ。これに対して、別の種類の実在論者である「事物の中」の実在論者(性質は、個別事例化されたときのみ実在すると考える人々)を、われわれは「アリストテレス主義者」と呼ぶ。とはいえ、プラトンやアリストテレスが公に打ち出していた実際の見解からすれば、こういったレッテルは、せいぜいのところ部分的にしか正確ではないだろう。本書の目的の1 つは、まさに、こういった不滅の知的党派にその名を貸し与えた著作家たちについて、彼らが実際に有していた見解を明らかにし、評価することにある。
ソクラテス・プラトン・アリストテレスという古典的な時代を過ぎると、われわれは彼ら以外の哲学者たちに出会うことになる。この哲学者たちは、日常的な語り方により広く溶け込んだ仕方で、われわれが今日も用いている言葉遣いにその名を残している。紀元前322 年のアリストテレスの死から始まるヘレニズムの時代において、アテナイの哲学の舞台では、エピクロス派・ストア派・懐疑派という3 つの異なる運動または学派が台頭した。今よりほんの少し前までは、これらの学派をより劣ったものとして扱う風潮があった。これらの学派は、古典的な時代の哲学者による申し分のない成果と比べて、哲学的な質の著しい低下を表しているとされたのである。しかし、今から1 つ前ぐらいの世代において、こういった考え方は正しい方向へとはっきりと改訂された。ヘレニズム期の哲学者に対する関心は一新され、彼らの影響力や価値の再評価がいたるところで行われた。今日では、エピクロス派とストア派、そして懐疑派は、古典的な哲学者に匹敵する体系と進歩した学説を発展させていたということがあまねく受け入れられている。少なく見積もっても、それらの学派が、古典的な哲学者の見解に重要な仕方で挑むところまで進んでいたということは、もはや確実である。本書は、こういった体系を発展させ古典的な哲学者たちに挑戦したヘレニズム期の哲学者たちに対する、最初の一歩となる解説をもって幕を閉じる。そこでは次のことが明らかになるだろう。今日われわれが「エピキュリアン〔快楽主義者〕」や「ストイックな人〔禁欲主義者〕」について語るとき、そこで用いられるこれらの呼び名は、ヘレニズム期の運動から来ている。そして、これらの呼び名がヘレニズム期の運動から取られていることは、ある程度はもっともなことである。しかしそれらは必ずしも、元来のエピクロス派やストア派が有していた実際の信念を正確に描いたものではないのである。
本書が提供する古代哲学は、その扱いにおいてかなり厳選されたものにならざるをえなかった。ここではいくつもの重要な論点が割愛されているが、この欠落は、本書を読んだ学習者が関連する一次または二次文献により幅広く当たることで埋められるだろう。そのために、解説を付した推薦図書目録を本文の後に示した。古代哲学をさらに広く学ぶことを望む学習者には、この目録を参照することが助けとなるだろう。学習者はそれらを通して、古代の哲学者の解釈と評価をめぐる生き生きとした学問的論争を味わい、願わくは、自らもそれに入り込むことになるのである。
想定される読者と方法
本書は、一貫して哲学者たちの議論に焦点を当てる。彼らの書いたものにはほかにも価値あるものがたくさんあるが、それらは割愛する。よって、たとえば、プラトンの散文が持つ文学的あるいは劇的側面に関してはほとんど言及しない。このようなアプローチが取られてはいるが、それは、プラトンの作品が持つこうした特徴は、哲学的な鉱脈を目指して彼の作品を掘り下げるさいには安心して無視できる、と本書が判断しているからではない。むしろ、プラトンや、本書で論じられるその他の哲学者の見解を理解するために、彼らがそれを提示する独自の仕方に注意することは、必要不可欠な事柄である。それでも、本書の議論においては、本書であらためて再現されない解釈上の論点に関しては、ほとんどの場合すでに何らかの解決がなされていると見なすことにする。そうするのは、あるときには、解釈上の争点に関して学者間の合意が幅広く成り立っているからである。とはいえ、打ち出される解釈に、より多くの論争の余地が残されている場合もある。いずれにせよ本書は、古代の哲学者が打ち出す中心的な哲学的立場を自ら理解し評価することを目指す学習者が、彼らの書いた著作そのものへと入り込むさいの助けとなったとき、その使命を全うする
ことになるだろう。
本書と同じシリーズに属する他の書物と足並みを揃えるため、この入門書もまた、哲学に関する若干の予備知識以外は前提せず、専門用語は出てくるたびに定義するよう努める。本書では、そこで扱われる哲学者にとって中心的な重要性を持つ論点を考察する。私は、そこで論じられる論点に習熟することが、次のような仕方で学習者の助けになることを望んでいる。第一に、最も重要なこととして、古代の哲学者の代表的な書物へと向かうための準備になること。第二に、専門家が古代の哲学者の絶えざる哲学的貢献を探究し評価するために書いた二次文献を活用するための準備になること。こういったことからして、本書は、古代の哲学者の哲学を現代の読者に向けて、つまり、プラトンやアリストテレスやストア派を最初に読んだとき、惹きつけられ深く考えさせられもするだろうが、十中八九は同時に違和感を覚えるだろう人々に向けて提示する、という責務に真剣に取り組む。最終的に本書は、古代の哲学者たちが現代の読者に教えうることはかなり多くあるという主張を、単なる陳腐なものに留まらない形で受け止める。彼らは特定の見解と、その見解を支える議論を提示しているが、それらは、今は亡き偉大な哲学者たちの見解だからという理由で真剣な考察を求めているのではない。そうではなく、それらは、たとえ間違っていたとしても依然として示唆的であるか、あるいは往々にして、十分に真であって今日も採用するに値する見解だからこそ、注意深い考察を求めているのである。いずれにせよ、これこそが、本書が現代の読者に投げかけたい挑戦である。
(傍点と注は割愛しました。pdfファイルでご覧ください)
訳者解説
本書は、Christopher Shields. Ancient Philosophy: A Contemporary Introduction(2nd ed. Routledge Contemporary Introductions to Philosophy. New York: Routledge, 2012)を日本語に訳したものである。本書の性格を一言でまとめれば、「分析哲学の精神に則って書かれた、哲学的議論として古代哲学を読むための入門書」というものになる。
著者であるクリストファー・シールズ教授は、1986 年に米国コーネル大学で博士号を取得し、米国コロラド大学ボルダー校や英国オックスフォード大学などを経て、現在は米国ノートルダム大学に籍を置いている研究者であり、長年にわたって世界の古代哲学研究を先導してきた。その研究内容は多岐にわたるが、特にアリストテレスを対象に多くの著作や論文を発表している。近年の業績で重要なものには、編者を務めたThe Oxford Handbook of Aristotle (Oxford University Press, 2012)や、本書と類似したアプローチでアリストテレスに的を絞ったAristotle (2nd ed. Routledge, 2013)、ギリシア語原典からの注釈つき翻訳であるDe Anima (Clarendon Press, 2016)などがある。ただし、教授の著作が日本語に訳されるのは、訳者たちの管見では本書が初めてとなる。経歴や著作に関しては、シールズ教授ご自身によるホームページ(http://cjishields.com/)や、インターネット上に掲載されたインタビュー記事(“Aristotle, Metaphysics and the Delicacy of Anachronism,” www.3-16am.co.uk)が詳しいので是非参照されたい。
本書でシールズ教授は、最初の哲学者といわれるタレスからはじまり、ソクラテス・プラトン・アリストテレスを経てヘレニズム期の哲学に至る一連の流れを扱う。これらは古代哲学を代表するテーマであり、関連する内容を論じる書物は日本語で書かれたものだけを見てもすでに相当な数に上る。しかし、ラウトレッジ社による、現代哲学を大学生向けに紹介することを主な目的とする「哲学への現代的入門」シリーズの一部として出版されたという経緯からもわかるように、本書は既刊のものとは区別される特色をいくつか有している。
以下の解説では、まずⅠ.近年の古代哲学研究の動向を踏まえながら日本で本書を刊行する意義と本書の特色を確認したうえで、Ⅱ.各章の内容を概観する。続いて、Ⅲ.古代哲学を学ぶために参考となる日本語文献を紹介し、Ⅳ.本訳書が出版されるまでの経緯を述べる。
Ⅰ 近年の古代哲学研究の動向と日本の現状
本書が扱う古代ギリシアの哲学者たちは2000 年以上前の人物である。率直な実感として、もはや化石とも言える彼らの説について、問うべきことや、学ぶべきことはないと考える人もいるだろう。本書を一読された方であれば、この疑念はすでに解消されているだろうが、古代哲学研究の国内外の現状を通じて、その疑念をあらためて払拭してみよう。
驚かれるかもしれないが、現代哲学と古代哲学の相性は悪くない。これにはいくつかの理由があるが、その1 つには、欧米の大学の哲学教育においては古代哲学が伝統的に重視されていることが挙げられよう。それゆえ、形而上学であれ、倫理学であれ、政治思想であれ、古代哲学で提示された見解は、現在でも1 つの立場として頻繁に参照される。たとえば、現在の倫理学の一領域を占めている「徳倫理学」の原型はプラトンとアリストテレスに見られる。ただし、このことは、古代哲学の知見がそのまま受け継がれ続けてきたことを意味しない。哲学は本質的に、先行する知見を積み上げることによって成されるものではないからである。すなわち、古代哲学の知見は、常に後世からの批判と検証のなかで、その姿かたちを変容させつつ、受け継がれてきたのである。
とはいえ、テクニカルな話になるが、その批判と検証を行うこと自体が容易ではない。何しろ、2000 年以上前に成立した古代ギリシア語のテキストである。しかも、オリジナルはもはやどこにもない。そもそも、ソクラテスは書物を著さなかったし、ソクラテス以前の哲学とヘレニズム哲学の大部分は断片的な形でしか文章が残されていない。さらに付け加えるならば、活版印刷が普及する前は、本は人間の手によって複写されて伝わってきた。その過程では写し間違いも、書き損じもあった。日本の古典でも同様であるが、そうやってできた「写本」は同じ題目の本でも異なったテキストを伝えている。現在の入手しやすいテキストは、校訂者が複数の写本を比較検討し、専門的知見を総動員して1 つの読み方を提案することによって成立している。ただし、この提案がオリジナルのテキストと同一だと確定させることは不可能である。仮にテキストを1 つに確定させたとしても、次に立ちふさがるのは、古代ギリシア語の壁である。現代語訳を作成しようとしても、訳語の選択、文法的理解、そして語られた事柄の理解といった困難が待っている。このような困難を乗り越えた先に、ようやく哲学的知見と向き合い、誠実に批判と検証を行う下地が整う。少なくとも、そのように考えられてきた。
古代哲学研究がいまだに続いている理由の1 つは、このような問題を抱えるがゆえに、テキストへの向き合い方に多くのバリエーションが開かれていることにある。このバリエーションは、どの哲学者に着目するか、どの議論に着目するか、どの概念に着目するか、といった扱う対象の多様性だけではなく、どのような態度で読んでいくか、という方法論上の多様性にも由来する。
さて、多様な読み方の方法のなかでも、分析哲学的解釈は、20 世紀に開花した比較的新しい手法である。分析哲学の出発点は、哲学的難問と思われてきた問題を、言語を適切に使用することで解決することにあった。そして、当然のようにこの姿勢は古代哲学にも向かった。初期の分析哲学者がしばしば古代哲学に関する研究論文を書いているのも、そういった事情による。
古代哲学を分析哲学的に読解するときには、たとえば次のような手続きを踏む。テキストに書かれたひとまとまりの議論を論理的に、最終的には論理記号レベルまで落とし込んで、作り直してみる。すると、その過程で、論点のずれや、論理の飛躍が明らかになってくる。このような発見は、古代の哲学者の知的能力に疑念をもたらすかもしれないが、ここでは次のように問うのである。このずれや飛躍を補ったり、正当化したりする前提や思考はどのようなものか? このような問いは、古代哲学の適切な理解だけでなく、扱われた事柄に関して哲学的で新しい理解へとわれわれを誘う。
このような分析哲学的手法は、グレゴリー・ヴラストス(Gregory Vlastos, 1907-1991)やG・E・L・オーウェン(Gwilym Ellis Lane Owen, 1922-1982)を始めとした20 世紀中期の古代哲学研究者が先導し、現在では研究者の間で一般的なものとなった。そして、欧米圏における分析哲学の隆盛は、古典への向き合い方にも一定の寄与を果たしているように思われる。その典型は、オックスフォード大学出版局によるClarendon Aristotle Series であり、西洋古典学の技能と知識がなくても深いテキスト分析に読者は触れることができる。上で述べたように、本書の著者であるシールズ教授も、このシリーズに関わっている。また、同出版局のOxford Handbook シリーズを始めとした概説書も、単なる概説に留まるのではなく、より細かなトピックに関してそれまでの研究成果を踏まえた議論を展開しており、一歩を踏み出そうとしている学生へのよい手助けになっている。
ただし、21 世紀の現在においては、分析哲学的手法の一般化は逆に歴史的知見や文学的手法の重要さに光を当てたように見える。たしかに、議論の論理的再構成は、その議論の問題点や、その問題を解決できる選択肢を示してくれるかもしれない。だが、どの解決がふさわしいかを選択する基準を与えてくれるわけではない。また、議論の解体と再構成はギリシア語のテキストに依存しているため、そのテキストをどう訳出するか、そもそもそのギリシア語の訳語は妥当か、といった問題を適切に判断するための文献学的知見はいまだに必要になる。
その意味では、本書が描いた古代哲学者たちの像も根底から覆される可能性を秘めている。しかし、あらためて強調しておきたいが、分析哲学的手法の利点は、古代哲学の知見の重みを現在のわれわれにもわかりやすく伝え、さらにその知見の内部に隠れた前提や態度をわれわれに見せてくれることにある。言わば、時代地域を超えて21 世紀の人間が古代哲学を吟味するための第一歩なのである。
ただし、こういった分析哲学的手法が開いた境地と日本の古代哲学の現状には、ある種の隔たりが燻り続けているように感じられる。この隔たりは、日本の研究状況が世界の潮流から遅れているということではない。上述の分析哲学的手法にしても早期に日本に導入されている。また、現在の日本の研究者も、最新の研究成果を踏まえながら、それを更新するような理解を提示しようと努力を重ねている。ここで言う隔たりとは、古代哲学研究と、日本社会に流布する古代哲学に関するイメージの間の隔たりである。
たしかに、日本人が古代哲学に高いハードルを感じるのは無理もない。時代も場所も遠く離れた2000 年以上前の東地中海地域が、われわれのものの考え方や生き方に直接関係するとは思われない。そして、多くの日本人がソクラテスやプラトンといった名前に初めて出会うのは、中学高校の「歴史」や「倫理」の科目を通じてであろう。残念なことに、そのときに得られた古代哲学に関する情報は、せいぜい哲学者の名前と代表的な考え方程度であって、中身の伴った理解が得られるのはその領域に詳しい教師に幸運にも巡り合った場合だけであろう。また、その幸運な出会いが動機となって大学で哲学を志したとしても、次に控えるのは言語の壁である。近現代の哲学であっても英語を始めとした外国語に習熟しなければならないのに、古代哲学の場合は古代ギリシア語やラテン語も学修せねばならない。それゆえ、意欲ある学生であっても、古代哲学との真剣なつき合い方を4 年という期間で把握することはきわめて難しい。
翻訳が盛んである日本では、本書で紹介している哲学者が残した文章の大部分を日本語で読むことができる。しかし、翻訳を読んだとしても、それだけでその内容を適切に把握することは難しい。もちろん、研究者による専門的研究成果の多くは、論文であれば近年ではインターネットを通じて読むこともできるし、専門書であっても大学の図書館を通じて閲覧できる。しかし、専門研究の問題意識や成果までただちに初学者の理解が及ぶわけではない。
われわれは、古典にさまざまな観点から接することができる。たとえば、議論のなかで気になった論点をつなぎ合わせるのも、接し方の1 つである。しかし、この接し方だけでは、おそらくその議論を適切に理解したことにはならないだろう。どうしてもわれわれは、われわれから見て目立つ主張─それはわかりやすかったり、自分の主張と一致したり、逆に対立するものであったりするが─に心を奪われてしまう。だが、哲学の遂行とは、ある主張を語ることではなく、その主張に至る道筋を通じて自分とは異なる他者と意見を1 つにすることを希のぞむ活動であるならば、哲学的古典の講読とは、議論の筋道を追体験することで、その古典が描く意見を一度自らのものとすることにその意義があるはずである。
本書は、古代哲学の入門書である。だが、本書が目指すのは、現代と古代の文化的な差異や、資料の伝達と関わる文献学的な問題、登場する哲学者たちの伝記的な紹介とその仕事について、網羅的で公平な説明を与えることではない。もちろん、このような情報は古代哲学を正確に理解するには必須だろう。だが、もしかするとこのような情報は読者に、古代哲学の知見がいかにわれわれと隔絶しているかを伝えてしまっていたのかもしれない。それに対し、本書はあえてそのような情報の紹介を最小限に留め、限られたテキストの再構成を通じて、古代哲学の知見がいかにわれわれに近しいかを示そうとしている。それによって明らかになった古代の思索の素朴な力強さは、哲学的思索を純粋に味わいたい読者に対し、これまでにはなかった道を開いてくれるだろう。
(以下、本文つづく。傍点は割愛しました)







