あとがき、はしがき、はじめに、おわりに、解説などのページをご紹介します。気軽にページをめくる感覚で、ぜひ本の雰囲気を感じてください。目次などの概要は「書誌情報」からもご覧いただけます。
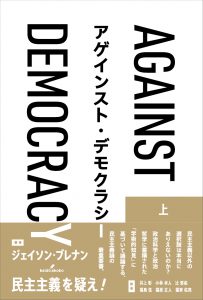

ジェイソン・ブレナン 著
井上 彰・小林卓人・辻 悠佑・福島 弦・福原正人・福家佑亮 訳
『アゲインスト・デモクラシー 上・下』
→〈「二〇一七年のペーパーバック版への序文」「序文と謝辞」「訳者解説」(pdfファイルへのリンク)〉
→目次・書誌情報・オンライン書店へのリンクはこちら:〈上巻〉・〈下巻〉
*サンプル画像はクリックで拡大します。「訳者解説」などの本文はサンプル画像の下に続いています。
二〇一七年のペーパーバック版への序文
二〇一六年は、デモクラシーにとってひどい年であった。対照的に、デモクラシーを批判する側にとっては良い年であった。以下がその証拠である。
・私はデモクラシーの欠陥を指摘するコラムや雑誌記事の執筆依頼を受け、一九ものコラムや記事を書いた。本書を執筆した二〇一四年もしくは二〇一二年には、同種の関心はなかった。
・また、投票すべきでない者もいる、という自説を論じるためにラジオにも呼ばれた。リスナーは、「わかっている! じゃあ、どうすりゃいい?」と言うために電話をかけてきた。その前年に同じ話題を同じ番組でしたときには、リスナーは、「よくもまあそんなことが言えるな!」と伝えるために電話をかけてきた。
・一〇月から一二月にかけて、日ごとに複数のメディアからインタビューを受けた。
・『アゲインスト・デモクラシー』は、主要メディアに広く取り上げられた。その範囲は、アメリカ、カナダ、イギリス、ドイツ、アイルランド、フランス、スウェーデン、ノルウェー、スイス、オランダなどにわたる。本書はこれまでに六つの言語に翻訳されている。
これは単なる私の履歴書ではない(まあ、そういう面もおそらくちょっとはある)。むしろ、私なりの手応えを示すものだ。私は二〇〇九年以来、政治参加についての最も神聖視されてきた理念に挑戦する本と論文を著してきた。すると二〇一六年に突如、人々は私の話に耳を傾けるようになったのだ。私の主張に同意しないかもしれないが、私の主張をこれまでよりずっと積極的に考えるようになった。
ブレグジットをめぐる国民投票で、僅差で「離脱」が勝利した。ブレグジットの投票が行われる前の月に、イプソス・モリの国民意識調査によると、イギリス国民がその決定にかかわる重要な事実について、体系的に誤解していたことがわかった。たとえば、離脱派は、EUからの移民がイギリスの人口の二〇%を占めると思っていた。残留派は一〇%と見積もっていた。双方とも間違っているが、離脱支持者の方がより0 0 間違っていた。真実は五%近くだ。また離脱派も残留派も、イギリスが移民に児童手当をいくら支払っているかについて、平均で実際の額の四〇倍から一〇〇倍ほど多く見積もっていた。双方ともEUからの外国投資の量をかなり低く見積もっていたし、中国からの投資の量をかなり多く見積もっていた。もちろんこのことは、残留が正しい決定だったことを証明するものではない。だが、重要な事実の受け止め方が間違っていればいるほど、離脱に投票する傾向があったというのは、きな臭い話のように思えてならない。
アメリカはアメリカで、乱痴気騒ぎに興じている。不安症に陥っている職場の同僚たちは、ドナルド・トランプがかなりの大惨事を引き起こすと考えているが、私はそうした見方には懐疑的だ。しかし、それにしても、大統領予備選挙での当初の支持は、著しく知識の乏しい投票者に由来するものであった。トランプが候補者指名で勝利したのは、部分的には共和党の予備選において知識の豊富な投票者が分裂したからだ。トランプが共和党の暫定候補になったとたん、本書の第二章と第三章で説明する政党内での〔政治的〕部族主義が横行した。「トランプに勝たせるな!」と主張していた共和党員の多くは、いやいやながらもトランプに投票した。
アメリカの左派は左派で、間違った情報だらけの経済ポピュリズムの悪い見本となっている。バーニー・サンダースは大雑把には、トランプと同様、保護主義者であり反移民論者である。経済学者のブラッド・デロングは、次のようにコメントしている。
以前からも広まっていた政治的に真実っぽい話が、いまや経済を主題にして、どんどん勢いよく広まっている。政治家は、経済的リアリティとの結びつきが非常に乏しい主張――まさに真実っぽく感じる主張――をしていて、それを実行しようとしている。それは無知からのケースもあれば、ひねた計算からのケースもある。
…トランプとサンダースは、貿易にかんする議論では終末論者だった。そしてクリントンも真実を放棄した。
第二章で論じるように、トランプとサンダースが推す経済のアイデアは、端的に何百年にもわたる経済学の研究と数多くの経験的証拠に反するものである。(以下、本文つづく。傍点と注番号は割愛しました)
序文と謝辞
一〇年前、私はほとんどの哲学的なデモクラシー理論にとまどいを覚えていた。私には、哲学者や政治理論家がデモクラシーをその象徴性に基づいて支持する議論にあまりに突き動かされているように思われたのだ。彼らは民主的プロセスについてかなり理想化された説明をしていた。それは、現実世界のデモクラシーとはほぼ似て非なるものである。こうした類の観念は、まったく魅力のないもののように思われた。私が思うに政治はポエムではないし、そうした理想的条件で私たちがなりたいのはアナーキストであって民主主義者ではない。
後に私は、哲学的なデモクラシー理論に対する自分の不満が、その分野を避ける理由ではなく、それに取り組む理由であることがわかった。少なくともデモクラシー理論には、〔あえて批判や反論を行う〕悪魔の代弁者を演じる人間が必要である。私は喜んでその役回りを演じるが、私の方が本当にそうした役回りから悪魔を擁護して、哲学者と政治理論家の方が天使を擁護しているかどうかは、いまとなっては疑わしい。
私の同僚の多くは、政治が私たちを一つにし、教育し、文明化し、公の友人同士にするという、政治についてのややロマンティックな見解を抱いている。私は、政治は私たちを敵対的なものにするとみている。すなわち、政治は私たちを引き離し、気力を奪い、堕落させ、公の敵同士にする。
本書『アゲインスト・デモクラシー』は、ある意味、二〇一一年の『投票の倫理』、二〇一四年の『義務投票制:賛成と反対』を含む三部作の三番目の作品である。『アゲインスト・デモクラシー』には、その二作品から取り上げたテーマもあるが、二作品よりも野心的な主張を擁護する作品である。『義務投票制』の半分にあたる私の担当パートは、義務投票制は正当化されないと論じるものである。『投票の倫理』では、公民的徳を実践する最善の方法は政治の外側にあり、ほとんどの市民は、たとえ投票する権利があったとしても、投票を控える道徳的義務があると主張している。本書はそうした議論をさらに進めるものである。そのため、仮に本書の議論が失敗しても、他の二冊の論証が失敗することを意味しない。本書での私の主張は、デモクラシーの実態が適切に明らかにされた場合、一部の人には投票権を付与するべきでない、あるいは、他の人と比較して弱い影響しか及ぼさない投票権を付与するべきだ、というものである。
「政治は私たちにとってろくでもないもので、私たちのほとんどは、自分たちの特性をふまえて政治への関与を最小限にすべきだ」というのが、本書の主要テーマの一つである。そのテーマを取り上げることを提案してくれた、プリンストン大学出版の編集者であるロブ・テンピオに感謝する(私の議論にロブは同意するかもしれないし、同意しないかもしれない)。「広範にわたる投票者の無能さに鑑みると、エピストクラシーの方がデモクラシーよりも優れている」という第二のテーマを追究するように提案してくれたジェフリー・ブレナンに感謝する。(以下、本文つづく)
訳者解説
小林卓人、辻悠佑、福島弦、福家佑亮
本書を手に取られる読者の関心を第一に惹くものは、そのタイトルであろう。現代のリベラル・デモクラシー(とされる)国家に生きる私たちにとって、「デモクラシーこそが私たちの社会にあるべき政治体制だ」という考えは、おそらくもっとも支配的な、あるいは権威的な考えの一つかもしれない。「民主的な」という形容詞は、制度や行為を記述するのみならず、それらを評価するための形容詞としてしばしば用いられてさえいる。「民主的な」はほぼ「良い/正しい」と同等の意味で用いられることがあり、「非民主的な/反民主的な」はほぼ「悪い/正しくない」と同等の意味で用いられることがある。本書のタイトル『アゲインスト・デモクラシー』は、まさにその考え方、ないしそのような語の使用法への異議を申し立てていると考えてよいだろう。
著者ジェイソン・ブレナンの目的は、この異議を、単なるセンセーショナルな政治的・倫理的スローガンとしてではなく、政治科学と政治哲学において蓄積されてきた広範な知見、および注意深い合理的推論に基づく最善の結論として申し立てることにある。著者の試みがこれらの学術分野における重要な貢献を見定めるための基準の一つ――論争的な結論を、良い根拠に基づいて支持すること――を満たそうとするものであることは、訳者一同が保証したい。
とはいえ、著者の異議が実際に正しいか否かは、読者の熟慮と今後の学術的論争に委ねられるべきである。この訳者解説では、著者を簡潔に紹介したのち、本書の思想的・理論的背景や議論(アーギュメント)の方法を紹介することで、そのような熟慮や論争のための下地を作ることを試みる。
著者紹介
本書の著者であるジェイソン・ブレナン教授は、現在、ジョージタウン大学のマクドノー・ビジネス・スクールに在籍している政治哲学者であり、アリゾナ大学で二〇〇七年に博士号を取得している。
著者紹介にあたって、まずは以下の著作一覧をご覧いただきたい。
著作一覧
・A Brief History of Liberty (Wiley-Blackwell, 2010), with David Schmidtz
・The Ethics of Voting (Princeton University Press, 2011)
・Libertarianism: What Everyone Needs to Know (Oxford University Press, 2012)
・Compulsory Voting: For and Against (Cambridge University Press, 2014), with Lisa Hill
・Why Not Capitalism? (Routledge, 2014)
・Markets without Limits (Routledge, 2015), with Peter Jaworski
・Political Philosophy: An Introduction (Cato Institute, 2016)
・Against Democracy (Princeton University Press, 2016)
・In Defense of Openness: Why Global Freedom Is the Humane Solution to Global Poverty (Oxford University Press, 2018), with Bas van der Vossen
・When All Else Fails: The Ethics of Resistance to State Injustice (Princeton University Press, 2018)
・Cracks in the Ivory Tower (Oxford University Press, 2019), with Phil Magness
・Good Work If You Can Get It: How to Succeed in Academia (Johns Hopkins University Press, 2020)
・Why Itʼs OK to Want to Be Rich (Routledge, 2020)
・Business Ethics for Better Behavior (Oxford University Press, 2021), with William English, John Hasnas, and Peter Jaworski
・Debating Democracy (Oxford University Press, 2021), with Hélène Landemore
・Democracy: A Guided Tour (Oxford University Press, 2022)
・Debating Libertarianism: What Makes Institutions Just? (Oxford University Press, 2023), with Samuel Freeman
・Debating Capitalism (Oxford University Press, 2023), with Richard Arneson
また、Routledge Handbook of Libertarianism(Routledge, 2017)の編者の一人(with Bas van der Vossen, David Schmidtz)でもある。右の著作以外にも、学術論文や学術書の章の執筆も精力的に行っている。Cato Institute をはじめ、リバタリアニズム系のシンクタンクで一般向けの活動も行っているほか、かつては、Bleeding Heart Libertarians という、後述する新たなタイプのリバタリアニズムを広めようとする研究者たちが運営していたブログの寄稿者でもあった(このブログは二〇二〇年に活動停止を宣言している)。
著作一覧を眺めるとわかるように、政治哲学者としてのブレナンは、デモクラシーや投票倫理の研究者であると同時に、自由市場に好意的なリバタリアニズムの研究者でもある。彼が一翼を担うリバタリアニズムはネオクラシカル・リベラリズムと呼ばれる。その特徴は、古典的リベラリズムにおける経済的自由の重視と平等主義的リベラリズムにおける社会正義の重視を結合させようとする点にある(cf. Brennan 2018; Brennan and Tomasi 2012; Tomasi 2012)。
ネオクラシカル・リベラリズムや本書の議論をブレナンが展開する際の共通点として、制度選択におけるPPE(Philosophy, Politics, and Economics)アプローチを採っていることが挙げられる。PPEアプローチによると、どのような制度を選択するべきかという問いに答えるためには、制度がどう機能するか、いかなるオルタナティブが実現可能なのかという経験的な理解が必要とされる。つまり、制度に対し規範的評価を下す際に社会科学的な検討を重視するのである。こうしたブレナンの観点は、意思決定手続きの評価を主題とする本書の議論にも強くあらわれている。たとえば、政治学から行動科学まで各種社会科学の知見が参照され、一部のデモクラシー論はデモクラシーとそのもとでの市民の振る舞いに過度な期待を抱いていると批判されている。あくまで今ここの社会に対する経験的理解を基礎に制度評価及び制度選択を構想するべきだとするブレナンの方針は、デモクラシーの現実をなおざりにしてきたデモクラシー理論に対する批判を含意している。
著者自身の背景紹介はここまでにして、以下では本書を思想史的背景や理論的背景のなかに位置づける作業に移りたい。
思想史的背景
デモクラシーへの懐疑
題名からもわかるように、本書は「デモクラシーに反対」する立場を鮮明にしている。政治思想史を振り返れば、古代から近代まで、デモクラシーに対する懐疑的な見解は決して突飛なものではない。ここでは、特に本書との関係で重要となるデモクラシー批判をごく簡単に振り返っておく。より詳しくデモクラシーについての思想史を辿りたい方には、政治思想史の教科書か、ここ数年の間だけでも参考になる書籍が多数出版されているので、そちらが適している(たとえば、宇野 2020)。
最初におさえておきたいのは、本書におけるデモクラシー批判の図式がデモクラシーの歴史と同程度に古い伝統をもつ点である。デモクラシーによる政治の起源の一つが古代ギリシアにあることは有名だが、思想史的にはプラトンやアリストテレスらはデモクラシーに対して批判的だったことも忘れてはならない(もちろん現代の「デモクラシー」と古代ギリシアの「デモクラシー」を単純に同一視するのは思想史的には注意すべきではあるが)。特にプラトンは、善のイデアを観照した哲学者こそが哲人王として統治をするべきであると考えた点で、徹底的なエピストクラシー(知者の支配)の支持者であり、かつデモクラシー批判者だった。デモクラシーは、扇動によって最悪の僭主政治に転落する手前の政体として位置づけられている(プラトン 1979)。また、アリストテレスにも、混合政体論的な発想と同時に、やはり理想的には政治は有徳者が担うべきだという発想があった。デモクラシーは、多数派の貧者の利益を追求する点で、アリストテレスにとっても堕落した政体であった(アリストテレス 2001)。要するに、プラトンやアリストテレスは、政治に携わる人々の質を極めて重視し、みんなの政治参加それ自体を歓迎してはいなかったのである。
リベラリズムVS.デモクラシー
本書の議論を思想史上に位置づける上でもう一つ確認しておくべきなのが、リベラル・デモクラシーにおけるリベラリズムとデモクラシーの緊張関係である。現在、両者は連名で政治体制のあり方を表しているが、このことは必然ではない。それどころか、政治的権力がいかに行使されるか次第では、当然デモクラシーといえど個人の自由への脅威となる。リベラリズムは個人の自由を大切にする考え方であり、たとえ政治的意思決定の結果であっても、他人が侵してはならない領域は個人の権利の名のもとに守られるべきだとされる(ゆえに憲法上の権利保障がある)。それに対して、デモクラシーは政治的権力の行使を広く市民に委ねる。アイザィア・バーリンは言う。「事実、デモクラシーが一人の市民から他の形態の社会においてならもちえたかもしれない数多くの自由を奪うかもしれないのと同じように、自由主義的な専制君主がその被治者にかなりの程度の個人的自由を許すということはまったく考えられる……〔中略〕……個人の自由とデモクラシーによる統治とのあいだにはなんら必然的な連関は存在しない」(バーリン 2018 p. 316)。
権力行使次第で個人の自由が脅かされるという点で、デモクラシーも警戒対象の例外でないことは、一九世紀の思想家たちの著述に顕著である。たとえばバンジャマン・コンスタンの有名な講演「近代人の自由と古代人の自由」は、古代人の自由としての政治参加を称揚する立場――ジャン・ジャック・ルソーが念頭に置かれている――に対して、近代における個人の自由を軽視していると批判を向ける(コンスタン 2020)。あるいは、アレクシ・ド・トクヴィルやジョン・スチュアート・ミルらは、「多数者の暴政」や「民主的専制」という言葉で知られるように、多数者の権力が個人に対して抑圧的に働くことを懸念した(トクヴィル 2005-2008; ミル 2019; 2020)。なお、こうした懸念は次の理論的背景の節でも触れるように、二〇世紀におけるウィリアム・ライカーらのデモクラシー批判にも受け継がれている。
もちろん、コンスタンは政治的意思決定への参加それ自体が放棄されてよいとは考えなかったし、トクヴィルやミルがデモクラシーに向ける期待も大きかった。デモクラシーのもとでは各個人が自分で考え判断するようになる、という期待である。しかし、特にミルに着目すると、市民の政治参加が権力行使のコントロールに資することや様々な教育効果を生むという期待は、必ずしも平等な参政権を支持するものではなかった。彼は、教育を受けた人々により大きな政治的権力を分配する「複数投票制」のような制度構想を提案している。こうした提案は、デモクラシーから逸脱する点で先の期待と矛盾しているように見えるかもしれない。だが、政治制度の帰結のみを気にかける道具的な態度からすれば、政治的平等からの逸脱を原理的に拒む理由はない。要するに、デモクラシーへの警戒、期待、逸脱はすべて、一貫した観点からのものである。
民主的な政治的権力を疑う本書は、こうした伝統の延長線上に位置づけることができる。あえていえば、ブレナンはリベラルではあるがデモクラットではないのである。そして彼の議論は、「市民の政治的平等を否定するなんてとんでもない」と簡単に片付けられるようなものではない。本書の議論は、現代のデモクラシーを対象にした規範的研究と経験的研究を踏まえて構築されているからである。以下では、そうした現代のデモクラシー研究を説明していこう。
理論的背景
デモクラシーの規範理論
本書は、デモクラシーに関する哲学的・経験的な研究を数多く参照している。まず、哲学的研究について説明しよう。政治哲学(ないし規範的政治理論)は、政治的・経済的・社会的諸制度やそれらに関わる人間の行為についての「べし(ought)」を探究する。ここでは、デモクラシー研究において扱われてきた規範的問いを、大まかに時系列に沿った仕方で整理する。
第一に、「民主的な政治体制は具体的にはどのような形態をとるべきか」という問いがある。この問いは、たとえば一九八〇年代頃から急速に進展した「熟議デモクラシー」の理論潮流において広く取り組まれてきた(Bohman and Rehg 1997; Cohen 2009; Manin 1987; 田村 2008; ハーバーマス 2002-2003)。この理論潮流によれば、理想的なデモクラシーとは、単に各人がすでに有しているとされる政治的選好を公正な仕方で政治的意思決定に反映するための装置ではない。そうではなく、人々の間での合理的かつ公正な熟議に基づく政治的意思決定を可能にする条件を整えるための制度や実践の体系である。この見解は、しばしばデモクラシーの「集計的構想」に対する「熟議的構想」からの批判として紹介される。こうした批判を展開する熟議デモクラシーの理論家たちは、民主的熟議を実現するために求められる制度や実践のさまざまな構想を提案している。
以上の第一の問いにどのように回答するにせよ、理論家たちは「政治体制は民主的であるべきだ」とする規範的見解を広く共有していた。第二の問いは、この見解自体の根拠づけを求めるものである。すなわち、「政治体制、とりわけ政治的意思決定手続きはなぜ民主的でなければならないのか」。この問いへの取り組みの中で、デモクラシーの道具的または非道具的な諸価値――正しい結果を生み出す傾向性、市民的徳を涵養する傾向性、自己決定や政治的平等の実現など――が提示されてきた(cf.Anderson 2009; Arneson 1993; Beitz 1989; Christiano 2008; Estlund 2008; Gould 1988; Kolodny 2014; Landemore 2012; Saffon and Urbinati 2013; Waldron 1999; 福家 2019)。詳細は後に触れるが、これらの価値について民主的体制は非民主的体制よりも優れているため、私たちは民主的体制を用いるべきである(さらに言えば、民主的体制は正統な権威を備える)、と論じられてきた。
しかし、この最後の点は論争的である。もちろん、デモクラシーは、自己決定や政治的平等の実現といった非道具的価値については非民主的体制よりも優れているかもしれない。しかし、正しい結果の産出や市民的徳の涵養はあくまで手続きの作動の帰結であり、こうした帰結を生じさせるにあたって、民主的な政治的手続きが非民主的手続きよりも道具的に優れているかどうかは自明ではない。たとえば、思想史的背景の節でも述べたように、個人の自由を脅かすような政治的決定が民主的手続きを通じて産出されることは容易に想像しうる。したがって、少なくとも道具的価値を重視する立場にとっては、非民主的な政治体制を擁護する理論的余地は十分にありうる。本書の言葉では、この考えは次のように表現される。「デモクラシーはハンマー以上のなにかではない。もしより良いハンマーを見つけられるなら、私たちはそれを使うべきである。」[本書上巻一七頁]
このように、政治体制を道具的に評価するか、それとも非道具的に評価するかによって、異なる政治体制(たとえばデモクラシーとエピストクラシー)の比較評価における結論も異なりうる。したがって、政治体制の比較評価を行うにあたって、私たちは「そもそも政治体制をどのような基準で評価すべきか」という哲学的問いにも取り組む必要がある(小林 2019)。次項では、この問いについて提示されてきた二つの大きな立場である道具主義と非道具主義の間の論争を整理する。
道具主義と非道具主義
道具主義とは、政治体制は、なんらかの良い帰結を生じさせるための道具として比較評価されなければならない、という主張である。道具主義に立てば、他の政治体制と比較して、より良い帰結を生じさせる傾向性のある政治体制であるという理由から、デモクラシーは正当化されることになる。他方で、政治体制には、良い帰結を生み出すことに還元し尽されない独自の価値が備わりうると考えるのが、非道具主義である。たとえば、自己決定や政治的平等の価値が、ここでの非道具的な価値に該当する。
単純化の謗りをおそれず言えば、次項で紹介する認識的デモクラシー論を除いて、これまでデモクラシーの擁護者の大半は非道具主義的な観点を中心にデモクラシーの擁護を企ててきた。これには、少なくとも二つの理由を考えることができる。一つは、デモクラシーを独裁や権威主義等の他の政治体制と区別するメルクマールには、自己決定や政治的平等の非道具的な価値が含まれているという見方である。もう一つは、道具主義が非民主的な政治体制の正当化に転用されるのではないかという懸念である(Saffon and Urbinati 2013 p. 446)。実際、デモクラシーの擁護者が非道具主義を重視する傾向は、本書でも論じられるトマス・クリスティアーノやデイヴィッド・エストランド、そして近年デモクラシーの正当化論において急速に支持を集めつつある関係的平等主義が、いずれも非道具的な価値を基軸として議論を展開していることからも看取できる。
さて、以上の背景を踏まえたうえで、デモクラシー以外の政治体制、とりわけ、本書の主題でもあるエピストクラシーを擁護する議論は、どのように特徴づけられるだろうか。ここで重要となるのが、非道具主義に対する態度である。本書でも何度も確認してきた通り、エピストクラシーの擁護者が一種の道具主義を採用していることは間違いない。しかし、デモクラシーの擁護者であっても、必ずしも道具主義を徹頭徹尾拒絶するわけではない。むしろ、非道具的な価値が優先するという条件の下で、道具的な価値も追求するという形で、両方の価値を考慮する論者が多い(たとえば、Estlund 2008 の立場はこうした両立主義に分類可能である)。
デモクラシーの擁護者とエピストクラシーの擁護者、両者の間に存在する最も大きな違いは、デモクラシーの正当化において、非道具的な価値の存立余地を認めるかどうかという点にある。ここで触れておかなければならないのは、デモクラシーの正当化において、非道具的な価値の存在を一切否定する純粋道具主義(pure instrumentalism)を明確な立場として打ち出したリチャード・アーネソンの存在である。アーネソンは、政治哲学や道徳哲学において広く業績のある哲学者だが、デモクラシー論においても、一九九〇年代初頭から現在に至るまで純粋道具主義を擁護する論文を継続的に発表している。アーネソン自身は、デモクラシーの正当化として有望な立場が純粋道具主義であると主張するにとどまり、積極的にエピストクラシーを擁護しているわけではない(もっとも、Arneson 2016 など近年の論文では、エピストクラシーの擁護可能性を認めている)。しかし、アーネソンの議論には、ブレナンにも引き継がれた二つの基本的な議論の方向性を見出すことができる。一つは、非道具的な価値を重視する議論を個別に論駁するという形で純粋道具主義を擁護する議論。もう一つが、デモクラシーの根幹をなす投票には他者への権力行使の契機が含まれるという指摘に基づく議論である。アーネソンは、他者に対する権力行使が正当化されるのは、生命や財産の保障等の基本的権利を最大限に実現する場合であり、かつその場合に限られるとして、純粋道具主義を擁護する(Arneson 1993 pp. 118-125; Arneson 2003 pp. 124-125)。こうした純粋道具主義からすれば、帰結――基本的権利を最大限に実現すること――以外の要素に価値を見出そうとする非道具主義は、デモクラシーの正当化において何の役割も持たないのである。
こうしてみると、本書におけるブレナンの主張は、アーネソンの純粋道具主義を踏襲しつつも、さらなる洗練を加えてエピストクラシー擁護に昇華させたものであることが分かる。第四章と第五章で展開される非道具主義への批判は、非道具主義的な議論を一つひとつ丁寧に論駁していくアーネソンの議論方針を受け継ぐものである。同時に、少なくとも以下の二つの点でブレナンは独自の発展を純粋道具主義に加えている。一つは、他者への権力行使が許容される条件を、より弱いものにしている点である。第六章において、無能な陪審員団とのアナロジーを巧みに用いつつ提示される有能性原理は、最も有能な政府を求めるのではなく、無能な政府を有能な政府に改善することを求める点で、ブレナン自身が指摘するように弱い(純粋)道具主義に立つ。二つ目の点が、経験科学の豊富な援用である。ブレナンは、現在の(アメリカの)平均的な市民がいかに無知で非合理的であるかを、実証的な政治科学を積極的に参照しつつ論じる。経験科学に裏打ちされた規範的な議論を展開する点も、アーネソンにはないブレナンの議論の特徴である。
以上の点に鑑みれば、本書におけるブレナンの主張は何の脈絡もない突飛な主張ではなく、政治哲学におけるデモクラシー論の発展を踏まえた、正統な議論であると言えるだろう。
認識的デモクラシー
先ほども述べたように、これまでデモクラシーの擁護者は非道具主義的な議論を好んで取り上げる傾向があった。しかし、道具主義に棹さしつつ、エピストクラシーの擁護者に負けじと、デモクラシーを力強く擁護する試みが近年注目を集めつつある。それが、ここで紹介する認識的デモクラシー(epistemic democracy)と呼ばれる議論だ。認識的デモクラシーの特徴は、政治的意思決定から独立した正しさや共通善が存在するという仮定の下、デモクラシーは、投票や熟議を通じてそうしたある種の「正しさ」に到達する蓋然性が高いと主張する点にある。別の表現を用いれば、民主的な意思決定を「正しさ」への到達に向けた集合知産出のメカニズムとみなす諸議論が認識的デモクラシーと呼ばれている。
歴史的に見れば、認識的デモクラシーの淵源は、奇しくもデモクラシーを堕落した体制と見做したアリストテレスの『政治学』にまで遡ることができる。ただ、認識的デモクラシーが一つの明確な立場として定式化されたのは、政治哲学者のジョシュア・コーエンが一九八六年に発表した論文「デモクラシーの認識的構想」によるところが大きい(Cohen 1986)。この論文の執筆背景には、個人の選好集計メカニズムとしてデモクラシーが抱える欠陥を鋭く指摘したライカーの著書『民主的決定の政治学――リベラリズムとポピュリズム』の存在がある(ライカー 1994)。ライカーは、投票に期待する役割に応じてデモクラシーのモデルを二つに分類した。一方のポピュリスト・モデルでは、投票を通じて現れる人民の意志が絶対視される。他方、リベラル・モデルでは、投票は定期的に開催される選挙を通じた権力抑制・監視以上の役割をもたない。ケネス・アロー以来の社会選択理論の成果に依拠し、ライカーはポピュリスト・モデルを厳しく批判した。思想史的背景との関連で言えば、こうしたライカーの議論も、リベラリズムとデモクラシーの緊張関係という問題系の延長線上にある。このような背景の下で、ライカーを批判し、三つ目のモデルとして認識的構想の可能性を指摘したのが、先に挙げたコーエンの論文である。
では、デモクラシーが「正しさ」に到達する見込みが高いとする主張を支える議論には、具体的にはどのようなものがあるのか。これについては、ブレナンが第七章で紹介している通り、(一)集計の奇跡、(二)コンドルセの陪審定理、(三)「多様性が能力に勝る定理(Diversity Trumps Ability Theorem)」の三つが、認識的デモクラシーが着目する集合知産出の代表的メカニズムである。ここでは、ブレナンが紙幅を割いて論じているエレーン・ランデモアの議論について簡単に紹介したい。
ランデモアの議論の出発点は、ルー・ホンとスコット・ペイジによって提出された「多様性が能力に勝る定理」だ。この定理によれば、特定の条件が満たされたとき、専門的な知識を持たない一般の人々によって構成されているが認知的多様性に優れる集団は、専門家を擁するが認知的多様性に劣る集団よりも、優れた問題解決能力を有する。ランデモアはこの定理に依拠しつつ、デモクラシーを擁護するために「多様性が能力に勝る定理」を超えて更に大胆な主張を行う。ここで彼女が着目するのが、問題解決に携わる人数が増えることで認知的多様性が増大する点だ。この認知的多様性と人数の間に正の相関関係があるという想定に基づき、人数をより多く含む意思決定は、それよりも人数が少ない意思決定と比較して、常に正しい結果に到達する蓋然性が高いという「数が能力に勝る定理(Numbers Trump Ability Theorem)」をランデモアは提唱するのである(Landemore 2012 p. 104)。ランデモアが主張する通り「数が能力に勝る定理」が成立するのならば、道具主義の観点からデモクラシーのエピストクラシーに対する優越を示すにあたって、この定理は強力な根拠になり得る。というのも、理論上エピストクラシーよりもデモクラシーの方が多くの人々に政治への参加を認めることは確実である。だとすれば、「数が能力に勝る定理」に従えば、実はエピストクラシーよりもデモクラシーの方が「正しさ」に到達する能力に優れているという結論が得られるからだ。
もっとも、ブレナンが第七章で指摘している通り、こうした認識的デモクラシーの議論が、数理モデルの妥当性や現実への適用可能性――有権者の絶望的なまでの(合理的)無知や非合理性――等について様々な問題を抱えていることも事実である。第二章を中心としてブレナン自身が適切な整理を提示しているのでここでは繰り返さないが、有権者の無知や非合理性について、スコット・アルトハウスやイリヤ・ソミン、ブライアン・カプラン達の指摘に認識的デモクラシー支持者は正面から取り組む必要がある(Althaus 1998; カプラン 2009; ソミン 2016; cf. Converse 2006; Delli Carpini and Keeter 1997)。とりわけ、動機づけられた推論(motivated reasoning)をはじめとして、自身が所属する集団に都合のいいように情報を取捨選択し、推論を捻じ曲げる党派的な思考の影響は深刻である(この点に関して重要な文献として、本書とほぼ同時期に刊行されたAchen and Bartels 2016 を参照されたい)。また、こうした社会科学的知見を豊富に援用するブレナンの方法には、著者紹介で言及したPPEアプローチが如実に表れている。認識的デモクラシーの最終的な妥当性についての判断は読者諸賢に委ねたいが、理想理論の次元において議論を進めがちな政治哲学に対して、現実の我々の思考を蝕む無知や様々な非合理性に注意を促し理論の再考を迫る点で、やはり本書におけるブレナンの主張は重要である。
本書の方法的特徴
最後に、本書の方法的特徴について二つの側面から論じたい。まず、我々の日常的直観を上手く剔出しながら論争的な結論を擁護する本書の方法を取り上げる。ブレナンの議論の進め方はこの点で政治哲学における議論のお手本とみなし得るため、その解説を通じて読者に政治哲学の方法と魅力を紹介できると考える。第二に、ブレナンの議論が、理想理論(ideal theory)と対比されるところの非理想理論(non-ideal theory)として専ら位置づけられている点を検討する。この点を取り上げるのは、ブレナンの議論の潜在的な弱みを指摘するためである。以下、順に見ていく。
日常的直観を用いた論争的結論の擁護
哲学者バートランド・ラッセルは、「哲学の要点は、語るに値しないようにみえるほど単純な事柄から始めて、誰も信じないような逆説的な事柄で終わることである」(ラッセル 2007 p. 36)と語った。これはなにも高名な哲学者がそう語ったという理由で重要なのではなく、哲学の議論方法について示唆的である点で重要である。自明な前提から逆説的な結論に達することは哲学的議論の強みとなる。というのも、そのような議論は出発点の自明性から説得力を得る一方で、結論の逆説性から、多くの人々が無意識に抱える思い込みや矛盾した考えを詳らかにするという学術的意義を得るためである。
本書は以上の方法が用いられている好例である。ブレナンが擁護を試みるのは、エピストクラシーはデモクラシーに対する有力なオルタナティブであり得る、という論争的な結論である。しかしながら、この結論を擁護するために本書でブレナンが提示する論拠は、難解な哲学的理論とは異なり、容易に理解でき、専門家・一般市民を問わず広く受け入れられている前提である。ブレナン自身の議論の最終的な成否はともかく、本書はこの点で優れた哲学的議論の範を示しているといえるだろう。
ブレナンの議論方法をより具体的に検討しよう。その第一のステップは、議論の分解である。我々は、整理して考えたのであれば受け入れない(退けない)ような結論をしばしば無批判に受け入れて(退けて)しまっている。そこでブレナンは、自説を擁護する場合でも対立的な見解を批判する場合でも、対象となる議論を論証のステップごとに分解し、議論の流れを可視化することからはじめる。これにより、論証ステップの瑕疵の有無がみてとりやすくなる。続く第二のステップが、このように可視化された論証ステップの検証である。ここでブレナンが効果的に用いるのが、アナロジーと思考実験である。これらは、論証の各ステップにおける瑕疵の有無を、広く受け入れられている前提や直観をテコにして明らかにするための重要な装置の役割を果たしている。
例を挙げよう。エピストクラシーよりもデモクラシーを選ぶ理由の一つとして、しばしば、デモクラシーはそれ自体人々の間の平等を表出する点で象徴的価値をもつと主張される。ブレナンはまずこの曖昧な議論を分解し、その一つの解釈が、「能力の欠如を理由に誰かから政治的権利を剝奪することはその人に対する不尊重を表出する点で不正である」という前提に依拠することを可視化する。続いてブレナンは、アナロジーや思考実験を用いてこの前提を攻撃する。たとえば、我々は通常、能力の欠如を理由に医師免許を持たない人に医療行為を禁じることはその人への不尊重を表出するとは考えない、というアナロジカルな例が持ち出される。加えて、目の前で喉を詰まらせた人を助けようとする医師に対し不尊重の表出を理由に抗議する男の例を用いた思考実験により、重大な局面ではむしろ能力上の差異に訴えるべきであるとの我々の直観が浮き彫りにされる。重要なのは、この議論が極めて常識的な直観に訴えかけているということだ。このようにブレナンは、アナロジーや思考実験を効果的に用いることで、広く共有された前提や直観をうまく炙り出し、デモクラシーは象徴的価値を持たないという論争的結論を擁護している。
政治哲学の真髄の一つは、政治的事象について我々が無批判に受け入れてしまっている前提を疑い、精査し、それをより精確なものに変えていくことに存する。ここで説明した議論方法は、このような政治哲学の営みを実現する上で重要な役割を果たしている。その好例としての本書でのブレナンの議論は、常識を疑い反省を促す政治哲学のポテンシャルを十二分に例証しているといえるだろう。ここで紹介した政治哲学の方法についてより詳しい解説を行なっている研究としては、たとえばデイヴィッド・レオポルド、マーク・スティアーズ編『政治理論入門』(レオポルド・スティアーズ 2011)の第一章を参照されたい。
理想理論と非理想理論
理想理論と非理想理論は、理論の理想度に関わる政治哲学上の区分である(cf. Stemplowska and Swift 2012; ロールズ 2010)。本書が着目する政治体制の比較についていえば、両者は大まかにいって次のように区別できる。市民が道徳的・認知的に理想的であることなどの好ましい社会的条件が満たされているとの想定の下で望ましい政治体制が何であるかを問うのが理想理論であり、そのような好ましい条件を欠いた、我々の目の前に広がる現実の社会的条件を所与として望ましい政治体制を探求するのが非理想理論である。
ここで注意が必要なのは、理想理論で擁護される政治体制が現実社会でも望ましいかは別問題だという点である。ブレナン自身の比喩を用いれば、パイロットの能力や天候が理想的であるとの反事実的想定の下では望ましい飛行機が、現実世界においても望ましいとは限らない。同様に、市民が道徳的・認知的に理想的であるとの想定の下で望ましい政治体制が仮にデモクラシーであったとしても、それが現実世界でも望ましいとは必ずしも言えないのである。
ここに、非理想理論の枠内でデモクラシーへの懐疑論を提示する本書のような議論が生まれる余地がある。ブレナンの考えは次のようなものである。もし人々が十全に知識を得ており、合理的であり、かつ道徳的に理にかなっているような理想的社会があるとしたら、その社会においてはデモクラシーが完璧に機能し、いかなるエピストクラシーよりも良い帰結を安定的に生じさせるのかもしれない。しかし、現実の人々の多くは、十全に知識を得ても、合理的でも、道徳的に理にかなってもいない。したがって、現実のデモクラシーは完璧には機能していないだろう。エピストクラシーは、このデモクラシーよりは良い帰結を安定的に生じさせるかもしれない。そうであれば、私たちがいまここで目指すべき体制はエピストクラシーなのかもしれない。このようなブレナンの議論に対し、理想的なデモクラシーは非理想的ないし理想的なエピストクラシーよりも優れていると主張しても議論がすれ違うのみである。ブレナンの議論に正面から向き合うならば、ブレナン自身が想定する非理想状況を念頭に置いたうえでの吟味が必要である。
この点を念頭に置いた上で、本書に対する解説者一同からの疑念を一つ提示したい。本書の主要な目的が、非理想理論の枠内でエピストクラシーがデモクラシーに対する有力なオルタナティブとなり得ることを示すことであるのならば、前述の制約はブレナン自身にも適用される。換言すればブレナンは、非理想的デモクラシーに対して、それと同程度の市民の道徳的・認知的欠陥を伴った非理想的エピストクラシーが擁護され得ることを示さなければならない。しかしながらブレナンは、非理想的なエピストクラシーがどのように機能するかについて十分な検討を行っていないのではなかろうか。
この疑念は、エピストクラシーの具体的な制度的提案がなされる唯一の箇所である第八章の議論を検討することでより明確になる。そこではエピストクラシーが取りうるいくつかの形態が素描されているが、現実社会においてそれらがどのように機能するかについての検討が十分になされているとは言い難い。現実世界のデモクラシーを悩ませる市民の道徳的・認知的欠陥は当然現実世界のエピストクラシーも悩ませるだろう。たとえば、相対的に少ない政治的権力しか与えられていない市民が二級市民扱いをされたり、そのような市民が政治体制の正統性を受け入れないことで政治社会全体の安定性が損なわれることは想像に難くない。これに対し、理想的なエピストクラシーは当該の問題を避けられると主張することは見当違いである。諸々の欠陥を伴った非理想的エピストクラシーがそれでも非理想的デモクラシーに優越しうることが示されなければ、エピストクラシーが有力なオルタナティブであることが十分に示されたとは言えないだろう。
エピストクラシーは有力な制度的選択肢であるとの主張をより困難にするのが、ブレナン自身一定程度の説得力を認めている「バーク的保守主義」に由来する考慮事項である。イギリスの政治家・思想家エドマンド・バークは、旧体制の抜本的改革を目指したフランス革命が極度の暴力と混乱を招いた点に着目し、制度変革は極めて慎重になされなければならないと説いた(バーク 1997)。既存の制度は我々が十分に把握することが困難な──一見したところ不合理なものも含む──複雑なメカニズムを介して作動しているのであり、その改革は仮に崇高な理念の下になされたとしても意図せざる悪い結果を招きがちである。この点でバークが正しいのであれば、制度改革に伴うリスクを補って余りある利益を改革がもたらすことを示す論証責任は、制度改革を唱える側が負うべきであろう。だが、右で確認したように非理想的エピストクラシーの考察が十分になされていないため、ブレナン自身がこの論証責任を果たせているとは言い難い。
デモクラシー擁護の文脈でしばしば引用されるウィンストン・チャーチルのものとされる言葉に、「デモクラシーは最悪の政体である。これまで試みられたあらゆる政体を除けば」というものがある。本書はこの種のデモクラシー擁護に対し、「早まるな、エピストクラシーという未だ試みられていない有力な政体があるではないか」と異議申し立てするものである。しかし先述の疑念が正しいのであれば、ブレナンは非理想理論の枠内でエピストクラシーがデモクラシーに対する有力なオルタナティブとなり得ることを十分に示せてはいない。そうであるならば、一見したところセンセーショナルな本書の議論も結局のところは、「デモクラシーは最悪の政体である。これまで試みられた、また近い将来試みられうるあらゆる政体を除けば」という凡庸な結論の、「デモクラシーは最悪の政体である」の部分を強化するものに過ぎないのかもしれない。(以下、本文つづく。傍点は割愛しました)

















