あとがき、はしがき、はじめに、おわりに、解説などのページをご紹介します。気軽にページをめくる感覚で、ぜひ本の雰囲気を感じてください。目次などの概要は「書誌情報」からもご覧いただけます。
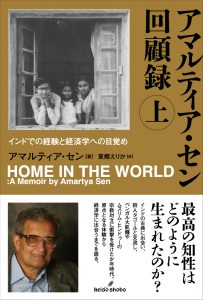

アマルティア・セン 著
東郷えりか 訳
『アマルティア・セン回顧録(上) インドでの経験と経済学への目覚め』
『アマルティア・セン回顧録(下) イギリスへ、そして経済学の革新へ』
→〈「はじめに」「第1章 ダッカとマンダレー」「第7章 最後のベンガル飢饉」「第15章 イギリスへ」「第18 章 何の経済学か?」「第25章 説得と協力」各章冒頭(pdfファイルへのリンク)〉
→目次・書誌情報・オンライン書店へのリンクはこちら:〈上巻〉・〈下巻〉
*サンプル画像はクリックで拡大します。「はじめに」などの本文はサンプル画像の下に続いています。
はじめに
物心ついたころの最初の記憶の一つは、船の大きな汽笛で起こされたことだった。もうじき三歳になるころのことだ。汽笛の音に不安になって私は起きあがったが、両親は何も心配はいらないのだと、カルカッタ〔現コルカタ〕からラングーン〔現ヤンゴン〕へ向かっていて、ベンガル湾を渡っているところだからと安心させてくれた。私の父は、現在はバングラデシュにあるダッカ大学で化学を教えており、客員教授としてマンダレーで三年間講義をすることになっていた。汽笛で目が覚めたとき、私たちの船はカルカッタからガンジス川を一六〇キロ下り終えて海に出たところだった(当時、カルカッタはまだかなり大型船の寄港地として機能していた)。これから数日間、ラングーンに到着するまで、海の真っ只中を進むことになるのだと父は説明してくれた。私はもちろん、海上の旅がどんなものかは知らなかったし、一つの土地から別の土地へ旅するいろいろな方法があることも知らなかった。それでも、冒険心が湧いたし、これまで一度も知らなかった何か重大なことが起こりつつあるのだという興奮は覚えた。ベンガル湾の深い青い水は、まるでアラジンの魔法のランプから湧きだしたかのようだった。
幼いころの記憶と言えば、ほぼすべてがビルマ(現在は軍が擁護する国名でミャンマーとも呼ばれる)にいたころのことで、私たち一家は三年ばかりそこで暮らしていた。私が覚えていることの一部は明らかに現実のことで、たとえば周囲を素晴らしい濠に囲まれたマンダレーの美しい宮殿や、イラワジ〔現エーヤワディー〕川の土手から見た印象的な景観、行く先々で見た形のよいパゴダ〔仏塔〕の存在などがあった。しかし、優雅なマンダレーの私の記憶は、ほかの人びとが語るひどく薄汚れた都市の説明とは一致しないかもしれない。また典型的なビルマ家屋だったわが家が、目を見張るほど美しかったと思うのは、そこが大好きだったために誇張されているのだろう。実際、私はこのうえなく幸せだった。
私はごく幼いころから旅をしてきた。ビルマで子供時代を過ごしたのち、ダッカに戻ったが、それからまもなく再びシャンティニケトンに引っ越して、そこで学ぶことになった。先見の明のある詩人、ラビンドラナート・タゴール〔ベンガル語ではロビンドロナト・タクル〕が実験的な学校を創設した場所だ。タゴールは私にも家族にも多大な影響を与えた。本書の原題名『Home in the World〔世界のなかの家〕』は、彼の著書『The Home and the World〔家と世界〕』から思いついたもので、タゴールの影響を反映している。
シャンティニケトンのタゴールの学校で一〇年間、楽しい日々を過ごしたあと、私はカルカッタへ行って大学教育を受けることになった。大学でも何人かの優れた先生と畏友に恵まれたが、学業をさらに補ってくれたのは、隣にあった喫茶店(コーヒーハウス)だった。素晴らしく活気のある議論や討論の場にたびたびなったのが、この店だった。私はそこからイギリスのケンブリッジ大学に留学した。このときもまた心躍る船旅で始まり、今回はボンベイ〔現ムンバイ〕からロンドンへと渡った。ケンブリッジの街も、私が学んだトリニティ・カレッジも、その壮大な古い歴史に私を引き込んだ。
その後、アメリカのマサチューセッツ州ケンブリッジのMIT〔マサチューセッツ工科大学〕と、カリフォルニア州スタンフォード大学で一年間、教壇に立った。私はさまざまな場所にしばらく根を下ろす試みをしたのちに、インドへ(パキスタンのラホールとカラチ経由で)帰国し、デリー大学で経済学、哲学、ゲーム理論、数理論理学、それに、比較的新しい科目であった社会的選択理論のコースを教えることになった。人生の最初の三〇年間の思い出は、熱心な若い教師として、自分の人生の新しい、より成熟した段階を予期しつつも、幸せな日々とともに終わった。
デリーで独り立ちするようになると、多岐にわたる経験をした若かりし日々を少々、振り返る時間ができた。世界の文明については二つのかなり異なる考え方があるのだと、私は結論づけた。一つの方法は「断片的」な視点に立ち、文明のさまざまな特徴は、それぞれかなり固有の文明の表明だと見なすものだ。断片相互の敵意に注目する特徴をあわせもつこの手法は、近年、大いにもてはやされ、長引く「文明の衝突」の兆候を示している。
別の手法は、「受け入れる(インクルーシヴな)」もので、究極的には一つの文明──おそらく世界文明と呼ぶべきもの──のさまざまな現象を探しだすことに専念するものだ。相互にかかわり合った根や枝からなる生命から、さまざまな花を咲かせる世界文明である。本書はもちろん、文明の本質を探るものではないが、お読みいただければわかるように、ここでは世界が提供するものを断片的に理解するのではなく、受け入れて理解する方法を取る。
中世の十字軍から前世紀のナチスの侵略にいたるまで、あるいは共同体間(コミュナル)の衝突から宗教的政治紛争まで、異なる信念同士のあいだで激しい闘争が生じてきたが、そのような衝突に対抗して統一を目指す勢力もまた存在してきた。目を凝らせば、一つの集団から別の集団へ、一国から他国へ、理解が広まってゆくのが見えるだろう。各地を回れば、より広く、より統合的な物語を示すヒントは否応なく見つかる。互いに学ぶ私たち人類の能力を、見くびってはならない。
影響を与え合う仲間がいるということは、とてつもなく建設的な経験となりうる。一〇世紀末から一一世紀初めにかけて、イランの数学者で長年インドで暮らしたビールーニーは『インド誌』のなかで、互いについて学ぶことは知識のためにも、平和のためにもなると述べた。彼は一〇〇〇年前のインドの数学、天文学、社会学、哲学、医学に関する素晴らしい報告書を書き、人間の知識が友情を通じていかに拡大するかも示す。ビールーニーがインド人に抱いた好感は、インドの数学と科学にたいする彼の関心と専門知識を高めた。しかし、このように好感を抱いたからといって、インド人を少しばかりからかうのに彼が遠慮することはなかった。インドの数学はたいへん優れているが、インドの知識人たちの最も稀有な才能は、それとはまるで異なるものだと、ビールーニーは言う。それは自分たちが知りもしない問題について、弁舌さわやかに語る能力なのである、と。
その才能がもし私にもあるとしたら、それを誇りに思うだろうか? それはわからないが、まずは自分の知っていることについて語ることから始めるべきだろう。この回顧録は、まさしくそのためのささやかな試みだ。あるいは、少なくとも私が実際に知っているにしろ知らないにしろ、私が体験したことについて語ろうとするものである。
第1章 ダッカとマンダレー
1
「ご自分の家(ホーム)はどこだとお考えですか?」と、私はロンドンで録画に向けて準備しているあいだにBBCのインタビュアーから尋ねられた。彼は私の略歴のようなものを見ていた。「向こうの〔アメリカのマサチューセッツ州〕ケンブリッジからこちらのケンブリッジへとただ引っ越して──ハーヴァード大学からケンブリッジ大学トリニティ・カレッジにこられた。何十年とイギリスに住んでおられたのに、まだインド国籍なので、おそらくパスポートは査証だらけなんでしょうね? それで、家はどちらなんですか?」これは一九九八年に、私が学寮長としてトリニティ・カレッジに再び戻ってきてすぐのことだった(そのためにインタビューを受けた)。「いまここですっかり家でくつろいだ(アット・ホームな)気分です」と私は答え、トリニティとは長年にわたる関係があり、学部生として、大学院生、特別研究員(フェロー)として、さらに教師としても過ごしてきたのだと説明した。しかし、向こうのケンブリッジのハーヴァード・スクエア近くにあった古いわが家でも充分にくつろいだ気分になったし、インドでも大いにくつろぐことができ、子供時代を過ごし、定期的に帰るのを楽しみにしているシャンティニケトンの小さなわが家ではとりわけそうだと、私は付け加えた。
「ということは、家という概念がないんですね!」と、BBCの男性は言った。「それどころか、私にはいくつかの居心地のいい家がありますが、家は唯一無二でなければならない、というあなたのお考えは、私のとは異なります」。BBCのインタビュアーはまるで納得していないようだった。
ほかにも不首尾に終わった同様の経験がある。何か一つだけ特定するように言われて、それに答えようと試みたときのことだ。「好きな食べ物は何ですか?」と聞かれるのだ。その質問にたいする答えはいくらでもあるが、私は通常、タリオリーニ・コン・ヴォンゴレとか、四川ダック、それにもちろんイリシュ・マチなどと、つぶやくことにしている。イリシュ・マチとはインドにいるイギリス人が有気音を勝手に変えて「ヒルシャ・フィッシュ」とよく呼んでいたものだ。ただし、挽(ひ)いたマスタードシードを使ってダッカ式にきちんと調理したものに限ると、私は説明を続けた。こうした答えで質問者が満足することはなく、こんな具合に聞き返された。「でも、どれが本当に好きな食べ物ですか?」
「どれも大好きなのです。ただし、どれか一つを私の唯一の好きな食べ物にして暮らしたくはありません」と、私は言った。質問者たちは通常、これではよい質問にたいするそこそこの回答を私から引きだしたとは考えなかった。しかし、運のいいときは、食べ物の話題ならば、お義理で相槌を打ってもらえることもあった。だが、「家」のように重要な問題では、絶対にそのように放免してはもらえない。「もちろん、本当にくつろげる特定の場所がどこかにあるはずですよね?」
2
なぜ、一つの場所でなければならないのか? たぶん、私はやたら容易に気が休まる質(たち)なのかもしれない。昔ながらのベンガル語では、「家はどちらですか?」という質問には、明確な意味がある。英語の質問が文字どおり伝えるものとは、まるで異なった意味だ。家──「ゴル」または「バリ」──は、数世代をさかのぼった一族の故郷のことであり、本人やごく近い祖先は別の場所で暮らしていても構わない。これと同様の使い方はインド亜大陸全土で見られ、英語の会話で使われた場合には、その考えはインド英語が独自につくりだした一種の地理的イメージとして訳されることがある。「どちらのご出身ですか?」その答えとなる「家/故郷」は、ゆうに数世代は前の祖先の出身地にもなりえて、本人は一度もそこを訪れたことがないかもしれない。
私が生まれた当時、家族はダッカ市に住んでいたが、実際には出生地はそこではない。一九三三年晩秋のことで、のちに知ることになったのだが、ヨーロッパでは途方もない数の家と人命が失われた年だった。この年、作家、芸術家、科学者、音楽家、俳優、画家など、六万人の専門家がドイツを離れ、大半はヨーロッパの別の国やアメリカへ移住した。若干の人──通常はユダヤ人──はインドにも亡命した。ダッカは、いまでは四方八方に広がり、どことなくつかみどころのない活気にあふれた都市となり、バングラデシュの首都でもあるが、当時はもっと静かでこぢんまりとした場所だった。そこでの暮らしはいつも優雅にゆったりと動いているように思われた。私たち家族は、ダッカ大学のキャンパスがあるロムナからそう離れていない、ワリと呼ばれる歴史的建造物の多い旧市街に住んでいた。父のアシュトシュ・シェン〔ベンガル語ではセンではなくシェンと発音する〕はダッカ大学で化学を教えていた。これはいずれも「昔のダッカ」で、現代のダッカはそこから何十キロ四方も先まで広がる。(以下、本文つづく。傍点は割愛しました)
第7章 最後のベンガル飢饉
1
一九四二年の初めには、私はすっかりシャンティニケトンに落ち着いたと感じていた。「平和の住処」ののどかな自然は、かなり印象的だった。そしてどこへでも徒歩か自転車で行けることが、何とも楽しかった。動力車がほとんど皆無であることは、この地の生活様式にどんどん慣れるにつれて、ありがたく思うようになった恵みだった。私は何よりも、シャンティニケトン・スクールのくつろいだ学究的な雰囲気を満喫していた。じつに興味深いあらゆる種類のことについて学ぶ機会があって、往々にしてカリキュラム外にそのような機会がさらにあることをありがたく思っていた。私は開架式で、利用者の立場に立った図書館をうろつき回りつづけ、自由気ままにあれこれ味見しては首を突っ込み、人生を様変わりさせていた。
とはいえ、自分自身の暮らしはそれほど順調であっても、周囲の世界で、インドの国内でも国外でも、緊張が高まっていることに私は気づき始めていた。激しい世界大戦は続いており、その東側の前線は私たちのほうへじりじりと近づいていた。だが、インドのかかえていた問題は、外の世界に端を発するものだけではなかった。ヒンドゥーとムスリムのあいだの緊張が政治的に醸成されていたのだ。そのうえ食品価格が急速に上がっていた。それによって生じた厳しい困窮状態は、ベンガルの多くの──おそらく大半の──家庭でつねに話題に上っていた。こうした問題や懸念はいずれも、私が一緒に暮らしていた祖父母を悩ませていたし、シャンティニケトンを頻繁に訪ねてきた私の両親をはじめ、親戚たちも同様だった。学校の休みに両親と過ごすためにダッカへ戻ると、そこでは不安な状況がいっそう肌身に感じられた。
2
飢饉の兆候を最初に見たのは、一九四三年四月のことだった。二〇〇万人とも三〇〇万人とも言われる人びとが犠牲になった、いわゆる「ベンガル大飢饉」のことである。食品価格は、飢饉前年の一九四二年にはかなり急速に上がり始めていた。
一九四三年春に授業が終わったとき、下の学年の生徒たちから、シャンティニケトンのキャンパスに入り込んできた精神錯乱状態らしい男が、二人のいじめっ子の生徒にひどくからかわれていると教えられた。私たちはこの野蛮な行為の現場──クリケット場の近く──へと向かった。二人のいじめっ子は、私たちの側の誰よりも個人としては腕力があったが、こちらは多勢だったので、力を合わせれば二人を押しとどめることができた。いじめていた二人が悪態をつきながらその場を去ると、私たちは犠牲者と話をしようと試みた。彼の話はほとんど首尾一貫していなかったが、一カ月近く何も食べていなかったのだと私たちは推測した。話をしているうちに、先生の一人が私たちのところへきてくれ、その先生から飢えが長引くとよく精神錯乱を引き起こすことを教えられた。
私がじかに飢饉の犠牲者と接したのは、それが初めてだった。だが、まもなく、飢餓から逃れようとして私たちの近所へほかの人びともやってきた。五月になって学期が終わり、夏休みに入ると、そうした人びとの数が増していった。飢えた犠牲者たちがますます大挙してやってくるなか、両親もシャンティニケトンで私と過ごすようになった(この時期は、ダッカ大学の父の仕事も休暇に入っていた)。七月に学校が始まったころには、細々とした人の流れは、悲惨な激流と化していた。人びとは食べられるものであれば何でも探し求めていた。大半は一六〇キロ近く離れたカルカッタへ向かう途中だった。カルカッタには生活困窮者を支援するための準備がなされているという噂があったからだ。こうした噂はとんでもなく誇張されたものだった。実際には、政府は何ら救済策を講じておらず、民間の慈善事業は嘆かわしいほど不充分だった。ところが、この噂のせいで、飢えた人びとはカルカッタへ行きたがった。カルカッタまでの旅を続けられるように、少しばかりの食べ物を──食べ残しや腐った食べ物でも──私たちに恵んでほしがっていた。
状況は悪化しつづけ、九月までにおそらく一〇万人ほどの困窮者が大都市へ向かう長旅の途中でシャンティニケトンを通過しただろうと私たちは考えた。助けを求めて、子供からも大人の男女からも聞こえつづけた泣き叫ぶ声が、七七年を経た今日でも私の耳にこだまする。私の祖母は、食べ物を乞う人がいれば誰にでも、タバコの缶いっぱい分の米は分け与えさせてくれたが、「たとえ胸が張り裂けても、缶いっぱい以上の米は誰にもあげてはいけないよ。できる限り多くの人を助けなければならないのだから」と説明した。小さな缶一杯分の米では、長くもたないことはわかっていたが、自分たちが少なくとも何かしらの援助はできることが私には嬉しかった。当時、やってきた人の一人は、第4章で述べたように、ジョッゲッショルだった。シャンティニケトンから六四キロほど離れたドゥムカからきた一四歳の、生死の境にあるほど飢えた少年で、私の伯母がすぐさま命を救うために彼の食事の面倒を見るようになった。(以下、本文つづく)
第15章 イギリスへ
1
私がイギリスに留学するという考えは、最初は父の頭のなかで芽生えた。父はロンドン大学で三年間、農芸化学の博士課程で学び、その大半をハートフォードシャー州ハーペンデンのロザムステッド研究所で過ごして大いに楽しんでいた。私ががんの放射線治療を受けていたとき、両親はこの治療騒動が終わったら私が楽しみにできるものを何か与えたがっていた。父はロンドン・スクール・オヴ・エコノミクス(LSE)のよい評判を聞いていたので、この大学に行きたくはないかと、私に尋ねた。「それはすごいね」と、私は答えた。「でも、それだけのお金があるの?」これは当然の質問だった。私の家は裕福ではなかったし、長年、大学の教師を務めた父はかなり薄給の身だったからだ。
ちょっと計算してみたところ、学費を含め、私がロンドンで三年間過ごせるだけの資金が──ちょうど──あると判断したのだと父は言った。当時は、イギリスへ留学するための奨学金などはまずなく、その時点で私が対象になりそうなものは間違いなく皆無だったが、幸い、学費はきわめて安かった。インフレ分を調整しても、今日の何分の一以下だ。
そのため、私は高線量放射線治療による体力消耗から回復したのち、自分が何をすべきかを検討することになった。私は先述したオミヨ・ダシュグプトとも話をした。オミヨおじは、確かに留学先はイギリスにすべきだと考えたが、LSE(彼は一九三〇年代初期にそこで博士号を取得した)ではなく、当時、経済学では世界一流だと彼が考えるケンブリッジに行くべきだと言った。
そこで、私はブリティッシュ・カウンシルの図書館に行って、イギリスの大学に関する情報を集めた。そこの図書館は、私が足繁く通っていた場所の一つで、魅力的であり、とても使いやすい場所だった。ケンブリッジのさまざまな学寮(カレッジ)に関する資料を調べていたとき、トリニティ・カレッジが私の目に飛び込んできた。このカレッジに関しては、いくつかの別々の理由から少しばかり知っていた。私のいとこのブッドはインド独立直後に、このカレッジでインド行政職の研修生として半年間を過ごしていた。私はブッドが大好きで、英語が読める以前の子供のころから、シェイクスピアの戯曲の裏話を彼から聞いていた(彼は私にとってチャールズ・ラムの『シェイクスピア物語』〔邦訳は岩波文庫など〕の生きた見本だった)。のちに成長して一六歳になったころ、ブッドが帰国してまもなく、トリニティについて語る彼の楽しそうな賛辞に耳をそばだてるようになった。カレッジのグレートコート〔という広い中庭〕にある時計が男女の声で交互に(つまり低い音と高い音で)時を告げるという彼の話すら楽しんだ。
私はさらにニュートンや〔フランシス・〕ベーコンについても、〔バートランド・〕ラッセルや〔哲学者のアルフレッド・N・〕ホワイトヘッド、〔哲学者のジョージ・E・〕ムーアにヴィトゲンシュタインについても、かなりよく知っていたし、トリニティの詩人たち(〔ジョン・〕ドライデンが私のお気に入りだったが、ほかにも〔アンドルー・〕マーヴェル、バイロン、テニスン、〔アルフレッド・E・〕ハウスマンなど)や、トリニティの数学者たち(〔ゴッドフリー・H・〕ハーディ、〔ジョン・E・〕リトルウッド、それに侮りがたき〔シュリーニヴァーサ・〕ラーマーヌジャン)やトリニティの物理学者、そして生理学者についても知っていた。
決定的瞬間が訪れたのは、二〇世紀でおそらく最も独創的なマルクス経済学者のモーリス・ドッブがトリニティで教えていて、ピエロ・スラッファも同様であることを発見したときだった。スラッファは経済学と哲学双方の主要な思想家で、偉大なマルクス主義思想家のアントニオ・グラムシの親友であり、同僚だった。そして彼らのほかにデニス・ロバートソンの名前も付け加えなければならない。ロバートソンは功利主義的経済学の第一人者で、優れた保守派の思想家でもあるが、マクロ経済学において素晴らしく独創的な研究も行なった人物だった。ある意味で、ジョン・メイナード・ケインズに関連づけられる考えを予期させるものだ。ドッブやスラッファ、ロバートソンとともに研究できる可能性は、何とも心ときめくものだった。私は自分の選択を強く確信していたので、トリニティに願書を出したばかりか、ほかのどのカレッジにも出願しなかった。実際には、「トリニティか不合格かだ」と、私は心を決めていた。
2
そしてたちまち、不合格になった。トリニティは私の願書を驚くほど速やかに却下し、「本年」はインドからあまりにも大勢の優秀な出願者がいたという、型どおりの説明がそこには付されていた。何とも残念なことだった。そこで、私はカルカッタ大学で勉強を続けることにした。私はプレジデンシー・カレッジで二年目を終了するところで、その年度が終われば何らかの学士号が取得できることになっていた(その学位を取得したころには私は一九歳になっていた)が、あと二年勉強すれば、本格的な大学の学位を得られることになり、(以下、本文つづく。注番号は割愛しました)
第18 章 何の経済学か?
1
一九五四年の夏、私はトリニティの大門からトリニティ・ストリートを渡った先にあるヒューウェルズ・コートの一室を与えられた。部屋は広々としていて、居心地のいい寝室とかなり大きな居間があった。しかしもちろん、当時のトリニティの学寮はたいがいそうだったが、洗面所に行くのに中庭を横切り、トリニティ・ストリートを渡って、タオルを片手にグレート・コートまで行ってシャワーを浴びなければならなかった。私の部屋はお湯が出なかった(それどころか水道がなかった)ので、室内清掃員が毎朝、洗顔や髭剃り用に熱い湯と水の入った二つの水差しと、それを注ぎ入れる白い大きなたらいを運んでくれた。
ようやく学寮で生活できるようになって私は嬉しかったが、プライオリ・ロードのハンガー夫人の家を離れるのは寂しかった。彼女が大好きになっていたのだ。それまでもずっと親切な人だったが、私が下宿していた一年間に彼女は人種間の平等を訴える活動家へと変身を遂げていた。一九五三年一〇月に最初に会ったときは、風呂のなかで私の肌の色が落ちるのではないかと心配していたのに、私が下宿を離れたころには、彼女は近所中の人に「すべての人間は平等」であることを理解する必要について説いて回るようになっていたのだ。
一九五四年六月にお別れに行くと、彼女はお茶と手作りのケーキを出してくれて、私がいなくなると寂しくなると言った。それから人種問題に関連して非常に進歩的なことを語りつづけ、彼女が定期的に通っているダンスクラブで、パートナーを探して待っていたアフリカ人男性と踊りたがらなかったイギリス人女性を、自分がいかに叱責したかを語った(「とても頭にきていたので、その男性をつかんで一時間以上、一緒に踊ったのよ。もう家に帰りたいと彼が言うまで」)。
何十年ものちの一九九八年一月にケンブリッジに戻ったとき、私はもう一度彼女に会いたくなり、学寮長宿舎へお茶に招いたら喜んでもらえるのではないかと思ったのだが、電話帳で探しても一家の名前は見つからなかった。そこで、プライオリ・ロードまで行ってみたが、ハンガー家がどこへ越したかは誰も知らないようだった。もちろん私が最後に彼女に会ったのは四四年も前のことで、彼女がまだそこに住んでいると期待した私が愚かだった。しかし、温かく親切だった大家さんの姿を一目も見られなかったことが、私には悲しかった。
2
ヒューウェルズ・コートに入寮すると、私は別の学部生ですぐそばの部屋に入っていたサイモン・ディグビーに歓迎された。彼は私より二年前の一九五一年にトリニティに入学しており、共通の友人はいたが、近くの部屋同士になるまで実際には知らなかった。私をヒューウェルズ・コートに迎えるために、サイモンがインド料理をつくってくれたことにはたいへん感動した。あいにく、その日、私の引っ越しは遅くなり、荷物をもって到着したのは真夜中近くだった。もちろん、私はサイモンがエビのカレーをつくって待っているなどと思いもしなかったのだ。私たちはご馳走を食べたが、私にはその晩、二度目の夕食だったし、彼にとってもそうだったに違いない。
サイモンのインドの歴史にたいする、なかでもムガル帝国以前のイスラーム史への熱意と深まる一方の造詣はすでに敬服に値するものだった。彼との会話は、私にとっては事実上、無料で個人指導を受けているようなものだった。しかし、私たちは現代の政治に関しては意見が食い違った。サイモンはパキスタンがムスリム国と呼べるのと同様に、インドをヒンドゥー国家と見なしたがっていたからだ。彼がおもに嫌悪していた一人がジャワハルラール・ネルーで、とくにネルーの歴史家ぶった側面だと彼が考えるものを嫌っていた(「彼の『父が子に語る世界歴史』〔邦訳はみすず書房〕以上の駄作はなかなか書けないよ、そうだろう」)。サイモンはネルーの政治にも強い違和感をもっていた。(以下、本文つづく。写真は割愛しました)
第25章 説得と協力
1
一九五三年の秋に私が渡英したころには、第一次世界大戦の直接の記憶はほぼ失われていたが、第二次世界大戦の記憶はまだヨーロッパ全土で生々しかった。戦争が始まる前の日々の苦痛に満ちた不安もまだ強く残っていた。当時の雰囲気は一九三九年初めに書かれたW・H・オーデンの「W・B・イェイツの思い出に」のなかで、よく捉えられている。
暗闇の悪夢のなかで
ヨーロッパ中の犬が吠え、
生きている民は待つ、
みな憎しみに閉じ込められつつ。
その後に続いた出来事は、オーデンが予期した最悪の事態を裏づけるばかりとなった。
イギリスで過ごした最初の数年間に、戦争までの時代がいかに不安なものだったのかという話をたくさん聞いた。世界大戦が再び繰り返される恐ろしい可能性はじつに多くのヨーロッパ人を苛み、自滅的な戦争に突入する不安のない、ヨーロッパの統一に向けた運動は政治的な統一を求める欲求に強く駆られていた。そのような結果を実現させたいという希望は、その運動を始めた二つの先駆的な文書によって明らかにもたらされた。一九四一年のヴェントテーネ宣言と、一九四三年のミラノ宣言である。ヨーロッパの統一を断固として、歯に衣を着せずに主張した四人のイタリア知識人たち──アルティエロ・スピネッリ、エルネスト・ロッシ、エウジェニオ・コロルニ、ウルスラ・ヒルシュマン──によって準備されたものだ〔ヒルシュマンはドイツ出身〕。
経済的な統合をはかる利点は、ヴェントテーネとミラノの両宣言を支持する人びとにはよく理解されていた。長期的には金融面の統合を目指すことすら、彼らに近い人びとによって明らかに示されていた(なかでも、のちにイタリア大統領となったルイジ・エイナウディによって)。ヨーロッパ統一の必要性の根底にあった直接の懸念は、通商や事業への配慮ではなく、統合された銀行業務や通貨協定(これらは後年実現することになった)でもなく、ヨーロッパの平和のために政治的な統一をはかる必要性だった。
私は七〇年にわたってヨーロッパ統一のプロセスを見守る機会に恵まれた。先に述べたように、ヒッチハイクをした若いころに、ヨーロッパのさまざまな国の人びとに気軽に出会い、密接にかかわったことや、それらの人びとの振る舞いや優先事項が似ていたことから、私には「ヨーロッパ」として一緒になりつつある地域にいるのだという感覚を味わった。当時の私の主たる動機は、政治的な英知を育むことではなく、ただヨーロッパをよく知り、旅行を楽しみたいだけだった。しかし徐々に、自分はヨーロッパ統合が展開する様子を眺めてもいるのだということが明らかになってきた。
統一したヨーロッパを誕生させることは長年の夢であり、この夢はキリスト教の普及に大いに助けられながら、文化的、政治的統合の波を何度もくぐり抜けてきた。ボヘミア王イジーは一四六四年にすでに汎ヨーロッパ統一について語っていた。その後の時代にも多くの人びとが彼に続いた。一八世紀には大西洋の向こうから、ジョージ・ワシントンがラ・ファイエット侯爵に、「いつの日か、アメリカ合衆国をモデルに、ヨーロッパ合衆国が誕生するでしょう」と書き送った。年月とともに、ジョージ・ワシントンの予測が実現するかもしれない事態になり始めた。
二〇二一年に本書を執筆するなかで、状況はハンガリーやポーランド、そして一部にはフランスやイタリアですら変わりつつある。世論はヨーロッパの統一に反対するようになり、ヨーロッパの民主主義の伝統による要求にすら反対の声が上がりつつある。この後ろ向きの姿勢はもちろん、イギリスでも非常に蔓延しており、二〇一六年のいわゆるブレグジットに関する国民投票では、ヨーロッパ連合を脱退することに賛成を投じた人がわずかながら多数となった。いまではヴェントテーネを逆戻りさせる風潮が強くなっている。
2
だが、その間の八〇年間に、ヨーロッパではいくつかの驚くべき成果が──法の支配、人権、参加型民主主義、経済協力に──見られ、そのいずれもが一九五三年に私がティルベリー・ドックスに上陸したときには、確実には期待できなかったものだった。私が見たなかで最も感動的なものはおそらく、国民保健サービス(NHS)をはじめ、福祉国家の発展に建設的な兆候が見られたことだった。この抜本的な変化は、社会にたいする新しい考え方と関係していた。(以下、本文つづく)














