あとがき、はしがき、はじめに、おわりに、解説などのページをご紹介します。気軽にページをめくる感覚で、ぜひ本の雰囲気を感じてください。目次などの概要は「書誌情報」からもご覧いただけます。
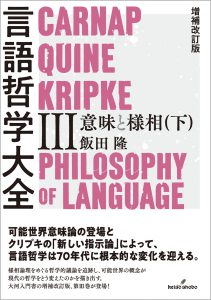 飯田 隆 著
飯田 隆 著
『増補改訂版 言語哲学大全Ⅲ 意味と様相(下)』
→〈「増補改訂版へのまえがき」「後記 二〇二四年(抜粋)」(pdfファイルへのリンク)〉
→〈目次・書誌情報・オンライン書店へのリンクはこちら〉
※第Ⅰ巻のたちよみはこちら⇒『増補改訂版 言語哲学大全Ⅰ 論理と言語』
※第Ⅱ巻のたちよみはこちら⇒『増補改訂版 言語哲学大全Ⅱ 意味と様相(上)』
*サンプル画像はクリックで拡大します。「まえがき」本文はサンプル画像の下に続いています。
増補改訂版へのまえがき
これまでの巻の場合と同じく、初版のテキストへの変更は最小限にとどめた。つまり、句読点とカッコ類の使い方を最近の私の使い方に改めたことと、初版より後に出た翻訳および文献への指示を註に付け加えたことが、主である。日本語以外の著作からの引用に際しては、既存の訳を掲げている場合も、特に断っていない限り、私自身の翻訳である。初版の5・3・1節の一一八頁から一二〇頁にかけて誤りがあったので訂正したが、これはごく一部の読者にだけ関係することだろう。
補註は主に第7章にかかわるので、これまでのように章ごとに番号を振るのではなく、全体を通しての番号にした。また、それぞれの補註で何が扱われているかが一目で見られるように表題も付けた。
本書の初版が出てから三十年近く経つが、ここで扱った話題に関しては、一九七〇年前後に生じたような大きな変化はないと思われる(だが、私が気付いていないだけで、すでにそうした変化は進行しつつあるのかもしれない)。ごく限られた範囲ではあるが、今回の改訂増補にあたって私が見た限りで大きな印象を与えられたのは、着想自体は前からあったアイデアが、きわめて具体的な仕方で仕上げられつつあることである。補註1で紹介した、固有名の変項説、および、補註5で紹介した、命題を測度とみなす命題態度についての理論が、それである。こうした例を見るにつけ、哲学では、すでに可能な道はすべて試されているようにみえても、常に新しい道を見出すことができることを痛感する。これはおおいに勇気づけられることである。
この巻に関しても、勁草書房編集部の土井美智子さんにすっかりお世話になった。コロナの流行がまだ収まらないなかで始まったこの巻の制作の全期間にわたって、細かな配慮をしていただいただけでなく、遠隔の地からの私の注文にもこたえていただけたことは本当にありがたかった。また、校正に際しては、第Ⅱ巻に引き続き、高取正大氏の手をわずらわせた。丁寧に見ていただいたことに心から感謝する。
二〇二三年一一月三〇日
飯田 隆
後記 二〇二四年
6 様相虚構主義
可能世界の本性を問題にするのではなく、可能世界の概念を用いてさまざな分野で探究を行う哲学者や言語学者の多くは、可能世界についての話を文字通りに取ることはしない。それはむしろ、ある種の虚構(フィクション)であるとさえ考えられている。これをまともに取って、可能世界を真剣に虚構として考察しようとする、様相虚構主義(modal fictionalism)という立場が生まれたのも当然かもしれない。実際、この三十年ほどのあいだに、この立場は、可能世界をめぐる哲学的議論の中心を占めるまでになっている。可能世界の話を文字通りに受け取る哲学者や言語学者はほとんどいないのに、なぜ可能世界論はこれほどの成功を収めたのだろうか。その大きな理由は、様相的事柄についてのわれわれの直観が、それほど体系的でも、また、一貫しているわけでもないという事実にある。さまざまな選択肢を示すことによって、そうした直観を整理し体系化するのに、可能世界論が有効であったことはまちがいない。とりわけ役に立ったのは、可能世界論が絵に描くことができ、それゆえ、操作することができるということである。可能世界論のこの特徴は、数学の多くの分野のもつ特徴であるだけでなく、一般性を追求する分野すべてにみられる特徴だろう。
複数的対象の想定は多くの哲学者からの非難を浴びたが、「お話」と受け取るならば、使い方さえまちがえなければ、そうされる筋合いはない。複数のものをそのまま複数のものとして扱うことは、複数的指示や複数的述語づけを常に行っている日本語の話者にとってさえむずかしい。複数のものをまとめて「ひとつ」として考える方がずっと操作しやすい。複数のものを「ひとつ」と考えることが問題を起こすのは、あまりにもたくさんのもの、たとえば、ありとあらゆる対象を「ひとつ」と考えるような場合である。これを「ひとつの」集合とするところから、ラッセルのパラドックスが生じるからである。このように複数的対象の想定には限界があるが、問題が生じないところで、この想定を使うことは許されてよい。
複数的対象という虚構の想定は、われわれの理解を助けるという心理的な理由による以上のものではない。これに対して、可能世界というものを想定したくなるのは、心理的な理由もあるが、それだけではない。
日常の場面で可能性について考えるとき、われわれは世界全体にわたる可能性のようなものを考えたりはしない。われわれが考えるのは、ずっと限られた範囲での可能性である。これからの日本の針路といったことを考えるときであっても、われわれが考える範囲は、たぶん地球上のことに限られるだろう。太陽系の全体とか、銀河系の全体とかに考えが及ぶことは決してない。しかし、太陽系や銀河系の歴史について考えることはできるし、なかにはそれを専門にしているひとだっている。可能世界を考えるということは、こうした思考を世界の全体にまで広げることにすぎないのではないだろうか。
われわれが考える可能性は、ごく限定された範囲での可能性ではあるが、その範囲がどこまでであるかは明確ではない。「今朝少し早く家を出ていたら、どうなっていただろうか」と考えるとき、自分の行動が影響したかもしれない範囲を正確に特徴づけることはできない。もしも世界全体がそうあったかもしれない可能性として、可能世界というものを想定できるならば、そうした可能世界のひとつひとつはその細部まで決まっているのだろうから、異なる可能性の各々をひとつの対象として扱うことができる。そのように対象化された可能性、すなわち、可能世界の集まりとして、自分の可能な行動の影響の範囲を考えることができる。この範囲を正確に特徴づけることは相変わらずできないとしても、それが、可能世界という対象の全体から成る集まりの内のある領域を占めるとみなせることは、少なくとも心理的には大きなちがいになる。可能世界のひとつひとつを点として含む図形中のある領域として描くことができるからである。
時間的延長をもたない点としての瞬間という概念は、一定の幅をもつ時間的持続からの「理想化」によって得られると考えるのと同様に、常に部分的な状況にだけかかわる可能性からの「理想化」によって、可能世界の概念が得られると考えることができる。だが、こうした理想化は、われわれ自身によって達成できるものだろうか。
可能世界に関して「現実主義」の立場をとる哲学者(本書一六三頁以下)は、可能世界とは、現実の存在者から構成されたものとみなす。しかし、ひとつの可能世界を構成するためには、その世界をあらゆる細部にわたって指定できるのでなくてはならない。それだけではない。可能世界の全体から成るシステムを構成するためには、あらゆる細部にわたって指定された可能性の全体を構成しなくてはならない。つまり、可能世界とは、われわれが構成できるようなものではないし、仮にわれわれと独立に存在するとしても、その細部にわたるまでわれわれが認識できるようなものではない。
可能世界の概念をその哲学の基礎に置いた二人の哲学者、ライプニッツとD・ルイスにおいては、こうした問題は生じない。ライプニッツにとって、現実世界以外の可能世界は、神の知性のうちに存在する。神の知性は無限であるから、神は、あらゆる可能世界をその細部にわたってまで認識している。他方、ルイスにとって、現実世界以外の可能世界は、現実世界と同じ種類のものであるから、現実世界と同様の確定性をもっている。
ライプニッツの可能世界論も、ルイスのそれも、大きな喚起力をもっている。前者をきっかけにヴォルテールの『カンディード』が生まれ、後者がジャック・ルーボーの詩集『ルイスの世界の複数性』を生んだことに、それはよく示されている。だが、同時に、かれらの可能世界論を本気で信じることはできない。ヴォルテールはもちろん信じていないし、ルーボーも本気では信じていないと私は想像する。
(以下、本文つづく。注は割愛しました)





