あとがき、はしがき、はじめに、おわりに、解説などのページをご紹介します。気軽にページをめくる感覚で、ぜひ本の雰囲気を感じてください。目次などの概要は「書誌情報」からもご覧いただけます。
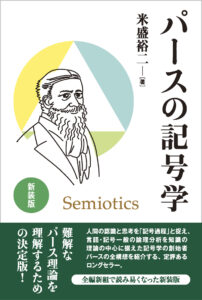 米盛裕二 著
米盛裕二 著
『新装版 パースの記号学』
→〈「まえがき」(pdfファイルへのリンク)〉
→〈目次・書誌情報・オンライン書店へのリンクはこちら〉
*サンプル画像はクリックで拡大します。「まえがき」本文はサンプル画像の下に続いています。
まえがき
チャールズ・サンダース・パース(Charles Sanders Peirce, 1839─1914)──アメリカの哲学者、論理学者、数学者、物理学者、化学者──はプラグマティズムの創始者であり、現代記号学(記号に関する一般理論)の創設者の一人である。パースは「かれの時代の最も偉大な形式論理学者」で、ブール、フレーゲ、シュレーダーらとともに現代の数学的論理学(または記号論理学)の先駆者でもあり、かれはまたデデキント、カントールらとともに集合論、超限数論に重要な貢献をし、数学の論理的哲学的分析の現代的発展における先駆者の一人でもある。パースはさらに自然諸科学の方法と成果に精通し、今世紀における科学方法論、科学哲学の発展に最も大きく貢献した人である。その上かれはすぐれた科学史家で、哲学史家(特に、スコラ哲学とカント哲学の権威)でもあり、そして現象学、科学的形而上学の分野でもきわめて独創的な思想を多作しており、パースは確かに「合衆国が生んだ最も多才で、最も深遠な、そして最も独創的な哲学者」と言える。
しかしパースは生前そして死後も久しく世に埋もれてきた不遇の人である。かれはマサチューセッツ州のケンブリッジに生まれ、生涯の前半は、恵まれた家庭で早くから科学的天才を認められて著名な父親(ベンジャミン・パース──ハーバード大学の数学および自然哲学の教授で、当時のアメリカにおける最大の数学者)の下で特別の家庭教育を受け、ハーバード大学を経て、期待どおりに数学、論理学、物理学、天文学、化学の多領域で頭角を現わし、地元アメリカおよび広くヨーロッパの学界で活躍し、きわめて目立った出世街道を歩んできた。しかしパースを知る人びとが一様に伝えているかれの偏窟な性格や、私生活の乱れ──特に、かれの先妻(ハリエット・メルシナ・フェイ──社会改良家、著述家で、ボストン社交界の有力者)との離婚問題──などに加えて、当時のアメリカの学界はまだ論理学の研究にあまり関心がなかったという、パースにとっては最も致命的な情勢があって、結局かれは長い間求めつづけてきた大学教授のポストを遂に得ることができず、後半生はあらゆる職を失って貧困と孤独と病苦のなかで過した不運な人であったと言われる。一八八七年には、まだ働き盛りの四十八才の若年でペンシルバニヤの山村ミルフォードに隠遁、その後は書評などで得たわずかの収入とW・ジェイムズら友人たちの施しに頼り、一方学界からもますます遠ざかって全く無名の人となり、そして最後の数年間は一文なしの極度の窮乏と不治の病に苦しみながら、しかしそれでもなお最後まで、出版の当てのない難解な学説を書きつづけ、莫大な手稿を遺して、一九一四年四月十九日に世を去った。
パースの遺稿はかれが死んだその年の末にハーバード大学哲学科が買集したが、しかし編集にかなり手間取り、J・ロイス、C・I・ルイスらの編集計画のあとを受けて、最終的にC・ハーツホーンとP・ワイスの編集で『チャールズ・サンダース・パース論文集』(Collected Papers of Charles Sanders Peirce, Harvard University Press)──六巻、以下『論文集』と略称する──が出版されたのは、パースの死後実に二十年後の一九三一─三五年においてであった。そして遺稿が大半を占めているこの『論文集』の出版によってパース哲学のほぼ全貌がはじめて世に出たのである。その後、一九五八年にA・バークスの編集でさらに二巻が加えられ、現在の『論文集』は八巻ある。しかし現在の『論文集』も完全なものではなく、目下アメリカ哲学会東部支部会の「チャールズ・S・パース学会」(The Charles S. Peirce Society)の中心メンバーたちによって、主編者M・フィッシの下で、パースの全著作の再編集が進められている。こうして地元のアメリカでも本格的なパース研究はむしろこれからはじまろうとしているところである。
パースがこのように長い間世に埋もれていたのは、何よりも、「パースはかれ自身の時代において理解されるにはあまりに時代に先んじていた」からである。実際、『論文集』で取り扱われている哲学的論理学的主題──記号学、記号論理学、数学基礎論、確率と帰納の論理、意味の検証理論、操作主義、アブダクション(仮説または発見の論理)、現象学など──は、すべてが、アメリカでは、一九三〇年代の中葉以降に、つまりパースの死後二十余年も経って、ようやく一般の哲学者たちの関心をひくようになったものである。アメリカで論理学、数学基礎論、科学哲学の研究が盛んになり、そしてそれらの分野におけるすぐれた先駆者で地元アメリカ出身のパースの存在が注目されるようになったのは、今世紀三十年代の中葉頃からアメリカ哲学界を風靡した外来の論理実証主義、分析哲学の影響によるものである。しかしパースの記号学、アブダクションの理論、現象学などは論理実証主義、分析哲学以後の、最近の新らしい時代におけるアメリカ哲学の主題であり、パースのそれらの学説はむしろこれから注目され、今後の論議に貢献するものであろう。そこでわたくしが本書の主題にパースの記号学説を選んだのも、最近わが国でも高まりつつある記号学的関心に応え、パースの学説をわが国におけるこれからの記号学の研究に役立てたいと考えたからである。
しかしわたくしはいわゆる記号学者ではない。わたくしはもともとはアメリカ哲学──特に、プラグマティズム──を研究している者で、わたくしが記号学と関わるようになったのはプラグマティズムを代表するアメリカの思想家たち──パース、デューイ、ミード、モリスら──がすべて記号学にも重要な貢献をしているからである。わたくしにとってはつまりアメリカ哲学、プラグマティズムの研究が主である。そして本書もわたくしのアメリカ哲学およびプラグマティズム研究の一環であり、その立場から行われた一つのパース研究である。わたくしはもちろん本書が一般の記号学者たちにも読まれることを願っているが、しかしわたくしがさらに念願していることは、本書がわが国におけるアメリカ哲学、プラグマティズムの研究に、とりわけパース哲学の研究に、少しでも貢献できることである。
わが国では鶴見俊輔氏が一九五〇年に氏の『アメリカ哲学』(世界評論社)においてパースの人と思想を紹介し、その後上山春平氏が氏の『弁証法の系譜』(未來社、一九六三年)で「パースの論理思想の弁証法的性格」に注目してきわめてユニークなパース紹介を行い、なお同氏の編訳『パース・ジェイムズ・デューイ』(世界の名著、第四十八巻、中央公論社、一九六八年)もわが国におけるパース研究の一つの重要な礎石を敷いたが、しかし後継者が少なく、わたくしの知る限りわが国ではパース哲学に関するまとまった研究書はまだ出ていない。もちろん拙著も表題が示すとおり主にパースの記号学およびそれに関連する学説を検討するもので、パース哲学の全体系を取り扱うものではなく、とてもパース哲学に関するまとまった研究と言えるものではない。しかしわたくしとしては、折角鶴見氏、上山氏らが先鞭をつけてくれたわが国におけるパース研究をさらに刺激するのに、本書が少しでも役に立てば幸に思う。
ところがパースを知る人びとが一様に述べているように、パース哲学はきわめて難解なものである。本書が取り扱っているパースの現象学、記号学、プラグマティシズムのそれぞれの学説の内容も難しいが、その上それらの学説を体系的に解釈し整合的に論述することは非常に難しい。T・ゴウジも言うように、「すぐれた編集にもかかわらず、『論文集』は断片的で、繰り返しが多く、体系がない」。『論文集』は独創的な哲学的論理学的思想の宝庫であるが、しかし意味の曖昧なところ、論議の連関が正確につかめないところ、辻つまの合わない部分も多く、あるいはたとえわたくしには理解できたようでも、しかし一般の読者に理解できるように解説することは容易でないところも多々ある。そこで本書では、パースのわかり難い言葉を直接引用するよりもわたくしなりの解釈で論議の連関を明確にしようとつとめたところも多く、できるだけ体系的に解説しかつ一般の読者にも理解できるように心がけたまではよいが、しかしそのために、逆にパースの思想を曖昧にし、パースの真意に反する過ぎた解釈を行ったり、あるいはひどい誤解もあろうかと思う。切に読者のご批判、ご教示を乞う次第である。
なおパースの『論文集』からの引用は各引用文の末尾に巻数とパラグラフ・ナンバーを示した。たとえば第五巻の二六五パラグラフは(5.265)とした。
わたくしが本書を世に出すことができたのは、何よりも、一九七二─七三年にACLS(American Council of Learned Societies)のフェローシップを得て、ハーバード大学哲学科で客員研究員として一年間集中的にパース研究を行うことができたお蔭であり、ここに深謝を表明したい。なお本書の出版が実現したのはわたくしの友人、東京工業大学の藤川吉美氏と早稲田大学の内田種臣氏のご尽力のお蔭である。遠い沖縄にいて中央の出版界に知り合いが少ないわたくしを勁草書房に紹介して下さったのは両氏であり、心から謝意を表したい。
また、本書の出版を快諾して下さった勁草書房、特に、熱心にご助力下さった伊藤真由美様に心からお礼を申し上げたい。
一九八一年三月
著 者





