10月刊行の『問答の言語哲学』について、著者入江幸男先生のブログ「哲学の森」では本書の各章の解説、追加説明を連載されています。読者の方々へのガイドとして、弊社サイトにも記事転載させていただくことになりました。全6回シリーズでお届けいたします。読む前に、読んだ後に、ぜひお楽しみください。[編集部]
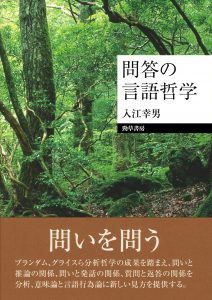
拙著『問答の言語哲学』(勁草書房、2020)について、解説したり、追加説明したり、ご批判やご質問に答えたりしたいとおもいます。素朴な疑問、忌憚のないご意見、励ましの声、なども歓迎いたします。→【哲学の森|入江幸男のブログ】
1 質問発話の特殊性
本書第1章では、命題内容の意味を問答推論関係として説明しました。第2章では、命題の特定文脈での発話の意味について説明しました。言い換えると発話が焦点を持つとはどういうことかについて説明しました。焦点位置の違いは、命題内容の与えられ方の違いであり、発話の意味は二重問答関係のなかで成立するということでした。第3章では、行為としての発話、言語行為を考察します。この章も3つに分かれています。3.1と3.2では、オースティンとサールの言語行為論の改良を提案します。3.3では、言語行為がどのようにして成立するのかを説明しました。
まず「3.1 質問と言語行為」では、オースティンとサールの言語行為論を紹介したのち、彼らが注目していなかった、質問発話の特殊性を説明しました。
サールは、言語行為を次のように分けていました。
(a) 発話行為(utterance act)=語(形態素、文)を発話すること(これは音声行為(phonetic act)、音韻行為(phonemic act)、形態素行為(morphemic act)からなる。)
(b) 命題行為(propositional act)=指示と述定を遂行すること
(c) 発語内行為=陳述、質疑、命令、約束などを遂行すること
(d) 発語媒介行為=発語内行為という概念に関係を持つものとして、発語内行為が聞き手の行動、思考、信念などに対して及ぼす帰結(consequence)または結果(effect)という概念が存在する。
さらに発語内行為を次のように区別していました。
(1)主張型(assertives) ┣ (p)
(2)行為指示型(directives) ! (p)
(3)行為拘束型(commissives) C (p)
(4)表現型(expressives) E (p)
(5)宣言型(declarations) D (p)
発語内行為を一般的にFとし、命題行為をpとすると、F(p)という一般的な表現になります。サールは、「質問」という発語内行為を、行為指示型の「依頼」の一種(情報提供の依頼)として説明し、それを?(p)と表記しました。
ところで、サールが強調するように、同じ命題内容でも異なる発語内行為を採ることがあります。例えば、「あなたを首にします」が、記述の場合(主張型)もあれば、約束の場合(行為拘束型)もあれば、宣言型の場合もあります。しかし、サールの表記法では、すべてとなります。
? (p)、 ┣ (p)
? (p)、 C (p)
? (p)、 D (p)
同じ命題内容の返答が異なる発語内行為を採るとすれば、それは質問がことなるからではないでしょうか。つまり質問がすでに返答の発語内行為を指定しているのです。「問いは、答えの半製品である」ということは、命題内容に関してだけでなく、発語内行為に関してもそうなのです。質問が、すでに返答の発語内行為を指定しているとすると、上記の問答は、次のように表現すべきです。
?┣ (p)、 ┣ (p)
?C (p)、 C (p)
?D (p)、 D (p)
一般的に表記すると質問と返答は、次のようになります。
?F (p)、 F (p)
以上のように、質問は、特殊な発語内行為であり、上記の5つの分類とは独立したものとして分類すべきです。
サールは、後に上記の発語内行為の5つの分類を修正していますので、本書ではもう少し詳しく説明していますが、基本的なアイデアはこのようなものです。
2 言語行為の新分類
「3.2 言語行為の新分類」では、従来の言語行為に「前提承認要求」という言語行為を追加することを提案します。
まず従来の言語行為の分類(発話行為、命題行為、発語内行為、発語媒介行為という分類)では、ヘイトスピーチをうまく扱えないことを説明しました。発話行為や命題行為は、命題内容へのコミットメントを含んでいないので、ヘイトスピーチを説明できない。他方で、本文で例を挙げて説明したのですが、発語内行為や発語媒介行為ではヘイトスピーチの働きをカバーしきれません。
次に、それをうまく説明するために「前提承認要求」という行為を付け加えて、<発話行為、命題行為、前提承認要求、発語内行為、発語媒介行為>と分類することを提案しました。その際に、これらの言語行為間の差異を明確にするために、ヴェンドラーによる動詞の分類を利用しました。これは行為の分類に使えるものです。彼は、動詞を次の4つに分類しました。
①状態動詞:「嫌う」「愛する」「所有する」など状態を表す動詞。
②実現動詞:「勝つ」「始める」「発見する」などある状態を実現する瞬間的な出来事を表す動詞。
③活動動詞:「走る」「「押す」など終着点を持たない行為を表す動詞。
④向実現動詞:「(絵)を描く」「「(椅子)を作る」「(小説)を読む」などの内在的な終着点を持つ動詞。
ちなみに、①と②は進行形を取りますが、③と④は進行形をとりません。
この分類によると、発語内行為を表す「主張する」「命令する」などの遂行動詞は、実現動詞に属します(ただし、すべての実現動詞が、遂行動詞になるのではありません)。これに対して、発語媒介行為を表現する「説得する」「実行させる」「受諾させる」などは、向実現動詞になります。
では、「前提承認要求」はどうなるのでしょうか。
発話が何を前提しているかは、発話が不適切になる場合を調べることによって、明らかにすることができます。発話が不適切なものになるケースについては、オースティンの分析があります。この分析を踏まえて、発話の前提として
論理的前提
意味論的前提
語用論的前提
を挙げることができます。
「前提承認要求」は、発話が成立するためのこれらの前提(論理的前提や意味論的前提や語用論的前提)を承認するように聞き手に要求する向実現行為、である。
話し手自身は、発話においてこれらの前提を承認している。この「前提承認」は、発語内行為の前提であり、発語内行為に含まれている実現行為である。しかし、話し手が承認しているこれらの前提を聞き手が承認するように要求するのが「前提承認要求」である。
この意味で「前提承認要求」は聞き手に、発語内行為が成立していることの承認を求めることでもある。これに対して、発語媒介行為は、同じく向実現行であるが、発語内行為の成立を聞き手が承認していることを前提した上でなりたつ行為である。
結論として言えることは、発語媒介行為、前提承認要求、発語内行為は、つぎのような実践的推論を構成するということです。
私は学生に水を持ってきても欲しい。(発語媒介行為の意図)
学生は短時間で水を持ってくることができる。(前提(真理性)承認要求)
私が学生に水を持ってくるように依頼することは正当である。(前提(正当性)承認要求)
∴私は学生に「水を持ってきてください」と依頼する。(発語内行為)
3 問答の不可避性
「3.3 言語行為の不可避性」では、これらの言語行為がそもそもどうして可能なのか、どうして成立するのかを考察しました。その答えは、ある種の「不可避性」によって、成立するということです。
まず、全ての発話は、暗黙的に質問であることを説明しました。すべての発語が、暗黙的に依頼(質問)であるとすると、すべての発話は聞き手に何らかの選択を求めていることになります。発語は、聞き手の選択を可能にするだけでなく、選択を迫り、選択を不可避なものにします。
次に、この選択の不可避性が、指示を可能にすること、指示を不可避なものにすることを説明しました。ある発話が問いの答えとして発話されるとき、それに含まれる指示詞や確定記述のような表現は、対象を指示できるというだけでなく、むしろ対象を指示しないことはできないことはできません。このような対象の指示の不可避性が、指示を成立させるのです。
次に、この種の伝達の「不可避性」がグライスの言う「協調の原理」で説明できることを示しました。「協調の原理」とは次のようなものです。
「会話の中で発言をするときには、それがどの段階で行われるものであるかを踏まえ、また自分の携わっている言葉のやり取りにおいて受け入れられている目的あるいは方向性[または問い]を踏まえたうえで、当を得た発言を行うようにすべきである」(Grice 1989: 26, 訳37、[ ]内は引用者の付記)
この「協調の原理」は、第3章で「会話の含み」の説明で述べたように、破ることができるのですが、しかし破ったとしても、破ることによってある意味を伝えようとしているのだと(「協調の原理」に則って)理解されてしまいます。つまり「協調の原理」は不可避的に私たちに迫ってくるのです。このことが、伝達の不可避性を成立させ、さまざまな言語行為を不可避的に成立させます。
最後に、この「協調の原理」の不可避性の成立の前提になっているのが、問答の不可避性であることを説明しました。未開の民族の人間に出会ったとき、私たちは「協調の原理」が成り立つことを前提できないのですが、しかしそのような状況でも、それぞれの振る舞いが問いかけとそれに対する答えとなってしまうことは、想定できます。つまり、問答の不可避性は、想定できます。
こうして、言語行為は最終的には問答の不可避性によって説明出来るでしょう。
次回は、第4章の見取り図を紹介します。[編集部]
入江幸男(いりえ・ゆきお) 1953年生香川県出身。1983年大阪大学大学院文学研究科博士課程単位修得退学。現在大阪大学文学研究科名誉教授、文学博士。著書に『ドイツ観念論の実践哲学研究』(弘文堂、2001年)、『ボランティア学を学ぶ人のために』(入江・内海・水野編、世界思想社、1999年)、『コミュニケーション理論の射程』(入江・霜田編、ナカニシヤ出版、2000年)、『フィヒテ知識学の全容』(入江・長沢編、晃洋書房、2014年)。訳書に『真理』(P. ホーリッジ/入江幸男・原田淳平訳、勁草書房、2016年)。
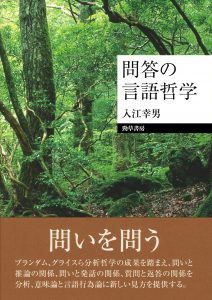 分析哲学の成果を踏まえ言語行為について問いと推論の関係、問いと発話との関係を分析、意味論と言語行為論に新しい見方を提供する。
分析哲学の成果を踏まえ言語行為について問いと推論の関係、問いと発話との関係を分析、意味論と言語行為論に新しい見方を提供する。
入江幸男 著
『問答の言語哲学』
https://www.keisoshobo.co.jp/book/b535722.html
ISBN:978-4-326-10287-7
A5判・272ページ・本体4,300円+税
本書のたちよみはこちら→【あとがきたちよみ『問答の言語哲学』】
