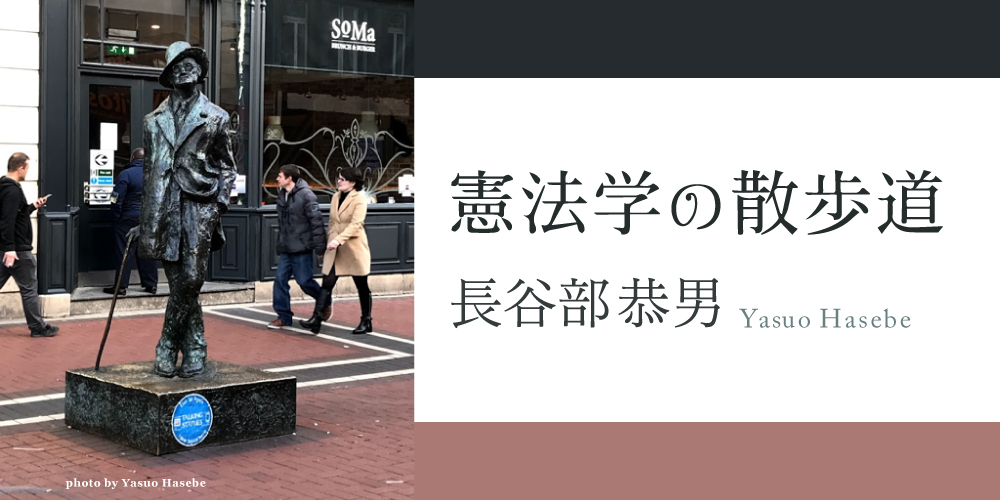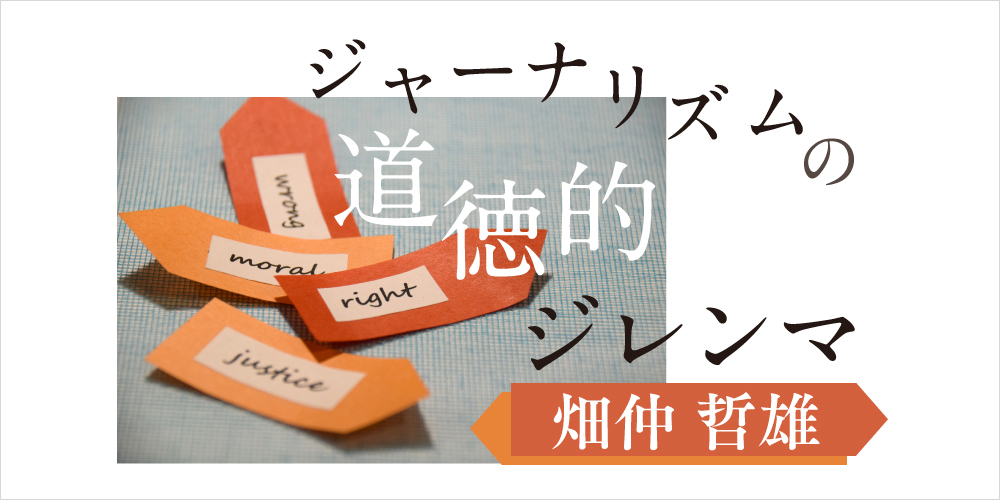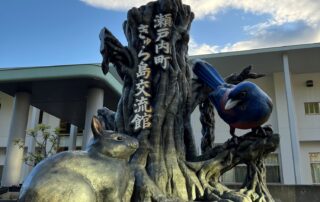コヨーテ歩き撮り#243
反射光に凝っていたことがあった。なぜか、すべてを美しくする。光源は太陽なのだが、太陽の光そのものに光が異議を申し立てる。反射光とは、いわば月の光。つまり昼間に地上に月が降りてくるようなもの。異界がやってくる。アムステルダムにて。 At one time in my life, I was obsessed with reflected light. I don’t know why. But it makes everything beautiful. It’s sunlight all right. It’s the light's protest against itself. Reflected light is akin to moonlight. So it’s as if the moon descended to earth during the day. You know what I mean? Another world arrives. In Amsterdam.