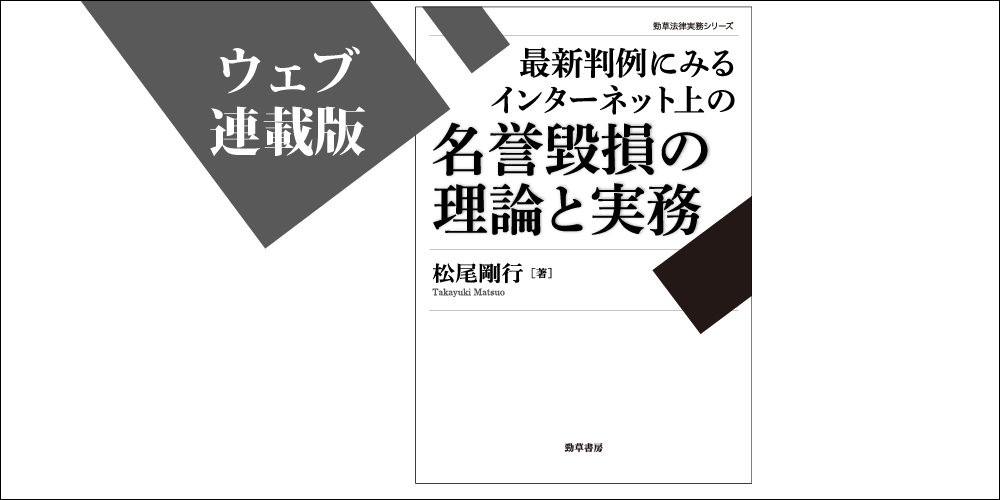2.裁判所の判断
最高裁判所は平成23年判決で、甲の取材を根拠に地方新聞社Bが主張した相当性の法理による免責を認めました。
つまり、通信社と新聞社の関係が「記事の取材、作成、配信及び掲載という一連の過程において、報道主体としての一体性を有すると評価することができる」場合においては、新聞社は通信社に取材を代行させたものとして、新聞社自身が取材を行っていなくとも、通信社の行った取材を根拠に相当性の法理による免責を主張することを認めたのです(注7)。
最高裁調査官によると、平成23年判決は平成14年判決を変更するものではなく、最判平成14年1月29日を前提に、たしかに通信社の配信という一事では免責されないとしても、一定の場合に免責の余地があると判示したものと理解できるとしています。
通信社の中には、本件の甲のように地方新聞社が共同で設立したところがあります。そして、通信社と地方新聞の間の密接な関係があり、一体とみなすことができる場合には、通信社が十分に取材すれば、地方新聞社が十分に取材したのとみなして、相当性の法理を適用して免責させることとしたのです(注8)。
3.本判決の教訓
以上は、基本的に、従来型の名誉毀損に関する議論であり、一見「インターネット上の名誉毀損」とは関係がないかのように思われます。
そこで、この法理をインターネット上の名誉毀損に拡張できるのか検討してみます。
たとえば、ある被疑者の殺人事件を新聞社がニュースとして流し、それを読んだあるインターネットユーザーがツイッター上で、その新聞社のニュースのURLと一緒に「殺人鬼の●●は極悪非道だ」などと投稿したとしましょう。もし新聞社のニュースが虚偽で、被疑者が完全な冤罪だったとすると、新聞社が名誉毀損として責任を負うリスクがあるだけではなく、そのユーザーも同じリスクがあるわけです。
そして、新聞社は自分の取材を根拠に相当性をもって免責される余地があるものの、ほとんどのユーザーは裏付け取材をしていません。そうすると相当性の法理では免責されないように思われるけれど、それでいいのかという問題です(注9)。
ここで、配信サービスの抗弁が使えないか、という議論があります。特に新聞社のサイトからFacebookやTwitterのSNSで記事のURLとコメントを投稿できる機能が準備されているならば、本判決のいう「一体性」があるとして、投稿をしたSNSユーザーは新聞社の取材を理由に免責されないかといった検討ができないでしょうか。
たしかに、調査官解説はこの判決の射程は広くはないとしているので、直接の適用は難しそうです(注10)。
ただ、最高裁が平成23年判決で地方新聞社を免責した理由は、そもそも地方新聞社自身で取材するのが期待できない状況があることを前提に、通信社が地方新聞社の代わりに取材をしたといってよいような密接な関係があった、そこで通信社が十分な取材をしていれば免責してあげようとしたものと思われます。もしこのような理解が正しければ、個別のインターネットユーザーに高度な取材を期待できない場合に、少なくとも新聞社自身が一般のインターネットユーザーによる拡散やコメントを期待してSNSによるコメント機能を設けているような状況であれば、新聞社がインターネットユーザーの代わりに取材をしたといってよいような密接な関係があったといえるのではないか、そしてそのような場合には、平成23年判決の法理を類推してインターネットユーザーを免責する余地があるかもしれません。
もっとも、これはあくまでも一つの考え方であり、今のところこれを肯定した裁判例はないことから、なおインターネットユーザーは自ら相当性を立証しなければならない可能性があることには留意が必要でしょう(注11)。
(注1)平成23年度最高裁判所判例解説民事編(上)423頁
(注2)最判平成23年4月28日民集65巻3号1499頁
(注3)Bはこの事故につき、業務上過失致死罪で起訴されたが、無罪判決を受け、これが確定している。
(注4)最判平成14年1月29日民集56巻1号185頁
(注5)「したがって、現時点においては、新聞社が通信社から配信を受けて自己の発行する新聞紙に掲載した記事が上記のような報道分野のものであり、これが他人の名誉を毀損する内容を有するものである場合には、当該掲載記事が上記のような通信社から配信された記事に基づくものであるとの一事をもってしては、記事を掲載した新聞社が当該配信記事に摘示された事実に確実な資料、根拠があるものと受け止め、同事実を真実と信じたことに無理からぬものがあるとまではいえないのであって、当該新聞社に同事実を真実と信ずるについて相当の理由があるとは認められないというべきである。」
(注6)最判平成14年3月8日判タ1091号71頁も、「掲載記事が一般的には定評があるとされる通信社から配信された記事に基づくものであるという理由によっては、記事を掲載した新聞社において配信された記事に摘示された事実を真実と信ずるについての相当の理由があると認めることはできない」とした。
(注7)「新聞社が、通信社からの配信に基づき、自己の発行する新聞に記事を掲載した場合において、少なくとも、当該通信社と当該新聞社とが、記事の取材、作成、配信及び掲載という一連の過程において、報道主体としての一体性を有すると評価することができるときは、当該新聞社は、当該通信社を取材機関として利用し、取材を代行させたものとして、当該通信社の取材を当該新聞社の取材と同視することが相当であって、当該通信社が当該配信記事に摘示された事実を真実と信ずるについて相当の理由があるのであれば、当該新聞社が当該配信記事に摘示された事実の真実性に疑いを抱くべき事実があるにもかかわらずこれを漫然と掲載したなど特段の事情のない限り、当該新聞社が自己の発行する新聞に掲載した記事に摘示された事実を真実と信ずるについても相当の理由があるというべきである。」
(注8)ただし、真実性に疑いを抱くべき事情があるにもかかわらず漫然と掲載した場合等特段の事情がある場合には免責が否定される可能性があります。
(注9)宍戸常寿「デジタル時代の事件報道に関する法的問題」東京大学法科大学院ローレビュー6号(2011年)212〜213頁参照。
(注10)「ある報道機関ないしジャーナリストが、第三者に取材を代行させ、その取材結果を何の裏付け取材をすることなく公表したからといって、当然に免責されるものではなく、免責を受け得る場合にはおのずと一定の限界がある」平成23年度最高裁判所判例解説民事編(上)434頁。
(注11)大島弁護士は「これは難しい問題ですね。まさにインターネット時代におけるネット上の表現の自由をどう構想していくべきか、ということになります。判例は「記事の取材、作成、配信及び掲載という一連の過程において、報道主体としての一体性を有すると評価することができるとき」という表現をしていることからも、報道主体とは一般的にいえない単なるインターネットユーザーが「一体性」論により免責されるとまでは、現時点では明確にはいえないでしょう。ただ「相当性の法理」と「一体性」論は併せて、表現の自由と名誉権の憲法的調整の法理の働きをしているという大前提があるわけです。ネット時代におけるこの憲法的調整を今後どう機能させていくかが問題となるでしょう。」とコメントしており、参考になる(https://keisobiblio.com/2016/04/28/matsuo10/3/)。
》》》これまでの連載一覧はこちら《《《

 2016年2月25日発売!
2016年2月25日発売!松尾剛行著『最新判例にみるインターネット上の名誉毀損の理論と実務』
時に激しく対立する「名誉毀損」と「表現の自由」。どこまでがセーフでどこからがアウトなのか、2008年以降の膨大な裁判例を収集・分類・分析したうえで、実務での判断基準、メディア媒体毎の特徴、法律上の要件、紛争類型毎の相違等を、想定事例に落とし込んで、わかりやすく解説する。
書誌情報 → http://www.keisoshobo.co.jp/book/b214996.html