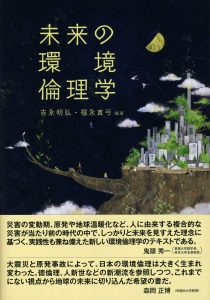 2018年4月に刊行された『未来の環境倫理学』の編著者・吉永明弘さんから、「21世紀の環境倫理学は、新しい問題と古い問題の両方に取り組まなければならない状況にある」という問題意識のもと、今後の課題に取り組むための提案をいただきました。そのキーワードとなる「開発事業における順応的管理」とはなにか? ぜひご一読、ご一考ください。[編集部]
2018年4月に刊行された『未来の環境倫理学』の編著者・吉永明弘さんから、「21世紀の環境倫理学は、新しい問題と古い問題の両方に取り組まなければならない状況にある」という問題意識のもと、今後の課題に取り組むための提案をいただきました。そのキーワードとなる「開発事業における順応的管理」とはなにか? ぜひご一読、ご一考ください。[編集部]
■『未来の環境倫理学』――3.11以降の環境倫理学を提示
2018年4月に『未来の環境倫理学』が刊行された。私は環境倫理学者の福永真弓とともに編者になり、3.11以後の環境倫理学の姿を提示すべく、リスク(福永)、原発事故(吉永)、放射性廃棄物(寺本剛)、気候工学(桑田学)といった具体的な問題に関する論考や、環境正義(福永)、徳倫理学(熊坂元大)、未来倫理(山本剛史)、人新世とポストヒューマニズム(福永)といった新しいトピックについての論考を一冊にまとめた。執筆者は比較的若い研究者ばかりである。
従来の環境倫理学のテキストは、1970年代~1980年代のアメリカの議論や、1990年代の日本の議論を中心に構成されることが多かった。これまではそれらの枠組みによって環境問題に応答しようとしてきたが、21世紀に我々の環境をめぐる状況が新たなフェイズに入り、そのような状況をふまえた環境倫理学が必要ではないかという問題意識が、『未来の環境倫理学』の基調をなしている。
具体的に言うと、3.11の東日本大震災と福島第一原発事故の後では、目に見えない「リスク」をどう考えるかが大きな関心事になっている。また気候変動を工学的に解決しようとする場合には、さまざまな「不確実性」をどうとらえるかが大問題となる。これらに正面から取り組む議論が必要だというのが著者たちの共通認識である。従来きちんと紹介されてこなかった環境正義や未来倫理について理解でき、最先端の情報(徳倫理学、気候工学、人新世、ポストヒューマニズム)をコンパクトに把握できるなど、環境倫理学のテキストとしては他に類のない、充実した内容になったと自負している。
■公害・地域開発問題は終わっていない
ただし、環境問題が新たなフェイズに入ったということは、従来型の環境問題がなくなったということを意味するものではない。従来型の環境問題も根強く残っており、従来の環境倫理学の議論が重要性をもつ領域はまだまだある。21世紀の環境倫理学は、新しい問題と古い問題の両方に取り組まなければならない状況にある。
ここで従来型の環境問題の存在を強調するのは、1990年代以降、「公害や開発の時代から地球環境問題の時代へ」という論調が現れ、それに対して宮本憲一や飯島伸子が苦言を呈したことが想起されるからだ。公害問題を告発してきた宮本は、2000年代にアスベストによる健康被害を調査し、「公害は終わっていない」ということをあらためて訴えている(『維持可能な社会に向かって』岩波書店などを参照)。
また、環境社会学者の飯島は、地球環境問題は、地域社会で相変わらず発生している公害問題や開発被害を見えにくくすることに効果を持ったと述べている。特に、「地球環境問題という大問題の前で地域環境問題などは取るに足らぬものと言わんばかり」の対応が見られることを批判している(『講座社会学12 環境』東京大学出版会、24頁)。
だからといって彼らは地球環境問題がまやかしだとは言っていない。結局のところ、地球環境問題やマクロな問題も地域の公害や開発も並行して存在しているというのが実情だろう。公害や開発を告発した本は、今でも読むに値する。明治末期に書かれた荒畑寒村『谷中村滅亡史』(岩波文庫)ですら古びていないのである。
ここで、地域の環境問題だけに目を向けて、よりマクロな問題を無視してしまうと、逆の落とし穴に落ちてしまうという批判があるだろう。懸命にまちづくりや自然再生の取り組みを行っても、たとえば戦争、気候変動による災害、地域の外で起こった原発事故などによってそれらの努力が水泡に帰すおそれがある。確かにその通りだが、このことは地域環境問題に取り組む人もおそらく心得ている(よりマクロな問題にも関心が開かれている)と思われる。ここで批判されているのは、よりマクロな問題に比べて地域の問題なんて大した問題ではないとする人の態度である。よりマクロな問題と地域の問題は二者択一ではなく、どちらも取り組むべき課題である。
■開発による自然破壊は今も存在する
時代の変化を強調する議論は、ある種の問題を過去のものとする効果をもってしまう。例えば「自然保護」に関してもトレンドがある。日本の自然保護は、尾瀬に代表される良好な自然景観の保護から始まった。しかし現在の主流は科学的生態学の知見に基づく「生態系サービス」の保全や、生物多様性条約に基づく「生物多様性の保全」という枠組みである。
「生物多様性国家戦略2012-2020」のなかでは、「生物多様性の四つの危機」がうたわれている。第一の危機は人間の介入による危機、いわゆる従来型の開発による自然破壊である。第二の危機は人間の介入を放棄したことによる危機、具体的には里山の荒廃などを指す。第三の危機は外来種や化学物質など人間が持ち込んだものによる危機、第四の危機は気候変動による危機である。ここには、自然を人の手(開発)から守るという従来型の問題意識と、自然の適切な管理をする(手入れ、外来種駆除)という比較的新しい問題意識が両方含まれている。したがってこの両方が重視されるべきなのだが、現在の生物多様性に関する政策や実践では、自然の適切な管理のほうに力点がおかれているように思われる。
里山保全や外来種駆除の重要性に異を唱えるつもりはないが、他方で、開発問題が現在でも変わらぬ相貌をもって存在することを見逃してはならない。メガソーラー設置のための森林伐採や、都市郊外や都市内に存在する緑地の伐採、それらの事業の進め方や住民の反対運動のようすを見ると、これまでの開発をめぐる問題状況と何ら変わらないように思える。また、今となっては必要性が疑わしいが、過去の計画を引きずって行われる都市計画道路の建設や、人口動態などを無視して行われる郊外の住宅開発など、時代錯誤ともいうべき地域開発を目にすることも多い。
■今でも根強いDAD型の手法と、事業評価の不在
このような自然破壊を引き起こす事業を横目に、近年盛んに行われているのが「自然再生事業」である。自然再生事業が流行している背景には、保全生態学の発展と自然保護観の変化がある。自然に対する人間の介入を差し控えるのではなく、人間が積極的に望ましい自然を作り出すわけだから、自然保護の考え方がだいぶ変わってきたことが分かるだろう。しかし、自然再生は大規模な事業になると、開発行為に似た様相を呈してくる。そこからは従来型の開発事業と同様の論点を取り出すことができる。
韓国ソウル市の清渓川(チョンゲチョン)の復元事業は、自然再生事業の成功例と目されている(2003年7月工事開始、2005年9月に完成)。それは川を暗渠化して建設された高架の高速道路を撤去し、都市に川を取り戻すという事業である。工事を始めた時期には、多くの市民がこの事業に賛同していたが、高速道路の近くで商売をしていた露店商や、近隣の商店街の商人たちからは根強い反対意見があった。
黄祺淵(ファン・ギヨン)他『清渓川復元』(日刊建設工業新聞社)は、この事業を「葛藤管理」に焦点を合わせて論じている。「葛藤管理」とは、「公共事業を中心とする公的施策の実施を巡ってさまざまな主体間で生じる社会的対立を、事前に予防したり、発生後に的確に対処して解決に導く一連の過程を総称する用語」とされる。著者たちによれば、これまでの韓国の事業はDAD(Decide-Announce-Defend)型の手法(葛藤管理方式)で行われていた。すなわち、住民の参加や同意なしに事業者が一方的に決定し(Decide)、それを住民に発表し(Announce)、あとはひたすら防御にまわる(Defend)という手法である。それに対して、清渓川復元事業は3000回以上に及ぶ丁寧な話し合いを行って商人たちの同意をとりつけた。この点を著者たちは大きく評価している(この評価はあくまで事業者寄りの立場からのものであり、留保が必要である。事業そのものについても、完成後の復元された姿には市民からの批判的な意見も見られる)。
ひるがえって日本の開発事業のやり方を見ると、ここで批判されているDAD型の手法がまだまだ主流であることに気づく。小平市の都市計画道路建設に関する本(『来るべき民主主義』幻冬舎新書)のなかで國分功一郎が憤っているのは、開発事業の中身とともに、形ばかりの「説明会」に代表されるDAD型の事業の進め方に対してなのである。
また、日本では適切な事業評価が行われ、事業計画に反映されているのかどうかがきわめて疑わしい。近年、環境への悪影響が懸念されている事業として、リニア新幹線の建設事業がある。少し前の本だが、橋山禮次郎『リニア新幹線 巨大プロジェクトの「真実」』(集英社新書)は、きわめて明快な事業評価を行っている。あらゆる開発事業を批判するのではなく、過去の事業を丁寧に評価し、成功した事業と失敗した事業の一覧表を載せている。著者の分析ではリニア新幹線は失敗することになるが、普通にこれを読んだら著者の分析と事業評価に反論することは難しいだろう。リニア新幹線建設事業は、こうした議論を黙殺して、粛々と進められているように思われる。
■「問題の所在が見えているのに改善されてこなかった」という問題
DAD型の手法の問題点や、事業評価のフィードバックの不在については、すでにさまざまな論者によって、表現は違えど繰り返し指摘されている。行政の無謬性は神話である、データの改ざんや利益相反による意思決定のゆがみがある、いったん路線が決まったことは妥当性がなくてもやり続けるというのはおかしい、といったことは昔から指摘されている。情報公開、住民参加、審議会の実質化、経済性や必要性の考慮、第三者機関による評価といったものは、昔から繰り返し要求されている。これらの重要性が理論的に確立され、制度的にもある程度担保されているにもかかわらず、DAD型の手法が今でもまかり通っており、チェックやフィードバックがなおざりにされていることが、日本に従来型の公害や開発の問題が存続している大きな理由といえる。
以上、さまざまな話題を並べてきたが、本稿の主張は、21世紀に入り、とりわけ3.11以降、我々の生きていく環境は新しいフェイズに突入し、環境倫理学においてもこれまでにない議論が求められていると同時に、従来型の環境問題も相変わらず存在するので、従来からの議論を過去のものとして捨て去ってはならない、ということである。
新しいフェイズにおいては、環境問題が複雑化し、目に見えない、見えづらい、不確実な問題(リスクの問題、気候変動など)が増えていることが強調されるだろう。それは間違いなくそうなのだが、一方で、シンプルで誰にでもはっきりと見える問題も相変わらず存在する(公害、地域開発など)。これからの環境倫理学者の役割の一つとして、「見えづらい問題を可視化すること」があるだろう。それに加えて、「問題の所在がシンプルではっきりと見えているのに適切な対応がとられず、改善されてこなかった」という課題にまっすぐに取り組む時期が来ていると思われる。
■事業を中止した場合に「ほめられる」仕組みをつくるべきだ
そこで最後に、倫理学の立場から具体的な提案をしてみたい。それは、開発事業において順応的管理(adaptive management)の考えを徹底すべきだということ、そのために事業を中止した人を「ほめる」仕組みをつくるべきだということである。
ここで倫理学の立場からというのは、ほめる(賞賛)・けなす(非難)というのが倫理的サンクションだからである(それに対して刑罰は法的サンクション)。倫理的サンクションは、SNS隆盛の時代において巨大な影響力をもつようになったといえよう。
次に、順応的管理とは、「対象に不確実性を認めたうえで、政策の実行を順応的な方法で、また多様な利害関係者の参加のもとに実施しようとする新しい公的システム管理の方法」である。もともとは保全生態学の用語だが、開発事業全般に適用できる考え方だといえる。「順応的管理においては、管理や事業を一種の実験とみなす。計画は仮説、事業は実験ととらえられ、監視の結果によって仮説の検証が試みられる。その結果におうじて、新たな計画=仮説をたて、よりよい働きかけを行うべく、事業の「改善」がめざされる」(鷲谷いづみ『生態系を蘇らせる』より)。つまり事業はすべて実験であり、社会的状況が変わったらそれに応じて事業も途中で柔軟に変えていくという考え方である。この考え方を徹底すれば、社会的状況が変わり時代に合わなくなった事業は中止を視野に入れるべきだということになるだろう。
順応的管理に基づいて事業を中止した人を「ほめる」というのはあながちおかしな話ではない。例えば登山隊のリーダーが、途中で天候が悪化したときに下山(登山の中断)を決意し、無事に山から下りた場合には、そのリーダーは非難されるのではなく賞賛されることだろう。状況が変わり、事業(登山)が成功しないことが分かった場合には、その事業(登山)を途中でやめることは賞賛に値するのである。
では、開発事業を中止した人がほめられる例はあるのかというと、例えば自治体の長が「開発中止」を宣言したときに環境団体から賞賛されることはよくある。逆に、開発を阻止し、緑地を保全した団体が、行政からほめられた例としては、「鎌倉の自然を守る連合会」の例がある。『鎌倉広町の森はかくて守られた』(港の人)は、連合会の25年にわたる緑地保全運動の記録である。ここには、2003年に全面保全が実現した後で、連合会は鎌倉市長から感謝され、神奈川県知事からたたえられ、国土交通大臣から表彰を受けたことが記されている。
それに対して、役所の人事評価は、事業を滞りなく進めた人が賞賛され、事業を中止した場合にはマイナスの評価になりがちである。特に外部からの声に押されて中止した場合はなおさらである。そうなると、事業を中止するモチベーションとメリットが役所にはないということになる。したがって、それを改善するには、例えば、順応的管理の考え方に基づいて事業を中止した部署を、外部機関がほめたたえること(例えば表彰するなど)が必要だろう。そのことによって、「どんな場合であれ事業の中止は失敗である」というメンタリティを打破し、「場合によっては事業の中止は英断である」という認識を根付かせることができるのはないか。間違ったことを批判するのも大切だが、正しいことを評価し、後押しすることも同じくらい大切なことだろう。
(*WEB雑誌「シノドス」に過去に寄稿した拙論も参照いただきたい。メガソーラーについては、「自然エネルギー開発に冷水を浴びせる――ウィナー『鯨と原子炉』の示唆と予言」https://synodos.jp/society/15162。都市内の緑地については、「都市に「緑地」はなぜ必要か――「市街化調整区域」を真面目に考える」https://synodos.jp/society/20444。順応的管理については、「都市計画道路に「見直し」が求められる理由――財政支出・住民投票・順応的管理」https://synodos.jp/society/17599。郊外の住宅地開発については、「どんな住まいがエコなのか――「都市の環境倫理」再論」https://synodos.jp/society/18874)。
著者:吉永明弘(よしなが・あきひろ)
2006年千葉大学大学院社会文化科学研究科修了(博士)。現在、江戸川大学社会学部准教授。著書に、『都市の環境倫理』(勁草書房、2014年)、『ブックガイド 環境倫理』(勁草書房、2017年)ほか。
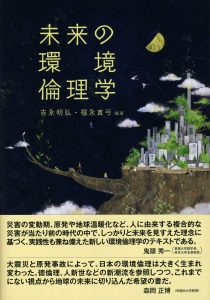 2018年4月発売!
2018年4月発売!吉永明弘・福永真弓 編著
『未来の環境倫理学』
ポスト・ヒューマニティーズの哲学思想、公共性の環境倫理学、3.11以降の原発と復興に関する倫理学等、90年代以降の環境倫理学・環境哲学の潮流を体系的に捉え直すと共に、実践を支える思想として、未来をつくっていく学問としての環境倫理学を提示する。人が「生きる場」としての「環境」、リアルな課題と対峙するテキスト。
あとがきたちよみ→「序章 本書が取り組む三つの課題」と「第I部 災後の環境倫理学【イントロダクション】」のページを公開しました。
書誌情報 → http://www.keisoshobo.co.jp/book/b351922.html
