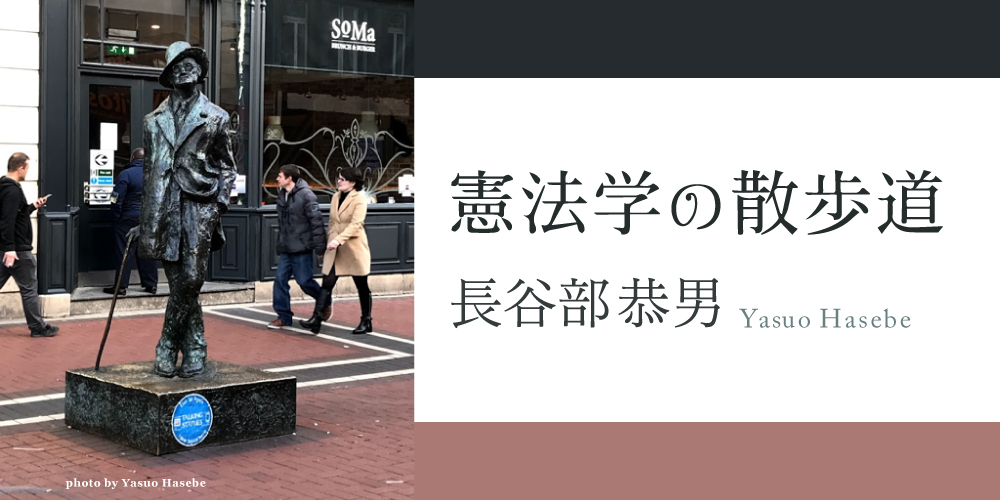アリストテレスの『政治学』は、その第2巻で、プラトンが『国家篇』で展開した理想の国家像を批判している。アリストテレスによれば、プラトンが描いているのは、全市民が子どもも妻も資産もすべてを共有する体制である。
実際に、プラトンが『国家篇』第5巻で描いているのは、「守護者」と呼ばれる国家の支配者層に限っての話であり、しかも、それは普通、「共有」という概念から想定されるような体制ではない。支配者層のメンバーにとっては、どんな物も「自分の物」ではない。どの女性が「自分の妻」ということもなく、どの子どもが「自分の子ども」ということもない。すべてが共有されているというよりは、誰も何も所有していない状態である。
守護者たちはそのため、自分たちの衣服や食べ物さえ、被支配層(一般民衆)から恵んでもらう物でまかなう必要がある。被支配層である農民や職人には、それぞれの財産があるはずである。自分だけの農地や種苗、仕事道具や原材料がなければ、農耕作も手工業も成り立たない。
プラトン自身が実際に描いている国家像が何かはともあれ、アリストテレスが批判しているのは、全市民が子どもも妻も財産も共有する体制であって、そんな体制を維持することは不可能だとアリストテレスは言う。
その1つの理由として彼が挙げるのは、人々は自分の物については配慮するが、公共の物は顧みようとしないということである。他人も気遣っていると思うと、人は自分で配慮しようとは思わなくなる。1つの家で奉公人の数が多くなればなるほど、1人1人の仕事が雑になるようなものだと、アリストテレスは言う。同様に、1人1人の父親にそれぞれ千人の息子がいるような状態では、すべての父親はおしなべて、すべての息子を軽んじるようになる(『政治学』第2巻第3章)。彼によれば、現在そうである通り、それぞれが自分の家庭を持ち、自分の財産を保有する制度の下でこそ、正しい国制は実現され得る。
時代は下ってヨーロッパは中世を迎える。『グラティアヌス教令集』*1は、「自然法によれば、あらゆる物はあらゆる者によって共有されていた」とし、「ある物が誰かの物と呼ばれ、他の物が他の者の物と呼ばれるようになった起源には、悪徳(iniquity)がある」とする*2。アダムとイヴが犯した罪のために、人の本性は歪み、全体の利益によりは、自分や身近な者の利益に関心が集中するようになった*3。アリストテレスが描く人の本性は、堕罪後の人の本性である。
旧約聖書に収められた『創世記』は、その冒頭で、神による天地創造の物語を描いている*4。地と海と、日と月と星と、鳥と獣と魚を創造した神は、最後に次のように言う。
われらの像に、われらの姿に似せて、人を造ろう。そして彼らに海の魚、空の鳥、家畜、地のすべてのもの、地上を這うすべてを支配させよう。
男と女を創造した神は、彼らに言う。
生めよ、増えよ。地に満ちてこれを従わせよ。神の魚、空の鳥、地を這うすべての生き物を支配せよ。
つづきは、単行本『神と自然と憲法と』でごらんください。
 憲法学の本道を外れ、気の向くまま杣道へ。そして周縁からこそ見える憲法学の領域という根本問題へ。新しい知的景色へ誘う挑発の書。
憲法学の本道を外れ、気の向くまま杣道へ。そして周縁からこそ見える憲法学の領域という根本問題へ。新しい知的景色へ誘う挑発の書。
2021年11月15日発売
長谷部恭男 著 『神と自然と憲法と』
四六判上製・288頁 本体価格3000円(税込3300円)
ISBN:978-4-326-45126-5 →[書誌情報]
【内容紹介】 勁草書房編集部ウェブサイトでの連載エッセイ「憲法学の散歩道」20回分に書下ろし2篇を加えたもの。思考の根を深く広く伸ばすために、憲法学の思想的淵源を遡るだけでなく、その根本にある「神あるいは人民」は実在するのか、それとも説明の道具として措定されているだけなのかといった憲法学の領域に関わる本質的な問いへ誘う。
【目次】
第Ⅰ部 現実感覚から「どちらでもよいこと」へ
1 現実感覚
2 戦わない立憲主義
3 通信の秘密
4 ルソー『社会契約論』における伝統的諸要素について
5 宗教上の教義に関する紛争と占有の訴え
6 二重効果理論の末裔
7 自然法と呼ばれるものについて
8 「どちらでもよいこと」に関するトマジウスの闘争
第Ⅱ部 退去する神
9 神の存在の証明と措定
10 スピノザから逃れて――ライプニッツから何を学ぶか
11 スピノザと信仰――なぜ信教の自由を保障するのか
12 レオ・シュトラウスの歴史主義批判
13 アレクサンドル・コジェーヴ――承認を目指す闘争の終着点
14 シュトラウスの見たハイデガー
15 plenitudo potestatis について
16 消極的共有と私的所有の間
第Ⅲ部 多元的世界を生きる
17 『ペスト』について
18 若きジョン・メイナード・ケインズの闘争
19 ジェレミー・ベンサムの「高利」擁護論
20 共和国の諸法律により承認された基本原理
21 価値多元論の行方
22 『法の概念』が生まれるまで
あとがき
索引
連載はこちら》》》憲法学の散歩道