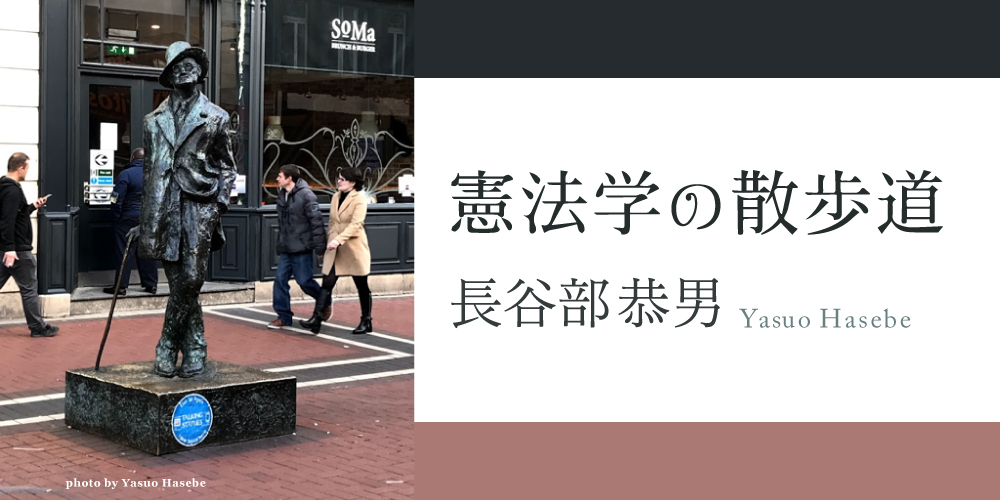「憲法学の散歩道」単行本化第2弾! 書き下ろし2編を加えて『歴史と理性と憲法と――憲法学の散歩道2』、2023年5月1日発売です。みなさま、どうぞお手にとってください。[編集部]
※本書の「あとがき」をこちらでお読みいただけます。⇒『歴史と理性と憲法と』あとがき
ジョン・ロックは1632年8月29日、イングランド南西部のサマセットに生まれた。父親は治安判事の書記や弁護士として働いた法律家で、1642年に議会とチャールズ1世の間で戦闘が開始されると、議会側の軍に参加した。ロックは父親が仕えた治安判事の推挽でロンドンのウェストミンスター校に入学し、さらにオクスフォードのクライスト・チャーチ・コレッジに進学した。1684年に除名されるまで、彼はクライスト・チャーチに籍を置くことになる。
ロックが修めた学問分野の1つは医学である。彼は1666年に財務卿のアンソニー・アシュレイ・クーパー──1672年より初代シャフツベリ伯──と知り合い、1668年には彼の企画でシャフツベリ伯の肝臓の手術が行われた。手術は成功し、伯の厚い信任を得たロックは伯の庇護の下で、医者、秘書、相談役、子女の教育掛など、さまざまな役割を果たす。
シャフツベリ伯の邸宅で生活したロックは、ロンドンの汚染された空気のために肺を病んだ。転地療養のため、彼は1675年から79年までフランスに滞在する。彼が『統治二論』の大部分を執筆したのは、帰国した79年から83年までのことと考えられている*1。
シャフツベリ伯と国王チャールズ2世との関係は、安定したものではなかった。伯は73年には大法官の職を解かれ、79年4月には枢密院議長に任命されるが、カトリックである王弟ジェームズから王位継承権を剥奪する企てを諦めようとしなかったため、同年10月に罷免された。ジェームズが継承権を失えば、王位は彼の娘でプロテスタントであるメアリー──名誉革命後に、夫であるウィリアム3世と共同王位に就くメアリー──に受け継がれる。
チャールズはジェームズの王権に制限を加えることと引き換えに王位継承権剥奪法案を取り下げるよう議会に求めたが、議会は承服しなかった。チャールズは1681年3月に議会を解散し、その後、議会を召集することはなかった。カトリック諸国の盟主であるフランスのルイ14世からの財政支援を得て、チャールズは議会抜きの王権行使による執政を開始した。
ロックは『統治二論』で、議会を召集し解散するのは執行権者であることを認める。しかし、その権限はあくまで、公共善を実現するため執行権者に信託されたものである*2。
立法部が集合し議決することが必要になったときに、政治的共同体の実力を握っている執行権力が、その力を利用してそれを妨げたらどうなるのだろうかと問われるかもしれない。それにたいして、私は、権威もなく、また、自分に寄せられている信託に背いて人民に実力を用いることは人民と戦争状態に入ることであり、その場合には、人民は立法部が彼らの権力を行使しうる元の地位に戻す権利をもつといいたい。……社会にとって必要なこと、あるいは国民の安全と保全とが賭けられていることから何らかの力の妨害によって遠ざけられた場合には、彼らはそれを実力によって排除する権利をもつからである*3。
必要があるにもかかわらず議会の召集を執行権が拒んだとき、人民は叛乱を起こすことができる。議会を通じた抵抗の途をふさがれたシャフツベリ伯は、実力行使に訴えることを企てる。1681年7月、彼は謀叛の嫌疑で逮捕され、ロンドン塔に送られた。11月末、大陪審は彼を不起訴とする。その後、陪審員選任への影響力をも削がれた伯は、82年11月オランダに亡命し、翌年1月死去した。
ロックがオランダに渡ったのは83年9月のことである。何がその直接のきっかけであったかは、明らかになっていない*4。彼がジェームズの王位排斥運動を主導したシャフツベリ伯の庇護下にあったことは、周知の事実である。それに加えて、政治権力の根拠が人民の同意にあり、政府が信託に背いて権限を行使したとき、叛乱が正当化されると主張する原稿をひそかに作成していたことが、要因の1つであったことが推測される。84年11月、チャールズの指示を受けて、クライスト・チャーチ・コレッジはロックのスチューデントシップ*5を剥奪した。
つづきは、単行本『歴史と理性と憲法と』でごらんください。
 憲法学の本道を外れ、気の向くまま杣道へ。山を熟知したきこり同様、憲法学者だからこそ発見できる憲法学の新しい景色へ。
憲法学の本道を外れ、気の向くまま杣道へ。山を熟知したきこり同様、憲法学者だからこそ発見できる憲法学の新しい景色へ。
2023年5月1日発売
長谷部恭男 著 『歴史と理性と憲法と』
四六判上製・232頁 本体価格3000円(税込3300円)
ISBN:978-4-326-45128-9 →[書誌情報]
【内容紹介】 勁草書房編集部webサイトでの好評連載エッセイ「憲法学の散歩道」の書籍化第2弾。書下ろし2篇も収録。強烈な世界像、人間像を喚起するボシュエ、ロック、ヘーゲル、ヒューム、トクヴィル、ニーチェ、ヴェイユ、ネイミアらを取り上げ、その思想の深淵をたどり、射程を測定する。さまざまな論者の思想を入り口に憲法学の奥深さへと誘う特異な書。
【目次】
1 道徳対倫理――カントを読むヘーゲル
2 未来に立ち向かう――フランク・ラムジーの哲学
3 思想の力――ルイス・ネイミア
4 道徳と自己利益の間
5 「見える手」から「見えざる手」へ――フランシス・ベーコンからアダム・スミスまで
6 『アメリカのデモクラシー』――立法者への呼びかけ
7 ボシュエからジャコバン独裁へ――統一への希求
8 法律を廃止する法律の廃止
9 憲法学は科学か
10 科学的合理性のパラドックス
11 高校時代のシモーヌ・ヴェイユ
12 道徳理論の使命――ジョン・ロックの場合
13 理性の役割分担――ヒュームの場合
14 ヘーゲルからニーチェへ――レオ・シュトラウスの講義
あとがき
索引
「憲法学の散歩道」連載第20回までの書籍化第1弾はこちら⇒『神と自然と憲法と』
連載はこちら》》》憲法学の散歩道