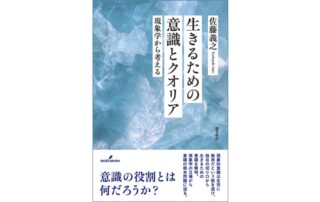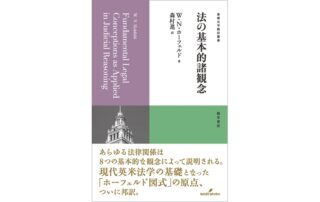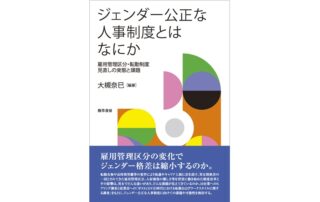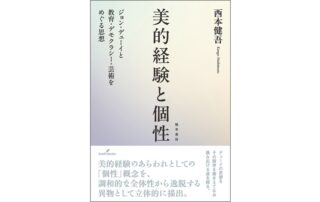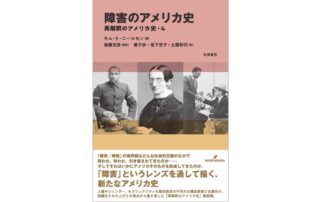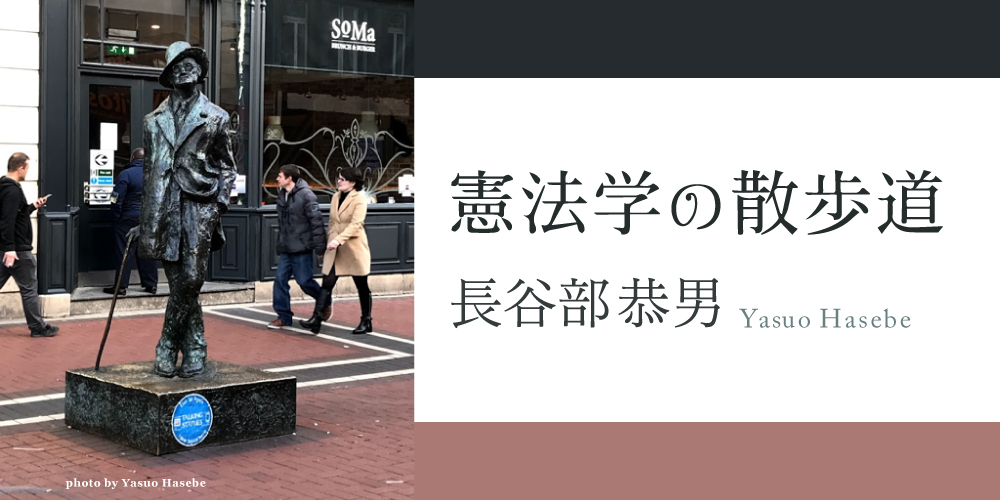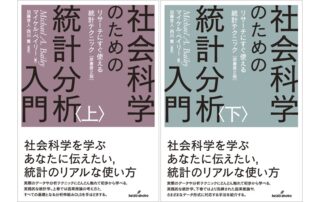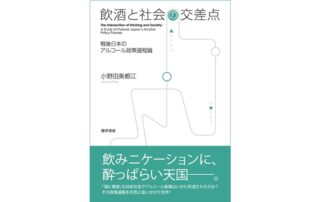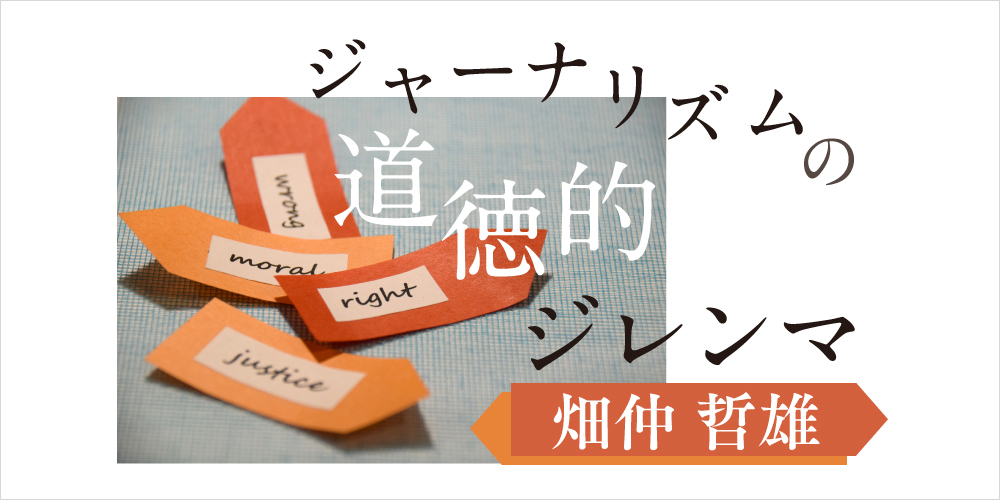あとがきたちよみ
『生きるための意識とクオリア――現象学から考える』
「はじめに」を公開しました。
あとがきたちよみ
『法の基本的諸観念』
「ホーフェルド法律関係論の現在」(吉良貴之)を公開しました。
コヨーテ歩き撮り#243
反射光に凝っていたことがあった。なぜか、すべてを美しくする。光源は太陽なのだが、太陽の光そのものに光が異議を申し立てる。反射光とは、いわば月の光。つまり昼間に地上に月が降りてくるようなもの。異界がやってくる。アムステルダムにて。 At one time in my life, I was obsessed with reflected light. I don’t know why. But it makes everything beautiful. It’s sunlight all right. It’s the light's protest against itself. Reflected light is akin to moonlight. So it’s as if the moon descended to earth during the day. You know what I mean? Another world arrives. In Amsterdam.
あとがきたちよみ
『ジェンダー公正な人事制度とはなにか――雇用管理区分・転勤制度見直しの実態と課題』
「はじめに」を公開しました。
あとがきたちよみ
『美的経験と個性――ジョン・デューイと教育・デモクラシー・芸術をめぐる思想』
「はしがき」を公開しました。
あとがきたちよみ
『障害のアメリカ史――再解釈のアメリカ史・4』
「序章」を公開しました。
憲法学の散歩道
第46回 不思議の国、オーストリア-ハンガリー帝国の形成と解体
ハンス・ケルゼンが中心となって形成された純粋法学は、根本規範を頂点とする法秩序として国家を把握する。国家と法秩序とは同一であり、法秩序と別個に国家が存在するとの観念は、擬人化にもとづくフィクションである。国家の機関として行動する諸個人の行為の効果を国家に帰責するための手掛かりとなる規範の体系としてのみ、国家は存在する。……
あとがきたちよみ
『社会科学のための統計分析入門――リサーチにすぐ使える統計テクニック[原書第2版](上・下)』
「序文」と「訳者あとがき」を公開しました。
あとがきたちよみ
『飲酒と社会の交差点――戦後日本のアルコール政策過程論』
「はじめに」「酒の入手困難期から酔っ払い天国の日々へ(抜粋)」を公開しました。
ジャーナリズムの道徳的ジレンマ
〈第27回・番外編〉増補改訂版刊行記念ミニ講義
「増補改訂版」刊行を記念して、著者の畑仲哲雄さんに本書ケース11「取材謝礼を要求されたら」にもとづいたミニ講義をお願いしました。みなさん、ぜひご覧ください。[編集部]
あとがきたちよみ
『増補改訂版 ジャーナリズムの道徳的ジレンマ』
「はじめに」「CASE:09オフレコ取材で重大な事実が発覚したら」「あとがき」を公開しました。
コヨーテ歩き撮り#242
奄美大島北部の美しい海岸にも漂着したプラスチックごみは散乱している。散乱どころか、君臨している。発泡スチロールにびっしりと付着しているのはエボシガイ。貝と呼ばれてはいても、むしろカメノテなどに近い甲殻類の航海者だ。しかしプラごみは、どうにかしなくてはならないね。たとえば毎週日曜日の午前8時から9時までの1時間、ビーチ利用者全員参加でゴミ拾いをやったらどうだろう。焼石に水と思われるかもしれないが、やる価値はあるだろう。島全体としてそんな試みを果たせるところがあるとしたら、それは奄美大島。 Plastic waste washed ashore litters the pristine coastlines in northern Amami Oshima. Sadly, it reigns. Densely attached to the Styrofoam are helmet shells. Though called shells, they are crustacean navigators closer to percebes. But we must do something about this plastic waste. For example, what if every Sunday from 8 to 9 a.m., all beachgoers spent an hour picking up trash? Participation mandatory. It might seem like a drop in the ocean, but it's worth doing. If any island could pull off such an initiative, it would be Amami Ōshima.