「汝自身を知れ」
ルネサンスの解剖学は、高度な図像表現や解剖劇場からさらに広がりを見せた。一つの側面は、同時期の大航海時代と共鳴した征服と名付けの文化である。解剖学が発展した時代はいわゆる大航海時代であり、南北アメリカを中心として、ヨーロッパに知られていない世界を発見して征服し、その地域に命名する姿勢が時代にみなぎっていた。それになぞらえて、解剖学も人体内部の世界を発見し征服し所有するという意味合いを担っていた。新たに発見された人体の部分には発見者の名前が付けられている。ローマで活躍した解剖学者バルトロメオ・エウスタキ(Bartolomeo Eustachi, d.1574)は、耳管のある部分の名称である「エウスタキオ管」にその名を残し、ガブリエレ・ファロッピア(Gabriele Fallopia, 1523-62)が発見した卵管は現在でも「ファロピウス管」と呼ばれている。ちなみに、ファロッピアはクリトリスを詳細に記述し、膣にそれまでとは違う言葉である vagina という名称を与えていることは、解剖学の発見と新世界の征服が、男性による女性の征服と響き合っていたことも示唆している。
その一方で、解剖学は、隠された内部を探求することのメタファーとして流行語になり、タイトルに『○○の解剖』を銘打った書物が数多く出版された。内部の探求の中でも、特に解剖学と結びついて使われたのは、自己の内面を探ることであった。「内部・内面の探求」という主題を通じて、解剖学はルネサンス文化の中心的な主題と融合しただけでなく、近代世界にとって中心的な問題である「自己」の主題と深く結びついた。
ルネサンスが近代社会に残した最大の遺産は、「自己」という問題だろう。かつてのように、家族や団体や集団などの集団的なアイデンティティのベールに包まれてまどろんでいた「個人」が、イタリア・ルネサンスとともに、そのベールの霧が晴れるようにして「個人」が発見され、それぞれの個人は「自己」と直面するようになったと考えるにせよ、「自己」をより構成主義的に捉えて、権威と他者とのせめぎあいを通じて作り上げられるような可塑的な「自己」という実体がルネサンス期に現れたと考えるにせよ、近代の入り口において「自己」がそれ以前よりも大きな問題として意識されたことは間違いない。この「自己」とは何か、外面と対比して定義される内面とは何かを問うことが、ルネサンス期の知識人たちの大きな関心となった。
身体の内部をあらわにする解剖学は、新たに時代の中心となった「自己を明らかにする」行為のメタファーとして捉えられた。ルネサンスの解剖学が、医学とその教育の改革という直接の役割をはるかに越えた広がりを同時代の社会と文化の中で獲得したのは、「自己を知る」という同時代の主題によるところが大きい。そして、この解剖学と広い文化を有機的に連結した主題を一言で表現したのがライデンの解剖劇場の骸骨によって掲げられている「汝自身を知れ」(Nosce te ipsum)という言葉であった。この言葉が解剖学を広い文化の中で位置づけるのに中心的だったことを示唆するのが、1615年にイギリスで出版された解剖学書、『小宇宙誌』(Microcosmographia)において、解剖学者でありジェームズ一世の侍医であったヘルカイア・クルック(Helkiah Crooke, 1576-1648)が書いた次の言葉である。
自分自身をよく知るものは、全てのことを知るのである。自分自身を知れば、まず神を知ることになるであろう。なぜなら、人間は神の姿に似せて創られており、神学者たちには「神の王国の神殿」と言われているからである。第2に、天使を知ることになるであろう。なぜなら、人間は天使と同じように知性が備わっているからである。そして、動物を知ることになるであろう。なぜなら、人間には、動物と同じ機能や感覚や欲求が備わっているからである。
このテキストが語るように、解剖学は「自己を知る」ことを可能にし、それを通じて万物を知ることへと至る知的な窓なのである。
解剖図譜の一部は「汝自身を知れ」という主題をあらわしている。解剖図譜の中でもっとも奇異なものは、解剖された死体がまるで生きているかのように、自ら皮を剥ぎ臓器をさらしているものである(図9)。これらの奇妙な図版は、たんに図版製作者の奇想ということにとどまらず、いくつかの機能を果たしている。その一つは、上でも触れたが、死体が解剖に共同して参加しているというフィクションを示すことで、解剖用の死体を調達する生々しい現場から距離をおくことであろう。また、解剖の対象となる死体に、自らの内部を「告白する」かのような身振りをとらせたのは、告白の儀式を通じて共謀的に知識がもたらされるという当時の知=権力の形式とも関係があるのだろう。そして、解剖学の文化にとってもっとも重要なことは、自らの身体の内部をあらわにする死体という主題が、キリストの受難のイメージと重ねられたことである。イエスは最後の晩餐でパンを取り、「これは私の体である」と言ってそれを裂いた。そして復活したイエスは、それを信じない弟子たちに、十字架で受けた手のひらと脇腹の傷に、指で触れさせ、その中に指を差し込ませて、自分であることを証明した。カラヴァッジオが17世紀の初頭に描いた『聖トマスの懐疑』は、その場面を描いて当時の人々に強い衝撃を与えた作品である(図10)。

図9 バルベルデ『人体構成論誌』より。Juan Valverde de Amusco, Historia de la composicion del cuerpo humano (Rome, 1560)

図10 カラヴァッジオ『聖トマスの懐疑』(1603)
ルネサンスの解剖学は、古代医学の復興と、事象としての人体の正確な記述と図示を目指した医学教育における革新的な営みであると同時に、そのメタファーの広がりを通じて、当時の社会における自己の問題とキリスト教における身体理解の問題と結びつけた文化的な装置であった。そして、古代の医学に対する崇拝と情熱が消え去った時代においても、解剖学という学問が、自己の問題と身体の象徴性を考えるときの鍵を握っているという信念は生き続けている。19世紀後半のアメリカでは、南北戦争後に解放されたアフリカ系アメリカ人の子供を主人公にして、彼に解剖学を教え、人体のメカニズムに合致した合理的な自己像(それは白人中産階級の自己像であると考えられていた)をもたせることを物語ったフィクション『サミー・タッブス』(Sammy Tubbs, 1887)が人気を博した(図11)。
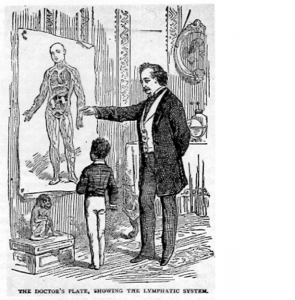
図11 Sammy Tubbs より。See Sappol (2002).
参考文献
Bylebyl, Jerome, “Interpreting the Fasciculo Anatomy Scene”, Journal of the History of Medicine and Allied Sciences, 1990(45), 285-316.
Bylebyl, Jerome, “The School of Padua: Humanistic Medicine in the Sixteenth Century”, in Charles Webster ed., Health, Medicine, and Mortality in the Sixteenth Century (Cambrdige: Cambridge University Press, 1979), 335-370.
Camporesi, Piero, Bread of Dreams: Food and Fantasy in Early Modern Europe (Cambridge: Polity, 1988).
Carlino, Andrea, Books of the Body: Anatomical Ritual and Renaissance Learning (Chicago: University of Chicago Press, 1999).
Clayton, Martin, and Ronald Philo, Leonardo Da Vinci: Anatomist (London: Royal Collection Publications, 2012).
Cunningham, Andrew, The Anatomical Renaissance: The Resurrection of the Anatomical Projects of the Ancients (Aldershot: Scolar Press, 1997).
Eisenstein, Elizabeth, The Printing Revolution in Early Modern Europe, 2nd ed. (Cambridge: Cambridge University Press, 2005).
Ferrari, Giovanna, “Public Anatomy Lessons and the Carnival: The Anatomy Theatre of Bologna”, Past & Present , no,117 (1987), 50-106.
Greenblatt, Stephen, Renaissance Self-Fashioning: From More to Shakespeare (Chicago: University of Chicago Press, 1980).
Greenblatt, Stephen, Shakespearean Negotiations: The Circulation of Social Energy in Renaissance England (Oxford: Clarendon, 1988).
Nutton, Vivian, “The Rise of Medical Humanism: Ferrara, 1464–1555”, Renaissance Studies 11(1997), 2-19.
O’Malley, Charles Donald, Andreas Vesalius of Brussels, 1514-1564 (Berkeley: University of California Press: Berkeley & Los Angeles, 1964).
Park, Katharine, Secrets of Women : Gender, Generation, and the Origins of Human Dissection (New York: Zone Books, 2006).
Roberts, K. B., and J. D. W. Tomlinson, The Fabric of the Body: European Traditions of Anatomical Illustration (Oxford: Clarendon, 1992).
Sappol, Michael, A Traffic of Dead Bodies: Anatomy and Embodied Social Identity in Nineteenth-Century America (Princeton, N.J. : Princeton University Press, 2002).
Sawday, Jonathan, The Body Emblazoned : Dissection and the Human Body in Renaissance Culture (London: Routledge, 1995).
Schupbach, William, Paradox of Rembrandt’s Anatomy of Dr Tulp (London: Wellcome Institute for the History of Medicine, 1982).
Siraisi, Nancy, Medieval & Early Renaissance Medicine : An Introduction to Knowledge and Practice (Chicago: University of Chicago Press, 1990).
Wear, A., R. K. French, and I. M. Lonie. eds., The Medical Renaissance of the Sixteenth Century (Cambridge: Cambridge University Press, 1985).
注
[1]この理由として、Park (2006)は、宗教と司法の役割、そして逆説的に聞こえるがガレニズムの役割の3点を挙げている。宗教的には、中世ヨーロッパでは聖人の身体の一部を聖遺物とすることや、遠方で死んだ家族の身体を解体・保存して故郷に送ることが行われていた。十字軍はこの慣習を拡大させている。この行為は1300年に教皇ボニファチウス八世によって禁止されているが、この禁令はあまり効力がなかったと考えられており、14世紀には人体の解体は宗教的に重要な行為であり続けたのである。司法においては、外科医による検死という法的な手続きが、イタリア、フランス、ドイツの各都市で成立したことが重要である。殺害された人体を検証して、その死因を定めることが外科医の任務の一つとなったため、人体を切り開くことからタブー性が取り除かれたと考えられる。ガレニズムについては、当時利用可能であったガレノスのラテン語訳やアラビア語の註釈からヨーロッパの医師が知ることができたガレノスの解剖は両義的な意味をもっていた。人体の代わりに動物を解剖したことは、人体を解剖してはいけないというメッセージと解釈されたと同時に、医学は解剖をするべきである、そしてできれば人体を解剖するべきであるというメッセージに解釈されたと推察できる。また、当時のスコラ哲学で隆盛していたアリストテレス哲学の機能と目的への注目は、医学において人体における臓器などの機能への興味を高めることにもなった。
[2]レオナルド・ダ・ヴィンチが15世紀末から16世紀にかけて実際に人体を解剖し、それを観察したスケッチが残っているが、その美しさと洗練された技術にもかかわらず、それらは現実の人体と対応しない間違った学説を再現した「図式」である。
[3]ダ・カルピの表紙絵が示唆する事象の重視は、もちろん、ダ・カルピが経験至上主義者であったことを意味しない。じっさい、ダ・カルピの先祖は床屋外科に携わり、エジプトのミイラの頭蓋骨から作った医薬を家伝の秘薬としていた。See Camporesi (1988).
[4]この植物園(オルト・ボタニコ、Orto Botanico)は、現在も原型をとどめて保存され、ユネスコの世界遺産の一つである。
これまでの連載一覧はこちら 》》》


