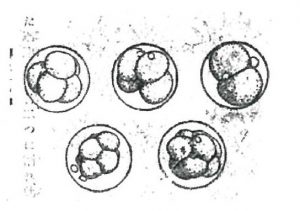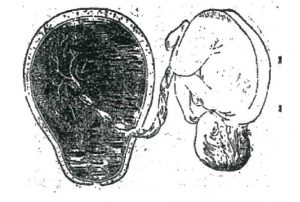第8回 家族の「きずな」を哲学する──私たちをつなぐものはどこにある?(下)
阿部ふく子×大島梨沙×宮﨑裕助×藤田尚志×宮野真生子
[愛――へだてがなくて、透明で、わかりあった関係?]

宮野真生子 福岡大学准教授。京都大学大学院文学研究科博士課程単位取得満期退学。日本哲学史、九鬼周造研究。著書に『なぜ、私たちは恋をして生きるのか』(ナカニシヤ出版、2014年)、『急に具合が悪くなる』(磯野真穂と共著、晶文社、2019年)、『出逢いのあわい』(堀之内出版、2019年)。編著に、シリーズ『愛・性・家族の哲学』1~3巻(藤田尚志と共編、ナカニシヤ出版、2016年)など。
で、さっき藤田さんからもご紹介があったと思うんですけども、ここのところしばらく、「恋愛」という概念は何なんだろう、今の日本でどういうふうに成立してきたんだろうというのをずっと考えていて、その中で恋愛の後には結婚が来るというのがよくあるパターンなわけですけれども、そこで言われている「愛」って何だろうというのを最近考えています。
後半部は、できるだけ開いた話題でいろんな方を巻き込んで議論したいというリクエストが宮﨑さんからありましたので、私からは何点か問題を投げるような感じで、一般的なお話を少し、と言いつつも、思想史の話も入れながらやっていきたいと思います。
さて、今日のテーマは「愛」です。この「愛」という言葉を聞いてまず何を思い浮かべるのかというのを皆さんに考えていただきたいんですけれども、さきほどの阿部さんのご発表では、「愛」というのは「一体」であるとか、「愛」というのは、ある種自然に出てくるものであると言われていて、「愛」にはやはり「一体性」とか、「一体」というイメージが強固にあるんだなというのを思いながら聞いていました。
私は実際、大学の授業で「愛の思想史」というのをやっているんですけれども、「愛」と聞いて思い浮かぶキーワードを9つ挙げてみてくださいというワークを講義のはじめによくやります。そうすると出てくるのが恋愛とか結婚、あと、家族愛とか子どもとの関係とかなんですね。あるいはJポップスや何か音楽のなかでこういう歌を聞くと「愛」について考えるな、というのありますかと質問すると、例えばRADWIMPSの歌なんか、よく出てきます。
ではそこでイメージされている「愛の形」というのがどういうものなのかな、と見ていくと、やっぱりさっきから出ている「一体性」――で、一体性って結局何かというと、隠しごとなどは、やっぱりないほうがいい。へだてがなくて、透明な、わかり合った関係という。「二人で一つ」って言いますよね。まさに阿部さんのヘーゲルの話の中でもありましたけども、一つのユニットの中の成員として関係をつくるということですね。そういうイメージ、これが正しいかどうかという話ではなくて、そういうイメージを私たちが持つことが多い。家族とか、愛とかを考えたときにへだてがなくて、透明な関係性で、わかり合っていて、溶け合っていて一個だと、そういうイメージを持つことがどうも多いみたいだね、というのがまず確認しておきたい前提です。
[愛の日本近代史(ざっくり)]
宮野 さて、こうしたイメージは一体、どのように出てきているんだろうというのをちょっと考えてみたい。今言ったみたいに、結婚とか、恋愛とか、家族というのに「愛」というのがくっついていて、かつ、その「愛」というのに何か、一体化や透明性といったものがあるとしたら、どこから来ているかというのを考えましょうというのが、今日の私のざっくりとしたお話の方向性です。
まず、結婚や家族に「愛」を結びつけるという考え方ですけども、そもそも結婚って愛ゆえにするのかという問題があります。もちろん、現代は恋愛結婚をする人が圧倒的多数です。たとえば、婚活というのはお見合いの一種だと思っている人が多いかもしれませんが、婚活のサイトを見るとおもしろいんですね。「みんなに恋愛結婚を提供します」というふうに書いてあって、婚活のサイトが提供しているのは、見合いではなく、恋愛結婚であるということがわかります。でも、そういうふうに、「愛」で結婚するというのは比較的最近の話です。
近代以前において家族というのは生活を共同でやっていく、あるいは経済的な共同体で、要するに、労働力として家族の成員が考えられている。子どもだって、家をつないでいくための存在で、要するに、さっきの前半の話でも、繰り返し、愛というのは感情だからとか、脆いからとかという話が出ていましたけども、そのような脆いもので家をつなげていくのは無責任なことで、むしろよくない、もっときちんとした家同士のつながりを持つということのほうが、結婚においては大事だというふうに考えられていたわけです。
ところが明治時代以降、つまり、近代になっていろいろ変わってきました。近代に入って日本に、いろんなものが入ってきますが、家族の形が変わるときに影響の大きかったものが三つあります。それがキリスト教、特にアメリカからやってきたプロテスタンティズムの影響、それから、近代医学の影響のもとで成立した母性主義、さらに産業形態と住まい方の変化です。
よく知られたことですが、近代の家族の特長というのは3つあります。夫婦を結ぶ絆としてのロマンティックラブ・イデオロギー、それから親子間、母子関係を規定する母性主義、それから、家族というものを一つの家庭としてまとめていく家庭イデオロギー、3つです。
それで、「夫婦の絆としてのロマンティックラブ・イデオロギー」と書いていますけれども、これは何かというと、要するに結婚というのは、愛し合った者同士、つまり恋愛結婚というのがベースになる。恋をして結婚するというのは、いいものと考えられている。その中で、やっぱりセックスというのは、愛し合った者同士でやりましょうと。その愛の証として子どもが考えられるところがある。これは割と今でもよくある、好きになったら結婚したい、で、子どもというのは私たちの愛の結晶よねという流れの考え方です。私たちは結婚をこうした順番で考えている傾向があるということですね。
こういった恋愛結婚がどういうふうに成立してきたのかというのは、いろんなプロセスがありますし、じゃあ、恋愛結婚をみんながするようになったのがいつからかというと、実は明治時代よりもっと後で、戦後の話になるんですけれど、でも、恋愛結婚というのが近代の日本で受け入れられるようになってきたきっかけとしては、キリスト教が輸入されて、友愛結婚という、二人の平等な個人を結びつける結婚が登場したことは間違いありません。
[恋愛結婚=近代的?]
宮野 もう一つ、念頭に置いておかないといけないのは何かというと、恋愛結婚できるということは、ある意味、進んでいると感じられていたということです。さっきも言ったように、明治時代になってみんなが恋愛結婚を一斉にするようになったという話ではないです。かなり上層の知識階層の人たちが、恋愛結婚いいよね、やろうよという話が出てくるんですけれども、そのときに、単にキリスト教の影響という話だけではなくて、もうちょっと社会状況とかかわっています。要するに自由で平等な個人の社会に、近代化して日本はなったんだと。そのときに、結婚だけ家の結びつきでやっているというのは非常に遅れている。個人の意志で、あなたが好き、私も好きという形でお互いを選ぶということこそが、西洋の近代化――まさに自由の実行――そのものを体現していることだ、というふうに考える人たちというのもいました。
だから、積極的に自由な交際をして、家同士のお見合いとかではなくて、お互いの意志を尊重した結婚をせねばならない。例えば、福沢諭吉も、意外かもしれないですけども、男女交際論とか、男女がどういうふうにおつき合いしたらいいかといった、社交の仕方についてある時期さかんに語っていますね。
[母性の規範化]
宮野 もう一つ大事なのが、母と子のつながりを強固なものにする、母性についての語りというのがたくさん出てくるということです。
明治の終わりから大正時代にかけて、家庭雑誌というものがけっこう出版されるようになり、そのなかで妊娠や胎児についての知識が結構広まってきます。そこで何が言われるかというと、母性を持っているのは自然のことなんだ、ということなんですね。
こういう、いわゆる母性愛言説を引っ張った人として、下田次郎という教育学者がいます。この人の書いた『母と子』という本はものすごく売れて23版を重ねています。もう1冊、『胎教』という、そのものずばりのタイトルの本がありまして、こちらも売れています。20版、30版と版を重ねていますけども、その中で彼が繰り返し言っているのは、ともかく、人間の母親というのは、自然の進化の結果として母性を持つようにできているのだということです。そこではかなり、母性を規範化して語るということが出てきます。
ではどうして、彼はこんなことを繰り返し言っているんだという話なんですけれども、すこし紹介しておきたいのは、そもそも胎児とか、子どもに対しての目線というのが、時代を追って変わってきているという話ですね。例えば江戸時代の『女重宝記集成』という本に出てくるのは、子どもがどういうふうな状態でおなかの中にいるのかという図(図1参照)です。
それに対して、さっき言った大正時代に出てくる大衆向けの家庭雑誌では、近代的な医学の知見を生かした妊娠の話や胎児の見方が出てきちゃうわけですね。子どもというのはこういうふうにおなかに収まっていますよとか、受精卵の分割ですよというような図版(図2、図3参照)もどんどん出てきます。そこで展開されるのは、非常に科学的な知識であり、自分のお腹のなかや胎児を客観的に、いわば第三者的に観るまなざしです。もう、仏のご加護はそこにはない。
このような図版が出てきた中で、当時の知識階層の男性たちが何を危惧したかというと、子どもを神聖なものとして扱う態度が薄れてくる、あたかも物のように見てしまうになるんじゃないかということです。そうした危機感のもとで多く出てきたのが、実は母性愛というものが人間の自然として備わっているんだよという言説です。
そもそも、こうした科学的な妊娠過程の図版を世に広めたのは下田次郎なんですが、子どもというものが、仏の化身が宿った非常にありがたいものだという見方から、受精卵はモノにすぎないというふうな捉え方になってしまってはやはりまずいな、と思ったんでしょうね。じっさい、『青鞜』の堕胎論争で原田皐月が受精卵のことを「母胎の附属物」で「本能的愛など感じない」と言ったりしますし。そして、下田が盛んに言うようになるのが天性としての母性みたいなことですね。母性というのは、自然の働きとして女性全てに備わっているのだと。
このとき非常に重視されるのが母乳の話です。前半の宮﨑さんの話でも、乳母のような育ての母の話があったんですが、この時代、実母が母乳で育てるというのがまさに母性のあらわれなんだ、というふうなことを言う人たちが増えてきます。
もちろん、母乳で育てるのが母性の表れというわけでもなければ、そもそも母性というもの自体を生得的なものとして語るのも問題含みですし、さらに、「母は子を愛して当たり前」というように規範化していくことはもってのほかなのですが、この時代はそこが疑われることなく母の愛というのは自然にあるんだということが繰り返し言われた。その中で、家庭の形というのも変わってくるわけですね。その背景には、産業の形態が変わっていって、サラリーマンとその妻という、今私たちがイメージするような夫婦と家庭の形というのがあります。
[愛によってつながる家族]
宮野 愛と家族の関係を考えるとき、もう一つ鍵となるのが「ホーム」という言葉です。巌本善治という、日本に恋愛結婚を広めた人として非常に有名な人がいます。彼は、いわゆる、私たちが「マイホーム」と言うとき「ホーム」が持っているイメージを打ち出した人です「マイホーム」というと、ただの家の話じゃないですよね。「マイホーム」というと温かいおうち、マイホーム欲しいみたいな、ちょっといいイメージがありますよね。そういう意味で「ホーム」をいい意味として使うようになったのがこの時代なんです。
巌本がどういうふうに書いているかというと、もう、「ホーム、ホーム」の連呼です。「昔のエデンの園は今もホームに残れり。後の天国の光は既にホームに照れり」というふうに、家族のいる家庭というのはいいところだ、ということを語ります。このとき、巌本が考えている結婚は、いわゆるお見合いではなくて恋愛に基づいて、お互いが愛し合ったところで形成されるものです。そうした愛情によってつながる家族が暮らす場所がホームというわけですね。
では、今私たちがいる「愛」をめぐる状況はどうなっているだろうと問いかけたいのですが、長らく日本人が選ぶ理想の夫婦として1位をとっていたカップルが田中将大さんと里田まいさんです。なぜ、この2人が理想なのか、そこでイメージされているものは何なのか。もちろん。この2人は恋愛結婚です。そして、子どもができて、温かい家庭。ご存じのとおり、里田まいさんというのは、田中選手が食べる料理をブログやSNSにアップして、愛がある、いい嫁ナンバーワン、みたいなことを言われているわけですけれども、すごくわかりやすいイメージだと思います。近現代における「愛」の配置を考えるときに、一つのモデルケースとも言える。
では、そこで言われている「愛」の形って何だろうと。前半の宮﨑さんのお話のときに、「信じることで家族になる」という話がありましたが、その「信」というのを裏打ちしているものは何だろうとなったときに、そこにあるものが「愛」と呼ばれるものなのか。では、そこで私たちが託している「愛」って何だろうというと、あなたの人生は私の人生、一つのユニットとしてお互い一緒にやっていくという、一体化とか、夫婦の同一化とか、母子の過剰な一体化とか、あるいは家族は一蓮托生だから、といった、家族だから助け合わないといけないという、ある種の一体化があるのだろうなと思います。
ただ、もとはといえば、近代における恋愛結婚というのは、自由と平等の選択の結果としておこなわれるものという話だったわけです。では、今見てきた「一つになる愛」は、そうした自由で平等なものの結果として行われているのかなという疑問を最後に呈しておきたいと思います。
[一体化した愛の実際]
宮野 「一つになる愛」は、実際どうだったんでしょうという話を考えたときに、ご存じの方も多いと思うんですが、高村光太郎と高村智恵子という2人の、大変有名な、近代に残る夫婦がいます。『智恵子抄』を読んだことある人もいると思うんですけれども、この2人というのは、まさにお互いを芸術家同士として互いに尊重する。籍は入れず、法律婚はしていないんですけども、自由恋愛して、結婚する。互いを選び、尊重するんだと。
結婚に際して、2人が何を言っているかというと、まさに「一体化した愛」というのをすごく語っています。例えば光太郎は「人類の泉」という詩で「あなたは本当に私の半身です」と呼びかけ、その後で、「僕のいのちとあなたのいのちとがよれ合い、もつれ合い、溶け合い、すべての差別見は僕等の間に価値を失ふ」(高村光太郎「人類の泉」)と謳い、お互いが自分の片割れであって、その2人が溶け合って、一つのユニットになるんだ、ということが繰り返し言われます。
それに対して、高村智恵子、妻のほうがどう応えるかというと、同じように応えるわけですよね。「潤され温められ、心の薫ずるおもいがする私達の家」、やっぱりここでも「家」が出てきますね。これは「箱としての家」じゃない、家族として家庭を持つという意味での「家」ですよね。
智恵子の言葉は「よきにせよ不可なるにせよ、おおうものなく赤裸で見透かしのそこに塵埃をとどむるをゆるさない」と続きます。まさに、お互い隠し事がなくて、透明な、つながった関係というのが2人の間にあると言われています。
では実際、この2人の関係はどういうものだったのか。光太郎だけではなく、智恵子自身も芸術家だったんですが、彼女は、自分のやりたいことというのはほとんどできないままに、結局終わるわけですよね。気がつくと智恵子が家事をとり仕切って、光太郎を支える形になっている。
このときに智恵子は何か強制されて自分の芸術家としての仕事を放棄していく、というわけではないんです。彼女は、もともと日本女子大を出ていて、いわゆる「新しい女」です。そんな彼女がまさに自分の意思で、できる女というか最先端の女として、「私は自分で自由恋愛して、結婚を選ぶ」というふうに、自分から結婚を選んでいくわけですね。彼女は福島が実家なんですけども、地元に帰ってしまったら家の都合で結婚させられる。だから、そんなところに自由平等はない。自分は、やりたいように近代的な生き方をするために自由な結婚を選ぶんだ、というわけです。これは、当初巌本たちが考えていた理想的な結婚のあり方ですよね。一方、光太郎のほうも、「僕たちは同志だ」と言う。これもすごくまぁ、いい感じです。
でも、結局どうなるかというと、才能があった光太郎と、智恵子自身の才能に関してはちょっとよくわからないところがあるんですけども(色弱だったという話もある)、彼女は絵描きとしては芽が出なかった。最終的には、夫光太郎を支えるための「妻」という立場におさまっていく。たとえば、『月に吠えらんねえ』という漫画はこのあたりの経緯を見事に書き出しているんですが、そのなかでは、智恵子に「あなたの妻、あなたという天才の付属物」と言わせています。
そう考えたときに、たしかに「愛」というのは「一体」なのかもしれないですが、その「一体」がどんなバランスで行われているのか、「僕たちは同志だ」とか「半身だ」とかと言っているけれども、そんなに平等な関係になっているのか。むしろ、「愛」という名前のもとでさまざまに起こっている不平等なことを、隠しているんじゃないか、ということですね。
[一体化に隠される不平等]
宮野 この一体化の不平等を見事に撃ったのが話題になったドラマ「逃げ恥」ですね。このドラマのなかに、すごく印象的なエピソードがあります。この物語は、大学院を出て仕事のない女性がシステムエンジニアの男性と「お仕事」としての結婚、つまり、契約結婚をすることから話が始まるんですが、少しずつ2人の関係が親密になっていくんです。そのうち、契約ではない形の結婚をしようか、となっていくんですが、そこで問題が発生します。2人が契約結婚をしたときの契約条件は女性側が家事労働を担い、それに対し男性が決まった金額を払うというものでした。
で、そのときに何か、例えば決められている仕事より多い仕事をこなさないといけないことになったとする。仕事だったら、決められたものと違う仕事をするならオプション料金を払うわけですよね。だって、決められている仕事以上のことをやるから。けれども、ところが契約じゃない、いわゆる結婚ってなったら違うかもしれないと女性側は気づく。だって、結婚しているということはあなたのことが好きなんだってことで、そしたら、少しその人のためにやることが多くなったからといってオプション料金くれとかいえない、むしろこの人のためにだったらやるのは当然、みたいに普通考えられているんじゃないかと。
そうすると、実は結婚って厄介だな、みたいなことを主人公の女性が言うわけです。仕事だと、きちんと決めて、これをやったらこう、これをやったらいくらとかって決まっているけれども、結婚で「愛」といったら、「愛があるんだから」で全て片づいちゃうじゃん、という話ですね。だから、もしかしたら、「愛」という言葉は、すごくいい側面もあるけども、「一体化」という名のもとに、すごく不平等なものを隠している可能性もあるんじゃないんでしょうかというのが、私からのお話です。
[家族の「きずな」と法の役割―結婚制度を手掛かりに]

大島梨沙 新潟大学准教授。北海道大学大学院法学研究科博士課程修了。民法学。共編著書に、『性的マイノリティ判例解説』(信山社、2011年)。共著に、『家族研究の最前線②出会いと結婚』(日本経済評論社、2017年)など。
まず、私がやってきた研究がどういうものだったかを簡単にご紹介したいと思います。私はこれまで、「カップル関係というものをいかに法律が取り扱うか」ということをテーマとしてきました。
なぜそういうところに興味を持ったかといいますと、法学部生であれば必ず学習するものとして、契約制度というものがあるわけですけれども、そこでは、平等な個人が1人1人自立していて、それぞれ責任を持っていて、そこで自ら、自由意思で意思表示をして契約関係に入る。その契約には拘束されることになるけれども、それは自らの自由意思でそれを望んだからだと教わる。このように、人と人との間に法がどのように適用されるか通常は丁寧に説明していくわけです。それがなぜか、家族の間に法が適用される場面になると十分に説明されないことが多く出てくる。理屈で全部説明できるはずだった世界が、家族の話になると何でこういうことになるんだろうと。カップル関係というのも人と人との関係ですから、普通に契約を語るときと同じように法学の世界では語っていいはずなのに、なぜこう、カップル関係、婚姻関係ということになると中身がぐだぐだになるんだろうか。そこに興味を持ったのです。
そこで、研究の具体的な素材としたのは、婚姻していないカップルが利用できるフランスのPACS制度(フランス語の原文では pacte civil de solidarité、日本語に訳しますと「民事連帯契約」となります)というものです。というのも、フランスのPACSは、契約の一種だと考えられているからです。婚姻とか家族制度とは違って、単なる契約なんだと位置づけている。しかし、何のためにあるかというと、カップルのために存在しているんです。同性であれ、異性であれ、共同生活を送る2人のために、2人が使う契約としてつくられています。日本ではきちんと法的に説明し切れていないカップル関係というものが契約として把握しうる。そういうちょうど私の問題意識に合う素材だったわけです。
ちなみに「民事連帯契約」のこの「連帯(solidarité)」という言葉は恐らく、日本語の「絆」という言葉のイメージに近い気がするんですね。つまり、フランスではいいイメージの言葉です。「連帯」っていう日本語だと、硬く感じてあまりいいイメージのように聞こえないですけども、これを日本語にもうちょっと語感を合わせて訳すとすると「絆」になると思います。ですので、PACSを研究対象としてきた私が、今回この、家族の「きずな」をテーマとする会に呼んでいただいて話ができることをとても嬉しく思います。
さて、こういった私のこれまでの研究の背景から、今回のテーマについては2つのことを考えました。1点目は、契約制度と比べて家族制度にどういう特徴があるのかという、私が今まで考えてきたことをお話することで、現在の法がとらえている家族の絆の特徴というものを提示できるのではないか。2点目は、―法を専門としていない人はあまり興味がないかもしれないんですが―家族の絆において法は一体どういう役割を果たすべきか。これは、私が自分の研究に取り組んでいる上でずっと考えていることですが、家族の絆においてもっと、私には見えていない法の役割みたいなものを考えていかないといけないのかもしれないとも感じています。この機会に、何かその示唆をいただけたらと思ったのです。
では、1つ目の点からお話したいと思います。具体的には、結婚と通常の契約とはどう違うのか。それから、結婚と、民事連帯契約、つまりフランスで共同生活のためにつくられた特殊な契約とはどう違うのかという点から家族のきずなを考えたいのです。ですが、お時間が15分しかない中で、結婚制度と、通常の契約と民事連帯契約を全部説明したら時間がなくなりますので、それぞれどのようなものかという話を飛ばしまして、今のところ私が、こういうものが家族の絆の特徴として抽出できるかなと思った、その結論だけをお話ししようと思います。
[法制度からみた家族の絆の特徴]
1.絆が公示されている
大島 まず、法制度から見た家族の絆というものの特徴は何だと言えるか――契約制度にはないけれども家族制度にはあるものは何か、という視点で見ていくことになりますけれども――、第1に、「他の人々にその絆というものが公示されている」という点が、大きな特徴だろうと思います。
ちなみに、普通の契約の場合は、公示はされていません。普通の契約というのは、売買契約ですとか、賃貸借契約ですとか、委任契約ですとか、種類としていろんなものがありますけれども、法学の世界では、それは契約をした当事者だけの関係、当事者だけを縛るというふうに考えまして、当事者だけで自由にやってください、という話になりますので、その契約の存在を第三者にわざわざ示すというようなことはしません。けれども、家族に関しては、公示されている。
では、どのような形で公示するか。日本の場合には、「氏による絆の明示」というものが存在します。同じ氏の人が同じ家族なんだ、氏が同じであれば家族だというふうに明示できる。ですから、夫婦は同氏でなければいけないというのが法律(民法750条)で定まっていて、日本の場合の絆の公示の仕方の一つになっている。それ以外に、戸籍(日本の場合は戸籍、フランスの場合は身分登録簿)にこの人たちは夫婦ですよ、親子ですよということを登録する。必要な人がその謄本や抄本を閲覧できる、という形で絆が公示がされています。
2.性規範を内包している
2点目が、「性規範を内包している」という特徴です。通常の契約に関するルールの中には、何か性規範を想起させるようなものは入っていません。これに対して、家族関係、特に婚姻関係には、性規範が含まれています。例えば、当事者の間に貞操義務――つまり浮気をしてはいけないという義務があります(民法770条1項1号からの解釈)。それから、父性の推定(民法上は嫡出推定と表記されています)、つまり妻が夫との婚姻中に妊娠した子どもは夫の子どもとする、というルールがあります(民法772条)。これは、夫婦には浮気をしてはいけないという義務があることを前提としたもので、性規範を内包しているといえます。さらに、モノガミー原則、つまり一夫一婦制(民法732条)というのも、ある人にとって継続的に性的な関係をもつ相手は1人でなければいけないという性規範を含んでいますし、近親婚の禁止(民法734条・735条・736条)、つまり近親者の間では結婚してはいけないというルールは、近親者の間で性的な関係を有してはいけないという性規範を内包しています。
家族の絆に関するルールにおいて「性規範を内包している」のはなぜなのか。家族の絆と性規範というものの、この不可分性を一体どう分析すべきか。これらについては、まだ自分の中でも答えが出ていません。性行為から子が誕生し親子関係が生じるため性規範も家族の絆に関するルールに含まれるというのは一つの説明でしょうが、それだけであれば、子と養子縁組をした夫婦や子をもつつもりのない夫婦でも貞操義務を負うことを説明できません。昔ですと、生まれてくる子どもの父親を定める方法として、夫婦の貞操義務と父性推定(妻が産んだ子は夫の子とする)は不可欠だったと言えるかと思うんですけれども、今は、必ずしもそうでなくてもいいように思いますし。実際の社会には性愛とは関係のない家族の絆のあり方もあるはずで、この法制度上の家族の絆の第2の特徴がなぜ生じるのかは考えなければいけないなと思っているところです。
3.絆の内容(権利義務の内容)が曖昧である
3点目は、「当事者内での絆の内容が曖昧である」という特徴です。婚姻をした当事者が負う義務というのは、同居、協力、扶助義務(民法752条)、それから婚姻費用の分担義務(民法760条)というものです。「協力する」というのは具体的に何をすればいいのか、「婚姻費用」とは何なのか、具体的にはいくら支払うのかなどは定められておらず、かなりざっくりとしています。
これを売買契約と比較してみますと、売買契約の場合は、売主はその売買の対象となった物を買主に引き渡す(厳密には、「財産権を相手方に移転」する)という義務、買主のほうはその代金を売主に払うという義務を負う(民法555条)ということになっているわけですので、当事者がどういう義務を負うかが具体的ではっきりしています。そして、その義務を履行しなかった場合にはこういう責任を負いますと法律に定められています。
これに対して、婚姻の場合は、当事者が婚姻をしたことによって相手に対して一体何をしなければいけないのか、それをしなかったらどういうサンクションを受けるのかというのが、漠然としています。たとえば、先ほどの話にもありましたが、家事といっても、一体どこまでの家事をすることが求められているのか、はっきりしないわけですね。「同居、協力、扶助義務」があるとしか法律は定めていない。後々離婚が問題になったときに、この義務を夫婦が果たしていたかどうかというのが考慮されるというぐらいの話で、ちゃんとその義務を履行しなかったことのサンクションというのもはっきりしない。これは、婚姻の特徴でもあるし、共同生活の特徴でもあります。フランスのPACSにもこういう、同じような特徴が見られます。カップル関係を民事連帯契約という契約で捉えたとしても、結局、当事者の負う義務というのは、「協力義務」とか「援助義務」といった表現となっており、その内容は曖昧なのです。
4.自由に合意できる範囲が狭い
4点目に挙げたいのが、「当事者が自由に合意できる範囲が狭い」という特徴です。通常の契約の場合は、当事者が自由に合意をできる。当事者はあくまでも自分の意思に拘束されるのであるから、自分の意思でそういう合意をしたのであれば、そのとおりそのルールが適用されますとなるはずです。しかし家族の場合、そうではない。当事者が合意したとしても、それは許されないとなる可能性がある。このように、当事者の自由な合意で変更することができない法律上の規定を「強行法規」と言います。家族法の部分の規定というのは、ほとんどが強行法規だと言われています。
ただし、このような説明にはクエスチョンマークがつくかもしれません。解釈の問題が実は入っているからです。家族に関する法律のすべてが強行法規なわけではなく当事者の合意で修正できる場面もあるとする学説もありますし、それから、普通の契約の場合でも、許されていない合意というのもある程度ある。したがって、この第4の特徴は、程度問題かなという気もいたします。
5.当事者以外の人にも法的な効果が発生
5点目が、「当事者でない人にも法的な効果が発生する」という特徴です。通常の契約ですと、契約を結んだ当事者の間だけでしか、法的な効果というのは発生しないことになります。これに対し、家族の絆については、その行為の直接の当事者でない人にも法的な効果が発生します。
例えば、自分の子が結婚すると、子の配偶者と自分との間に親族関係が発生します。そうすると、特別な事情があると裁判所が認定した場合には相互に扶養義務を負うことがあります。
もう一つの例としては、不貞の相手方の慰謝料支払責任というものがあります。例えば、夫が浮気をした場合に、その浮気の相手方が、夫の法律上の妻に慰謝料を支払わなければいけないというものです。このような請求ができるということは最高裁判所によって肯定されています(ただし夫の浮気の時点で既に別居状態にあった妻はこのような慰謝料請求はできないとされています。最判平成8年3月26日民集50巻4号993頁)。
結局、その絆の内部の人だけではなくて、そのほかの人たちもその絆を尊重すべきだというふうに位置づけられているというのが、この家族の絆というものの大きな特徴かと思います。
[家族の絆における法の役割]
大島 では、この家族の絆において法はどういう役割を果たしているのか。三つ挙げられるのではないかと思います。
まず「絆の可視化」という役割です。先ほどお話しました通り、家族の絆の影響は第三者にも及ぶため、この人たちがどういう関係かというのを明示しておく必要がある。その「絆の可視化」というところを、今日の日本では、法が担っています。しかし、可視化ということに関しては、必ずしも法がやる必要はないわけでして、かつては共同体の中で結婚式をあげるだけでよかったはずです。したがって、法にしかできない役割というわけではありませんが、今はこれが、法が担っている役割の一つということになるかと思います。
二つ目が「絆の保障」という役割です。これにも二つのレベルのものがあって、一つ目が、関係がうまくいっているときに、それを阻害しないというものです。例えば、部屋を借りるときに、借りたいという2人が「夫婦です」と言ったら貸主と契約を結びやすい、ということが今もあるかと思います。その理由の一つとして、夫婦には日常家事債務の連帯責任があること(民法761条)、つまり、2人のうちの一方が家賃を滞納しても他方がそれを支払う責任があるということが挙げられるように思います。その他にも、社会保障ですとか、税制において、この2人が共同生活をしているということに配慮した制度を設けることによって、その共同生活をしやすくする、というものがあるかと思います。
しかし、重要なのはもう一つの「トラブルが起きたときの保障」という方かと思います。こういうものとしては、離別時のお金の清算ですとか子どもの養育のあり方、DVとか児童虐待があったときの保護、一方が死亡してしまったときの他方の住居保護とか財産保護、というようなものが挙げられます。これらはぜひとも行ってもらいたいものですが、現在の法律による保護は十分ではない。特に日本の場合は、十分ではないと言えるかと思いますが、フランスでも様々な課題があります。結局、家族の絆にトラブルが起きたときの保障というものを法律が完全に行うというのは、やはり無理なんだろうと思うんですね。とはいえ、夫婦の一方が遺言を遺さずに死亡した場合に、生存配偶者がその死者の財産を相続できるなど、ある程度の保障までは法律ができる、担っているといえるでしょう。
3点目は「絆の選別(「望ましい」絆の提示)」という役割です。例えば、ある子どもの面倒をある女性が常に見ていたとしても、それだけでその女性がその子の「母」であると法律上も扱われるわけではありません。法は、誰が子の親となるのか、誰が配偶者となるのかについてのルールを定めており、それに合致しないと親であるとか配偶者であると認めません。社会生活上、「家族」のような実態がいくら存在しても法律がそれを家族と認めないことによって、社会に様々に存在する絆の中から特定の絆を選別し、それによって「望ましい」絆を提示するという役割を法が果たしている/果たしてしまっているように思います。
例えば、今の日本で言うと、法律上は同性同士では結婚できないと(解釈)されているわけですが、そうすると、これは、異性愛が正しい、男女で結婚することが正しい、というような話に結びつきやすくなってしまう。「異性愛が正しい」と直接法律で定めているわけではないけれども、法律が結婚することを認めていないような関係は社会的に承認されていないのだろうという含意をもって理解されてしまいます。
では、なぜ法律が選別という役割を果たしてしまっているのか。ここが難しいところかなと思うんですけども、絆の選別はいけないと言いつつも、その一方で、絆の選別を求めるようなニーズというのもあるのかなというふうに個人的には考えています。そもそも、「結婚したから認めてください」というふうに役所に行くときの気分というのは、「私たちの関係は特別です。ほかとは違います」というものであるわけで、ほかの人との関係と差別化しているわけですよね。ほかと差別化して、自分たちの関係を特別なものとして認めてもらいたい、そして、その関係を守ってもらいたいという。だから、そもそも結婚を求めるということにおいて、選別してもらいたいと思っている部分があるのかもしれない。そうすると、制度の側が(どのような関係が婚姻として認定しうる関係なのかを示さずに)選別しないとなるとそれはかえって意味がないことになるのかもしれない。
それから、法が絆の選別という役割を果たしているもう一つの背景には、誰が結婚できるかできないかというルールを通して、社会における性規範や性秩序を示そうとしているという部分があるのかなと。例えば近親間では結婚ができないというルールがありますけれども、それは、兄弟姉妹間では性的な関係を持ってはいけませんとか、親子間では性的な関係を持ってはいけませんという、性規範を示しているという側面がある。そのような性規範を定める方法として、子との間で性的な関係をもった場合に親に刑罰を与えるといったやり方もあると思いますが、それだけではなくて、「婚姻できませんよ」という形で、親子間で性的な関係を持ってはいけないという規範を示しているというわけです。
[安心の提供]
大島 最後に、家族の絆についての法に、一体何が求められているかということについてお話して終わりたいと思います。結局、絆を求めるときの根底には、不安、つまり1人では生きていけないとか、1人では寂しいとか、何かこう、不安というものがあるのではないか。けれども、その絆も壊れるかもしれない。だから、法で守ってもらって安心したい。「安心の提供」ということが法に求められているのかなと思うんですが、一体何を提供してもらえば安心できるのかというところが人によって違うので、難しいところかなと思っています。
結局、私たちは家族の絆に何を期待しているかというところを考えれば、望ましい法律というものもわかってくるのかなと思っているところです。長くなりましたが、私からは以上です。
宮﨑 では早速議論に移りたいと思います。まず、宮野先生と大島先生のお2人に、何かご質問、あるいはコメント等ありましたら、会場のほうからよろしくお願いします。
[別姓がなぜ日本では認められないのか]
質問者 大島先生に質問です。大島先生のレジュメの「絆の選別」というところ、例えば、家族の絆の特徴といったところに、性規範を内包しているというところで、2013年に婚外子の差別に違法判決がでた後でも戸籍上での婚外子の区分は残りましたよね。それは何でだったのかと、私、いまだにわからないんですよ。
「絆の選別」の基準のひとつが氏で、氏によって絆を明示するということなんですけれども、日本ではなぜ別姓が認められないのでしょうか。あるいはなぜ抵抗が非常に強いのでしょうか。すごく疑問なので、大島先生はどうお考えか、ぜひお聞きしたいです。(注:質問者の方の発言は、編集部で短くまとめさせていただきました)
大島 ありがとうございます。私もまだ完全にその答えというものがあるわけではないんですけども、「不安」とか「安心したい」というところがキーワードだと思っています。カップル関係というのは壊れやすいものですので、法制度が何らかの安心を提供しようとしますが、日本の場合は、実は、夫婦が同氏であるとか、生まれた子が「嫡出子」になるとか、そういう象徴的な部分でしか(結婚という)絆を守ってないんじゃないかなというのが、私の仮説なんです。
というのは、(日本の対局にある例として面白い)フランスの場合は、氏にあまりこだわらないかわりに、夫婦は財産において「一体である」ということを重視しているように見えます。フランスの法律は、夫婦の財産は、結婚している間は一体になるんだというふうに考えている(契約でそれとは違う定めをすることもできますが)。したがって、離婚をするときには、夫婦で形成した財産を清算する手続が必ず必要となり、夫婦の共通財産が半分ずつに分けられることになります。こういった財産的な保障を行うことにより、結婚という絆を守ろうとしている。
それから、子どもについて、父母が婚姻しているか否かによる「嫡出子」「自然子」という違いは今のフランスにはありません。親の状況がどうあれ、子に法的な父母が存在するならばその2人のどちらにも親権があり、子に対する養育責任があります。両親の離別後でも離別という事実だけで親子関係が断絶することのないように親子関係を法的に保護しています(実際には色々と困難な課題もあるようですが)。このようにして、フランスでは、絆の内容の部分に着目して、絆の実質を守ろうとしている一方、氏の同一性や子のカテゴライズといった象徴的な部分は、少し緩めることができたのだと思うのです。
翻って、日本の場合は、(別途契約を結ばない限り)夫婦は各自別々に自分の名前で得た財産を所有し管理できるものとして扱われ、法制度上は、所有者である一方が独断で家族にとって重要な財産を処分することもできます。財産の少ない側の当事者は、離婚時に配偶者から財産を分与してもらうことができますが、離婚とは別に元配偶者と合意することが必要で負担が大きいため、取り決め率が低くなっています。子どもも、父母が離婚したらどちらかのところへ行ってしまって、他方の親は子とはもう全く会えなくなってしまうというのが今までのやり方でした。このような不安な状況で、法律によって守ってもらえる部分がどこかといったら、もう象徴的なところしかないわけで、戸籍に家族として表示されているとか、名前が一緒になったんだからそう簡単に別れられないだろうとかって、そういうところにすがるしかない形になっているのではないか。そうだとすると、氏までが別々になってしまうことに不安を抱く人がいてもおかしくないのかもしれません。
宮﨑 ありがとうございます。他にいらっしゃいますか。今のようなご質問やお悩み相談でも大丈夫です。
[家族観、結婚観の多様性]
質問者 家族と言ったときに、今のところ出ているのが、夫と妻、ちょっと子どもが入るかな、というぐらいの範囲でしたが、子どもから見てのおじいちゃん、おばあちゃんに当たる人たちのことまで含めると、今回の議論は、少し変わってくるのかなと思います。
というのは子どもを育てる場は、今、核家族が主流じゃないですか。けれども、僕は小さいころ祖父母に預けられて育ててもらったので、僕の家族認識は、父母で終わらずに、祖父母まで含まれています。そういう考え方をすると、見え方が変わってきますかね。(注:質問者の方の発言は、編集部で短くまとめさせていただきました)

藤田尚志 九州産業大学教授。博士(哲学、リール第三大学)。フランス近現代思想、アンリ・ベルクソン研究。編著に、シリーズ『愛・性・家族の哲学』1~3巻(宮野真生子と共編、ナカニシヤ出版、2016年)。現在、「けいそうビブリオフィル」にて、『ベルクソン 反時代的哲学』を連載中(近刊)。
ただ、そのときに――これはもしかすると今日のさまざまな哲学的な議論の中では十分に強調できていなかったかもしれませんが――、デリダが常々慎重に言っているのは、今自分がしている議論は、あくまでも哲学的に概念をもう一回考え直したらどうなのかという話であって、実際の実地に下ろしたときにそう性急に事は運べない、ということです。しかしだからこそ、ここは法学の方々と協力してやっていけるところではないかなとも思っているんです。実際に下ろしていったときに、やっぱり軋轢というか、実際に実施していったときに問題がいろいろ生じてくると思うので、そこは考えるべきですね。
他に、何かつけ加えることはありますか? 宮﨑さんと阿部さんも、何かコメントがありましたら。

宮﨑裕助 新潟大学准教授。東京大学大学院総合文化研究科博士課程修了。哲学、現代思想。著書に『判断と崇高──カント美学のポリティクス』(知泉書館、2009年)、『ジャック・デリダ──死後の生を与える』(岩波書店、近刊)など。
宮野 そうですね。
宮﨑 それは、家事の大きさというか、子育てもそうだし、さっきの話で、結局、夫婦では担い切れないものがあるんじゃないかなと思うんですね。
宮野 はい、はい。
宮﨑 いや、もちろん単純に、男性の意識が甘いだけで、ちゃんと協力してやればいいだろうというふうにして、これは自分にもはね返ってくるんですけども、そういうことももちろんあるけれども、でも、実際に総量としては共働き家庭には担いきれない負担が強いられているということがある……。
宮野 それは、わかります。
宮﨑 でもだから、じゃあ単純に、おじいちゃん、おばあちゃんに頼るべきかというと、そうでもないしそうすべきでもない。だから、なんかイデオロギーの問題ではなかなかないんじゃないかなと思っているんですよね。
宮野 家事の問題は非常に言われていて、以前、東京でブックイベントをしたときに、シェアハウスの研究者の方とお話ししたんですけれども、そのときにも話題になったのが、日本は、要するに家事の要求レベルが高過ぎるんだと。例えば食事とかに対しての要求度が半端じゃない。なぜあそこまで高くしないといけないのか。それによって、すごく過剰な負担が発生していて、その負担が基本的にはやっぱり女性のほうにかかっているというのがあると。
それはそうだと思うんです。だから、家事をもっと、外部化したらいいんですけども、やっぱりそこが非常に難しいのは、さっき――これはちょっと、大島さんの話にもつながってくるんですけれども、家族だからしようがない、みたいなときに、「家族なんだから」ということに内包されているものが何かということなんですね。そこで、レベルの高い家事をすると、すごく頑張っていて、家族としての絆が――要するに、それが愛の証だ、みたいなところがあって、そういう弱みみたいなものが、やっぱりあるんですね。
宮﨑 女性のほうも、それをやらない女性は女としてだめ、みたいな。だから、世間の目を気にせざるをえないところがあるんですね。
宮野 そう、それはあると思う。気にする人はけっこういると思うんですよね。この前、ある女性研究者と、私たちちゃんと自分で稼いでいるんだし、そろそろ家事をアウトソーシングしていいよね、という話をしていたんですけども、なぜ私たち、こんなこと、「いいよね」って2人で確認しないといけないんだろうという(笑)だから、やっぱりそこのプレッシャーは結構大きいんじゃないかなと思いますね。
藤田 シンポジウム冒頭の話に戻る形で、今の発言につけ加えたいんですけれども、愛・性・家族を結婚という枠組みの中に強固にまとめ上げていくというのが近代までの結婚観の歴史であったとすると、近代から後の、現代の結婚観というのは、あまり愛・性・家族を一体化させすぎないという方向に、一体化させすぎるとみんなしんどくなるので、切り離してもいいというふうに考える方向に、少しずつシフトしてきていると言えるのではないかと思うんです。細かく見ればまだまだその方向には全然進んでいないという論拠をいくらでも挙げられるでしょうけれども、大局的に見ればやはりその方向に進んできていると言えると思います。家事やケアのアウトソーシングが議論できるようになってきた、ということ自体を「まだその程度に留まっているのか」ということも出来ますが、時代は確実にその方向にシフトしてきているとも言える。
例えば愛と性は結びついてなくてもいい、性と家族は結びついてなくてもいい、愛と家族は結びついてなくてもいい。もちろん、結びついていても構わないんですよ。それで幸せな結婚生活が送れるならそれでもいいんです。ただ、「家族なんだから、愛しているんだったら、これくらいやってくれて当然」とかいうのが、負担になる場合がある。そういう場合にしんどくなりすぎないようにするという意味で、「切断」、一度ちょっと切ってみるということは考えられるし、また実際に考えられてきているのかなと。
そういう見通しの下に『愛・性・家族の哲学』というこの3巻本を出したのですけれども、我々のテーゼとしては全然「愛・性・家族」を一体のものとして考えましょうという話ではなくて、むしろどうやったら切り離せるのか、実際にどう切り離されているのかを見定めるために一旦まとめて考えましょう、ということだったんです。
[儀式の役割]
質問者(古田徹也さん) 関係あるかどうか……。『アンチゴネー』を自分で読んだのが大学1年のころで、そのときの感想は、「葬式って大事なんだな」って。(笑)
恥ずかしながら、そういう感想を持ったんですが、その後、哲学を学ぶようになって、さまざまな哲学者がアンチゴネーを論じているんですが、ついぞ葬式の話が出てこなかったんですよね。
で、その違和感と近いものをきょうも感じることがあって、例えば新潟市の周辺にもばかばかしいほど豪華な結婚式場があったりする。大体平日は全部閉まっていて、祝日と土日だけで経営を成り立たせている。それほど結婚式を、どーんとやる人たちがいる。
きょうの「家族の絆の哲学、あるいは私たちをつなぐものはどこにあるのか」という問いを考えたとき、どうしてもそうした儀式的なものというか、区切り的なものというか、そういうものも外せないような気がしました。もちろん、そんなものは必要ない、例えば結婚式も、葬式もやらないもあり得るし、実際あるんだけども、それでも、多くの人は例えば人前式とか、なにかしら儀式的なものをやっている。
「いただきます」「おやすみなさい」と言ったりするのも儀式ですね。私は、結婚して2年ぐらい経ちますが、結婚前の長い独身にそういうものがほとんどない生活に慣れていて、逆に、結婚して、子どもができてからはそれがどんどんふえていくという経験をしていて、内面的な「愛」「信」、あるいは「安心・不安」というのも重要なんですけども、家族の絆とかつながりを考えたときに、そういう、ある種の型的なもの、外在性、あるいは象徴的なものが担うものがあるのではないか。家族の絆やつながりを考えるというのは、そういうものについて考えることでもあるのかなと。それだと言っているわけでは全然ないんですけども、この点について、何かちらっとコメントをいただければ。(注:質問者の方の発言は、編集部で短くまとめさせていただきました)

阿部ふく子 新潟大学准教授。東北大学大学院文学研究科博士後期課程修了。博士(文学)。近代ドイツ哲学、哲学教育研究。著書に『思弁の律動――〈新たな啓蒙〉としてのヘーゲル思弁哲学』(知泉書館、2018年)、共著に『人文学と制度』(未來社、2013年)など。
そういうことは「ヘーゲル哲学」から確認できるんですけれども、何かこう、全然本質的な答えではないかもしれませんが、今のご質問とお話を聞いていて私が思ったことがあります。私はドイツで在外研究をしていた当時に、ドイツの家庭を身近に見ていましたが、ヘーゲルの時代をはるかに越えて、ドイツは現在に至ってはすごくリベラルなので、日本のほうが、かえって儀式的なものをすごく重要視している空気があるなと、改めて思いました。
日本では、家族と一緒に御飯を食べるのが大事で、どちらかというと女性がそれを主にセッティングするような役割をして、というスタイルが今でも根強いと思います。ドイツでは、一緒に御飯を食べるというのをクリスマスなどのイベント以外では必ずしも重視してなくて、各人が、好きなときに自分で作って食べたりする。もちろんこれは一概にすべての家庭で言えることではないとは思いますが、一つの象徴的な違いだなと思いました。
あと違いを実感したのは、ドイツでは、「一緒に住まない」という選択や方向性が強いことですね。ヘーゲルも、子どもが巣立って出ていくことが家族の解体だというふうに言っているんですけれども、それが別の合理的な意味で 、現代のドイツで起きている。ドイツでは、子どもは基本的には18歳になればほぼ一様に家を出ていくし、地元にいたとしても、ひとり暮らしをする。それは、子どものみならず両親も自立を求めてのことだ。夫婦もそれを機に解消されることがあり、みんなが別々に住んで各々の生活を送るという流動的なスタイルはそんなに珍しくないと聞きました。
型や、儀式や形式というのは、自由になりたいという個々人の意志を尊重して合理化すれば、自然と撤廃されていくのだろうと思ったのですが、どうなのでしょう。それでもやはり残っている合理化することでは解決できない部分があって、それが、結婚式、葬式、一緒に御飯を食べるとか、一緒に住むとか、そういった形で表象しているのかなと思います。結婚・家族・愛というのを本当に自由な形にしたときに、それらの型が最後に残るのかどうかというのは、よくわからないですね。
質問者 ドイツでは、そういった、子どもがひとり立ちをした後に、家族が、解体されるということは、夫婦で離婚される方が多いんですか。
阿部 それぞれみたいなんですけれども、皆が皆そうではなくて、子どもが出ていく前に離婚する率も結構高いし、あと、子どもが出ていってから、夫婦で離婚はしないまま別居をして、お互いに個人主義的なスタイルで生活する人も珍しくないようです。
質問者 そうして別居した場合は、男性は、ある程度、仕事がちゃんとあって、生計が安定していると思うんですが……。
阿部 それも、多分それぞれだと思いますけれども。家計に関しては、私は詳しく見ていないからわからないのですが。
宮﨑 では、法律の専門家のお話をうかがいましょうか。
大島 恐らく、今の話には日本の法制度とドイツの法制度の違いがかかわっていると思います。日本の法制度では、離婚の際に(それまで専業主婦をしていた場合の)妻は、離婚とは別に財産分与というものを夫に請求し、夫と合意するか裁判所で審判を得なければ夫婦で協力して築いた財産を取得できないことになっています。夫が協力的でない場合にはあるべき額が分与されるかは分かりませんし、相応の審判を得るためにはお金と時間がかかります。これに対し、夫と死ぬまで添い遂げて、夫が先に遺言を残さずに死亡した場合には、相続において少なくとも遺産の半分は妻のものとされる。でも、それ以外の場合には、配偶者は保護されていないというのが日本の夫婦財産制なので、おっしゃるとおり、高齢になってから離婚したら、今の日本の高齢の女性の中には、自分が会社などで長く働いていたわけではない方も多いと思いますので、そうすると、財産的に困るという状況があると思います。
けれども、ドイツのように、離婚の際に弁護士がつき、(専業主婦の)妻が夫から一定の財産を得た上で離婚できるようにしている(ドイツの場合は婚姻中の夫婦の財産が共通になるわけではありませんが、離婚時に、それぞれが婚姻開始時に有した財産と婚姻解消時に有する財産の差額を算定し、それを夫婦間で半分ずつに分けるよう調整することとしていますし、夫婦間で収入に差がある場合、収入の少ない方が相手に対し、月々の扶養料の支払いを請求することができます)国であれば、離婚をそんなに恐れずにできるという部分があるかなとは思います。(財産面だけで見るならば)配偶者と添い遂げることに日本ほどの動機がないとも言えるかもしれません。
阿部 そうです、そうです。だから、日本も法制度を変えるべきかどうかが問題になっていると思います。
大島 それから、ちょっと戻って、先ほどの儀式の話なんですけれども、私は、日本の法律が儀式を無視していることをちょっと疑問だと思っています。フランスなどヨーロッパの国の場合の多くは、結婚の成立要件として必ず儀式を要求していて、第三者に公示するような形で儀式を大々的にやることになっています。日本の場合、社会的には儀式(結婚式)を行うことが多いかと思いますが、法律上は結婚の際に儀式を行う必要はありません。儀式の必要性について評価はいろいろあるでしょうけれど、私はやっぱり、第三者の前で結婚の意思を示すという儀式は、結婚という絆を法律上発生させる行為にとって必要なことなんじゃないかなというふうに思っています。法的に結婚すると、第三者にもその影響が及ぶ場合があるなど、先ほど私がお話しましたような特徴が生じるわけですので。日本の場合、届出だけで結婚できてしまいますが、あの届出を儀式と一緒だと言ってしまうのはやっぱりちょっと違うのではないか。
お葬式に関しても、法律では何も触れていなくて、お葬式をしなければならないとかどのような弔いをしなければならないというルールはないんですけれども、やっぱりお葬式も社会的に重要な儀式なんだと思います。亡くなった人の死を周囲の人たちが受け入れるために。
ただ、日本の今の法律がこの二つの儀式を扱えていないのは、そこに法律が手出しをできなかったという部分もあるんだと思います。昔はこれらは親族が行っていて、家単位で行うことであって、そこに国(法律)が手を出していくことができなかったという側面があるんだろうなと思います。
藤田 皆さん、今日参加していただいて、少し感じていただけたかなと思うんですけれども、こうやって家族の絆について考えてみるというのも一つの哲学のやり方なんです。もちろん他にもいろいろなやり方があるわけですが、一番最初の阿部さんのお言葉で、自分の実感から始まらないとダメだよねというのは、僕にはものすごく心強いというか、やっぱり哲学なり法学というのはそういう実感の部分とどこかで結びついていないといけないし――もちろんその実感が抽象的な形で出てきても構わないわけです――、実際今日のシンポジウムも私たちなりにそれを実践してみせたのだと思っています。
今日はいろいろ中途半端なところや至らないところもたくさんあったとは思いますが、トライしてみたというところでお許しいただければと思います。本当に長い時間おつき合いいただきまして、どうもありがとうございました。(拍手)
(おわり)
*宮野真生子さんは2019年7月22日にご逝去されました。心よりお悔やみ申し上げます。さまざまな事情が重なり、公開は今(2019年12月)になってしまいましたが、宮野さんには既にご校正をしていただいていました。登壇者、編集部ともに、この記事を通し、宮野さんの残された言葉と思想にふれる方が一人でも多くなることを願っています。
*《ジェンダー対話シリーズ》第6~8回は、2016年11月18日に新潟大学 五十嵐キャンパスで行われた「家族の「きずな」を哲学する──私たちをつなぐものはどこにある?」(登壇者:阿部ふく子、大島梨沙、宮﨑裕助、藤田尚志、宮野真生子、主催:新潟哲学思想セミナー(NiiPhiS))を元にしています。なお、本イベントの書き起こしは、科学研究費基盤研究(C)「フランス現代哲学における主体・人格概念の分析(愛・性・家族の解体と再構築を軸に)」研究課題番号:16K02151(研究代表者:藤田尚志)の助成を受けています。また、ウェブでの掲載にあたり、ナカニシヤ出版様のご協力を得ました。記して感謝申し上げます。
【登壇者プロフィール】
阿部ふく子 (あべ・ふくこ)新潟大学准教授。東北大学大学院文学研究科博士後期課程修了。博士(文学)。近代ドイツ哲学、哲学教育研究。著書に『思弁の律動――〈新たな啓蒙〉としてのヘーゲル思弁哲学』(知泉書館、2018年)、共著に『人文学と制度』(未來社、2013年)など。
宮﨑裕助 (みやざき・ゆうすけ)新潟大学准教授。東京大学大学院総合文化研究科博士課程修了。哲学、現代思想。著書に『判断と崇高──カント美学のポリティクス』(知泉書館、2009年)、『ジャック・デリダ──死後の生を与える』(岩波書店、近刊)( 本ウェブに掲載されたデリダの家族論の完全版が、近刊のこのデリダ論に収録されている。ぜひこちらもご覧いただきたい)など。
大島梨沙 (おおしま・りさ)新潟大学准教授。北海道大学大学院法学研究科博士課程修了。民法学。共編著書に、『性的マイノリティ判例解説』(信山社、2011年)。共著に、『家族研究の最前線②出会いと結婚』(日本経済評論社、2017年)など。
藤田尚志 (ふじた・ひさし)九州産業大学教授。博士(哲学、リール第三大学)。フランス近現代思想、アンリ・ベルクソン研究。編著に、シリーズ『愛・性・家族の哲学』1~3巻(宮野真生子と共編、ナカニシヤ出版、2016年)。現在、「けいそうビブリオフィル」にて、『ベルクソン 反時代的哲学』を連載中(近刊)。
宮野真生子 (みやの・まきこ)福岡大学准教授。京都大学大学院文学研究科博士課程単位取得満期退学。日本哲学史、九鬼周造研究。著書に『なぜ、私たちは恋をして生きるのか−−「出会い」と「恋愛」の近代日本精神史』(ナカニシヤ出版、2014年)、『急に具合が悪くなる』(磯野真穂と共著、晶文社、2019年)、『出逢いのあわい――九鬼周造における存在論理学と邂逅の倫理』(堀之内出版、2019年)。編著に、シリーズ『愛・性・家族の哲学』1~3巻(藤田尚志と共編、ナカニシヤ出版、2016年)など。2019没。
》》ジェンダー対話シリーズ・バックナンバー《《 【これまでの一覧は 》こちら《 】
第7回 家族の「きずな」を哲学する──私たちをつなぐものはどこにある?(中)
第6回 家族の「きずな」を哲学する──私たちをつなぐものはどこにある?(上)
第5回 愛・性・家族のポリティクス(後篇)
第4回 愛・性・家族のポリティクス(前篇)
第3回 息子の『生きづらさ』? 男性介護に見る『男らしさ』の病
第2回 性 ――規範と欲望のアクチュアリティ(後篇)
第1回 性 ――規範と欲望のアクチュアリティ(前篇)