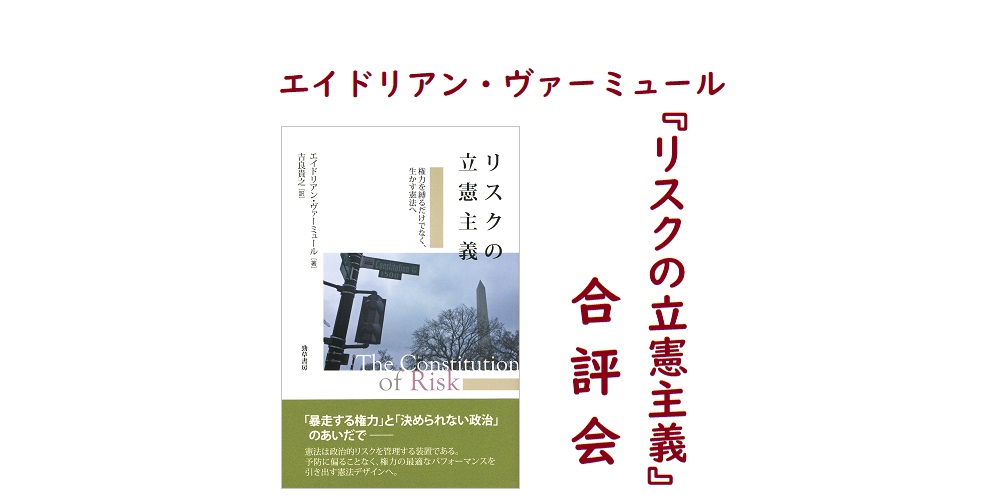
■憲法学とその目的:川鍋健(憲法学)(注1)
1 憲法の原理について
本書は、憲法の制定や、解釈にあたりリスク分析を導入し、「憲法、そして公法は一般に、政治的リスクを規制・管理する装置として最もよく理解される」(2頁、強調省略)、と主張する。ここで検討対象であるリスクとは、2階のリスクと呼ぶものである。制度設計(憲法の場合には権限配分)によって生じる悪い政治的結果の可能性のことであり、授権された機関がその権限に基づいて対処するリスクを1階のリスクと呼ぶのと対照している(4−5頁)。
2階のリスクへ対応するために著者が提唱するのは、最適化立憲主義である。「問題になりうるすべての政治的リスクをトレードオフ関係に置き、いかなる特定の種類の政治的リスクにも系統的な歪みやバイアスをかけることなく、当該状況に応じた適切な重みを与える」(14頁)。
この文脈で批判されるのが、予防的立憲主義(予防的アプローチ・マキシミン立憲主義)である。「憲法ルールは何よりもまず、公的な活動から結果的に生じるリスクに対し、予防策を強化すべきだというもの」(15頁)とされる。独裁、圧政、汚職、公職者の自己取引、少数者への権利侵害などの重大な政治的害悪を排除することが目的である。これは、従来的な立憲主義を想定しているようにも思われる。その極端なものとしてマキシミン立憲主義があげられる。政治におけるファットテール・リスクを回避するために、それが起こらないように予防的に対応するものとされる。
本書では、予防的立憲主義を採用すると、かえって害悪を招来する可能性が高くなりうること(第3章)、そして、自己裁定禁止原則など憲法原理の適用も、状況に応じてその緩厳は異なるべきこと(第4章以下)を論じている。
ここで問われるべきは、予防的立憲主義を採用すると、害悪を招来する可能性は高くなるのか、ということである。確かに、政治的リスクへの憲法典による予防が、起草者の意図通りには十分に機能しない可能性はある。他方で、比較憲法的には、ドイツ憲法は、政治的リスクの予防(闘う民主制の採用とナチス再来の阻止など)によって立憲主義が成功した例に見える。著者の指摘の重要さの一方で、予防アプローチの抱える問題の重大性は、相対的かもしれない。
加えて、予防的立憲主義は、事前に定めた憲法原理の厳格な適用によって政治的リスクに対応するわけではないのではないか。予防的立憲主義の「頼みの綱」(29頁)とされる自己裁定禁止原則の例外の多さの例証(第4章参照)は、最適化立憲主義の想定するリスクとその実現可能性に着目した柔軟な対応の望ましさを示したというより、そもそも著者の想定する予防的立憲主義であっても、憲法原理の適用に緩厳を認めていることを示しているかにみえる。
言論の自由についても言及がある(91頁以下、98頁以下、127頁以下など)が、この領域がその典型であるように思われる。定義づけ衡量(名誉毀損、わいせつ、煽動、営利表現への規制の容認)など、合衆国憲法修正1条で言論の自由への侵害を予防し、その保障が及ばない範囲が事後的に画定されるが、そのことを予防的立憲主義は排除しない。なぜなら、特に憲法典制定を典型として、憲法原理を抽象的な文言で定め、その具体的な意味の形成については後世に委ねることを認めるからである(注2)。
それゆえ、読み方によっては、予防的立憲主義と著者のいう最適化立憲主義との差異はそれほど大きくないようにも見える。しかし、著者が予防的立憲主義を攻撃することに含意しているのは、事前に何らかの憲法原理を定めることそのものの敵視であるかもしれない。もし著者の主張をラディカルに読むならば、憲法原理(この場合、憲法典制定も含む)を事前に定めることによって人権保障を行うことに対する挑戦、であるかに見えるからである。
現代アメリカ憲法学、ということだけ考えると、このような発想は珍しくはない。いわゆる生ける憲法論(living constitutionalism)の主張は、現代的な人権保障を実現するためには、必ずしも憲法典にこだわる必要はない、というものである(注3)。他方で、著者の議論はこの議論とも違って見える。なぜなら生ける憲法論では、①ある種の進歩史観に立って、歴史の過程に伴って憲法原理が洗練され、形成されることを前提とし、②誰か(裁判官、あるいは主権者人民)が憲法原理をそれとして決定するからである。
つまり、既存の憲法典にこだわる必要はないが、憲法(裁判官の形成する人権保障法理、あるいは主権者人民の意思)はあることになる。それに対して、著者の最適化立憲主義は、最適化が憲法だと答えることになるように思うが、評者はこの点について懐疑的である。
2 誰が、どのように、憲法の原理の採用、適用の緩厳を認定するか
最適化を憲法とするのが著者の考えであるとして、まず疑問に思うのは、人権保障のベースラインが、いかなる人権についても、アドホックに決定されてしまい、立憲主義を否定してしまうのではないかという点である。特に懸念されるのは、表現の自由、社会保障である。前者は、表現内容について少しでも社会に害悪を及ぼすと政府が考えた場合、規制を認めてしまう可能性がある(注4)。後者については、国家の財政状況により、社会保障制度をいかようにも縮小しても良いということになるのではないか(注5)。
次に、最適化を憲法とすることによって、著者は立憲主義ばかりではなく、民主主義を否定するのではないか、という疑問が浮かぶ。リスク分析という手法は一般の人々にとってわかりにくい。しかも、そのような手法を通じて導出される最適化は、およそ一般の人々がなしうるわざではない。それゆえ、そのような営みに携わることができる有能な人間のみが「憲法ルールの作成者(constitutional rulemaker)」となりうる、ということにならないだろうか。
もし、これが、憲法原理の適用の緩厳の問題としてのみ語られるならば、ある程度理解可能ではある。判例法理の形成や、行政の執行にあたっての法令解釈は、憲法原理の具体化であり、一定の自律性の下に形成されうるからである。他方で、そのような解釈は、法令解釈を終局的に行う司法権、あるいは司法権を授権している主権者人民によって判断を覆されうる、というのが従来型の憲法論と思われる。
しかし、著者の問題設定は、「憲法上のリスクを規制するのは(中略)新しい憲法秩序を設立した憲法起草者や設計者だけなのか。それとも既に設立され、機能している憲法システムの中で活動する公職者たちなど、他のアクターも含まれるのか」(6頁、強調引用者)というものである。
もちろん、ここで「憲法起草者や設計者」というのは、現実に草案を執筆する人のことだけを念頭に置いているかもしれない(第3章でジェームス・マディスン(James Madison)の多数者の専制を憲法で抑制する議論の功罪を扱っていることを参照)。しかし、もしこの主張が、憲法起草者と憲法内の主体とを同一視し、リスク分析さえすれば憲法内の主体に憲法起草者と同様の憲法原理の形成が可能である、ということであれば、問題がある。リスク分析に関する説明責任が十分に果たされるか、恣意的な分析がなされないかをチェックする必要があるからである。
3 翻訳とその目的
評者が観察する限り、本書は重要な示唆も含むものではあるが、それなりに問題含みの議論が展開されているのではないか、と感じる。それにもかかわらず、そのような議論をあえて翻訳する意義とはなにか、ということを考える必要があるのではないか。
まず、重要な前提として、自分が面白いと思えば、第一義的な理由は十分である。その一方で、それを翻訳すると、学界や社会にどのような影響を与えうるのか、を考える必要がある(注6)。その観点から、本書を訳した目的が気になる。
訳者は、本書を「権限配分にあたって一定の『スタイル』を持つことを戒めているのであり、執行権・行政権への権限集中を原理的に主張するものではない」が、「従来の司法中心主義的な法理論から脱却し、また立法府の民主的正統性を強調する近時の議論からも距離を取り、執行権・行政権のパフォーマンスにとっての制度に関心をシフトさせている」と整理している(260頁)が、この主張は、アメリカでも問題含みである印象がある(注7)が、日本憲法に適用可能性がある議論と考えた場合も、問題がある印象を持つ。
最も懸念されるのは、いわゆる緊急事態に関してである。人権制約を正当化する緊急事態条項がなくとも、政府の緊急事態の認定による不当に厳しい人権制約の正当化が、著者の議論からは可能ではないか。どのような人権について制約し、どの程度、どれくらいの期間にわたるのか、憲法あるいは法律の慎重な規律がないまま、行政府にリスクを判断するリソースが揃っているので、規制権限を委ねることも、著者の議論は正当化可能ではないか(注8)。
多様な考え方を日本の研究者として日本語で紹介することの価値は否定されないが、その紹介した考え方が都合よく時の権力に使われる可能性があることも考慮する必要がある。この観点から興味深いのは、ブルース・アッカマン(川岸令和、木下智史、阪口正二郎、谷澤正嗣監訳)『アメリカ憲法理論史:その基底にあるもの』、北大路書房、2020年(注9)に寄せられたアッカマンによる「日本語版への序文」(iii-xv頁)である。翻訳の影響ということにどれだけ自覚的だったかはわからないが、自らの議論自体は選挙が憲法改正国民投票の代替手段となりうる、という合衆国憲法史叙述である一方で、「十分かつ自由な討論を経て一般民衆が冷静に問題を検討し、一連の選挙の結果、国として憲法改正という決定を成すことが認められるとしても、深夜の暴力的な審議において、首相が憲法に反する強引な権力行使を行なった結果として国家の平和へのコミットメントが否定されるのを認めることにはならない」(xiv頁)という序文がつくことで、自らの議論が、選挙を通じてのインフォーマルな憲法変動が疑われる日本の政治状況を追認する(注10)ことを否定している。
本書翻訳についていえば、どのような影響があると見立て(なかっ)たか、という問題があるように思われる。
(注1)本稿は、2020年7月26日にオンラインで開催された「『リスクの立憲主義』オンライン合評会」においてパネリストとして書評報告したものを論文形式にまとめなおしたものである。それにあたっては、パネリストの岡田順太、清水潤、吉良貴之各氏及び参加者との議論を参照した。記してお礼申し上げる。
(注2)ここで念頭に置いているのは、著者が大統領権力の文脈で予防的立憲主義の議論として扱ったブルース・アッカマンの人民主権論(Bruce A. Ackerman, We the People, 3 vols., Harvard U. Pr., 1991, 1998, 2014. 第1巻の邦訳については本稿3で後述)のほか、法哲学者ロナルド・ドウォーキン(Ronald Dworkin)の権利論(Ronald Dworkin, Taking Rights Seriously, Harvard U. Pr., 1977. 邦訳として、小林公、木下毅、野坂泰司訳『権利論』、増補版、木鐸社、2003年;小林公訳『権利論II』、木鐸社、2001年)、アッカマンと同じく人民主権論を主張する憲法学におけるイェール学派の一人であり、憲法典制定と現代社会における柔軟な人権保障(後述する生ける憲法living constitution)をめぐる議論が両立可能だとする生ける原意主義(living originalism)を主張したジャック・バルキン(Jack Balkin)の議論(Jack Balkin, Living Originalism, Harvard U. Pr., 2011)などである。参照、川鍋健『人民主権と違憲審査:イェール学派の憲法学から』、一橋大学(博士号取得論文)、2019年。また、アッカマンやバルキンの議論の淵源となっている憲法理論を展開した、チャールズ・L・ブラックの議論について、参照、川鍋健「新たな憲法解釈の誕生:チャールズ・L・ブラックの議論から」、一橋法学19巻2号、2020年、189頁以下。
(注3)David A. Strauss, The Living Constitution, Oxford U. Pr., 2010; Ackerman, supra note 2, especially vol. 3.
(注4)ニュー・ディールに先立つロックナー期の精神的自由に関する判例法理にこのような傾向を認めるものとして、清水潤「ロックナー期憲法判例における『残余としての自由』、一橋法学10巻1号、2011年、183頁以下、241頁以下。
(注5)川鍋、前掲注2、「新たな憲法解釈の誕生」では、ブラックの生存権論とそれが必ずしもアメリカ憲法理論では受容されていないことを紹介している。彼は、合衆国憲法修正9条の規定から生存権を導くことができるとし、連邦議会の議員歳費決定権限の類推解釈から、一般の人々が生きていくために必要な価額を決定できるので、政府が生活保障制度を用意しなかったり、不十分な給付しか行わない場合、それは憲法違反にとわれるという。See also, Charles L. Black, Jr.(with a New Foreword by Philipp Chase Bobbitt), A New Birth of Freedom, Yale U. Pr., 1999.
なお、違憲審査制に関してブラックがしばしば法的解決の結論の妥当性を重視するリアリズム法学(legal realism)と整理されるのに対比して、権限配分に基づいてその矩を超えない限りで法的判断を下すことを重視するものとして語られるプロセス法学(legal process)の観点を日本の違憲審査制に導入し、生存権に関する判例についても論じた議論として、参照、山本龍彦「最高裁のなかの〈アメリカ〉—憲法的二次ルールとしての権限配分」、石川健治、山本龍彦、泉徳治編『憲法訴訟の十字路:実務と学知のあいだ』、弘文堂、2019年、169頁以下。
(注6)「一旦安定したポストについて業績作成にそれほどこだわる必要がなくなった学者ならば、自分の研究の独創性を過大評価せずに、自分は平凡な論文を書くよりも重要な本の翻訳をした方がよいのではないかと真剣に自問すべき」とまでいう自信はないが、「日本語で読めるようになれば日本の学界や読者層に大いに裨益する」という考え方には共感を持っている。参照、森村進「私の歩んできた法哲学研究の道」、一橋法学19巻1号、2020年、5頁以下、20頁。
(注7)大統領の自らに対する恩赦を正当化する議論について、特にそう思われる。
(注8)もっとも、現状の日本政府の対応には、日本国憲法上営業の自由や移動の自由に対する制約は法律によってもできないと装うことによって、日本国憲法に対して危機に対応できない憲法である印象を国民に植え付け、憲法改正の機運高揚につなげよう、という意図を感じないではない。実際は、休業命令や、感染症感染拡大の防止を目的とした移動の自由の最低限の制限は、正当な立法目的と、目的達成手段との合理的関連性があるものとして、法律により実現可能と思われる。
(注9)Ackerman, supra note i, vol. 1の翻訳。
(注10)山本龍彦「アメリカにおける『人民主権』論と憲法変動」、全国憲法研究会編『憲法問題28』、三省堂、2017年、45頁以下。
※本稿はJSPS科研費JP19K23152の助成を受けたものである。
■スタイルなき立憲主義という陥穽:清水潤(憲法学)
1 はじめに
エイドリアン・ヴァーミュール(吉良貴之訳)『リスクの立憲主義』(勁草書房、2019年)(以下、本書)は、その紙幅やサイズは、学術書としてはコンパクトな部類に入るといってよいであろう。しかし、本書は、「憲法とは何か」という根源的な問題に対して、ヴァーミュール(以下、著者)独自の大胆な解答が提示されており、その扱っているテーマは極めて壮大なものである。そして、著者の憲法観は、我が国の憲法学に馴染んだ読者にとっては、非常に挑戦的なものとして理解される可能性が大である。評者も、著者の憲法観に対してはおおむね警戒的である。
結論を先取りすれば、著者の憲法理論には、権力の濫用の経験に基づいて自由主義的に積み上げられてきた様々な憲法上の諸原則を骨抜きにする、あるいはより控えめに言っても、その重要性を相対化する危険性がある。例えば、「無罪推定」「表現の自由の優越的地位」といった諸原則が今なお遵守するに値するかを再検討に付すことに、法律家はある種の直観的な躊躇を覚えるであろう。しかし、ヴァーミュールが本書で我々に求めることは、まさにそのような作業である。
以下、本書の概要を簡単に要約したのち、本書の議論にいかなる内在的な問題が含まれているかを検討する。
2 憲法は政治的リスクの管理手段か
本書の中心的な主張は二つある。それは、「憲法によるルール作成は、政治的リスクを規制・管理する手段として理解するのが最も良い」ということ(注1)、そして「最適化立憲主義」と著者自ら名付ける憲法構想が、「予防的立憲主義」という憲法構想よりも優れていることを示すことである(1頁)。
「憲法によるルール作成は、政治的リスクの管理手段として理解するのが良い」とはどのような意味だろうか。著者は、環境や市場、テクノロジーなどから発生するリスクを一階 のリスクと呼ぶ。伝染病や災害など、我々が通常リスクとして認識しているのはこのようなリスクだろう。著者によれば、これらの一階のリスクとは区別される二階のリスクと呼ばれるリスクがある。それが政治的リスクであり、制度設計や公職者の権力行使に伴って発生するリスクである。例えば役所の機能不全、汚職、クーデタなどである(2‐5頁)。著者は、憲法とはかかる二階のリスク(政治的リスク)を適切にコントロールすることに役割があるというのである。やや分かりにくいが、具体的に言えば以下のようなことである。公務員の給与を下げすぎると汚職が多発するかもしれない。そこで公務員の給与について憲法上の規定を設ければ(注2)、そのようなリスクの発生が防止できるかもしれない、というようなことである。
このような憲法観自体が、日本の憲法学にとってそれほど自明なものではない。教科書的には、憲法は人権を保障し個人の尊厳を擁護することを目的としている。あるいは、プロセス憲法観、共和主義、国民主権などの、民主主義的要素を重視する憲法理論は、戦後を通して一定の支持を得てきた。しかし「憲法はリスク管理のための手段である」との思想が強い支持を得たことは恐らくなさそうである。確かに、憲法にそのような側面があること自体は、誰もが認めることであろう。しかしリスク管理を憲法の最大の目的とみなす点で、著者の議論は際立っているということは、最初に指摘されてよい点である。
このことの帰結は重大である。政治的リスクの定義次第では、人権や民主主義といった従来的な理念が全く重視されない憲法さえ、擁護可能になりうる。例えば、選挙権の平等な保護は、衆愚政治というリスクを常時発生させる。しかし、現在の憲法学が前提としている、投票価値の平等の価値理念の下では、平等選挙のメリットと衆愚政治のリスクを天秤にかけることは許されないはずである。
憲法を政治的リスクの管理手段として理解する本書において、平等選挙によって国民の厚生に壊滅的な打撃を与える帰結が発生する場合には、制限選挙や等級選挙のほうが望ましい、という結論が原理的には排除されない。このことを著者はどのように考えるのだろうか。リスクの計算や定義次第で、憲法が擁護しようとする価値が雲散霧消してしまう危険性がある。かかる危険性を排除するという意味で、憲法を一定の価値理念に奉仕する法として理解することにはなおメリットがあるはずである(注3)。そして、かかる立場からすれば、「リスク管理」という一見技術的な概念によって憲法を設計することはできず、価値理念の擁護や分析なくして憲法論は成り立たないことになる。
もっとも、本書では、憲法は政治的リスクの管理手段として理解するのが最も適切であるとの憲法理論については、詳細な議論や擁護はほとんどない。むしろ、このテーゼを前提として、いかなるアプローチがリスクを最も適切に管理できるかの議論が本書の大半を占める。そこで、本稿でも、本書の第一の主張についてはこの程度の確認を行うに留める。
3 「最適化立憲主義」の「予防的立憲主義」に対する優位
本書の真に重要な主張は、「最適化立憲主義」が「予防的立憲主義」よりも優れた憲法理論である、という点にある。最適化立憲主義とは、「問題になりうるすべての政治的リスクをトレードオフ関係に置き、いかなる特定の種類の政治的リスクにも系統的な歪みやバイアスをかけることなく、当該状況に応じた適切な重みを与える」(14頁)ような憲法論を指す。それに対し、予防的立憲主義とは、「公的な活動から結果的に害悪が生じるリスクに対し、予防策を強化すべき」(15頁)とする憲法論である。
この両者の区別を、表現の自由の規制立法に対するアプローチの違いから検討する。 予防的立憲主義によれば、政府に規制権限を与えることは思想統制のリスクを生じさせるので、表現の自由は厳格に保護されなければならない。その一方で、当該の表現を許容することで発生しうるリスクには無頓着となる。例えば、戦時中の反戦表現や、徴兵拒否を煽動する表現を政府は規制したいとする。予防的立憲主義者は、かかる表現規制がもたらしうる思想統制の危険や、政府に対する批判能力の喪失などの、表現規制に内在するリスクにのみ着目する。それに対して、最適化立憲主義者は、当該表現を許すことで、戦争遂行が困難になる危険や、戦争に負けることで民主主義体制が転覆するリスクなどを含めた、全てのリスクを考慮した上で、表現規制が憲法上可能かどうかを検討すべきと考える。最適化立憲主義の立場からは、Dennis判決における(注4)、表現を許容した場合のリスクと禁止した場合のリスクをフラットに天秤にかける総合考慮的なアプローチは、表現の自由は原則として規制されるべきでないとするBrandenburg判決よりも優れたアプローチを採用しているのである(56-57頁)(注5)。
同様に、著者は、「合理的な疑いの基準」は、冤罪のリスクにのみ着目した予防的アプローチに基礎を置くと批判している(60頁)。著者によれば、真犯人を逃すことで発生する治安上のリスクも併せて考慮しなければ、有罪判決を下す際の適切な証明の程度は決定できない。冤罪のリスクと、治安上のリスクを総合的に考慮し、全てのリスクを計算に入れる最適化アプローチが採用されるべきなのである。
もっとも、著者は、この二つのアプローチでは最適化立憲主義が優れていると述べるだけで、特定の憲法上の準則を擁護しているわけではない。全てのリスクを考慮に入れたうえで、なおBrandenburg判決のような厳格な審査基準とか、合理的な疑いの基準が維持される可能性もあるという(112-113頁)(注6)。
その意味で、予防的立憲主義に対する最適化立憲主義の優位とは、せんじ詰めれば、「特定のリスクにのみ着目すべきではなく、全てのリスクを考慮にいれて憲法ルールは作成されるべきだ」というある種、陳腐な命題に帰着する。著者も言うように、「関連する全てのリスクを重みづけすべきだということに、誰が原理的に反対するのだろうか?」(113頁)。いわゆる「人権派」の刑事弁護人でさえ、冤罪のリスクは何が何でも最小化されるべきであるという主張よりは、真犯人を釈放してしまうリスクを考慮に入れてもなお、冤罪のリスクの方が重いという論法の方を好ましいと感じるだろう。では、本書の主張は極めて常識的すぎて改めて述べるまでもないようなものなのか?
そうではないと著者はいう。著者は、ある種のリスクにのみ固執する強迫観念を戒める効用があるとして、最適化立憲主義の意義を強調する(114頁)。そして、個別的で文脈的に考えて憲法ルールを作成すべきこと、事実に開かれた考察をなすべきこと、極端を避けプラグマティックに考えるべきこと、柔軟性を維持し、成熟しバランスの取れたリスク計算をなすべきこと、などの教訓を、憲法ルール作成者に対してもたらすという理論的意義があるという(248-250頁)。
4 最適化立憲主義は陳腐な主張なのか
このように、筆者の提唱する最適化立憲主義は、陳腐で常識的なものであり、原理的にはだれも反対しないものであるようにも思える。確かに、最適化立憲主義は、一見したところは無害かつ陳腐であるかもしれない。しかし、最適化立憲主義の理論には、自由主義的な憲法論に対する執拗な批判と攻撃が含まれている。著者自身が適切に指摘するように、予防的立憲主義の基底には、権力に対する懐疑から出発して理論を組み立てようとする自由主義の哲学がある(16頁)。著者は、権力濫用の可能性を極度に恐怖する「リバタリアン・パニック」に予防的立憲主義が陥っていると批判する(111頁)。しかし、そのような権力への懐疑的態度をパニックとみなすのか、正常とみなすのかが最大の問題なのである。
著者は、憲法ルール作成をチェスに例える。偉大なチェスプレイヤーは「スタイルを持たない」。手癖や思い込み、抽象的で一般的な選り好みを避け、全ての可能性を計算して最善手を選ぶ。それに対し、平凡なプレイヤーは、粗いヒューリスティックや一般的方法に頼る(251頁)。確かにその通りで、藤井(聡太)将棋には「定跡がない」とも言われる。居玉は避けよ、とか、玉飛接近すべからず、とか、そういった一般的ルールを無視した将棋を彼は指す。それに対し、アマチュアは、そのような格言や定跡通りにプレイした方が、「すべての可能性を考慮に入れる」よりも遥かにマシな結果になることが多いだろう。その意味で「スタイル」とは、誤りを犯しやすい下手なプレイヤーに対する戒めに過ぎず、全ての手を読み切れるほどの手練れには不要なものである。
問題は、憲法ルールを作成する制憲者、裁判官、立法者は、そのようなチェスや将棋の名プレイヤーなのかどうかである。彼らに、「全ての可能性を適切に考慮して最善のルールを作成してください」というスタンスで臨むのか、それとも「表現の自由の優越的地位」や「冤罪の防止」などのような「一般的ルール」「粗いヒューリスティック」を押し付けることで、最善には程遠いにしてもよりマシな結果が得られると考えるのか。自由主義者は後者の立場を主張して譲らないのに対し、著者は前者の立場に立つ。その意味で、著者の擁護する最適化立憲主義は、陳腐な主張ではありえず、非常に先鋭な価値判断、つまり自由主義の拒否に由来するものと評価するのが適切であろう。著者からはパニックにしか見えない精神状態が、リバタリアンからは平静に見える。それはどのような規範的立場からものを見るかという違いに他ならない。
最適化立憲主義が反自由主義的な本質を内在させているという読みは、必ずしも的外れではないことが、著者の他の著作からも推察できる。著者は最近、「共通善の憲法論」なる理論を提唱している(注7)。著者は、保守派の戦略としての原意主義やリバタリアニズムを批判し、政府は強制的手段によって(場合によっては被治者の意思に反して)共通善を保全すべきと主張している。「憲法秩序の中心的な目的はよい統治の促進であって,それ自体を目的として「自由を守る」ことではない。権力に対する制約は共通善に寄与する限りでの,あくまで派生的な善なのである」(注8)として、例えばワクチンの強制的接種を拒否する憲法上の権利は存在しないと述べている。
また、著者は、カソリシズムの立場から、カソリック的価値観と国家を統合すべきとし、政教分離を批判している。具体的には、洗礼を受けたカソリック信者(confirmed catholic)に移民の優先権を与える政策を提唱している(注9)。勿論、本書の中にこのような主張が登場するわけではなく、最適化立憲主義の是非とこれらの主張は、さしあたりは区別して論じるべきものではある。しかし、本書が有する外観上の価値中立的な物言いの背後には、自由主義に対する挑戦があるという評者の指摘と平仄が合うものではあろう。
(注1)ここでいう憲法ルール作成は、制憲のみならず、判例法による違憲審査基準の定立などを含む(6頁)。著者は憲法と公法一般を並列的に扱っており、日本では法律レベルで行われている選挙制度や政党制度の組み立てなどの、実質的意味での憲法のルール作成も本書の射程から排除されないと思われる(2頁)。
(注2)例えば日本国憲法では49条、79条6項、80条2項にこの種の規定がある。そしてこの種の規定は、ある種の政治的リスク(例えば司法の独立に対する侵害)を回避するためのルールであることも自明であろう。
(注3)訳者の吉良氏から、一定の価値理念をリスク計算から除外してアプリオリに擁護することは思考停止ではないかとの指摘を受けた。しかし、例えば人種的平等のように、それを保障することがリスクを発生させるとしても、リスク計算を理由として覆してはならない権利があると想定することも可能である。このような立場の正当化には勿論哲学的な論証が必要であろう。しかし、ヴァーミュールはかかる権利の切り札性を真剣に受け取っていないかに見える。
(注4)Dennis v. United States, 341 U.S. 494 (1951). 政府転覆を唱道することを処罰する連邦法違反として、共産主義関係の本について教えていた共産党員のEugene Dennisが起訴された事例。合衆国最高裁は、政府が転覆されるリスクと表現の自由を衡量したうえで、処罰を合憲と判示した。本件については、ヴァーミュール以外からも、Dennis判決の誤りは比較衡量テストを用いたこと自体ではなく、衡量を誤り政府転覆の危険性を実際よりも重く受け止めすぎたことにある、との批評がある。Wilson Huhn, Scienter, Causation, and Harm in Freedom of Expression Analysis, 13 WM. & MARY BILL RTS. J. 125, 166 (2004). しかし、衡量テスト自体が表現の自由抑圧的に作用することを重視し、衡量テスト自体を拒否するのが一般的な見解と思われる。著名な憲法学者であるErwin Chemerinskyが、「Dennis判決の多数意見に与した裁判官たちは、害悪(政府転覆という害、清水注)があまりにも大きいので、そのリスクのいかなる増加も許容できないと信じていた。しかし、歴史的な後知恵からすれば特にそうなのだが、Dennis判決は大きく誤っていると思われる。今では多くの大学の通常の授業で読まれている四つの本(マルクス、エンゲルス、レーニン、スターリンの著作、清水注)について読んだり話したりしただけで処罰されたのである」ERWIN CHEMERINSKY, CONSTITUTIONAL LAW, PRINCIPLES AND POLICIES 1047 (5th ed. 2015). 本件が示唆するように、政府転覆というリスクはあまりにも大きく、恐怖を惹起するのに対し、共産主義は不人気な見解でありその抑圧は容易にされがちである。衡量テストを用いることはこのような危険性を排除できない。See Geffrey R. Stone, When Is Speech That Causes Unlawful Conduct Protected by Freedom of Speech? The Case of the First Amendment?, in THE OXFORD HANDBOOK OF FREEDOM OF SPEECH 340, 394 (Adrienne Stone and Frederick Schauer ed., 2021).
(注5)Brandenburg v. Ohio, 395 U.S. 444 (1969). 人種差別団体の指導者が、政府を転覆する可能性を示唆したとして起訴された事例。合衆国最高裁は、暴力や違法行為の唱道は、それが差し迫った違法行為(imminent lawless action)を煽動することに向けられていて、かつそのような違法行為が実際に煽動されたり行われたりする可能性がない限り処罰できないとした。違法行為の唱道に憲法上の厳格な制約を設けたこのBrandenburgテストは、煽動表現の保護基準を示したものとして今日高く評価されている。Chemerinsky, supra note 4, at 1049.
つまりヴァーミュールは、一般に高い評価を受けるBrandenburg判決よりも、一般に否定的な評価を受けるDennis判決を支持しているのである。評者は修正1条論の専門家ではないが、これが非常に挑発的な態度であることは明らかであろうと思われる。
(注6)では、「全てのリスクを考慮に入れる」とどのような準則が出てくるのか。全てのリスクを考慮に入れて憲法ルールを作成するなどというのは人間離れした所業であろう。特に問題となるのは司法審査の局面である。裁判官による憲法解釈が、最適化立憲主義に従うべきだとした場合、裸の利益衡量とか、目盛りのない物差しとか言われる、単なる価値判断を偽装するための「総合的利益衡量」が行われる可能性が高そうである。率直に言って、著者の最適化立憲主義なるものが、総合的利益衡量とどのように違うのか判然としなかった。
(注7)Adrian Vermeule, Beyond Originalism: The dominant conservative philosophy for interpreting the Constitution has served its purpose, and scholars ought to develop a more moral framework, https://www.theatlantic.com/ideas/archive/2020/03/common-good-constitutionalism/609037/
(注8)Ibid.
(注9)Adrian Vermerule, A Principle of Immigration Policy, https://mirrorofjustice.blogs.com/mirrorofjustice/2019/07/a-principle-of-immigration-priority-.html
後編は次週公開いたします。お楽しみに。[編集部]
■報告者紹介■
川鍋健(かわなべ・たけし)
早稲田大学政治経済学術院講師(任期付)
専門:憲法、比較憲法、アメリカ憲法
主な論文に、「アメリカ憲法学における人民主権論と日本憲法学への示唆」、憲法研究8号(2021年)、155頁以下;「人民の、人民による、人民のための憲法:アキル・リード・アマールの憲法論から」、一橋法学17巻2号(2018年)、435頁以下(第11回石橋湛山新人賞受賞)など。
Website: https://researchmap.jp/TakeshiKawanabe?lang=ja
清水潤(しみず・じゅん)
白鴎大学法学部准教授
専門:憲法、アメリカ法
主な論文に、「コモン・ロー、憲法、自由(1)~(8・完)」(中央ロー・ジャーナル14巻1号~15巻4号、2017-2019年)など。
Website: https://researchmap.jp/jshim
岡田順太(おかだ・じゅんた)
獨協大学法学部教授
専門:憲法学
著書に『関係性の憲法理論』(丸善プラネット、2015年)、『戦後日本憲政史講義−もうひとつの戦後史』(共著、法律文化社、2020年)、翻訳にヤニブ・ロズナイ『憲法改正が「違憲」になるとき』(共訳、弘文堂、2021年)など。
吉良貴之(きら・たかゆき)
宇都宮共和大学専任講師
専門:法哲学
主な論文に「行政国家と行政立憲主義の法原理」(『法の理論』39号、2021年)、「戦争と責任:歴史的不正義と主体性」(野上元・佐藤文香ほか編『「戦争と社会」という問い』(岩波書店、2021年)など。翻訳にキャス・サンスティーン『入門・行動科学と公共政策』(勁草書房、2021年)、シーラ・ジャサノフ『法廷に立つ科学』(監訳、勁草書房、2015年)など。
Website: https://jj57010.web.fc2.com
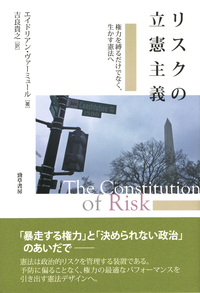 好評発売中!
好評発売中!エイドリアン・ヴァーミュール 著/吉良貴之 訳
『リスクの立憲主義 権力を縛るだけでなく、生かす憲法へ』https://www.keisoshobo.co.jp/book/b491626.html
ISBN:978-4-326-55086-9 四六判・328ページ 価格3,850円(税込)
憲法とは政治的リスクを規制管理する装置である。予防に偏ることなく権力の最適なパフォーマンスを引き出す憲法ルールのデザインへ。
※本書の「訳者あとがき」をたちよみ公開しています。→【こちらでご覧ください】
