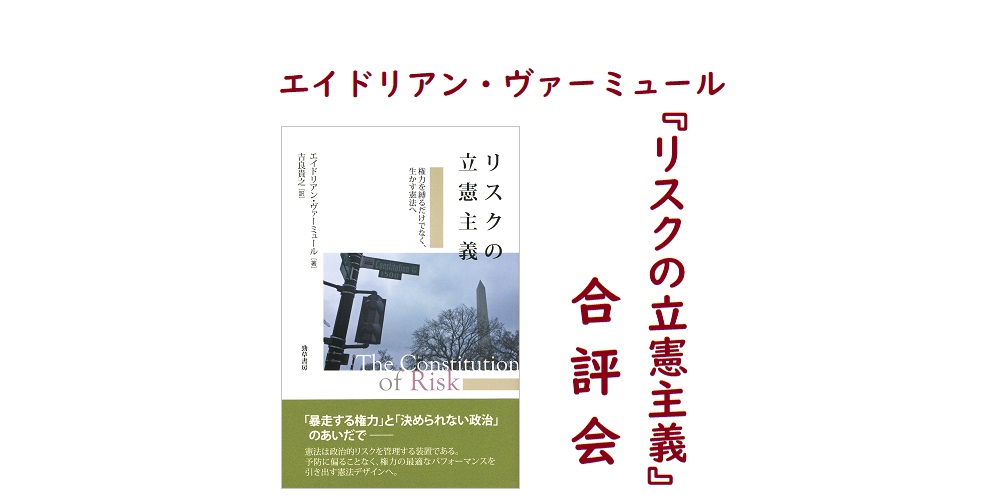
■現代憲法学を顧みる:岡田順太(憲法学)
1 はじめに
今回提示されたヴァーミュールの議論について、わが国の憲法学を「顧みる」契機となるという認識から若干のコメントを行う。全体的な感想やわが国の憲法学に与える示唆などを述べた後、(およそヴァーミュールが想定していない)今日的な日本の政治課題を3点取り上げて疑問点を提示する。
2 予防的立憲主義と最適化立憲主義➖顧みるツールとしてのヴァーミュール
(1)憲法学に与える視座
ヴァーミュールの議論は、条件プログラム/目的プログラムの構図(注1)、憲法学の意義についての「批判の学」/「構築の学」(注2)の構図に類似する要素が多い。今日の憲法学においては、それぞれの構図のうち前者に挙げた特性が、憲法観ないし憲法学の意義として多くの学説の支持を得ていると思われる。というのも、後者の議論に依拠することが、公権力の増大を生むことにつながりかねないとの危惧が存在するからである。そうした状況からすれば、最適化立憲主義を警戒的に捉えるものが多いと思われる(注3)。
ただ、予防的/最適化の視座から立憲主義を区別することの意味は決して小さいものではない。今日、政府批判の手法として、違憲とまでは言えないが、およそ立憲主義の観点から許容し難い事柄について「非立憲」との評価を行うことがあるが、その立憲主義の内容や根拠が必ずしも明確でないことも多い。そうした間隙を突くかたちで、当該批判が「予防的立憲主義の立場からすればそのように評価できるに過ぎない」というように相対化される可能性も秘めている。
もちろん最適化の議論の中で、何を「リスク」と置くかによって、具体的な統治機構の組織形態や運営方法も変わってくると思われる(注4)。その意味で、個別具体的な課題を離れた議論は極力避けるべきであるが、若干、冒頭に述べた今日の憲法学的な思考形態について触れながら、最適化立憲主義の議論の有する価値について論じてみたい。
戦前の憲法学は、法典解釈に重点を置いた概念法学的傾向を有しており、「結局は、いわゆる官僚法学、権力迎合の御用法学となった」(注5)という評価が戦後になされている。そこで、戦後憲法学が、それまでの学問的態度を反省し、「科学的な」「批判」に重点を置いた方法論に傾いたことは当然の成り行きといえる(注6)。そこでの「批判」的アプローチは、国家権力の集中と発動そのものを人権侵害、戦争開始の「リスク」と措定し、「1階」における規制行政における厳格な比例性と「2階における」(分配以前の)授権の抑制を求め、特に安全保障分野は「上下階」でのゼロリスクが求められたといえる。他方で、給付行政においては高度経済成長を背景として、国家権力の発動や行政機構の割拠主義が「リスク」とはされなかった(例:世代間正義の観点から問題となる公的年金制度の維持)。
その意味において、戦後憲法学は予防的立憲主義を総論としつつ、各論においてマキシミン立憲主義とユートピア的(マキシマックス)立憲主義(訳書14-16)に依拠していたと評し得る(ただし、中央省庁改革以前において、実務では「内務省」化が批判されつつも、自治大臣に国家公安委員長を兼務させる人事慣行により、非常時に消防と警察を一元的に指揮しうる体制が取られており、これは当時における(コンティンジェンシー理論的な)最適化アプローチの実例といえよう)。
ところが、地球規模での環境破壊、冷戦構造の崩壊と高度経済成長の終焉という不確定性が社会・経済分野に生じることで、「伝統的な法原則」の修正が迫られる。史的唯物論的な「客観的歴史法則」という安定軌道を走り抜けたマルクス主義憲法学が衰退し、戦後憲法学の一つの柱が失われたことも大きい。
特に、様々な環境変化により生じる「1階」の各種リスクについての関心が高まっているのは確かである。
しかしながら、「1階」のリスクへの関心に比して、「2階」の部分についての議論は鈍いように思われる。その背景としては、意思決定権限の集約や権限付与についての警戒感がいまだに強いことが考えられる。一連の橋本行革における政治主導の復権は評価が分かれるところであるが、官邸主導の政治に対する批判は、「安倍一強」時代においてますます大きくなっていった。ただし、そこでの批判は、問題が機構的なものであるのか、属人的なものであるのかといった考察が十分になされていない点にある。
他方で、「デザイン」という観点から、統治機構に関する考察をする論考も近時見られるところであり(注8)、そこにおける議論はまさに「最適化」を模索するものである。ただし、最適化された統治機構があったとして、それを使いこなす人材と能力をどう確保するかは別の課題として残る。
いずれにしても、最適化立憲主義の理論は、憲法学の来し方を顧みて、行く末を展望する上で示唆に富むものである。
(2)共通善立憲主義への布石?
ヴァーミュールのアメリカの学説的な評価は、清水・川鍋両先生に譲りたいが、近時のヴァーミュールは、共通善立憲主義(Common-good constitutionalism)の主張を展開している点が注目される(注9)。この主張と最適化立憲主義との関係については、別途検討を要すると思われるが、ヴァーミュールの法思想に関しては、同じシカゴ学派のサンスティーンとともに(注10)、次のような評価がなされている。
そうした点を踏まえると、ヴァーミュールの議論には何らかの「共通善」による結論先取りの論理構造が横たわっているとも考えられ、仮にそうだとすれば、現状の変革につながる議論ではなく、現状維持・現状肯定の議論として最適化立憲主義が機能するにとどまる可能性がある。この点は、わが国の戦後憲法学の多くが批判対象とした、官僚法学・御用法学へと回帰することを含意しているのではないか。
2016年にカトリックに改宗して以降、ヴァーミュールの思想からは宗教的言説(注12)が見え隠れするため批判者も多い。この点、カール・シュミットの「ローマカトリック教会と政治形態」を引き合いに出し、ヴァーミュールを「反動」、「非リベラル」の危険思想と評する保守系雑誌の記事もある(注13)。
本訳書は2014年に執筆されたものであり、現在のヴァーミュールの法思想とは必ずしも一致しないかもしれないが、現在の思想に続く一里塚となっている可能性もある。「危険思想」に至る可能性を秘めた理論なら尚更、学ぶ価値のある思想であるようにも思えるのである(注14)。
(3)小括
以上、本訳書の議論をはみ出して、戦後憲法学の課題やヴァーミュールの近時の思想ついて検討してきた。既述の通り、戦後憲法学は、特に戦前のイデオロギー的な憲法学を克服するために、「科学的」「批判」による理論構築を試みてきたところである。しかし、憲法学は何をもって「科学的」とするのか明らかにしないまま、「批判の学の構築」をしてきたのではなかろうか。憲法学が科学の一分野であろうとするのであれば、「立憲/非立憲」以上に「科学/非科学」の区分に敏感になるべきであろう。科学的営為がいつの間にか魅惑的な「非科学」へと傾倒し、元の木阿弥とならないためにも、ヴァーミュールから学ぶべき点は多いように思われる。
3 理論の検討――日本の具体例に即して
最適化立憲主義に対しては、「もっとも、リスク社会を真剣に捉えるのであれば、リスクのスパイラルを前提とした統治構造とは何かという問題に一層踏み込む必要があると思われる。単にコストベネフィットのバランスをとる必要があることを提示するだけではリスク社会の統治構造を十分に描き出しているとはいえず、三権それぞれの責務を明らかにする必要があると思われる」(注15)との指摘が重要である。
そこで、ここからは、最適化立憲主義(と予防的立憲主義の対比)の観点から、ヴァーミュールの想定しない日本特有の統治構造を題材として検討し、その理論の実効性・正当性を検証してみたい。以下、日本の統治機構特有の人事慣行、天皇制、解散権の3点を題材にする。
(1)憲法にない「2階」による最適化(または予防)
例えば、最高裁判事の任命は内閣の権限であり、人選についてはその裁量に委ねられるとするのが憲法上の原則であるはずが、実際は、判事の出身枠を基準として選任されるようになっている。あるいは、官僚の人事についても、法的には行政各部の長たる国務大臣の権限であるが、実際は、官僚団による自律的な決定が大きく影響している。こうした慣行が常例となっているために、内閣や国務大臣の意思でその流れに反する決定をすると、「政治介入」として非難の的になることがある。
近時では、弁護士枠で任命した山口厚最高裁判事の例(注16)や内閣法制局長官に次長からではない者を充てた小松一郎長官の例(注17)が挙げられる。また、検察官の定年延長や人事決定に関する問題もこの系譜に入る。
(疑問点)
◎このように、憲法(判例を含む)や法令にない「2階」に法的拘束力があるかのようにとらえることは、政治介入のリスクを「予防」するアプローチと見てよいのか。最適化立憲主義によれば、政治介入も「最適化」の要素として捉えるということになるという理解でよいのか。そもそも、官僚団の人事慣行を「立憲主義」の要素に入れることは適切なのか。
◎関連して、法案等の国会提出前に行われる与党審査の慣行は、憲法上の統治機構の外に設けられた「2階」であるが、これも内閣の独断で意思決定を行うリスクを「予防」するアプローチと見てよいか。
(2)最適化された天皇制?
天皇に国事行為と私的行為以外の行為を認めない学説(二行為説)と、国会開会式の「おことば」などの公的行為を内閣の統制(費用対効果?)のもとに認める学説(三行為説)は、天皇という非民主的な機関が民主的政治決定の過程へ影響を及ぼすリスクについての予防的立憲主義と最適化立憲主義として捉えることができるように思われる。ただ、近時の内閣が、天皇の社会的影響力を統制できているか疑問がある。
(疑問点)
◎皇位継承の方法を国民の熟議によって決することは困難であると思われるが、最適化立憲主義の見地から、そのような事項を検討するにあたって、どのような制度のデザインを提示し得ると考えるか。皇室典範特例法の制定時のように、内閣が有識者会議を設置して、専門家による意見集約をはかる方法が最適といえるか(注18)。
(3)解散権の所在と制限
解散権の所在と限界をめぐる学説上の論争は、69条限定説に立つGHQと7条3号説(非限定説)に立つ吉田内閣の代理戦争であった。
責任本質と均衡本質をめぐる議論の背景にあった解散権の限界論は、イギリスにおいて解散権の制約を法律によって課すことになったことから、日本でも再び注目されるようになった(注19)。しかし、これが足枷となり、EU離脱の国民投票以来の政治的停滞と混乱が続くことになるのは周知の通りである。
(疑問点)
◎ウェストミンスター型の統治機構は、歴史的過程において最適化を果たしてきたと評することができるが、解散権を制約することは最適化立憲主義の観点からするとどのように評価し得るのか。
(注1)条件プログラム的憲法観への批判として、棟居快行「『憲法と行政法』序説」高木光ほか編『行政法学の未来に向けて(阿部泰隆先生古稀記念)』(有斐閣、2012年)144-151頁。
(注2)高橋和之ほか「憲法60年―現状と展望<座談会>」ジュリスト1334号(2007年)2-38頁。
(注3)憲法学の現状を「ガラパゴス」と批判するものとして、篠田英明『ほんとうの憲法』(筑摩書房、2017年)。
(注4)西原博史「リスク社会・予防原則・比例原則」ジュリスト1356号(2008年)78-79頁は、「安心」概念による安全概念の主観化による比例原則の「空転」を問題視する。
(注5)上田勝美「憲法学の課題と方法―方法論的に見た戦後憲法学の動向と批判」中京法学3巻3号(1969年)18頁。
(注6)「戦後第一世代の憲法研究者に課せられた役割は、新憲法を『科学的』に認識する作業であった」のであり、一つの潮流がケルゼンの純粋法学、もう一つがマルクス主義法学に影響されて新憲法の理論形成に寄与した。江藤祥平『近代立憲主義と他者』(岩波書店、2018年)4-5・21頁。
(注7)長谷部恭男「法律とリスク」同編『法律からみたリスク』(岩波書店、2007年)4頁
(注8)近時のものとして、駒村圭吾・待鳥聡史編『統治のデザイン』(弘文堂、2020年)。
(注9)Adrian Vermeule, Beyond Originalism: The dominant conservative philosophy for interpreting the Constitution has served its purpose, and scholars ought to develop a more moral framework, The Atlantic, March 31, 2020.
https://www.theatlantic.com/ideas/archive/2020/03/common-good-constitutionalism/609037/
(注10)キャス・サンスティーン(那須耕介監訳)『熟議が壊れるとき』(勁草書房、2012年)177-202頁など参照。
(注11)山本龍彦「リチャード・ポズナー」駒村圭吾ほか編『アメリカ憲法の群像―理論家編』(尚学社、2010年)250頁。
(注12)Adrian Vermeule, A Christian Strategy, First Things (November, 2017).
https://www.firstthings.com/article/2017/11/a-christian-strategy#login
(注13)Elliot Kaufman, Editorship and the Art of Writing, National Review (December 1, 2017).(注14)樋口陽一「『危機』への知の対応」奥平康弘・樋口陽一編『危機の憲法学』(弘文堂、2013年)8-11頁は、「カール・シュミットを読まなければならないのか?」との問いへ応答する。
(注15)大林啓吾「感染症リスクと憲法」小山剛ほか編著『日常のなかの〈自由と安全〉』(弘文堂、2020年)413頁。
(注16)「『安倍色』に染まった最高裁判所」FACTA Online(2017年12月号)
https://facta.co.jp/article/201712041.html
(注17)「(特集)憲法解釈と人事」法律時報86巻8号(2014年)所収の論考参照。
(注18)拙稿「天皇の代替わりをめぐって」海外事情研究(熊本学園大学)(2020年)141-163頁。
(注19)岩切大地「解散権はだれのものか」朝日新聞2019年6月13日。
■権力の最適化は消極的になされるー訳者応答:吉良貴之(法哲学)
1 本書は「危険な」書なのか?
さて本書、エイドリアン・ヴァーミュール『リスクの立憲主義』(勁草書房、2019年、以下、特に断りのないページ数は本書のもの)は保守的・現状追認的な危険な書ではないかという懸念が、コメンテイター全員から続々と発せられている。私はあくまで訳者にすぎないのですべて擁護する必要はないのだが、本書の意義が十分に伝わらないのは本意でないので、以下、若干の応答を行う。いま寄せられている問題は、①本書の議論が本当にそういった保守的・現状追認的な種類のものなのか、②仮にそうである場合に何が困るのか、たとえば政治的に利用されるといった事態を警戒すべきなのかどうか、という2つの問いに分けられるだろう。私はいずれも否定する。
(1)最適化立憲主義の規範的内実は薄い
①について。著者のエイドリアン・ヴァーミュールは自身が保守的な論者であることを隠していないが、本書は学術書であって、当然ながら保守的イデオロギーを単に押し出すようなことはなされていない。また、本書のほとんどは消極的な作業にあてられており、規範的な内実はさほどない。著者としても、望ましい憲法がどうあるべきかを提示するのが目的ではないと述べている(22頁)。本書の大部分で行われているのは、憲法価値を追求するにあたって憲法をデザインするときに見落とされがちだったリスクやバイアスの存在、およびインセンティヴやキャパシティの欠如といったことの例示である。今後どのような憲法を作れば「成功」するのかを述べるのは難しいが、「失敗」の痛い経験はすでに十分に共有されている。本書は「憲法ルールの作成者」にそれを改めて意識するように求めている。「失敗」例なのだから、本書の議論を「ネガティヴ・チェックリスト」として参考にして権限分配の最適化を目指せばよい。「予防的立憲主義」が本書で批判されているのは、それが予防に偏りすぎて、リスクとそれに取り組む制度機関の組み合わせという権限配分の最適化に失敗する限りにおいてであって、最適化の結果としての予防的アプローチの可能性はまったく否定されていない。
こうした最適化アプローチは、統治者の認知能力の限界ゆえに実践的にはほとんど無意味ではないかと批判されやすい。これは著者の議論を設計主義的なものと捉えるための誤解であるように思われる。一階のリスク管理と二階の制度的キャパシティの対応をもって最適化とする著者が、そうした認知能力の不釣り合いを無視するはずもない(著者の同様の議論として特に、Law and Limits of Reason, Oxfor U. P., 2009、chap.3を参照)。もちろんすべてのリスクを計算できる理想的裁判官ハーキュリーズは現実には存在しないが、これまでのよくある失敗事例から学ぶことはさほどの認識能力を前提とせずとも可能である。もちろん、そうした例におけるリスク計算は批判に開かれたものであると著者も述べているし、私もいくつかの例ではあまり納得できなかったことは述べておく必要がある。しかしたいていの場合では、リベラルな民主主義体制における諸価値や憲法原理が便利なヒューリスティックとして役立つだろう。
こうした議論が保守的・現状追認的かというと、一概にそう言えるわけではない。岡田が指摘する形式主義の保守化問題(岡田2(2))は、ヴァーミュールにおいては制度的キャパシティに乏しい司法の憲法解釈方針(テクスト主義/原意主義)への消極的姿勢に対するものであるが、立法や行政が十分な制度的キャパシティをもって問題に取り組んでいる場合にまであてはまるわけではない。ある制度機関が保守的になるべきか、それともプラグマティムの本領を生かして実験的になるべきかは、リスクとキャパシティの組み合わせに依存する問題である。したがって、事柄によっては司法も実質的な判断に踏み込むことで積極的な役割を果たしうる。近年のヴァーミュールの「共通善立憲主義」構想はまさに司法への期待を述べるものである。
著者の「最適化立憲主義」構想は、どういった基準によって「最適化」を行うかを明示しない限り、規範的な内実が乏しいという批判もなされる。「最適化」というからには基準が与えられない限り何もできないのではないか、という疑問はもっともである。しかし、本書の主張の眼目は逆に、何らかの規範的立場を最初から取るような議論は多くの場合、予防的立憲主義と同様の陥穽に陥る、ということだ。著者は規範的主張としては「成熟した立場」という、あまり内実のなさそうな指針を述べるに過ぎない――むしろ、それ以上のことを述べてはならないという規範的主張として読むべきだろう――が、それさえも絶えざるリスク計算に向けて開かれている。したがって、とりわけリスク間のトレードオフを許さない種類の義務論的な立場は、本書の枠組みから外れざるをえない。関連リスクの最適化を行わずに特定の価値のみを追求するようでは、アルバート・ハーシュマンの「反動のレトリック」でいう無益・危険性・逆転といった結果になると批判される。
清水が指摘するように(清水2)、各種の憲法原理に「切り札」としての地位を与える論者からすれば、そうした相対化そのものが許容できないということになる。そうしたリベラル派の懸念に対し、ヴァーミュールは、近時の「共通善立憲主義」構想においてカトリック統合主義的な分厚い価値が入っているのではないかと批判された文脈で、共通善の中身は、結局のところリベラル派の法学者がロースクールで日々教えている「自由と平等」といった支配的な価値に過ぎないとかわしている(参照 )。そしておそらく本書の最適化が目指すところも、そのような大雑把な言葉でしか語ってはならないということになるだろう。むろん、ヴァーミュールはリベラル派に対しては露悪的な論調をとる論者なので、あまり文字通りに受け取るわけにもいかないのだが。
(2)本書の政治的影響力?
②について。以上のように、本書から単純な政治的主張を引き出すことは困難である。確かに著者は執行権への制約の緩和を随所で主張しているが、これは大統領権限の弱いアメリカ合衆国憲法体制を念頭に置いているからであって、首相の権限が比較的強い日本国憲法にそのままあてはまるわけではない。それについては川鍋が引いているアッカマンの翻訳の序文と同様、私も解説で念を押している。
さらにいうと、私は、たとえばかつての「批判的峻別論論争」で示されたような、憲法学における理論と実践の微妙な関係に対する問題意識を受け継いでいない。それは哲学的には支持しにくい議論であるし、実践的には学術的議論の影響力を過剰に見積もっている。私はむしろ、日本で社会科学的な学術成果の積極的な利用が少なすぎることのほうが問題であるとさえ思う。「批判の学」は「統治の学」と車の両輪であることが健全ではないだろうか。むろん、このように鈍感なのは私が憲法学専攻でないからということもあるのかもしれないが。
2 本書の学術的意義
本書の学術的意義について私がどのように考えたのかについては、本書の解説で詳しく述べているが、ここでは主に、最も包括的な批判を行っている川鍋の議論に答える形で敷衍したいと思う。
(1)予防的立憲主義はどれだけ問題か
本書の「予防的立憲主義」に対する批判は、あくまでそれが予防に偏りすぎることによって別の害悪を招く場合に限られている。あらゆるリスクを考慮に入れた判断の結果として予防的措置が擁護されうることは本文でも明示的に述べられている。したがって、川鍋の冒頭の問い「予防的立憲主義を採用すると、害悪を招来する可能性は高くなるのか?」には、「悪い予防は悪い結果を招来するだろう」と答えることになる。
これでは無内容に聞こえるだろうが、著者としては「予防」的立憲主義の発想は伝統的に、その対象リスクを過剰に見積もることが「多い」ことを示しているのであって、必然的にそうなるという主張はなされていない(その点で「印象操作」のような嫌らしさを感じられるのは理解できるのだが)。ドイツ憲法の「戦う民主制」の押し付けがましさを私は魅力的に思わないが、仮にそれが成功しているとすれば、著者の議論によれば、予防に成功しているのではなく最適化に成功しているのである。著者の枠組みでは「予防」は最適化の考慮要素の一つに過ぎず、予防と最適化とでは議論の階層が異なっている。したがって川鍋も適切に指摘する通り、予防的アプローチの是非は帰結に対して相対的である。つまり、最適化の結果として予防寄りになることもあれば、そうでないこともある。本書第4章の「自己裁定禁止原則」が多様な形で現れるのは、予防的アプローチが実際には多様なリスク計算を行っているからであって、「予防」だけで一貫させていないからである。つまり、自身の行っていることを十分に示す用語を用いていないがゆえの擬似的な多様性である。
(2)最適化立憲主義と人権保障
憲法的価値を事前に定めることによって人権保障を行うことに疑いを差し挟んでいるのではないか、という川鍋の指摘は重要である。本書の議論の対象はもっぱら統治機構のデザインであり、人権保障について論じる箇所はそれほど多くない。そのため、たとえばミランダ原則を司法による過剰な予防的対応であるかのように述べる記述(60頁)を見ると、危うさを感じることは確かである。
人権保障に関わるそうした懸念を和らげてくれるテキスト上の根拠は本書には残念ながら多くない。しかし、十分に長い時間をかけて確立されてきた人権について、それを覆すような計算外のリスクが実は存在していた、といったこともそうそうないだろう。著者があげる例も、テロ対策など、ほとんど例外的といってよさそうなものに限られている――現状ではパンデミックがその例に加わる。
著者の述べていることは、人権といっても無条件に尊重される切り札ではなく、見過ごされている競合リスクがないかどうか常に吟味されるべきだということである。そうした制約は現在、「公共の福祉」の名の下に一般的に行われている(近時の例でいえば、パンデミック防止のための「ロックダウン」は現行憲法上可能であるというリベラルな論者の主張がその典型である――そこで憲法25条(生存権と国の責務)を持ち出すのは、自由権と社会権という異なる人権を「公共の福祉」によって通約し、結果的に両者を弱体化させる危険な議論であると私には思われる)。それに対し、そもそも人権をそうしたリスク計算(相対化?)の対象にすべきではないという主張は、規範的にはともかく記述的に、現在の憲法実践をよく説明するものではないだろう。著者としても、既に十分に機能している人権や法原理をわざわざ捨て去ろうとか、事前に定める必要がないと主張してはいない。
こうした見方がアドホックなものか(川鍋2冒頭)というと、理論的にはそうでない。何らかの基準が与えられる限り、最適化の結果としての「正答」はある。これは著者の最近の論考での「右派ドゥオーキニアン」的な立場(ロナルド・ドゥオーキンのリベラルな解釈主義理論の保守派からの「簒奪」)につながっていると思われる。しかし、現実には明確な基準が与えられないことも多いし(それがすぐできると考えるのは予防的立憲主義の誤りを繰り返すことになるだろう)、権力によるアドホックな人権制約の危険はつねにありうる。著者はその歯止めをどう考えているのか。2006年の出世作Judging under Uncertainty, Harvard U.P.以来、著者は司法審査については裁判所の制度的キャパシティの不足を理由として一貫して批判的であった。本書でもところどころそうした司法不信が現れており、司法にはあまり期待されてはいない(いらないと言っているわけでもないので、どうも心配し過ぎだと思うのだが)。むしろ筆者は、行政にしかるべき権限を与えたほうがよりよい人権保障につながる、と考えているようである。たびたび出てくる「行政国家化」という表現は、行政が広範な人権保障の役割を担っていることも表している。
(3)最適化立憲主義における世論の力
川鍋は「最適化を憲法とすることによって、著者は立憲主義・民主主義を否定するのではないか」と問う。「立憲主義」をリベラルな憲法原理の「切り札」的理解として捉えるのであれば、あくまで「最適化」の一要素として相対化されていることは確かである。清水のいうように、そうした相対化は「否定」に等しいと捉える者も多いだろう。
民主主義についていえば、最終的な歯止めとして「世論」が憲法アクターとして想定されていることが重要である。本書での世論の位置付けは、憲法思想史的な記述(第3章)のなかで論じられていることもあってさほど明確でなく、またその力は社会状況の変化によって出現したものでもあるとされている(それが合衆国憲法の予防策の必然的帰結であるかのように論じられていることには議論の余地があるだろう)。ただ、緊急事態権力を論じた別の論考によるならば、著者はカール・シュミットの主権独裁論を引きながら憲法秩序の正統性の最終根拠として世論の支持をあげており、むしろポピュリスト的民主主義を称揚するかのような議論さえ行っている(Eric A. Posner & Adrian Vermeule“Demistfying Schmitt” in Oxford Handbook of Carl Schmitt, eds., Jens Meierhenrich & Oliver Simons, Oxford U. P., 2016)。本書の議論と合わせて見るならば、立法・行政・司法といった制度的アクターの権限と、世論の力を全体として最適化するような憲法デザインを行うべき、という読み方が整合的だと思われる。長谷部恭男が同論考について指摘するように、「世論」もむき出しの力の奔流ではない。あくまで憲法上の諸制度(表現の自由保障などのリベラルな枠組み)があって表出され、また我々にとって理解可能なものとなる(長谷部恭男「緊急事態序説」、憲法理論研究会編『展開する立憲主義』敬文堂、2017年)。
そこで最適化をどのように行うのかという問題については、書かれていないものも含めた憲法秩序において世論が最もよく機能するように位置づけるべき、という答えになるだろう。それを実際に行うのは誰なのか、という疑問については「憲法アクターであれば誰でも」ということになる。その範囲は権限分配や制度的キャパシティによって変わる。今回のコメンテイター三者はそれぞれに、こうした「最適化」主体の範囲が広がることは過重な負担をもたらすのではないかという懸念を述べているが、それはおそらく「最適化」を積極的な作業と捉えることによっている。ヴァーミュールの本書の議論は(少なくとも私の読む限り)最適化を阻害する要素を消極的に取り除くことが中心であり、それは現実にはローカルな持ち場での地道な作業になる。たとえば、サンスティーンが近年論じている規制手法「ナッジ」も、社会全体でのビッグ・プロジェクトが不可能になった時代のローカルな最適化の試みとして理解できる(キャス・サンスティーン(吉良貴之訳)『入門・行動科学と公共政策』勁草書房、2021年)。
(4)法哲学的に何が面白いのか
コメンテイター三氏の疑問は予防的立憲主義/最適化立憲主義という対比の是非や、著者の最適化アプローチが結局は権力拡大や現状追認につながるのではないかという点に集中した。それに対し、本書の大半はネガティヴ・チェックリストの提示であって特段の危険な規範的内容があるわけでもないと応答してきた。このように「危なそうに見えて実際は穏当」と示すことは、著者としても実際はそういう自己認識らしいので擁護方針として誤ってはいないだろうが、それが本書の魅力を高めることになるかというと心もとない。「最適化立憲主義」構想そのものはせいぜい常識的な主張に落ち着くのだから、本書の魅力の大半は膨大な具体例の見せ方にあるように思われる(私としては第3章の憲法思想史的な記述を最も面白く読んだ)。
他方、法・政治哲学的な面白さはまた別のところにあるように思われる。解説でも述べたが(264-265頁)、本書は近年の認識的デモクラシー論(epistemic democracy)を憲法上の統治機構論の側から捉え直すものでもある。認識的デモクラシー論は、民主的政治過程を集合的決定の「正解」にたどり着くための手段として理解し、その条件を問う議論である(Robert GoodinやDavid Estlundが代表的な論者)。特に第3~6章の「応用編」は、集合的意思決定がよりよいものになるための認識的な条件を――あくまで「ネガティブ・チェックリスト」方式であるが――考察している。こうした消極的な論法は、共著を多く書いているキャス・サンスティーンのプラグマティックな姿勢とも似通っている(意思決定をする集団の内部的多様性の重要性を「ノイズ」「系統バイアス」といった言葉を鍵に語るものとして、カーネマン、シボニー、サンスティーンの新刊『NOISE』(早川書房、2021年12月[原著も同年])を参照)。
「政治の状況」において正当性と区別される正統性に独自の規範的価値を与えるジェレミー・ウォルドロンや井上達夫の議論とは異なり、本書は正統性(legitimacy)を被治者の認知的な確信の度合いとしてドライに捉えている。世論の支持は法の各ブランチをエンパワーする重要な要素であり、法システムの適切な機能にあたって欠かせない。求められるのはそれを適切な水準に維持すること、つまり法システム全体において最適化することである。高すぎる正統性は独裁を招くし、低すぎる正統性は当該制度機関の機能不全を招く。著者が念頭に置く現代の行政国家の仕事において「比較不能な価値の迷路」はきわめて例外的な状況であって、それをむやみに強調したところで公法が対象としている凡庸にして広大な領域を的確に見ることはできない。むしろ、例外だらけの多様性によって特徴づけられる行政国家において、特権的な例外を想定するほうが危険である。
また、法概念論として興味深く思われるのは、著者の近年のロナルド・ドゥオーキンの解釈主義への接近である。本書の最適化立憲主義にもドゥオーキン的なホーリズム(法実践の「総体」を最善の光で照らし出す解釈戦略)の残響があるが、近時の著作では憲法解釈の方法としてロン・フラー的な法内在道徳とドゥオーキンの解釈主義を結合させるような興味深い議論がなされている。ますます肥大化・細分化する行政の仕事にって必要なのは細かいルールではなく、指針としての「原理(principle)」なのだという。フラーの法内在道徳(一般性、公布、遡及禁止、明確性、無矛盾性、不可能を命じないこと、恒常性、定立されたルールと公権力の行動の一致)は、行政においてとりわけ破られやすかったもの――最近のパンデミック対策を想起せよ――のネガティブ・チェックリストとして再評価される。キャス・サンスティーンとの共著Law and Leviathan: Redeeming the Administrative State, Belknap Press, 2020ではそうした議論が部分的になされているし、次のヴァーミュールの書Common Good Constitutionalism, Polity Press, forthcomingでは全面展開が予告されている。
3 日本の憲法学への応用可能性
日本の憲法学において、本書のような議論がどのように受け止められるかについてはよくわからない。岡田がまとめている通り、戦後憲法学において予防的アプローチが主流であったとすれば、本書のようにその相対化を目論む議論は警戒の対象となるだろう(それはそれで批判対象を提出する意義がある)。しかし個人的な印象としては、そうした統治機構論を正面から議論する伝統も憲法学の中にはずっとあっただろうし、とりわけ新しい世代において拒否感はかなり薄れているのではないかと思う。しかし特に2015年の「解釈改憲」騒動以降、一般的な媒体で目立つ「立憲主義」には権力制限規範としての憲法理解を強く押し出すものが多く、理論的にはかえって硬直化している感も否めない。
現在の日本の憲法状況に対しては、ここ1~2年で話題になったことが、あたかも予告されていたかのようにことごとく論じられており、結果的に時宜を得た出版だったと思う。特に新型コロナウィルス感染拡大にあたって、専門家委員会と行政の関係(第6章)を論じた箇所には多くの示唆があるだろう。他にも緊急事態条項の新設の是非や、検察人事と権力分立の問題など、本書の枠組みで論じられそうなことが多く話題にのぼった。そうした議論のなかで、本書があまり話題にならなかったことを私は残念に思っている。
岡田が提起している問題は、どれも日本的文脈のもとにあり、本書のアメリカ憲法の議論が直接に用いられるわけではない。しかし、本書は素材こそアメリカ憲法であるものの、著者としては現代の先進諸国の憲法に共通する基礎的な問題を扱っているということである。したがって、日本国憲法における射程を考えてみることは十分に有益な作業である。
(1)日本の憲法慣習と権限最適化
岡田が例に出している最高裁判事の「枠」などの人事慣行は、既に長い期間にわたっておおむね定着したものであり、憲法秩序の一部となっていると考えてよいだろう。
ヴァーミュールの基本的な理論動機としては、ますます複雑化する行政国家においていかなる憲法デザインが可能か、というものがある。本書は行政活動に対する立憲的統制を論じる「行政的立憲主義(administrative constitutionalism)」の書でもある。著者としては裁判官や官僚の人事慣行も当然に憲法秩序の一部であって立憲的統制の対象となる――実際はむしろ統制を緩め、エンパワーする方向だが――と考えるだろう。
人事慣行の問題についていえば、本書では最適化アプローチの支障となる多様なバイアスがあげられている(特に専門家委員会についての第6章)。優れた官僚がどういった人物であるかについては「正解」を想定することは、おそらくある程度は可能だろう。だとすると、そうした「正解」のある問題についてバイアスのある決定を避けるための立憲的統制はどのようなものであるか、と問いを立て直すことができる。同質的な官僚集団による自律的な決定はむしろ、集合的決定が正解に至るための条件である「認識的多様性」を欠いたものと評価できそうである。その場合、「政治介入」はそうしたバイアスを緩和する異質性(積極的に評価されるべき「ノイズ」)を持ち込むものといえるかもしれない。つまり、これまで考慮されてこなかった「最適化」の一要素でありうるということである。自律的な人事慣行にも恣意的な政治介入にもそれぞれ問題はあるが、本書のアプローチの特色はその単なる予防というよりも、両者において生じやすいバイアスを明らかにし、それらを打ち消し合わせるような最適な憲法デザインを考えることにある。マディソンのいうように、野望には野望を対抗させなければならない。
(2)天皇制と立憲主義
岡田があげる天皇制の例は、アメリカ合衆国憲法を第一に念頭に置く本書からすればおそらく最も語りにくいものだと思うが、さて何か言えるかどうか。
公的行為を独自類型として認めない「二行為説」が予防的アプローチで、認める「三行為説」が最適化アプローチと捉えられるかどうか。そうした見方ももちろん可能であろう。明仁は平成の30年間で「公的行為」の内実をそのまま作り上げたといえるが、それに対する立憲的統制のあり方を主題化しえない憲法論は、規範的にはともかく、現実の憲法秩序をよく見たものとはいえない。もっとも現状、天皇の公的行為が内閣の統制下にあるといえるかどうかは疑問なしとしない。たとえば「生前退位」をめぐる「おことば」は、民主的答責性を欠いた天皇個人の意思が立法に影響を与えたという点で――実際に「個人」という言葉が確実に意図的に用いられた――憲法上の大問題であると思われるが、その点の議論は残念ながらほとんどなされなかった。今後も内閣の統制を超えた部分で天皇個人の意思によって公的行為がなされるならば、それこそ暴走の危険があるし、ヴァーミュール風の言葉でいえば統治者としての制度的キャパシティがおぼつかない天皇が多くを担うのは二階のリスクの実現になってしまう。このキャパシティの問題だけでも、天皇の公的行為に多くを含めることは困難であると思われる。摂政を立てるなり、補佐役をつけることでの制度的キャパシティの強化は、生身の人間の一身的なコミットメントこそ「象徴」であるとした明仁によって否定されてしまった。
ただその一方、「国民に寄り添う」象徴天皇のあり方は世論による統制を自ら引き受けたものといえるだろうし、実際、明仁も徳仁も世論には十分に敏感であるように思われる。ヴァーミュール的には世論もまた憲法秩序の重要な構成要素であるから、現在のところ危うい均衡が保たれているようにも思われるが、いかにも心もとないことは確かである。たとえば生前退位を制度化し、悪しき天皇には世論による退位圧力が高まることを期待する最適化アプローチは可能だろうし、明仁が示した象徴天皇像はむしろそれを支持するかもしれない。
皇位継承の方法については、岡田の指摘する通り、国民の熟議による正解到達が望みにくい問題であるだろう。いかなる専門家会議であればそれが可能なのかもわからない(認識的多様性が正統性に結びつきにくい種類の問題である)。ただ、それは平時の問題であって、たとえば生前退位のときのように天皇の高齢化(および天皇によって実際に発せられた「お気持ち」)という緊急の必要があるときには世論の分極化も緩和されうる。今後もし、皇族男子が途絶えることが確実になったときには、女系天皇の容認なり、皇族の拡大なり、何らかの選択肢がやむをえないものとして世論の支持を受けることもあるだろう。それに任せてよいか、それともそれは世論の暴走であって最適化の失敗であるというべきか。
(3)解散権
イギリスにおける解散権の制約がブレグジット問題のデッドロックを招いたことは、本書のアプローチから最も消極的に評価される事例であろう。
日本において首相の権限は強いのか弱いのか。衆院の解散は政治的デッドロックを打ち破る強力な手段である。衆院と参院で多数派が食い違う「ねじれ国会」が生じやすいのは現憲法の構造的問題だが、衆院選挙で示される「民意」はそれを緩和しうる(「郵政解散」の例を想起せよ)。他方、首相の解散権が「強すぎる」権限であるとすれば最適化の失敗であるといえるが、小泉純一郎や安倍晋三を数少ない例外として、ここ数十年の日本の首相の権力基盤は実のところそれほど強くなかった。支持率低下によって「選挙に勝てない」とみなされればすかさず退陣へと追い込まれる(2021年秋の菅内閣の退任時の、自民党内の冷酷な対応を想起せよ)。世論(および自民党内の他の勢力)の圧力がきわめて強いといえるが、さてこれは「自由な」解散権があるとされること自体によって生じる問題だろうか。ことはそれほど単純ではなさそうである、と指摘するにとどめる。
4 本書を訳した目的
(1)学術的意義がある著作が翻訳されるべきである
川鍋は翻訳の意義を問うているが、学術書の翻訳なのだから、本書に学術的意義があり、翻訳されることによってさらに多くの読者を獲得することが望ましいと思ったから、という以上の理由は不要であると考えている。政治的影響力については1(2)で述べたように、そう簡単に利用できるようなものでもないし、私としては逆にそれが残念であるとさえ思っている。学術的意義をどう考えたかについては解説で述べ、本応答でも敷衍した。たとえ危険な主張につながりうるものであったとしても(そうでないと私は考えるし、本稿でもそう述べてきたが)、批判対象として提出することには意義がある。
ヴァーミュールは現在のアメリカ憲法学において一定の存在感のある論者であるものの、たとえばサンスティーンなどと比べ日本での知名度はさほど高くない。1冊きちんと訳すことは、読者拡大に大きく役立つことだろう。新世代のアメリカ憲法学の議論に関心を持つ読者が増えることを願っている。
どういったものを翻訳すべきかについては、立場が分かれることだろう。本書は単体として十分なアクチュアリティがあると私は思ったのだが、学術的な評価がある程度固まった古典的著作(それこそアッカマンの『アメリカ憲法理論史(We the People, vol.1)』北大路書房、2020年[原著1991年])の翻訳こそ優先されるべきだという考えも理解できる。そうすると本書のような「現役の」著作の翻訳は、もしかしたら意義のないものに労力をかける結果となるリスクがあるのも確かである。もっとも、そうしたリスクを取ることもまた、研究者としての目利きの能力が試される重要な機会だと考えている。今のところ、大きく外したと私は思っていないが、これは読者の判断に委ねざるをえない。
(2)「翻訳は業績にならない」は有害な思い込みである
なお、川鍋注5で引かれている森村進の翻訳論について私は基本的に賛同するが、より明確に、強く言いたいと思っている。まず、専門書の翻訳が他分野の研究者を含め、広く一般読者の獲得に役立つことには同意する。それは学界の発展におおいに寄与することだろう。しかし、次の2点が強調されるべきである。
(1) 森村は、自分の論文のなけなしのオリジナリティにこだわるよりは、真にオリジナルな業績を翻訳・紹介するほうが学界や一般読者にとって有益ではないかと真剣に自問すべきだという。森村自身がまさに世界レベルでのオリジナルな業績を残していることを考えると、この話はいささか皮肉っぽい印象を受けるが、しかしそもそも両者は両立しないわけでない。翻訳をするにあたっては当然ながら、原著を隅から隅まで読み込むことになる。それだけでなく、引かれている膨大な文献にも目を通す。それを踏まえれば自分の論文も書けるだろう。実際、私は本書の翻訳から得た知見をもとにいくつかの論文を書いた。論文を書くために翻訳はまたとない材料を与えてくれるのだから、論文と翻訳を別物のように考えてはいけない。森村の多くのオリジナルな業績にも、パーフィット『理由と人格』(勁草書房、1998年)のような記念碑的な翻訳を手掛けたことが大きく寄与しているだろう。森村にはいずれも同様にすぐれた業績であることを自慢してもらいたい。
また、(2)「一旦安定したポストについて業績作成にそれほどこだわる必要がなくなった学者」が翻訳を手掛けるべきだというのは、「翻訳は業績にならない」という誤った思い込みを強化させることにつながりかねない。人文・社会系の多くの分野の研究者にとって、その研究能力が赤裸々に表れるものが翻訳である。見事な翻訳は、それだけその研究者のテキスト読解能力を示し、本人の論文の信頼性を上げる(もちろん、ひどい誤訳があれば残酷にもその逆となる)。それを知っている研究者であれば翻訳業績を的確に評価するだろう。大学人事での翻訳業績の扱いといった生臭い話としても、遺憾ながらまったく評価されない場合もあるのだが、論文ほどではないにせよ、ある程度の評価がなされることも多い。これは場合によるとしか言いようがないが、少なくとも「翻訳は業績にならない」という一般論は事実として正確でない。もちろん、論文と比べた場合のコストパフォーマンスという問題は(特に若手研究者にとって)重要だが、上で述べたように、翻訳によって論文の材料を得れば一石二鳥でありうる。だから私は、安定したポストの有無にかかわらず、人文・社会系の研究者は、学界の発展といった高尚な目的のためだけでなく、まさに自己利益のために積極的に翻訳を手掛けるべきだと思っている。
■報告者紹介■
川鍋健(かわなべ・たけし)
早稲田大学政治経済学術院講師(任期付)
専門:憲法、比較憲法、アメリカ憲法
主な論文に、「アメリカ憲法学における人民主権論と日本憲法学への示唆」、憲法研究8号(2021年)、155頁以下;「人民の、人民による、人民のための憲法:アキル・リード・アマールの憲法論から」、一橋法学17巻2号(2018年)、435頁以下(第11回石橋湛山新人賞受賞)など。
Website: https://researchmap.jp/TakeshiKawanabe?lang=ja
清水潤(しみず・じゅん)
白鴎大学法学部准教授
専門:憲法、アメリカ法
主な論文に、「コモン・ロー、憲法、自由(1)~(8・完)」(中央ロー・ジャーナル14巻1号~15巻4号、2017-2019年)など。
Website: https://researchmap.jp/jshim
岡田順太(おかだ・じゅんた)
獨協大学法学部教授
専門:憲法学
著書に『関係性の憲法理論』(丸善プラネット、2015年)、『戦後日本憲政史講義−もうひとつの戦後史』(共著、法律文化社、2020年)、翻訳にヤニブ・ロズナイ『憲法改正が「違憲」になるとき』(共訳、弘文堂、2021年)など。
吉良貴之(きら・たかゆき)
宇都宮共和大学専任講師
専門:法哲学
主な論文に「行政国家と行政立憲主義の法原理」(『法の理論』39号、2021年)、「戦争と責任:歴史的不正義と主体性」(野上元・佐藤文香ほか編『「戦争と社会」という問い』(岩波書店、2021年)など。翻訳にキャス・サンスティーン『入門・行動科学と公共政策』(勁草書房、2021年)、シーラ・ジャサノフ『法廷に立つ科学』(監訳、勁草書房、2015年)など。
Website: https://jj57010.web.fc2.com
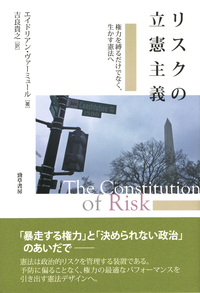 好評発売中!
好評発売中!エイドリアン・ヴァーミュール 著/吉良貴之 訳
『リスクの立憲主義 権力を縛るだけでなく、生かす憲法へ』https://www.keisoshobo.co.jp/book/b491626.html
ISBN:978-4-326-55086-9 四六判・328ページ 価格3,850円(税込)
憲法とは政治的リスクを規制管理する装置である。予防に偏ることなく権力の最適なパフォーマンスを引き出す憲法ルールのデザインへ。
※本書の「訳者あとがき」をたちよみ公開しています。→【こちらでご覧ください】
