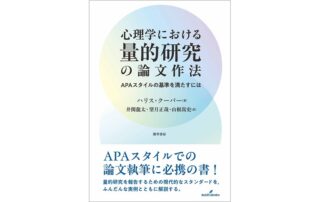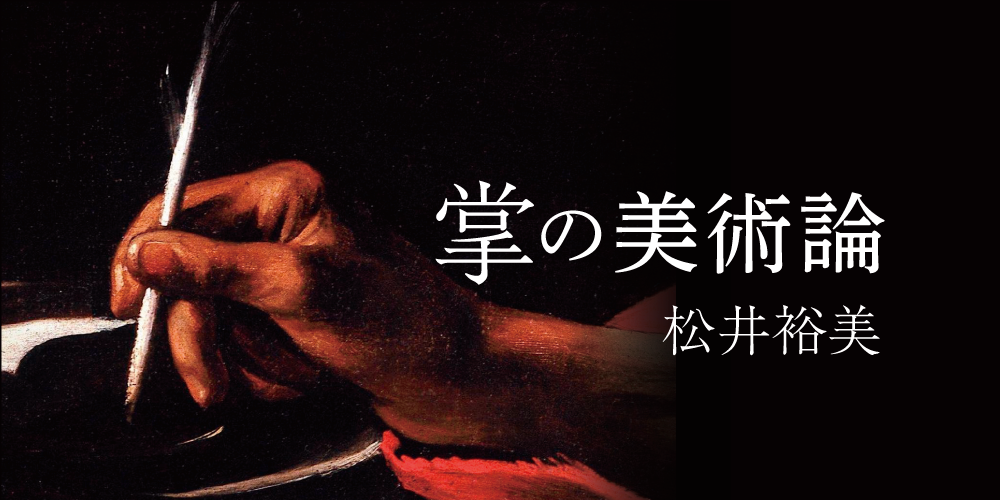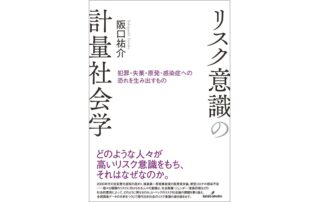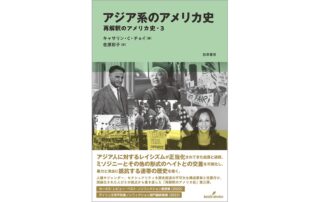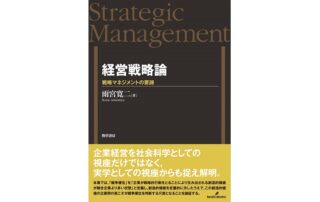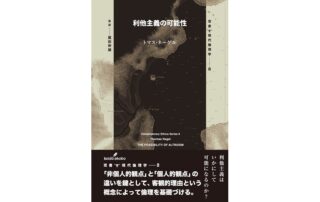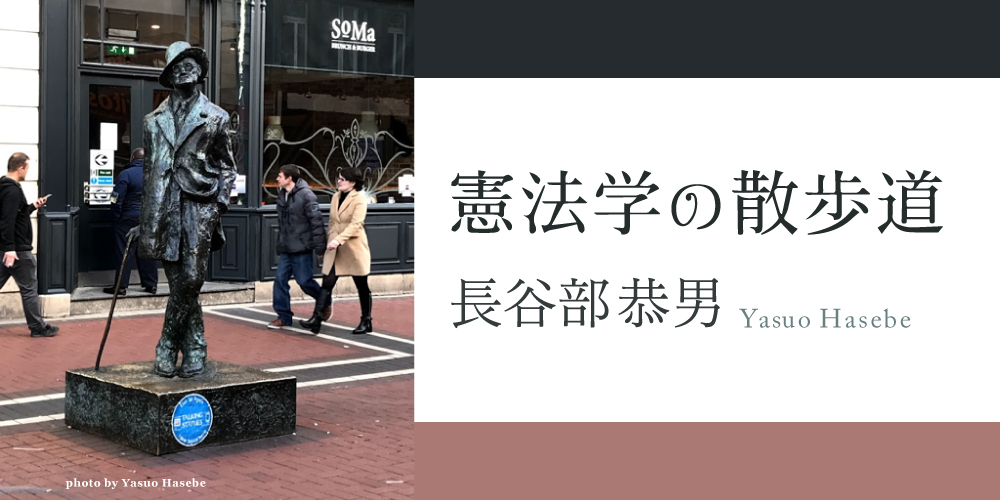あとがきたちよみ
『心理学における量的研究の論文作法――APAスタイルの基準を満たすには』
「第1 章 心理学研究のための報告基準」「訳者解説」を公開しました。
掌の美術論 第19回
顔に触れる――彼女たちの仮面を介して(前編)
好きな仮面を好きな時にかぶることができれば、とても楽だ。それは本当の感情を隠し、演じられた人格(ペルソナ)のみを人々に見せる。だが仮面が剥がれなくなってしまうことほど恐ろしいものはない。なぜなら人は、「自分とは誰か」ということを確認するとき、人の目に映った自分の姿について問わずにはいられないからだ。……
夢をかなえるための『アントレプレナーシップ』入門
㉙地域活性化とアントレプレナーシップ(2)
一言で地域活性化と言っても、企業と違い地域にはさまざまな利害関係者が存在し、その調整に大きなコストがかかります。地域においてはアントレプレナーが果たす役割も多様で、様々な活動が求められます。今回は地域と企業の相違点に焦点を合わせて、地域活性化におけるアントレプレナーの役割について触れていきます。
あとがきたちよみ
『リスク意識の計量社会学――犯罪・失業・原発・感染症への恐れを生み出すもの』
「はじめに」を公開しました。
あとがきたちよみ
『アジア系のアメリカ史――再解釈のアメリカ史・3』
「序文 大いなるヘイトの時代に執筆すること」を公開しました。
あとがきたちよみ
『経営戦略論――戦略マネジメントの要諦』
「はじめに」を公開しました。
あとがきたちよみ
『経済成長と産業構造 東アジア長期経済統計 第1巻』
「刊行の辞」「監修者まえがき」を公開しました。
あとがきたちよみ
『利他主義の可能性』
「監訳者解説」を公開しました。
コヨーテ歩き撮り#208
ジョグジャカルタ近郊の火山ムラピを見にくと、このみみずくに出会った。 Went to see Gunung Merapi, an active volcano, near JogJakarta. There I met this cute horned owl!
法+女性=変革! 『レイディ・ジャスティス』の舞台裏
第3回 司法女子パワーのポッドキャスト
本書『レイディ・ジャスティス』の著者ダリア・リスウィックは弁護士資格を持つジャーナリストである。「訳者あとがき」にも書いたとおり、リスウィックはスタンフォード・ロースクール修了後、連邦の控訴裁判所で裁判官の調査官を務めた。その後はしばらくローファームで働いたが、1999年にオンライン雑誌『スレート(Slate)』でマイクロソフト独占禁止法違反訴訟を取材する機会を得たのが転機となり、以後はローヤーとしての知識を活かし、同誌で連邦最高裁判所などの動向や法に関する記事を書いているほか、テレビのニュース番組にも解説者として出演している。
あとがきたちよみ
『図書館情報学概論 第2版――記録された情報の力』
「日本語版(初版)への序文」「日本語版第2 版への序文」を公開しました。
憲法学の散歩道
第40回 エウチュプロン──敬虔について
プラトンの対話篇の一つに「エウチュプロン」がある。さほど有名な対話篇とは言えないであろう。登場人物はソクラテスとエウチュプロンの二人だけ、エウチュプロンは若い預言者である。扱われているテーマは、敬虔(eusebeia; piety)とは何かであるが、確たる結論にいたることもなく、二人の対話は唐突に終わる。 対話の表面的な流れは、次の通りである。……