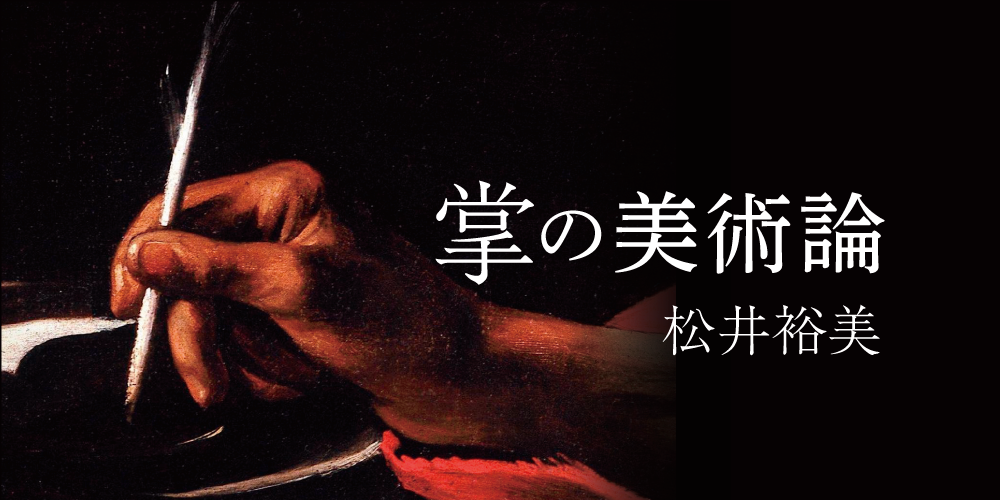掌の美術論 第18回
おもちゃのユートピア——その理論と実践の系譜(後編)
芸術家の作品や著述を振り返ってみると、20世紀美術と聖性の関わりを示す例には事欠かない。ナビ派やスーラの理論、あるいはヒルマ・アフ・クリントやクプカの抽象画における神秘主義。カンディンスキーが描く黙示録。マレーヴィチの絶対主義絵画に秘められた東方キリスト教の聖画像の記憶。モーリス・ドニが推進した「聖なる芸術」運動。第一次世界大戦で荒廃した大地を出発点としながら、ウィリアム・ブレイクの描く天地創造のイメージを介して1920年代に聖書の創世記を版画化し、30年代には線と球体の構築物で支配された月面旅行の場面を描いたポール・ナッシュ。第一次世界大戦を契機にキリスト教信仰に目覚め、第二次世界大戦後には教会装飾も手がけたキュビスムの画家アルベール・グレーズ。自然と人間との秘義的な融合を思い描いたシュルレアリスムの画家アンドレ・マッソン。カトリックの聖変化の儀礼や薔薇十字団の教えを、自らが開発したクライン・ブルーの顔料を用いてパロディー化したイヴ・タンギー。原始的な祝祭や儀礼を思わせる過激なパフォーマンスを展開し女性の身体性について問うたシンディ・シャーマン。以上はすべてこれまで論じられてきたことであるし、そのうちのいくつかについては私のこれまでの論考の中でも紹介してきたことなので、ここでは詳しく触れまい。実際このテーマに関わる作家は無尽蔵におり、その名をリスト化しようとしても終わりはなく、美術史研究が進めばリストはますます長大になるだろう。